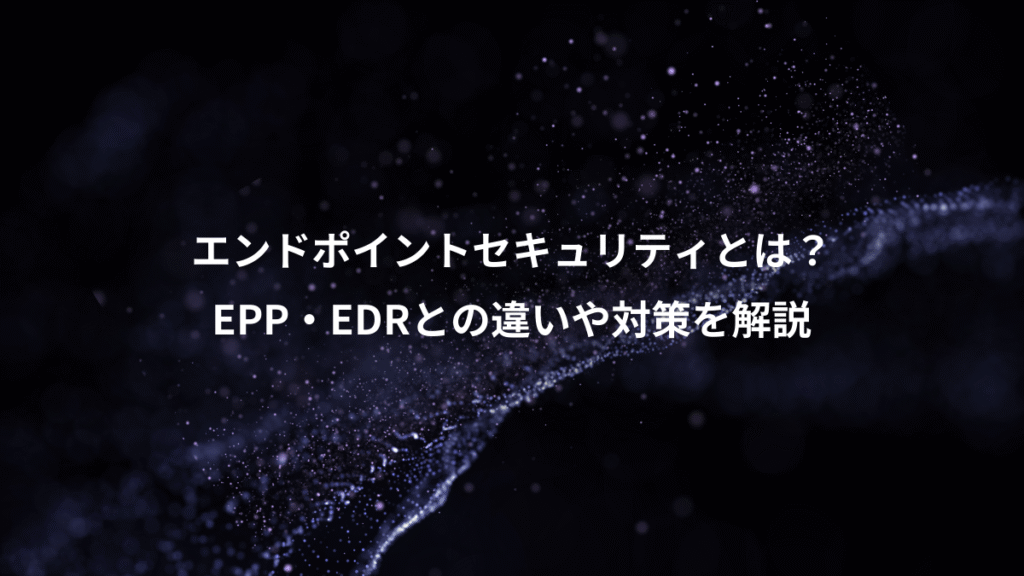現代のビジネス環境において、サイバーセキュリティの重要性はかつてないほど高まっています。特に、テレワークの普及やクラウドサービスの利用拡大に伴い、従来のセキュリティ対策だけでは不十分となりつつあります。こうした状況で注目を集めているのが「エンドポイントセキュリティ」です。
この記事では、エンドポイントセキュリティの基本的な概念から、なぜ今その重要性が増しているのか、そして具体的な対策方法までを網羅的に解説します。EPPやEDRといった専門用語についても、それぞれの役割や違いを分かりやすく紐解いていきます。本記事を通じて、自社のセキュリティ体制を見直し、強化するための一助となれば幸いです。
目次
エンドポイントセキュリティとは
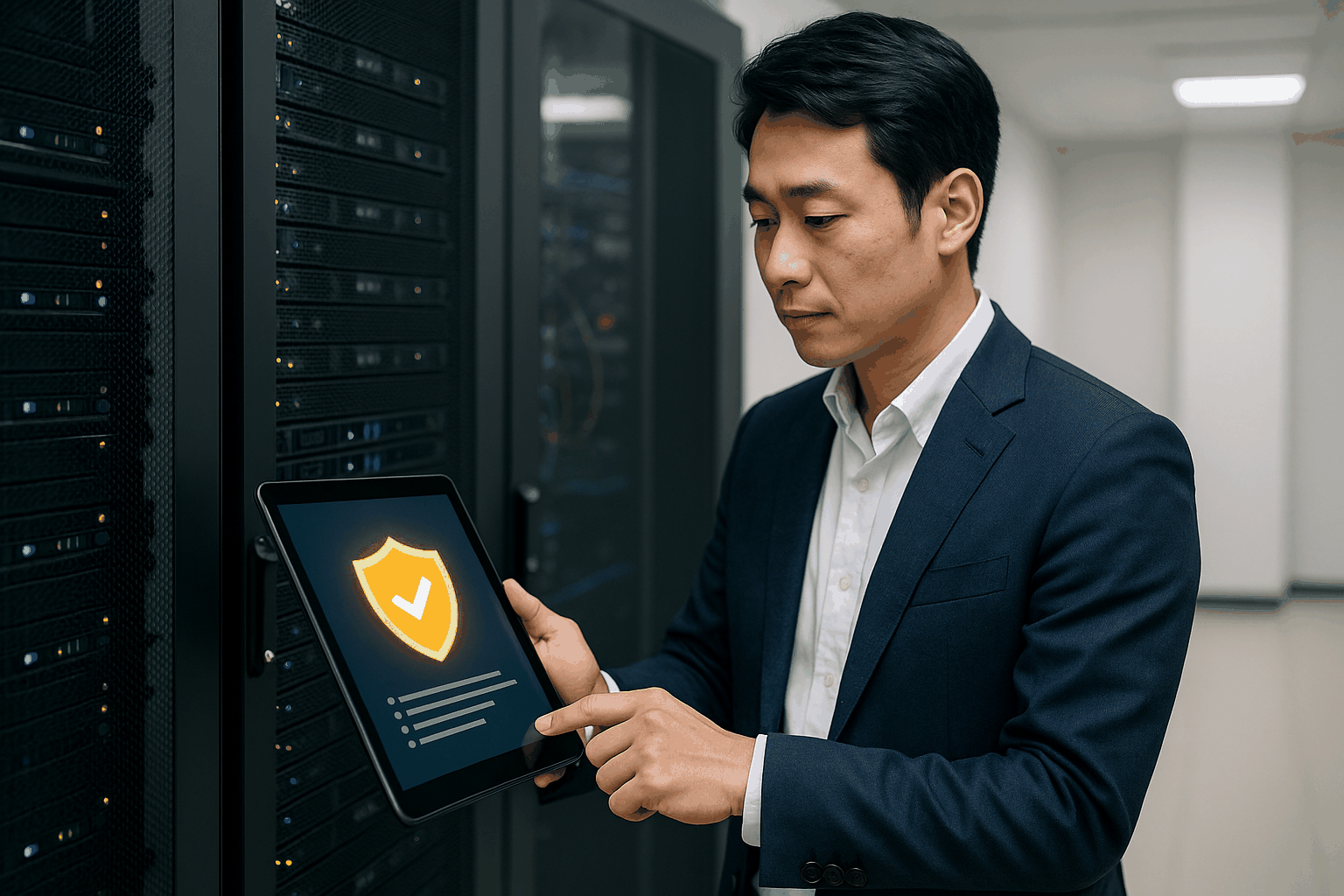
サイバーセキュリティ対策を語る上で、もはや欠かすことのできない「エンドポイントセキュリティ」。しかし、言葉自体は聞いたことがあっても、その正確な意味や対象範囲を正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。ここでは、まず「エンドポイント」が何を指すのかを明確にし、エンドポイントセキュリティの基本的な概念について深く掘り下げていきます。
エンドポイントが指すもの
エンドポイントとは、直訳すると「末端」や「終点」を意味します。ITの世界におけるエンドポイントとは、ネットワークに接続されている末端のデバイス全般を指します。具体的には、以下のような機器がすべてエンドポイントに含まれます。
- PC(デスクトップ、ノートPC)
- スマートフォン、タブレット
- サーバー(物理、仮想)
- プリンター、複合機
- POSレジ
- IoT機器(ネットワークカメラ、工場のセンサーなど)
これらはすべて、ユーザーが業務で直接操作したり、何らかのデータ処理を行ったりする「接点(Point)」であり、社内ネットワークやインターネットといった広大なネットワークの「末端(End)」に位置づけられます。つまり、エンドポイントとは、サイバー攻撃者にとって組織内部へ侵入するための入口となりうる、すべてのデバイスと考えることができます。
この「エンドポイント」を様々なサイバー脅威から保護するための対策、それこそがエンドポイントセキュリティです。従来のセキュリティ対策が、ファイアウォールなどを設置して社内ネットワーク全体を外部の脅威から守る「境界防御」に主眼を置いていたのに対し、エンドポイントセキュリティは、個々のデバイスそのものを保護することに焦点を当てます。
なぜ、デバイス個別の保護が必要なのでしょうか。それは、現代の働き方やIT環境の変化と密接に関係しています。例えば、社員が会社のノートPCを自宅やカフェに持ち出して仕事をするのが当たり前になりました。このノートPCは、もはや会社のファイアウォールという「城壁」の内側にはありません。保護されていない公衆Wi-Fiに接続すれば、マルウェア感染のリスクは格段に高まります。
また、会社のサーバーも重要なエンドポイントです。サーバーがマルウェアに感染すれば、そこに保存されている機密情報が盗まれたり、事業継続に不可欠なシステムが停止したりと、甚大な被害につながる可能性があります。
このように、ネットワークの「境界」が曖昧になった現代において、攻撃の入口となりうるすべてのデバイス、すなわちエンドポイントの一つひとつに堅牢なセキュリティ対策を施すことが、組織全体をサイバー攻撃から守るための生命線となるのです。
よくある質問:ネットワークセキュリティとエンドポイントセキュリティの違いは?
この二つは混同されがちですが、守る対象とアプローチが異なります。
- ネットワークセキュリティ:
- 対象: ネットワーク全体(社内LANなど)
- アプローチ: ネットワークの「境界」にファイアウォールやIDS/IPS(侵入検知・防御システム)を設置し、外部からの不正な通信や攻撃を水際で防ぐ。「面」で守るイメージ。
- エンドポイントセキュリティ:
- 対象: 個々のデバイス(PC、スマホ、サーバーなど)
- アプローチ: デバイス自体にセキュリティソフト(アンチウイルス、EDRなど)を導入し、マルウェア感染や不正な操作を防ぐ。「点」で守るイメージ。
両者は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。強固なネットワークセキュリティで不正な侵入を極力防ぎつつ、万が一侵入を許してしまった場合に備えて、エンドポイントセキュリティで個々のデバイスを保護し、被害の拡大を食い止める。この「多層防御」の考え方が、現代のセキュリティ対策の基本となります。
エンドポイントセキュリティが重要視される3つの理由
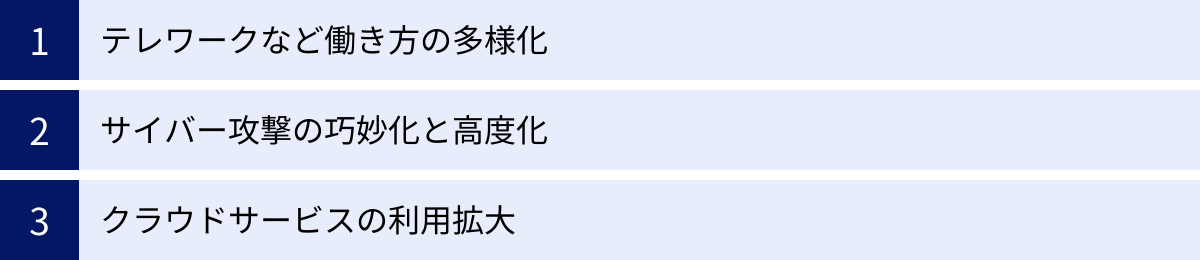
なぜ今、これほどまでにエンドポイントセキュリティが重要視されているのでしょうか。その背景には、私たちの働き方やビジネス環境の劇的な変化があります。ここでは、その主な理由を3つの側面に分けて詳しく解説します。これらの変化を理解することが、適切なセキュリティ対策を講じるための第一歩となります。
① テレワークなど働き方の多様化
エンドポイントセキュリティの重要性を押し上げた最大の要因は、テレワークやハイブリッドワークといった働き方の多様化です。従来、多くの従業員はオフィスに出社し、社内ネットワークという厳重に管理された環境で業務を行っていました。これは、いわばセキュリティの「城壁」に守られた中で仕事をするようなものでした。
しかし、パンデミックを契機にテレワークが急速に普及し、従業員は自宅、カフェ、コワーキングスペースなど、様々な場所から社内リソースにアクセスするようになりました。これは、守るべきエンドポイント(PCやスマートフォン)が、管理の行き届いた「城内」から、セキュリティレベルが不確かな「城外」へと拡散したことを意味します。
具体的に、テレワーク環境には以下のようなリスクが潜んでいます。
- 安全でないネットワークへの接続: 自宅のWi-Fiルーターは、セキュリティ設定が甘い場合があります。また、カフェなどの公衆Wi-Fiは、通信内容を盗聴される「中間者攻撃」のリスクが常に伴います。このような安全性の低いネットワークを経由して社内システムにアクセスすることは、攻撃者に侵入経路を与えかねません。
- 個人所有デバイスの業務利用(BYOD): 会社が許可している場合、個人所有のPCやスマートフォンで業務を行うことがあります。これらのデバイスには、会社の管理下にあるデバイスと同レベルのセキュリティ対策が施されていないことが多く、脆弱性が放置されている可能性があります。
- 物理的な盗難・紛失: ノートPCやスマートフォンを社外に持ち出す機会が増えれば、当然、盗難や紛失のリスクも高まります。デバイスが第三者の手に渡った場合、適切な対策がなされていなければ、内部のデータが容易に抜き取られてしまいます。
こうした状況下では、従来の「境界」で守るセキュリティ対策だけでは不十分です。VPN(Virtual Private Network)を使えば通信は暗号化されますが、それはあくまで「トンネル」を保護するだけです。VPNに接続する前の段階でPCがすでにマルウェアに感染していれば、そのPCはVPNを通じて社内ネットワークに脅威を持ち込む「トロイの木馬」になり得ます。
だからこそ、デバイスがどこにあっても、どのようなネットワークに接続していても、そのデバイス自体が自己防衛できる能力を持つ、すなわちエンドポイントセキュリティの強化が不可欠となるのです。
② サイバー攻撃の巧妙化と高度化
エンドポイントセキュリティの重要性が増している第二の理由は、サイバー攻撃そのものの手口が年々、巧妙化・高度化している点にあります。かつてのサイバー攻撃といえば、不特定多数にウイルスをばらまく愉快犯的なものが主流でした。しかし、現在では金銭や機密情報を狙った、より悪質で組織的な攻撃が後を絶ちません。
近年の代表的な攻撃手法には、以下のようなものがあります。
- ランサムウェア: 企業を狙った攻撃の代表格です。システムやファイルを使用不能な状態に暗号化し、復旧と引き換えに高額な身代金を要求します。近年では、データを暗号化するだけでなく、事前に窃取したデータを公開すると脅す「二重恐喝(ダブルエクストーション)」の手口が一般的になっています。
- 標的型攻撃(APT: Advanced Persistent Threat): 特定の組織をターゲットに定め、長期間にわたって潜伏しながら、機密情報などを継続的に窃取する攻撃です。非常に巧妙な手口で侵入するため、検知が極めて困難です。
- ファイルレスマルウェア: PCのディスクに不正なファイルを残さず、OSに標準搭載されている正規のツール(PowerShellなど)を悪用してメモリ上で活動するマルウェアです。ファイルの実体がないため、従来のファイルスキャン型のアンチウイルスソフトでは検知することができません。
- サプライチェーン攻撃: ターゲット企業を直接攻撃するのではなく、セキュリティ対策が手薄な取引先や、利用しているソフトウェアの開発元などを踏み台にして侵入する攻撃です。
これらの高度な攻撃は、従来のセキュリティ対策を容易にすり抜けてしまいます。特に、攻撃者が最初の侵入口として狙うのは、組織の防御網の中で最も脆弱になりがちな「人」と、その人が使う「エンドポイント」です。巧妙なフィッシングメールで従業員を騙して不正な添付ファイルを開かせたり、悪意のあるWebサイトへ誘導したりすることで、まず一台のエンドポイントを乗っ取ります。
一度エンドポイントへの侵入に成功すると、攻撃者はそのPCを踏み台にして、内部ネットワークの他のサーバーやPCへと感染を広げていきます(ラテラルムーブメント)。この最初の侵入をデバイスレベルで防ぐこと、そして万が一侵入されても、その後の不審な挙動を即座に検知して封じ込めることが、被害を最小限に抑える上で極めて重要です。そのためには、AIや振る舞い検知といった技術で未知の脅威にも対応できる、次世代のエンドポイントセキュリティが求められます。
③ クラウドサービスの利用拡大
三つ目の理由として、SaaS(Software as a Service)をはじめとするクラウドサービスの利用拡大が挙げられます。Microsoft 365やGoogle Workspace、Salesforceなど、今や多くの企業が業務に不可欠なツールとしてクラウドサービスを活用しています。
クラウドサービスの普及は、ビジネスの効率性や柔軟性を飛躍的に向上させましたが、同時にセキュリティの考え方を大きく変えました。従来、企業の重要なデータやアプリケーションは、社内のデータセンターにあるサーバーに保管されていました。しかし現在では、それらの多くが社外のクラウド環境に存在します。
これは、守るべき情報資産が社内ネットワークという「境界」の内側だけでなく、インターネット上の至る所に分散していることを意味します。従業員はオフィスからだけでなく、自宅や外出先など、様々な場所、様々なデバイスからこれらのクラウドサービスにアクセスします。
ここで問題となるのが、アクセス元のエンドポイントの信頼性です。
- 認証情報の窃取: マルウェアに感染したPCでクラウドサービスにログインすると、キーロガーなどによってIDとパスワードが盗まれ、アカウントが乗っ取られる危険性があります。
- 不正なデータアクセス: セキュリティ対策が不十分なデバイスから重要なデータにアクセスすれば、そのデータがデバイス上にダウンロードされ、情報漏洩につながる可能性があります。
- シャドーIT: 会社の許可なく従業員が個人的に利用するクラウドサービス(シャドーIT)もリスクの温床です。管理外のサービスに会社のデータが保存されることで、情報漏洩やコンプライアンス違反のリスクが生じます。
このようなリスクに対処するためには、クラウドサービスへのアクセスを許可する前に、「誰が(ID認証)」「どのデバイスから(デバイス認証)」アクセスしようとしているのかを厳格に検証する必要があります。この「デバイス認証」の根幹をなすのがエンドポイントセキュリティです。デバイスがマルウェアに感染していないか、OSやセキュリティソフトが最新の状態かといったデバイスの健全性(デバイスポスチャ)を確認し、安全なデバイスからのみアクセスを許可する。こうしたアプローチは、後述する「ゼロトラストセキュリティ」の根幹をなす考え方であり、クラウド時代に不可欠な対策といえます。
従来の境界型セキュリティとゼロトラストセキュリティ
エンドポイントセキュリティの重要性をより深く理解するためには、セキュリティモデルの大きなパラダイムシフトを知る必要があります。ここでは、これまで主流だった「境界型セキュリティ」とその限界、そして現代の主流となりつつある「ゼロトラストセキュリティ」の考え方について解説します。
従来の「境界型セキュリティ」の限界
境界型セキュリティ(Perimeter Security)は、その名の通り「境界」で守るという考え方に基づいたセキュリティモデルです。これを理解するためによく使われるのが「城と堀」の比喩です。
- 城(Castle): 守るべき資産がある社内ネットワーク
- 堀や城壁(Moat/Wall): インターネットなどの外部ネットワークとの境界
このモデルでは、社内ネットワーク(信頼できる内部)とインターネット(信頼できない外部)を明確に区別し、その境界線上にファイアウォールやプロキシサーバー、IDS/IPS(不正侵入検知・防御システム)といった防御壁を築き、外部からの攻撃を防ぐことに注力します。つまり、「社内は安全、社外は危険」という性善説に基づいたアプローチです。
この境界型セキュリティは、従業員が皆オフィスに出社し、社内のPCから社内のサーバーにアクセスするという、かつての働き方においては非常に有効でした。しかし、前述した「働き方の多様化」「サイバー攻撃の高度化」「クラウドサービスの利用拡大」という3つの大きな変化によって、その前提が崩れ、限界が露呈しています。
境界型セキュリティの限界点
- 「境界」の曖昧化・消滅: テレワークの普及により、従業員はノートPCやスマートフォンを社外に持ち出し、自宅やカフェのネットワークから社内リソースやクラウドサービスにアクセスします。これにより、守るべき「境界」そのものが曖愁になり、どこに防御壁を築けばよいのかが分からなくなりました。
- 内部に侵入された際の脆弱性: 境界型セキュリティの最大の弱点は、一度内部への侵入を許してしまうと、内部での活動(ラテラルムーブメント)に対しては比較的無防備である点です。攻撃者はフィッシングメールなどで従業員のPCを一台乗っ取れば、それを足がかりに、信頼されている内部ネットワーク内で他のサーバーや重要なデータベースへと容易にアクセスを拡大できてしまいます。
- 内部不正への対応困難: 悪意を持った内部関係者や、退職者による情報持ち出しといった内部不正に対して、境界型セキュリティはほとんど無力です。内部の通信は基本的に「信頼されたもの」として扱われるため、不正なデータアクセスや持ち出しを検知・阻止することが困難です。
- クラウドサービスとの相性の悪さ: 業務データやアプリケーションが社外のクラウド上にある場合、「境界の内側=安全」という前提そのものが成り立ちません。クラウドへのアクセスをすべて境界でコントロールすることは非効率であり、ビジネスのスピードを阻害する要因にもなります。
これらの理由から、もはや「場所」を基準に信頼性を判断する境界型セキュリティだけでは、現代の脅威から組織を守りきることはできないという認識が広まっています。
近年主流の「ゼロトラストセキュリティ」の考え方
境界型セキュリティの限界を克服するために登場したのが、ゼロトラストセキュリティ(Zero Trust Security)という新しい概念です。その名の通り、ゼロトラストは「何も信頼せず、すべてを検証する(Never Trust, Always Verify)」という原則に基づいています。
これは、ネットワークが社内(LAN)であろうと社外(インターネット)であろうと関係なく、すべてのアクセス要求を信頼できないもの(Untrusted)として扱い、その安全性を都度検証し、厳格な認証・認可を行ってから初めてアクセスを許可するという考え方です。境界型が「性善説」に基づいていたのに対し、ゼロトラストは「性悪説」に基づいているといえます。
ゼロトラストセキュリティを実現するためには、単一の製品を導入すれば完了というわけではなく、複数のセキュリティ技術や対策を組み合わせて、多層的な防御体制を構築する必要があります。その主要な構成要素には、以下のようなものがあります。
- ID管理と認証の強化:
- IAM (Identity and Access Management): 誰が、どのリソースにアクセスする権限を持つのかを一元的に管理します。
- 多要素認証(MFA): ID/パスワードだけでなく、スマートフォンアプリの通知や生体認証など、複数の要素を組み合わせて本人確認を強化します。
- デバイスの信頼性検証:
- エンドポイントセキュリティ(EPP/EDR): アクセス元のデバイスがマルウェアに感染していないか、OSやセキュリティソフトが最新の状態かを常に監視・検証します。これがゼロトラストにおける非常に重要な柱となります。
- IT資産管理/MDM: 組織が管理するデバイスを可視化し、セキュリティポリシーを適用します。
- アクセスの最小権限化:
- マイクロセグメンテーション: ネットワークを小さなセグメントに分割し、セグメント間の通信を厳しく制御することで、万が一侵害が起きても被害の横展開(ラテラルムーブメント)を防ぎます。
- SASE (Secure Access Service Edge): ネットワーク機能とセキュリティ機能をクラウド上で統合して提供するフレームワーク。場所を問わず、ユーザーとリソースに対して一貫したセキュリティポリシーを適用します。
- すべての通信の監視と分析:
- SIEM/SOAR: ネットワーク機器やサーバー、エンドポイントから収集したログを相関分析し、脅威を検知して対応を自動化します。
ゼロトラストにおいて、エンドポイントセキュリティは「アクセス元のデバイスは本当に信頼できるのか?」を判断するための根拠を提供する、極めて重要な役割を担います。どんなに強力なID認証を行っても、アクセス元のPCがマルウェアに乗っ取られていては意味がありません。ゼロトラストの考え方では、「正しいユーザー」が「信頼できるデバイス」を使って、初めてリソースへのアクセスが許可されるのです。このように、エンドポイントセキュリティは、従来の境界型防御の穴を埋め、ゼロトラストという新しいセキュリティパラダイムを実現するための土台となるのです。
エンドポイントセキュリティの主な対策6選
エンドポイントを保護するためには、様々なアプローチやソリューションが存在します。ここでは、現代のエンドポイントセキュリティを実現するために用いられる主要な6つの対策について、それぞれの役割と特徴を解説します。これらのツールは単独で機能するだけでなく、組み合わせて使用することで、より強固な多層防御を実現します。
① EPP(Endpoint Protection Platform)
EPP(Endpoint Protection Platform)は、サイバー攻撃の侵入を未然に防ぐ「予防」と「防御」に主眼を置いた、統合的なセキュリティプラットフォームです。従来のエンドポイント対策製品が個別の機能(アンチウイルス、パーソナルファイアウォールなど)を提供していたのに対し、EPPはこれらの機能を一つの製品にまとめ、一元管理コンソールから統合的に運用できるようにしたものです。
EPPが持つ主な機能
- 次世代アンチウイルス(NGAV): 後述する、AIや機械学習を用いて未知のマルウェアを検知する機能。EPPの中核をなします。
- パーソナルファイアウォール: エンドポイントごとに行われる不正な通信を監視し、ブロックします。
- Webフィルタリング/URLフィルタリング: 悪意のあるWebサイトやフィッシングサイトへのアクセスをブロックします。
- デバイス制御: USBメモリや外付けハードディスクといった外部デバイスの利用を制御し、不正なデータの持ち出しやマルウェアの持ち込みを防ぎます。
- 脆弱性対策: OSやアプリケーションの脆弱性をスキャンし、修正パッチの適用を促したり、仮想的に保護したりします。
EPPは、いわばエンドポイントに装備する「多機能な鎧」のような存在です。様々な方向からの攻撃(マルウェア、不正通信、悪性サイトなど)を入口でブロックし、脅威が内部に侵入することを防ぎます。多くの既知および未知の脅威を水際で食い止めることができるため、エンドポイントセキュリティの第一の防衛ラインとして非常に重要な役割を果たします。
② EDR(Endpoint Detection and Response)
EDR(Endpoint Detection and Response)は、EPPによる防御をすり抜けて侵入してしまった脅威を対象とする、侵入「後」の対策に特化したソリューションです。「検知(Detection)」と「対応(Response)」という名前の通り、その役割は脅威の侵入を前提として、いち早く異常を検知し、迅速に対応することにあります。
EDRの主な仕組みと機能
- 常時監視とログ収集: エンドポイントに導入されたエージェントが、PC内で行われるあらゆる操作(プロセスの生成、ファイル操作、レジストリ変更、ネットワーク通信など)を常時監視し、詳細なログデータを継続的に収集します。
- 不審な挙動の検知: 収集したログデータをクラウド上の分析基盤に送り、AIや脅威インテリジェンス(世界中の攻撃情報を集約したデータベース)を用いて分析します。これにより、単体のマルウェアだけでなく、正規ツールを悪用した攻撃など、従来の対策では見つけにくい「不審な挙動の連鎖」を検知します。
- インシデント対応支援: 脅威が検知されると、管理者にアラートで通知します。管理コンソールでは、攻撃がいつ、どこから侵入し、どのような経路で、どの範囲まで影響を及ぼしたのかが視覚的に表示されます。これにより、管理者は迅速に状況を把握し、遠隔からのネットワーク隔離やプロセスの停止といった対応(封じ込め)を行うことができます。
EPPが「泥棒が家に入らないようにする」ための対策だとすれば、EDRは「万が一家に侵入された場合に、即座にそれを検知し、被害が広がる前に捕まえる」ための監視カメラと警備員のような存在です。100%の防御が不可能な現代において、侵入後の被害を最小限に抑えるために、EDRはEPPと並んで不可欠な対策となりつつあります。
③ NGAV(Next Generation Antivirus)
NGAV(Next Generation Antivirus)は、その名の通り「次世代アンチウイルス」であり、従来型のアンチウイルスソフトの弱点を克服するために開発されました。現在では、多くのEPP製品にその中核機能として組み込まれています。
従来型のアンチウイルスは、「パターンマッチング」という手法に依存していました。これは、既知のウイルスの特徴を記録した定義ファイル(パターンファイル)と、PC内のファイルを照合し、一致するものがあればウイルスと判断する方式です。指名手配犯の写真と見比べて犯人を探すようなものです。
しかし、この方式には、以下のような大きな弱点がありました。
- 未知の脅威に弱い: 毎日数万〜数十万もの新種・亜種のマルウェアが生まれる現代では、パターンファイルの更新が追いつきません。そのため、登場したばかりの未知のウイルスは検知できません(ゼロデイ攻撃)。
- ファイルレス攻撃に無力: ディスクにファイルを残さないファイルレスマルウェアは、スキャン対象が存在しないため検知できません。
これに対し、NGAVはパターンマッチングに頼らず、以下のような先進的な技術を用いて脅威を検知します。
- 機械学習・AI: 正常なファイルが持つ何百万もの特徴をAIに学習させ、そこから逸脱する特徴を持つファイルを「悪意がある可能性が高い」と予測・判定します。
- 振る舞い検知(ビヘイビア法): ファイルやプロセスの「挙動」を監視し、「ファイルを勝手に暗号化し始める」「OSのシステムファイルを書き換えようとする」といった悪意のある振る舞いを検知してブロックします。
- サンドボックス: 疑わしいファイルを、PC本体から隔離された安全な仮想環境(サンドボックス)で実行させ、その挙動を分析してマルウェアかどうかを判断します。
NGAVは、未知の不審者(未知のマルウェア)でも、その怪しい素振り(振る舞い)から危険だと判断できる優秀な番犬に例えられます。このNGAVの登場により、エンドポイントの防御力は飛躍的に向上しました。
④ 従来型のアンチウイルス
現在でも、個人向けや一部の安価な法人向け製品として利用されているのが、従来型のアンチウイルスソフトです。前述の通り、既知のウイルスの特徴を記録した「パターンファイル」を用いてマルウェアを検知するのが主な仕組みです。
既知の脅威に対しては依然として有効であり、基本的な防御策として一定の役割を果たします。しかし、ビジネス環境で利用するには、その限界を正しく理解しておく必要があります。新種・亜種のマルウェアやファイルレス攻撃、ゼロデイ攻撃といった高度な脅威を防ぐことは極めて困難です。
現代の企業セキュリティにおいては、従来型のアンチウイルスのみで対策を完結させるのは非常に危険と言わざるを得ません。より防御範囲の広いEPP/NGAVへの移行や、EDRとの併用を検討することが強く推奨されます。
⑤ DLP(Data Loss Prevention)
DLP(Data Loss Prevention)は、マルウェア対策とは異なり、組織内部からの「情報漏洩」を防ぐことに特化したソリューションです。「Data Loss(データ損失)」ではなく「Data Leak(データ漏洩)」と訳されることもあります。
DLPは、社内の機密情報(顧客情報、設計図、財務データなど)や個人情報を識別し、それらが不正な経路で外部に持ち出されるのを監視・ブロックします。エンドポイントセキュリティの文脈では、PCにエージェントを導入してユーザーの操作を監視する「エンドポイントDLP」が中心となります。
DLPが監視・制御する主な操作
- 外部デバイスへのコピー: USBメモリやスマートフォンへの重要データのコピーを禁止する。
- メール送信: 個人用メールアドレスや、許可されていない宛先への重要データの添付をブロックする。
- Webアップロード: クラウドストレージやSNSなど、許可されていないWebサイトへの重要データのアップロードを禁止する。
- 印刷(プリントアウト): 重要文書の印刷を禁止、または印刷ログを取得する。
- スクリーンショット: 画面キャプチャによる情報窃取を防止する。
DLPは、悪意のある内部関係者による意図的な情報持ち出しだけでなく、従業員の不注意による偶発的な情報漏洩(メールの誤送信など)を防ぐ上でも非常に有効です。サイバー攻撃対策(EPP/EDR)と情報漏洩対策(DLP)を組み合わせることで、外部からの脅威と内部からのリスクの両方に対応できます。
⑥ IT資産管理・MDM
IT資産管理ツールやMDM(Mobile Device Management)も、広義のエンドポイントセキュリティにおいて重要な役割を担います。これらのツールは、組織が所有するすべてのエンドポイント(PC、サーバー、スマートフォン、タブレット)のハードウェア情報やソフトウェア情報を一元的に把握し、管理するためのものです。
セキュリティ対策における主な役割
- 脆弱性管理: どのPCに、どのバージョンのOSやアプリケーションがインストールされているかを可視化します。これにより、脆弱性が見つかった際に、影響を受けるデバイスを即座に特定し、セキュリティパッチの適用を強制することができます。パッチを適用せず脆弱性を放置することは、攻撃者に侵入の扉を開けておくようなものであり、その管理はセキュリティの基本です。
- セキュリティポリシーの強制: 禁止されているソフトウェアがインストールされていないか、アンチウイルスソフトが正常に稼働しているかなどをチェックし、ポリシー違反があれば是正を促します。
- リモートロック/ワイプ(MDM): スマートフォンやタブレットを紛失・盗難した場合に、遠隔でデバイスをロックしたり、内部のデータを消去したりして、情報漏洩を防ぎます。
適切なセキュリティ対策は、まず自社が「何を」「どれだけ」保有しているかを正確に把握することから始まります。IT資産管理/MDMは、その「把握」と「統制」を実現し、エンドポイントセキュリティ全体の土台を固めるための不可欠なツールです。
EPP・EDR・NGAVの違いを比較
エンドポイントセキュリティ対策を検討する際、特に混同しやすいのが「EPP」「EDR」「NGAV」の3つです。これらはそれぞれ異なる役割を持ちますが、機能が重複する部分もあるため、違いを正しく理解することが製品選定の鍵となります。ここでは、3つのソリューションを様々な角度から比較し、その関係性を明らかにします。
| 項目 | EPP (Endpoint Protection Platform) | EDR (Endpoint Detection and Response) | NGAV (Next Generation Antivirus) |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 侵入前の予防・防御(脅威を入口でブロック) | 侵入後の検知・対応(侵入を前提とし、被害を最小化) | 未知の脅威の検知・防御(EPPの進化形) |
| 対策フェーズ | 事前対策(侵入前) | 事後対策(侵入後) | 事前対策(侵入前) |
| 検知対象 | 既知・未知のマルウェア、不正なWebサイト、不正な通信など広範囲 | 不審な挙動、プロセスの異常、ラテラルムーブメント(横展開)の兆候 | 未知・亜種のマルウェア、ファイルレス攻撃、ランサムウェアの挙動 |
| 主要技術 | NGAV、パターンマッチング、振る舞い検知、ファイアウォール、デバイス制御など | ログ監視、脅威インテリジェンス、サンドボックス、フォレンジック分析 | AI、機械学習、振る舞い検知、エクスプロイト対策 |
| 導入効果 | マルウェア感染率の低下、包括的な防御力の向上 | インシデント対応の迅速化、被害範囲の特定、原因究明の効率化 | ゼロデイ攻撃など高度な脅威への防御力向上 |
| 比喩 | 多機能な鎧 | 監視カメラと警備員 | 優秀な番犬 |
この表からもわかるように、EPPとNGAVは「侵入前」、EDRは「侵入後」と、対策するフェーズが明確に異なります。また、NGAVはEPPを構成する重要な要素の一つという関係性も見て取れます。以下で、それぞれの特徴をさらに詳しく掘り下げていきましょう。
EPPとは(侵入前の予防・防御)
EPPを理解するキーワードは「統合(Platform)」と「予防(Protection)」です。サイバー攻撃がエンドポイントに到達し、活動を開始する前に、それを食い止めることを最大の目的としています。
先述の通り、EPPはNGAVの機能に加え、パーソナルファイアウォール、デバイス制御、Webフィルタリングといった、多彩な防御機能を一つのパッケージに統合したものです。これにより、マルウェアだけでなく、フィッシングサイトへのアクセスや不正な通信、USBメモリ経由でのウイルス持ち込みなど、様々な脅威ベクトルに対応できます。まさに、エンドポイントを外部の脅威から守るための「多機能な鎧」と言えるでしょう。
EPPのメリット
- 包括的な防御: 複数の防御機能を組み合わせることで、多層的な防御を実現し、攻撃の成功率を下げます。
- 運用管理の効率化: 複数のセキュリティ機能を一つの管理コンソールから設定・監視できるため、管理者の負担を軽減できます。
- コスト削減: 個別のツールを複数導入するよりも、トータルコストを抑えられる場合があります。
しかし、EPPだけで100%の防御が実現できるわけではありません。高度化するサイバー攻撃は、時にEPPの防御網さえもすり抜けてしまいます。そのため、EPPによる「予防」を基本としつつ、万が一の侵入に備えてEDRによる「検知・対応」の仕組みを組み合わせることが、現代のセキュリティ対策のベストプラクティスとされています。
EDRとは(侵入後の検知・対応)
EDRを理解するキーワードは「侵入前提」と「可視化」です。その思想の根底には、「100%の防御は不可能である」という現実的な認識があります。どんなに優れたEPPを導入しても、未知の攻撃手法や人的ミスによって、脅威の侵入を完全に防ぎきることはできません。
そこでEDRは、侵入を許してしまった後の活動に焦点を当てます。エンドポイント内のあらゆる操作ログを詳細に記録・分析し、攻撃の兆候となる「不審な挙動」を捉えます。例えば、「メールソフト(Outlook)からマクロ付きのWordファイルが開かれ、そこからコマンド実行ツール(PowerShell)が起動し、外部の不審なサーバーと通信を開始した」といった一連のプロセスを可視化します。
EDRのメリット
- インシデントの早期発見: 潜伏している脅威を早期に発見し、被害が拡大する前に対処できます。
- 被害範囲と原因の特定: 攻撃がどのように侵入し、どこまで影響が及んでいるかを正確に把握できるため、迅速かつ的確な復旧作業が可能になります。
- 高度な脅威への対応: 正規ツールを悪用するファイルレス攻撃など、EPPだけでは検知が難しい巧妙な攻撃を発見できます。
EDRは「監視カメラと警備員」に例えられます。常に内部を監視し、異常があれば即座にアラートを鳴らし、警備員(セキュリティ担当者)が駆けつけて対処するイメージです。ただし、EDRは大量のアラートを生成することがあり、その分析や判断には専門的な知識が求められます。そのため、自社での運用が難しい場合は、専門家が運用を代行するMDR(Managed Detection and Response)サービスの利用も有効な選択肢となります。
NGAVとは(未知の脅威への対策)
NGAVは、EPPの防御能力を飛躍的に高めた中核エンジンです。その最大の特徴は、AIや機械学習といった技術を駆使して、シグネチャ(パターンファイル)に依存せずに未知の脅威を検知できる点にあります。
従来型のアンチウイルスが「指名手配書(パターンファイル)」に載っている犯人(既知のマルウェア)しか捕まえられなかったのに対し、NGAVは「挙動」や「特徴」から、初対面の人物でも不審者かどうかを判断できる優秀な番犬のような存在です。
NGAVが優れている点
- ゼロデイ攻撃への対応: パターンファイルが存在しない、出現したばかりのマルウェア(ゼロデイマルウェア)にも対応できます。
- ファイルレス攻撃の検知: メモリ上での不審な振る舞いを検知することで、ディスクにファイルを残さない攻撃手法にも有効です。
- 運用負荷の軽減: パターンファイルの頻繁な更新が不要なため、エンドポイントへの負荷が少なく、管理も比較的容易です。
現在、市場に提供されている主要なEPP製品のほとんどは、このNGAVをマルウェア対策エンジンとして搭載しています。したがって、「EPPを導入する」ということは、多くの場合「NGAVの機能を含んだ統合的な防御プラットフォームを導入する」とほぼ同義になります。
結論として、これら3つの関係は「EPP ⊃ NGAV」であり、「EPP/NGAV」と「EDR」は相互補完の関係にあります。EPP/NGAVで侵入を可能な限り防ぎ、それでもすり抜けてきた脅威をEDRで捉えて対処する。この攻守の組み合わせこそが、理想的なエンドポイントセキュリティ体制と言えるでしょう。
エンドポイントセキュリティ製品を選ぶ3つのポイント
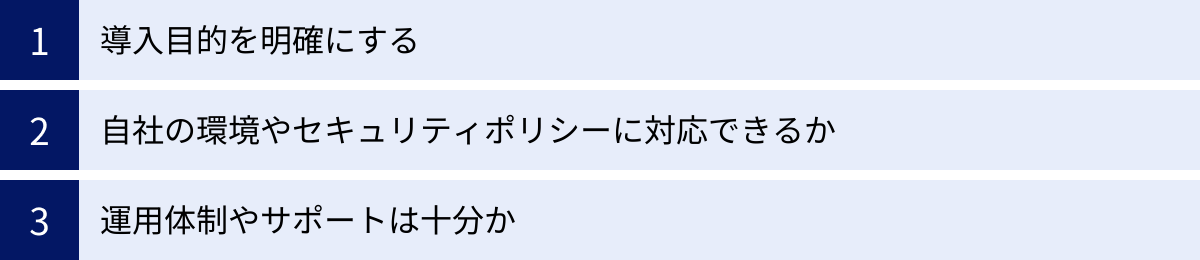
自社に最適なエンドポイントセキュリティ製品を導入するためには、単に知名度や機能の多さだけで選ぶのではなく、慎重な検討が必要です。ここでは、製品選定の際に特に重要となる3つのポイントについて解説します。これらを事前に整理しておくことで、導入後のミスマッチを防ぎ、投資対効果を最大化できます。
① 導入目的を明確にする
最も重要かつ最初のステップは、「なぜエンドポイントセキュリティを導入・強化するのか」「何から、どのように守りたいのか」という導入目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、数ある製品の中から自社に本当に必要なものを選ぶことはできません。
具体的には、以下のような観点から自社の現状の課題や優先順位を洗い出してみましょう。
- 最優先で対策したい脅威は何か?
- 例1:世間で猛威を振るっているランサムウェアによる事業停止リスクを最優先で低減したい。
- → この場合、未知のマルウェアをブロックする能力に長けたNGAVを搭載したEPPが必須となります。さらに、侵入された際の迅速な検知・復旧のためにEDRの導入も視野に入れるべきです。
- 例2:競合他社を狙った標的型攻撃による機密情報の窃取が懸念される。
- → この場合、EPPによる防御はもちろん、潜伏する攻撃者の不審な活動をあぶり出すEDRの重要性が非常に高くなります。
- 例3:従業員の不注意による個人情報や顧客情報の漏洩事故を防ぎたい。
- → この場合、マルウェア対策だけでなく、データの持ち出しを制御するDLP機能を持つ製品や、DLP専門ソリューションの追加を検討する必要があります。
- 例1:世間で猛威を振るっているランサムウェアによる事業停止リスクを最優先で低減したい。
- どのような環境を保護したいのか?
- 例1:テレワークの本格導入に伴い、社外で利用されるノートPCのセキュリティを強化したい。
- → クラウドから一元管理でき、場所を問わずポリシーを適用できるSaaS型のEPP/EDRが適しています。
- 例2:社内の重要なサーバー群を保護したい。
- → Windows Serverだけでなく、Linuxなど、対象サーバーのOSに対応している製品を選ぶ必要があります。サーバーに特化した保護機能(変更監視など)の有無も確認しましょう。
- 例3:個人所有デバイスの業務利用(BYOD)を許可しており、そのスマートフォンやタブレットを管理したい。
- → PCだけでなく、iOSやAndroidに対応したMDM機能を統合した製品が候補となります。
- 例1:テレワークの本格導入に伴い、社外で利用されるノートPCのセキュリティを強化したい。
このように、自社のビジネス環境、業界特有のリスク、そして最も避けたいセキュリティインシデントを具体的に想定することで、必要な機能の優先順位が明確になります。「全部入り」の多機能な製品が必ずしも最適とは限りません。自社の課題解決に直結する機能を備えた製品を選ぶことが、賢明な投資につながります。
② 自社の環境やセキュリティポリシーに対応できるか
次に、候補となる製品が自社のIT環境やルールに適合するかどうかを確認する必要があります。機能が優れていても、自社のシステムで利用できなければ意味がありません。
確認すべき主なポイント
- 対応OSとデバイス:
- 社内で使用しているPC(Windows, macOS)、サーバー(Windows Server, Linux)、モバイルデバイス(iOS, Android)など、保護対象となるすべてのOSに製品が対応しているかは必ず確認しましょう。特定のOSに対応していないと、そのデバイスだけがセキュリティホールになってしまいます。
- 提供形態(クラウド or オンプレミス):
- SaaS(クラウド)型: サーバー管理が不要で、導入が迅速かつ容易です。インターネット経由で管理コンソールにアクセスできるため、テレワーク環境との親和性が高いのが特徴です。近年の主流はこちらです。
- オンプレミス型: 自社内に管理サーバーを構築する形態です。厳格なデータ管理ポリシーを持つ企業や、閉域網での運用が必要な場合に選択されますが、初期コストや運用保守の負担が大きくなります。自社のシステム方針に合った提供形態を選びましょう。
- 既存システムとの連携(API連携など):
- すでに導入している他のセキュリティ製品(例:SIEM、ファイアウォール)やIT資産管理ツール、ID管理システムなどと連携できるかは重要なポイントです。API(Application Programming Interface)などを通じて連携できれば、各システムからの情報を集約して相関分析を行うなど、より高度なセキュリティ運用が可能になります。
- パフォーマンスへの影響:
- エンドポイントに常駐するセキュリティソフトは、PCの動作パフォーマンスに影響を与える可能性があります。特に、フルスキャン時やエージェントのアップデート時にCPUやメモリの使用率がどの程度上昇するのか、業務に支障が出ないレベルかを事前に確認することが望ましいです。多くのベンダーが提供している無料トライアルなどを活用し、実際の業務環境で検証することをおすすめします。
- 自社のセキュリティポリシーとの整合性:
- 自社で定めている情報セキュリティポリシー(例:「USBメモリは原則使用禁止」「特定のフリーソフトのインストールは禁止」など)を実現できる機能があるかを確認します。デバイス制御機能やアプリケーション制御機能の有無、設定の柔軟性などが評価ポイントになります。
これらの技術的な適合性を事前に細かくチェックすることで、導入後のトラブルを未然に防ぐことができます。
③ 運用体制やサポートは十分か
エンドポイントセキュリティ製品は、導入して終わりではありません。継続的に運用し、アラートに対応してこそ、その価値を発揮します。特にEDRのような高度な製品は、その傾向が顕著です。
確認すべき主なポイント
- 運用負荷と必要なスキル:
- EDRは、検知したアラート(脅威の疑いがある通知)が本物の攻撃かどうかを分析・判断(トリアージ)し、適切に対応する専門的なスキルと工数が必要になります。自社の情報システム部門やセキュリティ担当者が、その運用負荷に対応できる体制とスキルを持っているかを冷静に評価する必要があります。
- もし自社での運用が難しい場合は、MDR(Managed Detection and Response)やSOC(Security Operation Center)といった、ベンダーやパートナー企業が24時間365日体制で監視・分析・対応を代行してくれるアウトソーシングサービスの利用を検討しましょう。製品選定の際には、こうした運用支援サービスの有無や内容も重要な比較ポイントになります。
- 管理コンソールの使いやすさ:
- セキュリティ担当者が日常的に利用する管理コンソールは、直感的で分かりやすいかどうかが運用効率を大きく左右します。インシデント発生時に、誰が、いつ見ても、脅威の状況や影響範囲を迅速に把握できるダッシュボードやレポート機能を備えているかを確認しましょう。これも無料トライアルで実際に操作してみるのが一番です。
- ベンダーのサポート体制:
- 万が一のインシデント発生時や、製品の操作で不明な点があった場合に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかは非常に重要です。
- 日本語でのサポートは提供されているか。
- サポートの受付時間(平日日中のみか、24時間365日か)。
- 問い合わせ方法(電話、メール、チャットなど)。
- 導入時の設定支援や、担当者向けのトレーニングプログラムを提供しているか。
セキュリティ製品は、いわば「保険」のようなものです。いざという時に頼りになる、信頼できるパートナー(ベンダー)を選ぶという視点を持つことが、長期的に見て安心なセキュリティ運用につながります。
おすすめのエンドポイントセキュリティツール4選
市場には数多くのエンドポイントセキュリティ製品が存在し、それぞれに特徴があります。ここでは、国内で広く利用されており、機能や目的に応じて特色のある代表的なツールを4つ紹介します。自社の課題や目的に最も合致する製品はどれか、比較検討の参考にしてください。
注意:ここで紹介する情報は、各製品の公式サイト等で公開されている情報に基づいています。機能や仕様は変更される可能性があるため、導入を検討する際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。
| ツール名 | 提供形態 | 主な特徴 | 特に適したニーズ |
|---|---|---|---|
| LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版 | SaaS | 資産管理・MDMとセキュリティ対策の統合 | デバイスの「管理」と「保護」を両立させたい |
| Trend Micro Apex One SaaS | SaaS | EPP/EDR/NGAVのオールインワン、仮想パッチ | 侵入前後の対策を包括的に行いたい、脆弱性対策を重視 |
| CrowdStrike Falcon | SaaS | クラウドネイティブ、軽量エージェント、脅威インテリジェンス | 高度な脅威ハンティング、専門的なインシデント対応を重視 |
| Cybereason EDR | SaaS/オンプレミス | AIによる攻撃全体像の可視化(MalOp) | EDRの運用負荷を軽減し、攻撃のストーリーを迅速に把握したい |
① LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版
「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」は、エムオーテックス株式会社が提供する、IT資産管理、MDM、セキュリティ対策を一つのプラットフォームで実現するツールです。特に「資産管理」と「セキュリティ」をシームレスに連携させたい企業から高い評価を得ています。
主な特徴
- 統合管理: PC、スマートフォン、タブレットといった多様なデバイスのハードウェア・ソフトウェア情報を自動収集し、一元管理します。これにより、組織内のIT資産の現状を正確に把握できます。
- 多彩なセキュリティ機能: ウイルス対策機能(オプションでAIアンチウイルスも提供)に加え、操作ログの取得、Webフィルタリング、デバイス制御など、多岐にわたるセキュリティ機能を提供します。これにより、外部脅威対策と内部不正対策の両方をカバーできます。
- 脆弱性管理との連携: 収集したIT資産情報をもとに、OSやソフトウェアの脆弱性を可視化し、必要なパッチが適用されていないデバイスを特定。パッチの配布・適用までをサポートし、脆弱性を突いた攻撃のリスクを低減します。
このような企業におすすめ
- PCやスマホなど、管理すべきデバイスの種類が多く、その管理とセキュリティ対策を一つのツールで効率化したい企業。
- シャドーITの利用状況や従業員の操作ログを把握し、内部統制やコンプライアンスを強化したい企業。
- まずセキュリティの基本である「現状把握」と「脆弱性管理」から着実に取り組みたい企業。
参照:エムオーテックス株式会社公式サイト
② Trend Micro Apex One SaaS
「Trend Micro Apex One SaaS」は、セキュリティ業界のリーディングカンパニーであるトレンドマイクロ株式会社が提供する、SaaS型の統合エンドポイントセキュリティソリューションです。侵入前の防御から侵入後の検知・対応までをオールインワンで提供する点が大きな特徴です。
主な特徴
- 多層防御: NGAV(機械学習型検索など)、振る舞い検知、Webレピュテーション(不正サイトブロック)といったEPP機能と、高度なEDR機能を単一のエージェントで提供します。これにより、様々な種類の脅威に対して多層的な防御を実現します。
- 仮想パッチ(脆弱性対策): OSやアプリケーションの脆弱性を狙う攻撃を、ネットワークレベルでブロックする「仮想パッチ」機能を搭載しています。正規の修正パッチを適用するまでの間、一時的にデバイスを保護することができるため、緊急性の高い脆弱性への迅速な対応が可能です。
- 幅広い対応範囲: Windows、Mac、Linuxといった主要OSに加え、VDI(仮想デスクトップ)環境にも対応しており、多様なIT環境を保護できます。
このような企業におすすめ
- EPPとEDRの両機能を導入し、侵入前後の対策を包括的に実施したい企業。
- OSやアプリケーションの脆弱性管理に課題を抱えており、パッチ適用までのタイムラグを埋める対策を強化したい企業。
- 既存のトレンドマイクロ製品を利用しており、親和性の高いエンドポイント対策を導入したい企業。
参照:トレンドマイクロ株式会社公式サイト
③ CrowdStrike Falcon
「CrowdStrike Falcon」は、クラウドネイティブなエンドポイントセキュリティのパイオニアであるCrowdStrike, Inc.が提供するプラットフォームです。EDR市場を牽引する存在であり、特に高度な脅威検知能力とインシデント対応能力で世界的に高い評価を受けています。
主な特徴
- クラウドネイティブアーキテクチャ: 最初からクラウドで利用することを前提に設計されており、単一の軽量なエージェントを導入するだけで、NGAV、EDR、脅威ハンティング、デバイス制御など、多彩な機能を利用できます。エンドポイントへの負荷が極めて低いのが特徴です。
- 脅威インテリジェンス「Threat Graph」: 全世界のFalconプラットフォームから収集される膨大なイベントデータをリアルタイムで相関分析する独自のグラフデータベース「Threat Graph」を活用。これにより、他の環境では見過ごされるような微細な攻撃の兆候も高精度で検知します。
- プロアクティブな脅威ハンティング: 専門のアナリストチームが24時間365日体制で顧客環境を監視し、自動検知をすり抜ける可能性のある脅威をプロアクティブに探し出す「脅威ハンティング」サービス(Falcon OverWatch)も提供しています。
このような企業におすすめ
- 高度な標的型攻撃やゼロデイ攻撃への対策を最優先事項と考えている企業。
- インシデント発生時に、専門家による高度な分析や対応支援(MDR)を求めている企業。
- パフォーマンスへの影響を最小限に抑えつつ、最高レベルの保護を実現したい企業。
参照:CrowdStrike, Inc.公式サイト
④ Cybereason EDR
「Cybereason EDR」は、サイバーリーズン・ジャパン株式会社が提供する、AIを活用した分析能力に強みを持つEDRソリューションです。EDRの運用負荷を軽減しつつ、攻撃の全体像を直感的に把握できる点が特徴です。
主な特徴
- 攻撃の全体像を可視化する「MalOp」: Cybereasonの核となるのが「Malicious Operation(MalOp)」という独自の分析エンジンです。個別の不審なイベントを単なるアラートとして表示するのではなく、関連するすべてのアクティビティをAIが自動で相関分析し、一つの攻撃キャンペーンとしてストーリー立てて可視化します。
- 運用負荷の軽減: MalOpにより、セキュリティ担当者は大量のアラートに埋もれることなく、本当に対応すべき重大な攻撃(MalOp)に集中できます。これにより、インシデントのトリアージにかかる時間が大幅に短縮され、運用負荷が軽減されます。
- 直感的なUI: 攻撃の侵入経路、影響範囲、横展開の状況などがグラフィカルなタイムラインで表示されるため、専門家でなくても攻撃の全体像を直感的に理解しやすい設計になっています。
このような企業におすすめ
- EDRを導入したいが、専門の分析官が不足しており運用負荷が懸念される企業。
- インシデント発生時に、迅速に攻撃の根本原因や影響範囲を特定し、的確な対応を行いたい企業。
- 個々のアラート対応ではなく、攻撃の全体像を把握することに重点を置きたい企業。
参照:サイバーリーズン・ジャパン株式会社公式サイト
まとめ
本記事では、現代のビジネス環境に不可欠な「エンドポイントセキュリティ」について、その基本概念から重要視される背景、具体的な対策、そして主要なソリューションの違いまでを包括的に解説しました。
改めて、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- エンドポイントとは、PCやスマートフォン、サーバーなど、ネットワークに接続される末端のデバイス全般を指し、これらをサイバー攻撃から保護するのがエンドポイントセキュリティです。
- 重要性が増す背景には、①テレワークなど働き方の多様化、②サイバー攻撃の巧妙化・高度化、③クラウドサービスの利用拡大という3つの大きな環境変化があります。
- 従来の「境界型セキュリティ」では現代の脅威に対応できず、「何も信頼せず、すべてを検証する」という「ゼロトラストセキュリティ」の考え方が主流になっています。エンドポイントセキュリティは、このゼロトラストを実現するための重要な基盤です。
- 具体的な対策には、侵入前の「予防」を担うEPP/NGAVと、侵入後の「検知・対応」を担うEDRがあり、これらを組み合わせることが理想的な多層防御につながります。
- 製品選定においては、①導入目的の明確化、②自社環境への適合性、③運用体制とサポートの確認という3つのポイントが極めて重要です。
かつてセキュリティ対策は、情報システム部門の専門的な業務と捉えられがちでした。しかし、ビジネスのあらゆる側面がデジタル化された今、セキュリティは事業継続そのものを支える経営課題となっています。特に、社員一人ひとりが利用するエンドポイントは、組織全体のセキュリティレベルを左右する最前線です。
エンドポイントセキュリティは、もはや特別な対策ではなく、現代のビジネスを安全に遂行するための必須の基盤インフラであると認識し、自社の状況に合った最適な対策を継続的に見直し、強化していくことが求められています。