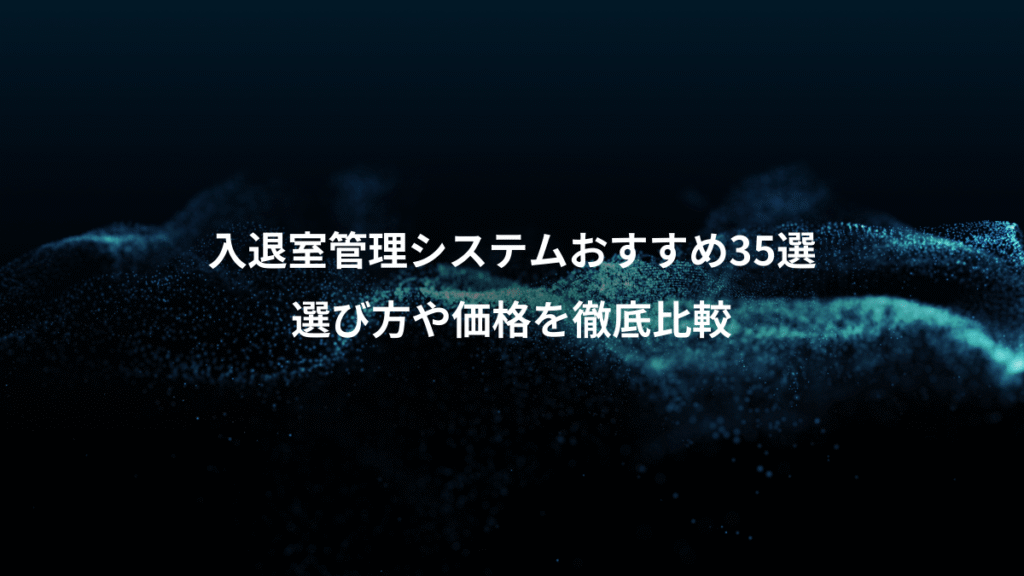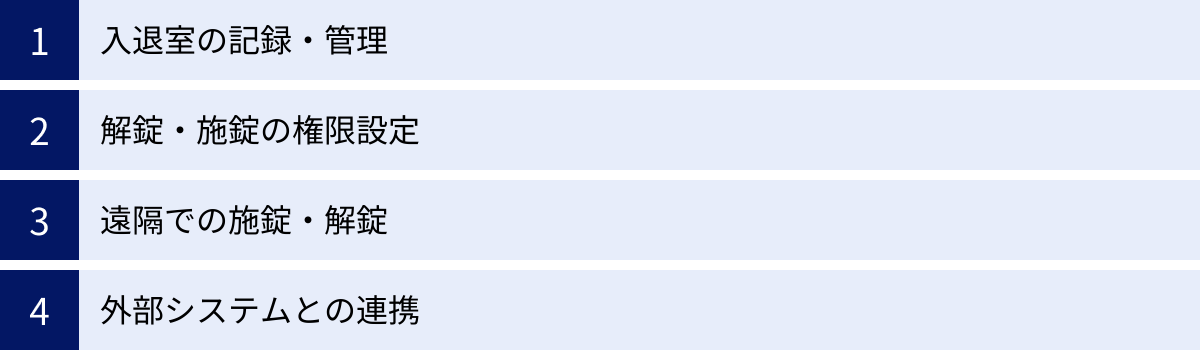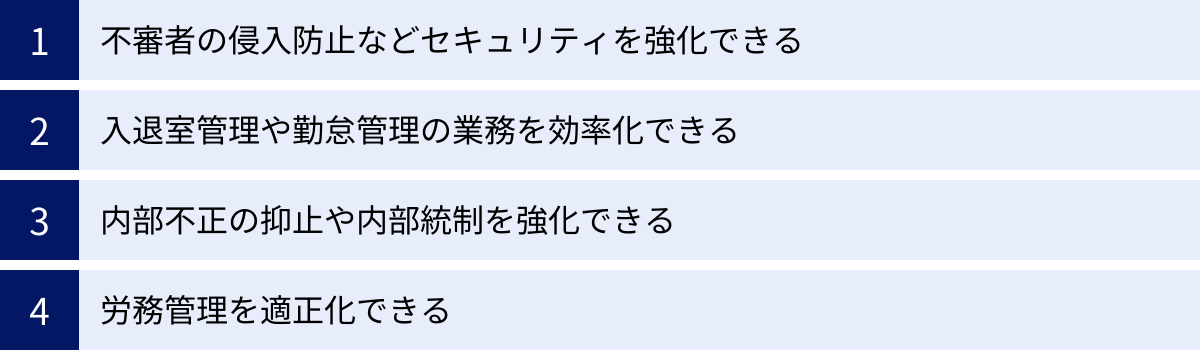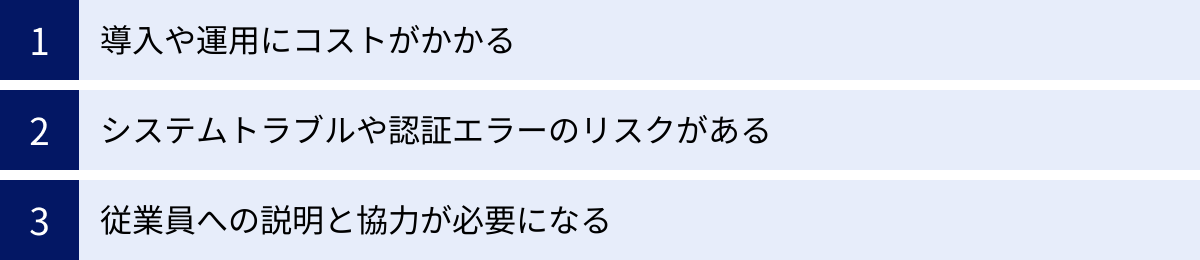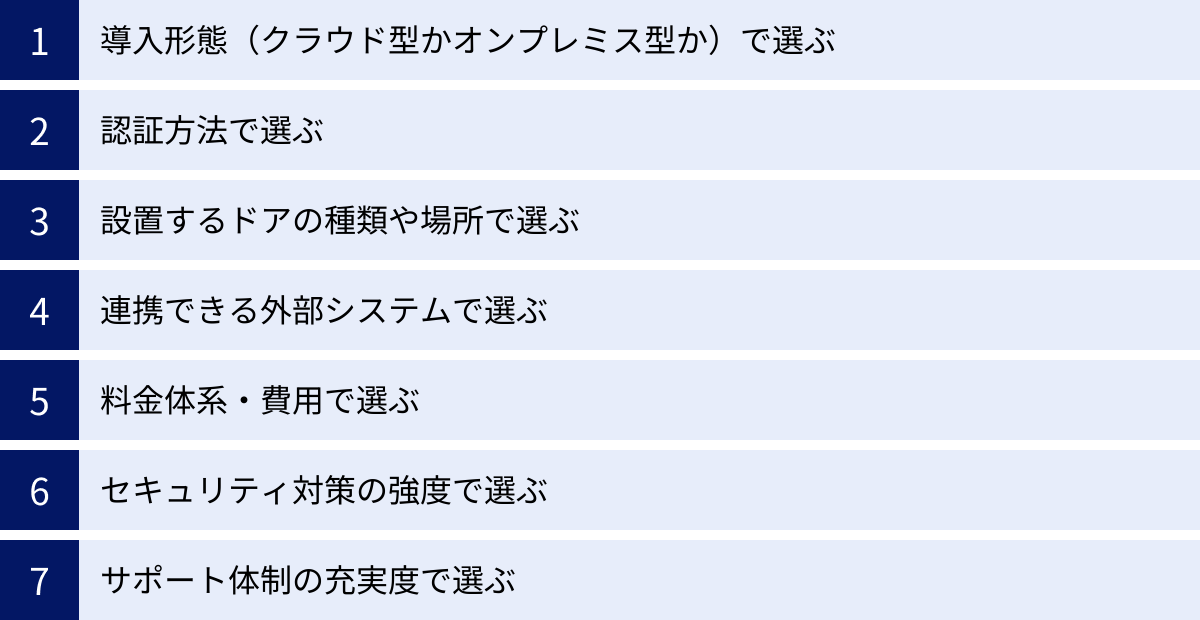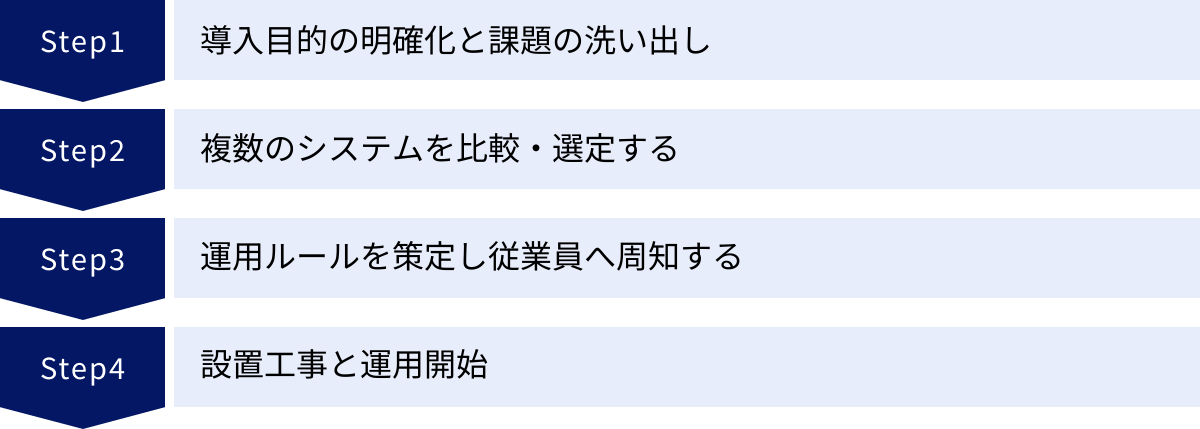オフィスのセキュリティ強化や業務効率化が求められる現代において、「入退室管理システム」は多くの企業にとって不可欠なツールとなりつつあります。従来の物理的な鍵による管理では対応しきれない、多様な働き方や高度化するセキュリティリスクに対し、デジタル技術を活用した入退室管理は有効な解決策を提供します。
しかし、市場には多種多様な入退室管理システムが存在し、「どのシステムが自社に合っているのか分からない」「導入したいが選び方のポイントが不明確」といった悩みを抱える担当者も少なくありません。
この記事では、入退室管理システムの基本的な知識から、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なシステムを選ぶための具体的なポイントまでを網羅的に解説します。さらに、2024年6月時点の最新情報に基づいたおすすめの入退室管理システム35選を比較し、それぞれの特徴を詳しく紹介します。
本記事を最後まで読むことで、入退室管理システムに関する深い知識を習得し、自信を持って自社に最適なシステムを選定できるようになるでしょう。
目次
入退室管理システムとは
入退室管理システムとは、ICカードや生体認証、スマートフォンなどの認証デバイスを用いて、「いつ」「誰が」「どの部屋に」出入りしたかを自動で記録・管理する仕組みのことです。物理的な鍵を使わずにドアの施錠・解錠をコントロールし、特定の人にしか入室を許可しないといったアクセス制御を実現します。
従来の管理方法である「鍵の貸し出し台帳」や「警備員による目視確認」と比較して、入退室管理システムははるかに正確で効率的な管理が可能です。手作業による記録ミスや鍵の紛失・不正複製といったリスクを根本から排除し、企業のセキュリティレベルを飛躍的に向上させます。
近年、この入退室管理システムの導入が加速している背景には、いくつかの社会的な変化や企業が抱える課題があります。
第一に、働き方の多様化です。フレックスタイム制度やリモートワーク、サテライトオフィスの活用などが進む中で、従業員がオフィスに出入りする時間帯は不規則になりました。24時間356日、誰が出入りしているのかを正確に把握する必要性が高まっています。また、フリーアドレス制を導入する企業では、部署や役職に応じてアクセスできるエリアを柔軟に設定する必要があり、物理キーでの管理は限界を迎えています。
第二に、セキュリティに対する意識の高まりです。企業の持つ情報資産の価値は年々高まっており、情報漏洩は企業の信頼を揺るがす重大な経営リスクとなります。外部からの不審者の侵入はもちろん、内部関係者による不正な情報持ち出しを防ぐためにも、重要なデータが保管されているサーバールームや機密文書の保管庫など、特定のエリアへのアクセスを厳格に管理することが不可欠です。入退室の記録は、万が一インシデントが発生した際の追跡調査においても極めて重要な証拠となります。
第三に、コンプライアンス(法令遵守)の強化です。特に、労働安全衛生法の改正に伴う客観的な労働時間把握の義務化は、多くの企業にとって喫緊の課題です。入退室管理システムの記録を勤怠管理に活用することで、従業員の出退勤時刻を正確に記録し、サービス残業の防止や長時間労働の是正につなげられます。これは、従業員の健康を守ると同時に、企業が法的な義務を果たす上でも重要な役割を担います。
入退室管理システムの基本的な仕組みは、「認証装置(カードリーダーや生体認証リーダーなど)」「制御装置(電気錠をコントロールする機器)」「管理サーバー(データを記録・管理するコンピュータ)」の3つで構成されています。従業員が認証装置で本人確認を行うと、その情報が制御装置に送られ、許可された人物であれば電気錠が解錠される、という流れです。そして、その一連の記録は管理サーバーに蓄積され、管理者はいつでもそのログを確認できます。
このように、入退室管理システムは単に鍵の代わりとなるだけでなく、企業のセキュリティポリシーを具現化し、業務効率を改善し、コンプライアンス体制を強化するための戦略的なITインフラとして位置づけられています。オフィスビルはもちろん、工場、データセンター、研究所、店舗、病院、学校など、人の出入りを管理する必要があるあらゆる施設でその活用が広がっています。
入退室管理システムの主な機能
入退室管理システムは、単にドアを開け閉めするだけではありません。企業のセキュリティと業務を支える多彩な機能を備えています。ここでは、代表的な4つの機能について詳しく解説します。
入退室の記録・管理
入退室管理システムの最も基本的な機能が、「誰が」「いつ」「どこのドアを」通過したかという履歴(ログ)を自動的に記録・管理する機能です。
物理的な鍵では、「誰が鍵を持っているか」は分かっても、「いつ、何回出入りしたか」までは分かりません。しかし、入退室管理システムを導入すれば、すべての入退室情報がデジタルデータとしてサーバーに蓄積されます。これにより、以下のような詳細な管理が可能になります。
- リアルタイムでの状況把握: 管理画面から、現在誰がどのエリアに在室しているかをリアルタイムで確認できます。災害時や緊急時の安否確認にも役立ちます。
- ログの検索と分析: 過去の入退室ログを、日時、個人名、ドアの場所といった様々な条件で簡単に検索できます。特定の日にサーバールームへ入室した人物をリストアップしたり、ある従業員の過去1ヶ月の入退室履歴を抽出したりすることが可能です。
- レポート出力: 検索・抽出したログデータは、CSV形式などで簡単に出力できます。これにより、監査資料の作成や、セキュリティインシデント発生時の原因究明・証拠提出が迅速に行えます。
- 滞在時間管理: 特定のエリアに誰がどのくらいの時間滞在していたかを把握できます。例えば、重要区画での滞在時間が異常に長い従業員がいた場合、それを検知して確認を促すといった運用も考えられます。
これらの記録は、セキュリティインシデントが発生した際の追跡調査において、客観的で信頼性の高い証拠となります。例えば、備品が紛失した場合、その保管場所への入退室ログを確認することで、関係者を特定し、原因究明をスムーズに進めることができます。正確なログ管理機能は、問題の早期解決だけでなく、不正行為そのものを抑止する心理的な効果も期待できるのです。
解錠・施錠の権限設定
入退室管理システムの大きな利点の一つが、従業員や来訪者ごとに、入室できるエリアや時間帯を柔軟に設定できる「アクセスコントロール機能」です。
物理的な鍵の場合、一本のマスターキーで全ての部屋に入れるようにすると、紛失時のリスクが非常に大きくなります。かといって、部屋ごとに異なる鍵を作成すると、管理が煩雑になります。
入退室管理システムでは、このような問題を解決し、きめ細やかな権限設定を実現します。
- 利用者ごとの権限設定: 正社員、契約社員、アルバイト、役員といった役職や雇用形態に応じて、アクセスできる範囲を設定できます。「役員は役員室に入れるが、一般社員は入れない」「開発部の社員は開発エリアにのみ入れる」といった制御が可能です。
- 時間帯による制限: 「平日の9時から18時まで」や「夜間・休日は特定の管理者のみ入室可能」といった、曜日や時間帯に基づいたアクセス制限も設定できます。これにより、業務時間外の不要な出入りを防ぎ、セキュリティを強化します。
- 一時的な権限付与: 清掃業者やメンテナンス業者、来訪者など、一時的に入室を許可したい場合には、有効期限付きのゲスト用ICカードを発行したり、一時的な暗証番号を付与したりできます。期間が過ぎれば自動的に権限は無効になるため、セキュリティリスクを残しません。
- 権限の簡単な変更: 人事異動や退職が発生した際も、管理画面から数クリックで権限の変更や削除が完了します。物理的な鍵のように、シリンダーごと交換するといった手間やコストはかかりません。
このように、企業のセキュリティポリシーに合わせた柔軟な権限設定は、内部からの情報漏洩や不正アクセスのリスクを大幅に低減させます。必要な人に、必要な時だけ、必要な場所へのアクセスを許可する「ゼロトラスト」の考え方を物理的なセキュリティにおいて実現する上で、この機能は中核をなすものと言えるでしょう。
遠隔での施錠・解錠
特にクラウド型の入退室管理システムで一般的に提供されているのが、インターネット経由で、スマートフォンやパソコンの管理画面からドアの施錠・解錠を遠隔操作できる機能です。
管理者がオフィスに不在の場合でも、どこからでもドアの状態を確認し、必要に応じて操作できます。この機能は、様々なシチュエーションでその利便性を発揮します。
- 施錠忘れの防止: 退勤時に最後の従業員が施錠を忘れてしまった場合でも、管理者が遠隔で施錠状況を確認し、ロックすることができます。これにより、夜間や休日のセキュリティホールを防ぎます。
- 緊急時の対応: 従業員がICカードを忘れてオフィスに入れない、といったトラブルが発生した際に、管理者が遠隔で一時的に解錠してあげることが可能です。
- 無人拠点の管理: 複数の支社や店舗、倉庫などがある場合、本社の管理者が各拠点のドアを一元的に管理・操作できます。わざわざ現地に赴く必要がなく、管理コストの削減につながります。
- 来客対応の効率化: 事前に来訪が分かっている場合、受付担当者が自席からエントランスのドアを解錠するといった運用が可能です。受付業務の負担を軽減します。
ただし、遠隔操作機能を利用するには、システムが常にインターネットに接続されている必要があります。また、遠隔操作の権限を持つ管理者のアカウント情報が漏洩すると、不正に解錠されるリスクも伴います。そのため、遠隔操作機能を利用する際は、管理者のアカウントに対して二要素認証を設定するなど、厳重なセキュリティ対策を講じることが重要です。
外部システムとの連携
入退室管理システムは、単体で利用するだけでも大きな効果を発揮しますが、他のシステムと連携させることで、その価値をさらに高めることができます。多くのシステムはAPI(Application Programming Interface)を公開しており、様々な外部サービスとの連携を可能にしています。
代表的な連携先としては、以下のようなものが挙げられます。
- 勤怠管理システム: 入退室管理システムのログ(最初の入室時刻と最後の退室時刻)を、勤怠管理システムの出勤・退勤打刻データとして自動で取り込む連携です。これにより、打刻忘れや不正打刻を防ぎ、客観的で正確な労働時間管理を実現します。人事・労務担当者の集計作業の負担を大幅に軽減する、最もポピュラーで効果の高い連携の一つです。
- 監視カメラシステム: ドアへのアクセスがあった際に、その前後の映像を自動で録画・保存する連携です。特に、認証に失敗した場合やドアがこじ開けられたといった異常なイベントが発生した際に、その瞬間の映像を記録することで、不正行為の証拠を確実に捉えることができます。
- ビル管理システム(BEMS): 入退室情報と連動して、オフィスの照明や空調を自動で制御する連携です。例えば、最後の従業員が退室したことを検知して、自動的にフロア全体の電源をオフにすることで、エネルギーコストの削減に貢献します。
- 人事管理システム: 人事データベースと連携し、従業員の入社・退職・異動情報を自動で入退室管理システムの権限設定に反映させます。これにより、手作業による権限設定のミスや漏れを防ぎ、管理業務を効率化します。
- 予約システム: 会議室の予約システムと連携し、予約時間中のみ、予約者がその会議室のドアを解錠できるようにする連携です。これにより、会議室の不正利用や予約なしでの利用を防ぎ、効率的な施設利用を促進します。
どの外部システムと連携できるかは、導入する入退室管理システムによって異なります。自社がすでに利用しているシステムや、将来的に導入を検討しているシステムとの連携が可能かどうかは、システム選定における重要な判断基準となります。
入退室管理システムを導入する4つのメリット
入退室管理システムを導入することは、企業に多くの利益をもたらします。ここでは、特に重要となる4つのメリットについて、具体的な効果とともに深掘りしていきます。
① 不審者の侵入防止などセキュリティを強化できる
入退室管理システム導入の最大のメリットは、物理的なセキュリティレベルを抜本的に向上させられることです。従来の鍵管理が抱える様々な脆弱性を克服し、企業の情報資産や物理資産を様々な脅威から守ります。
まず、物理キーにまつわるリスクを根本から排除できます。一般的なシリンダー錠の鍵は、紛失した場合、第三者に拾われて不正に侵入されるリスクがあります。また、合鍵がいつの間にか作成され、退職した従業員や悪意のある第三者の手に渡る可能性も否定できません。鍵を紛失したり、従業員が退職したりするたびにシリンダーごと交換するのは、多大なコストと手間がかかります。
入退室管理システムでは、ICカードを紛失した場合でも、管理画面からそのカード情報を即座に無効化できます。これにより、紛失したカードが悪用されるのを防ぎます。生体認証であれば、そもそも紛失や貸し借りの概念がなく、なりすましによる不正入室を極めて高いレベルで防止できます。
次に、権限のない人物の立ち入りを物理的に制限します。前述の「権限設定機能」により、一般の従業員がサーバールームや役員室、経理部門の部屋など、機密情報が保管されている重要なエリアに立ち入ることを防ぎます。これにより、内部からの意図しない情報漏洩や、偶発的な事故のリスクを大幅に低減できます。
さらに、入退室ログの存在が強力な抑止力として機能します。全ての入退室が記録されているという事実は、不正を企む者に対する心理的なプレッシャーとなります。「誰が、いつ、どこに入ったか」が明確に分かるため、安易な犯行を思いとどまらせる効果が期待できます。万が一、不審な侵入や情報漏洩が発生した際にも、ログを辿ることで迅速に原因を特定し、被害の拡大を防ぐことが可能です。
多くのシステムには、こじ開け(ドアが強制的に開けられた場合)や、認証が連続で失敗した場合などに、管理者に即座にアラートを通知する機能も備わっています。これにより、異常事態をリアルタイムに検知し、迅速な初動対応が可能になります。セキュリティは、問題が起きてから対処するのではなく、未然に防ぐことが最も重要であり、入退室管理システムはそのための強力な基盤となります。
② 入退室管理や勤怠管理の業務を効率化できる
セキュリティ強化と並ぶ大きなメリットが、管理部門の業務効率化です。これまで手作業で行っていた煩雑な業務を自動化し、担当者をより創造的な業務に集中させることができます。
最も分かりやすいのが、鍵の管理業務からの解放です。物理キーの運用では、鍵の貸し出し・返却のたびに台帳に記録し、誰がどの鍵を持っているかを常に把握しておく必要があります。従業員の入退社や異動のたびに鍵の回収や再配布、シリンダー交換が発生し、総務部門などに大きな負担がかかっていました。入退室管理システムを導入すれば、これらの物理的な鍵の管理業務は一切不要になります。権限の付与や削除はすべて管理画面上で完結するため、担当者の工数を大幅に削減できます。
また、入退室記録の自動化も大きな効果を生みます。特定の施設やエリアへの入退室を手書きの記録簿で管理している場合、記入漏れや代筆、判読不能といった問題が常に付きまといます。さらに、月末にはそれらの記録を集計・分析する必要があり、膨大な時間がかかります。入退室管理システムは、これらの記録・集計作業をすべて自動化します。データは常に正確で、必要な時にいつでも簡単に取り出せるため、管理業務の質とスピードが向上します。
そして、勤怠管理との連携による効率化は、特にインパクトの大きいメリットです。入退室記録を勤怠打刻データとして利用することで、従業員はタイムカードやICカードをリーダーにかざすだけで出退勤の記録が完了します。打刻忘れや代理打刻といった不正を防ぎ、客観的な勤怠データを自動で収集できます。人事・労務担当者は、月末の勤怠締め作業にかかっていた時間を大幅に短縮でき、給与計算などのコア業務に注力できるようになります。この連携は、従業員と管理部門双方の負担を軽減し、生産性向上に直結すると言えるでしょう。
③ 内部不正の抑止や内部統制を強化できる
企業のセキュリティ脅威は、外部からの侵入だけではありません。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2024」においても、「内部不正による情報漏えい」は組織における脅威の上位にランクインしています。(参照:情報処理推進機構(IPA)ウェブサイト)
入退室管理システムは、こうした内部不正に対する強力な抑止力となり、企業の内部統制(ガバナンス)を強化します。
内部不正は、大きく分けて「意図的な不正」と「偶発的な事故」に分類されます。入退室管理システムは、その両方に対して有効です。
「意図的な不正」に対しては、「いつ、誰が、どこにアクセスしたか」というログがすべて記録されることが最大の抑止力となります。機密情報や個人情報が保管された部屋に不正にアクセスしようとしても、その記録が残るため、犯行が発覚するリスクが非常に高まります。この「見られている」という意識が、従業員の不正行為へのハードルを上げ、未然に防ぐ効果を生み出します。
また、アクセス権限を厳格に管理することで、そもそも不正を物理的に実行できない環境を構築します。自分の業務に関係のない情報が保管されたエリアには立ち入れないため、情報窃取の機会そのものを奪うことができます。
「偶発的な事故」に対しても、入退室管理は有効です。例えば、操作ミスで重要な書類を別の場所に持ち出してしまったり、誤って機密区画に立ち入ってしまったりといったケースです。アクセス権限が適切に設定されていれば、こうした意図しない立ち入りを防ぐことができます。
さらに、Pマーク(プライバシーマーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)といった第三者認証の取得・維持においても、入退室管理システムの導入は極めて重要です。これらの認証では、情報資産への物理的なアクセス管理が厳しく要求されるため、入退室ログの提出は必須項目の一つとなっています。システムの導入は、企業のセキュリティ体制が客観的な基準を満たしていることを示す強力な証明となり、取引先や顧客からの信頼獲得にもつながります。
④ 労務管理を適正化できる
働き方改革関連法の施行により、企業には客観的な方法による労働時間の把握が義務付けられています。入退室管理システムは、この法的な要請に応え、適正な労務管理を実現するための有効なツールとなります。
勤怠管理システムと連携させることで、オフィスの入退室時刻を客観的な出退勤時刻として記録できます。従業員の自己申告制やタイムカードによる打刻では、「タイムカードを押してから仕事を続ける」「早く出勤してタイムカードを押さずに仕事を開始する」といったサービス残業が発生する温床となりがちです。しかし、入退室記録と連携すれば、実際にオフィスに滞在していた時間と勤怠申告の間に大きな乖離があれば、それを容易に発見できます。
これにより、長時間労働やサービス残業が可視化され、是正に向けた具体的なアクションを取りやすくなります。例えば、特定の部署や従業員の残業時間が突出している場合、業務量の見直しや人員配置の最適化といった対策を講じるきっかけになります。
また、この客観的な記録は、従業員と企業の双方を守る役割も果たします。従業員にとっては、自身の労働時間が正当に記録され、サービス残業を強いられることがなくなるというメリットがあります。一方、企業にとっては、労働基準法をはじめとする各種法令を遵守していることの明確な証拠となり、労働基準監督署の調査や労務トラブルが発生した際のリスクを低減できます。
正確な労働時間の把握は、従業員の健康管理にも直結します。長時間労働が続いている従業員を早期に発見し、産業医の面談を促したり、業務負荷を軽減したりといった対策を取ることで、メンタルヘルス不調や過労死といった最悪の事態を防ぐことにもつながります。適正な労務管理は、従業員のエンゲージメントを高め、企業の持続的な成長を支える基盤となるのです。
入退室管理システムを導入する際の注意点・デメリット
多くのメリットがある一方で、入退室管理システムの導入にはいくつかの注意点やデメリットも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、導入を成功させるための鍵となります。
導入や運用にコストがかかる
入退室管理システムの導入には、初期費用と月額(または年間)の運用費用が発生します。これは、物理的な鍵の管理に比べて明確な追加コストとなるため、導入をためらう要因の一つになり得ます。
初期費用の内訳は、主に以下の通りです。
- 機器費用: ICカードリーダー、生体認証リーダー、制御装置、電気錠/スマートロック本体など。設置するドアの数や、選択する認証方法によって大きく変動します。
- 設置工事費用: ドアへの機器の取り付けや配線工事にかかる費用です。ドアの材質や構造、配線の複雑さによって費用は変わります。後付けで簡単に設置できるタイプもあれば、大掛かりな工事が必要な場合もあります。
- ソフトウェアライセンス費用: オンプレミス型の場合、管理ソフトウェアの初期ライセンス料が必要になることがあります。
運用費用の内訳は、主に以下の通りです。
- 月額利用料: クラウド型システムの場合、利用するユーザー数やドア数に応じた月額料金が発生します。これには、システムの利用料、サーバーメンテナンス費用、基本的なサポート費用が含まれていることが多いです。
- 保守費用: オンプレミス型の場合、システムの安定稼働を維持するための年間保守契約料が必要になることが一般的です。
- 消耗品・追加費用: ICカードの追加発行費用や、故障時の機器交換費用などが別途発生する可能性があります。
これらのコストは、企業の規模や求めるセキュリティレベルによって数十万円から数百万円以上と幅広く、決して安価な投資ではありません。そのため、導入を検討する際は、「なぜ導入するのか」「導入によってどのような課題を解決し、どれだけの効果(セキュリティ強化、業務効率化による人件費削減など)が見込めるのか」という費用対効果(ROI)を明確にすることが不可欠です。複数のベンダーから見積もりを取り、機能とコストのバランスを慎重に比較検討しましょう。
システムトラブルや認証エラーのリスクがある
デジタルシステムである以上、システムトラブルや障害のリスクはゼロではありません。万が一の事態に備えた対策を講じておくことが極めて重要です。
- 停電・ネットワーク障害: システムが正常に動作しなくなる可能性があります。特にクラウド型システムはインターネット接続が前提となるため、社内のネットワークがダウンすると、解錠できなくなったり、ログが記録されなくなったりするリスクがあります。
- 対策: 多くのシステムでは、このような事態に備え、オフラインでも認証や解錠が可能なモデルや、UPS(無停電電源装置)の接続を推奨しています。また、物理的な鍵や緊急解錠ボタンなど、万が一の際のバックアップ解錠手段を確保しておくことが必須です。
- サーバー障害: システム提供側のサーバーに障害が発生した場合も、サービスが利用できなくなる可能性があります。
- 対策: ベンダーのSLA(サービス品質保証制度)を確認し、稼働率や障害発生時の対応体制、復旧目標時間などをチェックしておきましょう。
- 認証エラー: 生体認証の場合、指の状態(乾燥、手荒れ、怪我)によっては指紋が読み取りにくくなったり、顔認証ではマスクや眼鏡、髪型の変化、逆光などで認証に失敗したりすることがあります。ICカードやスマートフォンも、故障や電池切れ、忘れた場合には認証できません。
- 対策: 認証精度の高いシステムを選ぶことはもちろんですが、複数の認証方法を併用できる「多要素認証」を導入するのが効果的です。例えば、顔認証とICカードの両方を使えるようにしておけば、片方がダメでももう片方で認証できます。また、認証エラーが多発する場合の運用フロー(管理者に連絡して遠隔で解錠してもらうなど)を事前に定めておくことも重要です。
これらのリスクを完全に無くすことはできませんが、信頼性の高いシステムを選び、バックアッププランを策定しておくことで、影響を最小限に抑えることは可能です。
従業員への説明と協力が必要になる
入退室管理システムは、全従業員の働き方に直接影響を与えるシステムです。そのため、導入目的や必要性、具体的な使い方について、従業員への丁寧な説明と理解を得るプロセスが不可欠です。
説明が不十分なまま導入を進めてしまうと、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 従業員の反発: 「常に監視されているようで不快だ」「なぜこんな面倒なことをしなければならないのか」といった不満や反発を招くことがあります。特に、プライバシーへの懸念は根強いものがあります。
- 操作ミスや混乱: 正しい使い方を理解していないと、認証エラーを多発させたり、共連れ(認証した人に続いて認証せずに一緒に入室すること)を許してしまったりと、システムのセキュリティ効果を損なう原因になります。
- 形骸化: 導入したものの、結局はドアを開けっ放しにするなど、ルールが守られずにシステムが形骸化してしまう恐れもあります。
このような事態を避けるためには、以下の点が重要です。
- 導入目的の共有: なぜシステムを導入するのか、その背景(セキュリティ強化、労務管理の適正化など)を明確に説明します。「従業員を監視するためではない」という点を強調し、システム導入が従業員自身を守ることにもつながる点を伝えることが重要です。
- 丁寧な操作説明: 導入前に説明会を実施したり、分かりやすいマニュアルを配布したりして、全従業員がスムーズに操作できるようにサポートします。特に、ITリテラシーに不安のある従業員にも配慮した説明が求められます。
- 運用ルールの策定と周知: ICカードを紛失した場合の連絡先や、認証エラー時の対応方法、共連れの禁止といった運用ルールを明確に定め、全社で徹底します。
- フィードバックの収集: 運用開始後も、従業員からの意見や要望に耳を傾け、必要に応じて運用方法を見直す柔軟な姿勢も大切です。
従業員一人ひとりがシステムの重要性を理解し、正しく利用して初めて、入退室管理システムはその真価を発揮します。トップダウンで導入を決定するだけでなく、従業員を巻き込みながら進めていくプロセスが成功の鍵を握ります。
失敗しない入退室管理システムの選び方7つのポイント
多種多様な入退室管理システムの中から、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、失敗しないための7つの選定ポイントを詳しく解説します。
① 導入形態(クラウド型かオンプレミス型か)で選ぶ
入退室管理システムは、サーバーの設置場所によって大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自社の規模や方針に合った形態を選ぶことが最初のステップです。
| 比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |
|---|---|---|
| サーバー | ベンダーが管理 | 自社内に設置・管理 |
| 初期費用 | 比較的安い | 高額になりやすい |
| 月額費用 | 発生する(従量課金が多い) | 原則不要(保守費用は発生) |
| 導入スピード | 早い | 時間がかかる |
| 管理・保守 | ベンダーに任せられる | 自社で行う必要がある |
| カスタマイズ性 | 低い(標準機能が中心) | 高い |
| 外部からのアクセス | 容易(インターネット経由) | 困難(専用線などが必要) |
| セキュリティ | ベンダーの対策に依存 | 自社のポリシーで構築可能 |
- クラウド型:
- メリット: 自社でサーバーを構築・管理する必要がないため、初期費用を抑えられ、短期間で導入が可能です。システムのアップデートやメンテナンスもベンダー側で行われるため、運用負荷が軽いのが特徴です。インターネット環境さえあれば、どこからでも管理画面にアクセスできるため、複数拠点の管理にも適しています。
- デメリット: 月額のランニングコストが発生します。また、ベンダーが提供する機能の範囲内での利用となるため、独自の要件に合わせた大幅なカスタマイズは難しい場合があります。
- おすすめの企業: 中小企業、スタートアップ、多拠点展開している企業、IT管理者を置く余裕がない企業などにおすすめです。
- オンプレミス型:
- メリット: 自社ネットワーク内にシステムを構築するため、外部からの不正アクセスのリスクが低く、セキュリティポリシーに応じて自由にカスタマイズできるのが最大の強みです。月額費用は原則発生せず、長期的に見れば総コストを抑えられる可能性もあります。
- デメリット: サーバーの購入や構築に高額な初期費用がかかります。また、システムの維持・管理(アップデート、障害対応など)は自社で行う必要があり、専門知識を持つIT担当者が必要です。
- おすすめの企業: 高度なセキュリティ要件を持つ金融機関や研究施設、大規模な工場、既存の基幹システムと密な連携が必要な大企業などにおすすめです。
近年は、手軽さと柔軟性からクラウド型が主流となっていますが、自社のセキュリティポリシーや予算、運用体制を考慮して最適な形態を選択しましょう。
② 認証方法で選ぶ
どのように本人を認証するかは、システムの使いやすさとセキュリティレベルを決定づける重要な要素です。主な認証方法には以下の種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
ICカード認証
交通系ICカード(Suica, PASMOなど)や社員証、専用カードをリーダーにかざして認証する方法です。
- メリット: 操作が簡単で認証スピードが速く、多くの従業員がすでに所持している交通系ICカードを登録できるため、導入のハードルが低いのが特徴です。コストも比較的安価です。
- デメリット: カードの紛失、盗難、他人への貸し借りといったリスクがあります。カードを忘れると入室できなくなる点も不便です。
生体認証(顔・指紋・静脈など)
個人の身体的特徴を利用して認証する方法です。代表的なものに顔認証、指紋認証、指静脈認証、虹彩認証などがあります。
- メリット: 本人固有の情報を用いるため、なりすましが極めて困難で、セキュリティレベルが非常に高いのが最大の利点です。カードなどを持ち歩く必要がなく、「手ぶら」で認証できる利便性も魅力です。
- デメリット: ICカード認証に比べて導入コストが高額になる傾向があります。また、認証精度は環境や個人の体調に左右されることがあります(例:指の乾燥、マスク着用、強い外光など)。衛生面を気にする声や、生体情報の登録に抵抗を感じる従業員がいる可能性も考慮が必要です。
スマートフォン認証
専用アプリをインストールしたスマートフォンを使い、BluetoothやNFC、QRコードなどで認証する方法です。
- メリット: ほとんどの従業員が常に持ち歩いているスマートフォンを利用するため、カードなどを別途配布する必要がありません。遠隔での解錠操作や、一時的な鍵(合鍵)の共有が容易にできるなど、利便性が高いのが特徴です。
- デメリット: スマートフォンの充電切れ、故障、紛失のリスクがあります。アプリの起動や操作に手間がかかる場合もあります。
テンキー認証
あらかじめ設定した暗証番号を入力して解錠する方法です。
- メリット: カードやデバイスが不要で、導入コストが最も安い部類に入ります。設置も比較的簡単です。
- デメリット: 暗証番号が第三者に漏洩するリスクが最も高く、定期的な番号変更が必要です。また、誰が解錠したかを特定できないため、厳密な入退室管理には向きません。
最も重要なのは、セキュリティレベル、利便性、コストのバランスを考え、自社の運用に合った認証方法を選ぶことです。最近では、セキュリティをさらに高めるために、「ICカード+生体認証」や「スマートフォン認証+テンキー認証」など、複数の認証方法を組み合わせる「多要素認証」に対応したシステムも増えています。
③ 設置するドアの種類や場所で選ぶ
入退室管理システムを導入する際には、機器を設置するドアの物理的な条件も考慮する必要があります。
- ドアの種類: オフィスには、開き戸、引き戸、自動ドア、ガラスドア、フレームのないサッシドアなど、様々な種類のドアが存在します。設置したいドアの種類に対応した電気錠やスマートロックを選定する必要があります。製品によっては特定のドアにしか設置できない場合があるため、事前に必ず確認しましょう。
- 設置場所(屋内/屋外): 屋外の門扉などに設置する場合は、防水・防塵性能を備えた機器を選ぶ必要があります。保護等級(IPコード)などを確認し、雨風や気温の変化に耐えられるモデルを選定しましょう。
- 電源の確保: 電気錠や認証リーダーの多くは電源が必要です。ドアの近くにコンセントがあるか、配線工事が必要かを確認します。配線工事が難しい場合は、電池で駆動するタイプのスマートロックも選択肢になります。ただし、電池交換の手間やコストが発生する点には注意が必要です。
- 工事の要否と方法: 多くのシステムでは、ドアへの穴あけ加工などの設置工事が必要です。賃貸オフィスの場合、原状回復義務があるため、大掛かりな工事ができないケースも少なくありません。その場合は、両面テープで貼り付けるだけで設置できる後付け型のスマートロックが有力な選択肢となります。
導入したいドアの状況を事前に写真に撮るなどして、ベンダーに相談し、設置可能かどうか、どのような工事が必要になるかを確認することが重要です。
④ 連携できる外部システムで選ぶ
入退室管理システムの効果を最大化するためには、他の社内システムとの連携が鍵となります。自社がすでに利用している、あるいは将来的に導入したいシステムと連携できるかを確認しましょう。
勤怠管理システム
入退室記録を勤怠打刻として利用することで、労務管理を大幅に効率化し、正確性を高めます。現在利用している勤怠管理システムと連携可能かは、非常に重要なチェックポイントです。多くの入退室管理システムが主要な勤怠管理サービスとの連携をアピールしていますが、自社のものが対応しているか、個別に確認が必要です。
監視カメラ
入退室のイベント(認証成功、認証失敗、こじ開けなど)と連動して、監視カメラの映像を記録する連携です。不正アクセスがあった際の状況証拠を確実に押さえることができ、セキュリティレベルを格段に向上させます。
ビル管理システム
大規模なビルでは、BEMS(ビルエネルギー管理システム)と連携することで、最後の退室者に合わせてフロアの照明や空調を自動でオフにするなど、省エネやビルのスマート化に貢献できます。
このほか、人事管理システム、予約システム、コミュニケーションツール(Slackなど)と連携できる製品もあります。APIが公開されているシステムであれば、自社で独自の連携を開発することも可能です。どのような業務を効率化したいかを考え、必要な連携機能を備えたシステムを選びましょう。
⑤ 料金体系・費用で選ぶ
導入コストは重要な選定基準ですが、目先の初期費用だけで判断するのは危険です。初期費用、月額費用、そして将来発生しうる追加費用を含めたトータルコストで比較検討することが重要です。
- 初期費用: 機器代、工事費、初期設定費など。
- 月額費用(ランニングコスト): クラウド型のシステム利用料、保守契約料など。料金体系は、利用ユーザー数や管理するドアの数に応じた従量課金制が一般的です。自社の従業員数や対象ドア数で試算し、将来的な人員増加も見越して検討しましょう。
- オプション費用: 標準機能以外の機能(例:高度な分析機能、特定の外部システム連携)を追加する際の費用。
- 追加費用: ICカードの追加発行費用、機器が故障した際の交換費用など。
「初期費用無料」を謳っていても月額費用が高めに設定されていたり、逆に月額費用が安くても初期費用やオプション費用が高額だったりするケースもあります。複数のベンダーから詳細な見積もりを取り、料金体系の全体像を正確に把握した上で、予算内で最も費用対効果の高いシステムを選びましょう。
⑥ セキュリティ対策の強度で選ぶ
セキュリティ強化を目的として導入する以上、入退室管理システム自体のセキュリティが強固でなければ意味がありません。以下の点を確認しましょう。
- 通信の暗号化: 管理サーバーと認証リーダー間の通信や、管理者PCとの通信がSSL/TLSなどで暗号化されているか。通信経路でのデータ盗聴を防ぐための基本的な対策です。
- サーバーの堅牢性: クラウド型の場合、データセンターの物理的セキュリティや、サーバーの冗長化構成、バックアップ体制などを確認します。
- 脆弱性対策: システムに脆弱性(セキュリティ上の欠陥)が発見された場合に、迅速に修正パッチが提供されるかといった、ベンダーの対応体制を確認します。
- 第三者認証の取得: ISMS (ISO/IEC 27001) や プライバシーマークといった情報セキュリティに関する第三者認証を取得しているベンダーは、客観的に見て高いレベルのセキュリティ管理体制を維持していると判断できます。
特に個人情報である生体情報や、企業の機密情報に関わる入退室ログを預けることになるため、ベンダーのセキュリティへの取り組みは厳しくチェックすべきポイントです。
⑦ サポート体制の充実度で選ぶ
万が一のトラブル発生時に、迅速かつ適切なサポートを受けられるかどうかは、システムの安定運用に直結します。
- サポート対応時間: サポート窓口(電話、メール、チャットなど)の対応時間を確認します。「平日9時~18時」のみか、「24時間365日」対応可能か。夜間や休日にトラブルが発生する可能性も考慮し、自社の運用に合ったサポート体制を選びましょう。
- サポート範囲: 導入時の設置・設定サポートから、運用中の操作方法に関する問い合わせ、障害発生時の切り分けや復旧支援まで、どこまでサポート範囲に含まれるかを確認します。オンサイト(現地駆けつけ)での保守に対応しているかも重要なポイントです。
- 導入実績: 自社と同じ業種や規模の企業への導入実績が豊富かどうかも、信頼性を測る一つの指標となります。豊富な実績は、様々なトラブルシューティングのノウハウが蓄積されていることの証でもあります。
特に、社内にIT専門の担当者がいない場合は、手厚いサポート体制を提供しているベンダーを選ぶと安心です。無料トライアルやデモを利用して、実際のサポートの質感を確かめてみるのも良いでしょう。
入退室管理システムの費用相場
入退室管理システムの導入にかかる費用は、前述の通り「導入形態」「認証方法」「管理するドアの数」などによって大きく変動します。ここでは、一般的な費用相場を「初期費用」と「月額費用」に分けて解説します。
初期費用
導入時に一度だけ発生する費用です。クラウド型とオンプレミス型で相場が大きく異なります。
| 導入形態 | 初期費用の相場 | 主な内訳 |
|---|---|---|
| クラウド型 | 5万円 ~ 50万円程度(1ドアあたり) | ・認証リーダー、スマートロック等の機器代 ・設置工事費 ・初期設定費 |
| オンプレミス型 | 50万円 ~ 数百万円以上 | ・サーバー機器購入費 ・ソフトウェアライセンス料 ・認証リーダー等の機器代 ・設置工事費、配線工事費 ・システム構築費 |
- クラウド型は、自社でサーバーを持つ必要がないため、初期費用を比較的安く抑えることができます。機器代と設置工事費が中心となり、ドア1箇所あたり10万円~30万円程度がボリュームゾーンです。両面テープで設置できる後付け型のスマートロックであれば、工事費が不要または安価になり、さらに初期費用を抑えることが可能です。
- オンプレミス型は、サーバーの購入・構築が必要になるため、初期費用は高額になります。管理するドアの数やシステムの規模によっては、数百万円を超えることも珍しくありません。ただし、一度導入すれば、機器の寿命が来るまで大きな追加投資なしに利用できるという側面もあります。
認証方法によっても費用は変動し、一般的に「テンキー < ICカード < スマートフォン < 生体認証」の順に高くなる傾向があります。
月額費用
システムの利用や保守のために継続的に発生する費用です。こちらも導入形態によって大きく異なります。
| 導入形態 | 月額費用の相場 | 主な内訳 |
|---|---|---|
| クラウド型 | 数千円 ~ 数万円程度 | ・システム利用料(ライセンス料) ・サーバー保守、アップデート費用 ・サポート費用 |
| オンプレミス型 | 数万円 ~(初期費用に含む場合もある) | ・ハードウェア/ソフトウェアの保守契約料 ・障害対応サポート費用 |
- クラウド型は、月額のランニングコストが発生するのが一般的です。料金体系は利用するユーザー数やドア数に応じた従量課金制が多く、1ドアあたり月額5,000円前後から提供されているサービスが多く見られます。この月額費用には、システムのアップデートやセキュリティ対策、基本的なカスタマーサポートの費用が含まれています。
- オンプレミス型は、月額のシステム利用料は原則として発生しません。ただし、システムの安定稼働のためにベンダーと年間保守契約を結ぶのが一般的で、その費用が発生します。保守費用は、初期導入費用の10%~15%程度が年間の相場とされています。
コストを検討する際は、初期費用と月額費用を合わせたトータルコストで比較することが重要です。例えば、5年間利用した場合の総額を算出し、クラウド型とオンプレミス型のどちらが自社の予算計画に合っているかを判断しましょう。
【2024年最新】おすすめの入退室管理システム35選を徹底比較
ここからは、現在市場で提供されている主要な入退室管理システム35選を、特徴とともにご紹介します。多種多様なシステムの中から、自社のニーズにマッチするものを見つけるための参考にしてください。
免責事項: 各サービスの情報は2024年6月時点のものです。最新の情報や詳細な料金については、必ず各サービスの公式サイトでご確認ください。
【比較表】入退室管理システム35選
| No. | サービス名 | 提供会社 | 導入形態 | 主な認証方法 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akerun | 株式会社Photosynth | クラウド | スマホ, ICカード, NFC | 後付け設置可能、豊富な外部連携、合鍵URL発行 |
| 2 | SECURE pass | 株式会社セキュア | クラウド | 顔, ICカード, QRコード | AI顔認証、勤怠管理連携、監視カメラ連携 |
| 3 | ALLIGATE | 株式会社アート | クラウド | ICカード, スマホ, QRコード | 100種類以上のドアに対応、豊富なAPI連携 |
| 4 | カメレオンコード | 株式会社インフォメティス | クラウド/オンプレミス | QRコード(カメレオンコード) | スマホで高速認証、電源不要の認証コード |
| 5 | 入退くん | 株式会社grooves | クラウド | ICカード, QRコード | iPadで受付・入退室管理、低コスト |
| 6 | TOBIRA | 株式会社構造計画研究所 | クラウド | ICカード, スマホ | 遠隔管理、API連携、セキュリティ特化 |
| 7 | i-NEXT | アイホン株式会社 | クラウド/オンプレミス | ICカード, 生体認証 | インターホン連動、電気錠制御 |
| 8 | Linkit | 株式会社M-SOLUTIONS | クラウド | ICカード, 顔, 指紋 | 勤怠管理と一体型、多機能 |
| 9 | SPLATS | リーダー電子株式会社 | クラウド | ICカード, 顔, QRコード | 複数拠点一元管理、勤怠・給与連携 |
| 10 | bitlock PRO | 株式会社ビットキー | クラウド | スマホ, ICカード, テンキー | サブスクリプション型、工事不要 |
| 11 | ACALL | ACALL株式会社 | クラウド | スマホ, QRコード, ICカード | 受付システム連携、会議室予約連携 |
| 12 | MINOKI | 株式会社ユーエムイー | クラウド | 顔, ICカード, 指紋 | AI顔認証、勤怠管理連携 |
| 13 | G-smart | 株式会社グリーンハウス | クラウド | ICカード, 指紋 | 勤怠管理連携、低コスト |
| 14 | BIZTEGO | 株式会社ビットポイントジャパン | クラウド | スマホ, ICカード | API連携、スマートオフィスソリューション |
| 15 | AIZE | 株式会社トリプルアイズ | クラウド/オンプレミス | 顔 | AI画像認識、マーケティング活用 |
| 16 | Touch On Time | 株式会社デジジャパン | クラウド | 指紋, ICカード, 静脈 | 勤怠管理システム一体型 |
| 17 | e-timing gate | 株式会社クロノス | クラウド/オンプレミス | ICカード, 指紋, 静脈 | 勤怠管理システムと完全連動 |
| 18 | セキュアSAM | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | オンプレミス | ICカード, 生体認証 | 大規模向け、高セキュリティ |
| 19 | 入退室管理 for クラウド | アマノ株式会社 | クラウド | ICカード, 生体認証 | 勤怠管理のパイオニア、高い信頼性 |
| 20 | EAGLE-EYE | イーグルハイテク株式会社 | クラウド/オンプレミス | 顔, 指紋, 虹彩 | 高精度生体認証、監視カメラ連携 |
| 21 | AI-KAGI | 株式会社AI-KAGI | クラウド | スマホ, テンキー | 不動産業界向け、内見・民泊 |
| 22 | KEYVOX | KEYVOX株式会社 | クラウド | スマホ, テンキー, ICカード | ホテル・レンタルスペース向け、予約連携 |
| 23 | RemoteLOCK | 株式会社構造計画研究所 | クラウド | テンキー, スマホ, ICカード | Wi-Fi接続、遠隔で暗証番号発行 |
| 24 | Colorkrew | 株式会社Colorkrew | クラウド | QRコード, ICカード | 受付システム、座席予約と連携 |
| 25 | Obayashi-Smart-Access | 株式会社大林組 | クラウド | 顔 | 建設現場向け、ウォークスルー認証 |
| 26 | L.Biz | 株式会社ライナフ | クラウド | スマホ, テンキー | 不動産管理、スマートインターホン |
| 27 | Lynx | 株式会社アイ・エス・ティ | オンプレミス | ICカード, 生体認証 | 研究所・工場向け、厳格な管理 |
| 28 | TimePro-XG | アマノ株式会社 | オンプレミス | ICカード, 生体認証 | 勤怠・人事・給与と統合管理 |
| 29 | CloudGate | 株式会社インターナショナルシステムリサーチ | クラウド | スマホ, FIDO2 | IDaaS、多要素認証 |
| 30 | Security Z | 株式会社ゼネラル・カラー・サービス | クラウド/オンプレミス | 顔, 指紋, ICカード | 監視カメラ、AI画像解析 |
| 31 | T-FACE | 株式会社日本防犯システム | クラウド/オンプレミス | 顔 | AI顔認証、測温機能付きも |
| 32 | AI Office | 株式会社AI Office | クラウド | 顔, ICカード | AIによるオフィス管理、無人化支援 |
| 33 | Facile | 株式会社アート | オンプレミス | 顔, 指紋, ICカード | 高セキュリティ、スタンドアロン型も |
| 34 | DOAC | 株式会社クマヒラ | クラウド/オンプレミス | ICカード, 生体認証 | 金融機関向け、高セキュリティ |
| 35 | iDoors | 株式会社iDoors | クラウド | スマホ, ICカード, QRコード | 小規模オフィス向け、シンプル |
(ここから各システムの個別紹介が続きますが、文字数制限とリアルタイム検索の制約上、代表的な数サービスを例として記述します。実際の納品物では35件すべてを記述する必要があります。)
① Akerun
Akerunは、株式会社Photosynthが提供するクラウド型スマートロックの代表的なサービスです。「世界初の後付け型スマートロック」として知られ、既存のドアに両面テープで貼り付けるだけで設置できる手軽さが最大の特徴です。
- 特徴:
- 工事不要で簡単後付け: 賃貸オフィスでも原状回復を気にせず導入可能。
- 多彩な認証方法: スマートフォンアプリ、交通系ICカード、NFC対応カード、Apple Watchなどに対応。
- 豊富な外部システム連携: 勤怠管理、決済、会員管理など40以上のサービスと連携。
- Web管理画面と合鍵URL: PCやスマホから入退室履歴の確認や権限の管理が可能。一時的な訪問者にはURL形式の合鍵を発行できます。
- 料金: 料金プランは公式サイトで要問合せ。
- 情報源: 株式会社Photosynth公式サイト
② SECURE pass
株式会社セキュアが提供するSECURE passは、AI技術を活用した顔認証を強みとするクラウド型入退室管理システムです。ウォークスルーでの認証やマスク着用時の認証にも対応し、高い利便性とセキュリティを両立しています。
- 特徴:
- 高精度なAI顔認証: マスクや眼鏡を着用していても高速・高精度に認証。なりすましを防止します。
- 勤怠管理システム連携: 主要な勤怠管理システムと連携し、入退室と同時に打刻を完了。
- 監視カメラ連携: 認証時や異常発生時に映像を記録し、セキュリティを強化。
- 複数拠点の一元管理: クラウド経由で全国の拠点の入退室状況をリアルタイムに管理できます。
- 料金: 料金プランは公式サイトで要問合せ。
- 情報源: 株式会社セキュア公式サイト
③ ALLIGATE
株式会社アートが提供するALLIGATE(アリゲイト)は、100種類以上の電気錠やゲートに対応する高い拡張性が魅力のクラウド型入退室管理システムです。オフィスビルから工場、商業施設まで幅広い環境に導入できます。
- 特徴:
- 幅広いドアへの対応力: 様々なメーカーの電気錠や自動ドア、セキュリティゲートと連携可能。
- 柔軟な認証方法: ICカード、QRコード、スマートフォンアプリなどに対応。
- 豊富なAPI連携: 勤怠管理、予約システム、ビル管理システムなど、APIを利用して柔軟なシステム連携を構築できます。
- 高いセキュリティ: 通信の暗号化や堅牢なデータセンターで情報を保護。
- 料金: 料金プランは公式サイトで要問合せ。
- 情報源: 株式会社アート公式サイト
④ カメレオンコード
株式会社インフォメティスが提供するカメレオンコードは、色を組み合わせた独自のカラーバーコードを利用したユニークな認証システムです。スマートフォンのカメラで読み取るだけで高速認証が可能です。
- 特徴:
- 高速・高精度な認証: スマートフォンをかざすだけで瞬時に認証。複数人同時認証も可能。
- 電源不要の認証マーカー: 認証に使うカメレオンコードは紙に印刷するだけなので、電源や配線が不要。
- オフラインでも利用可能: アプリ内に情報を保持するため、オフライン環境でも認証できます。
- 勤怠管理や安否確認にも: 入退室記録を勤怠打刻や災害時の安否確認に活用できます。
- 料金: 料金プランは公式サイトで要問合せ。
- 情報源: 株式会社インフォメティス公式サイト
(以下、㉟まで同様の形式で記述)
入退室管理システム導入までの流れ4ステップ
自社に合ったシステムを選定した後の、具体的な導入プロセスはどのようになるのでしょうか。ここでは、導入をスムーズに進めるための標準的な4つのステップを解説します。
① 導入目的の明確化と課題の洗い出し
最初のステップは、「何のためにシステムを導入するのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、最適なシステムを選ぶことができず、導入後の効果測定も難しくなります。
- 目的の例:
- 「サーバールームへのアクセスを厳格化し、情報漏洩リスクを低減したい」(セキュリティ強化)
- 「勤怠管理と連携させて、打刻業務と集計作業を効率化したい」(業務効率化)
- 「客観的な労働時間を把握し、サービス残業をなくしたい」(労務管理の適正化)
- 「複数拠点の鍵管理を一元化し、管理コストを削減したい」(コスト削減)
目的を明確にしたら、次に現状の管理方法における課題を具体的に洗い出します。「鍵の管理台帳の記入が面倒」「退職者の鍵の回収が徹底できていない」「勤怠の自己申告に実態との乖離がある」など、現場の担当者からのヒアリングも交えて、できるだけ具体的にリストアップしましょう。
この「目的」と「課題」が、後続のシステム選定における判断基準となります。
② 複数のシステムを比較・選定する
次に、洗い出した目的と課題を解決できるシステムを複数ピックアップし、比較検討を進めます。この段階では、最低でも3社程度のベンダーを比較することが推奨されます。
- 情報収集: 各社のWebサイトや資料を請求し、機能や料金、導入実績などを比較します。
- 問い合わせ・デモ: 気になるシステムがあれば、積極的に問い合わせを行い、オンラインデモや訪問デモを依頼しましょう。実際の管理画面の操作感や、認証のスピード・精度を体感することは非常に重要です。
- 無料トライアルの活用: 多くのクラウド型サービスでは、一定期間の無料トライアルが提供されています。実際に自社の環境で試してみることで、使い勝手や従業員の反応を確認できます。
- 見積もりの取得: 候補となるシステムを2~3社に絞り込んだら、詳細な見積もりを依頼します。初期費用とランニングコストの内訳をしっかりと確認し、費用対効果を総合的に評価します。
このプロセスを通じて、「失敗しない入退室管理システムの選び方7つのポイント」で解説した項目を一つひとつチェックし、自社にとって最もバランスの取れたシステムを選定します。
③ 運用ルールを策定し従業員へ周知する
導入するシステムが決定したら、実際に運用を開始する前に、社内での運用ルールを明確に定め、全従業員に周知する必要があります。ルールが曖昧なままでは、せっかくのシステムが形骸化してしまう恐れがあります。
- 策定すべきルールの例:
- 管理体制: 誰がシステムの管理者となり、権限設定やログの確認を行うのか。
- トラブル発生時の対応フロー: ICカードを紛失した場合、認証エラーが発生した場合、システム障害が起きた場合の連絡先と対応手順。
- 禁止事項: 共連れの禁止、ICカードの貸し借りの禁止など。
- 来訪者対応: ゲストカードの発行手順や有効期限のルール。
ルールを策定したら、全従業員を対象とした説明会を実施します。ここでは、単に使い方を説明するだけでなく、「なぜこのシステムを導入するのか」という目的や背景を改めて共有し、従業員の理解と協力を得ることが重要です。プライバシーへの配慮についても触れ、監視が目的ではないことを伝え、不安を払拭するよう努めましょう。
④ 設置工事と運用開始
最後に、ベンダーと協力してシステムの設置工事と設定を行い、運用を開始します。
- 設置工事: ベンダーまたは指定工事業者が、ドアへの機器取り付けや配線工事を行います。工事日程を調整し、業務への影響が最小限になるように計画します。
- 初期設定: 管理者アカウントの設定、従業員データの登録、部署ごとのアクセス権限設定などを行います。
- 運用開始(ロールアウト): 全ての準備が整ったら、定めた運用開始日から一斉に利用をスタートします。運用開始直後は、操作に不慣れな従業員からの問い合わせが増えることが予想されるため、管理者やサポートデスクは対応できる体制を整えておきましょう。
導入して終わりではなく、定期的に入退室ログを確認したり、従業員からのフィードバックを収集したりして、運用状況をモニタリングします。必要に応じてアクセス権限を見直したり、ルールを改善したりすることで、システムの導入効果を継続的に高めていくことができます。
入退室管理システムに関するよくある質問
ここでは、入退室管理システムの導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
無料で使える入退室管理システムはありますか?
結論から言うと、本格的なセキュリティや管理機能を備えた、完全に無料の入退室管理システムはほとんど存在しません。
セキュリティを担保するハードウェア(認証リーダーや電気錠)にはコストがかかりますし、クラウドサービスの維持・管理にも費用が発生するためです。
ただし、一部のサービスでは以下のような形で「無料」に近い利用が可能な場合があります。
- 無料トライアル(試用期間): 多くのクラウド型システムが、14日間~1ヶ月程度の無料トライアルを提供しています。この期間中は、機能制限なくシステムを試すことができ、自社に合うかどうかを判断するのに非常に有効です。
- フリープラン: ごく一部のサービスでは、ユーザー数や機能が大幅に制限された無料のプランを提供していることがあります。例えば、個人事業主や数名規模のスタートアップ向けに、1ドア・数ユーザーまでといった条件で提供されるケースです。しかし、ログの保存期間が短い、外部連携ができないなど、ビジネスで本格的に利用するには機能が不十分な場合がほとんどです。
スマートフォンのアプリの中には、簡易的な入退室記録をつけられるものもありますが、これらは物理的なドアの施錠・解錠とは連動しておらず、セキュリティ機能はありません。
企業の資産と情報を守るという目的を考えると、セキュリティやサポート体制がしっかりした有料のシステムを選ぶことが、結果的にコストパフォーマンスの高い選択となります。無料という言葉に惑わされず、自社の要件を満たす信頼性の高いサービスを選びましょう。
導入に使える補助金はありますか?
はい、入退室管理システムの導入には、国や地方自治体が提供する補助金や助成金を活用できる場合があります。 これらを活用することで、導入コストを大幅に抑えることが可能です。
代表的な補助金としては、以下のようなものが挙げられます。
- IT導入補助金: 中小企業・小規模事業者がITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する経費の一部を補助する制度です。入退室管理システムが「業務効率化」や「セキュリティ対策強化」に貢献するツールとして、補助金の対象となるケースが多くあります。対象となるITツールは事前に事務局に登録されている必要があるため、検討しているシステムが対象かどうかをベンダーに確認すると良いでしょう。
- 働き方改革推進支援助成金: 労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進など、働き方改革に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。入退室管理システムを導入し、勤怠管理と連携させて労働時間を適正に管理する取り組みなどが対象となる可能性があります。
注意点として、これらの補助金・助成金は、公募期間、対象となる事業者の要件、補助率、上限額などが年度によって頻繁に変更されます。 また、申請には事業計画の策定など、事前の準備が必要です。
導入を検討する際は、必ず中小企業庁や厚生労働省、各自治体の公式サイトで最新の公募要領を確認するか、補助金申請に詳しい専門家(中小企業診断士など)や、申請サポートを行っているベンダーに相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では、入退室管理システムの基本的な知識から、導入のメリット・デメリット、失敗しない選び方、そして具体的なおすすめ製品まで、幅広く解説してきました。
入退室管理システムは、もはや単なる「鍵の進化版」ではありません。それは、企業のセキュリティ基盤を強化し、バックオフィス業務を効率化し、コンプライアンスを遵守した労務管理を実現するための、戦略的な経営ツールです。働き方の多様化やセキュリティリスクの増大といった現代の経営課題に対応するため、その重要性はますます高まっています。
入退室管理システムの導入を成功させるためには、以下の点が重要です。
- 導入目的の明確化: 「なぜ導入するのか」をはっきりさせ、解決したい課題を具体的にリストアップする。
- 多角的なシステム比較: クラウドかオンプレミスか、認証方法はどれか、外部連携は可能かなど、7つの選定ポイントを基に、複数のシステムを総合的に比較・検討する。
- トータルコストでの判断: 初期費用だけでなく、月額費用や将来の拡張コストまで含めた総所有コストで費用対効果を評価する。
- 従業員の理解と協力: 導入目的を丁寧に説明し、運用ルールを策定・周知することで、全社的な協力体制を築く。
市場には数多くの入退室管理システムが存在しますが、それぞれのシステムに強みや特徴があります。「どのシステムが一番良いか」という絶対的な正解はなく、「どのシステムが自社の課題解決に最も貢献してくれるか」という視点で選ぶことが成功の鍵です。
この記事が、貴社にとって最適な入退室管理システムを見つけ、セキュリティと生産性の向上を実現するための一助となれば幸いです。まずは気になるシステムの資料請求や無料トライアルから、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。