現代のビジネス環境において、サイバーセキュリティ対策は企業の存続を左右する重要な経営課題となっています。日々巧妙化・高度化するサイバー攻撃に対し、企業は限られたリソースの中でいかにして自社の情報資産を守り抜くかという難題に直面しています。特に、専門的な知識と経験を持つセキュリティ人材の不足は、多くの企業にとって深刻な悩みです。
このような背景から、セキュリティ対策の専門家集団に運用・監視を委託する「MSSP(Managed Security Service Provider)」の活用が急速に広がっています。MSSPは、24時間365日の監視体制や高度な専門知識を提供し、企業のセキュリティレベルを飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
しかし、一方で「MDR」や「SOC」といった類似サービスとの違いが分かりにくかったり、どの事業者を選べば良いのか判断が難しかったりするのも事実です。
本記事では、MSSPの基本的な概念から、その必要性、具体的なサービス内容、類似サービスとの違い、そして導入のメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、自社に最適なMSSPを選ぶための具体的なポイントや、おすすめの主要事業者についても詳しく紹介します。この記事を読めば、MSSPに関するあらゆる疑問が解消され、自社のセキュリティ戦略を次のステージに進めるための確かな一歩を踏み出せるでしょう。
目次
MSSPとは
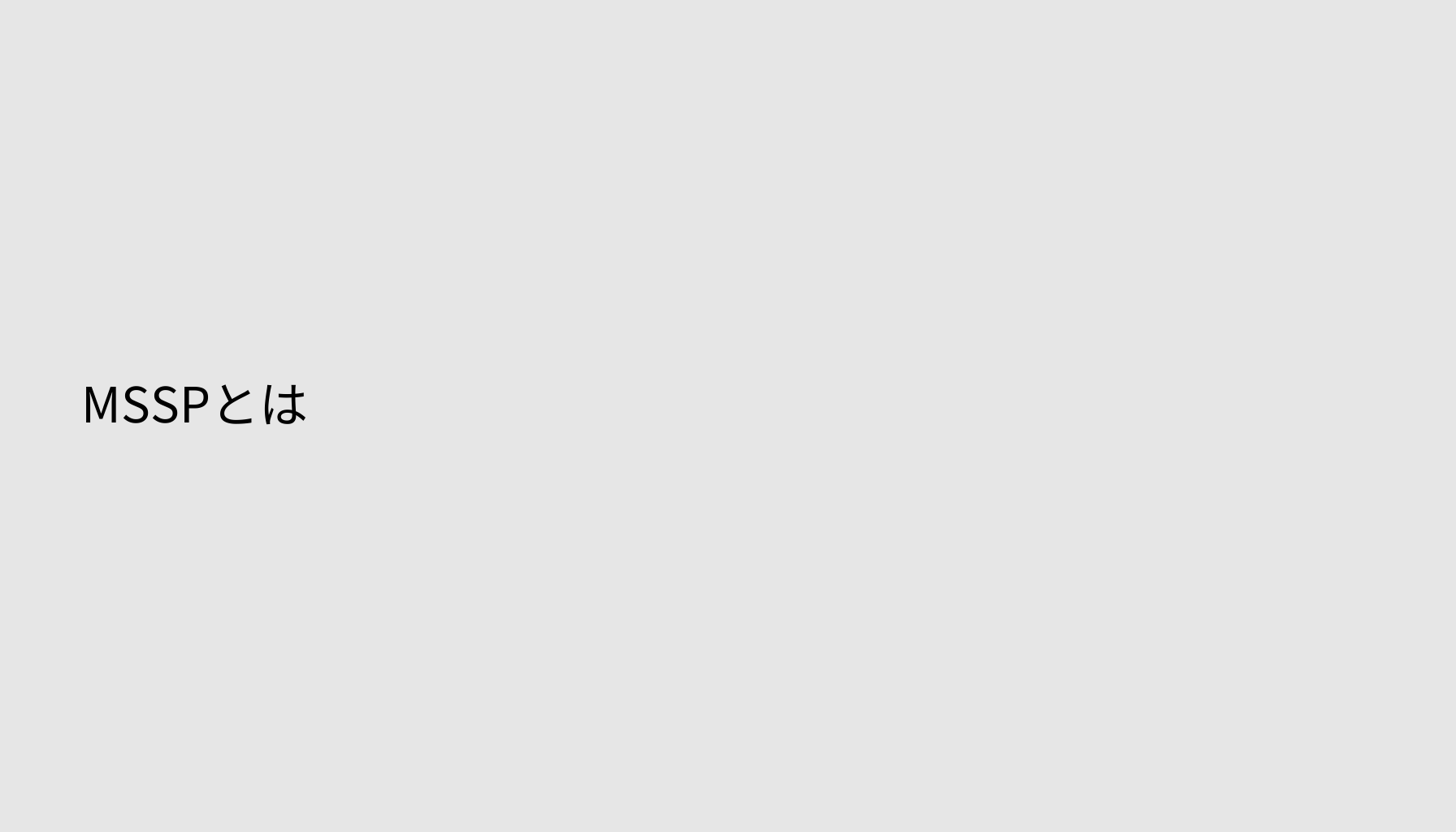
MSSPとは、「Managed Security Service Provider(マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー)」の略称であり、企業に代わってセキュリティ対策の運用・監視を行う専門的なアウトソーシングサービスを指します。顧客企業のネットワークやシステムに設置されたファイアウォール、WAF(Web Application Firewall)、IDS/IPS(不正侵入検知・防御システム)といった様々なセキュリティ機器を、専門のアナリストが24時間365日体制で遠隔から監視し、サイバー攻撃の兆候をいち早く検知・分析・通知することが主な役割です。
多くの企業にとって、自社だけで高度なセキュリティ体制を構築し、維持し続けることは非常に困難です。その最大の要因は、専門知識を持つセキュリティ人材の不足と、日々進化するサイバー攻撃への対応負荷の増大にあります。MSSPは、こうした企業の課題を解決するために生まれました。いわば、「企業のセキュリティ部門を外部の専門家チームが代行するサービス」と理解すると分かりやすいでしょう。
MSSPが提供する価値の核心は、単なる機器の監視に留まりません。複数のセキュリティ機器から集約された膨大なログ情報を、経験豊富なアナリストが横断的に相関分析することで、単体の機器では見つけられないような巧妙な攻撃の兆候を捉えます。そして、検知された脅威がビジネスにどのような影響を及ぼす可能性があるのかを評価し、顧客企業に対して具体的な対策を助言します。
具体的には、以下のような業務をカバーするのが一般的です。
- セキュリティ機器の監視とログ分析:ファイアウォールやWAFなどが記録する通信ログを常時監視し、不審なアクティビティがないか分析します。
- インシデントの検知と通知:マルウェア感染や不正アクセスといったセキュリティインシデントの兆候を検知した場合、即座に顧客へ通知し、被害の深刻度や影響範囲を報告します。
- セキュリティ機器の運用管理:最新の脅威に対応するためのシグネチャ(攻撃パターン定義ファイル)の更新や、セキュリティポリシーのチューニング、機器の稼働状況の確認など、日常的な運用業務を代行します。
- 脆弱性管理:システムやソフトウェアに存在するセキュリティ上の欠陥(脆弱性)を定期的に診断し、対策の優先順位付けと改善策を提案します。
- インシデント対応支援:実際にインシデントが発生した際に、被害の拡大を防ぐための初動対応や、原因を特定するための調査(フォレンジック)、復旧作業などを支援します。
これらのサービスを活用することで、企業は自社で専門家を雇用したり、24時間体制の監視チームを組織したりすることなく、高水準のセキュリティ対策を実現できます。情報システム部門の担当者は、煩雑なセキュリティ運用業務から解放され、DX推進や新規事業の企画といった、より戦略的な「コア業務」に集中できるようになります。
MSSPは、もはや大企業だけのものではありません。クラウド利用の普及やサプライチェーン攻撃のリスク増大により、近年では中小企業においてもその重要性が高まっています。自社のセキュリティ対策に不安を感じている、あるいはリソース不足に悩んでいるすべての企業にとって、MSSPは事業継続性を確保するための強力なパートナーとなり得るのです。
MSSPが必要とされる背景
なぜ今、多くの企業がMSSPの導入を検討し、実際に活用しているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境が抱える根深い課題が存在します。ここでは、MSSPが必要とされる二つの大きな理由、「セキュリティ人材の不足」と「サイバー攻撃の巧妙化・高度化」について詳しく解説します。
セキュリティ人材の不足
MSSPの需要を押し上げる最も大きな要因は、深刻なセキュリティ人材の不足です。多くの企業がサイバーセキュリティの重要性を認識しているにもかかわらず、対策を担う専門家を十分に確保できていないのが現状です。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発表した「DX白書2023」によると、IT人材の「量」について「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答した企業の割合は、日本企業で8割以上にのぼります。中でも、セキュリティ分野の専門人材は特に獲得競争が激しく、育成にも時間がかかるため、需要と供給のギャップは広がる一方です。
(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」)
セキュリティ人材が不足する理由は複合的です。
第一に、求められるスキルの高度化と多様化が挙げられます。現代のセキュリティ担当者には、ネットワーク、サーバー、クラウド、アプリケーションといった幅広いITインフラの知識に加え、最新の攻撃手法、法規制、国際標準など、常にアップデートし続けなければならない膨大な知識が要求されます。このような広範かつ深い専門性を持つ人材は、労働市場において非常に希少です。
第二に、人材育成の難しさがあります。座学だけで実践的なスキルを身につけることは難しく、実際のインシデント対応や攻撃分析の経験を積む機会は限られています。自社でゼロから専門家を育成するには、多大な時間とコスト、そして指導できるベテラン人材の存在が不可欠ですが、多くの企業にとってはその体制を整えること自体が困難です。
第三に、採用コストの高騰と離職リスクです。希少な人材であるため、セキュリティ専門家の給与水準は年々上昇しています。多額のコストをかけて採用できたとしても、より良い条件を求めて転職してしまうリスクも常に付きまといます。特に、24時間365日の対応が求められる監視業務は、担当者への心身の負担が大きく、定着が難しい職種の一つとされています。
このような状況下で、MSSPはセキュリティ人材不足に対する現実的かつ即効性のある解決策となります。自社で専門家チームを組成する代わりに、MSSPが抱える多数の経験豊富なアナリストやエンジニアの知見を、サービスとして利用できるのです。これにより、企業は採用や育成にかかるコストと時間を大幅に削減し、契約後すぐに専門家による高度なセキュリティ運用体制を構築できます。これは、自社のリソースだけで高品質なセキュリティを維持することが困難な企業にとって、計り知れないメリットと言えるでしょう。
サイバー攻撃の巧妙化・高度化
MSSPが必要とされるもう一つの大きな理由は、サイバー攻撃そのものが年々、巧妙化・高度化していることです。かつてのような無差別型のウイルスとは異なり、現代の攻撃は特定の企業や組織を狙い撃ちにし、執拗かつ複合的な手口で侵入を試みます。
近年の代表的な攻撃手法には、以下のようなものがあります。
- ランサムウェア攻撃の進化:ファイルを暗号化して身代金を要求するだけでなく、事前に窃取した情報を公開すると脅す「二重恐喝(ダブルエクストーション)」や、関係各所に攻撃を通知する「四重恐喝」など、手口が悪質化・巧妙化しています。
- 標的型攻撃(APT攻撃):特定の組織を標的に、長期間にわたって潜伏しながら情報を窃取する攻撃です。業務連絡を装った巧妙なメール(スピアフィッシング)などを入り口に、ゆっくりと内部の権限を奪取していくため、従来のセキュリティ製品だけでは検知が極めて困難です。
- サプライチェーン攻撃:セキュリティ対策が比較的脆弱な取引先や子会社を踏み台にして、本丸である大企業への侵入を狙う攻撃です。自社のセキュリティが強固でも、サプライチェーン全体で対策ができていなければリスクは残ります。
- AIの悪用:攻撃者もAI技術を活用し始めています。より自然で騙されやすいフィッシングメールの自動生成や、セキュリティシステムの防御を回避するマルウェアの開発など、攻撃の自動化と高度化が進んでいます。
このような高度な脅威に対抗するためには、もはやファイアウォールやウイルス対策ソフトといった個別のセキュリティ製品を導入するだけでは不十分です。様々な場所に設置されたセキュリティ機器から得られる膨大なログ情報をリアルタイムで収集し、それらを横断的に分析(相関分析)することで、攻撃の断片的な兆候をつなぎ合わせ、全体像を把握する能力が不可欠となります。
しかし、この相関分析を自社で行うには、SIEM(Security Information and Event Management)のような高度な分析ツールと、それを使いこなせる専門的なスキルを持つアナリストが必要です。さらに、攻撃は時間を選ばないため、24時間365日、片時も目を離さずに監視を続ける体制が求められます。
ここでMSSPの価値が発揮されます。MSSPは、最新の脅威情報(スレットインテリジェンス)を世界中から収集・分析し、それを自社の監視サービスに反映させています。専門のアナリストチームが24時間体制で顧客の環境を監視し、巧妙化するサイバー攻撃の予兆を早期に検知し、迅速に対応するための防波堤として機能します。個々の企業が単独で立ち向かうのが難しい高度な脅威に対し、専門家集団の知見と体制で対抗する。これが、MSSPが現代のビジネスに不可欠な存在となっている核心的な理由なのです。
MSSPの主なサービス内容
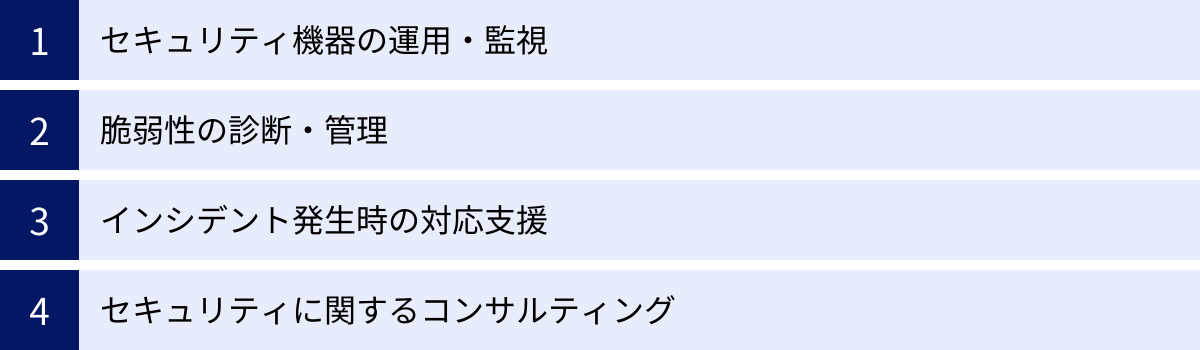
MSSPが提供するサービスは多岐にわたりますが、その中核をなすのは、企業のセキュリティ運用負荷を軽減し、専門的な知見で防御力を高めるための各種支援です。ここでは、多くのMSSPが提供する代表的なサービス内容を4つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。
セキュリティ機器の運用・監視
これはMSSPの最も基本的かつ中心的なサービスです。企業内に設置されたファイアウォール、WAF、IDS/IPS、UTM(統合脅威管理)といった、ネットワークの境界を守るセキュリティ機器の運用と監視を代行します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
- 24時間365日のリアルタイム監視:専門のアナリストが、セキュリティ機器から送られてくる膨大なログデータを常時監視します。これにより、深夜や休日といった情報システム部門の担当者が不在の時間帯に発生した攻撃も見逃しません。ビジネスの継続性を確保する上で、この切れ目のない監視体制は極めて重要です。
- ログの相関分析とインシデント検知:単一の機器のログだけを見るのではなく、複数の機器(例えばファイアウォールとWAF)からのログを突き合わせ、横断的に分析します。これにより、一見すると無害に見える通信の断片から、巧妙に隠された攻撃の兆候を浮かび上がらせることができます。不正アクセスやマルウェア感染の疑いがある通信を検知した場合、その脅威度を評価し、緊急度に応じて顧客に通知します。
- シグネチャ・定義ファイルのアップデート:新たな攻撃手法に対応するため、セキュリティ機器が攻撃を検知するための定義ファイル(シグネチャ)は常に最新の状態に保つ必要があります。MSSPは、最新の脅威情報を基に、これらのファイルを適切なタイミングで更新・適用します。
- ポリシーの最適化(チューニング):セキュリティポリシーが厳しすぎると正常な業務通信まで遮断してしまい(過検知)、逆に緩すぎると攻撃を見逃してしまいます(検知漏れ)。MSSPは、顧客のビジネス環境や通信の特性を理解した上で、セキュリティポリシーを定期的に見直し、過検知と検知漏れのバランスを最適化するチューニングを行います。
- 定期レポートの提出:月次などの単位で、監視期間中に検知されたインシデントの概要、攻撃の傾向、セキュリティ機器の稼働状況などをまとめたレポートを提出します。これにより、企業は自社のセキュリティ状態を客観的に把握し、今後の対策立案に役立てることができます。
これらの運用・監視業務をアウトソースすることで、企業は専門的で手間のかかる作業から解放され、セキュリティレベルの維持・向上を図ることができます。
脆弱性の診断・管理
サイバー攻撃の多くは、OSやソフトウェア、Webアプリケーションなどに存在する「脆弱性(セキュリティ上の欠陥)」を悪用して行われます。そのため、自社のシステムにどのような脆弱性が存在し、それがどれほど危険なのかを把握し、対策を講じることはセキュリティの基本です。MSSPは、この脆弱性管理のプロセスも支援します。
- 脆弱性診断サービスの提供:専用のスキャンツールを用いて、サーバーやネットワーク機器、Webアプリケーションに潜む既知の脆弱性を定期的に洗い出します。診断には、ネットワーク外部から行われる「プラットフォーム診断」や、Webサイトの動的な挙動を調べる「Webアプリケーション診断」などがあります。
- リスク評価と優先順位付け:発見された脆弱性は、その危険度に応じて評価されます。一般的には、世界共通の脆弱性評価システムであるCVSS(Common Vulnerability Scoring System)のスコアなどが用いられます。MSSPは、このスコアや攻撃の実現性、ビジネスへの影響度などを総合的に勘案し、どの脆弱性から優先的に対処すべきかを判断し、顧客に提言します。
- 対策の提案と管理:特定された脆弱性に対し、セキュリティパッチの適用や設定変更といった具体的な修正方法を提案します。対策が完了したかどうかを追跡管理し、再スキャンによって脆弱性が解消されたことを確認するまでをサポートするサービスもあります。
自社ですべてのシステムの脆弱性を網羅的に把握し、日々公開される新たな脆弱性情報に追随していくのは膨大な労力を要します。MSSPの脆弱性診断・管理サービスは、効率的かつ体系的に自社の弱点を把握し、計画的な対策を進めるための羅針盤となります。
インシデント発生時の対応支援
どれだけ高度な防御策を講じていても、100%サイバー攻撃を防ぎきることは不可能です。そのため、「インシデントは起こり得るもの」という前提に立ち、万が一発生してしまった場合にいかに被害を最小限に食い止め、迅速に復旧するかという「インシデントレスポンス(IR)」の体制が重要になります。MSSPは、この緊急時の対応も強力に支援します。
- インシデントの切り分けと影響範囲調査:インシデントの通知を受けた後、それが本当に攻撃なのか、誤検知ではないのかを迅速に切り分けます。攻撃であると判断した場合は、どの端末が感染したのか、どの情報が窃取された可能性があるのかなど、被害の影響範囲を特定するための調査を支援します。
- 封じ込めと根絶:被害の拡大を防ぐため、感染した端末をネットワークから隔離する「封じ込め」や、マルウェアを完全に駆除する「根絶」といった初動対応について、具体的な手順を助言します。リモートから直接的な操作を代行してくれるサービスもあります。
- デジタルフォレンジック支援:攻撃の手口や侵入経路、被害の全容を解明するため、PCのハードディスクやメモリに残された痕跡を専門的な技術で解析する「デジタルフォレンジック」の調査を支援、または実施します。この調査結果は、再発防止策の策定や、法的な報告義務を果たす上で重要な証拠となります。
- 復旧と再発防止策の提言:システムの正常な状態への復旧をサポートするとともに、今回のインシデントの原因分析に基づき、同様の攻撃を将来受けないようにするための恒久的な対策(セキュリティポリシーの見直し、新たなツールの導入など)を提言します。
インシデント発生時は、パニックに陥り、不適切な対応をしてしまうことでかえって被害を拡大させてしまうケースが少なくありません。冷静かつ的確な判断が求められる緊急時において、経験豊富な専門家が伴走してくれることは、企業にとって大きな安心材料となります。
セキュリティに関するコンサルティング
MSSPは、日々の運用・監視といった技術的なサービスだけでなく、より上流工程である企業のセキュリティ戦略全体に関わるコンサルティングサービスを提供することもあります。
- セキュリティポリシーの策定支援:企業の事業内容や文化、法規制などを踏まえ、実効性のある情報セキュリティポリシーや各種規程の策定を支援します。
- リスクアセスメント:企業が保有する情報資産を洗い出し、それぞれに潜むリスク(脅威と脆弱性)を評価し、対策の優先順位付けを行うプロセスを支援します。
- 認証取得支援:「ISMS(ISO/IEC 27001)」や「プライバシーマーク」といった、第三者によるセキュリティ認証の取得に向けたコンサルティングを提供します。
- セキュリティ教育・訓練:従業員のセキュリティ意識を向上させるため、標的型攻撃メール訓練やセキュリティ研修の企画・実施を支援します。
- 最新動向の情報提供:最新のサイバー攻撃トレンドや法改正の動向など、専門家でなければキャッチアップが難しい情報を定期的に提供し、企業のセキュリティ戦略に反映させるためのアドバイスを行います。
これらのコンサルティングサービスを通じて、企業は場当たり的な対策ではなく、自社の実情に即した体系的かつ継続的なセキュリティガバナンス体制を構築していくことができます。MSSPは、単なる監視代行業者ではなく、企業のセキュリティを包括的に支える戦略的パートナーとしての役割も担っているのです。
MSSPと類似サービスとの違い
セキュリティサービスの世界には、「MDR」「SOC」「SIEM」など、MSSPと混同されがちな用語が数多く存在します。これらの違いを正しく理解することは、自社の課題に最適なソリューションを選択する上で非常に重要です。ここでは、それぞれの用語の定義とMSSPとの関係性を、比較表も交えながら分かりやすく解説します。
MDRとの違い
MDRは「Managed Detection and Response(マネージド・ディテクション・アンド・レスポンス)」の略称で、MSSPと並んで近年注目度が高まっているサービスです。両者はサイバー攻撃から企業を守るという目的は共通していますが、その主眼とする領域とアプローチに明確な違いがあります。
| 比較項目 | MSSP (Managed Security Service Provider) | MDR (Managed Detection and Response) |
|---|---|---|
| 主な目的 | セキュリティ機器の運用・監視を通じた防御と負荷軽減 | 未知の脅威の検知・対応によるインシデント被害の最小化 |
| 主な監視対象 | ファイアウォール、WAF、IDS/IPSなどの境界型セキュリティ機器 | EDR、NDR、XDRなどのエンドポイントやネットワーク内部 |
| 脅威へのアプローチ | リアクティブ(受動的):既知の攻撃パターンやルールに基づき、インシデントを検知・通知する | プロアクティブ(能動的):脅威ハンティングなどを用いて、未知の脅威や潜伏する攻撃者の痕跡を積極的に探し出す |
| 提供価値 | 24/365の運用代行による情報システム部門の負荷軽減と網羅的な監視 | 専門アナリストによる高度な分析と迅速なインシデント対応(封じ込め等) |
| 対応の深度 | インシデントの検知・通知・分析が中心。対応は助言に留まることが多い。 | 検知後の具体的な対応(端末隔離、プロセス停止など)まで踏み込むことが多い。 |
MSSPの主な役割が、ファイアウォールなどの境界型セキュリティ機器の運用を代行し、既知の攻撃やルールベースで検知できる脅威をブロックすることにあるのに対し、MDRはより一歩踏み込んだサービスです。MDRは、PCやサーバーといった「エンドポイント」の挙動を監視するEDR(Endpoint Detection and Response)などのツールを活用し、従来の対策では検知が難しい未知のマルウェアや、システム内部に侵入した攻撃者の不審な振る舞いを「検知(Detection)」し、迅速に「対応(Response)」することに特化しています。
例えるなら、MSSPは「城壁や監視塔を24時間体制で管理・警備する衛兵」のような存在です。城壁に近づく敵を発見し、報告するのが主な任務です。一方、MDRは「城内に潜入したスパイや暗殺者を探し出し、捕縛する特殊部隊」に例えられます。彼らは衛兵の目をかいくぐって侵入した脅威に対し、プロアクティブ(能動的)な「脅威ハンティング」を行い、発見次第、被害が拡大する前に封じ込めるというミッションを担います。
近年では、MSSP事業者がMDRサービスを提供したり、両方の要素を組み合わせたサービスが登場したりするなど、境界は曖昧になりつつあります。しかし、基本的な考え方として、「運用負荷の軽減」を主目的とするならMSSP、「高度な脅威への対応力強化」を主目的とするならMDR、という棲み分けで理解すると良いでしょう。
SOCとの違い
SOCは「Security Operation Center(セキュリティ・オペレーション・センター)」の略称です。MSSPとしばしば混同されますが、両者は根本的に異なります。SOCは「組織・機能・場所」を指す言葉であり、MSSPは「サービス」を指す言葉です。
| 比較項目 | MSSP (Managed Security Service Provider) | SOC (Security Operation Center) |
|---|---|---|
| 分類 | サービス (アウトソーシングサービスの一種) | 組織・機能 (セキュリティ監視を行うチームや拠点そのもの) |
| 関係性 | 顧客企業のSOC機能を外部から提供する事業者 | 企業が自社で構築する場合 (プライベートSOC) と、MSSPに委託する場合 (アウトソースSOC) がある |
| 主体 | サービス提供事業者 (外部) | 自社 (内部) または MSSP (外部) |
| 導入の選択肢 | どのMSSP事業者と契約するかを選択 | 自社で構築するか、アウトソース (MSSP) するかを選択 |
つまり、MSSPとは「SOC機能をサービスとして外部に提供している事業者」のことです。企業がセキュリティ監視体制を構築しようと考えたとき、選択肢は大きく二つあります。一つは、自社で人材を雇用し、設備を整え、分析基盤を構築して「プライベートSOC(自社SOC)」を立ち上げること。もう一つは、そのSOC機能を丸ごと外部の専門事業者、すなわちMSSPに委託することです。
プライベートSOCを持つメリットは、自社のビジネスやシステム環境を深く理解した上で、きめ細やかな対応ができることや、社内にノウハウが蓄積されることです。しかし、その一方で、24時間365日体制を維持するための莫大な人件費、高度な専門人材の確保・育成の難しさ、分析ツールへの多額の投資といった高いハードルが存在します。
これに対し、MSSP(アウトソースSOC)を利用すれば、これらの課題を解決し、比較的低コストかつ短期間で高度な監視体制を確立できます。多くの企業にとって、自前でSOCを構築・維持するよりも、MSSPを利用する方が現実的かつ費用対効果の高い選択肢となることが多いのです。
結論として、SOCは「何をしたいか(=セキュリティ監視)」という目的を達成するための「機能・組織」であり、MSSPはその「機能・組織」を外部から調達するための「手段・サービス」と整理できます。
SIEMとの違い
SIEMは「Security Information and Event Management(セキュリティ情報・イベント管理)」の略称です。これもMSSPやSOCと関連が深い用語ですが、その位置づけは明確に異なります。SIEMは「ツール・製品・プラットフォーム」であり、MSSPは「サービス」です。
| 比較項目 | MSSP (Managed Security Service Provider) | SIEM (Security Information and Event Management) |
|---|---|---|
| 分類 | サービス (専門家による運用・監視サービス) | ツール・製品 (ログを統合管理・分析するためのソフトウェア/アプライアンス) |
| 役割 | SIEMなどのツールを「使う側」。専門家が分析・運用を行う。 | ログを「集約・分析する基盤」。様々な機器のログを正規化し、相関分析を可能にする。 |
| 関係性 | SIEMを効果的に活用するための専門知識と人的リソースを提供する。 | MSSPやSOCが日々の業務で活用する中核的なツールの一つ。 |
| 導入の課題 | 事業者の選定、契約範囲の定義 | 製品の選定、導入・設定の複雑さ、運用できる人材の不在 |
SIEMの主な機能は、ファイアウォール、サーバー、アプリケーション、各種セキュリティ製品など、組織内の多種多様なIT機器から出力されるログを一元的に収集・保管し、それらを横断的に分析して脅威の兆候を検知することです。いわば、セキュリティ分析を行うための「中央司令室」や「統合分析プラットフォーム」のような役割を果たします。
しかし、SIEMという高性能なツールを導入しただけでは、セキュリティは向上しません。膨大なログの中から本当に意味のある脅威の兆候を見つけ出すには、攻撃手法に関する深い知識と、分析の経験が豊富な専門アナリストが必要です。また、誤検知を減らし、検知精度を高めるためには、継続的なルールのチューニングが欠かせません。多くの企業では、SIEMを導入したものの、それを効果的に運用できる人材がおらず、「宝の持ち腐れ」になってしまうケースが後を絶ちません。
ここでMSSPの価値が生きてきます。MSSPは、まさにこのSIEMを使いこなすプロフェッショナル集団です。彼らは自社で高度なSIEM基盤を保有・運用しており、顧客から預かったログをその基盤に取り込んで分析します。あるいは、顧客がすでに導入しているSIEMの運用を代行するサービスも提供しています。
つまり、SIEMが「料理を作るための高性能なキッチン」だとすれば、MSSPは「そのキッチンを使いこなし、最高の料理を提供するシェフチーム」です。どんなに優れたキッチンがあっても、腕の良いシェフがいなければ美味しい料理は作れません。MSSPは、SIEMというツールのポテンシャルを最大限に引き出し、企業をサイバー攻撃から守るという価値を提供するのです。
MSSPを利用する4つのメリット
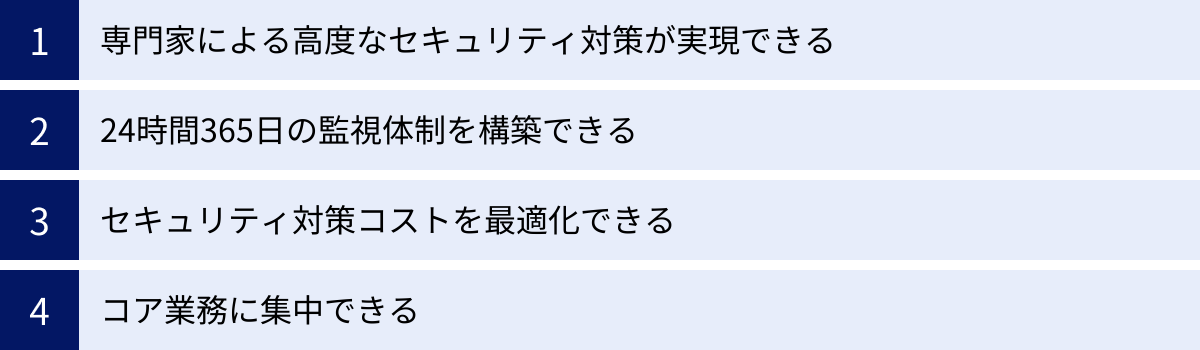
自社のセキュリティ運用を外部の専門家であるMSSPに委託することは、企業に多くの利点をもたらします。ここでは、MSSPを導入することで得られる代表的な4つのメリットについて、具体的な視点から詳しく解説します。
① 専門家による高度なセキュリティ対策が実現できる
MSSPを利用する最大のメリットは、自社だけでは構築が難しい、専門家による高度なセキュリティ対策を即座に実現できる点にあります。現代のサイバー攻撃は非常に巧妙であり、対抗するためには断片的な知識ではなく、体系的かつ最新の専門知識が不可欠です。
MSSPには、セキュリティアナリスト、インシデントハンドラー、フォレンジック調査官など、各分野に特化した専門家が多数在籍しています。彼らは日々の業務を通じて、世界中で発生する最新の攻撃手法や脆弱性に関する情報を常に収集・分析しており、その知見(スレットインテリジェンス)を監視業務に活かしています。
特に重要なのが、複数のセキュリティ機器からのログを横断的に分析する「相関分析」の能力です。例えば、ファイアウォールでは許可された「正常な通信」と、PC上のEDRが検知した「一見無害なプログラムの実行」が、それぞれ単体では警告に至らないかもしれません。しかし、専門家がこれらのイベントを時間軸で突き合わせると、「外部からの特定の通信をきっかけに、内部のPCで不審なプログラムが起動し、さらに別のサーバーへのアクセスを試みている」という、巧妙な標的型攻撃のシナリオが浮かび上がることがあります。
このような高度な分析は、特定の製品知識だけでは難しく、攻撃者の思考を理解し、多様なログの中から攻撃の痕跡を繋ぎ合わせる経験とセンスが求められます。自社でこうしたスキルを持つ人材を育成するのは非常に困難ですが、MSSPを利用すれば、契約したその日から、こうした専門家チームの能力を自社の防御力として活用できるのです。これにより、未知の脅威やゼロデイ攻撃(脆弱性の修正パッチが提供される前に行われる攻撃)に対する検知・対応能力が格段に向上します。
② 24時間365日の監視体制を構築できる
サイバー攻撃は、企業の業務時間内に行われるとは限りません。むしろ、システム管理者が手薄になる深夜や休日、長期休暇中を狙った攻撃が非常に多いのが実情です。もし、金曜日の夜にランサムウェアに感染し、週明けの月曜日に出社して初めて被害に気づいた場合、データ復旧や事業再開までに多大な時間を要し、ビジネスに致命的な損害を与えかねません。
このようなリスクに対応するためには、24時間365日、片時も目を離さない常時監視体制が不可欠です。しかし、これを自社で実現しようとすると、大きな壁にぶつかります。最低でも3交代制のシフトを組む必要があり、単純計算で監視担当者が5~6名は必要になります。前述の通り、専門人材の確保が困難な中で、これだけの人数を揃え、シフトを管理し、継続的に運用していくことは、コスト面でも労力面でもほとんどの企業にとって非現実的です。
MSSPは、この課題に対する明確な答えを持っています。彼らは、複数の顧客を同時に監視するシェアード型のサービスモデルを採用することで、一社あたりのコストを抑えながら、24時間365日の高品質な監視体制を提供しています。専門のアナリストが常に監視センター(SOC)に常駐し、システムが自動で発するアラートだけでなく、人間の目でなければ気づけないような僅かな異常の兆候にも注意を払っています。
この「切れ目のない監視」により、企業はいつ攻撃を受けても迅速に検知し、初動対応を開始できます。インシデントレスポンスにおいては、検知から対応までの時間が短ければ短いほど被害を小さく抑えられるため、事業継続計画(BCP)の観点からも、24時間365日の監視体制は極めて重要な意味を持つのです。
③ セキュリティ対策コストを最適化できる
一見すると、外部サービスであるMSSPの利用はコスト増につながるように思えるかもしれません。しかし、自社で同レベルのセキュリティ体制を構築・維持する場合と比較すると、多くの場合、トータルコスト(TCO: Total Cost of Ownership)を大幅に削減できる可能性があります。
自社で高度なセキュリティ監視体制(プライベートSOC)を構築する場合にかかるコストを分解してみましょう。
- 人件費:専門スキルを持つ人材の採用コスト、高い給与水準、24時間体制のための複数人分の人件費、教育・研修費用、福利厚生費など。
- 設備・ツール費用:SIEMやEDRといった高価なセキュリティツールの導入ライセンス費用、年間保守費用。監視センターを設置するための物理的なスペースやインフラの構築・維持費用。
- 運用・管理コスト:最新の脅威情報(スレットインテリジェンス)の購入費用、インシデント対応時の外部専門家への依頼費用など。
これらのコストは、初期投資だけでなく、継続的に発生するランニングコストも非常に高額になります。
一方、MSSPを利用する場合、これらのコストは月額のサービス料金にすべて含まれています。MSSPは、高度なツールや人材といったリソースを多くの顧客で共有するため、規模の経済が働き、一社あたりの負担額を低く抑えることができます。企業は、必要なサービスを必要な分だけ選択して利用できるため、過剰な投資を避け、予算を効率的に活用することが可能です。
つまり、MSSPは単なるコスト削減策ではなく、セキュリティ投資のROI(投資対効果)を最大化し、対策コストを「最適化」するための戦略的な選択と言えます。限られた予算の中で、最大限のセキュリティ効果を得たいと考える企業にとって、このメリットは非常に大きいでしょう。
④ コア業務に集中できる
多くの企業において、情報システム部門は少人数で幅広い業務を担っています。サーバーやネットワークの管理、社内ヘルプデスク、基幹システムの運用、そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進など、その役割は多岐にわたります。ここに、専門性が高く、常に緊張感を強いられるセキュリティ監視業務が加わると、担当者の負荷は計り知れません。
日々大量に発生するセキュリティアラートの確認、それが本当に脅威なのかどうかの調査(トリアージ)、セキュリティ製品のアップデートやチューニングといった定常的な運用業務は、多くの時間と精神的なエネルギーを消費します。結果として、本来注力すべき、企業の競争力を高めるための戦略的なIT企画やシステム開発といった「コア業務」にかける時間が圧迫されてしまうという問題が生じます。
MSSPを導入することで、情報システム部門は、この専門的かつ煩雑なセキュリティ運用業務から解放されます。セキュリティに関する日常的な監視や一次対応はMSSPに任せ、自社の担当者はMSSPからの報告を受けて最終的な意思決定を行ったり、より上位のセキュリティ戦略の策定に集中したりすることができます。
このように、専門性の高い業務を外部のプロに任せ、自社の貴重な人材リソースをより付加価値の高いコア業務に再配分することは、IT部門だけでなく、企業全体の生産性向上と競争力強化に直結します。MSSPの導入は、単なるセキュリティ対策のアウトソーシングに留まらず、企業の成長を加速させるための経営戦略の一環と捉えることができるのです。
MSSPを利用する際の3つのデメリット・注意点
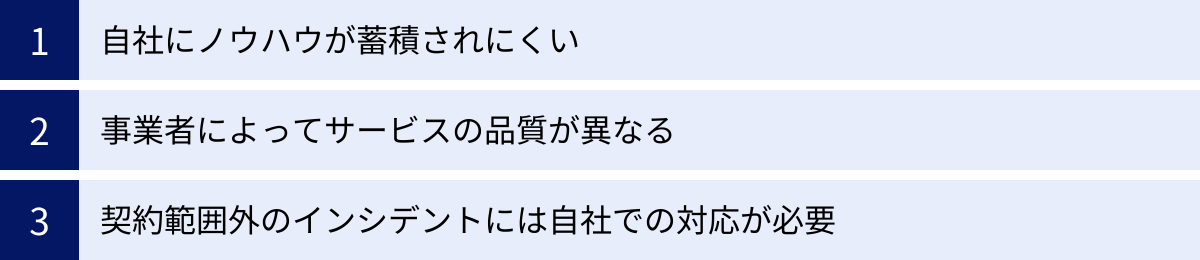
MSSPは多くのメリットを提供する一方で、導入を検討する際には知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、MSSPの価値を最大限に引き出すことができます。ここでは、代表的な3つのポイントを解説します。
① 自社にノウハウが蓄積されにくい
MSSPを利用するということは、セキュリティの運用・監視という実務を外部に委託することを意味します。これは、担当者の負荷を軽減する大きなメリットであると同時に、インシデントの検知や分析、対応といった実践的なスキルや知見が社内に蓄積されにくいというデメリットにもなり得ます。
日々のセキュリティアラートの分析や脅威の調査といったプロセスは、MSSPの専門アナリストが担うため、自社の担当者はその結果報告を受ける形が中心となります。インシデントが発生した際も、MSSPからの指示や助言に基づいて対応することはできますが、「なぜその対応が必要なのか」「攻撃者はどのような手口を使ったのか」といった深い部分までを自ら体験し、学ぶ機会は減少します。
この状態が長く続くと、企業はMSSPへの依存度が高まり、将来的にセキュリティ体制を内製化しようと考えた際や、契約するMSSPを変更しようとした際に、社内に知見を持つ人材がいないという問題に直面する可能性があります。また、MSSPからの報告内容を正しく理解し、適切な判断を下すためにも、ある程度のセキュリティ知識は社内に保持しておく必要があります。
【対策】
このデメリットを軽減するためには、MSSPを単なる「丸投げ先」と捉えず、「学習の機会」として積極的に活用する姿勢が重要です。
- 定期的な報告会での積極的な質疑応答:月次レポートなどを受け取るだけでなく、定例会を設けてもらい、検知されたインシデントの詳細や分析の根拠について深く質問しましょう。「なぜこれが脅威だと判断したのか」「他にどのような攻撃の可能性が考えられるか」といった問いを通じて、アナリストの思考プロセスを学ぶことができます。
- 詳細なレポートの要求:サマリーレポートだけでなく、分析の過程が分かるような詳細なレポートの提出を依頼できるか確認しましょう。
- 共同でのインシデント対応訓練:MSSPと連携し、インシデントを想定した共同の対応訓練(机上演習など)を実施することで、実践的なノウハウの移転を図ります。
- 将来的な内製化の計画:長期的には、すべての運用をアウトソースするのではなく、一部の分析業務や一次対応などを段階的に内製化していくロードマップを描き、MSSPにその支援を依頼することも有効なアプローチです。
MSSPと能動的にコミュニケーションを取り、彼らの持つ知識を吸収しようと努めることで、アウトソーシングのメリットを享受しつつ、社内のセキュリティレベルを着実に向上させていくことが可能です。
② 事業者によってサービスの品質が異なる
「MSSP」と一括りに言っても、そのサービス内容や品質は事業者によって千差万別です。安易に価格だけで選んでしまうと、「期待していたレベルの監視が受けられなかった」「いざという時に十分なサポートが得られなかった」といった事態に陥りかねません。
サービスの品質を左右する要素は多岐にわたります。
- アナリストのスキルと経験値:監視を担当するアナリストの技術レベルや経験は、検知の精度や分析の深さに直結します。経験の浅いアナリストが、マニュアル通りの対応しかできない場合、巧妙な攻撃を見逃すリスクが高まります。
- 脅威インテリジェンスの質と鮮度:どれだけ質の高い最新の脅威情報を収集し、それを迅速に監視ルールに反映できているかは、未知の攻撃への対応能力を大きく左右します。
- 対応のスピードと正確性:インシデントを検知してから顧客に通知するまでの時間、問い合わせに対する応答速度などは、サービス品質の重要な指標です。
- レポートの質:提出されるレポートが、単なるデータの羅列ではなく、経営層にも理解できるような分かりやすい言葉で、具体的なリスクと対策が示されているかどうかも重要です。
これらの品質は、ウェブサイトやパンフレットの表面的な情報だけでは判断が難しい部分です。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、事業者選定の段階で、サービスの品質を慎重に見極める必要があります。
【対策】
品質を見極めるためには、以下の点を確認することが有効です。
- SLA(Service Level Agreement)の確認:サービス品質保証制度であるSLAの内容を詳細に確認します。「インシデント検知から通知までの目標時間」「問い合わせへの応答時間」などが具体的に数値で定義されているか、そしてその基準が自社の要求レベルを満たしているかを精査します。
- アナリストの体制や資格:監視センター(SOC)の規模やアナリストの人数、保有しているセキュリティ関連資格(CISSP、GIACなど)について質問し、専門性の高さを確認します。
- 具体的なアウトプットのサンプル:過去に作成したレポートのサンプル(匿名化されたもの)や、インシデント通知のサンプルを見せてもらい、その分かりやすさや情報量を評価します。
- トライアル(試用)の可否:可能であれば、短期間のトライアル導入を行い、実際のサービスの品質や担当者との相性を確認することが最も確実な方法です。
③ 契約範囲外のインシデントには自社での対応が必要
MSSPは万能ではありません。彼らが提供するサービスは、契約書で定められた監視対象の機器や、対応範囲の業務に限定されます。この「責任分界点」を正しく理解しておかないと、いざという時に「それは契約範囲外です」と言われ、自社で対応せざるを得ない状況に陥る可能性があります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 監視対象外の端末でのインシデント:契約で監視対象を「サーバーとファイアウォール」としていた場合、社員個人のPCや、開発部門が管理する検証用サーバーでマルウェア感染が発生しても、MSSPの直接の監視範囲外となります。
- 物理的な対応が必要な場合:インシデント対応の一環として、サーバーの物理的な再起動や、ネットワークケーブルの抜き差しが必要になった場合、遠隔で監視しているMSSPは対応できません。現地での物理作業は、自社の担当者や、別途契約したオンサイト保守業者などが行う必要があります。
- 復旧作業の主体:MSSPは、インシデントの原因調査や封じ込めの「支援」は行いますが、OSの再インストールやデータのリストアといった最終的な「復旧作業」そのものは、顧客企業の責任範囲となるのが一般的です。
このように、MSSPを導入したからといって、自社のセキュリティ担当者が不要になるわけではありません。MSSPがカバーしない領域を誰がどのように対応するのか、社内の体制をあらかじめ整備しておくことが極めて重要です。
【対策】
契約範囲のリスクを管理するためには、以下の準備が不可欠です。
- 責任分界点の明確化:契約時に、MSSPのサービス範囲と自社の責任範囲を一覧表などの形で明確に定義し、双方で合意します。監視対象の機器リスト、インシデント発生時の各フェーズ(検知、分析、報告、封じ込め、根絶、復旧)における役割分担を具体的に文書化しておくことが望ましいです。
- 社内エスカレーションフローの整備:MSSPからインシデントの通知を受けた後、社内の誰に連絡し、誰が意思決定を行い、誰が実作業を行うのか、という一連の流れ(エスカレーションフロー)を事前に定義し、関係者全員で共有しておきます。
- インシデント対応計画(IRP)の策定:MSSPとの連携を前提とした、自社全体のインシデント対応計画(Incident Response Plan)を策定・文書化し、定期的に訓練を行うことが理想的です。
MSSPを効果的に活用するためには、彼らを信頼しつつも、自社が主体的にセキュリティを管理する意識を持ち、両者の役割分担を明確にしておくことが成功の鍵となります。
失敗しないMSSPの選び方!4つの比較ポイント
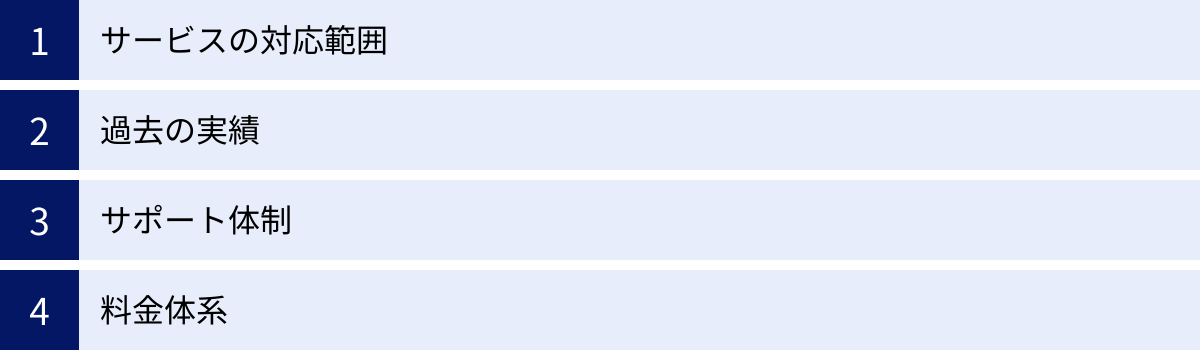
自社にとって最適なMSSPを選定することは、セキュリティ投資を成功させるための最も重要なステップです。数多くの事業者が存在する中で、何を基準に比較・検討すれば良いのでしょうか。ここでは、MSSP選びで失敗しないための4つの重要な比較ポイントを解説します。
① サービスの対応範囲
まず最初に確認すべきは、MSSPが提供するサービスの対応範囲が、自社のセキュリティ課題やIT環境と合致しているかという点です。事業者のサービス内容は多岐にわたるため、自社が何を求めているのかを明確にした上で、それを満たせるか評価する必要があります。
具体的には、以下の項目をチェックしましょう。
- 監視対象デバイス・環境:自社が監視してほしい対象は何かを明確にします。オンプレミスのサーバーやファイアウォールだけでなく、AWS、Azure、GCPといったパブリッククラウド環境、Microsoft 365やSalesforceなどのSaaS、エンドポイント(PC)、OT(工場などの制御システム)環境など、自社のIT資産を棚卸しし、それらの監視に対応しているかを確認します。特にクラウド環境への対応力は、近年の事業者選定において重要なポイントです。
- 対応するセキュリティ製品:すでに自社で導入しているセキュリティ製品(特定のメーカーのファイアウォールやEDRなど)がある場合、その製品の運用・監視に対応しているかは必須の確認項目です。対応していない場合、機器のリプレイスが必要になる可能性もあります。
- サービスの深度(どこまでやってくれるか):インシデント対応において、どこまでの作業を代行・支援してくれるのかを具体的に確認します。単なる「検知・通知」だけなのか、原因調査や分析レポートの作成まで行うのか、さらには端末の隔離といった「封じ込め」までリモートで実施してくれるのか。自社が求めるサポートレベルと、事業者が提供するサービスレベルに乖離がないかを確認することが重要です。
- 柔軟性と拡張性:現在はオンプレミス中心でも、将来的にクラウドへの移行を計画している場合、その移行に追随できる柔軟性があるか。ビジネスの成長に合わせて、監視対象を追加したり、新たなサービスをオプションで契約したりできるかといった、将来的な拡張性も考慮に入れるべきです。
自社の現状と将来像を描き、それに寄り添ってくれるサービス範囲を持つ事業者を選ぶことが、長期的なパートナーシップを築く上での第一歩となります。
② 過去の実績
サービスの品質や信頼性を測る上で、過去の実績は非常に重要な指標となります。長年の運用で培われたノウハウや、多様なインシデントへの対応経験は、机上の理論だけでは得られない実践的な能力の証です。
実績を評価する際は、以下の点に着目しましょう。
- 導入実績の数と継続率:単純な導入企業数も一つの目安ですが、より重要なのはサービスの継続率です。高い継続率は、顧客満足度の高さを物語っています。可能であれば、具体的な継続率の数値を確認してみましょう。
- 同業種・同規模企業への提供実績:自社と同じ業界や、同じくらいの規模の企業への導入実績があるかは特に重要です。例えば、金融業界であれば金融庁のガイドラインに関する知見が、製造業であればOTセキュリティに関する知見が期待できます。同業他社への実績が豊富であれば、業界特有の脅威や課題を深く理解している可能性が高く、より的確なサポートが受けられます。
- 対応したインシデントの具体例:守秘義務の範囲内で、過去にどのような種類のサイバー攻撃(ランサムウェア、標的型攻撃など)を検知し、どのように対応したのか、具体的な事例を聞いてみましょう。その説明の具体性や深さから、事業者の技術力や経験値を推し量ることができます。
- 公的機関や大手企業との取引実績:政府機関や金融機関、社会インフラを担う大手企業などは、非常に高いセキュリティレベルを要求します。これらの組織から選ばれているという事実は、その事業者の信頼性が客観的に証明されていると考えることができます。
ウェブサイトなどで公開されている情報だけでなく、商談の場で直接質問し、具体的な実績に裏打ちされた説得力のある回答が得られるかを見極めましょう。
③ サポート体制
インシデントはいつ発生するか分からず、発生した際には一刻を争う対応が求められます。そのため、緊急時に迅速かつ的確なサポートを受けられる体制が整っているかは、極めて重要な選定基準です。
サポート体制を評価する上でのチェックポイントは以下の通りです。
- 対応時間と連絡手段:24時間365日対応は多くのMSSPが謳っていますが、その実態を確認する必要があります。インシデント発生時の連絡手段は電話、メール、専用ポータルなど何が用意されているか。緊急連絡先に、深夜や休日でも専門のアナリストが直接応答してくれる体制になっているかを確認します。
- 日本語対応のレベル:外資系のMSSPの場合、レポートや技術者とのコミュニケーションが英語中心になることがあります。自社の担当者がスムーズに連携できるか、日本語でのサポートがどのレベルまで提供されるのか(メールのみ、電話も可など)を明確にしておく必要があります。
- SLA(サービス品質保証):前述の通り、SLAの内容は必ず確認します。「検知から通知まで平均XX分以内」といった具体的な目標値が設定されているか、その目標を達成できなかった場合のペナルティ(料金の減額など)が定められているかをチェックし、複数の事業者を比較検討します。
- コミュニケーションの質と頻度:日常的なコミュニケーションのあり方も重要です。定例報告会はどのくらいの頻度(月次、四半期など)で実施されるのか。その場で質問しやすい雰囲気か。担当のアカウントマネージャーやエンジニアとの相性も、長期的な関係性を築く上では見過ごせない要素です。
可能であれば、導入を検討している企業の担当者として、サポート窓口にデモの問い合わせをしてみるなど、実際の対応品質を体感してみるのも一つの手です。
④ 料金体系
コストは、事業者選定における重要な要素の一つですが、単純な価格の安さだけで判断するのは危険です。提供されるサービスの価値と価格のバランス、すなわちコストパフォーマンスを見極めることが肝要です。
料金体系を比較する際は、以下の点に注意しましょう。
- 課金モデルの理解:MSSPの料金体系は、監視対象のデバイス数、発生するイベント(ログ)の量(EPS: Event Per Second)、管理対象のユーザー数など、事業者によって様々です。自社の環境の場合、どの項目が課金のベースになるのか、将来的に対象が増えた場合に料金がどのように変動するのかを正確に理解する必要があります。
- 初期費用と月額費用の内訳:初期導入時にかかる費用と、月々のランニングコストの内訳を詳細に確認します。月額費用にどこまでのサービスが含まれているのか(レポート作成、定例会、問い合わせ対応など)、オプションサービスはどのようなものがあり、それぞれいくらかかるのかを明確にします。
- 隠れたコストの確認:契約範囲外のインシデントが発生し、追加の調査や対応を依頼した場合のスポット料金体系はどうなっているか。最低契約期間や、途中解約時の違約金の有無なども事前に確認しておくべきです。
- 複数社からの見積もり取得:必ず複数の事業者から見積もりを取得し、比較検討します。その際、単純な総額だけでなく、同じ価格帯でどのようなサービス内容の違いがあるのか、あるいは同じサービス内容でどれだけ価格が違うのかを詳細に比較することで、自社の予算と要求仕様に最もマッチした事業者を見つけ出すことができます。
安価なサービスには、それなりの理由(アナリストの経験が浅い、サポートが手薄いなど)があるかもしれません。自社が「何を」「どこまで」求めるのかを明確にし、その対価として妥当な価格を提示している、信頼できる事業者を選ぶ視点が不可欠です。
おすすめのMSSP事業者5選
日本国内には数多くのMSSP事業者が存在し、それぞれが独自の強みや特徴を持っています。ここでは、豊富な実績と高い信頼性を誇る代表的なMSSP事業者の中から、特に注目すべき5社をピックアップしてご紹介します。各社のサービス内容は常に更新されるため、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。
① NTTコミュニケーションズ株式会社
NTTコミュニケーションズは、日本最大級の通信事業者としての強固なインフラと、グローバルに展開するネットワークを活かしたセキュリティサービスを提供しています。同社のMSSPは「WideAngle」というブランド名で展開されており、コンサルティングから監視・運用、インシデント対応までをワンストップでカバーする包括的なサービスが特徴です。
- 強み・特徴:
- グローバルな脅威インテリジェンス:世界中に分散配置されたSOCと、NTTグループ全体で収集・分析される膨大な脅威情報を活用し、高度な分析能力を実現しています。
- 幅広いサービスポートフォリオ:基本的な機器監視に加え、MDR、脆弱性管理、クラウドセキュリティ、OTセキュリティなど、企業のあらゆるセキュリティ課題に対応できる幅広いメニューを揃えています。
- 通信事業者としての信頼性:長年にわたるネットワーク運用の実績とノウハウに裏打ちされた、安定したサービス品質が期待できます。大手企業や官公庁への導入実績も豊富です。
- おすすめの企業:
- グローバルに事業を展開しており、国内外の拠点を一元的に監視したい企業。
- セキュリティ対策を包括的にアウトソースし、戦略的なパートナーを求めている大企業。
(参照:NTTコミュニケーションズ株式会社 公式サイト)
② 株式会社ラック
株式会社ラックは、日本のサイバーセキュリティ業界の草分け的存在であり、1995年からセキュリティ事業を手掛ける老舗です。同社が運営するセキュリティ監視センター「JSOC(ジェイソック)」は、日本で最も歴史と実績のあるSOCの一つとして知られています。
- 強み・特徴:
- 国内最大級の監視実績:JSOCでは、官公庁から民間企業まで、非常に多くの顧客のセキュリティ監視を手掛けており、そこで蓄積された膨大な攻撃データと対応ノウハウが最大の強みです。
- 高度な分析力と独自インテリジェンス:熟練したアナリストによる高度な分析はもちろんのこと、自社の研究開発部門「サイバー・グリッド・ジャパン」が発信する独自の脅威情報や分析レポートは、業界内でも高く評価されています。
- 診断から監視までの一貫したサービス:セキュリティ診断(脆弱性診断)サービスでも国内トップクラスの実績を誇り、「自社の弱点を見つけ(診断)、それを守る(監視)」という一貫したアプローチが可能です。
- おすすめの企業:
- 実績と信頼性を最も重視し、日本の脅威動向に精通したサポートを求める企業。
- セキュリティ診断と監視を連携させ、効果的な対策サイクルを構築したい企業。
(参照:株式会社ラック 公式サイト)
③ NRIセキュアテクノロジーズ株式会社
NRIセキュアテクノロジーズは、野村総合研究所(NRI)グループのセキュリティ専門企業です。金融業界をはじめとする、極めて高いセキュリティレベルが求められる分野での豊富な実績と、高度なコンサルティング能力に定評があります。
- 強み・特徴:
- 金融業界における圧倒的な実績:親会社であるNRIが長年培ってきた金融システム構築・運用のノウハウを背景に、金融庁のガイドラインなど、業界特有の要件に準拠した高品質なサービスを提供しています。
- コンサルティングと運用の融合:セキュリティ戦略の策定やリスクアセスメントといった上流のコンサルティングから、具体的な監視・運用サービスまでをシームレスに提供できる点が強みです。
- 独自のセキュリティログ分析基盤:長年の運用ノウハウが詰め込まれた独自の分析プラットフォーム「FNC(Firewall Network Center)」を活用し、精度の高い監視を実現しています。
- おすすめの企業:
- 金融、保険業界など、厳格なコンプライアンスやガバナンスが求められる企業。
- 技術的な対策だけでなく、組織全体のセキュリティマネジメント強化を目指す企業。
(参照:NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 公式サイト)
④ SB C&S株式会社
SB C&Sは、ソフトバンクグループの一員として、国内外の多種多様なIT製品を取り扱うディストリビューターです。その強みを活かし、特定の先進的なセキュリティ製品に特化したマネージドサービスを提供しているのが大きな特徴です。
- 強み・特徴:
- 特定製品への深い知見:EDR製品(Cybereason、CrowdStrikeなど)や、Microsoft 365/Azure ADといった特定のプラットフォームのセキュリティ運用に特化したMSSを提供しています。ディストリビューターとして製品を熟知しているため、専門性の高い運用が期待できます。
- 最新ソリューションへの追随:世界の最新セキュリティトレンドをいち早くキャッチし、有望なソリューションをマネージドサービスとして提供するスピード感があります。
- 販売パートナーとの連携:全国の販売パートナー網と連携し、地域や企業規模を問わず、きめ細やかな導入支援を提供できる体制を持っています。
- おすすめの企業:
- すでに特定のEDR製品やMicrosoft 365を導入しており、その運用を専門家に任せたい企業。
- 最新のセキュリティ技術をいち早く活用したい、先進的な企業。
(参照:SB C&S株式会社 公式サイト)
⑤ 株式会社インターネットイニシアティブ (IIJ)
IIJは、日本で初めて商用インターネット接続サービスを開始したパイオニアであり、ネットワーク技術に関する深い知見と高い技術力を誇ります。その技術力をベースに、ネットワークからセキュリティ、クラウドまでを網羅する幅広いサービスを提供しています。
- 強み・特徴:
- ネットワークとセキュリティの融合:自社で提供するインターネット接続サービスやクラウドサービス(IIJ GIO)とセキュリティサービスを組み合わせることで、一貫性のある高品質な運用管理を実現できます。
- ワンストップでの提供:MSSPだけでなく、DDoS対策、WAF、メールセキュリティ、セキュアなリモートアクセスなど、企業が必要とするほぼ全てのセキュリティ機能を自社サービスとしてラインナップしており、窓口を一本化できるメリットがあります。
- 高い技術力と独自開発:バックボーンネットワークの運用で培った高い技術力を活かし、独自のセキュリティサービスや分析基盤を開発・提供しています。
- おすすめの企業:
- IIJのネットワークサービスやクラウドサービスをすでに利用している、あるいは導入を検討している企業。
- 複数のセキュリティ対策を一つの事業者に集約し、運用管理を効率化したい企業。
(参照:株式会社インターネットイニシアティブ (IIJ) 公式サイト)
まとめ
本記事では、MSSP(Managed Security Service Provider)について、その基本的な概念から必要とされる背景、具体的なサービス内容、類似サービスとの違い、メリット・デメリット、そして事業者の選び方まで、多角的に詳しく解説しました。
改めて要点を整理すると、MSSPは「深刻化するセキュリティ人材の不足」と「巧妙化・高度化するサイバー攻撃」という、現代企業が直面する二大課題に対する、極めて有効かつ現実的なソリューションです。
MSSPを導入することで、企業は以下のような大きなメリットを得られます。
- 専門家による高度なセキュリティ対策の実現
- 自社での構築が困難な24時間365日の監視体制の確立
- 人件費や設備投資を含めたトータルコストの最適化
- 情報システム部門のコア業務への集中による生産性向上
一方で、導入にあたっては、「社内にノウハウが蓄積されにくい」「事業者によって品質が異なる」「契約範囲外の対応は自社で行う必要がある」といった注意点も存在します。これらのデメリットを理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。
そして、最も重要なのが、自社の状況に最適なMSSP事業者を選定することです。「サービスの対応範囲」「過去の実績」「サポート体制」「料金体系」という4つの比較ポイントを念頭に置き、複数の事業者を慎重に評価・検討することが不可欠です。
サイバーセキュリティ対策は、もはやIT部門だけの一時的な課題ではありません。企業の事業継続性を守り、顧客や社会からの信頼を維持するための、重要な経営課題です。MSSPを単なるコスト削減のための「アウトソーシング先」として捉えるのではなく、自社の弱点を補い、共に成長していくための「戦略的パートナー」として位置づけること。その視点を持つことが、これからの不確実な時代を乗り越え、持続的な成長を遂げるための重要な一歩となるでしょう。

