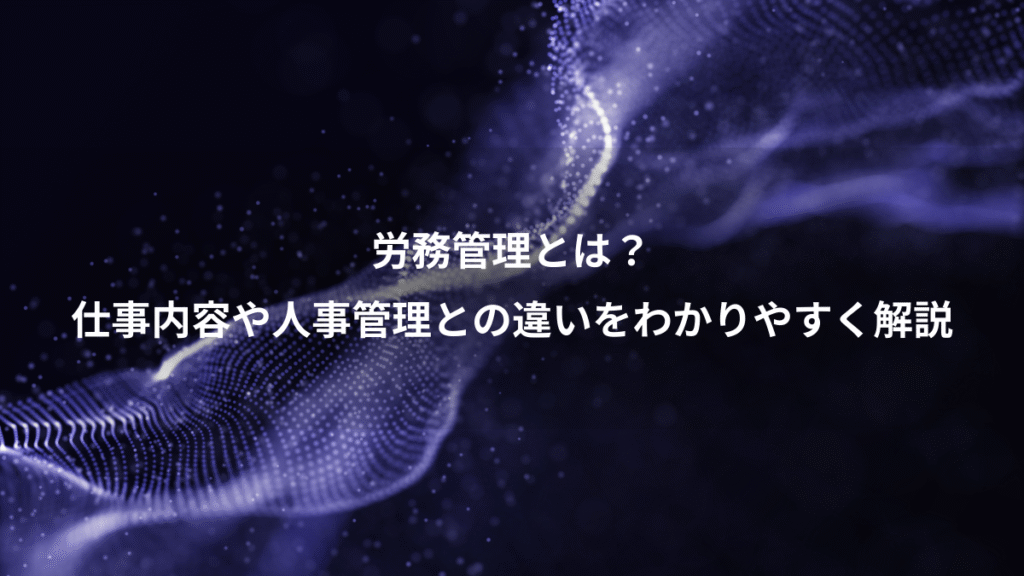企業の健全な成長と、そこで働く従業員の安心・安全な労働環境。この両輪を支える重要な機能が「労務管理」です。言葉は聞いたことがあっても、「具体的に何をするのか」「人事管理と何が違うのか」と疑問に思う方も少なくないでしょう。
本記事では、労務管理の基本的な定義から、その目的、具体的な仕事内容、そして人事管理や勤怠管理との明確な違いについて、専門用語を交えつつも分かりやすく解説します。さらに、現代の企業が直面する労務管理の課題と、それを乗り越えるための効率化手法、そして具体的な労務管理システムまで、網羅的にご紹介します。
この記事を読めば、労務管理が単なる事務作業ではなく、企業の未来を創る戦略的な活動であることが理解できるはずです。
目次
労務管理とは

労務管理とは、従業員が安心して意欲的に働ける環境を整備するため、労働に関する法令を遵守し、労働条件、福利厚生、安全衛生などを管理する企業活動全般を指します。具体的には、従業員の入社から退職までに発生する、労働契約、勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、就業規則の整備、安全衛生管理といった多岐にわたる業務が含まれます。
労務管理の根幹にあるのは、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法といった労働関連法規です。これらの法律は、労働者の権利を守り、最低限の労働条件を定めるためのものです。企業はこれらの法律を遵守する義務があり、労務管理は、その遵守を確実にするための重要な役割を担っています。
しばしば労務管理は、給与計算や社会保険手続きといった「守りのバックオフィス業務」と捉えられがちです。しかし、その本質はもっと深く、戦略的な意味合いを持っています。適切な労務管理は、従業員のモチベーションや生産性の向上に直結します。例えば、公正な労働時間管理や納得感のある給与体系は、従業員の企業に対する信頼感を育みます。また、安全で健康的な職場環境は、従業員の心身の健康を守り、長期的な活躍を後押しします。
このように、労務管理は、企業のコンプライアンス(法令遵守)体制の根幹をなし、労使間のトラブルを未然に防ぎ、従業員エンゲージメントを高めることで、最終的には企業の持続的な成長を支える基盤となるのです。
近年、労務管理の重要性はますます高まっています。その背景には、以下のような社会的な変化があります。
- 働き方の多様化: テレワーク、フレックスタイム制、副業・兼業など、従来の画一的な働き方が変化し、それぞれの働き方に合わせた複雑な労働時間管理やルール整備が求められるようになりました。
- コンプライアンス意識の高まり: 長時間労働やハラスメントなどの労働問題に対する社会的な関心が高まり、企業の労働環境が厳しく評価される時代になりました。SNSの普及により、企業の労務問題は瞬く間に拡散され、企業イメージや採用活動に深刻なダメージを与える可能性があります。
- 頻繁な法改正: 「働き方改革関連法」をはじめとして、労働関連法規は社会情勢の変化に合わせて頻繁に改正されます。企業は常に最新の法令をキャッチアップし、適切に対応し続けなければなりません。
これらの変化に対応し、企業と従業員双方にとってより良い関係を築くために、労務管理は不可欠な機能と言えるでしょう。単なる手続きの遂行に留まらず、企業の経営戦略と連動し、変化に柔軟に対応しながら、従業員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境を構築していくことこそ、現代における労務管理の核心です。
この記事の冒頭として、まずは「労務管理とは何か」という基本的な問いに対して、それが法律遵守を土台としながらも、従業員の働きがいを引き出し、企業の成長を支えるための戦略的な活動であることを理解しておくことが重要です。次の章では、その目的についてさらに詳しく掘り下げていきます。
労務管理の目的
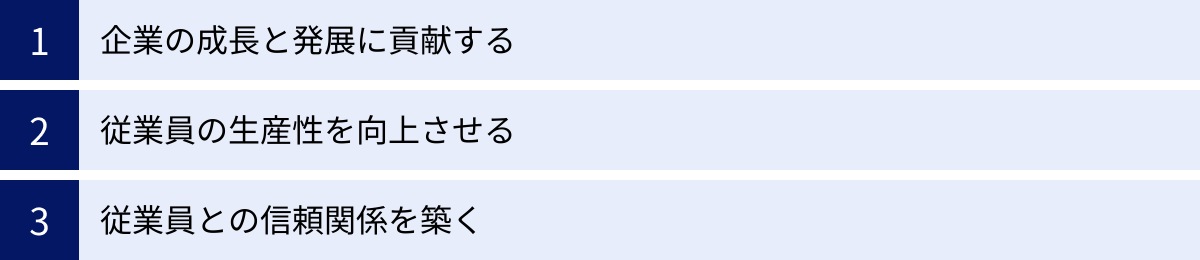
労務管理が目指すゴールは、単に法律を守ることだけではありません。その先にある、より大きな3つの目的、「企業の成長と発展への貢献」「従業員の生産性向上」「従業員との信頼関係構築」について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
企業の成長と発展に貢献する
労務管理は、一見するとコスト部門や管理部門の業務に見えますが、その実、企業の持続的な成長と発展に不可欠な基盤を築くという重要な目的を担っています。
第一に、徹底した法令遵守によるリスク管理が挙げられます。労働基準法や労働安全衛生法などの関連法規を遵守することは、企業の社会的責任の基本です。これを怠ると、労働基準監督署からの是正勧告や指導、悪質な場合には罰金や罰則が科される可能性があります。さらに、未払い残業代などを巡る労働審判や訴訟に発展すれば、金銭的な負担だけでなく、多くの時間と労力を費やすことになります。何より、「ブラック企業」というレッテルを貼られることによる企業ブランドの毀損は、採用活動の難化、顧客離れ、株価の下落など、経営に計り知れないダメージを与えかねません。適切な労務管理によってこれらのリスクを未然に防ぎ、経営の安定性を確保することは、企業が成長戦略を描く上での大前提となります。
第二に、健全な労務環境が経営基盤を強化するという側面があります。例えば、適切な勤怠管理によって長時間労働を抑制し、従業員の健康を守ることは、離職率の低下に繋がります。優秀な人材の定着は、採用や教育にかかるコストを削減し、組織全体の知識やノウハウの蓄積を促進します。また、従業員が安心して働ける環境は、新たな挑戦やイノベーションを生み出す土壌となります。労務トラブルが頻発するような職場では、従業員は萎縮し、本来の能力を発揮できません。逆に、企業が従業員を大切にする姿勢を明確に示せば、従業員は安心して業務に集中でき、結果として組織全体の活力が向上します。
第三に、社会的な信頼の獲得です。現代では、投資家や金融機関が企業の価値を評価する際に、財務情報だけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)といった非財務情報も重視するようになっています。労務管理は、この中の「S(社会)」と「G(ガバナンス)」に深く関わっています。従業員の権利を尊重し、働きやすい環境を提供している企業は、社会的に責任ある企業として評価され、投資や融資を受けやすくなる、あるいは優秀な人材が集まりやすくなるといった好循環が生まれます。
このように、労務管理は単なる事務作業ではなく、法的なリスクから企業を守り、安定した経営基盤を築き、社会的な信頼を獲得することで、企業の持続的な成長と発展を根底から支える戦略的な機能なのです。
従業員の生産性を向上させる
労務管理のもう一つの重要な目的は、従業員一人ひとりの生産性を最大限に引き出すことです。生産性とは、投入したリソース(労働時間、コストなど)に対して、どれだけの成果(売上、製品数など)を生み出したかを示す指標ですが、この向上には従業員のモチベーションやエンゲージメントが大きく影響します。
まず、公正で安心できる労働環境が、従業員の集中力を高めます。例えば、労働時間や休日が法律や就業規則通りにきちんと管理されていれば、従業員は「この会社はルールを守ってくれる」という安心感を得られます。給与が毎月決められた日に、残業代や手当を含めて正確に支払われることも同様です。このような基本的な信頼関係が土台にあるからこそ、従業員は日々の業務に余計な不安を抱くことなく、集中して取り組むことができます。逆に、給与計算が頻繁に間違っていたり、サービス残業が常態化していたりする職場では、従業員は不満や不信感を募らせ、仕事への意欲を失ってしまいます。
次に、適切な労働環境の整備が、従業員の心身の健康を維持し、パフォーマンスの安定化に繋がります。過度な長時間労働は、心身の疲弊を招き、注意力の散漫によるミスや事故、さらにはメンタルヘルスの不調を引き起こす原因となります。労務管理の役割は、勤怠データを分析して長時間労働の傾向がある部署や個人を特定し、業務分担の見直しや人員補充を提案するなど、未然に問題を防ぐことです。また、定期的な健康診断やストレスチェックの実施、ハラスメント相談窓口の設置といった安全衛生管理の徹底も、従業員が健康でいきいきと働き続けるために不可欠です。健康な従業員は、欠勤が少なく、高い集中力と創造性を発揮できます。
さらに、公平なルールと納得感のある制度が、従業員のモチベーションを刺激します。労務管理は、就業規則や賃金規程といった社内のルールブックを作成・運用する役割を担います。これらのルールが、全従業員に対して公平に適用されることで、組織内に規律と秩序が生まれます。また、福利厚生制度の充実は、従業員の生活を支え、企業への満足度(ES)を高める効果があります。「この会社は従業員のことを考えてくれている」と感じることで、従業員のエンゲージメント(企業への愛着や貢献意欲)は高まり、自発的に会社の成長に貢献しようという意識が芽生えます。
従業員が「大切にされている」と実感できる環境を整えることこそが、生産性向上の鍵です。労務管理は、その環境を制度的・物理的に構築し、維持していくための重要な役割を果たしているのです。
従業員との信頼関係を築く
企業という組織は、経営者と従業員という二つの当事者によって成り立っています。この両者の間に強固な信頼関係がなければ、組織としての一体感は生まれず、長期的な発展は望めません。労務管理は、この「信頼関係」を構築し、維持するためのコミュニケーションの要となります。
第一に、透明性と公平性の確保が信頼の基盤となります。労務管理の業務の中心には、就業規則や雇用契約書、賃金規程といった「ルール」の運用があります。これらのルールが全従業員に明確に周知され、特定の個人や部署だけが有利・不利になることなく、一貫した基準で公平に適用されることが極めて重要です。例えば、昇給や賞与の基準、休暇の取得ルール、懲戒処分の手続きなどが曖昧であれば、従業員は「会社は自分たちを正当に評価してくれないのではないか」という疑念を抱きます。労務管理担当者が、これらのルールを丁寧に説明し、問い合わせに誠実に対応することで、企業運営の透明性・公平性が担保され、従業員の会社に対する信頼感が醸成されます。
第二に、労務手続きを通じたコミュニケーションが信頼を深めます。入社手続き、育児休業や介護休業の申請、年末調整、退職手続きなど、労務管理は従業員のライフステージの様々な局面で関わります。特に、育児や介護といった個人的な事情に関わる手続きでは、制度の説明だけでなく、個々の従業員の状況に寄り添った丁寧な対応が求められます。このような場面で、企業側が親身になってサポートする姿勢を示すことで、従業員は「この会社は自分の人生を応援してくれる」と感じ、エンゲージメントが大きく向上します。これは、単なる事務手続きを超えた、重要なコミュニケーションの機会なのです。
第三に、労使トラブルの未然防止機能が信頼関係を守ります。従業員が労働条件や職場環境に対して抱く不満や疑問は、放置すると大きなトラブルに発展する可能性があります。労務管理は、従業員からの相談窓口としての役割も担います。「残業時間について疑問がある」「ハラスメントかもしれないと感じることがある」といった従業員の声に早期に耳を傾け、事実確認を行い、適切な対応をとることで、問題を深刻化させずに解決できます。このような問題解決のプロセスを通じて、従業員は「この会社は話を聞いてくれる」「問題を解決しようと努力してくれる」と感じ、信頼関係がより強固なものになります。
健全な労使関係は、一朝一夕に築けるものではありません。日々の労務管理業務を通じて、誠実さ、公平さ、透明性を積み重ねていくことによってはじめて、従業員と企業との間の揺るぎない信頼関係が構築されるのです。
人事管理・勤怠管理との違い
労務管理について学ぶ上で、しばしば混同されるのが「人事管理」と「勤怠管理」です。これらは互いに密接に関連していますが、その目的や業務範囲には明確な違いがあります。ここでは、それぞれの違いを整理し、労務管理の立ち位置をより明確にしていきましょう。
人事管理との違い
人事管理と労務管理は、どちらも企業の「ヒト」に関わる業務ですが、その焦点と目的に大きな違いがあります。端的に言えば、人事管理が「個々の従業員の価値を最大化し、組織を活性化させる」攻めの側面を持つのに対し、労務管理は「従業員が安心して働ける基盤を整え、企業のリスクを管理する」守りの側面が強いと言えます。
人事管理(Human Resource Management)は、経営資源である「ヒト」を最大限に活用し、企業の経営目標達成に貢献することを目的とします。その業務内容は、従業員のパフォーマンスやキャリアに直接的に働きかけるものが中心です。
- 採用: 企業の成長に必要な人材を定義し、募集、選考、採用する。
- 配置・異動: 個々の従業員の適性や能力、キャリアプランを考慮し、最適な部署や役職に配置する。
- 育成・研修: 従業員のスキルアップや能力開発を目的とした研修プログラムを企画・実施する。
- 人事評価: 従業員の業績や能力を公正に評価し、昇進・昇格や報酬に反映させる。
- 人事戦略: 経営戦略に基づき、将来の事業展開を見据えた人員計画や組織設計を行う。
一方、労務管理は、前述の通り、労働関連法規の遵守を前提として、全従業員が公平かつ安全に働ける環境を整備することが主目的です。業務内容は、個人の能力というよりは、労働者としての権利や義務、労働条件の管理が中心となります。
- 労働契約・就業規則: 労働条件を定め、社内ルールを整備する。
- 勤怠管理: 労働時間を正確に把握し、管理する。
- 給与計算: 労働の対価である給与を法令に基づき正確に計算し、支払う。
- 社会保険・労働保険: 法定の保険手続きを行う。
- 安全衛生管理: 従業員の心身の健康と安全を守る。
この違いを分かりやすく表にまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 労務管理 | 人事管理 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 労働環境の整備、法令遵守、労使関係の安定 | 経営資源(ヒト)の最大活用、組織パフォーマンスの向上 |
| 主な業務 | 勤怠管理、給与計算、社会保険手続き、安全衛生管理、就業規則管理 | 採用、配置、異動、育成・研修、人事評価、人事戦略策定 |
| 根拠法規 | 労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法など | 特定の根拠法はない(ただし、関連法規への配慮は必要) |
| 焦点 | 集団(全従業員)に対する公平なルール適用と基盤整備 | 個人(個々の従業員)の能力、適性、キャリア |
| 役割の比喩 | 会社の「土台」や「インフラ」を整備する役割 | 選手の「育成」や「戦略」を立てる監督・コーチの役割 |
もちろん、両者は完全に独立しているわけではありません。例えば、人事評価の結果は給与(労務管理)に反映されますし、長時間労働の問題(労務管理)を解決するためには、人員配置の見直し(人事管理)が必要になることもあります。人事管理と労務管理は、車の両輪のように連携し合うことで、はじめて企業と従業員の健全な関係を築き、組織全体のパフォーマンスを向上させることができるのです。
勤怠管理との違い
勤怠管理と労務管理の関係は、人事管理との関係よりもさらにシンプルです。結論から言うと、勤怠管理は、労務管理という大きな業務領域に含まれる、具体的なタスクの一つです。
勤怠管理とは、その名の通り、従業員の「勤怠」、すなわち出退勤時刻、労働時間、休憩時間、休日、休暇取得状況などを日々記録し、管理する業務を指します。主な目的は、従業員がいつ、どれだけ働いたかという「事実」を客観的に把握することです。
- 主な業務:
- タイムカード、ICカード、PCログ、生体認証などによる出退勤時刻の記録
- 残業時間、深夜労働時間、休日労働時間の集計
- 遅刻、早退、欠勤の管理
- 有給休暇やその他の休暇の申請・承認・残日数管理
一方、労務管理は、この勤怠管理によって収集されたデータをもとに、より広範な業務を行います。勤怠データは、労務管理における様々な判断や手続きの「元データ」となるのです。
- 勤怠データ活用の例:
- 給与計算: 勤怠データを基に、基本給に加えて時間外手当、深夜手当、休日手当などの割増賃金を正確に計算する。
- 法令遵守の確認: 36協定で定められた時間外労働の上限を超えていないか、休憩時間が適切に取得されているか、年5日の有給休暇取得義務を果たしているかなどをチェックする。
- 健康管理: 特定の従業員に長時間労働が集中していないかをモニタリングし、産業医の面談指導につなげるなど、健康障害を未然に防ぐためのアクションを起こす。
- 生産性分析: 部署ごとの残業時間の傾向を分析し、業務プロセスの改善や人員配置の見直しを検討するための材料とする。
つまり、「勤怠管理=労働時間の事実を記録するインプット」であり、「労務管理=その記録を基に給与計算や法令遵守、健康管理といったアウトプットを生み出し、改善策を講じるプロセス」と捉えることができます。
例えば、従業員がタイムカードを打刻する行為は「勤怠管理」の範疇です。しかし、その打刻データを見て、「Aさんの残業時間が今月80時間を超えそうだ。健康状態は大丈夫だろうか。上長に業務量の調整を相談しよう」と考えるのが「労務管理」の視点です。
勤怠管理は労務管理の基礎となる重要な業務ですが、それ自体がゴールではありません。正確な勤怠データをいかに活用し、従業員の保護と企業の健全な運営に繋げていくか、というより広い視点を持つのが労務管理であると理解しておきましょう。
労務管理の主な仕事内容
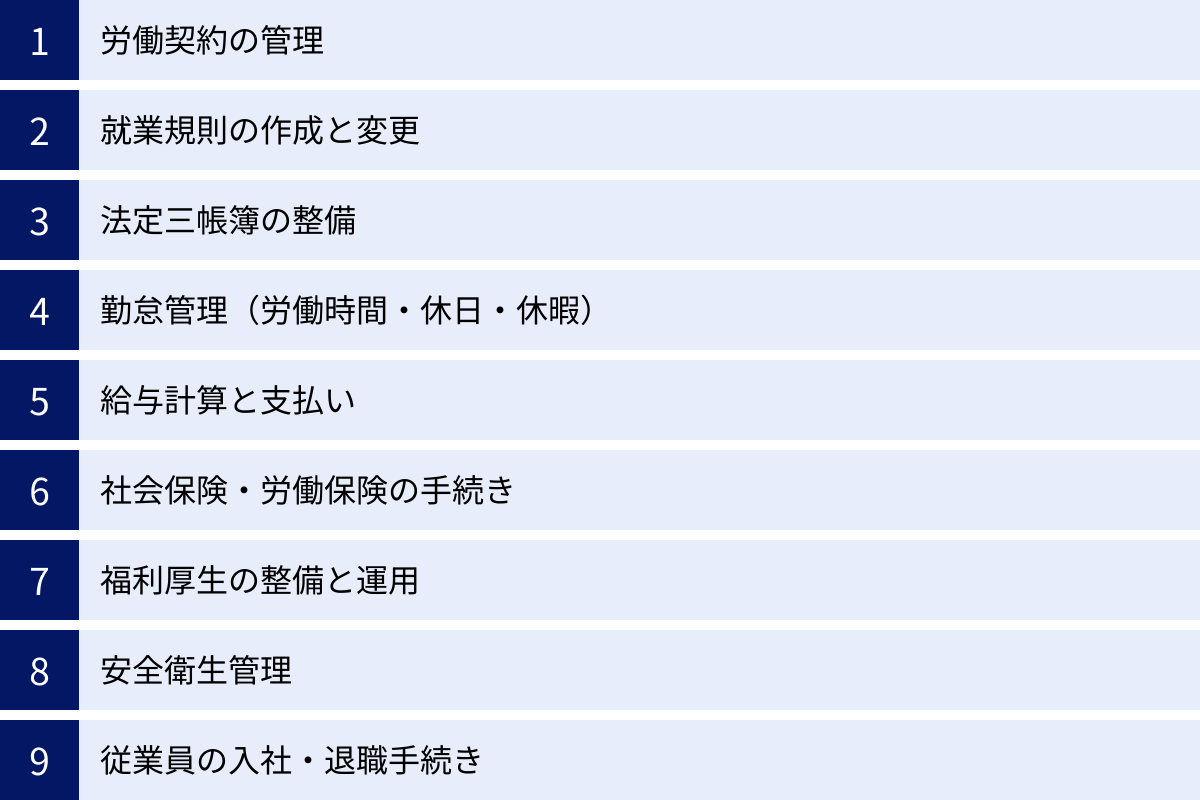
労務管理の業務は非常に多岐にわたりますが、ここでは企業活動の根幹をなす主要な仕事内容を9つに分けて、それぞれ具体的に解説します。これらの業務は、従業員が入社してから退職するまで、あらゆる場面で発生します。
労働契約の管理
従業員を雇用する際の最初のステップであり、労使関係の基本となるのが労働契約の締結です。労務管理では、この契約が法的に正しく、かつ円滑に行われるよう管理します。
主な業務は「労働条件通知書」の作成と交付です。企業は従業員を雇い入れる際、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示する義務があります(労働基準法第15条)。特に、以下の項目は書面(現在は従業員の希望があれば電子メール等も可)で明示しなければなりません。
- 労働契約の期間
- 就業の場所と従事すべき業務の内容
- 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇など
- 賃金の決定、計算・支払いの方法、締切・支払いの時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらの条件を曖昧にすると、後々の労使トラブルの原因となります。契約内容を双方で明確に合意し、その証拠として書面を交付することが、信頼関係の第一歩です。また、パートタイマーや契約社員などの有期労働契約の場合は、契約更新の有無や、更新する場合の判断基準についても明示する必要があります。
就業規則の作成と変更
就業規則は、その職場で働く上でのルールブックであり、賃金規程や服務規律、休日・休暇制度など、労働条件や従業員が遵守すべき規律を定めたものです。常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。
労務管理の重要な役割の一つが、この就業規則を法改正や会社の状況に合わせて適切に作成・変更し、管理することです。
- 作成・変更手続き: 就業規則を作成・変更する際には、従業員の過半数で組織する労働組合(ない場合は従業員の過半数を代表する者)の意見を聴取し、その意見書を添えて届け出なければなりません。一方的な変更は認められません。
- 周知義務: 作成・変更した就業規則は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示・備え付ける、書面を交付する、PC等でいつでも閲覧できるようにするなど、何らかの方法で従業員に周知する義務があります。周知されていなければ、その就業規則は法的な効力を持ちません。
- 内容の整備: 法令で必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」(労働時間、賃金、退職など)と、制度を設ける場合に記載が必要な「相対的必要記載事項」(賞与、安全衛生、懲戒など)を漏れなく記載します。
就業規則は、統一的・公平な労務管理を行うための基礎であり、労使間の無用なトラブルを防ぐための重要なツールです。
法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の整備
労働基準法では、企業に対して以下の3つの帳簿を作成し、適切に保管することを義務付けています。これらは総称して「法定三帳簿」と呼ばれ、労務管理の基本中の基本となる書類です。
- 労働者名簿: 従業員の氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇入年月日、退職年月日とその事由などを記載した名簿です。従業員の情報を正確に管理するために必要です。
- 賃金台帳: 従業員ごとに、氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外・休日・深夜労働時間数、基本給や手当の種類と額、控除額などを記載した台帳です。給与が正しく支払われていることを証明する重要な書類です。
- 出勤簿: 一般的にはタイムカードや勤怠管理システムの記録がこれに該当します。従業員の出退勤時刻を記録し、労働時間を客観的に把握するためのものです。
これらの帳簿は、労働基準監督署の調査(臨検監督)の際に必ず確認されるほか、未払い残業代請求などの労使トラブルが発生した際には、企業の主張を裏付ける重要な証拠となります。保存期間は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿ともに5年間(ただし当分の間は3年間)と定められています。これらの帳簿を正確に作成し、いつでも提示できる状態にしておくことが、企業のコンプライアンス体制を示す上で不可欠です。
勤怠管理(労働時間・休日・休暇)
前述の通り、勤怠管理は労務管理の中核をなす業務の一つです。単に出退勤を記録するだけでなく、それが法令に適合しているかを管理する責任があります。
- 労働時間の客観的な把握: 2019年の法改正により、企業はタイムカード、PCの使用時間の記録、ICカードなど、客観的な方法で従業員の労働時間を把握する義務が明確化されました。自己申告制を採る場合でも、実態と乖離がないか定期的に確認するなどの措置が必要です。
- 時間外労働・休日労働の管理: 従業員に法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合や、法定休日(週1日)に労働させる場合には、「36(サブロク)協定」を労使で締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。労務管理では、この協定で定めた上限時間の範囲内で残業が行われているかを常に監視します。
- 年次有給休暇の管理: 年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対し、企業は付与日から1年以内に最低5日間を取得させなければならない義務があります(時季指定義務)。労務管理担当者は、従業員ごとの有給休暇の取得状況を把握し、取得日数が5日に満たない従業員に対しては、時季を指定して取得を促すなどの対応が必要です。
これらの管理を怠ると、割増賃金の未払いや法令違反に繋がり、企業の信頼を大きく損なうことになります。
給与計算と支払い
従業員にとって最も関心の高い事項の一つが給与です。給与計算は、勤怠管理で集計したデータに基づき、従業員一人ひとりの給与額を正確に計算し、支払う業務です。
計算プロセスは複雑で、以下の要素を考慮する必要があります。
- 総支給額の計算: 基本給に、役職手当、資格手当、通勤手当などの各種手当を加算します。さらに、勤怠データから時間外手当、休日手当、深夜手当といった割増賃金を計算し、加えます。
- 控除額の計算: 総支給額から、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料といった社会保険料や、所得税、住民税といった税金を差し引きます(控除)。
- 差引支給額(手取り額)の決定: 総支給額から控除額を差し引いたものが、実際に従業員に支払われる金額となります。
また、給与の支払いには「賃金支払いの五原則」(労働基準法第24条)を遵守しなければなりません。
- 通貨払いの原則: 現金で支払う(例外として、本人の同意を得れば口座振込可)。
- 直接払いの原則: 従業員本人に直接支払う。
- 全額払いの原則: 税金や社会保険料など法令で定められたもの以外は、給与から天引きしない(例外として、労使協定があれば組合費などを天引き可)。
- 毎月1回以上払いの原則: 毎月少なくとも1回は支払う。
- 一定期日払いの原則: 「毎月25日」のように、支払日を特定して支払う。
給与計算はミスが許されない、非常に正確性が求められる業務です。
社会保険・労働保険の手続き
企業は、従業員を雇用する際に、法律で定められた社会保険および労働保険に加入させる義務があります。これらの保険に関する各種手続きを行うのも、労務管理の重要な仕事です。
社会保険(健康保険・厚生年金など)
主に病気やケガ、老齢、死亡などに備えるための保険です。
- 資格取得・喪失手続き: 従業員の入社時には「被保険者資格取得届」を、退職時には「被保険者資格喪失届」を年金事務所(または健康保険組合)に提出します。
- 被扶養者異動届: 従業員に扶養家族ができた場合や、扶養から外れた場合に手続きを行います。
- 算定基礎届: 毎年7月1日現在の全被保険者の標準報酬月額(保険料の計算の基礎となる額)を決定するため、4〜6月の報酬月額を届け出ます。
- 月額変更届: 昇給などで報酬が大幅に変動した場合に、標準報酬月額を改定するための手続きです。
労働保険(雇用保険・労災保険)
雇用保険は失業や育児・介護休業などに、労災保険は業務中や通勤中のケガや病気に備えるための保険です。
- 年度更新: 毎年1回、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算し、申告・納付します。
- 雇用保険の手続き: 従業員の入退社に伴う資格取得・喪失手続きを行います。特に退職時には、失業手当の受給に必要となる「離職票」の発行手続きが重要です。
- 労災保険の手続き: 業務災害や通勤災害が発生した場合、治療費や休業補償などの給付を受けるための請求手続きを行います。
これらの手続きは提出期限が厳格に定められており、遅延すると追徴金などが発生する可能性があるため、計画的な業務遂行が求められます。
福利厚生の整備と運用
福利厚生には、法律で義務付けられている「法定福利」(社会保険料の会社負担分など)と、企業が任意で設ける「法定外福利」があります。労務管理では、特に法定外福利の企画、導入、運用に携わります。
法定外福利の例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 住宅手当、家賃補助
- 家族手当、育児支援
- 慶弔見舞金(結婚祝金、出産祝金、傷病見舞金など)
- 社員食堂、食事補助
- 人間ドック費用の補助、フィットネスクラブの利用補助
- 社員旅行、レクリエーション活動
福利厚生制度を充実させることは、従業員満足度の向上、人材の採用・定着、企業イメージの向上に繋がります。労務管理担当者は、従業員のニーズを調査し、予算の範囲内で、自社の社風や経営方針に合った魅力的な福利厚生制度を設計・運用していく役割を担います。
安全衛生管理
従業員が安全で健康に働ける職場環境を確保することは、企業の重要な責務です。労働安全衛生法に基づき、様々な取り組みが義務付けられています。
- 安全衛生委員会の設置・運営: 一定規模以上の事業場では、安全や衛生に関する事項を調査審議するための委員会を設置し、毎月1回以上開催する必要があります。
- 健康診断の実施: 企業は従業員に対し、年に1回(深夜業などの特定業務従事者は年2回)、定期健康診断を実施する義務があります。労務管理では、対象者のリストアップ、医療機関との調整、結果の管理、有所見者への事後措置などを行います。
- ストレスチェックの実施: 従業員50人以上の事業場では、年に1回、ストレスチェックを実施することが義務付けられています。高ストレス者への医師による面接指導の申し出があった場合の対応も必要です。
- 職場巡視: 安全管理者や衛生管理者が定期的に職場を巡視し、危険な箇所や不衛生な箇所がないかを確認し、改善措置を講じます。
- ハラスメント対策: パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどを防止するための相談窓口の設置や研修の実施が法律で義務化されています。
これらの活動を通じて、労働災害や職業性疾病を未然に防ぎ、従業員が心身ともに健康で働ける職場を実現します。
従業員の入社・退職手続き
従業員のライフサイクルの入口と出口に関わる手続きも、労務管理の重要な業務です。
- 入社手続き:
- 労働契約の締結、労働条件通知書の交付
- 社会保険・労働保険の加入手続き
- 給与振込口座の確認
- 誓約書、身元保証書、個人情報取り扱い同意書などの必要書類の回収
- 就業規則や社内ルールの説明
- 退職手続き:
- 退職届の受理
- 社会保険・労働保険の資格喪失手続き
- 離職票、源泉徴収票などの必要書類の作成・交付
- 貸与品(PC、社員証など)の回収
- 最終給与の計算と支払い
これらの手続きを漏れなく、かつ迅速に行うことは、従業員との良好な関係を維持する上で非常に重要です。特に退職時の手続きがスムーズに行われることは、企業の評判にも影響します。
労務管理における近年の課題
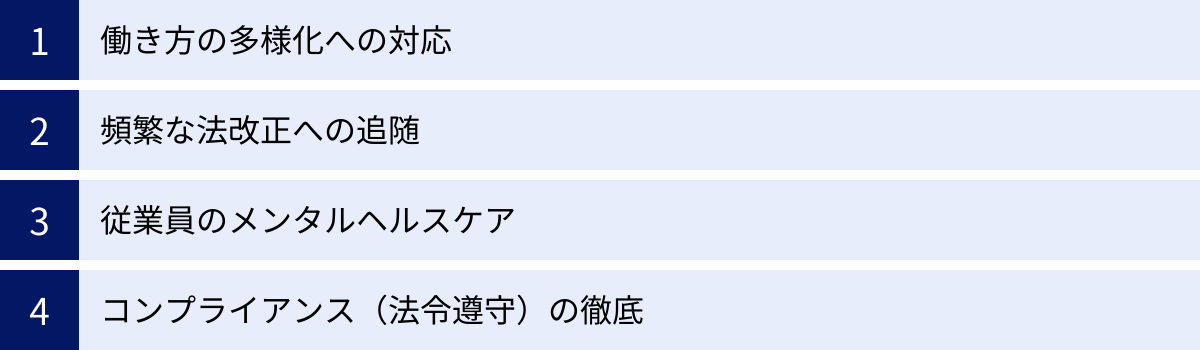
現代の企業を取り巻く環境は、目まぐるしく変化しています。それに伴い、従来の労務管理のあり方も大きな変革を迫られています。ここでは、企業が直面している代表的な4つの課題について解説します。
働き方の多様化への対応
かつて主流であった「正社員が毎日オフィスに出社し、定時まで働く」という画一的な働き方は、もはや当たり前ではありません。テレワーク(在宅勤務)、フレックスタイム制、時短勤務、そして副業・兼業など、従業員のライフスタイルや価値観に応じた多様な働き方が急速に普及しています。
この変化は、労務管理に新たな課題を突きつけています。
- 労働時間管理の複雑化: テレワークでは、従業員の労働時間を客観的に把握することが難しくなります。中抜け(業務時間中の私用による離席)の扱いをどうするか、始業・終業時刻をどう管理するかなど、新たなルール作りが必要です。また、フレックスタイム制ではコアタイムとフレキシブルタイムの管理、副業・兼業では自社と他社での労働時間の通算など、従来の管理手法では対応しきれないケースが増えています。適切な勤怠管理システムを導入し、客観的な記録を残すことが、サービス残業の温床化や長時間労働の見過ごしを防ぐために不可欠です。
- 人事評価の難しさ: オフィスで顔を合わせる機会が減ると、業務プロセスや勤務態度が見えにくくなり、成果物だけで評価せざるを得ない状況が生まれがちです。公平で納得感のある評価制度を維持するためには、評価基準の見直しや、定期的な1on1ミーティングによるコミュニケーションの活性化などが求められます。
- コミュニケーションと孤立の問題: テレワークが中心になると、従業員同士の偶発的なコミュニケーションが減り、チームの一体感が損なわれたり、新入社員が孤立感を深めたりするリスクがあります。チャットツールやWeb会議システムを効果的に活用するだけでなく、オンラインでの雑談会やチームビルディングの機会を意図的に設けるといった工夫が必要になります。
- セキュリティと費用負担: 自宅で業務を行う際のPCや通信環境のセキュリティ対策、そして通信費や光熱費といった費用の負担をどうするか、といった問題も労務管理上の重要な論点です。
これらの多様な働き方に柔軟に対応し、どの働き方を選択しても公平な処遇と安全な労働環境が保証されるような、新たな制度設計と運用が労務管理に求められています。
頻繁な法改正への追随
労働環境の改善や新たな働き方への対応を目的として、労働関連法規は頻繁に改正されています。近年でも、「働き方改革関連法」による大きな変更がありました。
- 時間外労働の上限規制: 36協定を結んでも超えられない、罰則付きの上限(原則月45時間・年360時間、臨時的な特別の事情があっても年720時間以内など)が設けられました。
- 年次有給休暇の年5日取得義務化: 企業は対象となる従業員に、年5日の有給休暇を確実に取得させなければならなくなりました。
- 同一労働同一賃金: 同じ企業内で働く正社員と非正規雇用労働者(パートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の、基本給や賞与、各種手当、福利厚生などにおける不合理な待遇差を解消することが求められます。
- 育児・介護休業法の改正: 男性の育児休業取得を促進する「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設や、育休取得の申し出・取得を円滑にするための雇用環境整備などが義務化されました。
これらの法改正に対応するためには、まず最新の法令情報を正確にキャッチアップし、その内容を深く理解する必要があります。その上で、就業規則や各種規程の改定、給与計算システムの変更、社内への周知徹底、管理職への研修など、実務レベルでの対応が求められます。
法改正への対応が遅れたり、解釈を誤ったりすると、法令違反となり、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、従業員からの訴訟リスクも高まります。継続的な情報収集と学習、そして専門家(社会保険労務士など)との連携が、これまで以上に重要になっています。
従業員のメンタルヘルスケア
仕事に関する強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される件数は増加傾向にあり、従業員のメンタルヘルスケアは企業の喫緊の課題となっています。特に、成果主義の浸透によるプレッシャーの増大、人間関係の希薄化、働き方の多様化に伴う孤独感などが、従業員の心に大きな負担をかけています。
この課題に対し、労務管理が担うべき役割は大きくなっています。
- ストレスチェック制度の適切な運用: 2015年から従業員50人以上の事業場で義務化されたストレスチェックを、単なる義務として形式的に実施するのではなく、その結果を有効に活用することが重要です。集団分析の結果から職場環境の課題を特定し、改善策に繋げる、高ストレス者に対して医師による面接指導を適切に勧奨し、フォローアップするといった取り組みが求められます。
- ハラスメント対策の徹底: パワーハラスメント防止措置が法的に義務化され、企業には相談窓口の設置や研修の実施などが求められています。被害者からの相談に適切に対応し、プライバシーを守りながら事実確認を行い、加害者への対処や再発防止策を講じる体制を構築しなければなりません。
- 長時間労働の是正: 長時間労働はメンタルヘルス不調の大きな要因です。勤怠データを継続的に監視し、過重労働の兆候がある従業員を早期に発見し、上長への働きかけや産業医面談に繋げることが重要です。
- 相談しやすい環境づくり: 従業員が不調を感じたときに、気軽に相談できる窓口(社内の人事労務担当者、産業医、保健師、外部のEAP(従業員支援プログラム)など)を整備し、その存在を広く周知することが、問題の早期発見・早期対応に繋がります。
メンタルヘルスケアは、問題が起きてから対応する「事後対応」から、問題が起きないように職場環境を整える「予防」へとシフトしていく必要があります。
コンプライアンス(法令遵守)の徹底
コンプライアンス(法令遵守)は、今や企業の存続を左右する最重要の経営課題の一つです。特に労務管理の領域では、その重要性が際立っています。
ひとたびサービス残業の常態化、不当解雇、ハラスメントなどの労働問題が発覚すれば、その影響は計り知れません。SNSや口コミサイトの普及により、従業員や元従業員による内部告発が瞬時に拡散し、「ブラック企業」というネガティブな評判が定着してしまうリスクがあります。
このような評判は、以下のような深刻な事態を引き起こします。
- 採用活動の困難化: 企業の評判を調べることが当たり前になった現在、悪い評判は学生や求職者に敬遠され、優秀な人材の確保が極めて難しくなります。
- 離職率の上昇: 既存の従業員のモチベーションが低下し、優秀な人材から流出していく事態を招きます。
- ブランドイメージの毀損: 顧客や取引先からの信頼を失い、売上の減少や取引の停止に繋がる可能性があります。
- 株価への影響: 上場企業であれば、株価の下落を招き、株主からの信頼も失います。
労務管理担当者には、自社に潜む労務リスクを洗い出し、未然に防止策を講じる役割が求められます。就業規則は実態に合っているか、36協定は適切に運用されているか、管理職はハラスメントに関する正しい知識を持っているか、といった点を常に点検し、改善していく必要があります。
コンプライアンスの徹底は、単なる「守り」の活動ではなく、企業の社会的信頼を築き、持続的な成長を実現するための「攻め」の投資であるという認識を持つことが重要です。
労務管理を効率化する2つの方法
ここまで見てきたように、労務管理の業務は多岐にわたり、専門性も高く、近年の環境変化によってその複雑性は増すばかりです。限られたリソースの中でこれらの課題に対応し、本来注力すべき戦略的な業務に時間を使うためには、業務の効率化が不可欠です。ここでは、そのための代表的な2つの方法をご紹介します。
① 労務管理システムを導入する
手作業やExcelでの管理に限界を感じている企業にとって、最も効果的な解決策の一つが「労務管理システム」の導入です。労務管理システムとは、入退社手続き、勤怠管理、給与計算、年末調整、社会保険手続きといった一連の労務業務を電子化・自動化し、一元管理するためのITツールです。
【労務管理システム導入の主なメリット】
- 圧倒的な業務効率化と自動化:
- 入退社手続き: 従業員がスマートフォンやPCから直接情報を入力することで、雇用契約書や社会保険の資格取得届などの書類が自動で作成されます。手書きや転記作業が不要になり、担当者の工数を大幅に削減できます。
- 年末調整: 従来は大量の紙の書類を回収・チェックする必要がありましたが、システムを使えば従業員がアンケート形式で回答するだけで、控除額の計算などが自動で行われます。
- Web給与明細: 給与明細を電子化して従業員に配布することで、印刷、封入、配布といった手間とコストを削減できます。
- ヒューマンエラーの削減と正確性の向上:
- 給与計算や社会保険料の計算など、複雑な計算をシステムが自動で行うため、手作業による計算ミスや転記ミスを防げます。データは一元管理されるため、情報の不整合も起こりにくくなります。正確なデータ管理は、コンプライアンス遵守の基礎となります。
- ペーパーレス化によるコスト削減とセキュリティ強化:
- 各種申請書や帳簿を電子データとして保存することで、紙の書類を保管するためのキャビネットや倉庫スペースが不要になります。また、印刷代や郵送費といったコストも削減できます。
- データにはアクセス権限を設定できるため、必要な人だけが情報にアクセスできるようになり、紙の書類よりも情報漏洩のリスクを低減できます。
- 法改正への迅速な対応:
- 社会保険料率の変更や新たな法律の施行など、頻繁な法改正に合わせてシステムが自動でアップデートされます。これにより、担当者が常に最新情報を追いかけなくても、法令に準拠した運用を維持しやすくなります。これは、労務管理における大きな安心材料です。
- 従業員の利便性向上とエンゲージメント強化:
- 従業員は、いつでもどこでもスマートフォンなどから勤怠打刻や休暇申請、住所変更などの各種手続きを行えるようになります。手続きのためにオフィスに行く必要がなくなり、利便性が大きく向上します。企業が従業員の働きやすさを考えているというメッセージにもなり、エンゲージメント向上に繋がる可能性があります。
【導入時の注意点】
- コスト: 初期導入費用や月額の利用料が発生します。費用対効果を十分に検討する必要があります。
- システム選定: 機能の豊富さだけでなく、自社の企業規模、業種、解決したい課題に合っているか、操作は分かりやすいか、サポート体制は充実しているか、といった多角的な視点で選定することが重要です。
- 社内への浸透: 新しいシステムの導入には、従業員への説明会やマニュアルの整備、操作トレーニングなどが必要です。導入して終わりではなく、全社的に活用されるための働きかけが欠かせません。
② アウトソーシング(外部委託)を活用する
もう一つの有効な手段が、労務管理業務の一部または全部を、専門知識を持つ外部の企業や専門家(特に社会保険労務士など)に委託する「アウトソーシング」です。
【アウトソーシング活用の主なメリット】
- 高度な専門性の確保:
- 社会保険労務士(社労士)などの専門家は、労働関連法規のプロフェッショナルです。頻繁な法改正にも迅速かつ正確に対応してくれるため、自社で対応する場合に比べて法令遵守のレベルが格段に高まります。複雑な社会保険手続きや助成金の申請、就業規則の作成・改定など、専門知識が求められる業務を安心して任せられます。
- コア業務への集中:
- 給与計算や社会保険手続きといった定型的・作業的な業務を外部に委託することで、社内の人事労務担当者は、より付加価値の高い戦略的な業務に集中できるようになります。例えば、人事評価制度の改善、従業員のキャリア開発支援、エンゲージメント向上のための施策立案など、企業の成長に直接貢献する活動に時間と労力を割くことができます。
- コスト削減の可能性:
- 特に中小企業において、労務管理のためだけに専門知識を持つ従業員を一人雇用するよりも、アウトソーシングを利用する方がトータルの人件費を抑えられる場合があります。また、担当者の採用や教育にかかるコストも削減できます。
- 業務の属人化防止:
- 労務管理業務が一人の担当者に集中している「属人化」の状態は、その担当者が休職や退職した場合に業務が完全にストップしてしまうという大きなリスクを抱えています。アウトソーシングを利用すれば、業務が組織的に行われるため、このようなリスクを回避し、業務の継続性を確保できます。
【活用時の注意点】
- 委託コスト: 当然ながら、継続的に委託費用が発生します。委託する業務範囲とコストが見合っているかを慎重に判断する必要があります。
- 情報漏洩のリスク: 従業員のマイナンバーや給与情報といった機密性の高い個人情報を外部に渡すことになるため、委託先のセキュリティ体制やプライバシーマークの取得状況などを厳しくチェックすることが不可欠です。
- 社内にノウハウが蓄積されにくい: 業務を完全に「丸投げ」してしまうと、自社に労務管理に関する知識や経験が蓄積されません。委託先と定期的にコミュニケーションを取り、報告を受けるなどして、自社の状況を常に把握し、管理する姿勢が重要です。
- コミュニケーションコスト: 自社の意図を正確に伝え、円滑に業務を遂行してもらうためには、委託先との密な連携が求められます。このコミュニケーションに手間がかかる場合もあります。
システム導入とアウトソーシングは、どちらか一方を選ぶだけでなく、組み合わせて活用することも有効です。例えば、日常的な勤怠管理や申請業務は労務管理システムで社内効率化を図り、専門性が高い社会保険手続きや就業規則の改定は社労士にアウトソーシングする、といったハイブリッドな活用法も考えられます。自社の状況に合わせて最適な方法を選択することが、労務管理の高度化と効率化を実現する鍵となります。
おすすめの労務管理システム4選
労務管理の効率化に不可欠な労務管理システム。ここでは、市場で高い評価を得ている代表的な4つのシステムを、それぞれの特徴とともにご紹介します。自社に最適なシステムを選ぶ際の参考にしてください。
※ここでの情報は2024年5月時点のものです。最新の機能や料金プランについては、必ず各社の公式サイトをご確認ください。
| システム名 | 提供会社 | 特徴 |
|---|---|---|
| SmartHR | 株式会社SmartHR | 圧倒的なシェアと抜群の使いやすさ。入社手続きから年末調整、タレントマネジメントまで幅広くカバー。 |
| freee人事労務 | freee株式会社 | freee会計とのシームレスな連携が強み。バックオフィス業務全体の一気通貫な効率化を実現。 |
| ジョブカン労務HR | 株式会社Donuts | 必要な機能だけを選んで導入できる柔軟性。勤怠管理や給与計算などシリーズ連携で強みを発揮。 |
| マネーフォワード クラウド人事管理 | 株式会社マネーフォワード | 人事データベースを中心に、組織シミュレーションや人事評価など戦略的な人事業務を支援。 |
① SmartHR
「SmartHR」は、多くの企業に導入されており、労務管理クラウド市場でトップクラスのシェアを誇るサービスです。最大の特長は、誰にとっても直感的で分かりやすいユーザーインターフェース(UI)にあります。人事労務の専門家でなくても、画面の指示に従って操作するだけで、簡単に入退社手続きや年末調整などを完結できます。
- 主な機能:
- 入社手続き・雇用契約: 従業員がスマホから情報入力するだけで、社会保険手続きに必要な書類が自動作成されます。雇用契約のオンライン締結も可能です。
- 年末調整: アンケート形式で質問に答えるだけで、面倒な申告書作成が完了。担当者のチェック作業も大幅に削減されます。
- 従業員データベース: 従業員情報を一元管理し、顔写真付きの組織図も自動で生成。異動シミュレーションも行えます。
- Web給与明細: 給与明細をオンラインで配布。ペーパーレス化を促進します。
- タレントマネジメント: SmartHRの強みとして、人事評価、従業員サーベイ(アンケート)といったタレントマネジメント機能も充実しており、労務管理に留まらず、戦略的な人事施策にも活用できます。
労務手続きのペーパーレス化・効率化を初めて進める企業や、従業員にも管理者にも使いやすいシステムを求めている企業に特におすすめです。
(参照:株式会社SmartHR 公式サイト)
② freee人事労務
「freee人事労務」は、クラウド会計ソフトで有名なfreee株式会社が提供するサービスです。最大の強みは、「freee会計」とのシームレスで強力な連携にあります。
- 主な機能:
- 勤怠管理から給与計算、年末調整まで: 従業員の勤怠打刻から給与計算、給与明細の発行、年末調整まで、一連の流れをシステム内で完結できます。
- 会計ソフトとの連携: 計算された給与や社会保険料のデータは、ボタン一つでfreee会計に連携され、会計仕訳が自動で作成されます。これにより、経理担当者の手間も大幅に削減され、バックオフィス全体の業務効率化に繋がります。
- 法令対応: 毎年のように変わる保険料率や税制改正にも自動でアップデート対応するため、常に最新の法令に準拠した計算が可能です。
特に、すでにfreee会計を利用している企業や、スモールビジネスから中堅企業まで、人事労務と経理のデータを一気通貫で管理し、バックオフィス業務全体を効率化したいと考えている企業に最適なシステムです。
(参照:freee株式会社 公式サイト)
③ ジョブカン労務HR
「ジョブカン」シリーズは、クラウド型業務支援システムとして幅広いラインナップを誇ります。「ジョブカン労務HR」は、その中核をなすサービスの一つです。特長は、必要な機能だけを選んで導入できる柔軟性とコストパフォーマンスの高さにあります。
- 主な機能とシリーズ連携:
- ジョブカン労務HR: 入退社手続き、従業員情報管理、年末調整、マイナンバー管理などを担います。
- シリーズ連携: 「ジョブカン勤怠管理」「ジョブカン給与計算」「ジョブカンワークフロー」など、他のジョブカンシリーズと組み合わせることで、自社のニーズに合わせた最適なシステム環境を構築できます。例えば、勤怠管理はすでに別のシステムを使っている場合、労務HRと給与計算だけを導入するといった選択が可能です。
- シンプルな操作性: シンプルで分かりやすい画面設計で、ITツールに不慣れな従業員でも使いやすいと評判です。
「まずは入退社手続きだけを効率化したい」「スモールスタートで導入し、将来的に機能を拡張していきたい」といったニーズを持つ企業や、コストを抑えつつ自社に必要な機能を選びたい企業に適しています。
(参照:株式会社Donuts 公式サイト)
④ マネーフォワード クラウド人事管理
「マネーフォワード クラウド」シリーズの一翼を担うのが「マネーフォワード クラウド人事管理」です。このサービスは、従業員情報を一元管理する「人事データベース」としての役割に重きを置いているのが特長です。
- 主な機能:
- 人事データベース: 従業員の基本情報、スキル、経歴、評価などを集約し、可視化します。
- 入退社・異動手続き: 従業員情報の変更に伴う各種手続きを効率化します。
- 組織図シミュレーション: ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、異動や組織改編のシミュレーションができ、最適な人員配置の検討を支援します。
- シリーズ連携: 「マネーフォワード クラウド勤怠」や「マネーフォワード クラウド給与」と連携することで、労務管理業務全体をカバーできます。
単なる労務手続きの効率化だけでなく、蓄積された従業員データを活用して、戦略的な人員配置や組織開発を行いたいと考えている企業、特に組織の成長や変化が速い企業にとって強力なツールとなるでしょう。
(参照:株式会社マネーフォワード 公式サイト)
まとめ
本記事では、「労務管理」というテーマについて、その基本的な定義から目的、具体的な仕事内容、人事管理との違い、そして現代的な課題とそれを解決するための効率化手法まで、包括的に解説してきました。
改めて要点を整理すると、労務管理とは以下の活動であると言えます。
- 法令遵守を土台とし、従業員が安心して働ける環境を整備する活動。
- 目的は、労務リスクを管理して企業の成長に貢献し、従業員の生産性を高め、労使間の信頼関係を築くこと。
- 仕事内容は、労働契約、就業規則、勤怠、給与、社会保険、安全衛生など、入社から退職までの多岐にわたる手続きと管理を含む。
- 人事管理が「個の最大化」を目指す攻めの役割なら、労務管理は「全体の基盤整備」を担う守りの役割であり、両者は車の両輪の関係にある。
そして現代において、労務管理は「働き方の多様化」「頻繁な法改正」「メンタルヘルスケア」「コンプライアンス徹底」といった、一筋縄ではいかない複雑な課題に直面しています。
これらの課題に効果的に対応し、企業の持続的な成長を実現するためには、もはや従来の手作業やExcelを中心とした管理手法には限界があります。労務管理は単なる事務作業ではなく、企業の未来を左右する戦略的な機能であるという認識のもと、積極的にそのあり方を見直す時期に来ています。
そのための強力な武器となるのが、「労務管理システム」の導入と「アウトソーシング」の活用です。これらの手法は、定型業務を効率化・自動化し、担当者を煩雑な作業から解放します。それによって生まれた時間とリソースを、従業員エンゲージメントの向上や、より働きやすい職場環境の構築といった、付加価値の高い業務に振り向けることが可能になります。
企業の最も重要な資産は「人」です。その人たちが安心して、意欲を持って、その能力を最大限に発揮できる環境を整えること。それこそが、労務管理に課せられた最大のミッションです。
この記事をきっかけに、まずは自社の労務管理の現状を振り返り、どこに課題があり、どのような改善が可能かを検討してみてはいかがでしょうか。その一歩が、企業の未来をより明るく、確かなものにするはずです。