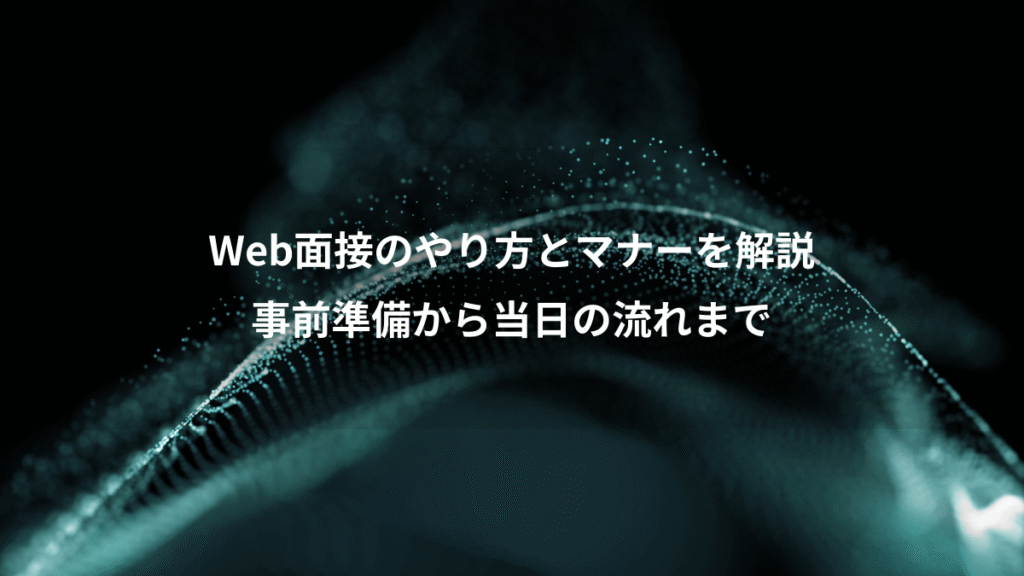近年、テクノロジーの進化と働き方の多様化に伴い、採用活動においてもWeb面接(オンライン面接)が急速に普及しました。場所を問わずに選考に参加できる利便性がある一方で、対面とは異なる独自の準備やマナーが求められます。初めてWeb面接に臨む方はもちろん、経験者であっても「これで本当に大丈夫だろうか?」と不安に感じる点は少なくないでしょう。
この記事では、Web面接の基本的な知識から、万全の体制で臨むための事前準備、好印象を与える当日の立ち居振る舞い、そして予期せぬトラブルへの対処法まで、網羅的に解説します。各ステップを丁寧に進めることで、自信を持って面接に臨み、あなたの魅力を最大限に伝える手助けとなるはずです。
目次
Web面接(オンライン面接)とは
Web面接とは、インターネットを介してパソコンやスマートフォンなどのデバイスを使用し、ビデオ通話形式で行われる面接のことです。オンライン面接とも呼ばれ、応募者は自宅やコワーキングスペースなど、企業が指定する場所以外からでも選考に参加できます。
新型コロナウイルス感染症の拡大を機に急速に普及しましたが、現在では感染症対策という側面に留まらず、採用活動のスタンダードな手法の一つとして定着しています。特に、一次面接や二次面接など、選考の初期段階で導入されるケースが多く見られます。遠隔地の優秀な人材にアプローチできる、採用コストを削減できるといった企業側のメリットも大きく、今後もこの流れは継続していくと予想されます。応募者にとっても、移動時間や交通費の負担がなくなるなど、多くの利点がある一方で、対面の面接とは異なる特有の注意点を理解しておくことが、選考を突破する上で極めて重要です。
対面面接との違い
Web面接と対面面接は、面接官と応募者がコミュニケーションを取り、相互理解を深めるという本質的な目的は同じです。しかし、その手段が「オンライン」か「オフライン」かによって、いくつかの重要な違いが生まれます。これらの違いを正しく認識し、Web面接ならではの対策を講じることが成功の鍵となります。
| 比較項目 | Web面接 | 対面面接 |
|---|---|---|
| 場所 | 自宅、コワーキングスペースなど自由度が高い | 企業のオフィスなど指定された場所 |
| 移動・費用 | 不要 | 必要(交通費、場合によっては宿泊費) |
| 必要な機材 | パソコン/スマホ、Webカメラ、マイク、安定した通信環境 | 基本的に不要(筆記用具や書類程度) |
| 雰囲気の伝わりやすさ | 限定的(非言語情報が伝わりにくい) | 伝わりやすい(空気感、熱意、人柄など) |
| コミュニケーション | タイムラグが発生しやすい、音声トラブルのリスク | スムーズな会話が可能 |
| 視線の合わせ方 | カメラのレンズを見る必要がある | 相手の目を見る |
| 面接官の情報 | 画面に表示される名前や役職を確認しやすい | 名刺交換などで確認 |
| カンペの使用 | 物理的に可能(ただしバレるリスク大) | 不可能 |
最も大きな違いは、非言語コミュニケーション(ノンバーバル・コミュニケーション)の伝達量です。対面面接では、表情、声のトーン、姿勢、ジェスチャー、場の空気感といった多くの情報が自然に伝わります。入室時の立ち居振る舞いや、話を聞く姿勢からも、その人の人柄や熱意を感じ取ることができます。
一方、Web面接では、画面というフレームを通しての情報伝達に限られるため、これらの非言語情報が著しく制限されます。カメラの画質やマイクの音質、通信環境によっては、微妙な表情の変化や声の抑揚が伝わりにくくなります。また、対面であれば感じ取れる「熱意」や「やる気」といった部分も、画面越しでは意図的に表現しないと伝わりづらい傾向があります。そのため、普段よりも少し大きめのリアクションや、ハキハキとした話し方を意識する必要があります。
さらに、通信環境という新たなリスク要因が加わる点も大きな違いです。対面面接では起こり得ない「音声が途切れる」「映像が固まる」といったトラブルが、Web面接では常に起こり得ます。こうしたトラブルへの備えができているかどうかも、評価の対象となり得るでしょう。
視線の合わせ方も独特です。対面では相手の目を見て話しますが、Web面接で画面に映る相手の目を見ていると、相手からは少し下を向いているように見えてしまいます。相手と目線を合わせるためには、デバイスのカメラレンズを見る必要があります。これは慣れが必要なため、事前の練習が不可欠です。
企業がWeb面接を行う目的
企業がWeb面接を積極的に導入する背景には、明確な目的とメリットが存在します。応募者側もその目的を理解することで、企業が何を重視しているのかを推測し、より効果的なアピールにつなげられます。
- 採用活動の効率化とコスト削減
最も大きな目的の一つが、採用プロセス全体の効率化です。対面面接の場合、面接官は応募者ごとに会議室を確保し、スケジュールを調整する必要があります。応募者が遠方に住んでいる場合は、移動時間も考慮しなければなりません。Web面接であれば、面接官は自席からでも面接に参加でき、移動時間がなくなるため、1日に対応できる面接の数を増やすことができます。
また、応募者の交通費支給や、遠方からの採用担当者の出張費、会場費といった採用にかかるコストを大幅に削減できる点も、企業にとって大きな魅力です。 - 採用ターゲットの拡大
Web面接は、地理的な制約を取り払います。地方や海外に住んでいる優秀な人材にも、対等な選考機会を提供できます。従来であれば、面接のために都市部まで足を運ぶことがネックとなり、応募をためらっていた層にもアプローチできるようになります。これにより、企業はより広範な母集団から、自社にマッチする人材を探し出すことが可能になります。特にUターン・Iターン転職や、グローバルな人材獲得を目指す企業にとっては、不可欠な採用手法となっています。 - 初期選考の迅速化
多くの応募者が集まる新卒採用や人気職種の募集では、初期選考に多くの時間と労力がかかります。Web面接を一次面接などの初期段階で活用することで、多数の応募者を迅速かつ効率的にスクリーニングできます。これにより、有望な候補者を早期に絞り込み、その後の対面での二次面接や最終面接にじっくりと時間をかける、といったハイブリッドな選考プロセスを組むことが可能です。 - 応募者のITリテラシーの確認
IT業界やWeb業界に限らず、現代のビジネスシーンでは、Web会議ツールの使用が当たり前になっています。Web面接をスムーズにこなせるかどうかは、応募者の基本的なITリテラシーや、新しいツールへの順応性を測る一つの指標となり得ます。事前の準備を怠らず、トラブルなく面接を終えること自体が、ビジネスパーソンとしての基礎能力のアピールにもつながるのです。 - 感染症対策と事業継続計画(BCP)
新型コロナウイルス感染症の流行は、Web面接普及の直接的なきっかけとなりましたが、これは感染症対策というだけでなく、企業の事業継続計画(BCP)の一環としても位置づけられています。今後、新たな感染症の流行や自然災害など、不測の事態が発生した場合でも、Web面接の仕組みが整っていれば、採用活動を止めることなく継続できます。これは、企業の持続的な成長にとって重要なリスク管理の一環です。
これらの目的を理解すると、企業がWeb面接において「スムーズなコミュニケーション能力」「基本的なITスキル」「計画性・準備力」といった点を注視していることがわかります。
Web面接のメリットとデメリット
Web面接は、応募者と企業双方にメリットをもたらしますが、同時にデメリットも存在します。両側面を正しく理解し、デメリットをいかにカバーするかが、Web面接を成功させるための重要なポイントです。
【応募者側のメリット】
- 時間と費用の節約: 面接会場への移動時間や交通費が一切かかりません。特に遠方の企業を受ける場合や、就職・転職活動で多くの企業を受ける場合には、大きな負担軽減となります。
- 場所の自由度: 自宅など、自分が最もリラックスできる環境で面接に臨めます。慣れた環境であるため、過度な緊張を和らげる効果が期待できます。
- スケジュール調整のしやすさ: 移動時間がないため、現職で働きながら転職活動をしている人でも、仕事の合間や終業後に面接の時間を確保しやすくなります。
- 物理的な資料の確認: カンペや手元資料を(見えない範囲で)確認しやすいという側面もあります。ただし、これに頼りすぎると不自然になるため注意が必要です。
【応募者側のデメリット】
- 通信環境に左右される: 最大のデメリットは、通信環境の安定性が面接の質を直接左右することです。通信が不安定だと、音声や映像が途切れ、コミュニケーションが阻害されるリスクがあります。
- 企業の雰囲気が分かりにくい: オフィスに足を運ばないため、社内の雰囲気や社員の働く様子などを肌で感じることができません。入社後のミスマッチにつながる可能性も否定できません。
- 非言語情報が伝わりにくい: 前述の通り、熱意や人柄が対面に比べて伝わりにくく、意図的な表現が求められます。
- 集中できる環境の確保が必要: 自宅で受ける場合、家族の生活音や予期せぬ来客など、集中を妨げる要因が発生する可能性があります。
【企業側のメリット】
- 採用コストの削減: 応募者の交通費、面接官の移動時間や人件費、会場費などを削減できます。
- 採用エリアの拡大: 国内外問わず、優秀な人材にアプローチできます。
- 選考の効率化・迅速化: スクリーニングを効率的に行い、採用プロセス全体のスピードを向上させます。
- 面接官の負担軽減: 移動の必要がなく、スケジュール調整が容易になるため、面接官の負担を軽減できます。
【企業側のデメリット】
- 応募者の本質が見抜きにくい: 画面越しの情報だけでは、応募者の人柄や潜在的な能力、細かな立ち居振る舞いなどを見極めるのが難しい場合があります。
- 自社の魅力が伝わりにくい: オフィスの雰囲気や設備、社員の活気といった、言語化しにくい自社の魅力を応募者に伝える機会が失われます。
- 通信トラブルによる機会損失: 応募者側の通信トラブルにより、有望な候補者との面接機会を失うリスクがあります。
- 情報漏洩のリスク: 面接内容を不正に録画・録音されるリスクがゼロではありません。
このように、Web面接には光と影の両側面があります。応募者としては、メリットを最大限に活かしつつ、デメリットである「通信環境」「雰囲気の伝わりにくさ」「集中できる環境」に対して、いかに事前準備で対策を打てるかが成功の分かれ道と言えるでしょう。
Web面接の事前準備は7ステップ
Web面接の成否は、事前準備で9割決まると言っても過言ではありません。当日に慌てないためにも、以下の7つのステップを一つひとつ丁寧に行い、万全の状態で臨みましょう。
① 安定したインターネット環境を整える
Web面接において最も重要なのが、安定したインターネット接続環境です。面接中に映像が固まったり、音声が途切れたりすると、コミュニケーションが円滑に進まないだけでなく、「準備不足」というマイナスの印象を与えかねません。
- 有線LAN接続を推奨: Wi-Fiは手軽ですが、電子レンジの使用や他のデバイスとの干渉など、予期せぬ要因で通信が不安定になることがあります。可能であれば、パソコンをLANケーブルでルーターに直接接続する「有線LAN接続」が最も安定しており、おすすめです。
- Wi-Fiを使用する場合の注意点: 有線LANが使えない場合は、Wi-Fiルーターの近くで接続しましょう。壁や障害物があると電波が弱まるため、できるだけルーターが見える場所が理想です。また、面接中は、他の家族に大容量のデータ通信(動画視聴やオンラインゲームなど)を控えてもらうようお願いしておくと、より安心です。
- 通信速度の確認: 事前にインターネットの速度テストサイト(「スピードテスト」などで検索すると見つかります)を利用して、通信速度を確認しておきましょう。Web会議ツールを快適に利用するための目安として、一般的に上り・下りともに10Mbps以上あれば十分とされていますが、安定性を考慮すると30Mbps以上あるとより安心です。特に、自分の映像を相手に送る「上り(アップロード)」の速度が重要になります。
- スマートフォンのテザリングは最終手段: 自宅に固定回線がない場合、スマートフォンのテザリング機能を利用する方法もあります。しかし、通信が不安定になりやすく、通信量制限に達してしまうリスクもあるため、あくまで最終手段と考えましょう。もし利用する場合は、データ通信量に余裕があるか必ず確認してください。
② パソコンやスマートフォンなどのデバイスを用意する
次に、面接に使用するデバイスを準備します。
- パソコン(PC)を強く推奨: Web面接には、画面が大きく、安定した設置が可能なパソコンの使用を強く推奨します。画面が大きいことで、面接官の表情がよく見え、コミュニケーションが取りやすくなります。また、キーボードでメモを取ったり、資料を確認したりする際にも便利です。カメラが内蔵されていない場合は、外付けのWebカメラを準備しましょう。
- スマートフォンやタブレットを使用する場合: パソコンを持っていない場合は、スマートフォンやタブレットでも面接は可能です。ただし、その場合はいくつかの注意点があります。
- 必ず固定する: 手で持ったまま面接を受けると、画面が揺れてしまい、相手に不快感を与えます。スマートフォンスタンドや三脚などを使って、目線の高さにしっかりと固定しましょう。
- 通知をオフにする: 面接中にメッセージアプリの通知音や着信音が鳴ると、集中が途切れるだけでなく、非常に失礼にあたります。必ず「おやすみモード」や「機内モード(Wi-Fiはオンにする)」などに設定し、すべての通知をオフにしてください。
- バッテリー切れに注意: ビデオ通話はバッテリーの消耗が激しいため、事前にフル充電しておくか、充電ケーブルを接続したまま面接に臨むのが安全です。
どちらのデバイスを使用する場合でも、OSやブラウザ、Web面接ツールのアプリは最新の状態にアップデートしておきましょう。古いバージョンだと、セキュリティ上の問題や、ツールが正常に動作しない原因となることがあります。
③ Web面接ツールを準備する
企業から指定されたWeb面接ツールを事前に準備し、使い方に慣れておくことは必須です。多くの企業では、Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsといった代表的なツールが使用されます。
代表的なWeb会議ツール(Zoom・Google Meet・Microsoft Teams)
企業から送られてくる案内に、使用するツールと接続用のURLが記載されています。事前にツールの特徴を把握し、インストールやアカウント作成が必要な場合は済ませておきましょう。
| ツール名 | 特徴 | アカウント作成 | 事前準備のポイント |
|---|---|---|---|
| Zoom | Web会議ツールの代表格。多くの企業で導入実績あり。機能が豊富で安定性が高い。 | 基本的に不要(招待URLから参加可能)。ただし、事前にアプリをインストールしておくとスムーズ。 | アプリを最新版にアップデートしておく。背景設定やマイク・カメラのテスト機能を事前に試しておく。 |
| Google Meet | Googleが提供。Gmailアカウントがあればすぐに利用可能。ブラウザベースで手軽に使える。 | 招待された側は不要な場合が多いが、Googleアカウントがあると便利。 | Google Chromeブラウザでの利用が推奨される。アカウント名やプロフィール画像が本名になっているか確認。 |
| Microsoft Teams | Microsoftが提供。Office 365との連携が強力で、ビジネスシーンで広く利用されている。 | 招待された側は不要な場合が多いが、事前にアプリをインストールしておくと安定する。 | アプリのインストールとアップデート。組織アカウントでログインしている場合、個人アカウントに切り替えるか、ゲストとして参加する。 |
これらのツールには、友人や家族に協力してもらい、実際に接続テストを行うことを強くおすすめします。音声が正しく聞こえるか、映像がきちんと映るか、背景は適切か、といった点を第三者の視点からチェックしてもらうことで、当日の不安を大幅に軽減できます。
アカウント名とプロフィール画像を確認する
Web面接ツールにログインする際、アカウント名がニックネームや無関係な文字列になっていないか、必ず確認してください。面接官が誰だか分からず、混乱させてしまいます。設定は必ず「氏名(フルネーム)」に変更しておきましょう。漢字表記が基本ですが、企業によってはひらがなやカタカナ、ローマ字表記を求められる場合もあるため、案内に従ってください。
同様に、プロフィール画像にも注意が必要です。プライベートで使用しているアニメのキャラクターやペットの写真などが設定されていると、ビジネスの場にふさわしくないと判断され、心証を損なう恐れがあります。プロフィール画像は設定しない(デフォルトのままにする)か、設定する場合は証明写真のようなクリアでフォーマルな写真にしましょう。
④ マイク付きイヤホンを用意する
Web面接では、クリアな音声コミュニケーションが不可欠です。パソコンやスマートフォンに内蔵されているマイクやスピーカーは、周囲の環境音を拾いやすかったり、音声がこもって聞こえたりすることがあります。
そこでおすすめなのが、マイク付きイヤホンの使用です。イヤホンを使うことで、以下のメリットがあります。
- クリアな音声を届けられる: 口元に近い位置にマイクがあるため、自分の声をクリアに相手に届けられます。
- 相手の声が聞き取りやすい: イヤホンから直接音声が聞こえるため、面接官の声が聞き取りやすくなり、聞き返す回数を減らせます。
- 生活音の防止: 周囲の雑音を拾いにくくし、自分の声だけを届けやすくなります。また、パソコンのスピーカーから出た音をマイクが拾ってしまうことで起こるエコー(ハウリング)を防ぐ効果もあります。
イヤホンは、高価なものである必要はありません。スマートフォンに付属しているものでも十分です。有線タイプのイヤホンは、充電切れや接続切れの心配がなく、安定しているため特におすすめです。ワイヤレスイヤホンを使用する場合は、面接時間に対してバッテリーが十分にあるか、必ず事前に確認しておきましょう。
⑤ 面接に集中できる場所を確保する
どこで面接を受けるかは、非常に重要な要素です。静かで、プライバシーが確保でき、面接に集中できる環境を整えましょう。
Web面接におすすめの場所
- 自宅の個室: 最もおすすめなのは、やはり自宅の個室です。リラックスでき、他人の目を気にせずに面接に集中できます。事前に家族に面接があることを伝え、その時間帯は部屋に入らないように、また静かにしてもらうよう協力を仰ぎましょう。
- コワーキングスペースの個室ブース: 自宅に適切な場所がない場合、有料のコワーキングスペースやレンタルスペースの個室ブースを利用するのも一つの手です。静かな環境と安定したインターネット回線が確保されている場合が多く、安心して面接に臨めます。
- 大学のキャリアセンターや個室: 在学中の学生であれば、大学のキャリアセンターなどがWeb面接用に個室ブースを貸し出している場合があります。予約が必要なことが多いので、早めに確認してみましょう。
カフェや図書館、公園など、公共の場所は絶対に避けるべきです。周囲の騒音が入るだけでなく、企業の機密情報に関わる会話が第三者に聞こえてしまう可能性があり、情報管理の意識が低いと判断されてしまいます。
背景とカメラ映り(明るさ)を確認する
面接官が目にする背景とあなたの顔の映り方は、第一印象を大きく左右します。
- 背景の整理整頓: 背景には、白い壁や無地のカーテンなど、シンプルで清潔感のある場所を選びましょう。背後にポスターや私物、洋服などが映り込むと、だらしない印象を与えたり、面接官の注意が散漫になったりします。生活感が出ないように、事前にしっかりと片付けておきましょう。
- バーチャル背景の利用は慎重に: Web面接ツールには、背景を隠すためのバーチャル背景機能があります。便利な機能ですが、企業の文化や職種によっては、カジュアルすぎると捉えられる可能性もあります。また、PCのスペックによっては動作が重くなったり、体の輪郭が不自然に消えたりすることもあります。基本的には実際の背景を整えるのがベストですが、もし使用する場合は、無地のシンプルな背景や、ぼかし機能に留めておくのが無難です。
- 明るさの確保(ライティング): 顔が暗く映ると、表情が分かりにくく、元気のない印象を与えてしまいます。自然光が正面から当たる窓際が最も理想的ですが、難しい場合は、照明を工夫しましょう。デスクライトなどを顔の正面から当てるか、安価なものでも効果が高い「リングライト」を用意すると、顔全体が明るく映り、血色が良く健康的な印象になります。画面に映る自分の顔を見ながら、ライトの位置を調整してみてください。逆光(背後に窓や強い光源がある状態)は顔が影になってしまうため、絶対に避けましょう。
⑥ 服装・身だしなみを整える
Web面接であっても、服装や身だしなみは対面面接と同様に重要です。画面に映るのは上半身だけと思いがちですが、不意に立ち上がった際などに全身が映る可能性もゼロではありません。
服装の選び方
- 企業の指示に従うのが基本: まずは企業からの案内メールを確認し、「スーツ着用」「私服可」「服装自由」などの指示に従います。
- 指示がない、または迷った場合はスーツが無難: 特に指示がない場合や、金融、公務員、大企業など、比較的堅い業界の場合は、リクルートスーツまたはビジネススーツを着用するのが最も安全です。清潔感があり、フォーマルな印象を与えられます。
- 「私服可」「服装自由」の場合: この場合でも、Tシャツやパーカーのようなラフすぎる服装は避けるべきです。「ビジネスカジュアル」を意識し、男性であれば襟付きのシャツやジャケット、女性であればブラウスやカットソーにジャケットを羽織るといったスタイルが適切です。色は白、紺、グレー、ベージュなど、清潔感のある落ち着いた色を選びましょう。
- 上下の服装を揃える: 上半身はスーツで、下は部屋着のスウェットパンツ、というのは絶対にやめましょう。何かの拍子に立ち上がった時に見えてしまうリスクがあるだけでなく、自分自身の気持ちの切り替えのためにも、上下ともに面接にふさわしい服装を着用することが大切です。
髪型・メイクのポイント
- 清潔感を第一に: 髪が顔にかからないように、すっきりとまとめましょう。寝癖などはもってのほかです。長い髪の女性は、後ろで一つに束ねると、清潔感が出て、お辞儀をしたときも邪魔になりません。
- Web面接用のメイク: 画面越しだと、通常のメイクでは顔色が悪く見えたり、ぼやけた印象になったりすることがあります。普段より少しだけ血色を良く見せるチークやリップを使い、アイラインを少しはっきり引くなど、メリハリを意識した「画面映え」するメイクがおすすめです。ただし、派手すぎるメイクは避け、あくまでナチュラルで健康的な印象を目指しましょう。
⑦ カンペの準備と効果的な使い方
Web面接では、物理的にカンペ(カンニングペーパー)を用意することが可能です。しかし、その使い方には細心の注意が必要です。
- カンペは「お守り」程度に: カンペを棒読みするのは絶対にNGです。視線が不自然に泳ぎ、面接官にはすぐに見抜かれます。熱意が伝わらず、コミュニケーション能力が低いと判断されてしまうでしょう。カンペは、あくまで「話すべきキーワード」や「逆質問のリスト」など、忘れてしまいがちな要点を書き出す程度に留めましょう。
- 効果的な使い方:
- 付箋にキーワードを書いてPCに貼る: 話したいことの要点(単語レベル)を小さな付箋に書き、カメラの横など、視線が大きく動かない位置に貼っておくと、自然に確認できます。
- 手元のノートに要点をまとめる: PCの横にノートを置き、話の構成やキーワードをメモしておきます。話しながら時折視線を落として確認する程度であれば、不自然には見えにくいです。メモを取るふりをして確認することもできます。
- 練習で内容を頭に入れるのが最善: カンペに頼るのではなく、事前に声に出して話す練習を繰り返し、話す内容を自分の言葉として頭に入れておくことが最も重要です。カンペは、万が一頭が真っ白になってしまった時のための、保険やお守りとして準備しておくのが理想的な付き合い方です。
Web面接当日の流れとマナー
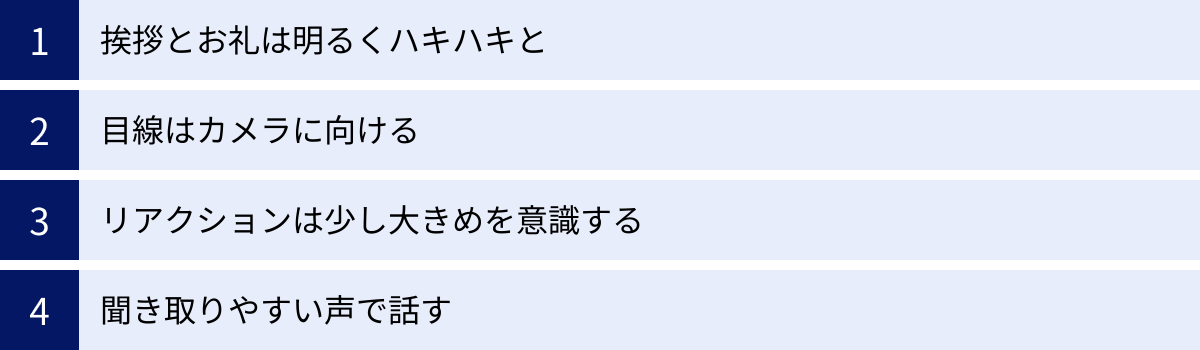
事前準備を万端に整えたら、いよいよ面接当日です。対面とは異なるWeb面接特有の流れとマナーを理解し、落ち着いて臨みましょう。
面接開始前:5〜10分前にはログインする
対面面接では、受付を済ませる時間として5〜10分前に到着するのが一般的です。Web面接でもこの考え方は同様で、指定された時刻の5〜10分前には入室(ログイン)を済ませておくのがマナーです。
- 早すぎるログインは避ける: 15分以上前など、あまりに早く入室すると、前後の面接や会議の都合で面接官がまだ準備できていない可能性があります。かえって迷惑をかけてしまう場合があるため、早すぎる入室は控えましょう。
- 直前の最終チェック: 5〜10分前になったら、企業から送られてきたURLをクリックして入室します。待機室に通される場合もあれば、直接面接画面につながる場合もあります。面接官が入室してくるまでの間に、以下の最終チェックを行いましょう。
- カメラの映り: 自分の顔が画面の中央に来ているか、明るさは十分か。
- マイクと音声: マイクがミュートになっていないか。イヤホンは正しく接続されているか。
- 背景: 背景に余計なものが映り込んでいないか。
- 服装・身だしなみ: 髪の乱れや服装のしわなどがないか。
- 待機中の姿勢: 待機画面で自分の顔が映っている場合でも、油断は禁物です。いつ面接官が入室してきても良いように、背筋を伸ばし、穏やかな表情で待機しましょう。スマートフォンをいじったり、あくびをしたりするのは厳禁です。
時間になっても面接官が入室してこない場合は、慌てずに5分程度待ってみましょう。それでも状況が変わらなければ、事前に知らされている緊急連絡先に電話かメールで状況を伝えます。
面接中:好印象を与える4つのポイント
面接が始まったら、いよいよ本番です。画面越しでもあなたの魅力がしっかりと伝わるよう、以下の4つのポイントを意識してコミュニケーションを取りましょう。
① 挨拶とお礼は明るくハキハキと
Web面接では、第一印象が特に重要です。面接官が入室したら、自分から明るくハキハキとした声で挨拶をしましょう。
- 開始時の挨拶: 面接官が入室し、相手の音声が聞こえることを確認したら、すぐに「〇〇大学の△△(氏名)です。本日はよろしくお願いいたします」と挨拶します。その際、座ったままで構いませんので、丁寧に一礼(軽く頭を下げる)すると、より丁寧な印象を与えます。
- 自己紹介: 面接官から促されたら、自己紹介を始めます。対面よりも声がこもりやすいため、いつもより少し高めのトーンで、明瞭な発声を心がけましょう。
- 面接中の相槌: 面接官が話している間は、ただ黙って聞いているだけでは、聞いているのかどうか不安にさせてしまいます。「はい」という返事や、適度な相槌、そして頷きを意識的に行うことで、話を真剣に聞いている姿勢をアピールできます。
- 感謝の言葉: 面接の機会をいただいたことへの感謝を最初に伝えるのはもちろん、面接の最後にも「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました」と、改めて感謝の気持ちを伝えましょう。
② 目線はカメラに向ける
Web面接で最も意識すべき、そして最も難しいのが「目線」です。対面面接では相手の目を見て話しますが、Web面接で画面に映る相手の目を見てしまうと、あなたの視線はやや下向きになり、相手からは「伏し目がちで自信がなさそう」「どこか違うところを見ている」という印象を持たれてしまいます。
相手に「目を見て話している」と感じさせるためには、パソコンやスマートフォンのカメラのレンズを見る必要があります。
- カメラの位置を意識する: 普段から、自分のデバイスのカメラがどこにあるのかを正確に把握しておきましょう。
- 話すときはカメラ、聞くときは画面: ずっとカメラを見続けるのは不自然ですし、相手の表情が分かりません。自分が話すときは意識してカメラのレンズに視線を送り、相手が話しているときは画面を見て表情や反応を伺う、というように使い分けるのがおすすめです。
- カメラの横に目印を貼る: どうしても画面の相手を見てしまうという人は、カメラのすぐ横に小さな矢印のシールや付箋を貼るなどして、意識が向くように工夫するのも一つの手です。
- 練習あるのみ: このカメラ目線は、慣れが必要です。事前に録画機能を使い、自分が話しているときの目線がどうなっているかを確認し、修正する練習を繰り返しましょう。
③ リアクションは少し大きめを意識する
画面越しでは、細かな表情の変化や頷きが伝わりにくくなります。無表情に見えてしまうと、「話に興味がないのでは?」「理解しているのだろうか?」と面接官を不安にさせてしまいます。
そのため、普段の対話よりも1.5倍くらい大きなリアクションを心がけましょう。
- 頷き: 面接官の話に合わせて、意識的に「うん、うん」と頷きます。ゆっくりと深く頷くことで、深く理解しようとしている姿勢が伝わります。
- 笑顔: 真剣な表情ばかりでなく、適度に笑顔を見せることも大切です。特に自己紹介や、自身の長所・成功体験を話すときなどは、口角を上げて明るい表情を作ることで、ポジティブで親しみやすい印象を与えられます。
- ジェスチャー: 身振り手振りを交えるのも効果的です。ただし、大げさすぎると画面の外にはみ出してしまったり、落ち着きのない印象を与えたりするので、胸から上の範囲で、要点を強調する際に軽く使う程度に留めましょう。
これらのリアクションは、あなたが積極的にコミュニケーションを取ろうとしている意欲の表れとして、面接官に好意的に受け取られます。
④ 聞き取りやすい声で話す
通信環境によっては、音声が不明瞭になることがあります。また、マイクを通した声は、肉声とは違って聞こえることも多いです。そのため、普段よりもさらに「聞き取りやすさ」を意識した話し方が求められます。
- 声のトーンとボリューム: いつもより少し高めのトーンで、はっきりと話すことを意識しましょう。ボソボソと話すと、自信がないように聞こえるだけでなく、単純に聞き取れない可能性があります。
- 話すスピード: 緊張すると早口になりがちですが、Web面接では通信のタイムラグも考慮し、少しゆっくりめのスピードで話すのが基本です。相手が聞き取りやすいペースを意識しましょう。
- 結論から話す(PREP法): これは対面面接でも同様ですが、Web面接では特に有効です。まず結論(Point)を述べ、次にその理由(Reason)、具体的な例(Example)、そして最後にもう一度結論(Point)を繰り返す「PREP法」を意識すると、話が簡潔で分かりやすくなります。
- 「間」を大切に: 相手が話し終わってから、一呼吸置いてから話し始めるようにしましょう。通信のタイムラグで、相手の発言に被せて話してしまう「会話被り」を防ぐことができます。焦らず、落ち着いて話す姿勢が、信頼感につながります。
面接終了時:相手が退出してから接続を切る
面接が終わり、最後の挨拶を交わした後にも、大切なマナーがあります。
面接官から「本日の面接は以上です。退出してください」といった指示があったら、「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。失礼いたします」と改めてお礼を述べ、丁寧に一礼します。そして、自分で接続を切るのではなく、相手が退出するのを待ちます。
これは、対面面接で、相手(お客様)が部屋を出て姿が見えなくなるまで見送るのと同じ意味合いを持つビジネスマナーです。面接官が退出したことを確認してから、静かに「接続を切る」または「退出」ボタンをクリックしましょう。最後の最後まで気を抜かず、丁寧な対応を心がけることが、良い印象を残すための最後の仕上げとなります。
ただし、面接官から「それでは、〇〇さんから退出してください」と指示された場合は、その指示に従い、「失礼いたします」と一言添えてから退出しましょう。
面接後:お礼メールを送る
Web面接後のお礼メールを送るかどうかは、意見が分かれるところですが、基本的には送ることをおすすめします。必須ではありませんが、丁寧な印象を与え、入社意欲の高さをアピールする追加の機会となり得ます。
- 送るタイミング: 面接当日中、遅くとも翌日の午前中までには送りましょう。時間が経ちすぎると、かえって印象が薄れてしまいます。
- 件名: 件名は「【Web面接のお礼】氏名(大学名)」のように、誰から何のメールかが一目で分かるようにします。
- 本文に盛り込む内容:
- 宛名(会社名、部署名、担当者名)
- 挨拶と氏名
- 面接のお礼
- 面接で特に印象に残ったことや、それによってさらに志望度が高まった点など(簡潔に)
- 入社意欲
- 結びの挨拶
- 署名(氏名、大学・学部、連絡先)
お礼メールは、あくまで感謝を伝えるためのものです。長文で自己PRを繰り返したり、面接での失敗を謝罪したりするのは避けましょう。簡潔で誠意の伝わる内容を心がけることが大切です。
Web面接でよくある質問と逆質問の対策
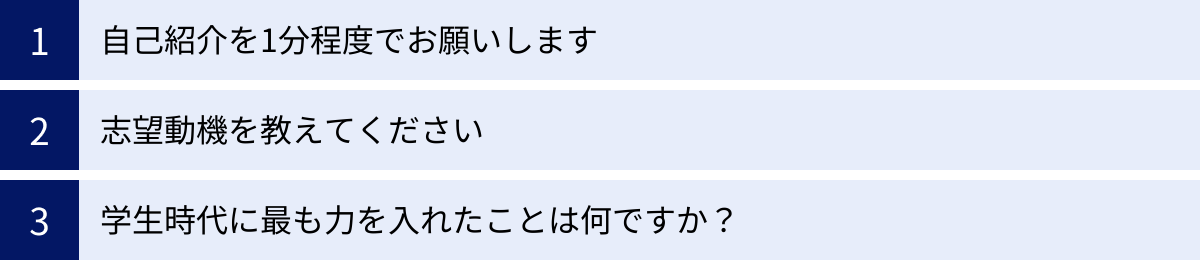
Web面接で聞かれる質問の内容は、基本的には対面面接と大きくは変わりません。しかし、Webという環境だからこそ、より分かりやすく、簡潔に伝える工夫が求められます。ここでは、頻出質問への対策と、評価を高める逆質問のポイントについて解説します。
Web面接で頻出の質問と回答例
自己PR、志望動機、ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)といった定番の質問は、Web面接でも必ず聞かれると考えて準備しておきましょう。回答のポイントは、「結論ファースト」と「具体的なエピソード」です。
1. 「自己紹介を1分程度でお願いします」
これは面接の冒頭で聞かれることが多く、第一印象を決める重要な質問です。
- 回答の構成要素:
- 氏名と所属(大学名など)
- 自分の強みやキャッチフレーズ
- その強みを発揮した具体的なエピソードの要約
- 入社後の貢献意欲
- 結びの挨拶
- Web面接でのポイント:
- 明るく、ハキハキとした声で始めることを特に意識します。
- 時間を意識し、ダラダラと話さず、1分以内に簡潔にまとめます。事前に声に出して時間を計っておきましょう。
- カメラ目線を意識し、自信のある表情で話すことが大切です。
(回答例)
「〇〇大学〇〇学部の△△と申します。本日は貴重な面接の機会をいただき、ありがとうございます。私の強みは、目標達成に向けた課題分析力と実行力です。大学時代の〇〇という活動では、当初目標としていた参加者数に届かないという課題がありましたが、原因を分析し、SNSを活用した新たな広報戦略を立案・実行しました。その結果、最終的には目標を120%達成することができました。この経験で培った課題解決能力を活かし、貴社でも〇〇といった領域で貢献したいと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。」
2. 「志望動機を教えてください」
企業への熱意と理解度を測るための質問です。なぜこの業界、なぜこの会社、なぜこの職種なのかを論理的に説明する必要があります。
- 回答のポイント:
- 「なぜこの会社でなければならないのか」を明確に伝えることが最も重要です。企業の事業内容、企業理念、社風などを深く研究し、自分の経験や価値観と結びつけます。
- 抽象的な言葉(例:「社会に貢献したい」「成長したい」)だけでなく、具体的な事業や取り組みに触れ、自分なりの考えを述べましょう。
- Web面接でのポイント:
- 熱意が伝わりにくい分、声のトーンや表情で「この会社で働きたい」という強い気持ちを表現することが求められます。
- 企業のWebサイトや資料などを画面に表示させて読むのではなく、自分の言葉で情熱を込めて語りましょう。
(回答例)
「私が貴社を志望する理由は、業界のリーディングカンパニーとして常に革新的なサービスを生み出し続ける姿勢に強く共感したからです。特に、貴社が注力されている〇〇事業は、私の大学での研究テーマである△△と深く関連しており、専門知識を活かせると考えています。また、先日拝見した〇〇様(役員など)のインタビュー記事で語られていた『失敗を恐れずに挑戦する文化』は、私が仕事選びで最も大切にしている価値観と一致します。貴社の一員として、これまで培ってきた課題解決能力を活かし、〇〇事業のさらなる発展に貢献したいと強く願っております。」
3. 「学生時代に最も力を入れたことは何ですか?(ガクチカ)」
応募者の人柄、価値観、ポテンシャル(目標達成能力、課題解決能力など)を知るための定番質問です。
- 回答のポイント:
- STARメソッド(Situation: 状況、Task: 課題、Action: 行動、Result: 結果)を意識して構成すると、分かりやすく伝えられます。
- どのような状況で、何を課題と捉え、それに対して自分がどう考え、どう行動したのか、そしてその結果どうなったのか、というストーリーを具体的に語ります。
- 結果(Result)は、定量的な成果(例:売上を10%向上させた)があればより説得力が増しますが、定性的な成果(例:チームの結束力を高めた、新しい仕組みを構築した)でも問題ありません。
- Web面接でのポイント:
- エピソードを生き生きと語るために、身振り手振りを少し交えたり、表情を豊かにしたりすると効果的です。
- 話が長くなりすぎないよう、要点をまとめて簡潔に話すことを心がけましょう。
(回答例)
「私が学生時代に最も力を入れたのは、飲食店でのアルバイトにおいて、新人教育の仕組みを改善したことです。(Situation)当時、新人の離職率の高さが課題となっており、その原因が教育体制の不備にあると考えました。(Task)そこで私は、店長に提案し、体系的な研修プログラムの作成に取り組みました。(Action)具体的には、既存のスタッフにヒアリングを行い、つまずきやすいポイントを洗い出し、写真付きの分かりやすいマニュアルを作成しました。また、先輩がマンツーマンで指導する『ブラザー・シスター制度』の導入を提案し、実行しました。(Result)その結果、導入後3ヶ月で新人の離職率は以前の半分以下に低下し、店舗全体のサービス品質の向上にも繋がりました。この経験から、主体的に課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決していくことの重要性を学びました。」
逆質問のポイントと質問例
面接の終盤に「何か質問はありますか?」と聞かれる「逆質問」は、単なる疑問解消の場ではなく、自己PRの絶好の機会です。意欲の高さや企業理解度を示すチャンスと捉え、質の高い質問を準備しておきましょう。
逆質問の目的:
- 入社意欲のアピール: 鋭い質問は「それだけ真剣に考えてくれている」という熱意の表れと受け取られます。
- 企業理解度の証明: 事前にしっかり調べていないとできない質問をすることで、企業研究の深さを示せます。
- 情報収集とミスマッチ防止: 入社後の働き方やキャリアについて具体的に知ることで、自分に合う会社かを見極めます。
逆質問の準備:
- 最低でも3〜5個は準備しておく: 面接の中で疑問が解消されることもあるため、複数の質問を用意しておくと安心です。
- 質問のジャンルを分ける: 「事業・戦略に関する質問」「仕事内容・働き方に関する質問」「キャリア・成長に関する質問」など、異なる角度からの質問を準備しておくと良いでしょう。
質の高い逆質問の例:
- 事業内容や今後の戦略に関する質問:
- 「〇〇事業について、今後の展望や課題について、差し支えのない範囲でお聞かせいただけますでしょうか。」
- 「御社の〇〇という企業理念を、社員の皆様はどのような場面で実感されることが多いですか。」
- 入社後の業務に関する質問:
- 「配属後は、どのようなスキルや知識を早期に身につけることが期待されていますでしょうか。」
- 「1日の業務の流れについて、典型的なスケジュールを教えていただけますか。」
- 「チームで仕事を進めることが多いと伺いましたが、チーム内でのコミュニケーションはどのような形(ツールや頻度など)で取られているのでしょうか。」
- キャリアパスや成長環境に関する質問:
- 「御社でご活躍されている方には、どのような共通点や特徴がありますでしょうか。」
- 「入社後に成果を出すために、今のうちから勉強しておくと良いことがあれば教えていただきたいです。」
- 面接官個人への質問:
- 「〇〇様(面接官の名前)が、このお仕事で最もやりがいを感じるのはどのような瞬間ですか。」
避けるべき逆質問:
- 調べればすぐに分かる質問: 企業のWebサイトや採用ページに明記されていること(例:福利厚生、年間休日数)を聞くのは、準備不足を露呈するだけです。「調べた上で、さらに深く知りたい」という聞き方ならOKです。
- 給与や待遇に関する質問(初期選考では特に): 選考の早い段階で待遇面ばかりを質問すると、仕事内容への興味が薄いと捉えられかねません。内定が近づいた段階で確認するのが一般的です。
- 「特にありません」と答える: 最も避けるべき回答です。入社意欲がないと判断されてしまいます。たとえ疑問が解消されていても、「丁寧にご説明いただいたので、現時点ではございません。ありがとうございました」とお礼を述べるなど、コミュニケーションを閉ざさない姿勢が大切です。
Web面接でよくあるトラブルと対処法
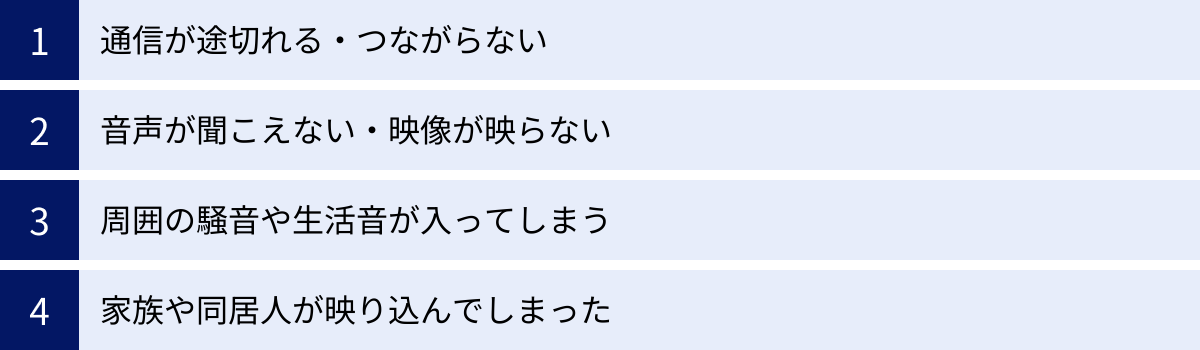
どれだけ万全に準備をしていても、予期せぬトラブルは起こり得ます。重要なのは、トラブルが発生した際に、慌てず冷静に対処する姿勢を見せることです。ここでは、よくあるトラブルとその対処法を事前に確認しておきましょう。
通信が途切れる・つながらない
最も頻繁に発生し、かつ面接への影響も大きいのが通信トラブルです。
- 原因:
- インターネット回線の混雑や不安定さ
- Wi-Fiルーターやデバイスの不調
- Web面接ツール側のサーバー障害
- 事前対策:
- 有線LAN接続を利用することが最も効果的な対策です。
- 事前に速度テストを行い、安定性を確認しておく。
- 企業の緊急連絡先(電話番号やメールアドレス)を必ず控えておく。これが最も重要です。
- Web面接ツールのアプリを再起動したり、デバイス自体を再起動したりしておく。
- 発生時の対処法:
- まずは落ち着く: 焦っても状況は改善しません。冷静になることが第一です。
- チャット機能で伝える: もしツールにチャット機能があれば、「通信環境が不安定なため、音声が途切れております。少々お待ちいただけますでしょうか」などと状況を伝えます。
- 再接続を試みる: 一度退出して、再度URLから入室し直します。これで改善することが多いです。
- デバイスを再起動する: それでも改善しない場合は、パソコンやスマートフォンを再起動してみます。
- 緊急連絡先に連絡する: 5分以上復旧しない場合や、完全に接続できなくなった場合は、すぐに控えておいた緊急連絡先に電話しましょう。「大変申し訳ございません。通信トラブルで接続できない状況です」と正直に伝え、指示を仰ぎます。無断で中断してしまうのが最悪の事態です。誠実に対応する姿勢を見せることが重要です。
音声が聞こえない・映像が映らない
「こちらの声が届かない」「相手の声が聞こえない」「自分の顔が映らない」といった機材関連のトラブルもよくあります。
- 原因:
- マイクやスピーカー、カメラがミュート(オフ)になっている。
- OSやブラウザの設定で、マイクやカメラへのアクセスが許可されていない。
- イヤホンやWebカメラの接続不良。
- Web面接ツール側で、正しいデバイスが選択されていない。
- 事前対策:
- 友人や家族と接続テストを行い、音声・映像が正常に機能するかを必ず確認する。
- OSの「プライバシー設定」やブラウザの「サイト設定」で、使用するツールに対してマイクとカメラのアクセスが許可されているかを確認しておく。
- 発生時の対処法:
- まずは設定を確認:
- ミュートになっていないか?: ツール画面のマイクアイコンやカメラアイコンに斜線が入っていないか確認します。
- 物理的なスイッチは?: イヤホンやWebカメラに物理的なミュートスイッチがある場合は、それがオフになっていないか確認します。
- ツールのデバイス設定を確認: Web面接ツールの設定画面を開き、「オーディオ設定」「ビデオ設定」などで、使用したいマイク、スピーカー、カメラが正しく選択されているかを確認します。複数のデバイスが接続されていると、意図しないものが選択されていることがあります。
- 接続を確認: イヤホンやWebカメラのケーブルを一度抜き差ししてみます。
- チャットで状況を伝える: 音声トラブルの場合、チャット機能を使って「申し訳ありません、音声が聞こえない(届かない)ようです。設定を確認いたしますので少々お待ちください」と伝えます。
- 再起動: 最終手段として、ツールの再起動やデバイスの再起動を試みます。その際も、チャットや緊急連絡先で状況を伝えることを忘れないようにしましょう。
- まずは設定を確認:
周囲の騒音や生活音が入ってしまう
自宅で面接を受ける際に起こりがちなトラブルです。
- 原因:
- 家族の声やテレビの音
- ペットの鳴き声
- インターホンや電話の着信音
- 救急車や工事の音などの外部騒音
- 事前対策:
- 面接があることを家族全員に伝え、静かにしてもらうよう協力を依頼する。
- ペットは別の部屋に移動させておく。
- インターホンや固定電話は、可能であれば一時的に音量を下げるかオフにする。
- 窓を閉め、外部の音を遮断する。
- 発生時の対処法:
- 予期せぬ音が入ってしまった場合: 「大変失礼いたしました」と一言簡潔に謝罪します。長々と弁解する必要はありません。すぐに会話に戻りましょう。
- 騒音が続く場合: 工事の音など、しばらく続くことが予想される場合は、「申し訳ございません。少々騒がしいようですので、ミュート機能を活用しながらお話しさせていただきます」と断りを入れると丁寧です。自分が話す時だけミュートを解除し、聞くときはミュートにする、という対応を取りましょう。
家族や同居人が映り込んでしまった
個室で受けていても、予期せず家族が部屋に入ってきてしまうこともあり得ます。
- 原因:
- 家族が面接中であることを忘れていた。
- 小さな子供がいる場合など。
- 事前対策:
- 部屋のドアに「面接中・入室禁止」といった貼り紙をしておくのが効果的です。
- ドアに鍵をかける。
- 発生時の対処法:
- 万が一映り込んでしまったら、慌てず騒がず、「大変失礼いたしました」と冷静に謝罪します。これも、その後の対応が重要です。動揺した姿を見せるのではなく、落ち着いて面接を続ける姿勢が、あなたの対応能力の高さを示すことにも繋がります。
トラブルは誰にでも起こりうることです。企業側もその点は理解しています。重要なのは、トラブルそのものではなく、その後の誠実で冷静な対応であることを肝に銘じておきましょう。
Web面接に関するQ&A
最後に、Web面接に関して多くの人が抱く細かな疑問について、Q&A形式で回答します。
スマートフォンで受けても大丈夫?
結論として、可能であればパソコン(PC)での受験を強く推奨しますが、スマートフォンでも受験は可能です。
企業側は、応募者がどのようなデバイスで参加してくるかを想定しています。ただし、スマートフォンで受ける場合は、PCに比べて不利にならないよう、以下の点に細心の注意を払う必要があります。
- 固定器具は必須: スマートフォンスタンドや三脚を使い、目線の高さで画面が揺れないようにしっかりと固定してください。手持ちでの参加は、画面が不安定になるだけでなく、片手が塞がってしまうため絶対に避けましょう。
- 通知は完全にオフ: 面接中にLINEの通知音や着信音が鳴るのは、マナー違反であり、集中力を著しく削ぎます。「おやすみモード」や「集中モード」に設定し、すべての通知をシャットアウトしてください。
- バッテリー対策: ビデオ通話はバッテリー消費が激しいため、フル充電しておくか、充電しながら面接に臨むのが安全です。
- 通信の安定性: Wi-Fi環境下で接続するのが基本です。モバイルデータ通信は不安定になるリスクや、通信制限の可能性があるため、できるだけ避けましょう。
PCを推奨する最大の理由は、画面の大きさによるコミュニケーションのしやすさと、設置の安定性にあります。面接官の表情をしっかり読み取れる、資料を画面共有された際に見やすいといったメリットは、PCならではです。もしPCが用意できるのであれば、そちらを優先しましょう。
イヤホンは使ったほうが良い?
はい、マイク付きイヤホンの使用を強く推奨します。
イヤホンは、もはやWeb面接における必須アイテムの一つと言えます。理由は以下の通りです。
- 音声品質の向上: 内蔵マイクよりも口元に近い位置のマイクで話すため、自分の声をクリアに相手に届けられます。「声が小さい」「こもって聞こえる」といった音声トラブルを大幅に減らせます。
- 聞き取りやすさの向上: 相手の声が耳に直接届くため、周囲の雑音に邪魔されずに集中して聞くことができます。聞き返しが減り、スムーズな会話につながります。
- ハウリングの防止: PCのスピーカーから出た音をPCのマイクが拾ってしまうことで起こる「キーン」という不快な音(ハウリングやエコー)を防ぐことができます。
- 生活音の低減: ある程度の生活音や環境音をシャットアウトし、面接に集中しやすくなります。
イヤホンは高価なものである必要はありません。安定性を重視するなら、充電不要で接続も安定している有線タイプが最もおすすめです。ワイヤレスタイプを使用する場合は、面接時間中にバッテリーが切れないよう、事前の充電を忘れないようにしてください。
カンペはどの程度まで許される?
Web面接ではカンペを用意できますが、その存在が面接官にバレてしまうと、「自分の言葉で話す能力がない」「準備不足で熱意が低い」といったネガティブな印象を与えかねません。
したがって、カンペの扱いには最大限の注意が必要です。
- 許容されるレベル:
- 話したいことの「キーワード」や「要点」のメモ: どうしても忘れたくない単語や、話の構成などを箇条書きにしたメモ程度であれば、許容範囲と言えるでしょう。
- 逆質問のリスト: 準備してきた逆質問のリストを手元に置いておくのは問題ありません。
- NGな使い方:
- 文章をそのまま読み上げる: 視線が一点に固定されたり、不自然に上下したりするため、ほぼ100%バレます。抑揚のない話し方になり、熱意も全く伝わりません。
- バレないための工夫:
- カメラの横に付箋を貼る: PCのカメラのすぐ横に、キーワードを書いた小さな付箋を貼っておけば、視線の移動を最小限に抑えられます。
- 画面の下部にメモを表示する: PCの場合、画面下部にテキストエディタなどを小さく表示させておく方法もありますが、視線が下がりがちになるため注意が必要です。
最も重要なのは、カンペに頼らずに話せるように、繰り返し練習しておくことです。カンペは、あくまで頭が真っ白になった時のための「お守り」や「保険」として準備する、という心構えで臨むのが理想的です。
お辞儀はしたほうが良い?
はい、お辞儀はするべきです。 ただし、対面とは少しやり方が異なります。
Web面接では、カメラに映る範囲が限られているため、対面のように深く腰から曲げる立礼をすると、画面から顔が消えてしまいます。そのため、座ったまま行う「座礼」で丁寧に行うのが適切です。
- お辞儀のタイミング:
- 面接開始時の挨拶: 「よろしくお願いいたします」と言った後。
- 面接終了時の挨拶: 「ありがとうございました」と言った後。
- お辞儀のポイント:
- 背筋を伸ばしたまま、首から頭を下げるように意識します。角度は30度程度で十分です。
- ゆっくりと頭を下げ、少し止めてから、ゆっくりと上げると、丁寧で落ち着いた印象になります。
- 焦ってカクンと頭だけを下げるのは、雑な印象を与えるので避けましょう。
お辞儀は、相手への敬意を示す日本の大切なビジネスマナーです。画面越しであっても、このマナーを自然に行うことで、あなたの丁寧さや誠実さを伝えることができます。忘れずに行いましょう。