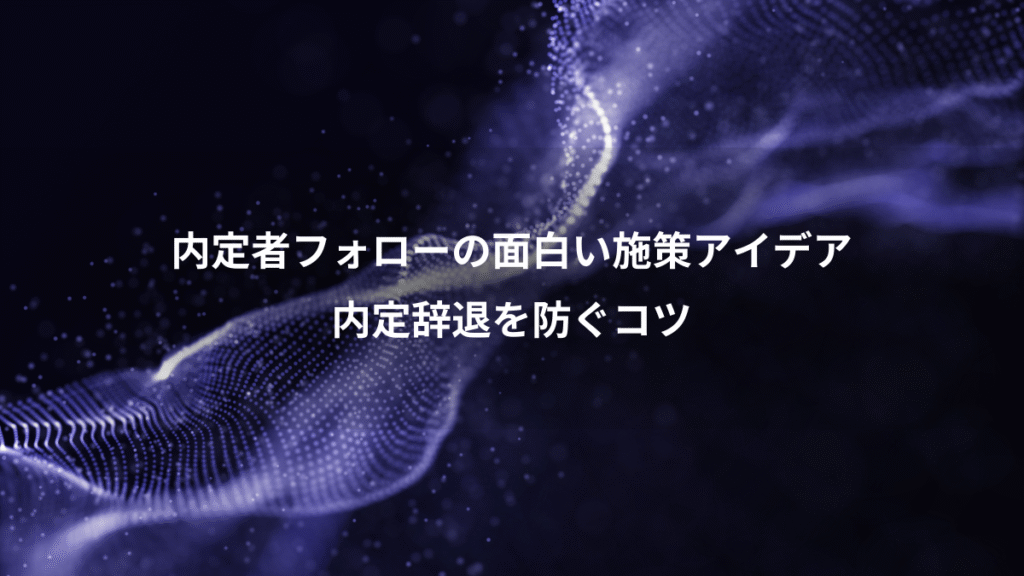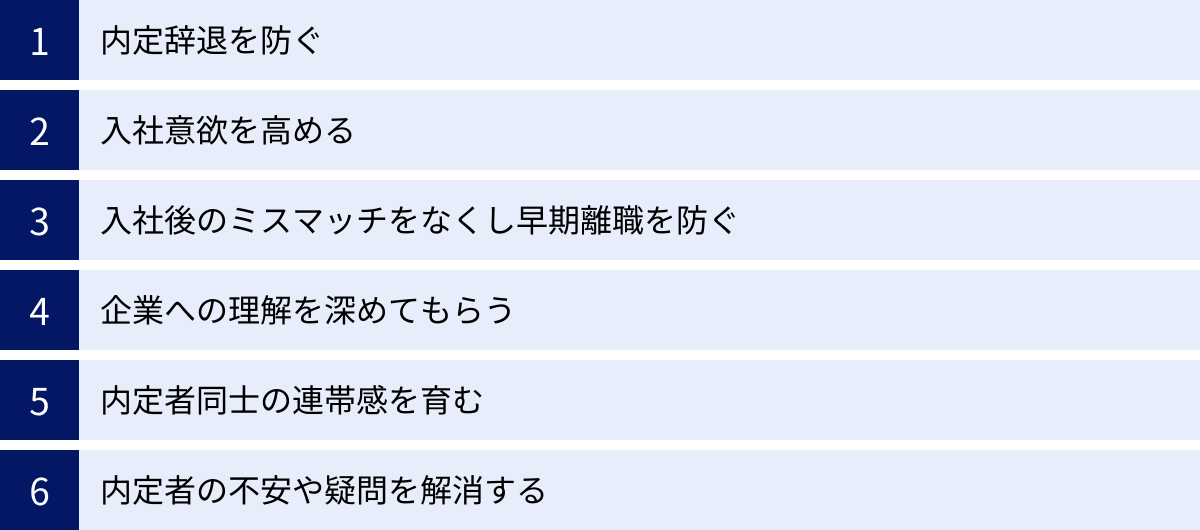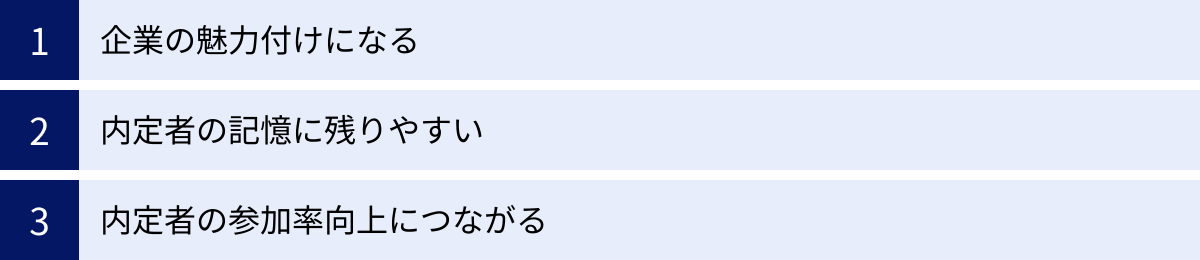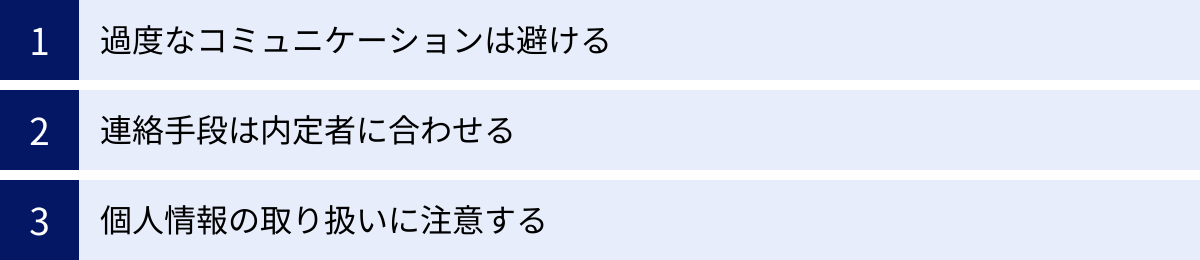採用活動が終わり、優秀な人材に内定を出せたとしても、それで安心はできません。内定者が入社を決意し、安心して社会人生活をスタートできるまでには、企業側の継続的なサポートが不可欠です。この重要なプロセスが「内定者フォロー」です。
特に近年の売り手市場や就労観の多様化を背景に、内定辞退は多くの企業にとって深刻な課題となっています。複数の内定を保持する学生が一般的になり、企業は内定を出した後も選ばれ続ける努力をしなければなりません。
そこで注目されているのが、画一的なフォローではなく、内定者の心をつかむ「面白い」施策です。本記事では、内定者フォローの基本から、内定辞退を防ぎ、入社意欲を最大限に高めるためのユニークで効果的な施策アイデアをオフライン・オンライン合わせて20選、ご紹介します。
内定者フォローの目的や成功のポイント、さらには便利なツールまで網羅的に解説しますので、これから内定者フォローを強化したいと考えている人事・採用担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
内定者フォローとは
内定者フォローとは、企業が内定を出した学生(内定者)に対して、内定承諾から入社までの期間にわたって行う、継続的なコミュニケーションやサポート活動全般を指します。この期間は、学生が社会人になるための準備期間であると同時に、複数の内定先の中から最終的な入社企業を決定する重要な時期でもあります。
かつての内定者フォローは、内定式の開催や事務連絡といった最低限の接触に留まるケースも少なくありませんでした。しかし、現代の採用市場においては、その役割と重要性が大きく変化しています。
主な活動内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 情報提供: 社内報の送付、会社の近況報告、入社手続きの案内など。
- コミュニケーション: 定期的な面談、懇親会、座談会、SNSでの交流など。
- 教育・研修: eラーNINGによるスキルアップ研修、ビジネスマナー研修、課題図書の提示など。
- 関係構築: 内定者同士や先輩社員との交流機会の創出、社内イベントへの招待など。
これらの活動を通じて、企業は内定者が抱える不安や疑問を解消し、入社へのモチベーションを高め、企業文化への理解を深めてもらうことを目指します。
なぜ今、これほどまでに内定者フォローが重要視されているのでしょうか。その背景には、いくつかの社会的な要因があります。
第一に、労働人口の減少に伴う採用競争の激化です。いわゆる「売り手市場」が続く中、学生は複数の企業から内定を得ることが一般的になりました。株式会社リクルートの就職みらい研究所が実施した「就職プロセス調査(2024年卒)」によると、2023年12月1日時点での内定辞退率は61.0%にものぼります。これは、内定を得た企業のうち辞退した企業の割合を示しており、多くの学生が複数の選択肢の中から入社先を吟味している実態を浮き彫りにしています。(参照:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職プロセス調査(2024年卒)」)
企業は、内定を出したというだけで安心できる状況ではなく、「選ばれ続ける」ための努力が求められているのです。
第二に、学生の価値観の多様化が挙げられます。終身雇用が当たり前ではなくなり、キャリア形成に対する考え方も変化しています。学生は給与や待遇といった条件面だけでなく、「自己成長できる環境か」「企業文化や社員の雰囲気が自分に合っているか」「社会に貢献できる仕事か」といった点をより重視するようになりました。内定者フォローは、こうした学生の価値観に寄り添い、自社の魅力を多角的に伝える絶好の機会となります。
第三に、コミュニケーション手段の変化です。SNSやチャットツールの普及により、企業と学生は以前よりも手軽に、そして頻繁にコミュニケーションをとれるようになりました。この変化は、オンラインでの交流会や個別面談など、内定者フォローの施策の幅を大きく広げました。一方で、他社も同様に手厚いフォローを行っているため、自社のフォローが手薄だと、内定者のエンゲージメントが低下し、辞退につながるリスクも高まっています。
内定者フォローは、もはや単なる内定辞退防止策ではありません。内定者が企業の一員となるための準備をサポートし、入社後のスムーズな立ち上がり(オンボーディング)を促し、最終的には早期離職を防いで長期的な活躍につなげるための、戦略的な人材育成の第一歩として位置づけられているのです。
内定者フォローの目的と重要性
内定者フォローは、単に内定辞退を防ぐためだけに行うものではありません。企業と内定者の双方にとって、多くの重要な目的を持っています。ここでは、内定者フォローがなぜ重要なのか、その具体的な目的を6つの側面から詳しく解説します。
内定辞退を防ぐ
内定者フォローの最も直接的で重要な目的は、内定辞退を防ぐことです。前述の通り、近年の売り手市場では、多くの学生が複数の内定を保持しています。内定承諾後から入社までの数ヶ月間、内定者は本当にこの会社で良いのか、もっと自分に合う会社があるのではないか、と悩み続けることも少なくありません。
この「内定ブルー」とも呼ばれる不安な時期に、企業からの接触が途絶えてしまうと、内定者は孤独感や不安感を募らせ、他社の魅力的な情報に心が揺らぎやすくなります。定期的な連絡や交流の機会を通じて、「企業が自分を気にかけてくれている」「歓迎されている」という実感を持ってもらうことが、内定辞退の抑止力として極めて重要です。
また、内定者フォローは、他社との比較検討において自社を優位に立たせるための重要な機会でもあります。給与や事業内容といった条件面で大きな差がない場合、「人事担当者や先輩社員の人柄が良かった」「会社の雰囲気が自分に合っていると感じた」といった情緒的な魅力が、最終的な入社の決め手になることは少なくありません。丁寧で心のこもったフォローは、こうした「人の魅力」「社風の魅力」を伝え、内定者の心を繋ぎ止める強力な武器となるのです。
入社意欲を高める
内定者フォローは、内定者の現状維持だけでなく、入社に対する意欲や期待感を積極的に高めていく目的も担っています。内定が出た直後は高いモチベーションを持っていたとしても、入社までの期間が長引くと、その気持ちが薄れてしまうことがあります。
企業は内定者フォローを通じて、自社のビジョンや事業の将来性、仕事のやりがいなどを具体的に伝えることで、内定者の「この会社で働きたい」という気持ちを再燃させ、さらに強固なものにできます。
例えば、以下のような施策が有効です。
- 経営層からのメッセージ: 企業のトップが自らの言葉で会社の未来や内定者への期待を語ることで、内定者は自分がその一員となることへの誇りと責任感を抱きます。
- プロジェクト紹介: 現在進行中の魅力的なプロジェクトや、社会に大きなインパクトを与えた過去の実績などを紹介することで、仕事の面白さやスケールの大きさを伝えられます。
- 社員の活躍: 若手社員が生き生きと働く様子や、キャリアを積んだベテラン社員のインタビューなどを共有することで、内定者は入社後の自分の姿を具体的にイメージし、キャリアへの期待を膨らませます。
このように、企業の魅力を継続的に発信し、内定者が入社後の自分をポジティブに想像できるような情報を提供し続けることが、入社意欲の向上に直結します。
入社後のミスマッチをなくし早期離職を防ぐ
採用活動における大きな課題の一つが、入社後のミスマッチによる早期離職です。多大なコストと時間をかけて採用した人材が、入社後すぐに辞めてしまうことは、企業にとって大きな損失です。内定者フォローは、このミスマッチを未然に防ぐための重要なプロセスです。
採用選考の短い時間だけでは、企業も学生もお互いのことを完全に理解するのは困難です。内定者フォローの期間は、お互いの理解を深めるための「お見合い期間」と捉えることができます。
企業側は、懇親会や社員との座談会などを通じて、自社のリアルな姿を伝える必要があります。仕事の良い面だけでなく、大変な面や乗り越えるべき課題についても正直に話すことで、内定者は現実的な期待を持って入社できます。
一方、内定者側も、フォロー期間中に社員と交流する中で、企業の文化や価値観、働き方が本当に自分に合っているかをじっくりと見極めることができます。もし、この段階で「何か違う」と感じたとしても、それは双方にとって不幸なミスマッチを防ぐ機会となります。
入社前に相互理解を深め、期待値のズレをなくしておくことが、スムーズなオンボーディングと入社後の定着・活躍に繋がり、結果として早期離職率の低下に貢献するのです。
企業への理解を深めてもらう
内定者は、就職活動を通じて企業の基本的な情報を得ていますが、その理解はまだ表層的なものであることが多いです。内定者フォローは、事業内容、組織構造、企業文化、独自の価値観といった、企業の全体像をより深く理解してもらうための絶好の機会です。
例えば、以下のような取り組みが考えられます。
- 部署紹介: 各部署の役割や業務内容、そこで働く社員の声などを紹介する。これにより、内定者は配属先の希望を具体的に考えたり、会社全体の仕組みを理解したりできます。
- 社内用語集: 業界特有の専門用語や社内で使われる略語などをまとめた資料を提供する。入社後のスムーズなコミュニケーションを助けます。
- 企業文化の共有: 会社の成り立ちや大切にしている理念、行動指針などをストーリーとして伝える。これにより、内定者は企業のDNAを理解し、共感を深めることができます。
こうした情報提供を通じて、内定者は「自分はこの会社で何をするのか」「どのように貢献できるのか」を具体的にイメージできるようになります。企業への理解が深まることは、帰属意識の醸成にも繋がり、単なる「内定先」から「自分の会社」へと意識が変化していくきっかけとなるのです。
内定者同士の連帯感を育む
社会人になるにあたり、多くの内定者は「同期とうまくやっていけるだろうか」「会社に馴染めるだろうか」といった人間関係に関する不安を抱えています。内定者同士の横のつながりを早期に構築することは、こうした不安を和らげる上で非常に効果的です。
内定者懇親会やグループワーク、研修などを通じて、内定者同士が顔を合わせ、コミュニケーションをとる機会を設けることで、自然と連帯感が生まれます。入社前に仲間がいるという安心感は、内定辞退の防止にも繋がります。
また、内定者同士のネットワークは、入社後にも大きな意味を持ちます。
- 相談相手: 仕事で壁にぶつかった時や悩みを抱えた時に、気軽に相談できる同期の存在は大きな支えとなります。
- 切磋琢磨: 同じスタートラインに立つ仲間として、互いに刺激し合い、高め合う存在になります。
- 部署間の連携: 将来、それぞれが異なる部署に配属された際に、同期のネットワークが部署間のスムーズな連携を助けることもあります。
企業は、内定者同士が交流しやすい場やきっかけを積極的に提供することが重要です。「同期」というかけがえのない関係性の土台作りを支援することも、内定者フォローの重要な役割の一つなのです。
内定者の不安や疑問を解消する
内定者は、社会人としての一歩を踏み出すにあたり、様々な不安や疑問を抱えています。
- 業務内容に関する不安:「自分にこの仕事が務まるだろうか」「どんなスキルが必要なのだろうか」
- 人間関係に関する不安:「上司や先輩はどんな人たちだろうか」「職場の雰囲気に馴染めるだろうか」
- 生活に関する不安:「勤務地はどこになるのか」「研修はどんな内容なのか」「福利厚生について詳しく知りたい」
こうした不安や疑問を放置しておくと、どんどん膨らんでしまい、最終的に内定辞退という決断に繋がることもあります。内定者フォローの基本は、内定者一人ひとりの声に耳を傾け、これらの不安や疑問を丁寧に解消していくことにあります。
個別面談や質問会、匿名で質問できるオンラインツールなどを活用し、内定者が本音で話せる環境を整えることが大切です。特に、年齢の近い若手社員がメンターとしてサポートする体制を整えると、内定者もより気軽に相談しやすくなります。
些細なことでも真摯に対応し、不安を一つひとつ取り除いていく地道なコミュニケーションが、内定者との信頼関係を築き、安心して入社の日を迎えてもらうための基盤となるのです。
近年の内定者フォローの傾向
社会情勢の変化やテクノロジーの進化に伴い、内定者フォローのあり方も年々変化しています。ここでは、近年の内定者フォローに見られる3つの主要な傾向について解説します。これらのトレンドを理解することは、自社のフォロー施策を現代の学生に合わせて最適化する上で不可欠です。
オンライン施策の増加
近年の最も顕著な傾向は、オンラインを活用した内定者フォロー施策の急速な増加と定着です。この背景には、新型コロナウイルス感染症の拡大によるリモートワークの普及や、デジタルネイティブ世代である学生がオンラインでのコミュニケーションに慣れ親しんでいることが挙げられます。
オンライン施策には、企業と内定者の双方にとって多くのメリットがあります。
| メリット | |
|---|---|
| 企業側のメリット | ・遠隔地に住む内定者にも等しくアプローチできる ・会場費や交通費などのコストを削減できる ・イベントの録画や資料の共有が容易で、参加できなかった内定者もフォローできる ・短時間で手軽に開催できるため、コミュニケーションの頻度を上げやすい |
| 内定者側のメリット | ・移動時間や交通費の負担なく参加できる ・学業やアルバイトとの両立がしやすい ・リラックスした環境(自宅など)から参加できる ・チャット機能などを使い、対面ではしにくい質問もしやすい |
具体的なオンライン施策としては、オンライン内定式、オンライン懇親会、Web会議システムを利用した先輩社員との座談会や個別面談、eラーニングによる研修などが広く実施されています。
ただし、オンライン施策が万能というわけではありません。画面越しのコミュニケーションでは、相手の細かな表情や場の空気を読み取りにくく、偶発的な雑談も生まれにくいため、深い関係構築には限界があるという側面もあります。そのため、最近ではオンラインの効率性とオフライン(対面)の持つ熱量や一体感を組み合わせた「ハイブリッド型」のフォローが主流になりつつあります。例えば、大規模な説明会はオンラインで実施し、少人数での懇親会やチームビルディングはオフラインで実施するなど、目的応じて最適な形式を選択することが重要です。
内定者とのコミュニケーション機会の増加
かつての内定者フォローは、内定式、懇親会、入社前研修など、数回程度のイベントが中心でした。しかし、現在では内定承諾から入社までの期間を通じて、継続的かつ多様なコミュニケーション機会を設ける企業が増えています。
この背景には、前述の通り、内定辞退率の高止まりと、学生が内定後も企業選択を続けるという実態があります。接触頻度が低いと、内定者は「自分は本当に入社を歓迎されているのだろうか」と不安になり、より頻繁にアプローチしてくる他社に魅力を感じてしまう可能性があります。
この傾向に対応するため、多くの企業が以下のような取り組みを行っています。
- 定期的な個別面談: 人事担当者や配属予定先の上司、メンターとなる若手社員などが、1〜2ヶ月に1回程度の頻度で内定者と1on1の面談を実施します。進捗状況の確認だけでなく、内定者の悩みや不安をヒアリングし、個別に対応します。
- SNSやチャットツールの活用: 内定者専用のSlackチャンネルやLINEグループを作成し、日常的なコミュニケーションの場として活用します。社員が会社の日常を投稿したり、内定者からの些細な質問に迅速に答えたりすることで、心理的な距離を縮めます。
- 細分化されたイベント: 一度の長大なイベントではなく、「若手社員との座談会」「女性社員とのランチ会」「技術職向け勉強会」など、テーマや対象者を絞った小規模なイベントを複数回開催します。これにより、内定者は自分の興味や関心に合わせて参加でき、より深い情報を得られます。
重要なのは、コミュニケーションの「量」だけでなく「質」も高めることです。一方的な情報発信に終始するのではなく、内定者一人ひとりの状況や性格を理解し、双方向の対話を心がけることが、エンゲージメントの向上に繋がります。
内定者への手厚いフォローの一般化
採用競争の激化は、内定者フォローの内容そのものにも変化をもたらしています。他社との差別化を図り、優秀な人材を惹きつけるため、より手厚く、個別最適化されたフォローを提供する企業が一般化しています。
単なる交流会や研修だけでなく、内定者のスキルアップやキャリア形成を具体的に支援するようなプログラムが人気を集めています。
- 入社前スキルアップ支援:
- eラーニング: プログラミング、語学、マーケティング、簿記など、職種に応じた専門スキルを入社前に学べる機会を提供します。学習の進捗に応じて社員がフィードバックを行うなど、手厚いサポート体制を整える企業もあります。
- 資格取得支援: 業務に関連する資格の取得を奨励し、受験費用や教材費を補助します。内定者の学習意欲を高め、入社後の即戦力化を促します。
- キャリア形成支援:
- メンター制度: 年齢の近い若手社員がメンターとなり、内定者の相談役となります。仕事内容だけでなく、社会人生活全般に関する不安や悩みに寄り添い、精神的な支えとなります。
- キャリア面談: 人事担当者やキャリアコンサルタントが、内定者一人ひとりの将来のキャリアプランについて面談を行います。入社後のキャリアパスを具体的に示すことで、働くことへのモチベーションを高めます。
- ユニークな体験の提供:
- 内定者アルバイト: 入社前に実際の業務を体験してもらうことで、仕事への理解を深め、ミスマッチを防ぎます。
- オリジナルグッズの送付: 会社のロゴが入った文房具やパーカー、ウェルカムキットなどを送付し、帰属意識を高めます。
これらの手厚いフォローは、内定者に「この会社は社員の成長を本気で支援してくれる」というメッセージを伝え、エンゲージメントを大幅に向上させます。他社がどのようなフォローを行っているかを把握し、自社の魅力やリソースを活かした独自のプログラムを企画することが、熾烈な人材獲得競争を勝ち抜く上で不可欠となっています。
面白い内定者フォロー施策を実施すべき理由
内定者フォローの重要性は理解できても、「なぜ『面白い』施策が必要なのか?」と疑問に思うかもしれません。事務的な連絡や一般的な懇親会だけでは不十分なのでしょうか。結論から言えば、現代の採用市場においては、内定者の心を掴む「面白さ」や「ユニークさ」が、他社との大きな差別化要因となります。ここでは、面白い内定者フォロー施策を実施すべき3つの理由を解説します。
企業の魅力付けになる
面白い施策は、企業のカルチャーや価値観を効果的に伝える強力なブランディングツールになります。例えば、画一的な研修ではなく、社会課題の解決を目指すワークショップを実施すれば、「社会貢献への意識が高い企業」というメッセージを伝えられます。また、社員が企画したeスポーツ大会を開催すれば、「遊び心やチームワークを大切にするフラットな社風」を体感してもらえます。
言葉で「私たちの会社は風通しが良いです」と説明するよりも、実際に若手社員と役員が一緒になってバーベキューを楽しんでいる場に参加してもらう方が、その社風は遥かにリアルに伝わります。施策の内容そのものが、企業のアイデンティティを表現するのです。
特に、学生が企業を選ぶ上で「社風」や「働く人」を重視する傾向が強まっている現在、ユニークな施策を通じて企業の「らしさ」を伝えることは、内定者の入社意欲を固める上で非常に効果的です。ありきたりなフォローでは伝わらない、自社ならではの魅力を体験してもらうことで、「この会社で働いたら楽しそうだ」「この人たちと一緒に仕事がしたい」という強い動機付けに繋がります。これは、給与や福利厚生といった条件面だけでは測れない、エンゲージメントの源泉となるのです。
内定者の記憶に残りやすい
内定者は多くの場合、複数の企業と並行してコミュニケーションをとっています。各社からメールが届き、様々なイベントに招待される中で、ありきたりな内容のフォローはすぐに忘れ去られてしまう可能性があります。
一方で、「面白かった」「こんな体験は初めてだった」と感じるようなユニークな施策は、内定者の記憶に強く刻まれます。例えば、「内定証書をパズルのピースとして送り、全員で集めて完成させる内定式」や「自社製品を使って謎解きゲームをクリアするオフィスツアー」などは、参加者に強いインパクトと感動を与えます。
このような記憶に残る体験は、「ピーク・エンドの法則」という心理学の法則によってもその効果が説明できます。これは、人はある出来事の記憶を、感情が最も高まった瞬間(ピーク)と、最後の瞬間(エンド)の印象で判断するというものです。面白い施策は、内定者フォロー期間における強力な「ピーク」となり、「あの会社は面白かった」というポジティブな印象を強く植え付けます。
このポジティブな記憶は、内定者が友人や家族に「こんな面白い会社から内定をもらったんだ」と自慢したくなるような、ポジティブな口コミ(バイラル効果)を生み出す可能性も秘めています。感情を揺さぶる体験を提供することが、数ある選択肢の中から自社を選んでもらうための重要な鍵となるのです。
内定者の参加率向上につながる
内定者フォローのイベントを企画しても、内定者が参加してくれなければ意味がありません。特に、内定者は学業の集大成である卒業論文や研究、アルバイトなどで忙しい時期を過ごしています。「参加は任意です」とされるイベントに対して、「面倒だ」「行く時間がない」と感じてしまうことも少なくありません。
ここで「面白さ」が大きな力を発揮します。「何だかよくわからないけど、面白そうだから行ってみよう」という好奇心や期待感は、内定者の参加を促す強力な動機となります。例えば、「内定者研修」と案内するよりも、「最新VR技術を使った未来のサービス開発ワークショップ」と案内する方が、内定者の興味を惹きつけ、参加へのハードルを下げることができます。
また、ゲーム性やエンターテイメント性の高い施策は、内定者同士のコミュニケーションを活性化させる効果もあります。初対面同士でいきなり「自己紹介をしてください」と言われても会話は弾みにくいですが、チームで協力して謎解きに挑戦するようなアクティビティがあれば、自然と会話が生まれ、一体感が醸成されます。
「義務感」ではなく「自発的な参加意欲」を引き出すことが、内定者フォローの質を高める上で非常に重要です。参加率が高まれば、それだけ多くの内定者と接点を持ち、企業の魅力を伝え、不安を解消する機会が増えることになります。結果として、施策全体の効果が最大化されるのです。
【オフライン】内定者フォローの面白い施策アイデア10選
ここでは、実際に顔を合わせるからこそ生まれる一体感や熱量を活かした、オフラインでの面白い内定者フォロー施策のアイデアを10個紹介します。定番の施策に一工夫加えることで、内定者の記憶に残る特別な体験を創出しましょう。
内定式
内定式は多くの企業が実施する定番イベントですが、形式的な社長挨拶と内定証書授与だけで終わらせてはもったいないです。面白さを加える工夫として、内定者を「お客様」ではなく「仲間」として歓迎する演出を取り入れてみましょう。
- サプライズ演出: 内定者一人ひとりのために、採用担当者や配属予定先の先輩が手書きのメッセージカードを用意しておく。あるいは、内定者の家族から預かったサプライズの手紙やビデオメッセージを上映するのも感動的です。
- 参加型コンテンツ: 内定証書をパズルのピースにし、全員で一つの絵を完成させる。あるいは、会社の未来について内定者と役員が対等な立場でディスカッションする場を設けるなど、内定者が受け身にならず主体的に参加できるコンテンツを企画します。
- ユニークな内定証書: 通常の紙の証書だけでなく、自社製品やサービスにちなんだユニークなアイテム(例えば、IT企業なら自分の名前が刻印されたキーボード、食品メーカーならオリジナルパッケージのお菓子など)を贈呈するのも記憶に残ります。
目的は、内定者に「この会社の一員になったんだ」という実感と誇りを持ってもらうことです。厳粛な雰囲気と、温かい歓迎ムードを両立させる工夫が求められます。
内定者懇親会・社員との交流会
懇親会も定番ですが、単なる食事会では会話が弾まないこともあります。共通の話題や目的を作ることで、自然なコミュニケーションを促進する工夫が重要です。
- テーマ設定: 「出身地のおすすめグルメ紹介」「学生時代に熱中したこと」など、毎回テーマを設定することで、会話のきっかけが生まれます。内定者のプロフィールを事前共有し、共通点のある社員をマッチングするのも良いでしょう。
- 体験型コンテンツ: 料理教室形式で一緒に料理を作ったり、自社製品を使ったワークショップを開催したりするなど、共通の作業を通じて自然な会話と連帯感が生まれる企画を取り入れます。
- 社内BARイベント: 就業後のオフィスの一部をBARスペースとして開放し、お酒や軽食を片手に、役員から若手まで様々な社員とフランクに話せる機会を設けます。普段は話せないような本音のトークが聞けるかもしれません。
重要なのは、内定者がリラックスして、多くの社員と話せる環境を整えることです。立食形式にする、定期的に席替えを促すなどの工夫も有効です。
先輩社員との座談会
内定者が最も知りたいのは、現場で働く先輩社員のリアルな声です。座談会をより有意義なものにするためには、内定者のニーズに合わせたテーマ設定と、本音を引き出す雰囲気作りが鍵となります。
- テーマ別座談会: 「1年目社員の失敗談と乗り越え方」「ワークライフバランスのリアル」「女性社員のキャリアパス」など、内定者の関心が高いテーマに絞って開催します。希望者制にすることで、より深い質疑応答が可能になります。
- 「NGなし」質問会: 参加する先輩社員に事前に協力を仰ぎ、「給料は?」「残業は?」「辞めたいと思ったことは?」といった、聞きにくい質問にも正直に答えてもらう会を設定します。企業の誠実な姿勢が伝わり、内定者の信頼を得られます。
- シャッフル座談会: 少人数のグループに分かれ、先輩社員が各グループを巡回する形式です。これにより、内定者は多くの先輩社員と密に話す機会を得られます。
内定者の「こんなはずじゃなかった」を防ぎ、入社後のリアルな姿をイメージしてもらうことが最大の目的です。人事担当者はファシリテーションに徹し、社員と内定者が本音で語り合える場を作りましょう。
内定者研修
入社前研修は、社会人としての基礎を学ぶ貴重な機会ですが、退屈な座学ばかりではモチベーションが低下します。ゲーム性や実践的な要素を取り入れ、楽しみながら学べるコンテンツを企画しましょう。
- ビジネスゲーム研修: チームで会社経営をシミュレーションするゲームや、コンセンサス(合意形成)を学ぶゲームなどを通じて、楽しみながら論理的思考力やチームワークを養います。
- 課題解決型研修: 実際に企業が抱える課題(例:「若者向けの新商品を企画せよ」)をテーマに、グループで解決策を企画し、最終的に役員にプレゼンテーションします。仕事の難しさと面白さをリアルに体感できます。
- 社外研修: 工場見学や顧客訪問など、普段は入れない場所を訪れることで、自社の事業への理解を深め、仕事の社会的意義を実感してもらいます。
研修の目的は、単に知識を詰め込むことではなく、仕事の面白さや、同期と協力して何かを成し遂げる達成感を味わってもらうことです。
グループワーク
グループワークは、内定者同士の相互理解を深め、チームで働くことの基礎を学ぶのに最適です。テーマ設定に工夫を凝らし、内定者の創造性や主体性を引き出しましょう。
- 自社のアセットを使った新規事業立案: 自社の技術やブランド、顧客基盤などを活用した新しいビジネスアイデアを企画・提案してもらいます。内定者の柔軟な発想が、実際の事業のヒントになることもあります。
- SDGs貢献ワークショップ: 自社の事業と関連付けながら、SDGs(持続可能な開発目標)に貢献できるアクションプランを考えてもらいます。企業の社会貢献への姿勢を示すとともに、内定者の当事者意識を高めます。
- 会社紹介動画の制作: 内定者の視点で、会社の魅力を伝えるPR動画を制作してもらいます。制作過程で社員にインタビューしたり、社内を撮影したりする中で、自然と企業理解が深まります。
完成度の高さよりも、チームで議論し、協力し合うプロセスそのものを重視することが大切です。社員はアドバイザー役に徹し、内定者の主体性を尊重しましょう。
オフィスツアー
オフィスツアーは、働く環境を具体的にイメージしてもらうための重要な機会です。ただオフィスを案内するだけでなく、インタラクティブな要素を加えて、体験価値を高めましょう。
- 謎解きオフィスツアー: オフィスの各所に謎を仕掛け、チームで協力して解きながらゴールを目指すゲーム形式のツアーです。楽しみながら自然に社内を巡ることができ、部署の役割なども学べます。
- 「私の仕事場」紹介ツアー: 各部署の社員がリレー形式で、自分のデスク周りや仕事内容、やりがいなどを紹介します。働く人の顔が見えることで、オフィスがより魅力的な空間に感じられます。
- フリーアドレス体験: フリーアドレス制を導入している企業であれば、内定者に実際に好きな席で短時間の作業を体験してもらうのも良いでしょう。働き方の自由度や雰囲気を肌で感じられます。
物理的な環境だけでなく、そこで働く人々の雰囲気や文化を感じてもらうことが、オフィスツアーを成功させるポイントです。
社内イベントへの招待
会社のカルチャーを最も直接的に感じられるのが、社員向けのイベントです。内定者を「ゲスト」として招待し、ありのままの会社の雰囲気を体験してもらいましょう。
- 運動会や社員旅行: 全社的なイベントは、部署や役職を超えた社員の交流が見られる絶好の機会です。内定者も一つのチームのメンバーとして参加することで、一体感を味わえます。
- ファミリーデー: 社員の家族を会社に招待するイベントです。社員を大切にする会社の姿勢が伝わり、内定者も安心して入社できます。
- 部活動やサークル活動への体験入部: 共通の趣味を持つ社員と交流することで、仕事以外のつながりも生まれ、入社後の楽しみが広がります。
ただし、参加は任意とし、内定者にプレッシャーを与えない配慮が必要です。あくまで「もし興味があれば」というスタンスで、企業のオープンな姿勢を見せることが重要です。
謎解き・脱出ゲームなどのチームビルディング
近年、チームビルディングの手法として人気が高いのが、謎解きや脱出ゲームです。共通の目標に向かってチームで協力する体験は、内定者同士の絆を急速に深めます。
- オリジナル謎解きゲーム: 自社の歴史や製品、企業理念などをテーマにしたオリジナルの謎解きゲームを制作します。楽しみながら自然と企業知識が身につきます。
- プロのイベント会社への委託: チームビルディングを専門とする企業に依頼すれば、質の高いプログラムを実施できます。オフラインだけでなく、オンラインやハイブリッドでの開催も可能です。
ゲーム中は、役割分担、情報共有、時間管理など、仕事に通じる様々な要素が求められます。遊びの中に学びの要素を組み込むことで、楽しみながら社会人としての基礎スキルを体験できます。
スポーツ大会やバーベキュー
体を動かすアクティビティや、屋外での開放的なイベントは、リラックスした雰囲気を作り出し、自然なコミュニケーションを促します。
- 種目の工夫: フットサルやバレーボールなど定番のスポーツも良いですが、運動が苦手な人も楽しめるよう、ボウリングやモルック、eスポーツなどを取り入れるのもおすすめです。
- 役割分担: バーベキューでは、買い出し係、火起こし係、調理係など、自然と役割分担が生まれます。共同作業を通じて、チームワークが育まれます。
重要なのは、全員が楽しめるような企画と配慮です。安全管理を徹底することはもちろん、スポーツが苦手な内定者が孤立しないよう、応援やサポート役といった役割を用意するなどの工夫をしましょう。
社員とのランチ会
大人数の懇親会とは異なり、少人数でのランチ会は、一人ひとりとじっくり向き合い、深い対話をするのに最適です。
- 社員の組み合わせ: 内定者の興味やキャリアプランに合わせて、話を聞いてみたい職種や経歴の社員をマッチングします。出身大学や出身地が同じ先輩社員とのランチも、親近感が湧きやすく効果的です。
- 場所の選定: オフィスの会議室ではなく、会社周辺のおしゃれなカフェやレストランなど、少し特別な空間を選ぶと、内定者の満足度も高まります。
- 頻度と継続性: 一度だけでなく、入社までに複数の社員とランチに行く機会を設けることで、内定者は多角的に会社の雰囲気を知ることができます。
1対1、あるいは少人数だからこそ聞ける本音や、個人的な悩み相談にも乗りやすいのがランチ会の大きなメリットです。丁寧な個別フォローが、内定者の心を繋ぎ止めます。
【オンライン】内定者フォローの面白い施策アイデア10選
時間や場所の制約を受けないオンライン施策は、内定者フォローの強力な武器です。ここでは、オンラインならではの特性を活かした、ユニークでエンゲージメントを高める施策アイデアを10個紹介します。
オンライン内定式
オンライン内定式は、単なるオフラインの代替ではありません。デジタルの特性を活かした双方向性のある演出で、記憶に残るイベントにしましょう。
- バーチャル空間の活用: メタバース(仮想空間)プラットフォーム上にオリジナルの式典会場を作り、内定者はアバターで参加します。リアルな内定式とは一味違った、未来感のある体験を提供できます。
- インタラクティブ機能の活用: チャットやアンケート、リアクションボタンなどを活用し、内定者がリアルタイムで参加できる企画を取り入れます。「社長への質問コーナー」や「同期の意外な一面を発見!クイズ」などで盛り上げましょう。
- オンラインとオフラインの融合: 事前に内定者の自宅へ「内定式キット」(内定証書、記念品、乾杯用のドリンクなど)を送付しておき、当日は全員で同じものを手にセレモニーを行うことで、一体感を醸成します。
オンラインだからこそできるクリエイティブな演出で、企業文化の先進性や柔軟性をアピールする機会にもなります。
オンライン懇親会
オンライン懇親会は、ただ雑談するだけでは間が持たず、一部の人しか話さない状況に陥りがちです。全員が参加できる「仕掛け」を用意することが成功の鍵です。
- フードデリバリーの活用: 全員の自宅に同じ食事や飲み物のセットを事前に配送します。同じものを飲食することで、離れていても一体感が生まれます。
- テーマ別ブレイクアウトルーム: 全体を少人数のグループ(ブレイクアウトルーム)に分け、「おすすめの映画」「学生時代のアルバイト」など、テーマを決めてディスカッションします。全員に発言機会が生まれ、相互理解が深まります。
- オンライン自己紹介ツール: 「趣味」「特技」「自分を動物に例えると?」といった項目を事前にオンラインホワイトボードなどに書き込んでもらい、それを見ながら自己紹介をすると、会話が弾みやすくなります。
ファシリテーターの役割が非常に重要です。時間を管理し、会話が途切れたグループに声をかけるなど、細やかな配慮が求められます。
オンライン面談
定期的なオンラインでの個別面談は、内定者一人ひとりの状況を把握し、不安をきめ細かくケアする上で最も効果的な手法の一つです。
- 担当者を分ける: 人事担当者との面談(事務連絡や制度に関する質問)、先輩社員との面談(業務内容や働き方のリアル)、上司となるマネージャーとの面談(キャリアパスの相談)など、目的別に面談相手を変えることで、多角的なフォローが可能になります。
- 「雑談」を大切にする: 本題に入る前に、学業の進捗や最近のプライベートな話題など、アイスブレイクの時間をしっかり設けます。リラックスした雰囲気を作ることが、本音を引き出すコツです。
- 記録と共有: 面談で話した内容(特に内定者の不安や希望)は、個人情報に配慮しつつ記録し、関係者間で共有します。これにより、次回のフォローや入社後の配属・育成に活かすことができます。
「いつでも相談できる場所がある」という安心感を提供することが、内定者のエンゲージメント維持に繋がります。
オンライン座談会
オンライン座談会は、場所の制約がないため、オフラインでは参加が難しい地方在住の内定者や、様々な部署の社員が参加しやすいというメリットがあります。
- 多様な社員の参加: 本社だけでなく、支社や海外拠点で働く社員にも参加してもらうことで、多様なキャリアパスや働き方を紹介できます。
- 匿名質問ツールの活用: Slidoなどのツールを使えば、参加者は匿名で質問を投稿できます。「こんなこと聞いてもいいのかな?」とためらってしまうような本音の質問が出やすくなります。
- テーマの事前公募: 内定者から事前に「話を聞きたいテーマ」を募集し、人気の高かったテーマで座談会を企画します。内定者のニーズに直接応えることで、満足度が高まります。
オフラインの座談会以上に、双方向性を意識した運営が求められます。チャットで寄せられた質問を積極的に拾うなど、参加者を置き去りにしない工夫が必要です。
オンラインゲーム大会
ゲームは、楽しみながら自然にコミュニケーションを促進する強力なツールです。内定者同士や社員との間の壁を壊し、チームの一体感を醸成するのに役立ちます。
- 誰でも楽しめるゲームの選定: 特定のスキルがなくても楽しめるパーティーゲームや、協力プレイが中心のゲーム(例:Among Us、Gartic Phoneなど)を選ぶのがポイントです。
- チーム対抗戦: 内定者と社員を混ぜた混合チームで対抗戦を行うと、自然と会話が生まれ、部署や役職を超えた交流が促進されます。
- eスポーツ大会: ゲーム好きの内定者が多い場合は、本格的なeスポーツタイトルで大会を開催するのも盛り上がります。実況や解説役を社員が務めるなど、イベントとしての演出にもこだわりましょう。
仕事とは全く違う側面から、お互いの人柄を知る良い機会になります。企業の遊び心をアピールすることもできます。
SNSの活用
多くの学生にとって最も身近なコミュニケーションツールであるSNSは、内定者フォローにおいても非常に有効です。クローズドな環境で、継続的かつ気軽に情報発信ができます。
- 内定者限定アカウント/グループの作成: Instagramの鍵付きアカウントや、Facebookグループ、Slackの専用チャンネルなどを活用します。
- 発信するコンテンツの工夫:
- 社員紹介: 若手社員の1日のスケジュール(Vlog風)、ベテラン社員のキャリアインタビューなど。
- 社内風景: オフィスの様子、ランチ風景、部活動の様子など、日常を切り取った投稿。
- Q&Aコーナー: 内定者から寄せられた質問に、動画や投稿で回答する。
- 内定者同士の自己紹介: 指定したハッシュタグで自己紹介を投稿し合う企画。
更新頻度を保ち、コメントや質問には迅速に返信するなど、丁寧な運用を心がけることで、内定者の帰属意識を高めることができます。
先輩社員インタビュー動画の配信
動画コンテンツは、文章や写真だけでは伝わりにくい社員の人柄や職場の雰囲気をリアルに伝えるのに適しています。
- 多様な社員へのインタビュー: 様々な職種、年代、経歴を持つ社員にインタビューすることで、多様なロールモデルを示します。仕事のやりがいだけでなく、苦労した経験やプライベートとの両立についても語ってもらうと、より深みが出ます。
- 「NGなし」を謳う: 事前に内定者から質問を募集し、それに先輩社員がNGなしで答える形式の動画は、信頼性が高く、満足度も高いコンテンツになります。
- Vlog(ビデオブログ)形式: ある社員の一日に密着するVlog形式の動画は、働く姿をより具体的にイメージさせることができます。
プロが作ったような綺麗な動画である必要はありません。スマートフォンで撮影した手作り感のある動画の方が、かえって親近感が湧き、リアルな雰囲気が伝わることがあります。
eラーニングによる研修
オンラインで完結するeラーニングは、内定者が自分のペースで学習を進められるため、学業などとの両立がしやすい研修手法です。
- ゲーミフィケーションの導入: 学習の進捗に応じてポイントが付与されたり、ランキングが表示されたり、バッジが獲得できたりするなど、ゲームの要素を取り入れることで、内定者の学習意欲を持続させます。
- マイクロラーニング: 1コンテンツあたり5〜10分程度の短い動画やテキストで構成することで、隙間時間にも学習しやすくします。
- 双方向性の確保: 学習内容に関する課題を提出させ、それに対して社員がフィードバックを行う仕組みを取り入れると、一方的な学習にならず、エンゲージメントが高まります。
ビジネスマナーや業界知識、専門スキルなど、入社後に役立つ実践的なコンテンツを提供することで、「この会社は自分の成長を支援してくれる」という印象を与えることができます。
社内報やメルマガの配信
定期的な情報提供は、内定者との関係性を維持する上で基本となります。内定者向けにカスタマイズしたコンテンツを配信することで、特別感を演出し、関心を引きつけましょう。
- 内定者向け特別コンテンツ: 「内定者紹介リレー」や「同期になる仲間へのおすすめ本紹介」など、内定者が登場する企画を用意します。
- 会社の最新ニュース: 新製品のリリース、メディア掲載、社内イベントの報告など、会社の「今」を伝える情報をタイムリーに発信します。
- 社員のコラム: 社員が持ち回りで、仕事のTIPSや休日の過ごし方など、パーソナルなテーマでコラムを執筆します。会社のカルチャーや社員の人柄が伝わります。
一方的な情報発信だけでなく、メルマガの最後にアンケートや質問フォームを設置し、内定者の声を聞く姿勢を見せることも重要です。
オリジナルグッズの送付
物理的な「モノ」を贈ることは、オンラインでのコミュニケーションが中心となる中で、企業の存在をリアルに感じてもらうための効果的なサプライズになります。
- ウェルカムキット: 会社のロゴが入ったパーカー、マグカップ、ノート、ステッカーなどをセットにして送付します。「#会社名 #内定者」などのハッシュタグでSNSへの投稿を促すのも良いでしょう。
- 課題図書: 会社の理念や事業に関連する書籍を、社長や役員からのメッセージカードを添えて贈ります。内定者の知的好奇心を刺激し、企業理解を深めてもらうきっかけになります。
- 季節の贈り物: 年末にはカレンダー、夏には暑中見舞いとして自社製品を送るなど、季節に合わせた細やかな心遣いは、内定者のロイヤリティを高めます。
単にモノを送るだけでなく、そこに手書きのメッセージを添えるなど、温かみが感じられる工夫をすることが、内定者の心を動かします。
内定者フォローを成功させるためのポイント
ユニークな施策を企画することも重要ですが、それらが真に効果を発揮するためには、根底にあるべき基本的な考え方や心構えがあります。ここでは、内定者フォローを成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。
内定者一人ひとりに合わせたフォローをする
最も重要なことは、内定者を「集団」としてではなく、「個人」として捉え、一人ひとりに合わせた個別最適化されたフォローを心がけることです。内定者と一括りに言っても、性格、価値観、抱えている不安、求める情報は様々です。
例えば、以下のような違いが考えられます。
- コミュニケーションの好み: 積極的に社員と交流したいタイプもいれば、静かに情報収集したいタイプもいます。
- 不安の種類: スキル面での不安が強い人もいれば、人間関係に不安を感じている人もいます。
- 情報ニーズ: キャリアパスを重視する人もいれば、ワークライフバランスを重視する人もいます。
こうした個々の違いを無視して、全員に同じフォローを画一的に提供しても、心には響きません。成功のためには、まず内定者一人ひとりを深く理解することがスタート地点となります。
具体的なアクション:
- 個別面談の徹底: 定期的な1on1面談を通じて、それぞれの内定者が今何を感じ、何を求めているのかを丁寧にヒアリングします。
- アンケートの活用: 内定者フォローで知りたい情報や参加したいイベントの種類について、定期的にアンケートを実施し、ニーズを把握します。
- フォロー内容のパーソナライズ: ヒアリングやアンケートの結果に基づき、「この内定者には、同じ大学出身のこの先輩社員を会わせてみよう」「この内定者は技術志向が強いから、専門的な勉強会に招待しよう」というように、提供する情報や機会を個別に調整します。
一人ひとりに「あなたを大切に思っている」というメッセージが伝わるような丁寧な対応が、最終的に強いエンゲージメントを築き上げます。
定期的にコミュニケーションをとる
内定承諾から入社までの期間は、数ヶ月から長い場合は1年近くに及びます。この長い期間、コミュニケーションが途絶えてしまうと、内定者の意欲は徐々に低下し、不安が増大していきます。細く長く、定期的なコミュニケーションを継続することが極めて重要です。
接触がイベント時だけに限られてしまうと、その間に関係性がリセットされてしまい、エンゲージメントが積み上がりません。大切なのは、特別なイベントがない時期にも、継続的な接点を持ち続けることです。
| 時期 | コミュニケーションのポイント |
|---|---|
| 内定直後 | 最も気持ちが高まっている時期。迅速に歓迎の意を伝え、今後の流れを丁寧に説明する。 |
| 夏休み・冬休み | 時間に余裕がある時期。少し踏み込んだ研修や、社員との交流イベントを設定しやすい。 |
| 卒業論文・研究の多忙期 | 学業を優先させる配慮が必要。負担の少ないメルマガやSNSでの情報提供が中心。 |
| 入社直前 | 不安が再燃しやすい時期。事務手続きの丁寧な案内とともに、歓迎ムードを高める。 |
コミュニケーションの頻度は、月に1〜2回程度が目安とされますが、これも内定者の反応を見ながら調整するのが良いでしょう。重要なのは、「忘れられていない」という安心感を内定者に与え続けることです。
フォローする時期・タイミングを意識する
内定者フォローは、ただ闇雲に実施すれば良いわけではありません。内定者の心理状態や状況の変化に合わせて、適切なタイミングで、適切な内容のフォローを行うことが効果を最大化します。
内定者の心理は、時期によって以下のように変化する傾向があります。
- 内定承諾直後(4月〜6月頃):
- 心理状態: 就職活動を終えた安堵感と、入社への期待感でモチベーションが高い。
- 有効なフォロー: 迅速なお祝いと歓迎のメッセージ。内定者懇親会で同期との繋がりを作る。今後のスケジュールを明確に示し、安心させる。
- 夏休み期間(7月〜9月頃):
- 心理状態: 少し落ち着き、「本当にこの会社でよかったのか」と考え始める時期(内定ブルー)。他社の情報も目に入りやすい。
- 有効なフォロー: 社員との座談会やオフィスツアーで、働くイメージを具体化させる。個別面談で不安をヒアリングする。
- 内定式前後(10月頃):
- 心理状態: 内定式を機に、入社の実感が湧き、気持ちが再び高まる。同期との連帯感も生まれる。
- 有効なフォロー: 印象に残る内定式を企画する。内定者同士の交流を深めるワークショップなどを実施する。
- 卒業研究・試験期(11月〜2月頃):
- 心理状態: 学業で多忙になり、企業との接触が負担に感じられることもある。
- 有効なフォロー: 参加を強制するイベントは避け、eラーニングやメルマガなど、本人のペースで関われるフォローが中心。負担にならない程度の個別連絡で、気にかけている姿勢を見せる。
- 入社直前期(3月頃):
- 心理状態: 社会人生活への期待と不安が入り混じる時期。
- 有効なフォロー: 入社手続きや研修の具体的な案内。歓迎ムードを盛り上げるメッセージや、部署の先輩からの連絡などで、安心して入社日を迎えられるようにサポートする。
この心理的な流れを理解し、戦略的にフォロープランを設計することが、成功への近道です。
内定者の本音を聞き出す工夫をする
内定者フォローの目的の一つは、内定者の不安や疑問を解消することですが、内定者は企業の担当者に対して、遠慮して本音を言えない場合があります。「こんなことを聞いたら、評価が下がるのではないか」と考えてしまうのです。
そのため、企業側には内定者が安心して本音を話せるような環境を作る工夫が求められます。
具体的なアクション:
- 聞き役を使い分ける: 人事担当者には言いにくいことも、年齢の近い若手社員になら話しやすい場合があります。メンター制度を導入し、定期的に若手社員が相談に乗る機会を設けましょう。
- 匿名性を担保する: オンラインの匿名質問ツールや、無記名のアンケートを活用し、「誰が言ったか分からない」状況で意見や質問を収集します。ここで集まった本音に対して、全体説明会などで誠実に回答する姿勢を見せることが重要です。
- 「何でも聞いていい」という雰囲気作り: 面談の冒頭で「今日の面談は選考とは一切関係ないので、どんな些細なことでも、ネガティブなことでも、安心して話してください」と明確に伝えるだけでも、心理的なハードルは大きく下がります。
内定者の沈黙を「満足」と捉えるのではなく、「何か言えないことがあるのかもしれない」と考える姿勢を持ち、積極的に本音を引き出す努力を続けることが、真の信頼関係構築に繋がります。
内定者フォローを行う際の注意点
内定者フォローは、良かれと思って行ったことが、かえって内定者の負担になったり、不信感を招いたりする危険性もはらんでいます。ここでは、内定者フォローを効果的に行うために、特に注意すべき3つの点について解説します。
過度なコミュニケーションは避ける
内定辞退を防ぎたいという思いが強すぎるあまり、過度なコミュニケーションをとってしまうのは逆効果です。頻繁すぎる電話やメール、イベントへの参加の強要などは、内定者にプレッシャーを与え、「就活終われハラスメント(オワハラ)」と受け取られかねません。
内定者はあくまで学生であり、卒業論文や研究、学業、アルバイトなど、入社前にやるべきことがたくさんあります。企業の都合を押し付けるのではなく、内定者の状況を尊重する姿勢が不可欠です。
避けるべき行動の具体例:
- 高頻度の連絡: 毎日や週に数回など、必要以上に連絡する。
- 即時返信の要求: メッセージを送った後、すぐに返信がないことを催促する。
- 参加の強要: 「任意参加」としながらも、欠席すると理由をしつこく聞いたり、不参加によって不利益があることを匂わせたりする。
- 他社の選考状況の詮索: 「他の内定先は辞退したか」としつこく確認する。
コミュニケーションの量よりも質を重視し、一回一回の接触が内定者にとって有益でポジティブな体験になるよう心がけましょう。連絡頻度やイベントの回数については、事前に内定者の意向を確認するのも一つの方法です。常に「内定者の負担になっていないか」という視点を持つことが大切です。
連絡手段は内定者に合わせる
コミュニケーションを円滑に進めるためには、内定者が普段から使い慣れている、あるいは希望する連絡手段を用いることが重要です。企業側が使いやすいからという理由で、一方的に連絡手段を決めつけるのは避けるべきです。
現代の学生の多くは、メールよりもLINEやSlackなどのチャットツールでのコミュニケーションを好む傾向にあります。一方で、フォーマルな連絡はメールを希望する学生や、電話での直接対話を好む学生もいるかもしれません。
推奨される対応:
- 初回連絡時に希望を確認: 内定承諾後、最初の連絡を取る際に「今後の連絡は、メール、LINE、電話など、どの方法がご希望ですか?」とヒアリングし、記録しておきます。
- 複数のチャネルを用意: 内定者フォローツールや専用SNSなど、複数のコミュニケーションチャネルを用意し、内定者が選びやすいようにします。
- 内容による使い分け: 緊急の連絡や重要な事務連絡は電話やメール、日常的な雑談や簡単な質疑応答はチャットツール、というように、連絡内容の重要度や性質に応じて手段を使い分けるのも効果的です。
内定者のコミュニケーションスタイルに寄り添う姿勢を見せることは、細やかな配慮として伝わり、企業への信頼感を高めることに繋がります。
個人情報の取り扱いに注意する
内定者同士の交流を促す目的で、本人の同意なく個人情報を他の内定者に共有することは、個人情報保護の観点から絶対にあってはなりません。
特に注意が必要なケース:
- 内定者名簿の配布: 氏名、大学名、連絡先などを記載した名簿を作成し、安易に配布する行為は非常に危険です。必ず一人ひとりから、どの情報をどこまで共有して良いか、書面等で明確な同意を得る必要があります。
- SNSグループへの強制参加: LINEグループなどへの参加を強制し、本人が意図しない形で連絡先が他の内定者に知られてしまう状況を作るのは避けるべきです。参加は任意とし、招待する前にその旨をしっかり説明しましょう。
- プライベートへの過度な干渉: 内定者の個人的なSNSアカウントを探したり、フォローを強要したりする行為は、プライバシーの侵害にあたります。公私混同と受け取られ、強い不快感を与える可能性があります。
個人情報は、内定者からの信頼の証です。企業は、個人情報保護法を遵守し、厳格な管理体制のもとで慎重に取り扱う責任があります。内定者フォローに関わる全ての社員が、個人情報保護の重要性を正しく理解し、細心の注意を払うよう徹底することが不可欠です。
内定者フォローに役立つおすすめツール
効果的な内定者フォローを効率的に実施するためには、専用ツールの活用が非常に有効です。ここでは、内定者フォローに役立つツールの概要と、具体的なサービスを4つ紹介します。
内定者フォローツールとは
内定者フォローツールとは、内定者とのコミュニケーション、情報提供、進捗管理などを一元化し、人事担当者の業務負担を軽減しながら、フォローの質を高めることを目的としたシステムです。
多くのツールには、以下のような機能が搭載されています。
| 機能カテゴリ | 具体的な機能 |
|---|---|
| コミュニケーション機能 | ・内定者専用SNS、掲示板、チャット機能 ・人事や先輩社員との1on1メッセージ機能 |
| 情報提供・管理機能 | ・お知らせやイベント情報の一斉配信 ・FAQや資料のデータベース化 ・内定者情報の管理、ステータス(承諾、辞退など)の可視化 |
| イベント・研修管理機能 | ・イベントの出欠管理、リマインドメールの自動送信 ・eラーニングコンテンツの配信、学習進捗の管理 |
| アンケート機能 | ・アンケートの作成、配信、自動集計 ・内定者のコンディションや満足度の定期的な測定 |
これらのツールを導入することで、連絡の抜け漏れ防止、業務の効率化、内定者エンゲージメントのデータに基づいた分析などが可能になり、より戦略的な内定者フォローが実現できます。
sonar ATS
sonar ATS(ソナー エーティーエス)は、株式会社Thinkingsが提供する採用管理システムです。その機能の一部として、強力な内定者フォロー機能も備わっています。
- 特徴: 採用活動の初期段階である応募者管理から、内定後のフォロー、さらには入社後のデータ連携まで、採用プロセス全体を一気通貫で管理できるのが最大の強みです。
- 主な機能:
- 内定者専用マイページの発行
- LINEとの連携による個別・一斉のメッセージ配信
- イベントの作成と出欠管理
- アンケートの実施と分析
- 内定者一人ひとりのステータス管理
- こんな企業におすすめ: 採用フロー全体の情報を一元管理し、業務効率を大幅に改善したい企業。採用担当者だけでなく、現場の社員や役員も巻き込んだ全社的な採用・フォロー活動を行いたい企業。
(参照:sonar ATS 公式サイト)
内定者パック
内定者パックは、新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」を運営する株式会社i-plugが提供する、内定者フォローに特化したサービスです。
- 特徴: 内定承諾から入社までの期間を「0年目」と位置づけ、内定者の成長を支援するコンテンツが充実している点が特徴です。特に、質の高いeラーニングプログラムに定評があります。
- 主な機能:
- 内定者研修(オンライン、オフライン)の企画・実施
- ビジネス基礎を学べるeラーニングコンテンツ
- 内定者懇親会などのイベント企画・運営サポート
- 適性診断ツール「eF-1G」の提供
- こんな企業におすすめ: 内定者フォローのノウハウが少なく、専門家のサポートを受けながら質の高い研修やイベントを実施したい企業。入社前のスキルアップ支援を手厚く行い、即戦力化を促したい企業。
(参照:株式会社i-plug 公式サイト)
aircord
aircord(エアコード)は、株式会社Tomoniが提供する内定者フォロー専用のSNSツールです。
- 特徴: SNS形式のインターフェースが学生にとって非常に馴染みやすく、気軽に利用できる点が魅力です。クローズドな環境で、内定者同士や社員との活発なコミュニケーションを促進します。
- 主な機能:
- タイムライン形式の掲示板
- ダイレクトメッセージ機能
- 課題提出や日報機能
- イベントの出欠管理
- プロフィール機能
- こんな企業におすすめ: 内定者同士の横のつながりを早期に構築させたい企業。堅苦しい雰囲気ではなく、フランクでオープンなコミュニケーションを重視する企業。
(参照:aircord 公式サイト)
EDGE
EDGE(エッジ)は、株式会社No Companyが提供する、オンラインでのチームビルディングや内定者研修に特化したサービスです。
- 特徴: 「全員主人公」をコンセプトに、物語体験型のオンラインイベントを提供している点がユニークです。謎解きゲームやコンセンサスゲームなど、エンターテイメント性が高く、参加者の主体性を引き出すプログラムが豊富です。
- 主な機能:
- オンライン謎解き脱出ゲーム
- オンラインコンセンサスゲーム
- 企業理念浸透を目的としたワークショップ
- イベントの企画から当日の運営までをトータルでサポート
- こんな企業におすすめ: オンラインでの内定者フォロー施策で、参加者の満足度や一体感を高めたい企業。ありきたりな研修ではなく、記憶に残るユニークな体験を提供したい企業。
(参照:EDGE 公式サイト)
まとめ
本記事では、内定者フォローの重要性から、内定辞退を防ぎエンゲージメントを高めるための面白い施策アイデア、成功のポイント、注意点、そして役立つツールまで、網羅的に解説しました。
激化する採用競争の中で、内定者フォローはもはや単なる事務手続きや辞退防止策ではなく、企業の未来を担う人材を育成するための最初の、そして極めて重要なステップです。内定承諾から入社までの期間を、いかに内定者にとって有意義で、心躍る体験にできるかが、他社との差別化を図り、優秀な人材を惹きつけておくための鍵となります。
今回ご紹介した20のアイデアは、あくまで一例です。最も大切なのは、自社のカルチャーやビジョン、そして何よりも「内定者一人ひとり」に真摯に向き合い、自社ならではの心のこもったフォローを企画・実行することです。
面白い施策を通じて、内定者に「この会社を選んで本当に良かった」「この仲間たちと働くのが楽しみだ」と感じてもらうことができれば、それは内定辞退の防止に留まらず、入社後のスムーズな活躍、そして長期的な企業成長の礎となるはずです。
この記事が、貴社の内定者フォローをより効果的で、より魅力的なものへと進化させる一助となれば幸いです。