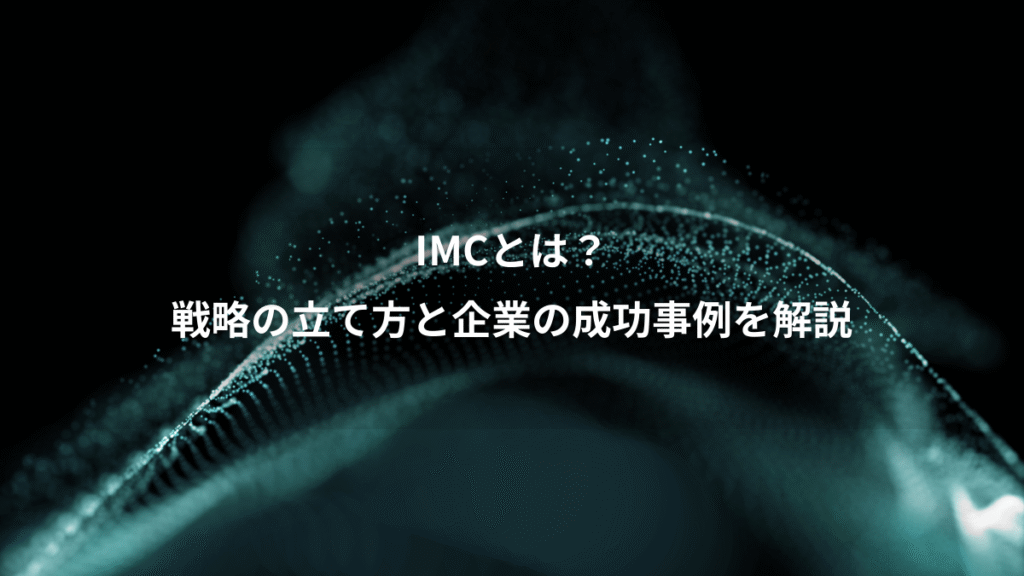現代のマーケティング環境は、デジタル技術の進化と消費者の行動様式の変化により、かつてないほど複雑化しています。無数の情報チャネルから日々膨大なメッセージが発信される中で、企業が生活者に自社の製品やサービスの価値を届け、深い関係性を築くことは容易ではありません。
このような時代背景から、今、改めて注目を集めているのが「IMC(Integrated Marketing Communication:統合型マーケティングコミュニケーション)」という考え方です。IMCは、広告、PR、販売促進、SNS、Webサイトといった個別のマーケティング活動をバラバラに行うのではなく、一貫した戦略のもとに統合し、相乗効果を最大化させるアプローチです。
この記事では、現代マーケティングの要ともいえるIMCについて、その基本的な概念から、なぜ今重要視されるのかという背景、具体的な戦略の立て方、そして実践する上でのポイントまでを網羅的に解説します。IMCを理解し、自社のマーケティング活動に活かすための一助となれば幸いです。
目次
IMC(統合型マーケティングコミュニケーション)とは

IMC(Integrated Marketing Communication)は、日本語で「統合型マーケティングコミュニケーション」と訳されます。これは、企業が顧客や潜在顧客に対して行うあらゆるコミュニケーション活動を、戦略的に統合・調整し、一貫性のある明確なメッセージを届けることで、その効果を最大化しようとするマーケティングのアプローチです。
従来、企業のマーケティング活動は、広告、PR(広報)、販売促進(セールスプロモーション)、ダイレクトマーケティング、イベント、Webマーケティングといった各手法が、それぞれの専門部署によって個別最適化される傾向にありました。例えば、広告代理店はテレビCMを、PR会社はプレスリリースを、Web制作会社はWebサイトを、それぞれが独立して企画・実行する、といった形です。
しかし、この「サイロ化(縦割り)」されたアプローチでは、各チャネルで発信されるメッセージやブランドイメージに食い違いが生じ、顧客に混乱を与えかねません。最悪の場合、それぞれの施策が互いの効果を打ち消し合ってしまう可能性すらあります。
IMCは、こうした課題を解決するために生まれました。中心には常に「顧客」を据え、顧客がブランドと接触する可能性のある全ての「タッチポイント(顧客接点)」において、統一されたブランド体験を提供することを目指します。
IMCの構成要素を分解すると、その本質がより深く理解できます。
- 統合型(Integrated): バラバラになりがちな各マーケティング手法やチャネルを、一つの戦略的な目標の下に連携させ、相乗効果を生み出すことを意味します。メッセージの統合、チャネルの統合、組織の統合など、多層的な統合が含まれます。
- マーケティング(Marketing): IMCは単なる情報発信の手法ではありません。市場を分析し、顧客を理解し、自社の製品やサービスが持つ価値を定義し、それを適切な価格と流通経路で提供するという、マーケティング全体のプロセスと密接に連携しています。
- コミュニケーション(Communication): 企業から顧客への一方的な情報伝達(-munication)ではなく、顧客からの反応や対話を含む双方向のやり取り(Com-munication)を重視します。顧客の声に耳を傾け、関係性を構築していくプロセスそのものがIMCの核となります。
具体例を挙げてみましょう。ある化粧品会社が、20代の若者向けに新しいスキンケア商品を発売するケースを考えます。
【従来のサイロ化されたアプローチ】
- 広告部: 人気タレントを起用したテレビCMを放映し、商品の認知度向上を目指す。
- Web担当部: 商品の機能や成分を詳細に解説するLP(ランディングページ)を作成し、リスティング広告を出稿する。
- 広報部: 美容系雑誌の編集部に向けてプレスリリースを配信し、記事掲載を狙う。
- SNS担当部: Instagramでインフルエンサーに商品を提供し、レビュー投稿を依頼する。
- 販売促進部: ドラッグストアでの購入者向けに、サンプル品のプレゼントキャンペーンを実施する。
この場合、各施策はそれぞれの目標(CMの視聴率、LPのCVR、記事掲載数など)を追いかけますが、全体としての一貫性が欠けている可能性があります。CMの華やかなイメージと、LPの科学的な訴求、インフルエンサーのカジュアルな投稿のトーンがバラバラだと、顧客は「このブランドは結局何を伝えたいのだろう?」と混乱してしまうかもしれません。
【IMCに基づいたアプローチ】
- コアメッセージの設定: まず、「ありのままの自分を好きになる、自信の素肌へ」といった、ターゲットの心に響く統一されたコアメッセージを開発します。
- チャネル横断のストーリー設計:
- ティザー期(発売前): InstagramやTikTokで「#ありのままの自分」といったハッシュタグキャンペーンを展開し、若者たちの共感を醸成。インフルエンサーには、商品の宣伝ではなく、自身の「ありのまま」に関するストーリーを投稿してもらう。
- ローンチ期(発売時): テレビCMでは、タレントが完璧に作り込まれた美しさではなく、自然体で生き生きとした表情を見せることでコアメッセージを表現。CMの最後に「続きはWebで」と誘導し、Webサイトでは、CMの世界観と連動したデザインの中で、利用者のリアルな声や開発者の想いを伝えるコンテンツを用意する。
- エンゲージメント期(発売後): 店頭では、CMやWebサイトと同じトーンのPOPを設置。購入者がSNSで「#自信の素肌」をつけて投稿すると、次回の購入時に使えるクーポンがもらえるキャンペーンを実施。集まったUGC(ユーザー生成コンテンツ)を公式サイトやSNSで紹介し、さらなる共感の輪を広げる。
- PR活動: 雑誌やWebメディアには、単なる商品情報だけでなく、このキャンペーン全体の背景にある思想やストーリーを提供し、より深い理解を促す記事化を目指す。
このように、IMCでは全てのコミュニケーション活動がコアメッセージを中心に有機的に連携し、一貫したブランドストーリーを多角的に伝えます。これにより、顧客は様々なタッチポイントで同じ世界観に触れることになり、ブランドへの理解と共感が深まります。結果として、単発の施策を足し合わせた以上の、強力なブランド構築と販売促進効果が期待できるのです。
IMCは、単に複数のメディアを使う「クロスメディア」や「メディアミックス」とは一線を画します。クロスメディアがメディア間の連携に主眼を置くのに対し、IMCは顧客体験(CX)の視点から、メッセージ、チャネル、組織、目標など、マーケティングコミュニケーションに関わるあらゆる要素を統合する、より包括的で戦略的な概念であると言えるでしょう。
IMCが現代のマーケティングで重要視される3つの背景
なぜ今、多くの企業がIMCの導入に力を入れているのでしょうか。その背景には、現代の市場環境を特徴づける、無視できない3つの大きな変化が存在します。これらの変化は、従来のマーケティング手法の限界を浮き彫りにし、IMCの必要性をかつてないほど高めています。
① 消費者の購買プロセスの変化
第一の背景は、インターネットとスマートフォンの普及がもたらした、消費者の情報収集・購買行動の劇的な変化です。かつて、消費者が商品情報を得る手段は、テレビ、新聞、雑誌、ラジオといったマスメディアや、店頭での説明など、比較的限られていました。企業が発信する情報を消費者が受動的に受け取るのが一般的で、その購買プロセスは「AIDMA(アイドマ)」モデルで説明されてきました。
- Attention(注意): CMなどで商品を知る。
- Interest(関心): 面白そうだと興味を持つ。
- Desire(欲求): 欲しいと感じる。
- Memory(記憶): 店頭で思い出す。
- Action(行動): 購入する。
しかし、現代の消費者は、気になる商品があればすぐにスマートフォンで検索し、公式サイトはもちろん、比較サイト、レビューサイト、個人のブログ、SNS上の口コミなど、ありとあらゆる情報を能動的に収集・比較検討します。企業からの公式情報だけでなく、他のユーザーによるリアルな評価(UGC:User Generated Content)が、購買意思決定に大きな影響を与えるようになりました。
このような変化を捉えた新しい購買行動モデルとして、「AISAS(アイサス)」が提唱されています。
| モデル | プロセス |
|---|---|
| AIDMA | Attention → Interest → Desire → Memory → Action |
| AISAS | Attention → Interest → Search(検索) → Action → Share(共有) |
AISASモデルの最大の特徴は、「Search(検索)」と「Share(共有)」というインターネット時代ならではの行動が組み込まれている点です。消費者は購入前に自ら情報を探し(Search)、購入後にはその体験をSNSなどで共有(Share)します。そして、その共有された情報が、また別の誰かの「Attention」や「Search」の対象となる、という循環が生まれています。
この購買プロセスの変化は、マーケティングコミュニケーションに大きな影響を与えました。企業はもはや、一方的な情報発信だけで消費者の心を動かすことはできません。検索された時に信頼できる情報を提供できているか、SNSでポジティブな共有を生み出せているか、といった視点が不可欠になります。
消費者が接触するタッチポイントは、オンライン(Webサイト、SNS、動画広告など)とオフライン(店舗、イベント、DMなど)を複雑に行き来します。例えば、Instagramの広告で商品を知り(Attention/Interest)、公式サイトで詳細を確認し(Search)、レビューサイトで口コミをチェックし(Search)、実店舗で商品を試してから(Action検討)、最終的にECサイトで購入する(Action)、といった具合です。
このような複雑なカスタマージャーニーにおいて、もし各タッチポイントで発信されるメッセージやブランドイメージに一貫性がなければ、消費者は途中で混乱し、離脱してしまうでしょう。だからこそ、全てのタッチポイントを統合的に管理し、シームレスで一貫した顧客体験を提供するIMCの考え方が不可欠なのです。
② メディアの多様化と複雑化
第二の背景として、コミュニケーションチャネル、すなわちメディアの爆発的な多様化と複雑化が挙げられます。かつてマーケティングコミュニケーションの中心にあったのは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌という「4マス媒体」でした。これらのメディアは広範なリーチ力を持つため、企業はここに広告を投下することで、多くの消費者にメッセージを届けることができました。
しかし、インターネットの登場以降、メディア環境は一変しました。
- Webサイト: オウンドメディア、コーポレートサイト、LP(ランディングページ)
- SNS: X (旧Twitter)、Instagram、Facebook、TikTok、LINE
- 動画プラットフォーム: YouTube, Vimeo
- デジタル広告: リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告、動画広告
- その他: メールマガジン、プレスリリース、インフルエンサーマーケティング、ポッドキャスト、ウェビナー、メタバース
これらのデジタルメディアは、それぞれが異なる特性とユーザー層を持っています。例えば、TikTokは若年層向けの短い動画コンテンツ、Facebookは実名制で比較的高い年齢層のコミュニティ形成、Xはリアルタイム性の高い情報拡散、といった特徴があります。
メディアが多様化したことで、企業はターゲット顧客に合わせてチャネルをきめ細かく使い分けることが可能になりました。しかし、それは同時に、コミュニケーション活動の全体像を把握し、管理することを非常に困難にしました。
各メディアの担当者がそれぞれのKPI(例:WebサイトのPV数、Instagramのフォロワー数、広告のクリック率)だけを追い求めて個別最適化を進めた結果、企業全体として発信するメッセージが分断され、チグハグな印象を与えてしまう「チャネル・サイロ」の問題が深刻化しています。
例えば、テレビCMでは高級感あふれる世界観を訴求しているのに、Xの公式アカウントが非常に砕けた口調でキャンペーン告知を行っていたら、顧客はブランドの本当の姿をどう捉えればよいでしょうか。また、Web広告とメールマガジンで、同じキャンペーンなのに異なる割引率を提示してしまったら、顧客の不信感を招きかねません。
このような事態を防ぎ、多様なメディアを効果的に活用するためには、全てのチャネルを俯瞰し、一貫したブランドメッセージのもとに統合・連携させるIMCの視点が不可欠です。IMCでは、各メディアの特性を理解した上で、それぞれの役割を明確に定義し、カスタマージャーニーの各段階において最適なチャネルを組み合わせる「チャネルミックス」を設計します。これにより、メディア間の相乗効果(シナジー)を生み出し、マーケティングROI(投資対効果)を最大化することを目指すのです。
③ ブランディングの重要性の高まり
第三の背景は、市場の成熟化とグローバル化に伴う、ブランディングの重要性の高まりです。多くの業界で技術がコモディティ化(均質化)し、製品の機能や品質、価格だけで競合との差別化を図ることが難しくなりました。どこで買っても同じような性能の商品が、同じような価格で手に入る時代において、消費者は何を基準に選択を行うのでしょうか。
その答えの一つが「ブランド」です。消費者は、単に機能的な便益(ベネフィット)を得るためだけでなく、そのブランドが持つ世界観、ストーリー、価値観に共感し、そのブランドを選ぶことで得られる情緒的な価値や自己表現を求めるようになっています。
- 「このブランドの服を着ると、自分もおしゃれで洗練された人間になったように感じる」
- 「環境問題に真摯に取り組むこの企業の製品を買うことで、社会貢献に参加したい」
- 「クリエイティブな挑戦を応援するこのブランドの姿勢が好きだ」
このように、ブランドへの共感や信頼、愛着といった「顧客ロイヤルティ」が、継続的な購買や推奨行動に繋がる重要な資産となっています。強力なブランドを構築できれば、価格競争から脱却し、安定した収益を確保することが可能になります。
このブランディングにおいて、IMCは決定的な役割を果たします。ブランドイメージやブランドへの共感は、一度の広告や一つの出来事で形成されるものではありません。顧客がブランドと接触するあらゆる機会、つまり広告、PR記事、Webサイトのデザイン、SNSでの対話、店舗での接客、製品のパッケージ、コールセンターの応対といった、全てのタッチポイントでの体験が積み重なって、時間をかけて醸成されるものです。
もし、これらの体験に一貫性がなく、矛盾したメッセージが発信されていたら、どうなるでしょうか。顧客の中に、明確で好ましいブランドイメージを築くことはできません。例えば、広告では「お客様一人ひとりに寄り添う」と謳っているのに、コールセンターの対応がマニュアル一辺倒で冷たかったとしたら、顧客は失望し、ブランドへの信頼を失ってしまうでしょう。
IMCは、全ての顧客接点において、ブランドが約束する価値(ブランド・プロミス)を一貫して伝え、体現することを目指すアプローチです。これにより、顧客の中にブレのない強力なブランドイメージを構築し、深い信頼関係と顧客ロイヤルティを育むことができるのです。製品やサービスが簡単に模倣される時代だからこそ、模倣することが極めて困難な「強いブランド」を築くための戦略として、IMCの重要性がますます高まっているのです。
IMC戦略を導入する3つのメリット
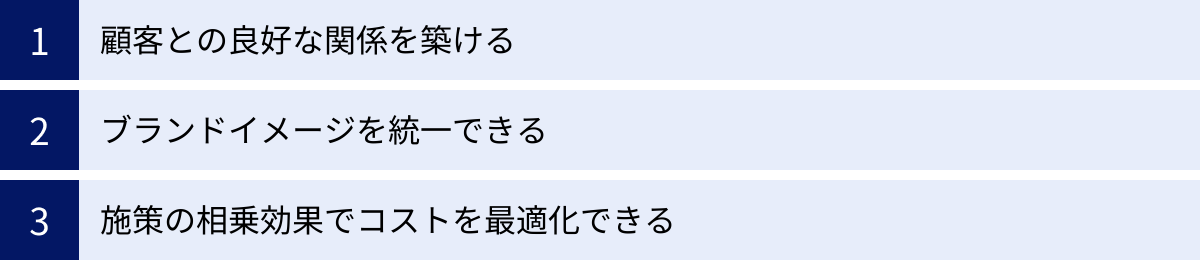
IMC戦略を導入し、統合的なマーケティングコミュニケーションを実践することは、企業に多くの恩恵をもたらします。サイロ化されたアプローチでは得られない、IMCならではのメリットは大きく分けて3つ存在します。これらを理解することは、IMC導入の目的を明確にし、社内の合意形成を図る上でも重要です。
① 顧客との良好な関係を築ける
IMC戦略を導入する最大のメリットは、顧客一人ひとりとの間に、長期的で良好な関係性を構築できることです。IMCの根底には、企業が伝えたいことを一方的に発信するのではなく、「顧客を深く理解し、顧客にとって価値のある情報や体験を提供する」という顧客中心の思想があります。
あらゆるタッチポイントで一貫したメッセージとトーン&マナーを維持することで、顧客はブランドに対して明確なイメージを抱き、理解を深めることができます。「このブランドは、いつもこういう価値観を大切にしているんだな」「どんなチャネルでも、親しみやすい姿勢は変わらないな」といった認識が積み重なることで、次第にブランドへの親近感や信頼感が醸成されていきます。
例えば、あるアウトドアブランドが「自然との共生」をコアメッセージに掲げたとします。
- Webサイト: 環境に配慮した素材や製造プロセスを詳しく紹介する。
- SNS: 製品の魅力だけでなく、自然の美しさや環境保護活動の様子を発信する。
- 店舗イベント: 地域の清掃活動や、親子で参加できる自然観察会などを開催する。
- 製品: 長く使える丈夫な作りで、修理サービスも充実させる。
このように、全てのコミュニケーション活動を通じて「自然との共生」という姿勢が一貫していれば、顧客は単なる製品の購入者としてではなく、ブランドの価値観を共有するパートナーとして、強いエンゲージメントを感じるようになります。
さらに、現代のIMCでは、CRM(顧客関係管理)システムやMA(マーケティングオートメーション)ツールなどを活用し、顧客データに基づいたパーソナライズされたコミュニケーションが可能です。顧客の購買履歴や行動履歴に応じて、その人が本当に関心を持ちそうな情報や特典を、最適なタイミングとチャネルで届けることができます。
「以前購入したジャケットに合うパンツの新色が出ましたよ」といったレコメンドメールや、「〇〇様のお住まいの地域で、来週イベントが開催されます」といったLINEでの通知は、顧客に「自分のことを理解してくれている」という特別な感覚を与え、ブランドへの愛着を深めます。
このような継続的で質の高いコミュニケーションは、一度きりの購入で終わらない、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の高い優良顧客を育てる上で極めて重要です。顧客との強い絆は、競合他社への乗り換えを防ぐ強力な防壁となり、企業の持続的な成長を支える基盤となるのです。
② ブランドイメージを統一できる
第二のメリットは、強力でブレのないブランドイメージを構築し、市場における認知と評価を高められることです。前述の通り、ブランドイメージは顧客が体験する情報の断片の集合体です。IMCによってこれらの断片を意図的にコントロールし、一貫したストーリーに編み上げることで、企業の望むブランド・アイデンティティを顧客の心の中に正確に植え付けることができます。
もしIMCが導入されていなければ、各部門がそれぞれの判断でコミュニケーションを行うため、ブランドイメージが拡散・希薄化するリスクが常に伴います。
- 広告部が訴求する「革新的なテクノロジー」
- 広報部が発信する「社会貢献への取り組み」
- 営業部が強調する「業界最安値の価格」
これらはどれも企業の一側面ではあるものの、同時に発信されると、顧客は「この会社は結局、技術が売りなのか、社会貢献がしたいのか、それとも安さが魅力なのか?」と混乱し、明確なブランドイメージを持つことができません。これでは、顧客の記憶に残る強いブランドを築くことは困難です。
IMCを導入し、例えば「革新的なテクノロジーで、サステナブルな社会を実現する」といった中核となるブランド・プロミスを定め、全ての活動をこのプロミスに沿って展開すれば、状況は一変します。
- 広告: テクノロジーの先進性だけでなく、それがどう環境負荷を低減するかに焦点を当てる。
- PR: 社会貢献活動も、自社の技術を活かしたユニークな取り組みとして発信する。
- 価格: 単なる安売りではなく、技術革新によるコストダウンの結果であることを伝え、価値を損なわない。
このように、全てのタッチポイントで同じ方向を向いたメッセージを発信し続けることで、「テクノロジー×サステナビリティ」という独自のブランドポジションが確立されます。顧客は、その企業名を聞いただけで、この明確なイメージを連想するようになります。
この統一されたブランドイメージは、ブランドエクイティ(ブランドが持つ資産価値)の向上に直結します。高いブランドエクイティを持つ企業は、市場で優位な立場を築き、価格決定権を持ち、優秀な人材を引きつけ、新たな事業展開も有利に進めることができるようになります。メッセージのブレによる顧客の混乱を防ぎ、意図した通りのブランドを構築できること。これは、競争が激化する現代市場を勝ち抜く上で、計り知れない価値を持つメリットです。
③ 施策の相乗効果でコストを最適化できる
第三のメリットは、経済的な側面、すなわちマーケティング活動全体の費用対効果を高め、コストを最適化できる点です。これは「シナジー効果」とも呼ばれ、IMCの大きな魅力の一つです。
サイロ化されたアプローチでは、各施策が独立して動くため、重複した投資が発生したり、連携不足によって機会損失が生まれたりすることが少なくありません。例えば、広告部とWeb担当部が連携していなければ、多額の費用をかけて獲得した広告からのアクセスを、最適化されていないWebサイトで無駄にしてしまう、といった事態が起こり得ます。
IMCでは、各マーケティング施策を一つの大きな流れの中に位置づけ、有機的に連携させます。これにより、「1 + 1」が2ではなく、3にも4にもなるような相乗効果が期待できます。
【シナジー効果の具体例】
- 認知から獲得へ: テレビCMやWeb動画広告で広く商品やサービスの認知を獲得(認知)。
- 興味関心の育成: 広告で興味を持ったユーザーが検索した際に、詳細な情報を提供するオウンドメディアや比較記事を用意しておく(興味関心)。
- エンゲージメントの深化: オウンドメディアから公式SNSに誘導し、フォロワーになってもらう。SNSでユーザー参加型のキャンペーンを実施し、ブランドへの愛着を深める(エンゲージメント)。
- 購買への後押し: SNSのフォロワーやWebサイト訪問者に対して、リターゲティング広告やメールマガジンで限定クーポンを配信し、購買を後押しする(比較検討・購買)。
- 推奨の促進: 購入者に対して、レビュー投稿や友人紹介を促すプログラムを用意し、ポジティブな口コミ(UGC)を広げてもらう(共有・推奨)。
この一連の流れでは、各施策が次の施策へと顧客をスムーズに引き渡し、バトンのように繋いでいくことで、最終的なコンバージョンへと導いています。CMで獲得した認知がWebサイトへの訪問を促し、Webサイトでの体験がSNSでのエンゲージメントを生み、それが最終的な購買に繋がる。このように、各施策がお互いの効果を高め合っているのです。
また、コスト削減の観点からもメリットがあります。
- クリエイティブの共通化: コアとなるメッセージやビジュアルを一度開発すれば、それを各チャネルに合わせて展開できるため、チャネルごとにゼロから制作するよりもコストと時間を削減できます。
- 重複投資の回避: 部署間で情報が共有されるため、「A部署とB部署が、同じターゲットに対して別々に広告を出稿していた」といった無駄な投資を防げます。
- 効果的なリソース配分: 全体の効果を測定・分析することで、どのチャネルの組み合わせが最もROIが高いかが明確になります。これにより、効果の低い施策の予算を削り、効果の高い施策にリソースを集中させるといった、データに基づいた賢明な意思決定が可能になります。
IMCは、単にメッセージを統一するだけでなく、マーケティング投資全体を最適化し、ビジネスの成長を加速させる経営戦略でもあるのです。
IMC戦略を導入する際の2つのデメリット
IMC戦略は多くのメリットをもたらす強力なアプローチですが、その導入と実践は決して容易ではありません。理想を掲げるだけではうまくいかず、企業が直面しがちな現実的な課題、すなわちデメリットや障壁が存在します。ここでは、代表的な2つのデメリットを掘り下げ、その背景と乗り越えるためのヒントを探ります。
① 部門間の連携が難しい
IMCを実践する上で、最も大きく、そして根深い障壁となるのが「部門間の連携の難しさ」です。IMCの本質が「統合」にある以上、組織の壁を越えた協力体制は絶対不可欠です。しかし、多くの日本企業に見られる伝統的な組織構造は、この「統合」とは相容れない側面を持っています。
【連携を阻む要因】
- 組織のサイロ化(縦割り構造): 企業の組織は多くの場合、機能別に編成されています。広告宣伝部、広報部、営業企画部、デジタルマーケティング部、カスタマーサポート部など、それぞれの部門が専門性を持ち、独立して業務を遂行しています。この構造は専門性を高める上では効率的ですが、部門間のコミュニケーションを希薄にし、「自分の部署の仕事だけやっていればよい」という意識を生み出す原因となります。
- 異なるKPI(重要業績評価指標): 各部門は、それぞれ異なるKPIを目標として設定していることがほとんどです。広告部は「認知度」「CM視聴率」、Web担当部は「サイト流入数」「CVR」、営業部は「売上高」「契約件数」といった具合です。IMCで全体の最適化を目指そうとしても、各部門は自部門のKPI達成を優先するため、他部門への協力が後回しになったり、利害が対立したりすることがあります。「全体の売上のためにはWebサイトの改善が必要だが、Web担当部のKPIは流入数なので、CVR改善の改修にはリソースを割けない」といったケースは典型例です。
- 情報共有の欠如: 部門間で定常的な情報共有の場や仕組みがなければ、お互いが何をやっているのかを知る由もありません。「広報部が大きなメディア露出を獲得したのに、営業部はその情報を知らず、商談で活用できなかった」「SNSでキャンペーンが始まっていることを、店舗スタッフがお客様から聞いて初めて知った」など、連携不足による機会損失は至る所で発生します。
- 企業文化とセクショナリズム: 長年培われてきた企業文化や、自部門の利益を優先するセクショナリズム(縄張り意識)も、連携を阻む大きな壁となります。新しい取り組みに対する抵抗感や、「なぜ他部署の仕事を手伝わなければならないのか」といった反発が生まれることも少なくありません。
これらの課題を克服し、部門間のスムーズな連携を実現するためには、付け焼き刃の対策では不十分です。経営層の強いリーダーシップと、組織構造そのものへのメス入れが必要になる場合もあります。
【解決へのアプローチ】
- IMC推進チームの設置: 各部門から代表者を集めた、部門横断型のプロジェクトチームや専門部署を設置します。このチームがハブとなり、各部門の活動を調整し、情報共有を促進します。
- 共通の目標(KGI)の設定: 部門ごとのKPIの上位に、IMC戦略全体で目指す共通のゴール、すなわちKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標、例:ブランド好意度の向上、新規顧客獲得数)を設定し、全関係者で共有します。これにより、各部門が同じ方向を向いて協力する動機付けが生まれます。
- トップダウンでのコミットメント: 経営トップがIMCの重要性を理解し、「全社的に取り組むべき最重要課題である」という明確なメッセージを発信することが極めて重要です。トップの強力なコミットメントは、部門間の壁を取り払い、変革を推進する大きな力となります。
- 定期的な情報共有会議: 定期的に関係者が一堂に会し、各施策の進捗や成果、課題を共有する場を設けます。これにより、認識のズレを防ぎ、新たな連携のアイデアが生まれる土壌を作ります。
- 統合ダッシュボードの導入: 各チャネルのデータを一元的に可視化できるダッシュボードを導入し、関係者全員がリアルタイムで状況を把握できるようにすることも有効です。
部門間の連携は、IMC成功の鍵を握る最重要課題です。組織的な障壁を認識し、粘り強くその解消に取り組む覚悟が求められます。
② 施策全体の効果測定が難しい
IMCのもう一つの大きなデメリットは、統合されたコミュニケーション活動全体の効果を正確に測定することの難しさにあります。複数のマーケティング施策が複雑に絡み合い、相互に影響を与え合うため、最終的な成果(売上など)が「どの施策の、どの部分の貢献によるものか」を明確に切り分けることが非常に困難なのです。
例えば、ある顧客が商品を購入した場合、その購入に至るまでには、
- テレビCMで商品を認知し、
- 雑誌の記事で興味を持ち、
- Web広告をクリックしてサイトを訪れ、
- SNSで口コミを検索し、
- 最終的に店頭のPOPを見て購入を決めた
…といった複雑な経緯があるかもしれません。この場合、売上への貢献度はCM、雑誌、Web広告、SNS、POPにどう配分されるべきでしょうか?この問いに完璧に答えることは、現実的にはほぼ不可能です。
【効果測定を難しくする要因】
- アトリビューションの問題: アトリビューションとは、コンバージョン(成果)に至る各タッチポイントの貢献度を評価することです。多くの場合、コンバージョン直前のタッチポイント(この例では店頭POP)のみが評価されがちですが(ラストクリックモデル)、その手前にあったCMや雑誌記事といった認知・興味喚起の施策の貢献を無視することはできません。しかし、その貢献度を定量的に測定するための、万能なモデルは存在しないのが現状です。
- オフライン施策のデータ化の困難さ: Web広告やサイトアクセスといったオンライン施策はデータ計測が比較的容易ですが、テレビCM、雑誌広告、交通広告、イベントといったオフライン施策の効果を、オンラインの成果と直接結びつけて計測することは技術的に困難な場合が多くあります。
- 時間差(タイムラグ)の影響: 認知度向上のための施策(ブランディング広告など)は、すぐに売上に結びつくとは限りません。数ヶ月後、あるいは数年後にじわじわと効果が現れることもあり、短期的なROI(投資対効果)だけではその価値を正しく評価できません。
- 外部要因の存在: 売上は、マーケティング活動だけでなく、景気の動向、競合の動き、天候、社会的なトレンドなど、様々な外部要因の影響を受けます。これらの要因とマーケティング施策の効果を切り分けて分析することは、極めて複雑な統計的アプローチを必要とします。
この「効果測定の難しさ」は、IMC活動の予算確保や、継続的な改善を困難にする要因となります。施策の貢献度を明確に説明できなければ、経営層から「本当にその投資に見合う効果があるのか?」と疑問を呈され、予算を削減されてしまうかもしれません。また、何がうまくいっていて、何を改善すべきかが見えにくいため、PDCAサイクルを回しづらくなるという問題も生じます。
【解決へのアプローチ】
- 中間KPIの設定と計測: 最終的なKGI(売上など)だけでなく、カスタマージャーニーの各段階に応じた中間的なKPIを設定し、それを丹念に追跡します。例えば、「認知段階:指名検索数、広告のリーチ数」「興味・関心段階:サイト滞在時間、動画視聴完了率」「比較・検討段階:資料請求数、カート投入数」などです。これらのKPIを組み合わせることで、直接的な売上貢献が見えにくい施策の価値も評価しやすくなります。
- マーケティングミックスモデリング(MMM): 統計的な手法を用いて、売上などのKGIと、様々なマーケティング施策の投入量や外部要因のデータを分析し、各要素の貢献度を推計するモデルです。専門的な知識が必要ですが、IMC全体のROIを評価し、最適な予算配分を導き出す上で強力なツールとなります。
- 統一された計測基盤の構築: アンケート調査によるブランドリフト調査(広告接触者と非接触者の意識変化を比較)や、特定のクーポンコードの使用、オフラインでの行動をトラッキングするビーコン技術の活用など、オフラインとオンラインの効果を統合的に把握するための工夫を行います。
- テストと学習のアプローチ: 最初から完璧な効果測定を目指すのではなく、A/Bテストなどを通じて、小規模な仮説検証を繰り返すことも重要です。例えば、「このクリエイティブは、こちらのチャネルで効果が高い」といった知見を一つひとつ積み重ねていくことで、徐々に全体の最適化に近づいていくことができます。
施策全体の効果測定は依然として挑戦的な課題ですが、様々な手法を組み合わせ、長期的な視点で粘り強く分析に取り組む姿勢が、IMCを成功に導くためには不可欠です。
IMC戦略の立て方を5つのステップで解説
IMC戦略を絵に描いた餅で終わらせず、実効性のあるものにするためには、論理的で体系的なプロセスに沿って計画を立てることが重要です。ここでは、IMC戦略を立案し、実行・改善していくための基本的な5つのステップを解説します。このプロセスは、あらゆる業種・規模の企業に応用可能な汎用的なものです。
① ステップ1:市場・顧客・競合を分析する
全ての戦略立案の出発点は、自社が置かれている現状を客観的かつ正確に把握することです。思い込みや勘に頼るのではなく、データに基づいた冷静な分析が、その後の全てのステップの土台となります。この段階では、主に「3C分析」などのフレームワークを活用して、外部環境と内部環境を多角的に分析します。
- 市場・顧客(Customer)の分析:
- 市場規模と成長性: ターゲットとする市場はどのくらいの大きさで、今後拡大するのか、縮小するのか。
- 顧客ニーズ: 顧客はどのような課題や欲求を抱えているのか。何を求めて製品やサービスを購入するのか。
- 購買行動: 顧客はどこで情報を収集し、何を基準に比較検討し、どのようなプロセスで購入を決定するのか(カスタマージャーニーの把握)。
- マクロ環境分析(PEST分析など): 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)といった、自社ではコントロールできない外部環境の変化が、市場や顧客にどのような影響を与えるかを分析します。
- 競合(Competitor)の分析:
- 競合の特定: 直接的な競合はどこか。代替品となるような間接的な競合は存在するか。
- 競合の戦略: 競合はどのような製品を、どのような価格で、どのようなチャネルで販売しているか。
- 競合のコミュニケーション: 競合はどのようなメッセージを発信し、どのようなマーケティング活動(広告、SNSなど)を行っているか。その強みと弱みは何か。
- 自社(Company)の分析:
- 自社の強み(Strength)と弱み(Weakness): 技術力、ブランド力、顧客基盤、販売網、組織文化など、競合と比較した際の自社の長所と短所は何か(SWOT分析)。
- 自社の現状: 現在の売上、シェア、利益率はどうなっているか。ブランドはどのように認知されているか。
- 経営資源: IMC戦略に投入できる予算、人材、時間はどのくらいか。
このステップの目的は、市場における機会(Opportunity)と脅威(Threat)を明らかにし、自社の強みを活かしてその機会を掴むための戦略的な方向性(KSF:Key Success Factor、成功要因)を見出すことです。ここでの分析が曖昧だと、その後の戦略全体が的外れなものになってしまうため、最も時間をかけて丁寧に行うべきプロセスです。
② ステップ2:ターゲットとペルソナを明確にする
市場分析の結果を踏まえ、次に「誰に(Whom)」メッセージを届けるのかを具体的に定義します。市場全体を漠然と狙うのではなく、自社の強みが最も活かせる、あるいは最も大きな機会が見込める特定の顧客層に絞り込む「ターゲティング」を行います。
ターゲティングを行う際には、以下のような切り口(セグメンテーション変数)で市場を細分化します。
- 地理的変数(ジオグラフィック): 国、地域、都市規模、人口密度など。
- 人口動態変数(デモグラフィック): 年齢、性別、所得、職業、学歴、家族構成など。
- 心理的変数(サイコグラフィック): ライフスタイル、価値観、興味・関心、性格など。
- 行動変数(ビヘイビアル): 購買履歴、使用頻度、求めるベネフィット、ロイヤルティなど。
そして、絞り込んだターゲット顧客層を、よりリアルで具体的な人物像として描き出す「ペルソナ設定」を行います。ペルソナとは、ターゲットを代表する架空の人物モデルのことです。
【ペルソナ設定の項目例】
- 基本情報: 氏名、年齢、性別、居住地、職業、年収、家族構成
- パーソナリティ: 性格、価値観、口癖
- ライフスタイル: 1日の過ごし方、趣味、休日の過ごし方
- 情報収集行動: よく見るWebサイト、SNS、雑誌
- 悩みや課題: その人物が抱えている仕事上・私生活上の悩み
- ゴール: その人物が達成したい目標
ペルソナを詳細に設定する目的は、マーケティングに関わる全ての関係者が「〇〇さん(ペルソナ名)ならどう感じるか?」「〇〇さんには、この表現は響くか?」といった共通の目線で議論できるようにすることです。抽象的な「20代女性」ではなく、「カフェ巡りが趣味で、サステナビリティに関心が高い、都内在住28歳Webデザイナーの佐藤みさきさん」と考えることで、コミュニケーションの解像度が格段に上がり、より顧客の心に寄り添った施策を生み出すことができるようになります。
③ ステップ3:コミュニケーションの目標(KGI・KPI)を設定する
ターゲットとペルソナが明確になったら、そのターゲットに対してコミュニケーション活動を通じて「何を達成したいのか」というゴールを具体的に設定します。この目標設定は、活動の成果を評価し、改善を繰り返すための羅針盤となるため、極めて重要です。目標は、KGIとKPIの2つの階層で設定します。
- KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標):
- IMC戦略全体で最終的に目指す、ビジネス上のゴールです。
- 例:「半年間で、新規顧客の売上を前年比150%にする」「1年間で、ターゲット層におけるブランド第一想起率を10%から20%に引き上げる」
- KGIは、企業の経営目標と直結した、具体的で測定可能な数値目標であることが求められます。
- KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標):
- KGIを達成するための中間的な指標であり、各コミュニケーション施策のパフォーマンスを測るためのものです。
- KPIは、カスタマージャーニーの各段階(認知、興味・関心、比較・検討、購買、推奨など)に応じて設定します。
| カスタマージャーニー段階 | KPIの例 |
|---|---|
| 認知 | 広告表示回数、リーチ数、指名検索数、Webサイトへの新規セッション数 |
| 興味・関心 | 記事の読了率、動画の視聴完了率、サイト滞在時間、SNSのエンゲージメント率 |
| 比較・検討 | カタログダウンロード数、価格シミュレーション利用数、メールマガジン登録数 |
| 購買 | CVR(コンバージョン率)、購入単価、ROAS(広告費用対効果) |
| 推奨・ロイヤルティ | LTV(顧客生涯価値)、NPS®(顧客推奨度)、UGC(ユーザー生成コンテンツ)数 |
このように、KGIという山頂を目指すために、KPIという道標をいくつも設定するイメージです。各KPIをクリアしていくことで、最終的にKGIの達成に繋がるという論理的な関係性を構築することが重要です。また、目標設定の際には、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限(Time-bound)という「SMART」の原則を意識すると、より実効性の高い目標となります。
④ ステップ4:コミュニケーションプランを設計・実行する
目標が定まったら、いよいよそれを達成するための具体的なコミュニケーションプランを設計します。ここでは、「何を(What)」「どのように(How)」伝えるかを考えます。
- コアメッセージの開発(What):
- ターゲットの心に響き、自社の提供価値を端的に表現する、一貫した中核的なメッセージを開発します。このメッセージが、全てのコミュニケーション活動の背骨となります。
- 例:「〇〇で、あなたの毎日がもっと輝く」「未来のために、今選ぶテクノロジー」
- コミュニケーションミックスの設計(How):
- ターゲットの行動やメディア接触習慣を踏まえ、どのチャネル(メディア)を組み合わせてメッセージを届けるかを計画します。これを「コミュニケーションミックス」や「チャネルミックス」と呼びます。
- 広告、PR、SNS、オウンドメディア、イベントなど、多様なチャネルの中から、カスタマージャーニーの各段階で最も効果的なものを選択し、組み合わせます。
- 各チャネルの役割を明確にすることが重要です。「テレビCMは認知獲得、Webサイトは深い理解の促進、SNSはファンとの交流」といったように、役割分担を決めます。
- クリエイティブの制作:
- コアメッセージを、各チャネルの特性に合わせて最適な表現(コピー、デザイン、映像など)に落とし込みます。
- テレビCM、Webバナー広告、SNS投稿、記事コンテンツなど、具体的な制作物を準備します。ここでも、全てのクリエイティブでトーン&マナーを統一し、一貫したブランド体験を創出することを意識します。
- 実行計画(アクションプラン)の策定:
- 誰が、いつまでに、何をするのかを具体的に定めた実行計画を作成します。タイムライン(スケジュール表)や役割分担表を作成し、関係者全員で共有します。
計画が固まったら、いよいよ実行に移します。実行段階では、計画通りに進んでいるかを常にモニタリングし、予期せぬ事態に迅速に対応することが求められます。
⑤ ステップ5:効果測定を行い改善を繰り返す
コミュニケーションプランを実行したら、それで終わりではありません。IMCは一度実行して完結するものではなく、継続的な改善を繰り返すプロセスです。そのために不可欠なのが、実行した施策の効果測定と、その結果に基づく次のアクションの計画です。これは、いわゆる「PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)」を回すことに他なりません。
- 効果測定(Check):
- ステップ3で設定したKPIとKGIが、目標に対してどの程度達成できたかを測定します。
- Google Analyticsなどのアクセス解析ツール、SNSの分析ツール、CRMデータ、広告効果測定ツール、アンケート調査など、様々な手段を用いてデータを収集します。
- 収集したデータを分析し、「どの施策がうまくいったのか」「どこに課題があったのか」を明らかにします。例えば、「広告からのサイト流入は多かったが、直帰率が高かった。LPの構成に問題があるのではないか?」といった仮説を立てます。
- 改善(Action):
- 分析結果から得られた示唆をもとに、次の打ち手を考えます。
- 成功要因の横展開: うまくいった施策は、なぜ成功したのかを分析し、他の施策にもその要素を取り入れます。
- 課題の改善: うまくいかなかった施策は、その原因を特定し、改善策を立案します。クリエイティブを修正する、ターゲットを見直す、チャネルを変更するなど、具体的な改善アクションを決定します。
そして、この改善策を次の「Plan(計画)」に反映させ、再び「Do(実行)」→「Check(測定)」→「Action(改善)」というサイクルを回していきます。このPDCAサイクルを継続的に、そしてスピーディーに回し続けることが、IMC戦略を常に最適化し、成果を最大化させるための鍵となります。市場や顧客は常に変化しています。その変化に柔軟に対応し、進化し続けることこそが、現代のマーケティングに求められる姿勢なのです。
IMC戦略の立案に役立つフレームワーク
IMC戦略をゼロから構築するのは簡単なことではありません。しかし、先人たちが築き上げてきた思考の型、すなわち「フレームワーク」を活用することで、思考を整理し、抜け漏れなく戦略を立案することが可能になります。ここでは、IMC戦略の各フェーズで特に役立つ代表的な3つのフレームワークを紹介します。
顧客視点で考える「4C分析」
マーケティングの古典的なフレームワークに、企業視点の「4P分析」があります。これは、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)の4つの要素を企業側がどうコントロールするかを考えるものです。しかし、IMCの根底にあるのは徹底した顧客中心主義です。そこで重要になるのが、4Pを顧客視点から捉え直した「4C分析」です。
| 企業視点 (4P) | 内容 | 顧客視点 (4C) | 内容 |
|---|---|---|---|
| Product (製品) | 企業が提供する製品やサービスの機能・品質 | Customer Value (顧客価値) | 顧客がその製品・サービスから得られる価値や便益 |
| Price (価格) | 企業が設定する製品・サービスの価格 | Cost (顧客にとってのコスト) | 顧客が製品・サービスを得るために支払う金銭的・時間的・心理的コスト |
| Place (流通) | 製品・サービスを顧客に届ける場所や経路 | Convenience (利便性) | 顧客が製品・サービスを購入・利用する際の利便性やアクセスのしやすさ |
| Promotion (販促) | 広告や販売促進などのコミュニケーション活動 | Communication (コミュニケーション) | 企業と顧客との双方向の対話や関係性構築 |
【4C分析の活用方法】
IMC戦略を立案する際、常にこの4Cの視点に立ち返ることが重要です。
- Customer Value(顧客価値): 「我々の製品は高機能だ(Product)」と考えるのではなく、「この機能は、顧客のどのような課題を解決し、どんな喜びをもたらすのか(Customer Value)」を突き詰めて考えます。これが、全てのコミュニケーションの核となるメッセージの源泉になります。
- Cost(顧客にとってのコスト): 単に「価格が安い(Price)」と訴求するのではなく、「この製品を手に入れるために顧客が費やす時間や手間、心理的な負担も含めたトータルコストは、得られる価値に見合っているか(Cost)」を考えます。例えば、購入手続きが複雑であれば、それは顧客にとって大きなコストになります。
- Convenience(利便性): 「全国の店舗で販売している(Place)」だけでなく、「顧客が欲しいと思った時に、いつでも、どこでも、最も簡単な方法で手に入れられるか(Convenience)」を追求します。オンラインストアの使いやすさ、注文から配送までのスピード、多様な決済手段の提供などがこれにあたります。
- Communication(コミュニケーション): 企業からの一方的な情報発信(Promotion)ではなく、「顧客との対話を通じて信頼関係を築けているか(Communication)」を自問します。SNSでのコメントへの丁寧な返信や、アフターサポートの充実度などが、この視点での評価対象となります。
4C分析は、企業本位の独りよがりな戦略に陥ることを防ぎ、真に顧客に寄り添ったIMCを設計するための羅針盤となります。
購買行動モデル「AIDMA」「AISAS」
顧客が製品やサービスを認知してから購入に至るまでの心理的・行動的なプロセスをモデル化したものが「購買行動モデル」です。これを理解することで、カスタマージャーニーの各段階で、顧客がどのような状態にあり、どのようなコミュニケーションが有効かを設計するのに役立ちます。代表的なモデルが、前述した「AIDMA」と「AISAS」です。
| モデル | プロセス | 概要 |
|---|---|---|
| AIDMA (アイドマ) | Attention (注意) → Interest (関心) → Desire (欲求) → Memory (記憶) → Action (行動) | マスメディアが主体の時代の伝統的なモデル。 |
| AISAS (アイサス) | Attention (注意) → Interest (関心) → Search (検索) → Action (行動) → Share (共有) | インターネット普及後の現代的なモデル。検索と共有が特徴。 |
【購買行動モデルの活用方法】
自社のターゲット顧客の購買プロセスが、どちらのモデル(あるいはその亜種)に近いかを分析し、各段階に対応したコミュニケーションプランを設計します。
- AISASモデルをベースにしたIMCプランの例:
- Attention(注意)/ Interest(関心):
- 施策: テレビCM、Web動画広告、インフルエンサーマーケティング、SNS広告
- 目的: まずは知ってもらい、興味のきっかけを作る。感情に訴えかけるクリエイティブが有効。
- Search(検索):
- 施策: SEO(検索エンジン最適化)、リスティング広告、オウンドメディア(ブログ記事)、レビューサイト対策
- 目的: 検索したユーザーに対して、信頼できる詳細な情報を提供し、疑問や不安を解消する。競合製品との比較情報も有効。
- Action(行動):
- 施策: 使いやすいECサイト、LP(ランディングページ)の最適化、店舗での接客、送料無料キャンペーン
- 目的: 購入への最後の障壁を取り除き、スムーズな購買体験を提供する。
- Share(共有):
- 施策: SNSでのハッシュタグキャンペーン、レビュー投稿のインセンティブ、アンバサダープログラム
- 目的: ポジティブな口コミ(UGC)の創出を促し、それが次の顧客のAttention/Interestに繋がる好循環を生み出す。
- Attention(注意)/ Interest(関心):
このように、購買行動モデルをフレームワークとして使うことで、顧客の心理状態に合わせた、一貫性のあるコミュニケーションのシナリオを体系的に構築できます。
戦略プロセス全体を管理する「R-STP-MM-I-C」
「R-STP-MM-I-C」は、アメリカの経営学者フィリップ・コトラーが提唱したマーケティング・マネジメント・プロセスを、IMCの文脈で捉え直したフレームワークです。調査から管理まで、IMC戦略の立案・実行プロセス全体を網羅しており、自分が今どの段階にいるのかを見失わないための地図として機能します。
- R:Research(調査・分析)
- 戦略立案の最初のステップ。市場、顧客、競合、自社(3C分析など)の現状を調査・分析します。
- 前述の「IMC戦略の立て方」のステップ1に該当します。
- STP:Segmentation, Targeting, Positioning(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)
- 市場を細分化し(Segmentation)、狙うべき市場を定め(Targeting)、その市場における自社の独自の立ち位置を明確にします(Positioning)。
- ステップ2の「ターゲットとペルソナの明確化」と密接に関連します。ポジショニングは、「競合と比べて、自社はターゲット顧客にどのような独自の価値を提供できるか」を定義するプロセスです。
- MM:Marketing Mix(マーケティング・ミックス)
- STPで定めた戦略を具体化するための戦術、つまり4P(製品、価格、流通、販促)を組み合わせるプロセスです。
- IMCの文脈では、特にPromotion(販促)の部分を、4Cの視点でCommunicationとして捉え、広告、PR、SNSなどのコミュニケーション・ミックスを設計します。ステップ4の「コミュニケーションプランの設計」がこれにあたります。
- I:Implementation(実行)
- 計画したマーケティング・ミックスを、具体的なアクションプランに落とし込み、実行する段階です。
- ステップ4の「実行」部分に該当します。
- C:Control(管理・評価)
- 実行した活動の成果を測定・評価し、目標とのギャップを分析。その結果を次の計画にフィードバックするプロセスです。
- ステップ5の「効果測定と改善」に該当します。
この「R-STP-MM-I-C」は、IMC戦略が場当たり的な施策の寄せ集めになるのを防ぎ、調査から管理までの一貫した論理的な流れを担保する上で非常に有効なフレームワークです。戦略立案に行き詰まった時、このプロセスに立ち返ることで、思考を整理し、次の一手を見出す助けとなるでしょう。
IMC戦略を成功に導く3つのポイント
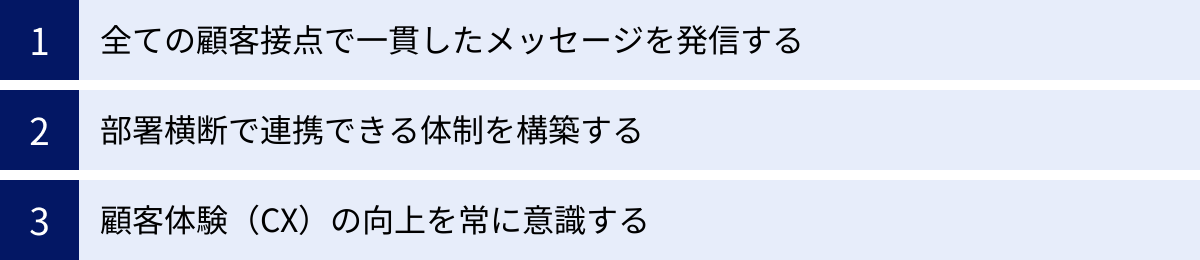
IMC戦略は、ただフレームワークに沿って計画を立てるだけで成功するものではありません。その戦略を組織に根付かせ、継続的に成果を生み出すためには、常に意識しておくべき重要な心構え、すなわち成功のポイントが存在します。ここでは、数々の企業の試行錯誤の中から見えてきた、特に重要な3つのポイントを解説します。
① 全ての顧客接点で一貫したメッセージを発信する
これはIMCの根幹をなす最も基本的な原則ですが、実践し続けることは意外と難しいものです。「一貫性」を保つためには、まず全社で共有されるべき「コアメッセージ」と「ブランドパーソナリティ」が明確に定義されている必要があります。
- コアメッセージ: ブランドが顧客に約束する中核的な価値を、簡潔で記憶に残りやすい言葉で表現したもの。例:「Just Do It.」(ナイキ)
- ブランドパーソナリティ: ブランドを擬人化した際の性格やトーン&マナー。例:「親しみやすい」「革新的」「信頼できる」「洗練されている」など。
これらが明確に定義されていなければ、担当者や部署によって解釈が異なり、発信するメッセージにブレが生じてしまいます。まずは、「我々は何者で、顧客に何を約束するのか」というブランドの根幹を、経営層も含めた関係者全員で徹底的に議論し、言語化することから始めましょう。
そして、そのコアメッセージとブランドパーソナリティを、全ての顧客接点(タッチポイント)で体現していく必要があります。
- 広告クリエイティブ: ビジュアルやコピーがブランドパーソナリティを反映しているか。
- Webサイト: デザインや文章のトーンが一貫しているか。
- SNS: 投稿内容やユーザーへの返信が、ブランドらしい言葉遣いになっているか。
- 店舗: 内装やBGM、スタッフの接客態度がブランドの世界観を伝えているか。
- 製品パッケージ: デザインがブランドイメージと合致しているか。
- コールセンター: オペレーターの応対が、ブランドの約束する姿勢(例:親身、迅速)を体現しているか。
重要なのは、チャネルごとに表現を最適化しつつも、根底に流れる思想や価値観は決してブラさないということです。例えば、TikTokでは若者向けのテンポの良い表現を使い、ビジネス向けのWebセミナーでは専門用語を交えた丁寧な解説をするかもしれません。しかし、どちらのチャネルでも、そのブランドならではの「革新性」や「顧客への誠実さ」といった核となるパーソナリティは一貫して感じられるべきです。
この一貫性を組織的に担保するために、「ブランドガイドライン」を作成し、全社員や外部パートナーに共有・浸透させることが非常に有効です。ガイドラインには、ロゴの使用ルールやカラースキームといった視覚的要素だけでなく、ブランドのミッション、ビジョン、バリュー、そしてコミュニケーションのトーン&マナーなどを明記します。これにより、誰もが同じ基準でブランドを表現できるようになり、一貫性の維持に大きく貢献します。
② 部署横断で連携できる体制を構築する
前述のデメリットでも触れた通り、組織の壁はIMC推進における最大の障壁です。したがって、意図的に部署の壁を壊し、横断的な連携を促進する「仕組み」と「文化」を構築することが、成功のための不可欠な条件となります。
【仕組みの構築】
- IMC推進責任者(CMOなど)の任命: IMC戦略全体に責任を持ち、各部門を統括するリーダーを明確にすることが第一歩です。この責任者が強力なリーダーシップを発揮し、部門間の利害を調整し、全社を同じ方向へと導きます。
- 部門横断チームの設置: 各部門から実務担当者を集めたタスクフォースや常設チームを組織します。このチームが、具体的なキャンペーンの企画・実行において、ハブとしての役割を果たします。
- 定例会議の開催: 週次や月次で関係部署が集まる定例会議を設定し、進捗、成果、課題、そして各部署で得られた顧客からのインサイトなどを共有します。この場が、形式的な報告会ではなく、活発な議論と新たなアイデア創出の場となるようなファシリテーションが重要です。
- 共通の目標(KGI/KPI)と評価制度: 部署ごとの個別KPIだけでなく、IMC戦略全体の成功に連動した共通の目標を設定し、それを各部署の評価に組み込むことで、協力体制へのインセンティブが働きます。
【文化の醸成】
仕組みを作るだけでは、人は動きません。連携を当たり前とする文化を育むことも同様に重要です。
- トップからの継続的なメッセージ発信: 経営トップが、朝礼や社内報などあらゆる機会を通じて、なぜIMCが重要なのか、なぜ部門連携が必要なのかを繰り返し語りかけ、その重要性を全社に浸透させます。
- 成功体験の共有: 部門連携によって生まれた成功事例を、社内で積極的に共有し、称賛します。「あの部署と協力したら、こんなに良い結果が出た」という事実が、次の連携へのモチベーションとなります。
- 非公式なコミュニケーションの促進: 社内SNSやランチ会、シャッフルミーティングなど、部署の垣根を越えた偶発的なコミュニケーションが生まれる機会を設けることも、心理的な壁を取り払う上で有効です。
部署横断の連携体制は一朝一夕には築けません。トップの強い意志のもと、仕組みと文化の両面から、粘り強く改革を進めていく姿勢が求められます。
③ 顧客体験(CX)の向上を常に意識する
IMCは、単に統一されたメッセージを発信するだけの活動ではありません。その最終的な目的は、顧客との良好な関係を築き、ブランドのファンになってもらうことにあります。そのためには、コミュニケーションの受け手である顧客が、ブランドとの全ての関わりの中で何を感じ、どう思うか、すなわち「顧客体験(CX:Customer Experience)」を常に中心に据えて思考する必要があります。
顧客体験は、広告を見てブランドを認知する瞬間から始まり、Webサイトでの情報収集、店舗での購買、製品の使用、アフターサポート、そして次の購買へと続く、一連の長い旅(カスタマージャーニー)全体を指します。IMCを成功させるには、この旅の全てのタッチポイントで、顧客にポジティブで価値のある体験を提供し続けることが不可欠です。
【CX向上のための視点】
- シームレスな体験: 顧客がオンラインとオフラインを行き来する際に、情報や体験が途切れないように設計します。「Webサイトでチェックした商品の在庫が、最寄りの店舗ですぐに確認できる」「店舗で受けたカウンセリングの履歴が、オンラインのマイページでも見られる」といった、チャネル間のスムーズな連携が求められます。
- パーソナライゼーション: 全員に同じメッセージを送るのではなく、顧客一人ひとりの興味関心や行動履歴に合わせて、最適な情報や提案を行います。データ活用がその鍵となりますが、単なるデータ分析に留まらず、「この顧客は、今何を求めているだろうか」と想像力を働かせることが重要です。
- 感情への配慮: 顧客体験は、機能的な利便性だけで決まるものではありません。むしろ、「ワクワクした」「安心した」「感動した」「自分のことを分かってくれた」といった感情的な要素が、顧客ロイヤルティに大きな影響を与えます。全てのコミュニケーションにおいて、顧客の感情に寄り添う姿勢が大切です。
- 顧客の声の傾聴と反映: アンケート、レビュー、SNSのコメント、コールセンターへの問い合わせなど、あらゆるチャネルから寄せられる「顧客の声(VoC:Voice of Customer)」を真摯に受け止め、それをサービスやコミュニケーションの改善に活かす仕組みを構築します。顧客を、共にブランドを創り上げていくパートナーと捉える姿勢が、CXを継続的に向上させる原動力となります。
IMC戦略をレビューする際には、常に「この施策は、顧客体験の向上に貢献しているか?」「カスタマージャーニーのどこかで、顧客にストレスや不満を与えていないか?」と自問自答する習慣を持つことが、真に顧客から愛されるブランドを築くための鍵となるのです。
IMC戦略の企業成功事例7選
ここでは、IMC戦略を巧みに実践し、強力なブランドを築き上げている企業の事例を7つ紹介します。これらの事例は、特定のキャンペーンの成功だけでなく、企業活動全体を通じて一貫したメッセージと価値観を伝え続けている点が特徴です。
※以下に記載する情報は、各社の公開情報や信頼性の高い報道に基づきますが、戦略は常に変化するものであることをご了承ください。
① 無印良品
無印良品は、IMCのお手本ともいえる企業です。「これがいい、ではなく『これでいい』」という独自の思想を、あらゆる顧客接点で体現しています。
- コアメッセージ: 華美な装飾を排し、本当に必要なものを、本当に必要なかたちでつくるという「素」の思想。
- コミュニケーション:
- 広告: 派手な広告宣伝は行わず、製品そのものが持つ魅力を静かに伝える。
- 店舗: シンプルで統一された空間デザイン、見やすい陳列、丁寧な商品説明POPなど、店舗全体がブランドの世界観を表現するメディアとなっている。
- 製品: ロゴを目立たせないシンプルなデザイン、長く使える品質、環境に配慮した素材選びなど、製品自体が最も強力なコミュニケーションツール。
- Web/アプリ: 「MUJI passport」アプリを通じて顧客と繋がり、商品情報だけでなく、「くらしのヒント」といったライフスタイル提案型のコンテンツを発信。
- イベント: 地域の生産者と連携したマルシェや、専門家を招いたワークショップなど、顧客の暮らしに寄り添う活動を展開。
広告に頼らずとも、製品、店舗、Web、イベントといった全てのタッチポイントで「無印良品らしさ」という一貫した体験を提供することで、熱狂的なファンを世界中に生み出しています。(参照:株式会社良品計画 公式サイト)
② ナイキ
ナイキは「Just Do It.」という、世界で最も有名なブランドスローガンの一つを核に、力強いIMCを展開しています。
- コアメッセージ: すべての人の内なるアスリート魂を刺激し、行動を促す。
- コミュニケーション:
- 広告: トップアスリートを起用し、彼らの挑戦や勝利のストーリーを通じて、感動とインスピレーションを与える。近年では、社会的なメッセージ性の強いキャンペーンも展開し、ブランドの姿勢を明確に示している。
- デジタルプラットフォーム: ランニングアプリ「Nike Run Club (NRC)」やトレーニングアプリ「Nike Training Club (NTC)」を提供。単にシューズを売るのではなく、ユーザーのランニングやトレーニングといった「体験」そのものをサポートすることで、日常生活に深く入り込み、ブランドとの強い絆を構築している。
- SNS: 各プラットフォームの特性に合わせ、新作情報の発信だけでなく、ユーザーとのインタラクティブなコミュニケーションや、アスリートの生の声を届ける場として活用。
- イベント: 「Nike+ Run Club」などのコミュニティ活動を通じて、ランナー同士が繋がる場を提供。
製品、広告、デジタルサービス、コミュニティ活動が一体となり、「Just Do It.」というメッセージを多角的に補強し、スポーツをするすべての人にとって不可欠なブランドとしての地位を確立しています。(参照:NIKE, Inc. 公式サイト)
③ レッドブル
レッドブルは「製品を売るな、体験を売れ」というマーケティング哲学を体現する企業です。「レッドブル、翼をさずける。」のキャッチコピーのもと、エナジードリンクそのものではなく、それがもたらす「興奮」や「挑戦」といった世界観を売っています。
- コアメッセージ: 限界への挑戦をサポートし、人々に翼をさずける。
- コミュニケーション:
- コンテンツマーケティング: 自社で「レッドブル・メディアハウス」というメディア企業を持ち、エクストリームスポーツ、音楽、eスポーツなど、様々なカルチャーに関する高品質な映像や記事を制作・配信。もはや飲料メーカーではなく、メディアカンパニーとしての側面が強い。
- イベント/アスリート支援: 「Red Bull Air Race」のような大規模なスポーツイベントを自ら主催するほか、世界中の独創的なアスリートやアーティストをサポート。彼らの活動を通じて、ブランドの「挑戦」のイメージを体現する。
- サンプリング: ブランドのターゲット層が集まるイベント会場などで、製品を無料配布。製品体験を通じて、ブランドの世界観を直接伝える。
従来の広告手法に頼らず、人々が熱狂するカルチャーそのものを創り出し、支援することで、ブランドがそのカルチャーの中心的存在となる。このユニークなIMC戦略が、レッドブルを唯一無二のブランドにしています。(参照:Red Bull Japan 公式サイト)
④ 日本コカ・コーラ
日本コカ・コーラは、季節性やイベントを捉えた巧みなIMCで知られています。「Coke ON」アプリの活用も特徴的です。
- コアメッセージ: 人々が集う、楽しくハッピーな瞬間に寄り添う。
- コミュニケーション:
- 季節キャンペーン: 夏の「Coke MIX」、冬の「リボンボトル」など、季節ごとのテーマを設定し、テレビCM、店頭プロモーション、SNSキャンペーンを全国で一斉に展開。
- 製品のメディア化: 自分の名前やメッセージを入れられる「ネームボトル」のように、製品パッケージ自体をパーソナライズされたコミュニケーションツールとして活用し、SNSでの共有(UGC)を促進。
- Coke ONアプリ: 対応自販機でスタンプを貯めるとドリンクがもらえるだけでなく、歩くだけでスタンプが貯まる「Coke ONウォーク」機能など、顧客の日常に溶け込み、継続的な接点を生み出すプラットフォームとなっている。
- 音楽/スポーツ連携: アーティストとのタイアップソングや、オリンピック・FIFAワールドカップのパートナーシップなど、人々が情熱を注ぐコンテンツとブランドを結びつける。
マス広告からデジタル、店頭まで、全てのチャネルが連動し、年間を通じて「コカ・コーラのあるハッピーなシーン」を創出し続けることで、国民的飲料としての地位を盤石なものにしています。(参照:日本コカ・コーラ株式会社 公式サイト)
⑤ 今治タオル
今治タオルは、地域ブランドの再生におけるIMCの金字塔ともいえる事例です。クリエイティブディレクター佐藤可士和氏によるブランディングが有名です。
- コアメッセージ: 安心・安全・高品質なジャパンクオリティの象徴。
- コミュニケーション:
- 品質基準の可視化: 「5秒ルール(タオル片を水に浮かべ、5秒以内に沈み始める)」という独自の品質基準を設定。この分かりやすい基準が、品質保証の強力なメッセージとなった。
- 統一されたビジュアルアイデンティティ: 白・赤・青のトリコロールカラーを用いたロゴマークを開発。このマークを全ての製品に付けることを義務化し、一目で今治タオルと分かるようにした。
- PR戦略: ロゴマークに込めた想いや「5秒ルール」の背景にあるストーリーをメディアに積極的に発信し、共感を獲得。
- 販路の統一感: 百貨店や直営店での展開において、ロゴを活かした統一感のある売り場づくりを徹底。パッケージデザインも統一し、ギフトとしての価値を高めた。
品質という本質的な価値を、ロゴという強力なシンボルに集約させ、それをあらゆるタッチポイントで一貫して訴求することで、「高級タオルの代名詞」という圧倒的なブランドポジションを短期間で確立しました。(参照:今治タオル工業組合 公式サイト)
⑥ 資生堂
150年以上の歴史を持つ資生堂は、伝統と革新を融合させたIMCを展開しています。長年培ってきた顧客との絆を、デジタル技術でさらに深化させています。
- コアメッセージ: 美の力を通じて、人々を幸せにし、サステナブルな社会を実現する。
- コミュニケーション:
- オフライン(店頭): 百貨店のカウンターに常駐する美容部員(ビューティーコンサルタント)による、対面での丁寧なカウンセリングが最大の強み。顧客一人ひとりの肌の悩みに寄り添う体験が、深い信頼関係を築いてきた。
- オンライン(Web/アプリ): 総合美容サイト「ワタシプラス」を運営。オンラインでの商品購入はもちろん、美容部員によるオンラインカウンセリングや、AIによる肌診断など、デジタルを活用したパーソナルなサービスを提供。
- データ連携: 店頭でのカウンセリング履歴と、Webサイトでの購買・閲覧履歴といったデータを統合。オンラインとオフラインを横断した、シームレスで一人ひとりに最適化された顧客体験(CX)の実現を目指している。
- 広告/PR: 各ブランド(例:「SHISEIDO」「クレ・ド・ポー ボーテ」)の世界観を表現する洗練された広告を展開する一方、サステナビリティ活動やダイバーシティ&インクルージョンに関する企業姿勢も積極的に発信。
伝統的な強みである「人によるおもてなし」と、最先端の「デジタル技術」を掛け合わせ、OMO(Online Merges with Offline)型のIMCを推進することで、時代の変化に対応し続けています。(参照:株式会社資生堂 企業情報サイト)
⑦ ANA(全日本空輸)
ANAは、「安全」という航空会社の根源的な価値を基盤に、高品質なサービスと「おもてなし」の心を伝えるIMCを展開しています。
- コアメッセージ: あんしん、あったか、あかるく元気!
- コミュニケーション:
- 広告: 有名人やアスリートを起用し、旅のワクワク感や、世界と日本を繋ぐ役割をエモーショナルに描くテレビCMを展開。
- 従業員の行動: 空港のグランドスタッフから客室乗務員、整備士に至るまで、全ての従業員が「あんしん、あったか、あかるく元気!」というグループ行動指針を共有。その一貫した立ち居振る舞い自体が、最も強力なブランドコミュニケーションとなっている。
- デジタルチャネル: 使いやすいWebサイトやアプリでの予約・搭乗手続きはもちろん、SNSでは就航地の魅力や航空機の豆知識などを発信し、旅への期待感を醸成。
- マイレージクラブ: 「ANAマイレージクラブ」という強力なロイヤルティプログラムを通じて、顧客との長期的な関係を構築。フライトだけでなく、提携店での買い物など、日常生活の様々なシーンでマイルが貯まる仕組みを提供し、ブランドへのエンゲージメントを高めている。
- 機内サービス: 機内食や機内エンターテイメント、機内誌「翼の王国」など、機内での体験一つひとつにこだわり、ANAならではの品質と「おもてなし」を伝える。
広告から現場の従業員の行動、ロイヤルティプログラムまで、全ての接点が一貫して「信頼」と「心地よさ」を感じさせるものとなっており、顧客の高いロイヤルティに繋がっています。(参照:ANAホールディングス株式会社 公式サイト)
まとめ
本記事では、IMC(統合型マーケティングコミュニケーション)について、その基本概念から重要視される背景、メリット・デメリット、戦略の立て方、そして企業の成功事例までを網羅的に解説してきました。
現代のマーケティング環境は、消費者の購買行動が複雑化し、メディアが多様化する中で、従来のサイロ化されたアプローチでは立ち行かなくなっています。このような時代において、広告、PR、SNS、店舗など、あらゆる顧客接点(タッチポイント)を一つの戦略の下に統合し、一貫したブランド体験を届けるIMCは、もはや特別な手法ではなく、企業の持続的な成長に不可欠な経営戦略となっています。
IMCを導入することで、企業は以下のような大きなメリットを得られます。
- 顧客との良好で長期的な関係を構築できる
- 市場において、ブレのない強力なブランドイメージを確立できる
- 各施策の相乗効果により、マーケティングコストを最適化できる
一方で、その実践には「部門間の連携」や「施策全体の効果測定」といった、組織的・技術的なハードルが伴うことも事実です。
しかし、これらの課題を乗り越え、IMCを成功に導くためのポイントは明確です。
- 全ての顧客接点で一貫したメッセージを発信すること
- 部署の壁を越えて連携できる体制を構築すること
- 常に顧客体験(CX)の向上を意識すること
IMC戦略の立案は、まず自社が置かれている環境を冷静に分析することから始まります。そして、「誰に」「何を」「どのように」伝えるのかを明確にし、具体的な目標(KGI/KPI)を設定した上で、計画を実行し、その結果を測定して改善を繰り返す(PDCA)という地道なプロセスが求められます。
今回ご紹介した企業の成功事例からも分かるように、成功している企業は例外なく、顧客を深く理解し、自社のコアとなる価値を、あらゆる活動を通じて粘り強く、そして一貫して伝え続けています。
自社のマーケティング活動に課題を感じているのであれば、まずはこの記事で解説したIMCの考え方を取り入れ、自社のコミュニケーションの現状を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。小さな一歩からでも、顧客との新しい関係性を築くための道は開けるはずです。