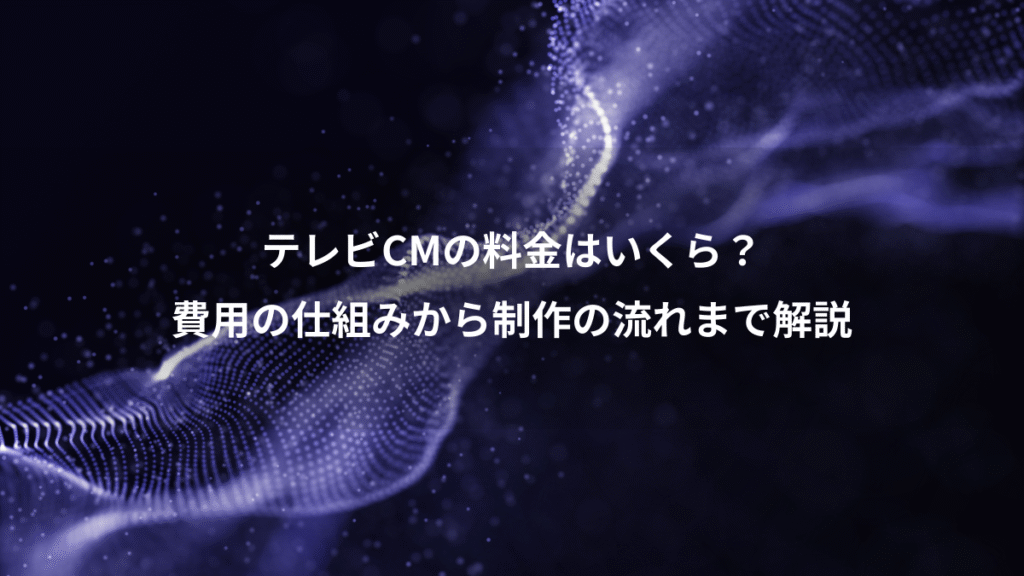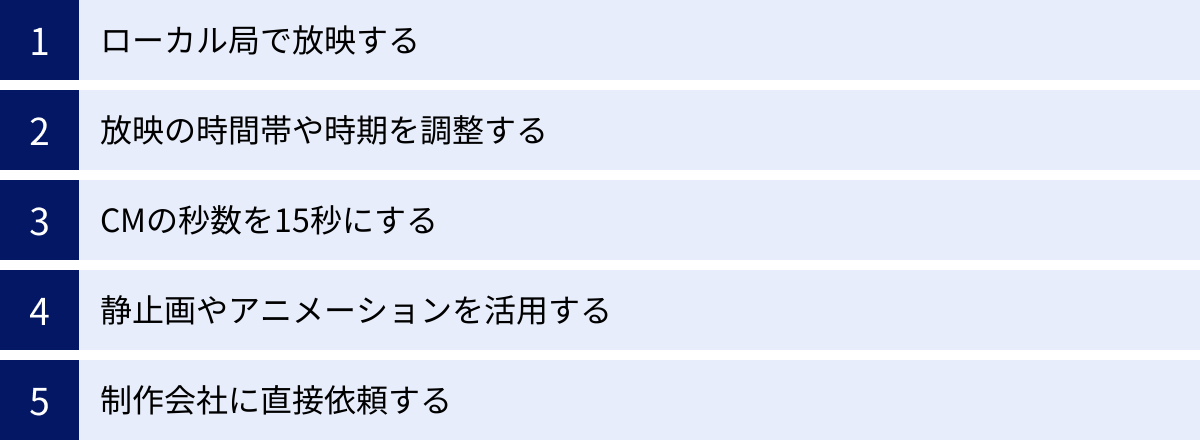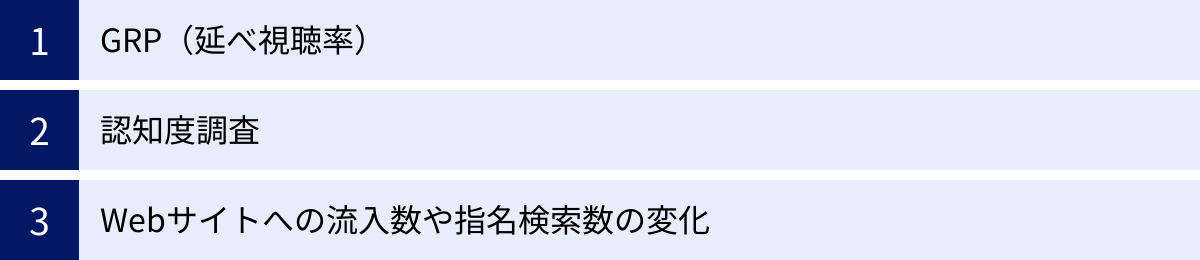テレビCMは、企業のブランド認知度を飛躍的に高め、多くの人々に商品やサービスを知らせるための強力なマーケティング手法です。しかし、その一方で「費用がどのくらいかかるのか想像もつかない」「料金体系が複雑で分かりにくい」といった声をよく耳にします。
この記事では、テレビCMの出稿を検討している企業の担当者様に向けて、CMにかかる費用の全体像から、その内訳である「放映費」と「制作費」の仕組み、料金相場、そして費用を抑えるための具体的な方法まで、網羅的に解説します。
さらに、CMを放映するまでの流れや、メリット・デメリット、効果測定の指標についても詳しく説明します。この記事を読めば、テレビCMの費用に関する疑問が解消され、自社のマーケティング戦略にCMを組み込むべきかどうかの具体的な判断材料を得られるでしょう。
目次
テレビCMにかかる費用の全体像
テレビCMの出稿を考える際、最初に把握しておくべきなのが、費用の全体構造です。テレビCMにかかる費用は、大きく分けて「放映費」と「制作費」の2つから構成されています。これらは全く性質の異なる費用であり、それぞれに独自の料金決定メカニズムが存在します。
まず「放映費」とは、制作したCMをテレビ局の電波に乗せて視聴者に届けるための費用、いわば「広告枠」の購入費用です。一方、「制作費」は、CM映像そのものを作り上げるために必要な費用を指します。
重要なのは、この2つの費用を合算したものが、テレビCMの総額になるという点です。 例えば、非常に低コストでCM映像を制作できたとしても、全国ネットのゴールデンタイムに放映すれば放映費は莫大になります。逆に、豪華なタレントを起用して高額な制作費をかけたCMでも、地方の深夜帯に数回放映するだけなら、放映費は比較的安価に収まります。
したがって、テレビCMの予算を計画する際は、放映と制作の両面から費用を検討し、自社の目的やターゲット、そして予算規模に応じて最適なバランスを見つけることが不可欠です。
費用の内訳は「放映費」と「制作費」の2種類
テレビCMの総費用を理解するためには、まず「放映費」と「制作費」という2つの構成要素を正確に理解する必要があります。
放映費:CMをテレビで流すための費用
放映費は、テレビ局に対して支払う「広告枠の料金」です。この費用は、CMがどれだけ多くの人々に見られる可能性があるかによって大きく変動します。具体的には、どのテレビ局で流すか(全国ネットのキー局か、特定の地域のローカル局か)、どの時間帯に流すか(視聴率の高いプライムタイムか、深夜か)、どのくらいの期間・回数流すか、といった要素で決まります。
放映費には、特定の番組のスポンサーとしてCMを流す「タイムCM」と、番組を指定せず時間帯や期間を指定してCMを流す「スポットCM」の2種類があり、それぞれ料金体系や特徴が異なります。一般的に、テレビCMの総費用の大部分を占めるのがこの放映費であり、数百万円から数億円規模にまでなることも珍しくありません。
制作費:CM映像を作るための費用
制作費は、CMの映像コンテンツそのものを制作するためにかかる費用全般を指します。これには、企画の立案や絵コンテの作成といったプランニング費用から、監督やカメラマンなどのスタッフ人件費、スタジオやロケ地の使用料、撮影機材のレンタル費、映像編集やCG加工の費用、ナレーションやBGMの費用まで、多岐にわたる項目が含まれます。
制作費の金額を大きく左右する最大の要因は、企画内容の複雑さと、出演者(タレント)や使用する楽曲です。例えば、実写撮影ではなくCGやアニメーションで構成したり、有名なタレントではなく一般のモデルを起用したり、オリジナルの楽曲ではなくフリー素材を使用したりすることで、制作費を大幅に抑えることが可能です。制作費の相場は、シンプルな構成であれば数十万円から可能ですが、有名なタレントを起用し、海外ロケなどを行う大規模なものになると、1億円を超えるケースもあります。
このように、テレビCMの費用は「どこで、いつ、どれだけ流すか(放映費)」と「どのような内容のCMを作るか(制作費)」という2つの軸で決まることを、まずは念頭に置いておきましょう。
テレビCMの料金相場
テレビCMの料金相場は、前述の通り放映費と制作費の組み合わせによって決まるため、一概に「いくら」と言うことは非常に困難です。その範囲は最低ラインの数十万円から、大規模なキャンペーンでは数億円以上にまで及びます。
ここでは、いくつかのパターンに分けて大まかな料金相場のイメージを掴んでみましょう。
| 項目 | 概要 | 放映費の相場 | 制作費の相場 | 合計費用の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 全国規模のキャンペーン | キー局のプライムタイムを中心に、全国で大規模に放映。有名タレントを起用。 | 1億円〜 | 3,000万円〜1億円以上 | 1億3,000万円〜 |
| 準キー局エリアでの展開 | 関西や中京エリアなど、特定の広域圏で集中的に放映。 | 2,000万円〜5,000万円 | 1,000万円〜3,000万円 | 3,000万円〜 |
| ローカル局でのテストマーケティング | 特定の都道府県のローカル局で、時間帯を絞って放映。制作もシンプルに。 | 100万円〜500万円 | 50万円〜500万円 | 150万円〜 |
| 最低限の出稿(地方局・深夜) | 地方のローカル局で、深夜帯などに短期間・少数回放映。静止画やアニメーションで制作。 | 30万円〜 | 30万円〜100万円 | 60万円〜 |
※上記はあくまで目安であり、実際の料金は放送局、時期、制作内容によって大きく変動します。
表からも分かる通り、テレビCMの費用はまさにピンキリです。重要なのは、自社のマーケティング目的(新商品の全国的な認知度向上、特定エリアでの店舗集客、企業のブランディングなど)を明確にし、その目的を達成するために最適な予算配分を考えることです。
例えば、全国展開を目指す新商品のローンチであれば、キー局での大規模な放映が必要となり、相応の予算が求められます。一方で、特定の都市圏でサービスを展開する企業であれば、その地域のローGカル局に絞って出稿することで、費用を抑えつつ効果的なアプローチが可能です。
次の章からは、「放映費」と「制作費」それぞれについて、その仕組みや料金を決定する要素をさらに詳しく掘り下げていきます。
テレビCMの「放映費」を徹底解説
テレビCMの総費用の中でも、特に大きな割合を占めるのが「放映費」です。放映費とは、完成したCM素材をテレビの電波に乗せて視聴者の家庭に届けるための、いわば「場所代」や「掲載料」に相当します。この放映費の仕組みを理解することが、効果的かつ効率的なCM出稿戦略を立てる上で極めて重要になります。
放映費は単純な一本あたりの価格ではなく、様々な要素が複雑に絡み合って決定されます。ここでは、放映費の基本的な仕組みから相場、そして価格を決定づける具体的な要素について、詳細に解説していきます。
放映費の仕組みと相場
テレビCMの放映費は、基本的に「CMの価値」によって決まります。その価値とは、「どれだけ多くの、そしてどのようなターゲット層の視聴者に見られる可能性があるか」という点に集約されます。視聴率が高い番組や時間帯ほど、より多くの人々にリーチできるため、広告媒体としての価値が高まり、結果として放映費も高額になります。
放映費の算出には、主に「パーコスト」という考え方が用いられます。これは、視聴率1%あたりのCM放映にかかるコストを示す指標です。例えば、ある時間帯のパーコストが1万円だとすると、視聴率10%の番組で15秒CMを1本流すのにかかる費用は「1万円 × 10% = 10万円」と計算されます。このパーコストは、放送局や時間帯、CMの種類によって変動します。
放映費の相場は、前述の通り非常に幅広く、地方のローカル局で深夜帯に数本流すのであれば数十万円程度から可能な一方、東京のキー局でゴールデンタイムに全国ネットで放映するとなると、15秒CM1本あたり100万円を超えることも珍しくありません。大規模なキャンペーンでは、放映費だけで数億円に達することもあります。
放映費を決める4つの要素
放映費は、主に以下の4つの要素の組み合わせによって決まります。これらの要素を理解することで、自社の予算と目的に合わせて、どのような出稿戦略を取るべきかが見えてきます。
放送局(キー局・準キー局・ローカル局)
CMを放映する放送局の種類は、放映費に最も大きな影響を与える要素の一つです。放送局は、その放送エリアの広さによって大きく3つに分類されます。
| 放送局の種類 | 放送エリア | 特徴 | 放映費の目安 |
|---|---|---|---|
| キー局 | 関東広域圏(全国ネットワークの中心) | 日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京の5局。全国に番組を配信しており、最もリーチが広い。 | 最も高額 |
| 準キー局 | 近畿広域圏、中京広域圏など | 毎日放送、朝日放送テレビ(近畿)、中京テレビ、東海テレビ(中京)など。キー局に次ぐ広いエリアをカバー。 | 高額 |
| ローカル局 | 各都道府県 | 特定の都道府県のみを放送エリアとする。地域に密着した情報を発信。 | 比較的安価 |
当然ながら、放送エリアが広く、視聴可能人口が多いキー局が最も放映費が高く、ローカル局が最も安価になります。全国的なブランディングや新商品発売の告知など、日本全国の幅広い層にアプローチしたい場合はキー局への出稿が効果的ですが、莫大な予算が必要です。一方、店舗ビジネスなど特定の地域に根ざした事業の場合、そのエリアのローカル局に出稿することで、費用を抑えながらターゲットに効率よくアプローチできます。
CMの種類(タイムCM・スポットCM)
CMの放映形態には、大きく分けて「タイムCM」と「スポットCM」の2種類があり、どちらを選ぶかによって料金体系や特性が大きく異なります。
- タイムCM: 特定の番組のスポンサーとして、その番組の放送時間内にCMを放映する形態です。番組とセットで契約するため、長期間(通常は2クール=6ヶ月以上)の契約が基本となります。
- スポットCM: 番組を指定せず、「平日の朝の時間帯」「週末のゴールデンタイム」といった形で、大まかな時間帯と期間、そして目標とする視聴率(GRP)を指定してCMを放映する形態です。
一般的に、タイムCMは特定の番組の視聴者層に深くアプローチできるためブランディングに適しており、スポットCMは柔軟な予算設定で幅広い層にリーチできるため認知度向上に適しています。 料金面では、タイムCMの方が契約期間が長い分、総額は高くなる傾向がありますが、スポットCMはセールス期間などを狙って集中的に投下することも可能です。これらの詳細なメリット・デメリットは後ほど詳しく解説します。
CMの秒数(15秒・30秒)
テレビCMで最も一般的な秒数は15秒です。その他にも30秒、60秒、あるいはそれ以上の長尺CMも存在します。当然ながら、CMの秒数が長くなるほど、放映費は高くなります。
一般的に、30秒CMの放映費は15秒CMの2倍、60秒CMは15秒CMの4倍といったように、秒数に比例して高くなるのが基本です。しかし、放送局や時間帯によっては、30秒CMの方が15秒CMよりも単価が割安に設定されている「30秒 ưu遇」といったケースも存在します。
多くの情報を伝えたい、あるいはブランドストーリーをじっくりと見せたい場合は30秒以上のCMが効果的ですが、予算を抑えたい場合や、特定のメッセージを繰り返し刷り込みたい場合は15秒CMが適しています。
放映する時間帯や曜日
「いつCMを流すか」も、放映費を大きく左右する重要な要素です。テレビの視聴率は、時間帯や曜日によって大きく変動するためです。多くの人がテレビを視聴している時間帯ほど、広告価値が高まり、放映費も高騰します。
テレビ業界では、時間帯を以下のように区分しています。
- プライムタイム(19時~23時): 一日で最も視聴率が高い時間帯。家族層や若者層など、幅広い視聴者がテレビを見ている。放映費は最も高額。
- ゴールデンタイム(19時~22時): プライムタイムの中でも特に視聴率が高いコアな時間帯。
- Aタイム(7時~9時、12時~14時、17時~19時など): 主婦層や高齢者層の視聴が多い時間帯。プライムタイムに次いで放映費が高い。
- Bタイム、Cタイム(上記以外の時間帯、深夜など): 視聴率が比較的低い時間帯。放映費は安価。
新商品の認知度を一気に高めたい場合はプライムタイムへの出稿が効果的ですが、特定のターゲット層(例:主婦層)に絞ってアプローチしたい場合はAタイムを狙う、あるいは予算を抑えて放映回数を増やしたい場合はB・Cタイムを活用するなど、目的に応じた時間帯の選択がコストパフォーマンスを高める鍵となります。
タイムCMとは
タイムCMとは、特定のテレビ番組の提供スポンサーとして、その番組内で放送されるCMのことです。「この番組は、ご覧のスポンサーの提供でお送りします」というアナウンスと共に企業名が表示されるのが特徴です。
契約は通常、2クール(6ヶ月)単位が基本となり、長期間にわたって同じ番組でCMを放映し続けることになります。これにより、番組の視聴者に対して継続的にアプローチすることが可能です。
タイムCMのメリット
- ① ターゲット層への的確なアプローチ: 番組には特定の視聴者層(例:アニメなら若年層、報道番組なら中高年層、ドラマなら女性層など)がいます。自社の商品やサービスのターゲットと合致する番組を選ぶことで、非常に効率的にメッセージを届けられます。
- ② 高いブランディング効果: 特定の番組を長期間サポートすることで、「〇〇(番組名)の会社」というイメージが定着し、企業の信頼性や好感度、ブランドイメージの向上に繋がります。番組内容と企業イメージが合致すれば、その相乗効果は絶大です。
- ③ 安定した視聴率の確保: スポットCMと違い、番組の放送時間内に確実にCMが流れるため、安定した視聴環境が保証されます。人気番組であれば、高い視聴率が期待できます。
タイムCMのデメリット
- ① 費用が高額になりやすい: 最低契約期間が長いため、総額の放映費はスポットCMに比べて高額になる傾向があります。また、人気番組のスポンサー枠は競争が激しく、料金も高騰します。
- ② 柔軟な出稿調整が難しい: 一度契約すると、期間中の放映中止や内容の変更が困難です。市場の変化に合わせた柔軟な広告展開には向きません。
- ③ 番組の不祥事リスク: 万が一、提供している番組が低視聴率に陥ったり、出演者が不祥事を起こしたりした場合、企業のイメージまで損なわれるリスクがあります。
スポットCMとは
スポットCMとは、番組を指定せず、放送局が定めた時間帯のCM枠を購入して放送するCMのことです。「Aタイムに50本」「1週間で100GRP分」といった形で、期間や量(GRP)を目標に発注します。
タイムCMのように特定の番組と紐づかないため、様々な番組の間でランダムに放送されます。契約期間の自由度が高く、1週間といった短期間からでも出稿が可能です。
スポットCMのメリット
- ① 柔軟な予算設定と短期集中出稿: 最低出稿金額が比較的低く、予算に応じて柔軟に出稿量を調整できます。 新商品の発売キャンペーンやセール告知など、特定の期間に集中的にCMを投下したい場合に非常に有効です。
- ② 幅広い層へのリーチ: 様々な番組の間で放送されるため、特定の視聴者層に偏らず、より多くの不特定多数の人々にアプローチできます。サービスの認知度を一気に高めたい場合に適しています。
- ③ 低コストでの出稿が可能: タイムCMに比べて単価が安く、少ない予算から始められるため、テレビCMのテストマーケティングとしても活用しやすいのが特徴です。
スポットCMのデメリット
- ① ターゲットの絞り込みが困難: どの番組で放送されるか指定できないため、自社のターゲット層と無関係な視聴者にもCMが届いてしまい、広告効率が低下する可能性があります。
- ② ブランディング効果は限定的: タイムCMのように特定の番組イメージと連動することがないため、企業やブランドのイメージ向上に繋げにくい側面があります。
- ③ 視聴環境が不安定: 放送時間が固定されていないため、視聴者のザッピング(チャンネルを頻繁に変える行為)の対象になりやすく、確実に見てもらえる保証はありません。
| 比較項目 | タイムCM | スポットCM |
|---|---|---|
| 目的 | ブランディング、ターゲット訴求 | 認知度向上、キャンペーン告知 |
| 契約期間 | 長期(2クール〜が基本) | 短期(1週間〜)から可能 |
| 費用 | 総額は高額になりやすい | 比較的安価から始められる |
| 柔軟性 | 低い(途中変更が困難) | 高い(予算や時期を調整しやすい) |
| ターゲット精度 | 高い(番組視聴者層に依存) | 低い(幅広い層にリーチ) |
| ブランディング効果 | 高い | 限定的 |
テレビCMの「制作費」を徹底解説
テレビCMの費用を構成するもう一つの大きな要素が「制作費」です。これは、15秒や30秒の映像作品をゼロから作り上げるために必要なすべてのコストを指します。放映費が「広告枠」の費用であるのに対し、制作費は「広告物そのもの」の費用と言えます。
制作費は、企画内容やクオリティによって大きく変動するため、放映費以上に相場を掴むのが難しい部分です。シンプルなものでは数十万円から可能ですが、有名タレントの起用や大規模なロケ、高度なCGなどを駆使すれば、数千万円から1億円を超えることもあります。ここでは、制作費の仕組みと相場、そしてその具体的な内訳について詳しく解説します。
制作費の仕組みと相場
テレビCMの制作費は、「どのようなクリエイティブ(表現)で、誰を使い、どこで撮影し、どのように仕上げるか」という要素によって決まります。制作に関わる「人」「モノ」「場所」「時間」のすべてがコストとして積み上がっていくイメージです。
制作費の相場は非常に幅広く、一概に定義することは困難です。しかし、大まかな目安として以下のように分類できます。
- 低予算(50万円~300万円):
- 内容: 静止画(写真やイラスト)のスライドショー、シンプルなアニメーション、既存素材の活用など。
- 特徴: 新規の撮影は行わないか、行っても小規模なものに限定。タレントは起用せず、ナレーターやモデルも比較的安価な人材を起用。コストを最優先する場合の選択肢。
- 中予算(300万円~1,000万円):
- 内容: オリジナルの実写撮影(スタジオや近郊ロケ)、比較的シンプルなCGやモーショングラフィックス。
- 特徴: プロの監督、カメラマン、照明技師などのスタッフで撮影チームを編成。舞台で活躍する俳優や、知名度が上がり始めたモデルなどを起用することも可能。多くの企業CMがこの価格帯で制作されています。
- 高予算(1,000万円以上):
- 内容: 有名タレントや俳優の起用、海外ロケや大規模なセットでの撮影、高度で写実的なVFX(視覚効果)やフルCGアニメーション。
- 特徴: 日本を代表するような著名なクリエイター(監督、CMプランナーなど)が参加。オリジナルのCMソングを有名アーティストに依頼することも。制作費の大部分をタレントの出演料や楽曲使用料が占めるケースが多い。
予算を決める際は、CM出稿の目的を明確にすることが重要です。例えば、「とにかく安く、商品の基本情報を伝えたい」のであれば低予算の制作で十分かもしれません。しかし、「企業のブランドイメージを刷新し、信頼感を醸成したい」という目的であれば、相応のクオリティが求められるため、中〜高予算の制作が必要になります。
制作費の主な内訳
CMの制作費は、多くの細かい項目の積み重ねで構成されています。ここでは、主な内訳を4つのカテゴリーと「その他費用」に分けて解説します。
企画費(プランニング費用)
CM制作の根幹をなす、アイデアや設計図を作るための費用です。ここでのクオリティが、CM全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。
- CMプランナー費: CM全体のコンセプトやストーリー、キャッチコピーなどを考案する専門家への報酬。
- 絵コンテ・字コンテ制作費: 企画内容を具体的な映像イメージに落とし込むための絵コンテ(イラストによる設計図)や、字コンテ(文字による設計図)の作成費用。
- プレゼンテーション費: 広告主に対して企画を提案する際にかかる費用。
企画費の相場は、制作費全体の10%~20%程度が目安とされています。
スタッフ人件費
企画を実際の映像として形にする、プロフェッショナルたちの人件費です。関わるスタッフの人数や実績によって大きく変動します。
- プロデューサー: 制作全体の予算管理、スケジュール調整、スタッフの選定など、プロジェクト全体を統括する責任者。
- プロダクションマネージャー(PM): プロデューサーの補佐役。撮影準備や現場進行など、実務全般を担当する。
- ディレクター(監督): 映像の演出を手掛ける中心人物。演技指導やカメラワーク、編集の方向性などを決定する。
- 撮影スタッフ: カメラマン、照明技師、音声技師、美術デザイナーなど。
- その他: スタイリスト、ヘアメイク、ロケーションコーディネーターなど。
著名な監督やカメラマンを起用すれば当然コストは上がりますが、映像のクオリティも格段に向上します。
撮影・機材費
撮影を実際に行うための費用です。ロケーションや使用する機材によって大きく変動します。
- 撮影機材費: 高性能なシネマカメラ、レンズ、クレーン、ドローン、照明機材などのレンタル費用。
- スタジオ使用料: 屋内での撮影を行う場合のスタジオレンタル費用。セットを組む場合は、その美術費も含まれる。
- ロケーション費: 屋外で撮影する場合の場所代(ロケハン費用、許可申請費用、施設使用料など)。海外でのロケとなると、渡航費や宿泊費なども加わり、費用は跳ね上がります。
- 美術・小道具費: CMの世界観を構築するための背景セットや小道具、衣装などの制作・購入・レンタル費用。
編集・MA費
撮影した素材を一本のCM映像として完成させる、ポストプロダクション(後処理)工程の費用です。
- オフライン編集・オンライン編集費: 撮影した映像素材をつなぎ合わせ、CMの尺に合わせてカット割りを行う編集作業の費用。
- CG・VFX制作費: コンピュータグラフィックスや特殊効果を加える場合の費用。内容の複雑さによって大きく変動する。
- MA(Multi Audio)費: ナレーション収録、BGMや効果音(SE)の挿入、全体の音量バランス調整など、音声に関するすべての作業を行う費用。ナレーターへの報酬もここに含まれる。
- カラリストによる色調整費(グレーディング): 映像全体のトーンや色味を調整し、映像のクオリティを高める作業。
その他費用(タレント出演料・楽曲使用料など)
上記のカテゴリーに含まれないものの、制作費に大きな影響を与える費用です。
- タレント出演料(ギャラ): 制作費の中で最も変動幅が大きい項目。 有名な俳優やタレントを起用する場合、数千万円以上の出演料がかかることもあります。契約期間(クール数)や競合他社のCM出演制限(競合規定)などによっても金額は変動します。
- 楽曲使用料:
- 既存楽曲: 有名アーティストの楽曲などを使用する場合の著作権使用料。人気曲ほど高額になる。
- オリジナル楽曲制作: CMのために新たに楽曲を制作する場合の作曲・編曲・演奏費用。
- 著作権フリー音源: 比較的安価、または無料で利用できる音源。
- 交通費・宿泊費: スタッフやキャストの移動や宿泊にかかる費用。
| 費用の内訳 | 主な項目 | 費用の目安(制作費1,000万円の場合) |
|---|---|---|
| 企画費 | CMプランナー、絵コンテ作成など | 100万円~200万円 |
| スタッフ人件費 | 監督、カメラマン、プロデューサーなど | 200万円~300万円 |
| 撮影・機材費 | スタジオ代、ロケ費、機材レンタルなど | 200万円~300万円 |
| 編集・MA費 | 映像編集、CG制作、ナレーション収録など | 100万円~200万円 |
| その他費用 | タレント出演料、楽曲使用料など | 変動大(この例では200万円~400万円を想定) |
このように、テレビCMの制作費は多くの要素で構成されています。予算を検討する際は、どの部分に重点を置き、どの部分のコストを抑えるかを戦略的に考えることが重要です。
テレビCMの費用を安く抑える5つの方法
テレビCMは高額な投資というイメージが強いですが、工夫次第で費用を大幅に抑えることが可能です。特に、初めてテレビCMに挑戦する企業や、限られた予算で最大限の効果を狙いたい企業にとって、コスト削減は重要な課題です。ここでは、CMの総費用(放映費+制作費)を安く抑えるための具体的な5つの方法を紹介します。
① ローカル局で放映する
放映費を抑える最も効果的な方法の一つが、全国ネットのキー局ではなく、特定の都道府県を対象とするローカル局(地方局)でCMを放映することです。
前述の通り、放映費は放送エリアの広さ(視聴可能人口)に大きく比例します。キー局の放映費が15秒CM1本あたり数十万円から100万円以上するのに対し、ローカル局であれば数万円程度から、場合によってはそれ以下で放映できるケースもあります。
特に、以下のような企業にとっては、ローカル局への出稿は非常に費用対効果の高い戦略となります。
- 店舗ビジネス: スーパーマーケット、不動産会社、飲食店など、商圏が特定の地域に限られる事業。
- 地域密着型サービス: 地元の士業、学習塾、リフォーム会社など。
- テストマーケティング: 全国展開の前に、特定のエリアで商品の反応を見たい場合。
まずは自社の事業エリアをカバーするローカル局に絞って出稿することで、無駄な広告費を削減し、ターゲット顧客に効率よくアプローチできます。
② 放映の時間帯や時期を調整する
CMを放映する「時間」と「時期」を戦略的に選ぶことも、放映費の節約に繋がります。
時間帯の調整
テレビの放映費は、視聴率の高い「プライムタイム(19時~23時)」が最も高額です。この時間帯を避け、比較的視聴率が落ち着いている平日の昼間(Aタイム)や、深夜・早朝(B・Cタイム)を狙うことで、放映単価を下げることができます。
例えば、主婦層がターゲットなら平日の昼間の情報番組やドラマの枠、若者層がターゲットなら深夜のアニメやバラエティ番組の枠を狙うなど、ターゲットの視聴習慣に合わせて時間帯を選ぶことで、コストを抑えつつ効果的なリーチが期待できます。
時期の調整
テレビCMの出稿量は、年間を通じて変動します。多くの企業が新年度や年末商戦に向けて広告予算を投下する3月、9月、12月は需要が高まり、放映費も高騰する傾向にあります。
一方で、企業の広告活動が比較的落ち着く2月や8月は「ニッパチ」と呼ばれ、CM枠の需要が低下し、通常よりも安い価格で放映枠を確保できる可能性があります。これらの閑散期を狙ってキャンペーンを実施するのも、賢いコスト削減策の一つです。
③ CMの秒数を15秒にする
テレビCMの基本となる秒数は15秒です。30秒CMはより多くの情報を伝えられる、あるいはブランドの世界観を深く表現できるというメリットがありますが、放映費は単純計算で15秒CMの約2倍かかります。
コストを抑えたい場合、まずは基本の15秒CMで制作・放映することを検討しましょう。 15秒という短い時間でも、伝えたいメッセージを一つに絞り、インパクトのある映像やキャッチーな音楽と組み合わせることで、十分に視聴者の記憶に残るCMを作ることは可能です。
複数のメッセージを伝えたい場合でも、30秒CMを1本流す代わりに、メッセージの異なる15秒CMを2種類制作し、時間帯やターゲットに合わせて放映するといった戦略も考えられます。これにより、総放映費を抑えながら、多様な訴求が可能になります。
④ 静止画やアニメーションを活用する
制作費を抑える上で非常に効果的なのが、大掛かりな実写撮影を避け、静止画(写真やイラスト)やアニメーションを主体としたCMを制作することです。
実写撮影には、監督やカメラマンをはじめとする多くのスタッフの人件費、ロケーション費、スタジオ代、機材費など、多額のコストがかかります。特にタレントを起用すれば、その出演料が制作費の大部分を占めることも少なくありません。
これに対し、
- 静止画CM: 商品写真やイラスト素材に、テロップ(文字情報)とナレーション、BGMを加えて構成する手法。撮影が不要なため、制作費を数十万円レベルにまで抑えることが可能です。
- アニメーションCM: オリジナルのキャラクターや図形を動かしてストーリーを表現する手法。実写では表現が難しい内容も自由に映像化でき、撮影に比べてコストを抑えやすいのが特徴です。
これらの手法は、特にWebサービスやアプリ、BtoB向けの商材など、ビジュアルで派手に見せるよりも、機能やメリットを分かりやすく説明することが重要な場合に有効です。
⑤ 制作会社に直接依頼する
テレビCMの依頼先は、大きく分けて「広告代理店」と「映像制作会社」があります。一般的に、多くの企業は広告代理店に相談し、企画から放映枠の買い付け(メディアバイイング)、制作までをワンストップで依頼します。これは非常に便利な方法ですが、代理店が介在することで中間マージンが発生します。
もし、CMの制作(映像を作ること)だけを依頼し、放映枠の確保は自社で行う、あるいは別の手段を考えるのであれば、映像制作会社に直接依頼することで、コストを抑えられる可能性があります。
ただし、この方法には注意点もあります。広告代理店はテレビ局との強いコネクションを持っており、有利な条件で放映枠を確保できるノウハウがあります。制作会社に直接依頼した場合、メディアバイイングの交渉を自社で行う必要があり、専門的な知識がないと難しい場合があります。
制作費を抑えたい、かつクリエイティブのクオリティにこだわりたい場合には有効な選択肢ですが、放映までのプロセスを自社で管理できる体制があるかどうかを検討する必要があります。
テレビCMを放映するまでの流れ6ステップ
テレビCMは、アイデアが生まれてから実際にテレビで放映されるまで、多くの工程と時間を要するプロジェクトです。そのプロセスは、クリエイティブな作業と、放送基準に適合させるための厳格な手続きが組み合わさっています。ここでは、一般的なテレビCMが放映に至るまでの流れを、6つのステップに分けて具体的に解説します。
① 広告代理店・制作会社への相談
すべての始まりは、広告主(企業)が広告代理店や制作会社に相談するところからスタートします。この最初の段階は「オリエンテーション(オリエン)」と呼ばれ、プロジェクトの成功を左右する非常に重要なステップです。
企業側は、以下の情報をできるだけ具体的に伝える必要があります。
- CMの目的: なぜCMを放映したいのか?(例:新商品の認知度向上、企業のブランディング、ECサイトへの誘導など)
- ターゲット: 誰にメッセージを届けたいのか?(例:20代女性、ファミリー層、経営者層など)
- 予算: 放映費と制作費を合わせた総額はどのくらいか?
- 期間: いつからいつまで放映したいのか?
- 訴求したい内容: 商品やサービスの最も伝えたい強みは何か?
これらの情報に基づき、広告代理店や制作会社は、最適なCM戦略の方向性を検討します。この段階でのコミュニケーションが密であるほど、後の企画提案の精度が高まります。
② 企画・絵コンテ制作
オリエンテーションの内容を受けて、広告代理店のCMプランナーや制作会社のディレクターが、CMの具体的な企画案を作成します。通常、複数の異なる切り口の企画案が提案され、広告主はそれらの中から最も目的に合致するものを選びます。
企画が決定すると、次はその内容を映像の設計図である「絵コンテ(画コンテ)」に落とし込みます。絵コンテには、カットごとの構図、登場人物の動きや表情、セリフやナレーション、BGMや効果音のイメージなどが詳細に描かれます。これにより、関係者全員が完成形の映像イメージを共有できるようになります。
この段階で、キャスティング(出演者の選定)、ロケーションハンティング(撮影場所探し)、スタッフィング(監督やカメラマンの決定)なども並行して進められます。
③ 撮影・素材制作
絵コンテで固まった映像プランに基づき、いよいよ実制作に入ります。実写CMの場合は「撮影」、アニメーションやCGのCMの場合は「素材制作」がこのステップの中心となります。
実写撮影の場合
監督、カメラマン、照明、音声、美術といった専門スタッフが集結し、スタジオやロケ地で撮影が行われます。出演者(タレントやモデル)は、監督の演出指示に従って演技をします。撮影は天候に左右されることもあり、スケジュール通りに進めるためのプロダクションマネージャーの手腕が問われます。
アニメーション・CG制作の場合
イラストレーターがキャラクターや背景を描き、アニメーターがそれらを動かしていきます。CGの場合は、モデリング(形状作成)、テクスチャリング(質感設定)、リギング(動きの設定)、アニメーションといった専門的な工程を経て映像が作られます。
同時に、ナレーターによるナレーションの収録や、CMソングのレコーディングなども行われます。
④ 編集・MA(音入れ作業)
撮影・制作された映像や音声の素材を、一本のCMとして完成させる最終仕上げの工程です。この工程は「ポストプロダクション」とも呼ばれます。
- 編集(Editing): まず、撮影した映像素材をつなぎ合わせる「オフライン編集」で、CMの流れと尺(時間)を確定させます。その後、高解像度の本データを使って映像を差し替える「オンライン編集」を行い、テロップ(文字情報)やロゴを挿入し、色味を調整(カラーグレーディング)して映像を完成させます。
- MA(Multi Audio): 完成した映像に、音を加えていく作業です。収録したナレーション、BGM、効果音(SE)を映像に合わせて配置し、それぞれの音量バランスを最適化します。このMA作業によって、CMの臨場感や訴求力が格段に向上します。
この編集・MA作業を経て、CMのマスターデータ(完成品)が出来上がります。
⑤ 放送局の考査
完成したCMは、すぐに放映できるわけではありません。テレビ局に納品する前に、その内容が放送に適しているかどうかを審査する「考査」というプロセスを通過する必要があります。 考査は、広告代理店やテレビ局の専門部署によって行われます。
考査には、主に2つの側面があります。
- 表現考査: 広告表現が、法律(景品表示法、薬機法など)や日本民間放送連盟が定める「放送基準」に違反していないかをチェックします。誇大な表現、差別的な表現、視聴者に不快感を与える可能性のある内容などが厳しく審査されます。
- 業態考査: 広告主である企業そのものが、テレビCMを放映するにふさわしいかどうかを審査します。反社会的な企業でないか、事業内容に問題はないかなどが確認されます。
考査で修正指示(NG)が出た場合は、指摘された箇所を修正し、再度考査を受ける必要があります。この考査をクリアして初めて、CMは放映の許可を得られます。
⑥ 納品・CM放映開始
考査を無事に通過したCMのマスターデータは、指定されたフォーマットで各テレビ局に納品されます。近年は、物理的なテープではなく、オンラインでのデータ搬入が主流となっています。
納品が完了し、あらかじめ契約していた放映スケジュールに基づき、いよいよテレビでのCM放映が開始されます。企画のスタートから放映開始までにかかる期間は、一般的に2ヶ月~3ヶ月程度が目安ですが、企画の難易度やタレントのスケジュールなどによっては、半年以上かかることもあります。
テレビCMを放映するメリット・デメリット
テレビCMは依然として非常に影響力の大きい広告媒体ですが、その特性を正しく理解し、自社の戦略に合致しているかを判断することが重要です。ここでは、テレビCMを放映することのメリットとデメリットを、それぞれ3つの観点から整理して解説します。
テレビCMの3つのメリット
① 広い層にアプローチできる
テレビCMが持つ最大のメリットは、その圧倒的なリーチ力です。インターネットやSNSが普及した現在でも、テレビは依然として老若男女問わず多くの人々が日常的に接触するマスメディアです。
- 網羅性: 特定の趣味や関心を持つ層にしか届かないWeb広告とは異なり、テレビCMは地域や年代、性別を超えて、不特定多数の非常に幅広い層に対して一度にメッセージを届けることができます。 これは、全国的に知名度を高めたい新商品や、誰もが利用する可能性のあるサービス(日用品、食品、金融サービスなど)の広告において、絶大な効果を発揮します。
- 受動的な接触: 視聴者は、能動的に情報を探しにいかなくても、番組を見ているだけで自然とCMに接触します。これにより、自社の商品やサービスをまだ知らない潜在顧客層にも、その存在を認知させることが可能です。
② 企業の信頼性やブランドイメージが向上する
テレビCMを放映しているという事実そのものが、企業の社会的な信頼性やブランドイメージを大きく向上させる効果を持ちます。
- 社会的信用の獲得: 前述の通り、テレビCMは放送局による厳格な「業態考査」と「表現考査」をクリアしなければ放映できません。つまり、「テレビCMを放映している企業=厳しい審査を通過した信頼できる企業」という認識が、視聴者の中に無意識のうちに生まれます。この「ハロー効果」は、特にスタートアップ企業やBtoB企業が取引先からの信頼を得る上で、強力な武器となり得ます。
- ブランディング効果: 印象的な映像や音楽、キャッチコピーを繰り返し届けることで、視聴者の心に企業や商品のポジティブなイメージを刷り込むことができます。特定の番組のスポンサーとなる「タイムCM」であれば、番組の持つイメージと自社ブランドを強く結びつけ、より深いレベルでのブランディングが可能です。
③ 短期間で認知度を高められる
テレビCMは、短期間で集中的に情報を投下することで、商品やサービスの認知度を爆発的に高める力を持っています。
- 反復効果(ザイオンス効果): 同じCMに繰り返し接触することで、視聴者はその商品や企業に対して親近感や好感を抱きやすくなります。スポットCMなどを活用して、キャンペーン期間中に大量のCMを放映することで、この効果を最大化できます。
- 話題性の創出: クリエイティブが優れたCMや、インパクトのあるCMは、SNSなどで拡散され、二次的な話題を生むことがあります。「あの面白いCMの会社」として認知されれば、広告費以上の効果が期待できます。新商品の発売や大規模なセールの告知など、短期間で一気に市場の注目を集めたい場合に、テレビCMは最も効果的な手段の一つです。
テレビCMの3つのデメリット
① 費用が高額になる
テレビCMの最大のデメリットは、やはりその費用の高さです。放映費と制作費を合わせると、他の広告媒体に比べて桁違いのコストがかかることが一般的です。
- 初期投資の大きさ: ローカル局で最低限の出稿をする場合でも、数百万円単位の予算が必要になることが多く、全国規模のキャンペーンとなれば億単位の投資が求められます。このため、体力のある大企業でなければ、なかなか手が出しづらいのが実情です。
- 費用対効果の見極めの難しさ: 多額の投資に見合うだけのリターン(売上増加やブランド価値向上)が得られるかどうかを、事前に正確に予測することは困難です。投資に失敗した場合の経営的なリスクは、Web広告などとは比較になりません。
② 詳細な効果測定がしにくい
Web広告がクリック数やコンバージョン率といった指標で詳細な効果をリアルタイムに測定できるのに対し、テレビCMは直接的な効果測定が難しいというデメリットがあります。
- 定性的な評価が中心: GRP(延べ視聴率)といった指標で「どれだけの人に見られたか」の規模は測れますが、CMを見た人が実際に商品を「購入したか」「ブランドを好きになったか」を直接的に数値化することは困難です。効果測定は、CM放映後のアンケート調査や、売上データとの相関分析といった間接的な手法に頼らざるを得ません。
- 改善のPDCAが回しにくい: Web広告であれば、効果の悪い広告クリエイティブをすぐ停止し、別のものに差し替えるといった迅速な改善が可能です。しかし、テレビCMは一度制作・放映を開始すると、内容の変更が容易ではないため、効果が出ていなくてもPDCAサイクルを高速で回すことはできません。
③ ターゲットを細かく絞り込めない
テレビCMは幅広い層にリーチできる反面、特定のターゲット層に絞って広告を配信する「ターゲティング」の精度が低いという弱点があります。
- マス向けの媒体: Web広告のように、ユーザーの年齢、性別、興味関心、検索履歴などに基づいてピンポイントで広告を出し分けることはできません。例えば、20代男性向けのニッチな商品を、主婦層が多く見る昼間の番組で放映しても、広告費の多くは無駄になってしまいます。
- コスト効率の課題: 自社の商品やサービスのターゲットが非常に限定的な場合、テレビCMというマス向けの媒体は、コスト効率が悪くなる可能性があります。ターゲットではない大多数の視聴者にも広告が届いてしまうため、一人あたりのターゲット顧客獲得単価(CPA)が高騰しがちです。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| リーチ | ① 広い層にアプローチできる(老若男女問わず) | ③ ターゲットを細かく絞り込めない(マス向け) |
| ブランド・信頼性 | ② 企業の信頼性やブランドイメージが向上する(考査による信用) | – |
| 効果・スピード | ③ 短期間で認知度を高められる(反復効果・話題性) | ② 詳細な効果測定がしにくい(Web広告との比較) |
| コスト | – | ① 費用が高額になる(他の広告媒体との比較) |
テレビCMの効果測定で使われる主な指標
テレビCMは詳細な効果測定がしにくいというデメリットがありますが、全く効果が測れないわけではありません。投下した多額の費用に対するリターンを評価し、次なるマーケティング施策に活かすためには、適切な指標を用いて効果を可視化することが不可欠です。ここでは、テレビCMの効果測定で一般的に使われる主要な3つの指標・手法について解説します。
GRP(延べ視聴率)
GRP(Gross Rating Point:延べ視聴率)は、テレビCMの効果測定において最も基本的な量的指標です。これは、特定の期間に放映したCMが、どれだけの世帯に視聴されたかの「延べ」の割合を示します。
計算式は非常にシンプルです。
GRP (%) = 世帯視聴率 (%) × CM放映回数 (本)
例えば、世帯視聴率10%の番組でCMを5本放映した場合、GRPは「10% × 5本 = 50GRP」となります。また、視聴率8%の番組で3本、視聴率5%の番組で4本放映した場合は、「(8% × 3) + (5% × 4) = 24 + 20 = 44GRP」と計算されます。
GRPは、CMキャンペーンの規模を示す指標として、広告代理店との取引や放映プランの策定において広く用いられます。スポットCMを発注する際には、「1週間で〇〇GRP分のCMを放映してください」といった形で目標値を設定するのが一般的です。
GRPの役割と限界
- 役割: キャンペーンのリーチ規模を客観的な数値で把握できる。異なるキャンペーンの出稿量を比較する際の共通言語となる。
- 限界: GRPはあくまで「延べ」の数値であるため、実際に何人の人がCMを見たか(ユニークリーチ)や、一人が何回CMを見たか(フリークエンシー)を正確に知ることはできません。 例えば、100GRPは「視聴率10%の番組に10回」でも、「視聴率1%の番組に100回」でも達成できますが、視聴者への影響は異なります。また、視聴率の数値はあくまで「テレビがついている世帯」の割合であり、個人が本当に画面を見ていたかを保証するものではありません。
したがって、GRPはCM出稿の「量」を測る指標と割り切り、次に紹介する質的な指標と組み合わせて評価することが重要です。
認知度調査
GRPがCMの「量」を測る指標であるのに対し、CMの「質」、つまり視聴者の意識や態度にどのような変化をもたらしたかを測るのが「認知度調査」です。これは、マーケティングリサーチ会社などを通じて、一般の消費者を対象にアンケート調査を行う手法です。
一般的には、CM放映「前」と放映「後」の2回、同じ内容の調査を実施し、その結果を比較することでCMの効果を測定します。
主な調査項目には以下のようなものがあります。
- ブランド認知度: 「〇〇(企業名や商品名)を知っていますか?」
- 助成想起(Re-aided Awareness): 選択肢の中から知っているものを選んでもらう。
- 純粋想起(Unaided Awareness): 「知っている〇〇をすべて挙げてください」と自由に回答してもらう。
- CM認知度: 「〇〇のテレビCMを見たことがありますか?」
- CM内容理解度: 「CMで最も印象に残ったことは何ですか?」
- ブランドイメージ: 「〇〇に対してどのようなイメージを持っていますか?」(例:信頼できる、革新的、親しみやすいなど)
- 購入・利用意向: 「今後、〇〇を購入・利用したいと思いますか?」
これらの調査結果を分析することで、「CM放映によって、ターゲット層のブランド認知度が〇%向上した」「CMを見た人は見ていない人に比べて、購入意向が〇ポイント高い」といった、より具体的で深掘りした効果検証が可能になります。多額の費用を投じるCMキャンペーンにおいては、その投資対効果を判断するための重要なデータとなります。
Webサイトへの流入数や指名検索数の変化
近年、テレビCMの効果測定において非常に重要視されているのが、デジタルデータとの連携です。テレビCMを見た視聴者が、その直後や後日にどのような行動を取ったかを、Web上のデータから分析する手法です。
この手法の大きなメリットは、アンケート調査のように対象者を抽出する必要がなく、全量データに近い形でユーザーの反応をリアルタイムに把握できる点です。
具体的には、以下の2つの指標がよく用いられます。
- Webサイトへの流入数: CM放映期間中、特にCMが流れた直後の時間帯に、自社のWebサイトへのアクセス数が急増するかどうかを分析します。Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを用いて、「参照元なし(ノーリファラー)」や「自然検索(オーガニックサーチ)」経由のセッション数の変化を注視します。CMの最後に「詳しくはWebで」と表示し、サイトへの誘導を促すのはこの効果を狙ったものです。
- 指名検索数の変化: 「指名検索」とは、企業名、商品名、サービス名といった固有名詞で直接検索されることを指します。CM放映によって、これらの指名検索のボリュームがどれだけ増加したかを、Googleトレンドなどのツールで分析します。指名検索の増加は、視聴者がそのブランドに対して明確な興味・関心を持ったことの証左であり、非常に重要な成果指標です。
これらのデジタル指標を定点観測することで、どの時間帯のCMがWebサイトへの流入に繋がりやすいか、どのクリエイティブが指名検索を喚起したかなど、より具体的な分析が可能になり、次回のCMプランニングの最適化に繋げることができます。
テレビCMの依頼先と選び方のポイント
テレビCMを成功させるためには、信頼できるパートナー選びが不可欠です。CMの依頼先は、主に「広告代理店」と「映像制作会社」の2つに大別されます。それぞれに異なる特徴と強みがあり、自社の目的や体制、予算に応じて最適な依頼先を選ぶ必要があります。ここでは、それぞれの特徴と、選ぶ際のポイントについて解説します。
広告代理店に依頼する
広告代理店は、クライアント(広告主)のマーケティング課題を解決するため、広告に関するあらゆる業務を代行する企業です。テレビCMに関しては、企画立案から制作会社の選定、メディアプランニング(どの局で、いつ、どれだけ放映するか)、放映枠の買い付け、効果測定までをワンストップで請け負ってくれるのが最大の特徴です。
広告代理店に依頼するメリット
- ① 包括的なサポート: CM制作だけでなく、放映枠の確保や効果分析、さらにはテレビCMと連動したWeb広告やイベントなど、統合的なマーケティング戦略の提案を受けられます。CMに関する専門知識が社内にない場合でも、安心して任せることができます。
- ② メディアバイイング力: 広告代理店、特に大手はテレビ局との長年の取引関係があり、強い交渉力を持っています。これにより、人気の番組枠を確保しやすかったり、有利な条件で放映枠を買い付けたりできる可能性があります。
- ③ 豊富な実績とノウハウ: 数多くのCM案件を手掛けてきた実績から、成功・失敗事例に基づいた戦略的なアドバイスが期待できます。市場データや調査結果も豊富に保有しており、客観的なデータに基づいたプランニングが可能です。
広告代理店に依頼するデメリット
- ① 中間マージンの発生: 代理店は、制作会社やテレビ局との間に立つため、手数料(マージン)が発生します。同じ内容のCMでも、制作会社に直接依頼する場合に比べて、総費用は高くなる傾向があります。
- ② コミュニケーションの階層: クライアント → 代理店 → 制作会社という伝言ゲームになりやすく、意図が正確に伝わりにくかったり、意思決定に時間がかかったりする場合があります。
選び方のポイント
広告代理店と一口に言っても、電通や博報堂のような全てを扱う「総合広告代理店」から、特定の業種やテレビCMに特化した「専門広告代理店」、インターネット広告に強い代理店まで様々です。自社の事業規模や課題に合わせて、「総合的な提案力が欲しいのか」「テレビCMに特化した知見が欲しいのか」を明確にし、それぞれの強みを持つ代理店を選ぶことが重要です。
映像制作会社に依頼する
映像制作会社は、その名の通り、CMやプロモーションビデオといった映像コンテンツの「制作(クリエイティブ)」を専門とする企業です。企画の具体化(演出コンテ作成)から、撮影、編集、MAまで、映像を作り上げるプロセスに特化しています。
映像制作会社に依頼するメリット
- ① 高い専門性とクオリティ: 映像制作のプロフェッショナル集団であるため、クリエイティブの品質に強いこだわりを持っています。特定のテイスト(例:ドキュメンタリー調、CG駆使など)を得意とする会社も多く、作りたい映像のイメージが明確な場合に、高いクオリティが期待できます。
- ② コストの透明性と柔軟性: 代理店を介さないため、中間マージンが発生せず、制作費の内訳がより透明になります。予算が限られている場合でも、「この予算内でどこまでできるか」といった相談に柔軟に乗ってくれることが多いです。
- ③ 直接的なコミュニケーション: 監督やプロデューサーと直接やり取りできるため、企画意図や細かいニュアンスが伝わりやすく、スピーディーな意思決定が可能です。
映像制作会社に依頼するデメリット
- ① メディアバイイングは自社で: 制作会社は基本的に映像を作るまでが仕事です。完成したCMをどのテレビ局で放映するかといったメディアプランニングや放映枠の買い付けは、原則として広告主自身が行うか、別途広告代理店に依頼する必要があります。
- ② マーケティング戦略の視点: 制作会社は「良い映像を作ること」がミッションであり、広告代理店のように市場分析やターゲット設定といった上流のマーケティング戦略までをカバーしていない場合があります。
選び方のポイント
映像制作会社を選ぶ際は、まずその会社の制作実績(ポートフォリオ)を必ず確認しましょう。自社のブランドイメージや、作りたいCMの方向性と、その会社の作風が合っているかを見極めることが最も重要です。また、予算感やコミュニケーションのしやすさも重要な選定基準となります。
| 依頼先 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|---|
| 広告代理店 | ・ワンストップで全て任せられる ・メディアバイイング力が強い ・統合的なマーケティング提案 |
・中間マージンが発生する ・コミュニケーションが間接的になりがち |
・CMの知見がなく、丸ごと任せたい企業 ・全国規模の大型キャンペーンを実施したい企業 ・Webなど他施策との連携を重視する企業 |
| 映像制作会社 | ・制作費を抑えられる可能性がある ・クリエイティブの品質が高い ・直接的なコミュニケーションが可能 |
・放映枠の確保は自社で行う必要がある ・マーケティング戦略の視点は弱い場合がある |
・社内にCMの知見がある程度ある企業 ・制作したい映像のイメージが明確な企業 ・とにかく制作費を抑えたい企業 |
テレビCM制作におすすめの会社5選
テレビCMのパートナー選びは、キャンペーンの成否を左右する重要な決断です。ここでは、それぞれ異なる強みを持つ代表的な会社を5社紹介します。総合広告代理店から、インターネット広告に強い代理店、そして制作に特化した会社まで、自社のニーズに合った依頼先を見つけるための参考にしてください。
※以下に掲載する情報は、各社の公式サイトなどを基にした客観的な紹介であり、特定の順位や優劣を示すものではありません。
① 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
株式会社博報堂DYメディアパートナーズは、博報堂DYグループの中核をなす総合メディア事業会社です。日本の広告業界をリードする存在の一つであり、テレビCMをはじめとするマスメディアの取り扱いに圧倒的な強みを持ちます。
- 特徴: テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といった従来型のメディアから、デジタルメディア、屋外広告まで、あらゆるメディアを統合した包括的なメディアソリューションを提供できるのが最大の強みです。長年にわたるテレビ局との強固な関係性を背景に、質の高い広告枠の確保や、効果的なメディアプランニングを実現します。また、博報堂の持つ高いクリエイティブ力と連携し、戦略立案からクリエイティブ制作、メディアバイイング、効果検証までを一気通貫でサポートします。
- おすすめの企業: 全国規模での大規模なブランディングキャンペーンを検討している大手企業や、テレビCMと他のメディアを連動させた統合的なマーケティング戦略を求める企業に適しています。
参照:株式会社博報堂DYメディアパートナーズ公式サイト
② 株式会社電通
株式会社電通は、日本最大手の総合広告代理店であり、国内の広告市場においてトップシェアを誇ります。その影響力は国内に留まらず、グローバルなネットワークも有しています。テレビCMの領域においても、数多くの象徴的なキャンペーンを手掛けてきた実績があります。
- 特徴: 卓越したクリエイティブ制作力と、大規模なキャンペーンを成功に導く実行力に定評があります。国内外の著名なクリエイターとのネットワークも豊富で、話題性の高いCM制作を得意とします。また、膨大なマーケティングデータを活用した精緻な戦略立案や、テレビ局との強力なパイプを活かしたメディア交渉力も大きな強みです。スポーツイベントや文化事業などとのタイアップも得意としており、多角的なアプローチが可能です。
- おすすめの企業: 業界のリーダーとして強いメッセージを発信したい企業や、社会現象となるようなインパクトのあるCMキャンペーンを目指す企業にとって、最適なパートナーとなり得ます。
参照:株式会社電通公式サイト
③ 株式会社サイバーエージェント
株式会社サイバーエージェントは、インターネット広告事業で国内トップクラスの実績を誇る企業です。そのデジタル領域での知見を活かし、テレビCMの領域においても独自のサービスを展開しています。
- 特徴: 「運用型テレビCM」という新しい概念を提唱し、テレビCMの効果をデジタル広告のように可視化・分析することに強みを持っています。CM放映後のWebサイトへの流入数や、指名検索数の変化などをリアルタイムに近い形で分析し、その結果を基に放映プランを最適化していくアプローチを得意とします。従来のテレビCMの弱点であった「効果測定のしにくさ」を、デジタルの力で克服しようとする点が特徴的です。
- おすすめの企業: テレビCMとWebマーケティングをシームレスに連携させたい企業や、データに基づいてCMの効果を厳密に測定し、PDCAを回していきたいと考える企業に特におすすめです。
参照:株式会社サイバーエージェント公式サイト
④ 株式会社LOCUS
株式会社LOCUS(ローカス)は、動画制作に特化した企業で、特に中小企業やベンチャー企業向けのサービスに強みを持っています。テレビCMの制作においても、比較的リーズナブルな価格帯から対応しているのが特徴です。
- 特徴: 「適正価格で高品質な動画」をコンセプトに、クライアントの予算や目的に応じた柔軟な制作体制を構築しています。800名以上のクリエイターネットワークを活用し、実写からアニメーション、CGまで幅広いジャンルの映像制作が可能です。大手広告代理店に比べてコストを抑えやすいため、初めてテレビCMに挑戦する企業や、限られた予算で効果的なCMを制作したい企業にとって、心強いパートナーとなります。
- おすすめの企業: 予算を抑えてテレビCMを制作したい中小・ベンチャー企業や、まずはテスト的にCMを放映してみたいと考えている企業に適しています。
参照:株式会社LOCUS公式サイト
⑤ ムービット株式会社
ムービット株式会社は、動画制作・映像制作サービス「ムビラボ」を運営する企業です。高品質なクリエイティブを、比較的低価格かつスピーディーに提供することに注力しています。
- 特徴: 企画から撮影、編集までを自社内のスタッフで一貫して行うことで、コストパフォーマンスの高い映像制作を実現しています。特にアニメーション動画やサービス紹介動画を得意としており、テレビCM制作においても、そのノウハウを活かした分かりやすく訴求力の高いクリエイティブを提供します。制作費を抑えつつも、しっかりとしたクオリティのCMを作りたいというニーズに応える体制が整っています。
- おすすめの企業: 制作費を重視しつつも、テンプレート的ではないオリジナルのCMを制作したい企業や、Web動画広告とテレビCMを並行して検討している企業にとって、良い選択肢となるでしょう。
参照:ムービット株式会社公式サイト
| 会社名 | 特徴 | 強み |
|---|---|---|
| ① 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ | 総合メディア事業会社 | 統合メディア戦略、メディアバイイング力 |
| ② 株式会社電通 | 日本最大手の総合広告代理店 | 高いクリエイティブ力、大規模キャンペーンの実行力 |
| ③ 株式会社サイバーエージェント | インターネット広告大手 | 運用型テレビCM、データに基づく効果測定・最適化 |
| ④ 株式会社LOCUS | 中小・ベンチャー向け動画制作 | リーズナブルな価格帯、柔軟な制作体制 |
| ⑤ ムービット株式会社 | 動画制作サービス「ムビラボ」運営 | コストパフォーマンス、スピーディーな制作 |
テレビCMに関するよくある質問
ここまでテレビCMの費用や流れについて詳しく解説してきましたが、まだ具体的な疑問をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、クライアントから特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. テレビCMは最低いくらから出稿できますか?
A. これは最も多い質問の一つですが、放映費と制作費を合わせて、最低でも60万円~100万円程度が一つの目安となります。
この金額の内訳は、主に以下のようになります。
- 放映費: 最も安価な選択肢は、地方のローカル局で、視聴率の低い深夜帯(Cタイム)などにスポットCMを数本放映するケースです。これであれば、放映費自体は30万円程度から可能な場合があります。
- 制作費: 撮影を行わず、静止画(イラストや写真)とナレーション、BGMで構成するシンプルなCMであれば、制作費も30万円~50万円程度に抑えることが可能です。
ただし、これはあくまで最低ラインの金額です。当然ながら、この予算では放映エリアや回数、クリエイティブの表現に大きな制約がかかります。
重要なのは、最低金額で出稿すること自体が目的ではなく、その投資でどのような効果を得たいのかを明確にすることです。 例えば、特定の1県だけでよいので、新店舗のオープンを告知したいといった明確な目的があれば、地方局への低予算出稿も有効な戦略となり得ます。自社の目的と、かけられる予算のバランスを広告代理店や制作会社に相談してみるのが良いでしょう。
Q. CMの制作期間はどれくらいですか?
A. 企画のスタート(オリエンテーション)から、実際の放映開始まで、一般的には2ヶ月~3ヶ月程度を見ておくのが標準的です。
大まかな期間の内訳は以下の通りです。
- 企画立案・コンテ制作: 2週間~1ヶ月
- 撮影準備(キャスティング、ロケハンなど): 2週間~1ヶ月
- 撮影・素材制作: 数日~1週間
- 編集・MA(ポストプロダクション): 1週間~2週間
- 考査・納品: 1週間~2週間
ただし、これはあくまで目安です。以下のような要因によって、期間は大きく変動します。
- タレントのキャスティング: 人気タレントを起用する場合、スケジュールの調整に数ヶ月かかることも珍しくありません。
- 企画の複雑さ: 海外ロケや大規模なセット、高度なCGを要する企画の場合は、準備や制作に通常より長い時間が必要です。
- 意思決定のスピード: 広告主側での企画決定や修正指示の確認に時間がかかると、その分全体のスケジュールも遅延します。
余裕を持ったスケジュールを組み、早めに準備を開始することが、スムーズな進行の鍵となります。
Q. 放送できない業種や内容はありますか?
A. はい、あります。テレビは公共の電波を使用するメディアであり、その影響力の大きさから、すべての業種や表現が自由にCMを放映できるわけではありません。
テレビ局は、日本民間放送連盟が定める「放送基準」に基づいて、CMの内容を厳しく審査(考査)します。この基準により、放送ができない、あるいは表現に厳しい規制がかかる業種や内容が存在します。
主に、以下のようなものが挙げられます。
- 法律で禁止されているもの: 公序良俗に反する内容、人権侵害や差別を助長する表現、詐欺的な商法など。
- 業種による規制:
- 医療・医薬品・健康食品: 薬機法(旧薬事法)により、効能効果に関する誇大な表現や、安全性の誤認を招く表現は厳しく禁じられています。
- 金融・不動産: 金融商品取引法や貸金業法、宅地建物取引業法などに基づき、リスクや利率、取引条件などを正確に表示する義務があります。
- ギャンブル関連: 競馬や競輪などの公営競技を除き、基本的には放送が認められていません。パチンコ・パチスロ店のCMは、時間帯の制限や、射幸心を煽らない表現への配慮が求められます。
- その他: 探偵業、たばこ、一部のアルコール飲料なども厳しい規制の対象となります。
- 表現による規制:
- 比較広告: 他社の商品を誹謗中傷したり、客観的なデータに基づかない比較をしたりすることはできません。
- 誇大広告: 「世界一」「絶対に儲かる」といった客観的な根拠のない最上級表現や断定的な表現は使用できません(景品表示法)。
これらの規制は非常に専門的で複雑なため、企画段階から広告代理店や制作会社と十分に協議し、放送基準に準拠したクリエイティブを制作することが不可欠です。
まとめ
本記事では、テレビCMにかかる費用の全体像から、「放映費」と「制作費」の詳細な内訳、費用を抑える方法、放映までの具体的な流れ、そしてメリット・デメリットに至るまで、網羅的に解説してきました。
最後に、この記事の要点を改めて整理します。
- テレビCMの費用は「放映費」と「制作費」で構成される: CMをテレビで流すための「放映費」と、CM映像そのものを作るための「制作費」、この2つの合計が総費用となります。
- 放映費は「どこで・いつ・どう流すか」で決まる: キー局かローカル局か、プライムタイムか深夜か、タイムCMかスポットCMか、といった要素で大きく変動します。
- 制作費は「どんな内容のCMを作るか」で決まる: 実写撮影、タレント起用、CGの活用度など、クリエイティブの内容によって数十万円から1億円以上まで、費用は大きく異なります。
- 工夫次第で費用は抑えられる: ローカル局への出稿、放映時間帯や時期の調整、静止画やアニメーションの活用など、戦略的にプランニングすることで、限られた予算でもテレビCMの実施は可能です。
- メリット・デメリットの理解が重要: テレビCMは、広い層へのリーチ力と高い信頼性獲得という強力なメリットを持つ一方で、高額な費用と効果測定の難しさというデメリットも抱えています。自社の目的と照らし合わせ、慎重に判断することが求められます。
- 依頼先選びが成功の鍵: 全てを任せたいなら「広告代理店」、制作のクオリティやコストを重視するなら「映像制作会社」など、自社の状況に合ったパートナーを選ぶことが不可欠です。
テレビCMは、もはや一部の大企業だけのものではありません。その仕組みを正しく理解し、戦略的に活用すれば、企業の成長を加速させるための強力なエンジンとなり得ます。この記事が、皆様のテレビCM出稿に向けた第一歩を、力強く後押しできれば幸いです。