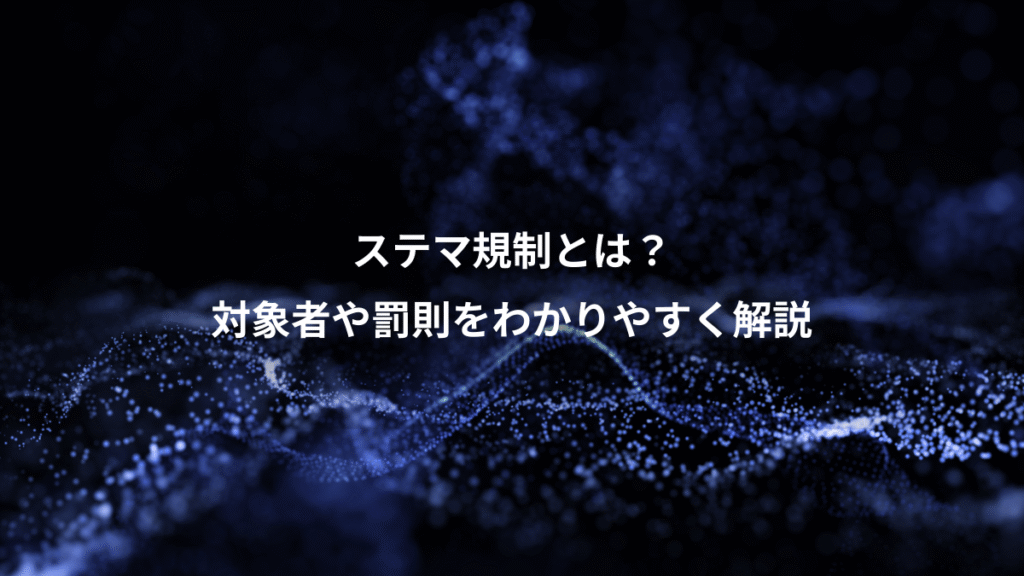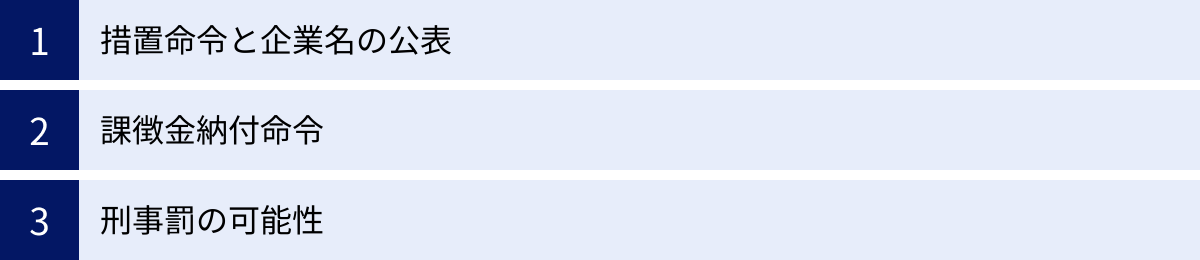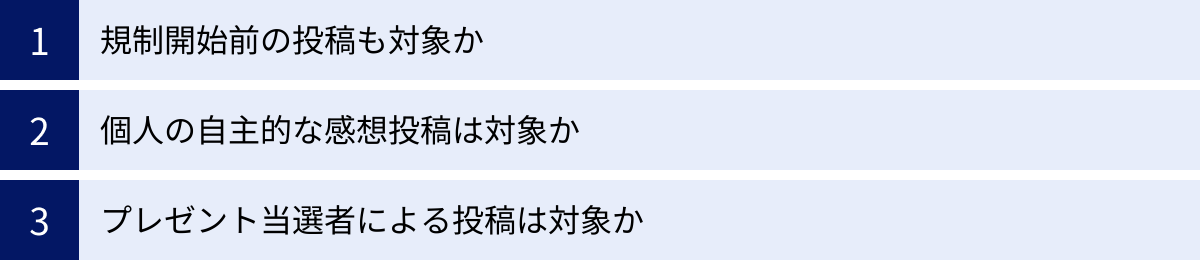近年、SNSや口コミサイトの影響力が増大する中で、消費者の購買行動は大きく変化しました。友人やインフルエンサーの「おすすめ」を参考に商品を選ぶことは、もはや日常的な光景です。しかし、その「おすすめ」が、実は企業から金銭や商品の提供を受けて行われる「広告」であったとしたらどうでしょうか。
2023年10月1日、このような広告であることを隠した宣伝行為、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」を規制する新たなルールが施行されました。この規制は、正式には景品表示法(景表法)の「不当表示」の一つとして位置づけられています。
この記事では、ステマ規制の基本的な定義から、規制の対象者、具体的な判断基準、違反した場合の罰則、そして事業者が取るべき対策まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。気づかないうちに違反してしまうリスクを避け、消費者との健全な信頼関係を築くために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
ステマ規制とは?2023年10月から始まった新しいルール
2023年10月1日から、日本でもついに「ステマ規制」が本格的にスタートしました。この新しいルールは、インターネット上の情報が消費者の購買意思決定に大きな影響を与える現代において、非常に重要な意味を持ちます。ここでは、ステマの基本的な定義から、法律上の位置づけ、そして規制が導入された社会的な背景までを詳しく掘り下げていきます。
ステルスマーケティング(ステマ)の定義
ステルスマーケティング(Stealth Marketing)、通称「ステマ」とは、消費者に広告・宣伝であることを隠して、商品やサービスを宣伝する行為を指します。「ステルス(stealth)」は「隠密」「こっそり行う」といった意味を持つ言葉で、その名の通り、消費者に気づかれないようにマーケティング活動を行う手法の総称です。
具体的には、以下のようなケースがステマに該当します。
- 企業がインフルエンサーに対価(金銭や物品提供など)を支払い、その事実を隠して、あたかも個人的に愛用しているかのようにSNSで商品を紹介してもらう。
- 企業が自社の従業員や外部の業者に指示し、一般の消費者を装ってECサイトや口コミサイトに自社製品を絶賛するレビューを書き込ませる。
- アフィリエイトプログラムを利用しているブロガーが、広告収入を得る目的で特定の商品を推奨しているにもかかわらず、その旨を明記せずに「中立的な立場での徹底比較」などと謳う記事を公開する。
これらの行為の最大の問題点は、消費者を「欺く」ことにあります。消費者は、その情報が第三者による公平で中立的な評価や感想であると誤認してしまいます。その結果、本来であれば選ばなかったかもしれない商品やサービスを購入してしまうなど、自主的かつ合理的な商品選択が歪められてしまうのです。
広告には、発信者が誰であるか、その意図が何であるかを明らかにする「広告表示の原則」があります。テレビCMであれば、それが企業の宣伝であることは誰の目にも明らかです。しかし、ステマはこの原則を無視し、情報の信頼性を根底から揺るがす行為であるため、長年にわたり問題視されてきました。消費者の信頼を裏切るだけでなく、正当なマーケティング活動を行っている他の事業者の努力を無にしかねない、不公正な競争手段でもあるのです。
ステマ規制は景品表示法のひとつ
今回のステマ規制は、独立した新しい法律として制定されたわけではありません。「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」における禁止行為(不当表示)の一つとして追加されたものです。
景品表示法は、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることを目的とした法律です。そのために、大きく分けて2つのことを規制しています。
- 景品類の規制: 過大な景品付き販売によって、消費者が本来の商品の品質や価格ではなく、景品の魅力に惑わされて衝動買いしてしまうのを防ぐためのルールです。
- 表示の規制(不当表示の禁止): 商品やサービスの内容や取引条件について、実際よりも著しく優良または有利であると偽って表示し、消費者を誤認させる行為を禁止するルールです。
これまで、不当表示の主な類型は以下の2つでした。
- 優良誤認表示: 商品・サービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優れていると見せかける表示。(例:普通の牛肉を「松阪牛」と偽って販売する)
- 有利誤認表示: 商品・サービスの価格、その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると見せかける表示。(例:「今だけ半額」と表示しながら、実際にはずっと同じ価格で販売している)
しかし、従来の優良誤認・有利誤認の枠組みだけでは、広告であることを隠すステマ行為を十分に取り締まることが困難でした。そこで、2023年10月1日、新たに「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が不当表示の対象として追加されました。これが、いわゆる「ステマ規制」の正体です。
(参照:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」)
この規制は、表示内容が事実であったとしても(例えば、紹介された商品の性能が本当に優れていたとしても)、それが「広告であることを隠している」という事実自体を問題視するものです。これにより、表示内容の真偽を問わず、広告であることを隠す行為そのものが景品表示法違反となる道が開かれました。
ステマ規制が導入された背景
ステマ規制がこのタイミングで導入された背景には、インターネット、特にSNSの爆発的な普及が大きく関係しています。
1. UGC(ユーザー生成コンテンツ)の影響力増大
ブログ、X(旧Twitter)、Instagram、YouTube、TikTokといったSNSプラットフォームの利用が日常化し、消費者は企業が発信する公式情報だけでなく、他の一般消費者やインフルエンサーが発信する情報(UGC: User Generated Content)を、購買の際の重要な判断材料とするようになりました。特に、自分と価値観が近いと感じるインフルエンサーの「本音のレビュー」は、時に企業の広告よりも強い影響力を持つことがあります。
2. 広告と口コミの境界線の曖昧化
このUGCの影響力に目をつけた企業は、インフルエンサーや一般ユーザーに自社の商品やサービスを宣伝してもらう「インフルエンサーマーケティング」や「口コミマーケティング」を積極的に活用するようになりました。これ自体は正当なマーケティング手法ですが、その過程で広告であることを明示しない「ステマ」が横行しやすくなったのです。
消費者側から見ると、どれが純粋な個人の感想で、どれが企業案件なのかを見分けるのが非常に困難な状況が生まれました。
3. 消費者トラブルの増加と海外の動向
実際に、「インフルエンサーのおすすめを信じて購入したが、期待外れだった」「口コミサイトの高評価を信じたのに、全く違うサービスだった」といった消費者トラブルが後を絶ちませんでした。消費者庁が2022年に実施した「ステルスマーケティングに関する実態調査」では、回答した消費者の約4割が「ステマと疑われる表示・広告に接したことがある」と回答しており、問題の深刻さが浮き彫りになりました。
(参照:消費者庁「ステルスマーケティングに関する実態調査報告書」)
また、海外に目を向けると、アメリカの連邦取引委員会(FTC)やイギリスの競争・市場庁(CMA)などは、以前からステマに対する厳しいガイドラインを設け、違反者には高額な罰金を科すなど、厳格な対応を取ってきました。こうした国際的な潮流も、日本国内での法整備を後押しする一因となりました。
これらの背景から、消費者を保護し、公正で透明性の高いデジタル広告市場を確立するため、日本でも法的な規制が必要であるという社会的コンセンサスが形成され、今回の景品表示法改正へと繋がったのです。ステマ規制は、広告であることを隠して消費者を欺く行為を取り締まり、誰もが安心して情報を信頼できる健全な市場環境を作るために不可欠なルールと言えるでしょう。
ステマ規制の対象者は誰?
ステマ規制が導入されたことで、「インフルエンサーとして活動している自分も罰せられるのか?」「アフィリエイトブログを運営しているが、大丈夫だろうか?」といった不安を抱く方も多いかもしれません。ここで最も重要なのは、法律が誰に対して責任を問い、罰則を科すのかを正確に理解することです。結論から言うと、規制の直接的なターゲットは広告を依頼する「事業者」です。
規制の対象は事業者(広告主)
景品表示法におけるステマ規制で、直接的な規制の対象となるのは「事業者(広告主)」です。事業者とは、商品やサービスを供給する側、つまりメーカー、販売業者、サービス提供会社などを指します。
なぜなら、景品表示法は、商品やサービスの「表示」に対する責任を、その表示内容の決定に関与した主体、すなわち事業者に負わせるという考え方に基づいているからです。たとえ広告の表示をインフルエンサーやアフィリエイターといった第三者に依頼した場合でも、その表示は事業者の「事業としての表示」の一部と見なされます。表示内容を最終的にコントロールしているのは、あくまで広告主である事業者である、という整理です。
例えば、化粧品メーカーがインフルエンサーに新商品のPRを依頼し、そのインフルエンサーが広告であることを隠して投稿した場合、景品表示法違反の責任を問われるのは、投稿を行ったインフルエンサーではなく、PRを依頼した化粧品メーカーとなります。
この仕組みは、規制の実効性を担保する上でも合理的です。無数の個人(インフルエンサーやブロガー)を個別に監視・摘発するのは現実的ではありません。それよりも、広告活動の源流である事業者に責任を集中させることで、事業者自身が主体的に、依頼する第三者に対して適切な表示を行うよう管理・監督することを促す効果が期待できます。したがって、事業者は自社の広告活動だけでなく、委託先の第三者が行う表示についても、自社の責任として管理する義務を負うことになります。
インフルエンサーやアフィリエイターは直接の対象外
では、広告の依頼を受けて実際に投稿を行うインフルエンサーや、アフィリエイトサイトを運営するアフィリエイター、広告代理店などはどうなるのでしょうか。
現行の景品表示法では、これらの第三者は規制の「直接の」対象者ではありません。つまり、ステマに該当する投稿を行ったとしても、消費者庁から措置命令を受けたり、課徴金を科されたりするのは、あくまで広告主である事業者です。
しかし、これは「インフルエンサーやアフィリエイターは何をしても問題ない」という意味では決してありません。法律上の直接的な罰則がないからといって、ステマに加担することのリスクは非常に大きいのです。具体的には、以下のような間接的なペナルティや不利益が考えられます。
- 広告主(事業者)との関係悪化・契約解除:
事業者が景品表示法違反で処分を受けた場合、その原因となった投稿を行ったインフルエンサーやアフィリエイターとの取引関係は悪化、もしくは解消される可能性が極めて高いでしょう。事業者側は、自社に損害を与えた相手と取引を継続したいとは考えません。 - フォロワーや読者からの信頼失墜(炎上リスク):
インフルエンサーやブロガーにとって、フォロワーや読者からの「信頼」は何よりの資産です。ステマを行っていたことが発覚すれば、「お金のためにファンを騙していた」と見なされ、一瞬で信頼を失います。一度失った信頼を回復するのは非常に困難であり、いわゆる「炎上」状態となって活動の継続が難しくなるケースも少なくありません。 - プラットフォームからのペナルティ:
アフィリエイトの場合、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)は利用規約でステマ行為を禁止していることがほとんどです。規約違反が発覚すれば、ASPから提携を解除されたり、アカウントを停止されたりする可能性があります。 - 事業者からの損害賠償請求:
広告代理店やインフルエンサーが、広告主である事業者の指示(例:「必ず広告であることを明記してください」)に反してステマを行った結果、事業者が消費者庁から処分を受けた場合、事業者は被った損害(課徴金、信頼失墜による売上減など)について、広告代理店やインフルエンサーに対して損害賠償を請求する可能性があります。
以下の表は、各関係者の立場と責任を整理したものです。
| 関係者 | 景品表示法上の規制対象か | 負う可能性のある責任・リスク |
|---|---|---|
| 事業者(広告主) | 直接の対象 | 措置命令、企業名公表、課徴金、刑事罰 |
| インフルエンサー | 直接の対象ではない | 広告主との契約解除、フォロワーからの信頼失墜、炎上リスク |
| アフィリエイター | 直接の対象ではない | ASPからの提携解除、広告主からの契約解除、サイトの評価低下 |
| 広告代理店 | 直接の対象ではない(※) | 広告主からの損害賠償請求、社会的信用の失墜 |
(※)ただし、広告代理店が広告内容の決定に実質的に深く関与し、事業者と一体と見なされるような悪質なケースでは、事業者と同様に扱われる可能性もゼロではありません。
結論として、法律上の直接的な罰則は事業者に課されますが、インフルエンサーやアフィリエイターも間接的に大きな影響を受けるため、事業者と協力して適切な表示を行う社会的・倫理的な責任があると理解することが重要です。
規制対象となる広告の2つの判断基準
どのような表示がステマ規制の対象となるのか。消費者庁が公表している運用基準では、2つの重要な判断基準が示されています。規制対象となるには、「① 事業者の表示(広告)であること」と「② 事業者の表示であることが消費者にとって分かりにくいこと」の両方の要件を満たす必要があります。どちらか一方だけでは、規制の対象とはなりません。この2つの基準を正しく理解することが、意図せぬ違反を防ぐ鍵となります。
① 事業者の表示(広告)であること
第一の基準は、その表示が「事業者の表示」と見なされるかどうかです。これは、事業者が自社のウェブサイトやSNSアカウントで行う表示だけを指すのではありません。第三者(インフルエンサー、ブロガー、一般消費者など)による表示であっても、事業者がその表示内容の決定に関与したと認められる場合は、「事業者の表示」と判断されます。
ポイントは、「事業者が表示内容の決定に関与したか」という実態です。形式的に誰が投稿したかではなく、その裏に事業者の意図や働きかけがあるかどうかが問われます。消費者庁のガイドラインでは、以下のような場合に「事業者の表示」と判断されうることが示されています。
1. 事業者が第三者に明示的に依頼・指示している場合
これは最も分かりやすいケースです。事業者と第三者との間で、広告・宣伝を目的とした明確なコミュニケーションが存在する場合です。
- 具体例:
- メールやDMで「この商品について、このような長所を強調してSNSに投稿してください」と依頼する。
- インフルエンサーとの間で、投稿内容、投稿日時、使用するハッシュタグなどを定めた契約書を交わす。
- 投稿に対して金銭的な報酬を支払う。
- アフィリエイトプログラムを通じて、特定の商品の紹介を依頼し、成果に応じた報酬を支払う。
2. 事業者による明確な依頼・指示がなくても、実態から判断される場合
直接的な指示がなくても、客観的な状況から見て、第三者が事業者の意図を汲んで表示を行ったと判断されるケースも含まれます。
- 具体例:
- 事業者から無償で商品を提供されたインフルエンサーが、ネガティブな内容を投稿しないよう事業者側から示唆されている(あるいは、そうしなければ今後の関係に悪影響が出るとインフルエンサーが認識している)。
- 事業者がインフルエンサーに対し、商品やサービスに関する詳細な説明資料を提供し、その内容に沿った投稿を期待していることがうかがえる。
- SNSキャンペーンなどで、「〇〇(商品名)の好きなところ」をテーマに投稿を募集し、優れた投稿に高額な景品を提供する場合。この場合、応募者は好意的な内容を投稿するよう実質的に誘導されていると見なされる可能性があります。
3. 事業者と第三者の間に社会通念上、一体と見なせる関係性がある場合
表示を行う第三者が、事業者と密接な関係にある場合も「事業者の表示」と見なされます。
- 具体例:
- 事業者の子会社の従業員が、その身分を隠して親会社の商品を褒める投稿をする。
- 業務委託契約など、事業者の事業に深く関与している関係者が、その関係性を明らかにせずに宣伝行為を行う。
4. 事業者が第三者の表示を自社の宣伝として利用する場合
第三者が自発的に行った表示であっても、事業者がそれを自社の広告として積極的に活用した場合は、その時点で「事業者の表示」と見なされることがあります。
- 具体例:
- 一般ユーザーの好意的な投稿を、事業者が許諾を得て自社の広告物(ウェブサイト、パンフレットなど)に「お客様の声」として転載する。
- ただしこの場合、転載時に「個人の感想です」と注釈を入れたり、広告であることが文脈上明らかな場所に掲載したりすれば、後述の「分かりにくい表示」には該当しないため、問題とはなりません。
重要なのは、金銭の授受の有無だけが判断基準ではないという点です。無償の商品提供、サービスの割引、イベントへの招待といった経済的な利益の供与も、投稿を依頼するための「対価」と見なされ、事業者の関与を示す一因となり得ます。
② 事業者の表示であることが消費者にとって分かりにくいこと
第一の基準である「事業者の表示」に該当したとしても、それだけではステマ規制の対象にはなりません。その上で、「事業者の表示であることが、一般の消費者にとって分かりにくいこと」という第二の基準を満たす必要があります。
言い換えれば、たとえ企業がお金を払ってインフルエンサーに宣伝を依頼したとしても、その投稿を見た消費者が「これは広告だな」と正しく認識できる状態であれば、それはステマではなく、正当な広告活動として認められます。問題となるのは、広告であるという事実を隠したり、消費者が気づきにくいように表示したりするケースです。
では、「分かりにくい表示」とは具体的にどのようなものでしょうか。
- 「広告」「PR」といった文言が全くない:
最も典型的な違反例です。事業者の依頼であることが一切示されていません。 - 広告表記が消費者に認識できないほど不明瞭:
形式的に「広告」と表示していても、消費者がそれを認識できなければ意味がありません。- 表示位置が不適切: 大量のハッシュタグの羅列の中に「#PR」を紛れ込ませる。「続きを読む」をクリックしないと見えない場所に記載する。
- 表示が小さすぎる、色が薄い: 背景に溶け込むような薄い色の文字で記載したり、判読困難なほど小さなフォントサイズで表示したりする。
- 表示時間が短い: 動画広告で、冒頭や末尾に一瞬だけ「この動画はプロモーションを含みます」と表示する。
- 分かりにくい言葉を使っている: 「タイアップ」などの言葉は、一定の知識がある人には伝わりますが、全ての消費者が広告を意味すると理解できるとは限りません。より直接的な「広告」「宣伝」といった言葉を使うのが望ましいとされています。
- 広告であることを否定するような表現との併用:
「これは広告です」と表示しつつも、「あくまで個人の感想ですが…」「忖度なしのガチレビュー!」といった文言を併記することで、広告であるという事実を曖昧にしようとする表示。 - 第三者を装ったなりすまし:
事業者の従業員が、身分を隠して一般消費者を装い、口コミサイトに投稿するようなケース。これは表示上、事業者の広告であるとは全く分かりません。
結局のところ、「事業者が関与している(①)にもかかわらず、その事実を隠したり、分かりにくくしたりしている(②)場合」に、ステマ規制の対象となる、という2つの要件をセットで理解することが極めて重要です。この両方を満たしたときに初めて、景品表示法違反の「不当表示」が成立します。
規制対象とならないケース
ステマ規制は、全ての広告や口コミを禁止するものではありません。むしろ、正当な広告活動や消費者の自由な意見表明を保護し、悪質な行為だけを排除することを目的としています。したがって、規制の対象とならない「セーフ」なケースを理解することも、事業者や情報発信者にとっては非常に重要です。主に、「消費者が自主的に行う投稿」と「広告であることが社会通念上明らかな表示」の2つが、規制の対象外となります。
消費者が自主的に行う投稿
ステマ規制の根幹にあるのは、「事業者の表示内容への関与」を問う点です。逆に言えば、事業者の関与が一切ない、純粋に消費者が自らの意思で行う投稿は、規制の対象には全く含まれません。 この点は、消費者の自由な表現活動を萎縮させないために、非常に重要な原則です。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 自分で購入・利用した商品やサービスへの感想:
ある消費者が、自腹でレストランに行き、その料理やサービスの感想を個人のSNSアカウントやグルメサイトに投稿する。これは、事業者からのいかなる依頼も受けていないため、規制の対象外です。たとえその内容が絶賛するものであっても、あるいは酷評するものであっても、それは個人の自由な意見表明として尊重されます。 - 事業者からの依頼や対価がない投稿:
アパレルブランドの展示会に招待されたブロガーが、特に事業者から投稿を依頼されたわけでもなく、報酬も受け取らずに、自らの意思で「素敵な新作がたくさんありました」とブログに書く。この場合、事業者の「表示内容の決定への関与」がないため、「事業者の表示」とは見なされず、規制対象外となります。 - 内容の指示がない物品提供の場合:
少し判断が難しいのが、事業者から無償で商品サンプルを受け取ったケースです。この場合でも、事業者側がその後の情報発信(投稿)について、内容やタイミングに関する指示・依頼を一切行わず、投稿するかどうかも含めて完全に個人の自由に委ねているのであれば、「事業者の表示」には該当しないと判断される可能性があります。
ただし、この点はグレーゾーンになりがちです。事業者側からすれば「良い感想を投稿してくれるだろう」という期待が、受け取った側からすれば「何か投稿しないと申し訳ない」という心理的なプレッシャーが働き、実質的に事業者の意図が反映される可能性があるからです。
そのため、たとえ法的に「セーフ」と判断される可能性があるとしても、消費者との信頼関係を維持する観点からは、「#商品提供」「#サンプルレビュー」のように、事業者から物品提供があった事実を自主的に明記することが強く推奨されます。 このような透明性の高い姿勢が、結果的に情報発信者自身の信頼性を高めることに繋がります。
要するに、ステマ規制は「企業の金で動いているのに、それを隠して消費者を騙す」行為を取り締まるものであり、消費者が自発的に発信する声(UGC)を制限するものでは断じてないのです。
広告であることが社会通念上明らかな表示
もう一つの対象外となるケースは、「事業者の表示」ではあるものの、その表示が広告であることが社会の常識として誰の目にも明らかである場合です。これは、ステマ規制の要件②「事業者の表示であることが消費者にとって分かりにくいこと」に該当しないためです。わざわざ「これは広告です」と断るまでもなく、その形式や媒体からして、誰もが宣伝だと理解できる表示がこれにあたります。
社会通念上、広告であることが明らかな表示の具体例は以下の通りです。
- テレビ、ラジオ、新聞、雑誌の広告:
番組の合間に流れるCMや、新聞・雑誌の広告枠に掲載されている情報は、古くから確立された広告媒体であり、消費者はそれを事業者の宣伝として認識しています。 - 事業者の公式サイト、公式SNSアカウント、公式ブログでの情報発信:
「〇〇株式会社」の公式サイトや、「【公式】〇〇」といった名前のSNSアカウントで発信される商品情報は、その事業者自身による宣伝であることが自明です。消費者は、その情報が事業者側の視点から発信されていることを理解した上で閲覧します。 - ECサイト内の自社店舗ページ:
Amazonや楽天市場などのECモールに出店している事業者が、自社の店舗ページ内で商品説明を行う場合。これも、販売者自身による宣伝であることが明確です。 - 街頭の看板やデジタルサイネージ、交通広告:
駅や電車内、ビルの壁面などに設置されている広告も、事業者の宣伝であることが一目瞭然です。 - 事業者が配信するプレスリリース:
企業がメディア関係者に向けて新製品や新サービスを発表する公式文書(プレスリリース)も、企業の広報・宣伝活動の一環であることが社会的に認知されています。
ただし、これらの「広告であることが明らかな媒体」であっても、注意が必要なケースがあります。例えば、事業者の公式サイト内に設けられた「愛用者の声」というコーナーが、実際には金銭を支払って第三者に書かせたものであるにもかかわらず、その事実を隠してあたかも自発的な感想であるかのように掲載した場合、それは「なりすまし型」のステマに該当する可能性があります。媒体が公式サイトであっても、その中の一つのコンテンツが消費者を欺く手法で作られていれば、規制の対象となりうるのです。
結論として、「事業者の関与がない純粋な個人の感想」と「誰が見ても広告とわかる表示」は、ステマ規制の対象外であると整理できます。事業者は、自社のマーケティング活動がこれらのどちらかに該当しない場合、広告であることを明確に表示する義務があると認識する必要があります。
ステマ規制に違反した場合の罰則・ペナルティ
ステマ規制は景品表示法の一部であるため、違反した場合には同法に基づいた厳しい措置が取られます。多くの事業者が最も懸念するのは、このペナルティの内容でしょう。違反した場合のリスクは、単なる罰金の支払いに留まりません。企業名が公表されることによる社会的信用の失墜という、非常に深刻なダメージを受ける可能性があります。ここでは、具体的な罰則・ペナルティの内容を3つの段階に分けて解説します。
措置命令と企業名の公表
消費者庁または都道府県が、景品表示法違反(この場合はステマ)の事実を認定した場合、まず事業者に対して「措置命令(そちめいれい)」という行政処分を下します。措置命令は、違反行為を是正し、再発を防止するための具体的な行動を命じるものです。その内容は主に以下の通りです。
- 違反行為の差止め:
現在行われているステマに該当する表示を、直ちに中止・撤回することが命じられます。 - 一般消費者への周知徹底(お詫び広告など):
事業者が不当な表示を行っていた事実を、一般の消費者に広く知らせることが求められます。多くの場合、全国紙などの新聞に「お詫び広告」を掲載する方法が採られます。これは事業者にとって大きな経済的負担となるだけでなく、自社の過ちを公に認めることになり、ブランドイメージを著しく損ないます。 - 再発防止策の実施:
同様の違反行為を二度と起こさないために、具体的な再発防止策を策定し、実行することが命じられます。例えば、社内での景品表示法に関する研修の実施、広告表示に関するチェック体制の構築、従業員向けのガイドラインの策定などが含まれます。
そして、措置命令が下された場合、原則としてその事実が消費者庁のウェブサイトで公表されます。 公表される情報には、違反した事業者名、商品・サービス名、違反表示の概要、措置命令の内容などが含まれます。
(参照:消費者庁「景品表示法に基づく措置命令」)
これが、事業者にとって最も恐ろしいペナルティと言えます。一度「ステマ企業」として名前が公になると、その事実はインターネット上に半永久的に残り続けます。これにより、以下のような深刻な経営的ダメージを受けるリスクがあります。
- レピュテーションリスク: 社会的信用が失墜し、ブランドイメージが大きく低下する。
- 顧客離れ: 消費者や取引先からの信頼を失い、売上が減少する。
- 株価下落: 上場企業の場合、株価に悪影響が及ぶ可能性がある。
- 人材採用への悪影響: 企業の評判が悪化し、優秀な人材の確保が困難になる。
課徴金納付命令
措置命令に加えて、違反内容が悪質な場合には「課徴金納付命令」が出されることがあります。これは、不当表示によって事業者が得た不当な利益を国庫に納付させる、金銭的な制裁です。
ただし、ここで注意が必要なのは、ステマ(広告であることを隠す行為)自体が、直接的に課徴金の対象となるわけではないという点です。課徴金の対象となるのは、あくまで従来の「優良誤認表示」と「有利誤認表示」です。
つまり、ステマという「手段」を用いて、商品の内容(品質)や取引条件(価格)について消費者を欺く「優良誤認表示」や「有利誤認表示」を行った場合に、課徴金が科されることになります。
- 例1(優良誤認+ステマ): 効果が実証されていないサプリメントについて、インフルエンサーに依頼し、広告であることを隠して「これを飲んだら1ヶ月で10kg痩せた!」といった、商品の効果を著しく過大に見せる投稿をしてもらう。
- 例2(有利誤認+ステマ): 実際には高額な追加料金が必要なサービスについて、アフィリエイターに依頼し、広告であることを隠して「月額1,000円ポッキリで全機能が使える!」といった、取引条件を著しく有利に見せるレビュー記事を書いてもらう。
課徴金の額は、原則として、違反行為が行われた期間中(最大3年間)の対象商品・サービスの売上額の3%と定められています。売上規模の大きな商品であれば、課徴金額は数千万円から数億円に上る可能性もあります。
なお、事業者が消費者庁の調査が入る前に、違反の事実を自主的に報告(自主申告)した場合には、課徴金額が2分の1に減額される制度があります。これは、事業者の自浄作用を促すためのインセンティブとなっています。
刑事罰の可能性
景品表示法には、行政処分だけでなく刑事罰も規定されています。ただし、これが適用されるのは極めて限定的なケースです。
具体的には、事業者が出された「措置命令」に正当な理由なく従わなかった場合に、刑事罰の対象となります。
罰則の内容は、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり)」、そして法人に対してはより重い「3億円以下の罰金」が科される可能性があります。
(参照:不当景品類及び不当表示防止法 第三十六条、第三十八条)
現状、ステマ規制違反が発覚して、直ちに刑事罰が科されるという可能性は低いと考えられます。しかし、消費者庁からの度重なる指導や命令を無視するような、極めて悪質な事業者に対しては、最終手段として刑事罰が適用されうる、ということは念頭に置いておくべきです。
まとめると、ステマ規制に違反した場合のペナルティは、「措置命令と企業名公表による信用の失墜が最大のダメージであり、内容によっては多額の課徴金や刑事罰につながるリスクもある」と理解しておく必要があります。事業者にとって、規制遵守はもはや単なるコンプライアンス課題ではなく、事業の存続そのものに関わる重要な経営課題なのです。
事業者がやるべきステマ規制対策5選
ステマ規制への対応は、マーケティングや広報部門だけの問題ではありません。経営層から現場の従業員、さらには外部の協力者に至るまで、全社的に取り組むべき重要な課題です。ここでは、事業者が意図せず規制に違反してしまうことを防ぎ、消費者との健全な信頼関係を築くために実施すべき具体的な対策を5つ紹介します。
① 「広告」「PR」などを分かりやすく表示する
最も基本的かつ効果的な対策は、事業者が関与する表示には、それが広告であることを消費者に分かりやすく明記することです。これは、ステマ規制の核心である「事業者の表示であることが消費者にとって分かりにくいこと」という要件を回避するための直接的な手段です。
消費者庁のガイドラインでも、以下のような対応が推奨されています。
- 明確な文言の使用:
「広告」「PR」「宣伝」「プロモーション」といった、誰が見ても広告・宣伝であることが直接的に伝わる言葉を選びましょう。「タイアップ」といった言葉は業界用語に近く、全ての消費者に伝わるとは限らないため、より平易な言葉との併記が望ましいです。また、「〇〇社から商品の提供を受けて投稿しています」のように、関係性を具体的に記述するのも非常に有効です。 - 分かりやすい場所への表示:
表示する位置も重要です。SNSの投稿であれば、消費者が最初に目にする投稿文の冒頭に記載するのが最も確実です。「続きを読む」を押さないと見えない場所や、大量のハッシュタグの末尾に埋もれさせるような表示は「分かりにくい」と判断されるリスクがあります。 - 媒体に応じた適切な表示方法:
動画であれば、動画の冒頭や、視聴中に常に表示されるテロップなどに入れるのが効果的です。ライブ配信の場合は、配信者が口頭で繰り返し「この配信は〇〇社の提供でお送りしています」と伝えることも有効です。 - SNSプラットフォーム機能の活用:
Instagramの「タイアップ投稿(ブランドコンテンツ)」ラベルや、YouTubeの「プロモーションを含みます」チェックボックスなど、各SNSプラットフォームが公式に提供している広告表示機能を積極的に活用しましょう。これらの機能を使うことで、統一されたフォーマットで広告であることを明示でき、消費者にも伝わりやすくなります。
「広告」と表示することで消費者に敬遠されるのではないか、という懸念を持つ事業者もいますが、むしろ逆です。情報を隠すような不誠実な態度は、発覚した際に信頼を大きく損ないます。一方で、正直に広告であることを示す透明性の高い姿勢は、長期的には消費者からの信頼獲得に繋がります。
② 第三者との関係性を明記する
インフルエンサーやブロガーに商品やサービスの紹介を依頼する場合、その関係性を明確にすることも重要です。前述の「広告」「PR」の表示に加えて、どのような関係性のもとで情報発信が行われているのかを具体的に示すことで、より透明性が高まります。
- 金銭の授受がある場合: 「〇〇社とのタイアップ企画です」「本記事はプロモーションを含みます」
- 物品提供のみの場合: 「〇〇(商品名)は△△社様からご提供いただきました」「#商品提供」
- イベント招待の場合: 「〇〇社の新作発表会にご招待いただきました」
特に、金銭的な報酬はなくても商品提供やイベント招待がある場合は、それが投稿の動機になっていると消費者に誤解を与えないよう、関係性を正直に開示することが望ましい対応です。このような誠実な姿勢は、インフルエンサー自身の信頼性を守ることにも繋がります。
③ 社内や関係者へのルールを周知徹底する
ステマ規制への対応は、一部の担当者だけが知識を持っていれば良いというものではありません。経営層から全ての従業員、そして広告代理店やインフルエンサーといった外部の協力者まで、関わる全員が規制の重要性を理解し、共通のルールのもとで行動することが不可欠です。
- 社内研修の実施:
定期的に全社、あるいは関連部署を対象とした景品表示法・ステマ規制に関する研修会を実施し、知識のアップデートと意識の向上を図りましょう。違反した場合のリスクや、具体的なOK/NG事例を共有することが効果的です。 - 外部パートナーへの説明と契約への明記:
広告代理店やインフルエンサー、アフィリエイターと契約する際には、ステマ規制の内容を丁寧に説明し、理解を求めることが重要です。さらに、契約書や発注書の中に「景品表示法を遵守し、事業者の表示である旨を消費者に分かりやすく表示すること」といった条項を明確に盛り込み、法規制の遵守を義務付けましょう。万が一、パートナーがこの義務に違反した場合には、契約を解除できるような取り決めをしておくこともリスク管理の一環です。
④ 従業員のSNS投稿ガイドラインを策定する
従業員が個人的に使用しているSNSアカウントも、ステマのリスク源となり得ます。例えば、従業員が善意から自社製品を個人のアカウントで紹介したとしても、会社の業務指示があったとみなされたり、あるいは会社の利益のために投稿していると判断されたりすれば、「事業者の表示」と見なされる可能性があります。
こうした意図せぬ違反を防ぐために、従業員のSNS利用に関する明確なガイドラインを策定し、周知徹底することが極めて重要です。ガイドラインには、以下のような項目を盛り込むと良いでしょう。
- 基本原則: 個人の発信が会社の評判に影響を与える可能性があることの認識。
- 身分の明示: 業務に関連する内容を発信する際は、会社の従業員であることをプロフィールなどで明記する。
- 広告表示の義務: 会社の指示や依頼で投稿する場合は、必ず「#PR」「#広告」などを付け、会社との関係性を明記する。
- 個人的な投稿のルール: 個人的な意見として投稿する場合でも、それが会社の公式見解ではないことを明確にする(例:「個人の感想です」)。
- 禁止事項: 未公開情報、機密情報、顧客情報、他社への誹謗中傷などの投稿を厳禁とする。
- 炎上時の対応: 問題が発生した場合は、速やかに上長や担当部署に報告する。
⑤ キャンペーンの投稿ルールを明確にする
「#〇〇(商品名)をつけて投稿すれば、抽選でプレゼント!」といった、ユーザー投稿型のSNSキャンペーンも注意が必要です。このようなキャンペーンへの投稿は、プレゼントというインセンティブ(対価)によって投稿を促しているため、個々のユーザーの投稿が「事業者の表示」と見なされる可能性があります。
そのため、キャンペーンを実施する際には、応募要項などに以下の点を明記し、参加者に遵守を求めることが重要です。
- 投稿が広告宣伝に利用される旨の明示: 「投稿いただいた内容は、当社の広告宣伝物(ウェブサイト、SNSなど)に利用させていただく場合があります」といった注意書きを入れる。
- 広告・キャンペーンであることの表示依頼: 投稿に「#〇〇キャンペーン」「#プロモーション」など、広告やキャンペーン参加を目的とした投稿であることが分かるハッシュタグを含めてもらうよう、ルールとして設定する。
これらの対策を講じることで、キャンペーン投稿がステマ規制に抵触するリスクを大幅に低減できます。
【シーン別】注意すべき広告表示の具体例
ステマ規制の理論を理解しても、実際のマーケティング活動でどのように判断すればよいか迷う場面は少なくありません。ここでは、事業者が特に関わることが多い4つのシーンを想定し、規制に抵触する可能性のあるNG例と、適切な対応であるOK例を具体的に比較しながら解説します。
SNSでの商品紹介
インフルエンサーマーケティングが主流となる中、SNSでの商品紹介は最も注意が必要なシーンです。
- NG例:
化粧品メーカーが、美容系インフルエンサーに1投稿10万円の報酬を支払って新製品のファンデーションのPRを依頼。インフルエンサーは、報酬を受け取っている事実を一切隠し、「#運命のファンデ に出会った…!カバー力もツヤ感も最高すぎる。これはリピ確定。#コスメ購入品 #愛用コスメ」といったキャプションと、大量のハッシュタグのみで投稿した。- 【問題点】 事業者からの明示的な依頼と対価の支払いがあるため「事業者の表示」に該当します。しかし、投稿には「#PR」などの広告表記がなく、あたかもインフルエンサーが自発的に見つけて愛用しているかのように装っているため、「事業者の表示であることが消費者にとって分かりにくい」状態です。これは典型的なステマです。
- OK例:
同じく化粧品メーカーがインフルエンサーにPRを依頼。インフルエンサーは、投稿文の冒頭に「【〇〇(企業名)様ご提供】」または「#PR」と明確に記載した上で、「〇〇(企業名)から新発売のファンデーションをお試しさせていただきました!少量で伸びが良くて、気になる毛穴をしっかりカバーしてくれます…」とレビューを投稿した。さらに、Instagramの「タイアップ投稿」機能を使い、「〇〇(企業名)とのタイアップ投稿」というラベルを表示させた。- 【適切な点】 事業者の表示であることを、投稿文の冒頭、ハッシュタグ、そしてプラットフォームの公式機能という複数の方法で、消費者に分かりやすく伝えています。これにより、消費者は広告であることを認識した上で情報を評価できるため、ステマには該当しません。
アフィリエイトサイトやブログでのレビュー
アフィリエイトは、成果報酬型の広告手法として広く利用されていますが、ここでも透明性が求められます。
- NG例:
あるブロガーが、複数の動画配信サービスを比較するランキング記事を作成。記事内には各サービスへのアフィリエイトリンクが設置されているが、その事実については一切触れていない。さらに、実際にはサービスの優劣に関わらず、アフィリエイト報酬単価が最も高いサービスを「総合評価第1位!最もおすすめ!」と紹介していた。- 【問題点】 アフィリエイトリンクを設置している時点で、事業者の広告プログラムに参加しており、「事業者の表示」と見なされます。広告であることを隠し、中立的なレビューを装っているため「分かりにくい表示」に該当します。さらに、報酬額に基づいてランキングを操作しているとすれば、優良誤認表示にも問われる可能性がある悪質なケースです。
- OK例:
ブロガーは、記事の冒頭(ファーストビュー)に「この記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)が含まれています」と、枠で囲むなどして目立つように表示した。その上で、各サービスのメリット・デメリットを客観的な視点で比較し、ランキングの根拠(「料金の安さ」「作品数の多さ」など)を明確に示した。- 【適切な点】 記事が広告収益を目的としていることを冒頭で正直に開示しているため、読者はその前提で情報を読むことができます。これにより「分かりにくい表示」ではなくなり、ステマ規制をクリアできます。
口コミサイトやECサイトでの高評価レビュー
いわゆる「サクラレビュー」や「やらせ口コミ」は、ステマの典型例として厳しく監視されています。
- NG例:
あるECサイトに出店している健康食品販売業者が、クラウドソーシングサイトで「当社の商品に星5つのレビューを書いてくれたら1件500円」といった内容でライターを募集。その結果、実際には商品を使用していない複数のワーカーによって、絶賛する内容の高評価レビューが多数投稿された。- 【問題点】 事業者が対価を支払ってレビュー投稿を依頼しているため「事業者の表示」です。投稿者は一般購入者を装っており、広告・依頼であることが全く分からないため「分かりにくい表示」です。これは悪質ななりすまし型のステマであり、消費者の判断を著しく誤らせる行為です。
- OK例:
ECサイトの事業者が、商品発送時の案内状に「商品をお使いいただき、よろしければレビューのご投稿にご協力ください」と記載したチラシを同封した。レビュー投稿は任意であり、内容(評価の高低)は購入者の自由に委ねられていることを明記した。特典としてクーポンを付ける場合も「レビュー投稿いただいた方全員に」とし、高評価を条件にしなかった。- 【適切な点】 レビュー投稿を「お願い」するに留め、内容をコントロールしようとしていないため、投稿されたレビューは「事業者の表示」とは見なされにくいです。高評価を条件としないインセンティブの提供は、一般的に許容される販売促進活動の範囲内と解釈されます。
従業員による自社製品の紹介
従業員の善意の投稿が、意図せずステマと判断されるリスクにも配慮が必要です。
- NG例:
ソフトウェア開発会社の営業部長が、個人のX(旧Twitter)アカウントで、自身の身分を明かさずに「最近話題の〇〇(自社サービス名)、使ってみたけどマジで神。業務効率が爆上がりした。これ使わないとかありえない」と、一般ユーザーを装って投稿した。- 【問題点】 従業員による投稿は、会社の利益に繋がるため「事業者の表示」と見なされる可能性が高いです。身分を隠しているため「分かりにくい表示」に該当し、なりすまし型のステマと判断されるリスクがあります。
- OK例:
同じ営業部長が、プロフィールに「〇〇株式会社で営業部長をしています」と明記した上で、「自社製品の宣伝で恐縮ですが…(笑) #PR 当社の〇〇(サービス名)、特に△△の機能が便利で、お客様からも好評です!ご興味ある方はぜひ!」と投稿した。- 【適切な点】 自身の所属と役職を明かし、さらに「#PR」と付けることで、会社との関係性と広告宣伝の意図があることを明確にしています。これにより、透明性が担保され、ステマには該当しません。
ステマ規制に関するよくある質問
ステマ規制に関して、事業者や個人の情報発信者が抱きがちな疑問について、Q&A形式で解説します。
規制開始前の投稿も対象になりますか?
はい、対象になる可能性があります。
ステマ規制は2023年10月1日に施行されましたが、その効力は「施行日以降に消費者が見ることができる表示」に対して及びます。したがって、たとえ投稿されたのが規制開始前(2023年9月30日以前)であっても、施行日である10月1日以降もインターネット上で公開され続けている場合は、規制の対象となります。
例えば、2022年にインフルエンサーに依頼して行われたステマ投稿が、削除や修正をされずに2023年10月1日以降もブログやSNS上で閲覧可能な状態になっていれば、それは景品表示法違反と見なされる可能性があります。
そのため、事業者は過去に遡って自社が関与した第三者による表示(インフルエンサー投稿、アフィリエイト記事、口コミなど)を総点検し、ステマに該当するおそれのあるものについては、速やかに「広告」「PR」といった表示を追加するか、あるいは投稿自体を削除・非公開にするといった対応を取る必要があります。
個人が自主的にSNSで感想を投稿しても対象になりますか?
いいえ、対象になりません。
この点は多くの人が心配するポイントですが、明確に「対象外」です。ステマ規制が問題にしているのは、あくまで「事業者が関与しているにもかかわらず、広告であることを隠す表示」です。
個人が、事業者からのいかなる依頼や指示、対価の提供も受けることなく、完全に自らの意思と判断で、自分で購入した商品や利用したサービスについて感想をSNSやブログに投稿する行為は、純粋なUGC(ユーザー生成コンテンツ)であり、消費者の自由な意見表明として尊重されます。
その内容が商品を絶賛するものであっても、あるいは厳しい批判であっても、事業者の関与がない限り、景品表示法上の問題が生じることは一切ありません。ステマ規制は、消費者の自由な口コミ活動を萎縮させるためのものではないのです。
プレゼント企画の当選者による投稿は対象になりますか?
はい、対象となる可能性が高いと考えられます。
「当社の新商品を抽選で100名様にプレゼント!当選した方は、商品の感想をSNSに投稿してください」といったプレゼントキャンペーンは、慎重な対応が求められます。
この場合、当選者に対して提供される「プレゼント(商品)」が、投稿をしてもらうための「対価(経済上の利益)」と見なされる可能性があります。そして、当選者にSNS投稿を義務付けている場合、それは事業者が投稿内容の決定に(少なくとも投稿するという行為自体に)関与していると判断され、「事業者の表示」に該当する可能性が非常に高くなります。
もし当選者が、事業者との関係性(プレゼント企画の当選者であること)を明示せずに、あたかも自腹で購入したかのように感想を投稿した場合、それは「事業者の表示であることが消費者にとって分かりにくい」状態となり、ステマ規制に抵触するおそれがあります。
このリスクを避けるためには、事業者側がキャンペーンのルールとして、当選者に以下のような対応を求めるのが賢明です。
- 投稿の際には、必ず「#〇〇プレゼントキャンペーンに当選」「#プロモーション」など、キャンペーンによる投稿であることが分かるハッシュタグや文言を入れてもらう。
- 投稿内容は当選者の自由な感想に委ね、好意的な内容を書くことを強要しない。
このように、事業者と投稿者の関係性を明確にすることで、透明性を確保し、ステマ規制違反のリスクを回避することができます。
まとめ
本記事では、2023年10月1日から施行されたステマ規制について、その定義から対象者、判断基準、罰則、そして事業者が取るべき具体的な対策までを網羅的に解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを改めて確認しましょう。
- ステマ規制とは: 広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為を禁止する、景品表示法の新しいルールです。
- 規制の対象者: 法律上の直接的な責任を負うのは、広告を依頼した「事業者(広告主)」です。インフルエンサーやアフィリエイターは直接の罰則対象ではありませんが、信頼失墜や契約解除といった重大なリスクを負います。
- 規制対象の判断基準: ①事業者が表示内容の決定に関与しており、かつ②その事実が消費者にとって分かりにくいという、2つの要件を両方満たした場合に規制対象となります。
- 違反した場合のペナルティ: 主に「措置命令」と「企業名の公表」が行われ、社会的信用に深刻なダメージを与えます。内容によっては多額の「課徴金」が科されることもあります。
- 事業者がやるべき対策: 「広告」「PR」の分かりやすい表示を徹底することが最も重要です。それに加え、関係性の明記、社内・関係者へのルール周知、従業員向けガイドラインの策定、キャンペーンルールの明確化などが不可欠です。
ステマ規制の導入は、日本のデジタルマーケティングにおける大きな転換点です。これまでグレーゾーンとされてきた行為が明確に禁止されたことで、事業者にはより一層、誠実で透明性の高いコミュニケーションが求められるようになりました。
一見、事業者にとっては厳しい規制に思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、これは大きなチャンスでもあります。ステマ規制は、短期的な売上よりも、消費者との長期的な信頼関係を重視する時代の要請です。
事業者、インフルエンサー、そして私たち消費者が一体となって、透明性の高い情報発信を当たり前の文化として根付かせていくこと。それこそが、公正で健全なデジタル市場を創造し、ひいては自社のブランド価値を守り、育てていくための最も確実な道筋と言えるでしょう。