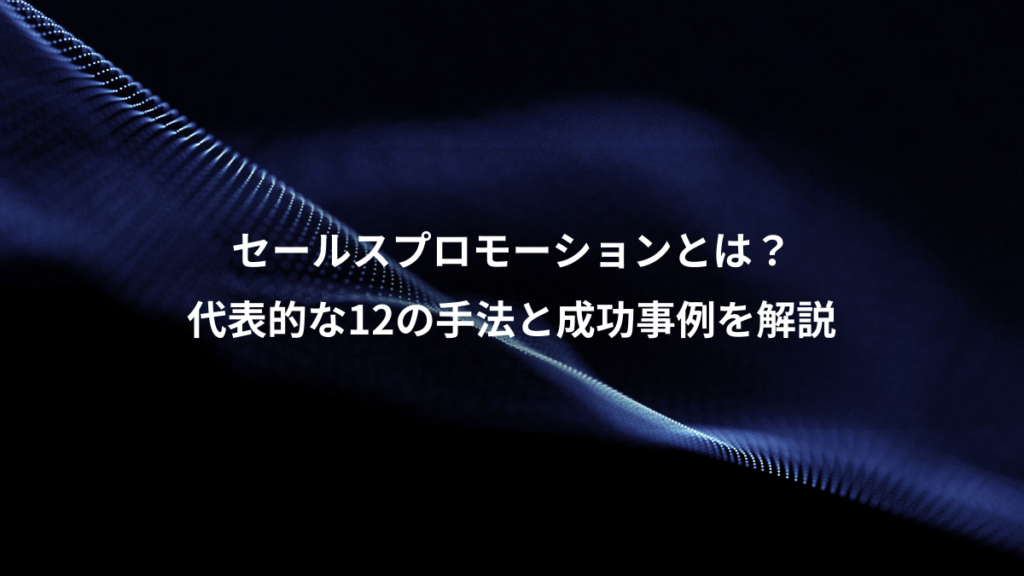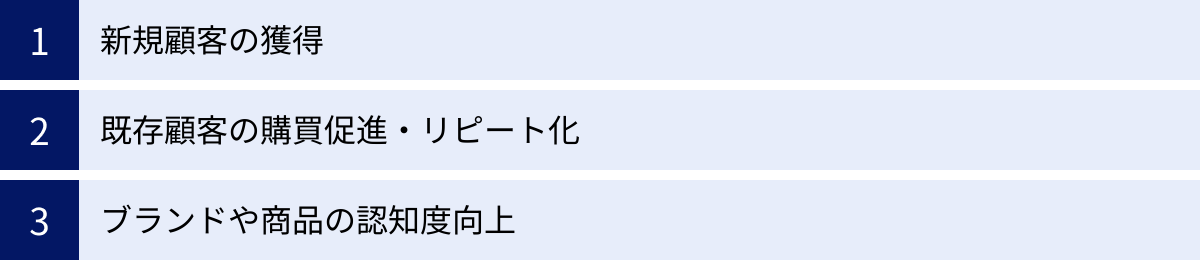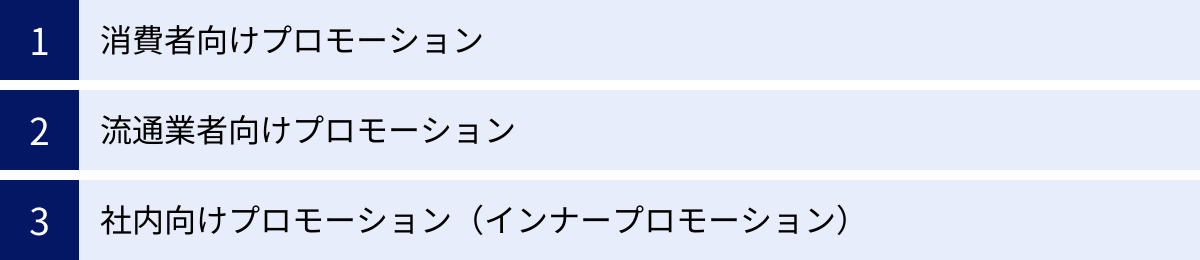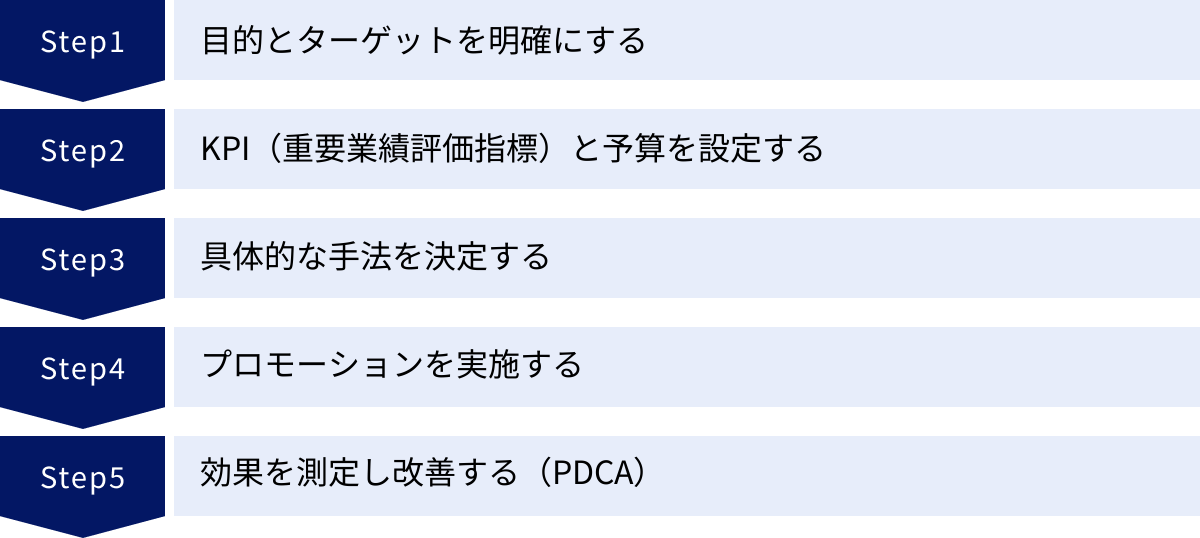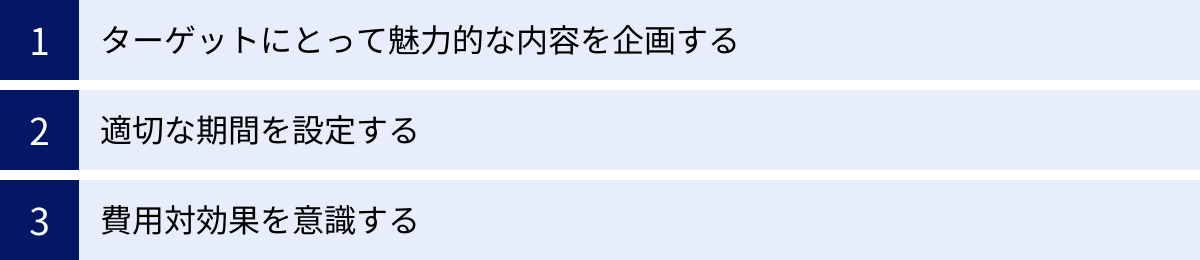企業の売上向上や顧客獲得において、戦略的なアプローチは不可欠です。数あるマーケティング手法の中でも、消費者の購買意欲に直接働きかけ、短期的な成果を生み出す強力な武器として知られているのが「セールスプロモーション(Sales Promotion、以下SP)」です。
この記事では、セールスプロモーションの基本的な概念から、広告との違い、具体的な目的や手法、そして成功に導くための企画ステップまでを網羅的に解説します。これからセールスプロモーションに取り組みたいと考えているマーケティング担当者の方や、既存の施策を見直したい経営者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社の成長戦略を描いてみてください。
目次
セールスプロモーション(SP)とは?
セールスプロモーションとは、企業や店舗が顧客の購買意欲を刺激し、製品やサービスの購入を促進するための一連の販売促進活動を指します。具体的には、割引クーポンや景品、サンプリング、イベント開催など、消費者に直接的なメリットを提供することで、最終的な購買行動へと後押しすることを目的としています。
SPは、マーケティング活動全体の中でも特に「行動喚起」に特化した施策であり、その効果が比較的短期間で現れやすいという特徴があります。新商品の発売時や販売が伸び悩んでいる時期、あるいは競合との差別化を図りたい場面など、様々なビジネスシーンで活用される重要な戦略です。
マーケティングにおける位置づけ
セールスプロモーションの役割をより深く理解するために、マーケティング活動全体における位置づけを確認しておきましょう。
一般的に、マーケティング戦略は「マーケティング・ミックス」と呼ばれるフレームワークで整理されます。その代表的なものが「4P」です。
- Product(製品): どのような製品やサービスを提供するか。
- Price(価格): いくらで提供するか。
- Place(流通): どこで、どのように提供するか。
- Promotion(販売促進): どのようにして顧客に製品やサービスの存在を知らせ、購入を促すか。
この4つの要素の中で、セールスプロモーションは「Promotion(販売促進)」に含まれる具体的な活動の一つです。ただし、Promotion活動はSPだけではありません。Promotionは主に以下の4つの要素で構成されていると考えられています。
- 広告(Advertising): テレビCM、新聞広告、Web広告など、メディアを通じて不特定多数に情報を伝え、ブランドや商品の認知度・イメージ向上を目指す活動。
- 広報・PR(Public Relations): プレスリリースやメディアへの情報提供などを通じて、社会やメディアと良好な関係を築き、企業や商品に対する好意的な評判を獲得する活動。
- 人的販売(Personal Selling): 営業担当者が顧客と直接対面し、商品説明や提案を行うことで購買を促す活動。
- セールスプロモーション(Sales Promotion): 上記3つ以外の、消費者の購買意欲を直接刺激するすべての販売促進活動。
つまり、SPは広告やPRで高めた認知度や好感度を、実際の「購買」という最終的な成果に結びつけるための、いわば「最後の一押し」を担う重要な役割を果たしています。いくら優れた広告で商品の魅力を伝えても、消費者が「今、買うべき理由」を感じなければ、購入には至らないケースは少なくありません。SPは、その「理由」を創出し、消費者の背中を押すための強力なトリガーとなるのです。
例えば、テレビCMで美味しそうな新商品のスナック菓子を知ったとします(広告)。その後、スーパーの店頭で「新発売記念!今だけ10%増量」というPOP広告(SP)を見かけたらどうでしょうか。「CMで見て気になっていたし、お得だから買ってみよう」と、購入する可能性は格段に高まるはずです。このように、SPは他のプロモーション活動と連携することで、その効果を最大化できます。
セールスプロモーションと広告の違い
セールスプロモーション(SP)と広告は、どちらも「Promotion(販売促進)」活動の一環であり、しばしば混同されがちです。しかし、その目的やアプローチ、効果の現れ方には明確な違いがあります。両者の特性を正しく理解し、適切に使い分けることが、効果的なマーケティング戦略の鍵となります。
ここでは、SPと広告の主な違いを「目的」「アプローチ」「効果の期間」「対象」という4つの観点から整理し、解説します。
| 比較項目 | セールスプロモーション(SP) | 広告(Advertising) |
|---|---|---|
| 主目的 | 行動喚起(購買、来店、会員登録など) | 認知・態度変容(認知度向上、ブランドイメージ構築) |
| アプローチ | 直接的なインセンティブ提供(割引、景品など) | 間接的な情報提供(メッセージ、世界観の伝達) |
| 効果の期間 | 短期的(キャンペーン期間中など) | 中長期的(ブランド資産の蓄積) |
| 主な対象 | 見込み顧客、既存顧客、流通業者、社内 | 不特定多数の潜在顧客 |
目的の違い:「買う理由」を作るSPと、「知ってもらう・好きになってもらう」広告
最も大きな違いは、その主目的にあります。
セールスプロモーションの最大の目的は、消費者の「行動」を直接的に引き出すことです。具体的には、「商品を買う」「店に来る」「会員登録する」「資料請求する」といった、売上に直結するアクションを促します。そのために、「今だけ割引」「購入者限定プレゼント」といった、消費者が「今、行動しないと損だ」と感じるような直接的なインセンティブ(動機付け)を提供します。SPは、いわば「買う理由」をその場で提供する活動です。
一方、広告の主目的は、ブランドや商品の「認知度向上」や「好意的なイメージの形成(態度変容)」にあります。テレビCMやWeb広告などを通じて、商品が持つ価値やブランドの世界観を伝え、「このブランドは信頼できる」「この商品は魅力的だ」と消費者に感じてもらうことを目指します。広告は、すぐに購買に繋がらなくても、消費者の心の中にブランドの存在感を刻み込み、将来的な購買選択肢の一つとして記憶してもらうための活動と言えます。
アプローチの違い:直接的な働きかけと間接的な働きかけ
目的の違いは、アプローチ方法の違いにも繋がります。
SPは、クーポン、割引、景品、ポイント還元など、金銭的・物質的なメリットを直接的に提供することで、消費者の購買へのハードルを下げます。アプローチは非常に具体的で、消費者にとっての「お得感」が分かりやすいのが特徴です。
対して広告は、ストーリーや音楽、映像美、キャッチコピーといったクリエイティブな表現を用いて、情緒的な価値やブランドのメッセージを間接的に伝えます。消費者に直接的なメリットを提示するのではなく、商品やブランドに対する共感や憧れを醸成することで、間接的に購買意欲を喚起しようとします。
効果の期間の違い:即効性のSPと持続性の広告
効果が現れるまでの期間も異なります。
SPは「期間限定」「数量限定」といった形で実施されることが多く、その効果は比較的短期間で、かつ明確に現れる傾向があります。キャンペーン期間中の売上や来店客数の増加といった形で、成果を測定しやすいのがメリットです。しかし、その効果はプロモーションが終了すると同時に薄れてしまうことが多く、持続性は低いと言えます。
一方、広告はブランドイメージや信頼性を時間をかけてじっくりと構築していく活動です。そのため、効果が現れるまでには中長期的な時間が必要となります。一度築き上げたブランドイメージは企業の大きな資産となり、長期にわたって安定した売上を支える基盤となります。広告の効果は直接的な売上として測定しにくい側面もありますが、その影響は持続的です。
両者の連携が成功の鍵
ここまでSPと広告の違いを解説してきましたが、両者は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。効果的なマーケティングを展開するためには、両者をうまく連携させることが不可欠です。
例えば、以下のようなシナリオが考えられます。
- 認知(広告): テレビCMやSNS広告で新商品の発売を大々的に告知し、ターゲット層に広く認知させる。
- 興味・関心(広告・PR): 人気インフルエンサーによる商品レビューや、Webメディアでの特集記事を通じて、商品の魅力や利用シーンを具体的に伝え、興味・関心を深める。
- 比較・検討(SP): 公式サイトで「初回限定お試しセット」を用意したり、店頭でサンプリングを実施したりして、試用機会を提供する。
- 購買(SP): 「発売記念クーポン」を配布したり、「購入者限定のプレゼントキャンペーン」を実施したりして、最終的な購買を後押しする。
このように、広告で「認知」と「興味」の土台を築き、セールスプロモーションで「検討」から「購買」への最後のひと押しを行うことで、一貫性のある強力な顧客体験を生み出し、マーケティング効果を最大化できるのです。
セールスプロモーションの主な目的
セールスプロモーション(SP)は、単に「売上を上げること」だけが目的ではありません。より具体的に、どのような成果を目指して実施されるのかを理解することで、自社の課題に合った最適な施策を選択できます。SPの主な目的は、大きく分けて「新規顧客の獲得」「既存顧客の購買促進・リピート化」「ブランドや商品の認知度向上」の3つに分類されます。
新規顧客の獲得
まだ自社の商品やサービスを利用したことのない潜在顧客に、最初の購入を促すことは、事業成長における重要なステップです。しかし、消費者は使い慣れた商品や信頼しているブランドから、未知の商品へ乗り換えることに抵抗を感じるものです。セールスプロモーションは、この心理的な障壁を乗り越えさせるための強力なきっかけを提供します。
なぜSPが新規顧客獲得に有効なのか?
新規顧客は、商品の品質や価値をまだ知りません。そのため、「試してみて損はない」「お得だから買ってみよう」と感じさせる、リスクを低減し、メリットを分かりやすく提示するアプローチが効果的です。
- 試用のハードルを下げる: サンプリング(試供品配布)や無料トライアルは、新規顧客が金銭的なリスクなしに商品を体験できる絶好の機会です。「使ってみたら意外と良かった」という発見が、本購入へと繋がります。特に、化粧品や食品、ソフトウェアなどで有効な手法です。
- 最初の購入を後押しする: 「初回限定割引」や「ウェルカムクーポン」は、「初めて買うなら今が一番お得」という強力なメッセージとなり、購入の決断を後押しします。これは、ECサイトの会員登録促進や、サブスクリプションサービスの加入者増を狙う際によく用いられます。
- 話題性を創出し、注目を集める: 大規模なプレゼントキャンペーンや、ユニークな景品がもらえるプレミアムプロモーションは、SNSなどで話題になりやすく、これまでブランドを認知していなかった層にも情報を届けることができます。話題性がきっかけで興味を持ち、初めての購入に至るケースも少なくありません。
具体例のシナリオ:
新しくオーガニックシャンプーを発売した化粧品メーカーが、ドラッグストアの店頭でミニサイズのサンプルを配布する(サンプリング)。同時に、商品に貼られたQRコードから応募できるプレゼントキャンペーンを実施し、SNSでの拡散を促す。これにより、品質への不安を払拭しつつ、お得感を演出し、新規顧客のトライアル購入を促進します。
既存顧客の購買促進・リピート化
新規顧客の獲得には、既存顧客維持の5倍のコストがかかるとも言われています(1:5の法則)。そのため、一度購入してくれた顧客との関係を維持・深化させ、継続的に購入してもらうこと(リピート化)は、安定した事業基盤を築く上で極めて重要です。セールスプロモーションは、既存顧客に対する感謝の意を示すとともに、次回の購入を促すための有効な手段となります。
なぜSPが既存顧客の育成に有効なのか?
既存顧客はすでに商品の価値をある程度理解しています。彼らにとっては、「もっとお得に買いたい」「買い続けることで特別なメリットが欲しい」というニーズが存在します。SPは、このニーズに応えることで顧客ロイヤルティを高めます。
- 購買頻度・購買単価の向上: 「2点購入で10%OFF」「あと500円で送料無料」といったプライスプロモーションは、顧客にもう一品購入させる(クロスセル)や、より高価な商品を選ばせる(アップセル)きっかけとなり、顧客単価の向上に繋がります。
- 継続利用のインセンティブ: ポイントプログラムは、購入金額に応じてポイントが貯まり、次回の買い物で割引として利用できる仕組みです。「ポイントが貯まっているから、またあのお店で買おう」という動機付けになり、顧客の囲い込み(ロックイン効果)に繋がります。
- ブランドへの愛着醸成: 「会員限定セール」や「優良顧客向け特別イベント」など、ロイヤルティの高い顧客を優遇する施策は、顧客に「自分は特別な存在だ」と感じさせ、ブランドへの愛着や信頼感を深めます。これにより、単なるリピーターから、ブランドを積極的に他者に推奨してくれる「ファン」へと育成できます。
具体例のシナリオ:
あるカフェチェーンが、専用アプリでスタンプカード機能を提供(ポイントプログラム)。ドリンク1杯購入で1スタンプが貯まり、10スタンプで好きなドリンク1杯が無料になる。さらに、月に10回以上利用するヘビーユーザーには、限定の「ゴールド会員」ステータスを付与し、常に5%OFFで購入できる特典を提供する。これにより、顧客の来店頻度を高め、ロイヤルティ向上を図ります。
ブランドや商品の認知度向上
セールスプロモーションは、直接的な販売促進だけでなく、ブランドや商品の存在をより多くの人に知ってもらう「認知度向上」の目的でも活用されます。特に、広告だけではリーチしきれない層へ情報を届けたり、商品の特徴を体験的に伝えたりする際に効果を発揮します。
なぜSPが認知度向上に有効なのか?
SPは、消費者が参加し、体験できる「イベント性」を持つものが多く、記憶に残りやすいという特徴があります。また、SNSとの親和性が高い手法も多く、情報が自然に拡散していく効果が期待できます。
- 体験を通じた理解促進: 展示会への出展や店頭での実演販売は、商品の機能やメリットを顧客が五感で直接体験できる場です。言葉で説明するだけでは伝わりにくい商品の魅力を深く理解してもらうことで、強い印象を残し、認知度を高めます。
- 話題性の創出と情報拡散: SNSを活用したキャンペーン(例:「#商品名」で投稿すると抽選でプレゼントが当たる)は、ユーザーの参加を促し、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を自然発生させます。友人や知人からの投稿は広告よりも信頼されやすく、爆発的な情報拡散(バイラル)を生む可能性があります。
- メディア露出の獲得: ユニークなイベントプロモーションや大規模なキャンペーンは、テレビやWebニュースなどのメディアに取り上げられることがあります。これにより、広告費をかけずに多くの人の目に触れる機会(パブリシティ)を得られ、認知度を飛躍的に高めることが可能です。
具体例のシナリオ:
ある飲料メーカーが、夏フェスの会場でブースを出展(イベントプロモーション)。新発売のエナジードリンクを無料で配布(サンプリング)し、ブース内に設置したフォトジェニックな撮影スポットで写真を撮り、指定のハッシュタグを付けてSNSに投稿すると、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンを実施する。これにより、ターゲット層に直接商品をアピールし、SNSでの拡散を通じてブランドの認知度を一気に高めます。
セールスプロモーションの3つの対象
セールスプロモーションは、誰に対して行うかによって、その目的や手法が大きく異なります。ターゲットとなる対象は、主に「消費者」「流通業者」「社内(従業員)」の3つに大別されます。それぞれの対象の特性を理解し、適切なアプローチを選択することが、プロモーション効果を最大化する上で重要です。
消費者向けプロモーション
一般の消費者を対象とし、最終的な購買行動を直接促すためのプロモーションです。私たちが日常生活で最も目にする機会が多いのが、この消費者向けプロモーションであり、セールスプロモーションと聞いて多くの人が思い浮かべるのはこのタイプでしょう。
- 目的:
- 新規顧客のトライアル購入促進: 新商品や未利用サービスを試してもらうきっかけを作る。
- 既存顧客のリピート購入促進: 継続的な購入を促し、顧客ロイヤルティを高める。
- 購買数量・単価の増加: 一度の買い物での購入点数や金額を増やす(ついで買い、まとめ買いの促進)。
- ブランドスイッチの喚起: 競合他社の商品から自社商品へ乗り換えてもらう。
- ブランド認知度・好意度の向上: 話題性のあるキャンペーンを通じて、ブランドの存在を広く知らせる。
- 代表的な手法:
- プレミアムプロモーション: 商品購入者に景品(ノベルティ)をプレゼントする。
- プライスプロモーション: 期間限定の割引、増量、セット販売などを行う。
- クーポン配布: 次回以降の購入で使える割引券を配布する。
- サンプリング: 試供品や試食を提供し、商品を体験してもらう。
- ポイントプログラム: 購入金額に応じてポイントを付与し、顧客を囲い込む。
- イベントプロモーション: 展示会や実演販売、体験イベントなどを開催する。
- SNSキャンペーン: フォロー&リツイートやハッシュタグ投稿などで参加を募る。
成功のポイント: 消費者向けプロモーションでは、ターゲットとなる消費者のインサイト(深層心理)を的確に捉え、「欲しい」「お得だ」「参加したい」と思わせる魅力的な企画が不可欠です。ターゲットの年齢層、ライフスタイル、価値観などを深く分析し、彼らの心に響くインセンティブやコミュニケーションを設計することが成功の鍵となります。
流通業者向けプロモーション
卸売業者や小売業者など、自社の商品を消費者に届けるまでの流通過程に関わるチャネル(販売経路)の協力を得るためのプロモーションです。「トレードプロモーション」とも呼ばれます。メーカーがどれだけ良い商品を作っても、流通業者が積極的に販売してくれなければ、消費者の手には届きません。
- 目的:
- 新規取り扱いの促進: 自社商品を新たに店舗に置いてもらう。
- 配荷率の向上: より多くの店舗で商品を取り扱ってもらう。
- 陳列場所の優位性確保: 店頭の目立つ場所(ゴールデンゾーン)に商品を陳列してもらう。
- 販売数量の増加: 流通業者自身の販売意欲を高め、より多くの商品を販売してもらう。
- 在庫の適正化: キャンペーンなどに合わせて、適切な量の在庫を持ってもらう。
- 関係性の強化: メーカーと流通業者との良好なパートナーシップを築く。
- 代表的な手法:
- 販売コンテスト: 設定期間中の販売実績に応じて、販売店や担当者に報奨金や旅行などを提供する。
- 販売奨励金(リベート): 目標販売数量を達成した場合に、売上の一部をキャッシュバックする。
- 協賛広告(アローワンス): 小売店のチラシや広告に自社商品を掲載してもらう際、その費用の一部をメーカーが負担する。
- 陳列コンテスト: 自社商品の陳列方法の美しさや独創性を競い、優れた店舗を表彰・報奨する。
- 販売員教育の支援: 商品知識や販売方法に関する研修会を実施し、販売員のスキルアップをサポートする。
成功のポイント: 流通業者向けプロモーションでは、単に「これを売ってください」とお願いするのではなく、流通業者にとってのメリット(売上向上、利益率改善、集客効果など)を明確に提示することが重要です。Win-Winの関係を築き、「このメーカーの商品を扱えば儲かる」「このメーカーはサポートが手厚い」と思ってもらうことが、継続的な協力関係に繋がります。
社内向けプロモーション(インナープロモーション)
自社の従業員、特に営業担当者や販売員を対象に行うプロモーションです。「インナープロモーション」や「モチベーションプロモーション」とも呼ばれます。企業の理念や商品への情熱を社内に浸透させ、従業員の士気を高めることで、最終的に顧客へのサービス品質や販売力の向上を目指します。
- 目的:
- モチベーションの向上: 従業員のやる気を引き出し、エンゲージメントを高める。
- 商品知識の深化: 新商品や重点商品に関する理解を深め、自信を持って顧客に提案できるようにする。
- 営業・販売スキルの向上: 成功事例の共有や研修を通じて、組織全体のレベルアップを図る。
- 企業理念やビジョンの浸透: 全従業員が同じ方向を向いて業務に取り組む一体感を醸成する。
- 目標達成意欲の喚起: 設定された販売目標などに対するコミットメントを強める。
- 代表的な手法:
- インセンティブ制度: 個人の販売実績や目標達成度に応じて、報奨金や特別休暇、表彰などのインセンティブを与える。セールスコンテストもこの一種です。
- 社内表彰制度(アワード): 優秀な成績を収めた従業員やチームを全社的に表彰し、功績を称える。
- キックオフミーティング: 新年度や大型キャンペーンの開始時に、全社的な目標や戦略を共有し、士気を高めるイベントを開催する。
- 社内報やイントラネットでの情報共有: 成功事例や商品開発の裏話、トップメッセージなどを発信し、従業員のエンゲージメントを促進する。
- 研修・勉強会の実施: 新商品に関する勉強会や、外部講師を招いたスキルアップ研修などを実施する。
成功のポイント: 社内向けプロモーションでは、公平性と透明性のある評価基準を設けることが極めて重要です。一部の優秀な従業員だけが常に勝者となるような制度ではなく、誰もが努力すれば報われると感じられるような仕組みを設計することが、組織全体のモチベーション向上に繋がります。「やらされ感」をなくし、従業員が自発的に目標に向かって挑戦したくなるような、ポジティブな雰囲気作りが成功の鍵を握ります。
セールスプロモーションの代表的な手法12選
セールスプロモーションには多種多様な手法が存在します。ここでは、消費者向け、流通業者向け、社内向けのそれぞれで代表的な手法を12種類ピックアップし、その特徴やメリット、活用時の注意点を詳しく解説します。自社の目的やターゲットに最適な手法を見つけるための参考にしてください。
プレミアムプロモーション(景品・ノベルティ)
商品やサービスの購入者に対して、景品(プレミアム)や記念品(ノベルティ)を提供する手法です。消費者の「何かをもらえるならお得だ」という心理に働きかけ、購買の動機付けを強化します。
- 種類:
- ベタ付け景品: 商品にもれなく景品が付いてくるタイプ(例:飲料の首掛け景品、雑誌の付録)。
- 総付景品: 特定の条件(例:〇円以上購入)を満たした全員に景品を提供するタイプ。
- 懸賞景品: 購入者を対象に抽選を行い、当選者に景品を提供するタイプ。
- メリット: 購入の直接的な後押しになる、ブランドイメージに合った景品で好感度を高められる。
- 注意点: 景品表示法(景表法)による規制があります。提供できる景品の最高額や総額には上限が定められているため、企画段階で必ず確認が必要です。また、景品の魅力が低いと効果が薄く、逆に景品目当ての購入ばかりになると、商品自体のファンが育ちにくい側面もあります。
プライスプロモーション(割引・値引き)
期間限定で商品の価格を直接的に引き下げる、最も分かりやすく即効性の高い手法です。消費者の価格に対する敏感さを利用し、購入へのハードルを一気に下げます。
- 種類:
- 単純値引き: 「通常価格1,000円→800円」のように価格を下げる。
- 割引率表示: 「レジにて全品20%OFF」のように割引率を提示する。
- 増量パック: 価格は据え置きで内容量を増やす(実質的な値引き)。
- セット割引: 関連商品をまとめて購入すると割引になる(例:シャンプーとリンスをセットで買うと100円引き)。
- メリット: 効果がすぐに売上として現れやすい、新規顧客のトライアルを促しやすい。
- 注意点: 多用すると商品の定価が分かりにくくなり、ブランド価値を損なうリスクがあります。「安いのが当たり前」というイメージが付くと、通常価格では売れにくくなる可能性があります。利益率の低下も考慮し、期間や対象商品を限定して計画的に実施することが重要です。
クーポン配布
特定の商品やサービスを割引価格で購入できる券(クーポン)を配布する手法です。新聞の折り込みチラシや雑誌、Webサイト、アプリなど、多様な媒体で配布できます。
- 種類:
- 紙クーポン: チラシや雑誌に印刷されたもの。
- デジタルクーポン: スマートフォンの画面で提示するもの。
- 購入時発行クーポン: 購入後のレシートに次回来店時に使えるクーポンが印字されるもの。
- メリット: リピート利用を促進しやすい(特に次回使えるクーポン)、ターゲットを絞った配布が可能(例:アプリ会員限定)、効果測定がしやすい(クーポン回収率など)。
- 注意点: 割引率が低いと利用されず、配布コストだけがかかる可能性があります。また、利用条件(有効期限、対象商品など)を分かりやすく記載しないと、顧客とのトラブルの原因になることもあります。
サンプリング(試供品配布)
商品の試供品(サンプル)を無料で配布し、実際に試してもらうことで良さを体験してもらう手法です。特に、品質に自信がある新商品や、使ってみないと魅力が伝わりにくい商品に適しています。
- 配布場所: 店頭、街頭、イベント会場、雑誌の付録、Webサイトからの申し込みなど。
- メリット: 商品の価値を直接体験してもらえるため、納得感を持って購入に繋がりやすい、口コミの発生源になりやすい。
- 注意点: サンプルの製造コストや配布コストがかかるため、費用対効果の見極めが重要です。ターゲット層がいない場所で配布しても効果は薄いため、配布場所の選定が成功を左右します。配布後にアンケートを実施するなど、本購入に繋げるための工夫も求められます。
ポイントプログラム
購入金額に応じてポイントを付与し、貯まったポイントを値引きや景品交換に利用できる仕組みです。顧客の継続利用を促し、囲い込む(ロックインする)効果が期待できます。
- 種類: ポイントカード、スマートフォンアプリなど。
- メリット: リピート率の向上に直結する、顧客データの収集・分析に活用できる、優良顧客の育成に繋がる。
- 注意点: システム導入や運用にコストがかかります。また、多くの企業が導入しているため、ポイント還元率や特典内容で他社との差別化を図らないと、効果が薄れがちです。顧客にとっては、複数のポイントカードを管理するのが負担になることもあります。
イベントプロモーション(展示会・実演販売)
特定の場所でイベントを開催し、顧客と直接コミュニケーションを取りながら商品をアピールする手法です。
- 種類:
- 展示会・見本市: 業界関係者や関心の高い顧客が集まる場でブースを出展する。
- 店頭での実演販売: スーパーでの試食販売など、その場で商品の使い方や魅力を実演する。
- 体験イベント: ワークショップやセミナー、新商品の体験会などを開催する。
- ポップアップストア: 期間限定で店舗を出店し、ブランドの世界観を伝える。
- メリット: 商品の魅力を五感で伝えられる、顧客と深いコミュニケーションが取れる、ブランドへのエンゲージメントを高められる。
- 注意点: 企画から実施までに多くの時間とコスト、人員が必要です。集客がうまくいかないと、コスト倒れになるリスクがあります。イベントの目的を明確にし、ターゲットに響くコンテンツを準備することが成功の鍵です。
POP広告
「Point of Purchase(購買時点)」の略で、店舗内の商品棚やレジ周りなどに設置される広告物のことです。消費者が商品を手に取る最終段階で、購買意欲を刺激する役割を果たします。
- 種類: ポスター、のぼり、パネル、商品棚のプライスカード、電子モニター(デジタルサイネージ)など。
- メリット: 低コストで始められる、購買の最終決定を後押しする効果が高い、タイムリーな情報提供が可能。
- 注意点: 情報を詰め込みすぎると読まれず、逆効果になります。一目でメリットが分かるような、簡潔でインパクトのあるデザインやキャッチコピーが求められます。設置する場所や高さによっても視認性が大きく変わるため、顧客の目線を意識した工夫が必要です。
SNSキャンペーン
Twitter(X)やInstagram、FacebookなどのSNSプラットフォームを活用して行うプロモーションです。ユーザーの参加と拡散を促すことで、低コストで高い認知度向上が期待できます。
- 種類:
- フォロー&リツイート/いいねキャンペーン: 公式アカウントをフォローし、対象の投稿をリツイートやいいねすることで応募が完了する。
- ハッシュタグキャンペーン: 指定のハッシュタグを付けて写真やコメントを投稿してもらう。
- クイズ・診断キャンペーン: ユーザーが楽しめるコンテンツを提供し、結果をシェアしてもらう。
- メリット: 情報が爆発的に拡散(バイラル)する可能性がある、ユーザーとの双方向コミュニケーションが可能、ファンの育成に繋がる。
- 注意点: 企画がターゲットに響かないと全く盛り上がらずに終わる可能性があります。また、景品目当ての懸賞アカウントばかりが集まると、本来の目的であるファン獲得に繋がりません。炎上リスクも常に考慮し、慎重な運用が求められます。
懸賞・プレゼントキャンペーン
クイズに答えたり、商品についている応募シールを集めたりすることで、豪華な景品が当たる抽選に応募できるキャンペーンです。消費者の「一攫千金」や「特別な体験」への期待感を煽ります。
- 種類:
- オープン懸賞: 商品購入の有無にかかわらず誰でも応募できる。
- クローズド懸賞: 商品購入者のみが応募できる。
- メリット: 話題性が高く、短期間で多くの注目を集めることができる、ブランド認知度の向上に貢献する。
- 注意点: プレミアムプロモーション同様、景表法による規制があります。特にクローズド懸賞は景品総額に厳しい制限があるため注意が必要です。応募の手間がかかりすぎると参加者が減ってしまうため、Webやハガキなど、手軽に応募できる方法を用意することが重要です。
販売コンテスト(流通業者向け)
設定した期間内に、自社商品の販売実績が優れていた小売店や卸売業者、またはその担当者を表彰し、報奨を与える手法です。流通業者のモチベーションを直接的に刺激します。
- 報奨の種類: 報奨金(インセンティブ)、旅行、表彰盾、豪華賞品など。
- メリット: 流通業者の販売意欲を劇的に高めることができる、メーカーと流通業者の関係性を強化できる。
- 注意点: 評価基準の公平性・透明性が不可欠です。特定の有力な店舗ばかりが有利になるような設定では、他の店舗の士気を下げてしまいます。店舗の規模や地域性を考慮したハンディキャップを設けるなど、誰もが目標を持てるような設計が求められます。
販売奨励金(流通業者向けリベート)
一定期間の仕入れ額や販売額など、あらかじめ設定した目標を達成した流通業者に対して、その金額の一部を後から払い戻す(キャッシュバックする)制度です。
- メリット: 流通業者の安定した仕入れ・販売を促進する、自社商品の取り扱いシェアを高める効果がある。
- 注意点: 制度が複雑だと流通業者に理解されにくく、モチベーションに繋がりません。また、リベートを前提とした価格交渉が行われることもあり、メーカー側の利益を圧迫する可能性も考慮する必要があります。
インセンティブ制度(社内向け)
自社の営業担当者や販売員など、従業員の目標達成度に応じて報奨を与える制度です。従業員の士気を高め、組織全体の販売力向上を目指します。
- 報奨の種類: 金銭的インセンティブ(ボーナス、歩合給)、非金銭的インセンティブ(表彰、昇進、特別休暇、研修機会など)。
- メリット: 従業員のモチベーションを明確な形で引き出すことができる、個人の成果が正当に評価される文化を醸成する、営業目標の達成に直結する。
- 注意点: 個人間の過度な競争を煽り、チームワークを阻害するリスクがあります。個人目標だけでなく、チーム目標も設定するなど、協調性を損なわない工夫が必要です。また、短期的な成果ばかりを追い求め、顧客との長期的な関係構築がおろそかにならないような評価軸も重要です。
セールスプロモーションを企画する5つのステップ
効果的なセールスプロモーションは、思いつきや場当たり的なアイデアで成功するものではありません。戦略的な視点に立ち、計画的に準備・実行・評価を行うプロセスが不可欠です。ここでは、セールスプロモーションを企画し、成功に導くための基本的な5つのステップを解説します。このフレームワークに沿って進めることで、施策の精度を高め、投資対効果を最大化できます。
目的とターゲットを明確にする
すべての戦略の出発点となるのが、「誰に、何を達成してほしいのか」を明確に定義することです。この最初のステップが曖昧なままでは、以降のすべての判断がぶれてしまいます。
- 目的(Why)の明確化:
- なぜ、今プロモーションを行う必要があるのか?
- 達成したい最も重要なゴールは何か?
- 例:「新商品の初動売上を最大化する」「休眠顧客を掘り起こし、リピート率を5%改善する」「競合の新商品発売に対抗し、シェア低下を防ぐ」
- 目的は、前述した「新規顧客の獲得」「既存顧客の育成」「認知度向上」といった大枠から、さらに具体的なレベルまで落とし込みます。目的は一つに絞り込むか、優先順位をつけることが重要です。複数の目的を同時に追うと、施策が中途半端になりがちです。
- ターゲット(Who)の明確化:
- このプロモーションは、誰に向けたものか?
- ターゲットの属性(年齢、性別、居住地など)や、心理・行動特性(価値観、ライフスタイル、購買動機など)は何か?
- 例:「健康志向が強く、SNSでの情報収集に積極的な30代女性」「ポイントを貯めるのが好きな当店のリピーター」「まだ当社の主力商品を使ったことがない、競合A社のユーザー」
- ターゲットを具体的に描くことで、彼らの心に響くメッセージやインセンティブが何かを考えやすくなります。「すべての人」をターゲットにすると、結果的に誰の心にも響かないプロモーションになってしまいます。
KPI(重要業績評価指標)と予算を設定する
目的が定まったら、次はその達成度を測るための具体的な指標(KPI)と、投下できるコスト(予算)を決定します。このステップは、プロモーションの成否を客観的に評価し、将来の改善に繋げるために不可欠です。
- KPI(What)の設定:
- KPI(Key Performance Indicator)とは、目的の達成度合いを定量的に測定するための指標です。
- 目的が「新規顧客の獲得」であれば、KPIは「新規購入者数」「キャンペーンサイトからの新規会員登録数」「初回限定クーポンの利用枚数」などが考えられます。
- 目的が「既存顧客の育成」であれば、KPIは「リピート購入率」「一人当たりの購入単価(LTV)」「ポイントプログラムの利用率」などが設定できます。
- 具体的で測定可能な数値目標(例:新規会員登録数1,000人)を設定することが重要です。
- 予算(How much)の設定:
- プロモーションにどれだけの費用をかけられるかを明確にします。
- 予算には、景品やサンプルの原価、広告費、イベント会場費、ツール利用料、人件費など、プロモーションに関わるすべてのコストを含めて計算します。
- 設定したKPIを達成することで得られるであろう利益(売上増加、LTV向上など)と、投下する予算のバランスを考慮することが重要です(ROI: 投資対効果)。過去のデータや類似の施策の実績を参考に、現実的な予算を組みましょう。
具体的な手法を決定する
目的、ターゲット、KPI、予算という土台が固まったら、いよいよ具体的なプロモーション手法(How)を選定します。
- 手法の選定:
- 前述した12の手法などを参考に、設定した目的とターゲットに最も効果的だと思われる手法を選びます。
- 例:新規顧客に商品の良さを体験してほしい(目的)なら「サンプリング」、既存顧客のリピートを促したい(目的)なら「ポイントプログラム」や「会員限定クーポン」が適しています。
- 複数の手法を組み合わせることも有効です。例えば、SNSキャンペーンで認知を広げ、店頭のPOP広告とクーポンで購買を後押しする、といった連携が考えられます。
- プロモーション内容の具体化:
- 手法が決まったら、その詳細を詰めていきます。
- 期間(When): いつからいつまで実施するのか。商品の需要期や競合の動向も考慮して決定します。
- 場所(Where): オンライン(自社サイト、SNS)か、オフライン(店舗、イベント会場)か。
- インセンティブ: 割引率、景品の内容、ポイント還元率など、顧客に提供する具体的なメリットを決めます。ターゲットにとって魅力的で、かつ予算内に収まるものを選定します。
- クリエイティブ: キャッチコピー、デザイン、キャンペーンサイトの構成など、顧客との接点となるコミュニケーションツールを準備します。
プロモーションを実施する
綿密な計画が立てられたら、いよいよ実行フェーズに移ります。計画通りにスムーズに実施するためには、事前の準備と関係各所との連携が鍵となります。
- 事前準備:
- 景品や販促物の発注・納品スケジュールの確認。
- キャンペーンサイトや応募フォームの動作テスト。
- 社内(営業、店舗スタッフ)や社外(流通業者、広告代理店)への情報共有と協力依頼。特に、店舗スタッフがキャンペーン内容を正しく理解していないと、顧客とのトラブルに繋がるため、マニュアルの配布や説明会の実施が重要です。
- 実施中のモニタリング:
- プロモーションを開始したら、それで終わりではありません。
- 設定したKPIの中間指標を定期的にチェックし、計画通りに進んでいるかを確認します。例えば、Webキャンペーンであれば、アクセス数や応募数の推移を日々確認します。
- 予期せぬトラブル(システムの不具合、想定以上の応募による景品不足など)が発生した場合に、迅速に対応できる体制を整えておくことも重要です。
効果を測定し改善する(PDCA)
プロモーション期間が終了したら、必ずその結果を評価し、次回の施策に活かすための学びを得る必要があります。このプロセスが、組織のマーケティング能力を継続的に向上させます。
- 効果測定(Check):
- 事前に設定したKPIが目標値を達成できたかどうかを定量的に評価します。
- 売上データ、Webサイトのアクセス解析データ、アンケート結果など、様々なデータを収集・分析します。
- 「売上は目標を達成したが、利益率は悪化した」「応募数は多かったが、ターゲット層からの応募は少なかった」など、多角的な視点で成果と課題を洗い出します。
- 改善(Action):
- 測定結果から得られた考察をもとに、「何が成功の要因だったのか」「なぜ目標を達成できなかったのか」「次はどう改善すべきか」を議論し、ナレッジとして蓄積します。
- 成功要因は、他の施策でも応用できる「勝ちパターン」として横展開します。
- 失敗要因は、次回の企画で同じ過ちを繰り返さないための貴重な教訓となります。
- このPlan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)のPDCAサイクルを回し続けることが、セールスプロモーションの成功確率を継続的に高めていく上で最も重要です。
セールスプロモーションを成功させるためのポイント
これまで見てきたように、セールスプロモーションの企画・実行には多くのステップがありますが、その成否を分ける特に重要なポイントがいくつか存在します。ここでは、数々の施策に共通する、成功のために押さえておきたい3つの核心的なポイントを深掘りします。
ターゲットにとって魅力的な内容を企画する
セールスプロモーションの成否は、「ターゲット顧客の心を動かせるかどうか」に尽きると言っても過言ではありません。企業側が「これはお得だろう」と考えても、ターゲットがそれに魅力を感じなければ、プロモーションは空振りに終わってしまいます。
- ターゲットインサイトの深掘り:
- ターゲットは、普段どのような生活を送り、何に悩み、何を求めているのか?彼らの「インサイト(本音、深層心理)」を深く理解することが出発点です。
- 例えば、ターゲットが「節約志向の主婦」であれば、単純な値引きや増量が響くかもしれません。しかし、ターゲットが「自分の時間を大切にする独身のビジネスパーソン」であれば、時短に繋がる便利なサービスや、特別な体験ができるイベントの方が魅力的に映る可能性があります。
- アンケート、インタビュー、SNS上の声の分析などを通じて、ターゲットのリアルな価値観を掴むことが重要です。
- 「お得感」の多様な形を理解する:
- 魅力的な内容とは、必ずしも金銭的なメリットだけを指すわけではありません。
- 金銭的価値: 割引、キャッシュバック、ポイント還元など。
- 希少価値: 「会員限定」「数量限定」「期間限定」など、今しか手に入らないという特別感。
- 体験価値: 普段できない特別な体験(イベント参加、工場見学など)。
- 情報価値: 専門家によるセミナー、役立つノウハウの提供など。
- 自己表現価値: オリジナルグッズが作れる、SNSで自慢できるフォトスポットなど。
- これらの価値を、ターゲットのインサイトに合わせて組み合わせることで、単なる「値引き」ではない、心に残るプロモーションを企画できます。
- 失敗例から学ぶ:
- (失敗例)高級化粧品ブランドが、安易な割引キャンペーンを実施した結果、ブランドイメージが低下し、既存のロイヤル顧客が離れてしまった。
- (改善策)割引ではなく、「購入者限定でプロのメイクアップアーティストによるメイクレッスンにご招待」といった体験価値を提供する。これにより、ブランド価値を損なうことなく、顧客満足度を高めることができます。
適切な期間を設定する
プロモーションの実施期間は、その効果に大きく影響します。短すぎても長すぎても、期待した成果は得られません。「機会損失」と「陳腐化」の両方を避けられる、最適な期間を見極める必要があります。
- 短すぎる場合のリスク:
- 認知・浸透不足: プロモーションの存在がターゲットに十分に知れ渡る前に終了してしまい、参加機会を逃す人が続出します。特に、口コミでの広がりを期待するような施策では、ある程度の期間が必要です。
- 機会損失: 「やっていることに気づかなかった」「忙しくて参加できなかった」という声が多くなり、本来獲得できたはずの売上や顧客を逃してしまいます。
- 長すぎる場合のリスク:
- 緊急性の喪失: 「いつでもやっている」という認識が広まり、「今すぐ買わなくてもいいや」と購買が先延ばしにされてしまいます。SPの強みである「最後の一押し」の効果が薄れてしまいます。
- 陳腐化・マンネリ化: プロモーションが常態化し、顧客にとっての「特別感」や「お得感」が失われます。
- ブランド価値の毀損: 特に長期間の値引きは、「安いのが当たり前」というイメージを定着させ、プロモーション終了後に通常価格で売れなくなるリスクを高めます。
- 適切な期間設定の考え方:
- 商品の購買サイクルを考慮する: 化粧品や日用品のように購買頻度が高い商品は比較的短期間でも効果が出やすいですが、自動車や家電のような高額商品は検討期間が長いため、ある程度の期間が必要です。
- プロモーションの目的と連動させる: 新商品の発売直後など、短期集中で一気に話題を作りたい場合は短期間。リピート習慣を根付かせたい場合は、数ヶ月単位での計画が必要になることもあります。
- 季節性やイベントを活用する: クリスマスやバレンタイン、ボーナス商戦など、消費者の購買意欲が高まる時期に合わせて期間を設定すると、相乗効果が期待できます。
費用対効果を意識する
セールスプロモーションは、売上を増やすための「投資」です。したがって、投じた費用に対してどれだけのリターン(利益)があったのか、ROI(Return on Investment)の視点を常に持つことが重要です。売上が伸びても、それ以上にコストがかかっていれば、ビジネスとしては失敗です。
- コストの全体像を把握する:
- プロモーションにかかる費用は、景品の原価や割引額だけではありません。
- 直接コスト: 景品・サンプル原価、割引による減収分、広告宣伝費、印刷物制作費、イベント運営費、ツール利用料など。
- 間接コスト: 企画・運営にかかる人件費、通常業務への影響など。
- これらのコストを可能な限り正確に見積もり、予算計画に盛り込む必要があります。
- 効果を多角的に測定する:
- リターンは、短期的な売上増加だけで測るべきではありません。
- 短期的な効果: 売上、利益、新規顧客数、客単価など。
- 中長期的な効果: リピート率の向上、顧客生涯価値(LTV)の増加、ブランド認知度・好意度の向上、SNSでのUGC(ユーザー生成コンテンツ)数など。
- これらの指標を総合的に評価することで、プロモーションの真の価値を判断できます。例えば、短期的には赤字でも、獲得した新規顧客のLTVが高ければ、長期的には成功した投資と評価できるかもしれません。
- PDCAサイクルでの改善:
- 実施したプロモーションのROIを分析し、「なぜこのコストがかかったのか」「どうすればもっとコストを抑えられたか」「どの施策が最もROIが高かったか」を振り返ります。
- この分析結果を次回の企画に活かすことで、より費用対効果の高いプロモーションへと改善していくことができます。データに基づいた意思決定こそが、継続的な成功の鍵となります。
セールスプロモーションに役立つおすすめツール3選
セールスプロモーション、特にデジタルを活用したキャンペーンを効率的かつ効果的に実施するためには、専用のツールを活用するのがおすすめです。ここでは、SNSキャンペーンやデジタルギフト、電子クーポンの分野で多くの企業に利用されている代表的なツールを3つ紹介します。
ATTERU
ATTERUは、株式会社2BCが提供するSNSインスタントウィンツールです。インスタントウィンとは、ユーザーがキャンペーンに参加したその場で当落結果が分かる仕組みのことで、高い参加率と拡散効果が期待できます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な機能 | Twitter(X)、Instagram、LINEに対応したインスタントウィンキャンペーンの実施 |
| 特徴 | ・最短即日でキャンペーンを開始できる手軽さ ・リツイート、ハッシュタグ投稿、アンケート回答など多様な応募条件を設定可能 ・1日1回応募できる「毎日応募」機能で、キャンペーン期間中の継続的な参加を促進 ・動画視聴を応募条件にすることで、商品やサービスの理解度を深めることが可能 ・専門スタッフによるサポート体制 |
| 活用シーン | ・新商品の認知度向上、発売記念キャンペーン ・公式SNSアカウントのフォロワー獲得 ・イベントや店舗への集客促進 |
| 料金 | 要問い合わせ(キャンペーンの規模や内容に応じて個別見積もり) |
ATTERUを活用することで、これまで手間のかかっていた抽選作業や当選者への連絡などを自動化でき、キャンペーン運営の工数を大幅に削減できます。ユーザーの参加ハードルを下げつつ、高いエンゲージメントを生み出したい場合に非常に有効なツールです。
参照:ATTERU 公式サイト
dgift
dgiftは、株式会社デジマースが提供する法人向けのデジタルギフトサービスです。コンビニ商品やカフェのドリンク、各種ポイントなどを、URL形式で手軽に配布できます。SNSキャンペーンの景品や、アンケート謝礼、資料請求のインセンティブなど、幅広い用途で活用されています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な機能 | デジタルギフトの発行・配布システム |
| 特徴 | ・コンビニ商品からECサイトのギフト券まで、1,000種類以上の豊富なラインナップ ・1個から発注可能で、小規模なキャンペーンにも対応 ・ギフトが実際に利用された分だけ費用が発生する「実績費用型」プランがあり、無駄なコストを削減可能 ・API連携により、自社のシステムやアプリにデジタルギフト機能を組み込むことも可能 |
| 活用シーン | ・SNSキャンペーンや懸賞の景品 ・アンケート回答や会員登録の謝礼 ・営業活動におけるインセンティブ(資料請求のお礼など) |
| 料金 | 初期費用・月額費用は0円。ギフトの実績費用+発行手数料(要問い合わせ) |
dgiftを使えば、景品の在庫管理や梱包、発送といった物理的な手間が一切不要になります。ユーザーにとっても、近くの店舗ですぐに交換できる手軽さが魅力であり、キャンペーン参加の満足度を高める効果が期待できます。
参照:dgift 公式サイト
Smart Kpon
Smart Kponは、株式会社エムディーピーが提供するスマートフォン向け電子クーポン(デジタルクーポン)サービスです。スタンプラリーやレシート応募キャンペーンなど、多様な販促機能を組み合わせることができます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な機能 | 電子クーポンの発行・消込、スタンプラリー機能、レシート応募キャンペーン機能など |
| 特徴 | ・特許技術である「スマホ画面にスタンプを押す」というユニークなクーポン消込方法(もぎり処理)が特徴 ・来店回数に応じて特典が変わるステップアップクーポンや、友人にクーポンをプレゼントできるソーシャルギフト機能も搭載 ・専門知識がなくても、管理画面から簡単にキャンペーンを作成・設定できる ・利用状況をリアルタイムで分析でき、効果測定や次回施策への改善が容易 |
| 活用シーン | ・店舗へのリピート来店促進(スタンプラリー、リピーター向けクーポン) ・購買促進(マストバイキャンペーン) ・商業施設などでの回遊性向上(デジタルスタンプラリー) |
| 料金 | 要問い合わせ(利用機能や規模に応じて個別見積もり) |
Smart Kponは、顧客のリピート化やロイヤルティ向上を目指す施策に特に強みを発揮します。紙のクーポンやスタンプカードをデジタル化することで、顧客の利便性を高めると同時に、企業側は正確な顧客データを取得・活用できるようになります。
参照:Smart Kpon 公式サイト
これらのツールは、それぞれに特徴や強みがあります。自社のプロモーションの目的やターゲット、予算に合わせて最適なツールを選定し、活用することで、より洗練された効果的なセールスプロモーションを実現できるでしょう。
まとめ
本記事では、セールスプロモーション(SP)の基本的な概念から、広告との違い、目的、対象、そして具体的な12の手法に至るまで、網羅的に解説してきました。さらに、プロモーションを成功に導くための企画ステップや重要なポイント、役立つツールについても触れました。
セールスプロモーションとは、単なる値引きや景品提供に留まらず、顧客の購買行動を喚起し、企業と顧客の関係性を深めるための戦略的なコミュニケーション活動です。その本質は、顧客のインサイトを深く理解し、「今、買うべき理由」「このブランドを使い続けたい理由」を的確に提供することにあります。
この記事で解説した内容を、改めて重要なポイントとしてまとめます。
- SPの役割: 広告やPRで築いた認知・好意を「購買」という具体的な行動に繋げるための「最後の一押し」を担う。
- 成功の鍵: 「誰に(ターゲット)」「何を(目的)」を明確にし、ターゲットの心に響く魅力的なインセンティブを、適切な手法・期間・予算で提供すること。
- 企画のプロセス: 目的とターゲットの明確化から始まり、KPI・予算設定、手法決定、実施、そして効果測定と改善(PDCA)という一連のサイクルを回すことが不可欠。
- 多角的な視点: 消費者だけでなく、流通業者や社内従業員といった異なる対象へのアプローチも、ビジネス全体の成功には欠かせない。
セールスプロモーションの世界は奥深く、常に新しい手法やアイデアが生まれています。しかし、その根底にある「顧客の心を動かす」という原則は変わりません。
まずは、自社の現状の課題が「新規顧客の獲得」なのか、「既存顧客の育成」なのか、あるいは「ブランドの認知度向上」なのかを明確にすることから始めてみましょう。そして、その課題解決に最も貢献しそうなプロモーション手法を、本記事を参考に検討してみてください。計画的に、そして何よりも顧客の視点に立って企画・実行すれば、セールスプロモーションはあなたのビジネスを次のステージへと押し上げる強力なエンジンとなるはずです。