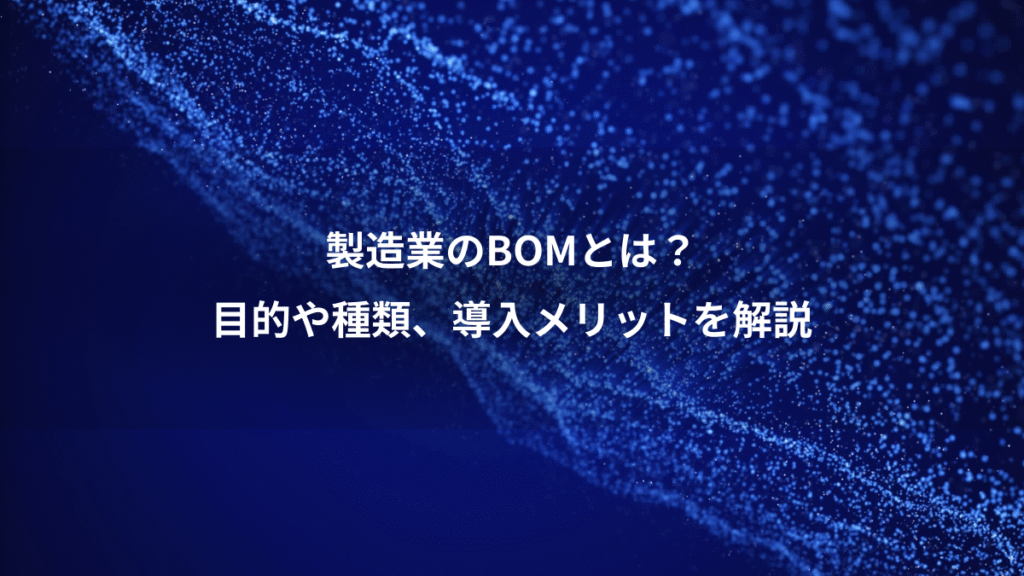製造業において、製品は数多くの部品や材料から成り立っています。これらの部品情報を正確に管理し、生産活動全体を円滑に進めるために不可欠なのが「BOM(部品表)」です。BOMは、単なる部品のリストではなく、製品の設計、生産、購買、コスト管理といったあらゆる業務の基盤となる重要なマスターデータです。
本記事では、製造業の根幹を支えるBOMの基本的な知識から、その目的、種類、管理方法、そしてBOM管理を効率化するシステムの選び方まで、網羅的に解説します。BOM管理に課題を抱えている方や、これからBOMシステムの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
BOM(部品表)とは
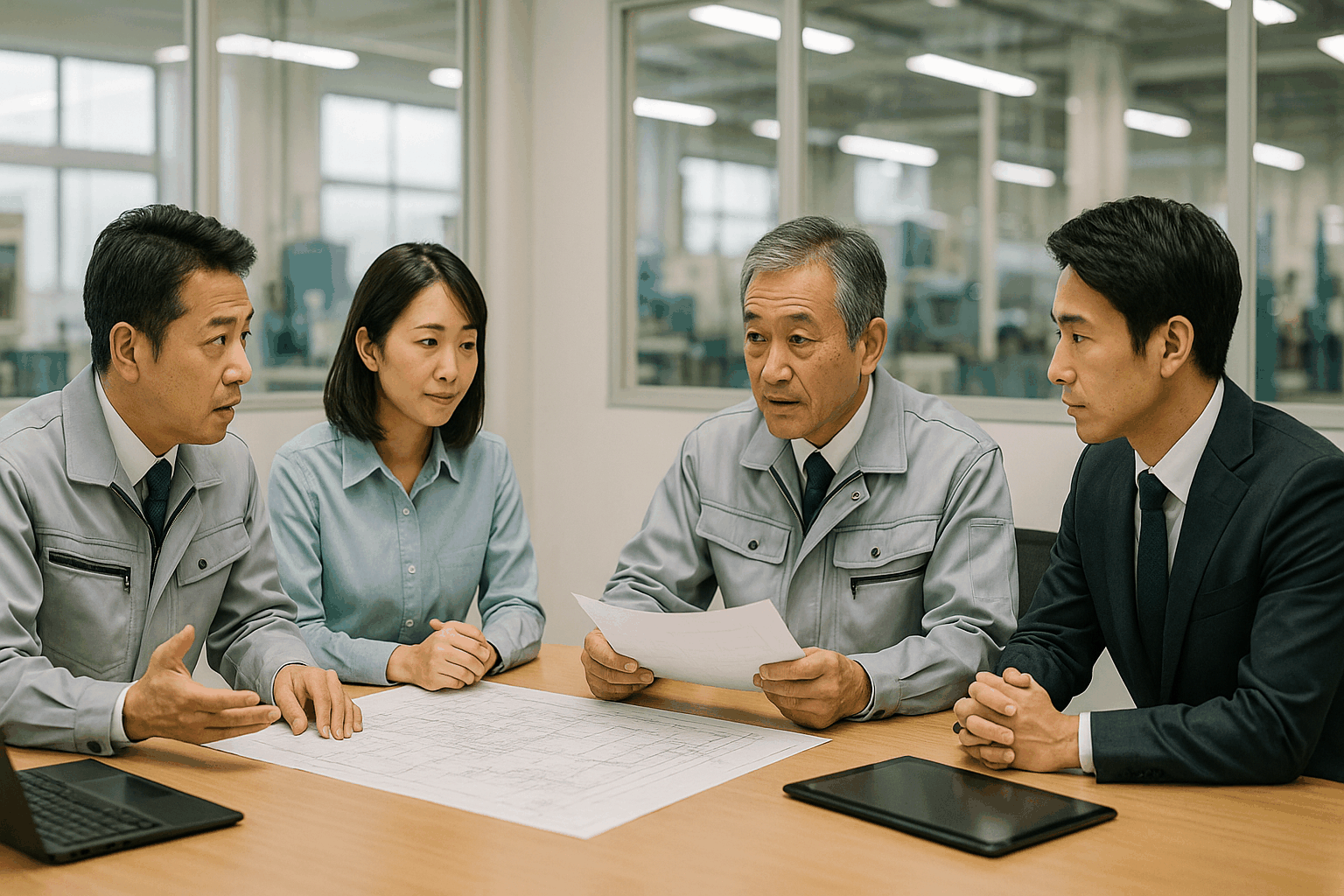
BOM(ボム)とは、「Bill of Materials」の略語で、日本語では「部品表」と訳されます。BOMは、特定の製品を1単位製造するために必要な部品、半製品、原材料などの品目と、それぞれの数量、単位、そしてそれらの親子関係を階層構造で体系的に示した一覧表です。
製造業におけるBOMは、製品の「レシピ」や「設計図」に例えられます。例えば、カレーライスを作るためには、カレールー、じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、肉、そして水といった材料が、それぞれ決まった量だけ必要です。この材料とその分量をリストアップしたものがレシピであり、製造業におけるBOMも同様の役割を果たします。
しかし、BOMは単に材料をリストアップするだけではありません。製品がどのように組み立てられるか、その構造を示す点が大きな特徴です。例えば、「自転車」という最終製品を考えてみましょう。自転車は「フレーム」「ハンドル」「サドル」「ホイール」といった大きな部品(親部品)で構成されます。さらに、「ホイール」は「リム」「スポーク」「ハブ」「タイヤ」「チューブ」といった部品(子部品)から成り立っています。このように、製品を頂点として、それを構成する部品、さらにその部品を構成する下位の部品へと展開していく階層構造(ツリー構造)で情報を管理するのがBOMの最大の特徴です。
BOMには、主に以下のような情報が含まれます。
- 階層(レベル): 製品構造における部品の位置づけを示します。最終製品をレベル0とすると、その直下の部品はレベル1、さらにその部品を構成する部品はレベル2となります。
- 品目コード(品番): 各部品や製品を社内で一意に識別するための番号です。
- 品目名(品名): 部品の名称です。
- 数量: 親部品を1単位作るために必要な子部品の数量です。
- 単位: 個、kg、m、Lなど、数量の単位です。
- 仕様・規格: 部品のサイズ、材質、色などの詳細情報です。
- 図面番号: 関連する設計図面への参照情報です。
- 調達区分: 内製、購入、外注などの区分です。
これらの情報は、製造業のあらゆる部門で活用されるため、BOMは「マスターデータの中のマスターデータ」とも呼ばれ、その精度と鮮度が企業全体の生産性や収益性を大きく左右します。
BOMと部品リストの違い
BOMとよく似た言葉に「部品リスト(パーツリスト)」があります。どちらも製品を構成する部品の一覧ですが、その目的と情報の持ち方に明確な違いがあります。
部品リストは、一般的に特定の製品や組み立て工程に必要な部品を平面的に(階層構造を持たずに)一覧にしたものを指します。例えば、ある組み立てラインで使う部品だけを抜き出したリストや、保守・修理で交換する可能性のある部品だけをまとめたリストなどがこれにあたります。いわば、製品の一側面を切り取った単純なリストです。
一方、BOMは、製品全体の構造を体系的に表現することを目的としています。前述の通り、親子関係を持つ階層構造で管理されるため、「どの部品が、どのユニットに、いくつ使われているか」という構成情報が明確です。この構造的な情報があることで、後述する生産管理や原価計算、設計変更への対応などが可能になります。
| 項目 | BOM(部品表) | 部品リスト |
|---|---|---|
| 主な目的 | 製品の構成・構造を体系的に定義する | 特定の目的(組立、保守など)で必要な部品を一覧化する |
| 構造 | 階層構造(親子関係)を持つ | 平面的(フラット)な一覧形式 |
| 情報の網羅性 | 製品を構成するすべての部品・材料を網羅 | 特定の目的に応じて一部の部品を抜粋 |
| 主な用途 | 生産計画、原価計算、購買計画、設計変更管理など全社的 | 特定の組立工程、保守マニュアル、見積作成など限定的 |
具体例で考えてみましょう。「ノートパソコン」という製品があったとします。
- 部品リストの例: 「キーボード交換マニュアル」に添付される部品リスト。ここには、交換に必要な「キーボードユニット」「固定用ネジA(4本)」「接続ケーブルB(1本)」といった情報のみが記載されます。
- BOMの例: ノートパソコン全体のBOM。最上位に「ノートパソコン(製品)」があり、その下に「液晶ディスプレイユニット」「キーボードユニット」「マザーボードユニット」「バッテリー」「外装ケース」などがぶら下がります。さらに「マザーボードユニット」の下には「CPU」「メモリ」「各種チップ」「基板」などが階層的に連なります。
このように、部品リストは特定の文脈で使われる部分的な情報であるのに対し、BOMは製品そのものの定義であり、製造活動全体の基盤となるマスターデータであるという点が、両者の決定的な違いです。正確なBOMを構築し、一元管理することが、製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上での第一歩と言えるでしょう。
BOM(部品表)の目的
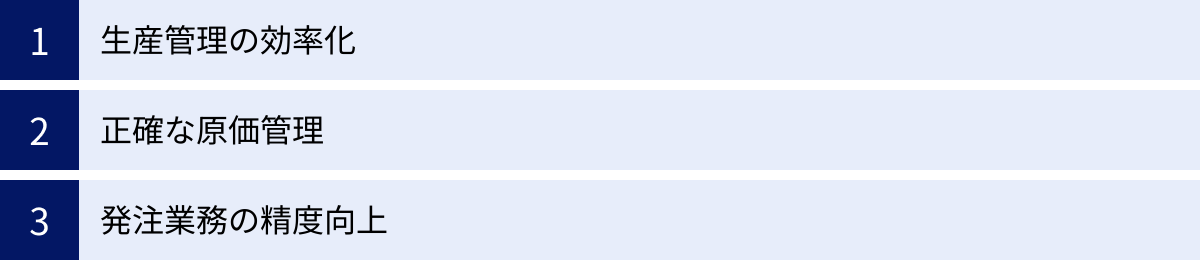
BOMは、なぜ作成し、維持管理する必要があるのでしょうか。その目的は多岐にわたりますが、大きく分けると「生産管理の効率化」「正確な原価管理」「発注業務の精度向上」の3つが挙げられます。これらは相互に関連し合っており、BOMが製造業の根幹を支える理由そのものです。
生産管理の効率化
製造業において、顧客が求める製品を、求める納期までに、適切な品質で生産することは至上命題です。この「いつ、何を、どれだけ作るか」という生産計画を立てる上で、BOMは絶対に必要な情報となります。
BOMは、MRP(Material Requirements Planning:資材所要量計画)システムの根幹をなします。MRPとは、生産計画に基づいて、製品を作るために「どの部品が」「いつまでに」「どれだけ必要か」を自動的に計算する仕組みです。
例えば、「製品Aを100台、来月末までに生産する」という生産計画が立てられたとします。このとき、MRPシステムは製品AのBOMを参照します。
- 所要量計算(正展開): BOMを最上位の製品Aから下位の部品へと展開(正展開)していきます。製品Aを1台作るのに部品Bが2個、部品Cが5個必要だとすれば、100台作るためには部品Bは200個、部品Cは500個必要だと計算します。さらに、部品Bが部品Dと部品Eからできている場合、その所要量も連鎖的に計算されます。
- リードタイム計算: 各部品の調達や製造にかかるリードタイム(日数)もBOMや関連マスターに登録されています。MRPは、製品Aの完成希望日から逆算して、各部品をいつまでに手配・製造開始しなければならないかを算出します。
- 在庫引当: 現在の在庫量を考慮し、実際に発注または製造指示が必要な正味の所要量を割り出します。
もしBOMが存在しなかったり、情報が不正確だったりした場合、これらの計算はすべて手作業で行うことになります。その結果、計算ミスによる部品の欠品や手配遅れが発生し、生産ラインが停止してしまうリスクが高まります。また、逆に過剰に部品を発注してしまい、不要な在庫を抱えることにもなりかねません。
正確なBOMに基づいて生産管理を行うことで、部品の欠品や過剰在庫を防ぎ、生産計画の精度を高め、結果として納期遵守率の向上と生産リードタイムの短縮を実現できます。これは、企業の競争力に直結する非常に重要な目的です。
正確な原価管理
製品の価格競争が激化する現代の製造業において、製品原価を正確に把握し、コントロールすることは経営上の最重要課題の一つです。BOMは、製品の原価を計算するための最も基本的な情報を提供します。
製品の原価は、大きく「材料費」「労務費」「経費」から構成されます。このうち、製品原価の大部分を占めることが多い「材料費」は、BOMを使って算出されます。これを「標準原価計算」と呼びます。
具体的には、BOMに登録されている各部品の数量に、それぞれの部品の標準単価(購入価格や内製加工費)を掛け合わせ、それらをすべて積み上げていくことで、製品1単位あたりの標準材料費を計算します。
例えば、
- 製品X = 部品Y(2個) + 部品Z(5個)
- 部品Yの標準単価 = 100円
- 部品Zの標準単価 = 30円
この場合、製品Xの標準材料費は (100円 × 2個) + (30円 × 5個) = 350円 となります。
BOMが整備されていることによる原価管理上のメリットは、単に原価が分かるというだけではありません。
- 原価シミュレーション: 設計変更を検討する際に、新しい部品構成での原価がどう変わるかを事前にシミュレーションできます。「部品Yを高機能だが高価な部品Y’(単価150円)に変更すると、原価はいくら上がるのか」「コストダウンのために部品Zを安価な部品Z’(単価25円)に置き換えると、どれだけ原価を下げられるのか」といった検討が容易になり、設計段階でのコスト作り込み(原価企画)を支援します。
- 原価差異分析: 実際に製造にかかったコスト(実際原価)と、BOMから算出した標準原価を比較することで、差異の原因を分析できます。材料の歩留まりが悪かったのか、購入価格が想定より高かったのかなどを特定し、改善活動に繋げることができます。
- 見積作成の迅速化: 新規の引き合いがあった際に、類似製品のBOMを流用・編集することで、迅速かつ精度の高い見積原価を算出できます。
このように、BOMはコストを可視化し、戦略的な原価低減活動や迅速な意思決定を可能にするための羅針盤としての役割を担っています。
発注業務の精度向上
生産に必要な部品を、必要なタイミングで、必要な量だけ調達する購買・発注業務は、生産活動を止めないために極めて重要です。この発注業務の精度も、BOMによって大きく向上します。
前述のMRPの仕組みにより、生産計画から必要な部品の正味所要量が自動的に算出されます。購買担当者は、この算出結果に基づいて発注業務を行えばよいため、手作業による計算ミスや、勘や経験に頼った発注による過不足を根本的に防ぐことができます。
具体的には、以下のような効果が期待できます。
- 発注漏れの防止: BOMに登録されている部品は、MRPによって必ず所要量計算の対象となります。これにより、「うっかりあのネジを発注し忘れた」といったヒューマンエラーを防ぎ、部品欠品による生産停止リスクを低減します。
- 過剰在庫の抑制: 必要な量だけを計画的に発注するため、不要な在庫を持つ必要がなくなります。過剰在庫は、保管スペースや管理コストを圧迫するだけでなく、キャッシュフローの悪化にも繋がるため、その抑制は経営上非常に重要です。
- 発注業務の効率化・自動化: システムによっては、MRPで算出された発注要求データを基に、発注書を自動で作成・発行する機能もあります。これにより、購買担当者は見積取得や納期交渉といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
- サプライヤーとの連携強化: 正確な所要量情報(内示情報)を早期にサプライヤーと共有することで、サプライヤー側も生産計画が立てやすくなり、結果として納期の安定化に繋がります。
このように、BOMは生産の現場からバックオフィスの原価管理、購買業務に至るまで、製造業のバリューチェーン全体を貫く共通言語として機能します。BOMを正確に維持管理することは、部門間の連携をスムーズにし、企業全体の業務効率と収益性を向上させるための土台作りそのものなのです。
BOM(部品表)の主な種類
BOMは、利用する部門や目的によって、その表現形式や含まれる情報が異なります。企業の活動フェーズ、つまり「設計」「製造」「保守」の各段階で、それぞれに最適化されたBOMが使われるのが一般的です。ここでは、その代表的な3種類のBOM、「E-BOM」「M-BOM」「S-BOM」について解説します。
| BOMの種類 | 正式名称 | 主な目的 | 主な利用者 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| E-BOM | Engineering BOM(設計部品表) | 製品の機能・構造を定義する | 設計・開発部門 | 機能単位での構成。図面情報と強く連携。製造方法は考慮されない場合がある。 |
| M-BOM | Manufacturing BOM(製造部品表) | 製品の製造プロセスを定義する | 生産管理・製造・購買部門 | 製造工程順の構成。加工情報、外注情報、リードタイムなどが含まれる。 |
| S-BOM | Service BOM(サービス部品表) | 製品の保守・メンテナンスを管理する | サービス・保守部門 | 保守対象となる部品や交換単位で構成される。販売情報と連携する場合がある。 |
E-BOM(設計部品表)
E-BOM(Engineering BOM)は、日本語で「設計部品表」と呼ばれ、製品の設計・開発部門で作成・利用されるBOMです。その主な目的は、製品がどのような機能を持つ部品で構成されているか、その技術的な仕様や構造を定義することにあります。
E-BOMは、CAD(Computer-Aided Design)ツールで作成された3Dモデルや2D図面と密接に連携していることが多く、設計成果物そのものと言えます。構成は、製品の機能的なまとまり(アセンブリ)を重視して作られます。例えば、自動車のエンジンであれば、「シリンダーブロック」「ピストン」「クランクシャフト」といった機能単位で構成が組まれます。
E-BOMに含まれる主な情報は以下の通りです。
- 品目コード、品名
- 図面番号、ドキュメント番号
- 設計変更番号(版数)
- 材質、重量、表面処理などの技術仕様
- 設計担当者
E-BOMの段階では、必ずしも製造方法が確定しているわけではありません。例えば、「接着剤」や「塗料」といった副資材は、設計仕様として定義されますが、製造現場でどのくらいの量を使うか、どの工程で使うかといった具体的な情報は含まれないことがあります。また、ある部品を自社で加工する(内製)のか、外部から購入するのかといった調達方法も、この段階では未決定の場合が多いです。あくまで「設計上の部品構成」を示すのがE-BOMの役割です。
M-BOM(製造部品表)
M-BOM(Manufacturing BOM)は、日本語で「製造部品表」と呼ばれ、生産管理、製造、購買といった部門で利用されるBOMです。E-BOMを基にして、実際に製品を製造するために必要な情報を付加・再編成して作成されます。
M-BOMの目的は、効率的で間違いのない生産を実現することです。そのため、構成は設計上の機能単位ではなく、製造工程の順序や組み立てのしやすさを考慮して作られます。E-BOMでは一つの部品として扱われていたものが、M-BOMでは「購入部品」「中間加工品」「半製品(サブアセンブリ)」などに分割して管理されることもあります。
例えば、E-BOMでは「筐体(きょうたい)」という一つの部品だったものが、M-BOMでは、
- 購入品の「鋼板」
- 鋼板をプレス加工した「内製加工品A」
- 内製加工品Aを塗装した「内製加工品B」
というように、製造プロセスを反映した構成に変わります。
M-BOMに含まれる主な情報は以下の通りです。
- E-BOMの基本情報
- 製造工程(工程順、作業内容)
- 使用する設備や治具
- 加工時間、リードタイム
- 調達区分(内製、購入、外注)
- 発注先(サプライヤー)情報
- 歩留まり率
このように、M-BOMは「どのように作るか」という視点に立った情報が豊富に含まれており、前述したMRP(資材所要量計画)や生産指示、原価計算の直接的なインプットデータとなります。
多くの企業では、E-BOMとM-BOMが別々に管理されており、設計変更があった際にE-BOMからM-BOMへの情報伝達が遅れたり、変換作業でミスが発生したりすることが課題となっています。この課題を解決するため、近年ではE-BOMとM-BOMを一つのデータベースで統合的に管理する「統合BOM」という考え方も注目されています。
S-BOM(サービス部品表)
S-BOM(Service BOM)は、日本語で「サービス部品表」や「保守部品表」と呼ばれ、製品が出荷された後のアフターサービスやメンテナンス業務で利用されるBOMです。
その目的は、顧客への迅速かつ正確な保守部品の供給や、修理作業の効率化です。S-BOMは、M-BOMを基に作成されることもありますが、その構成は保守・メンテナンスの観点から再構築されます。
例えば、製品のすべての部品が保守対象になるわけではありません。S-BOMでは、故障しやすい部品、定期的な交換が必要な消耗品、顧客が交換作業を行う可能性のある部品などが中心にリストアップされます。
また、部品の提供単位も異なります。製造ではネジ1本単位で管理していても、サービスでは複数の関連部品をまとめた「修理キットA」といった単位で販売・管理することがあります。S-BOMは、このようなサービス固有の提供単位を反映した構成になります。
S-BOMに含まれる主な情報は以下の通りです。
- 保守部品の品目コード、品名
- 交換手順書へのリンク
- 互換性のある代替部品の情報
- 販売価格
- 保証期間
近年、製造業では「モノ売り」から「コト売り」(サービス化)へのシフトが進んでいます。製品のライフサイクル全体で収益を上げるためには、アフターサービス事業の強化が不可欠です。S-BOMを適切に管理することは、顧客満足度の向上と、新たな収益源の確保に繋がる重要な取り組みと言えるでしょう。
BOM(部品表)の構造形式
BOMは、そのデータの表現方法(構造形式)によって、大きく2つのタイプに分類されます。それが「ストラクチャ型(多段階型)」と「サマリー型(一段階型)」です。どちらの形式でBOMを管理するかは、BOMを利用する目的や、管理のしやすさに大きく影響します。
ストラクチャ型(多段階型)
ストラクチャ型BOMは、製品の階層構造をそのまま表現する形式です。親部品と子部品の関係性が明確に示され、製品がどのようなユニットや部品で構成されているかをツリー構造で多段階にわたって把握できます。これは、本記事でこれまで説明してきたBOMの基本的な考え方に最も近い形式です。
【ストラクチャ型BOMの例:自転車】
- Level 0: 自転車(最終製品)
- Level 1: フレームAssy
- Level 1: ハンドルAssy
- Level 2: ハンドルバー
- Level 2: グリップ (2個)
- Level 2: ブレーキレバー (2個)
- Level 1: ホイールAssy (2個)
- Level 2: リム
- Level 2: ハブ
- Level 2: スポーク (36本)
- Level 2: タイヤ
この形式の最大のメリットは、製品の構造が直感的に理解できることです。これにより、以下のような業務が容易になります。
- 設計変更の影響範囲の特定: 例えば、「スポーク」の仕様を変更する場合、それが「ホイールAssy」を通じて「自転車」という最終製品に影響することがすぐに分かります。もし同じスポークが他の製品にも使われていれば、その影響範囲も追跡できます(逆展開)。
- 中間組立品の管理: 「ハンドルAssy」や「ホイールAssy」といった半製品(サブアセンブリ)単位での生産計画や在庫管理が可能になります。
- 原因究明: 製造工程で不具合が発生した際に、どのユニットのどの部品が原因であるかをBOMの階層をたどって特定しやすくなります。
一方で、デメリットとしては、データの構造が複雑になり、管理に手間がかかる点が挙げられます。特に、Excelなどの表計算ソフトでこの階層構造を厳密に管理しようとすると、ファイルの構成が複雑化し、メンテナンスが非常に困難になります。そのため、ストラクチャ型BOMを本格的に運用するには、後述するBOMシステムなどの専用ツールを利用するのが一般的です。
サマリー型(一段階型)
サマリー型BOMは、特定の製品を作るために必要なすべての部品を、階層構造を持たずに一覧(フラットなリスト)で表示する形式です。製品を構成する中間組立品などはすべて展開され、最終的に必要となる個々の部品(最下層の部品)とその総量だけがリストアップされます。
【サマリー型BOMの例:自転車1台分】
| 品目コード | 品名 | 総数量 | 単位 |
|---|---|---|---|
| P001 | フレームAssy | 1 | 個 |
| P002 | ハンドルバー | 1 | 個 |
| P003 | グリップ | 2 | 個 |
| P004 | ブレーキレバー | 2 | 個 |
| P005 | リム | 2 | 個 |
| P006 | ハブ | 2 | 個 |
| P007 | スポーク | 72 | 本 |
| P008 | タイヤ | 2 | 個 |
この形式のメリットは、シンプルで分かりやすいことです。特定の製品を作るために、結局どの部品が合計でいくつ必要なのかが一目で分かります。そのため、以下のような用途に適しています。
- 総所要量の把握: 購買部門が発注する部品の総量を計算する際に便利です。
- 部品ピッキングリストの作成: 製造現場で、1台分の製品を組み立てるために集めるべき部品リストとして活用できます。
- データ管理の容易さ: 階層構造がないため、Excelなどでも比較的簡単に管理できます。
しかし、サマリー型には大きなデメリットがあります。それは、部品間の親子関係や製品の構造が全く分からないことです。これにより、以下のような問題が生じます。
- 設計変更の影響が不明: 「スポーク」の仕様を変更した場合、このリストだけを見ても、それがどのユニット(ホイールAssy)に影響するのか、また、他のどの製品にも影響するのかが分かりません。
- 中間組立品の管理ができない: 「ホイールAssy」という単位での管理ができないため、工程ごとの進捗管理や在庫管理が難しくなります。
- 類似製品への流用が困難: 製品の構造が分からないため、新しい製品を設計する際に、既存のユニットを流用するといった検討ができません。
結論として、現代の複雑な製品開発・生産プロセスにおいては、ストラクチャ型(多段階型)でBOMを管理することが必須と言えます。サマリー型は、ストラクチャ型のBOMから必要な情報を抽出して、特定の用途(発注リストなど)のために一時的に作成される帳票、と位置づけるのが適切な運用です。BOM管理のシステム化を考える際には、このストラクチャ型BOMをいかに効率的に、かつ正確に管理できるかが重要なポイントとなります。
BOM(部品表)を導入するメリット
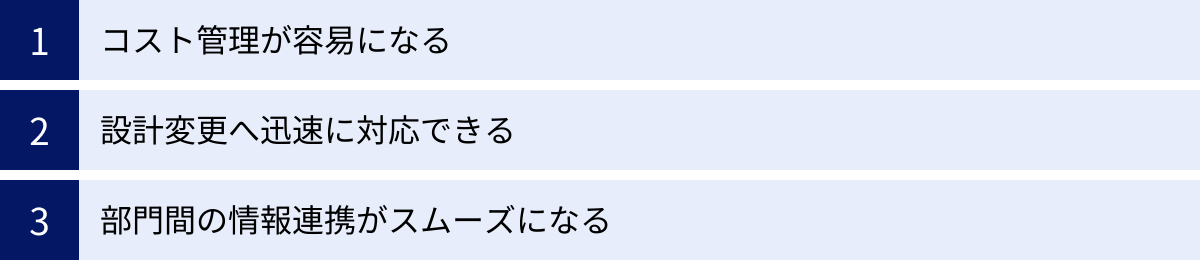
BOMを整備し、全社で一元的に管理・活用できる体制を整えることは、企業に多くのメリットをもたらします。それは単なる業務効率化に留まらず、企業の収益性や競争力を根本から強化するポテンシャルを秘めています。ここでは、BOMを適切に導入・運用することによる具体的なメリットを3つの観点から解説します。
コスト管理が容易になる
製造業にとって、原価、特に製品原価の大部分を占める材料費の管理は、利益を確保するための生命線です。BOMは、このコスト管理を精緻化・高度化するための基盤となります。
まず、製品の標準原価を正確に把握できることが最大のメリットです。BOMに登録された各部品の数量と、マスタに登録された部品単価を掛け合わせることで、理論上の製品原価を算出できます。これにより、個々の製品の採算性を正確に評価し、戦略的な価格設定や、不採算製品の見直しといった経営判断が可能になります。
さらに、BOMの活用は、事後的な原価把握に留まりません。設計・開発の初期段階でコストを予測し、作り込む「原価企画」が可能になります。例えば、新製品の設計中に、高価な部品Aを採用した場合と、安価だが性能が若干劣る部品Bを採用した場合の製品原価を、BOMを使って瞬時にシミュレーションできます。これにより、目標原価を達成するための最適な部品構成を、製造開始前(コストの大部分が確定してしまう前)に検討できます。これは、コスト競争力を高める上で非常に強力な武器となります。
また、市場環境の変化にも迅速に対応できます。為替レートの変動や、特定の材料価格が高騰した際に、その影響がどの製品の原価に、どの程度インパクトを与えるかをBOMを使って素早く分析できます。これにより、価格改定や代替部品への切り替えといった対策を、他社に先駆けて講じることが可能になります。
このように、BOMは単なる部品リストではなく、企業のコスト構造を可視化し、戦略的なコストマネジメントを実現するための羅針盤として機能します。
設計変更へ迅速に対応できる
市場のニーズの多様化や技術革新のスピードアップに伴い、製品の仕様変更や改良(設計変更)は日常的に発生します。この設計変更にいかに迅速かつ正確に対応できるかが、企業の対応力(アジリティ)を測る指標となります。BOMは、複雑な設計変更管理プロセスを円滑に進める上で不可欠なツールです。
設計変更が発生すると、その影響は設計部門だけでなく、購買、製造、品質保証、サービスなど、社内の多くの部門に及びます。BOMがなければ、これらの情報を正確に関係各所に伝達するのは至難の業です。
- 影響範囲の正確な特定: ストラクチャ型のBOMを使えば、ある部品の変更が、どのユニットを経由して、どの最終製品に影響を及ぼすのかを瞬時に特定できます(逆展開)。これにより、変更対応の漏れを防ぎます。例えば、あるネジの材質を変更した場合、そのネジが使われているすべての製品をリストアップし、強度やコストへの影響を漏れなく評価できます。
- 関連部門への迅速な情報伝達: 設計変更情報は、BOMを介してリアルタイムで関連部門に共有されます。購買部門は新しい部品の手配を開始し、古い部品の在庫をどう処理するかを計画します。製造部門は、工程の変更や新しい治具の必要性を検討します。このような連携がスムーズに行われることで、手戻りやロスコストの発生を防ぎます。
- 版数管理(バージョン管理): いつ、どの製品から新しい仕様に切り替えるか(適用時期の管理)は非常に重要です。BOMシステムでは、設計変更の履歴(版数)が正確に記録されるため、「製品シリアル番号XXXまでは旧仕様、YYYからは新仕様」といった管理が確実に行えます。これにより、市場での混乱や誤った部品での修理などを防ぎます。
設計変更への対応の遅れは、機会損失やブランドイメージの低下に直結します。BOMを中心とした情報管理体制を構築することで、変化に強い、俊敏な企業体質を作り上げることができます。
部門間の情報連携がスムーズになる
多くの製造業では、設計、購買、生産管理、製造といった部門が、それぞれの業務に最適化された異なる情報やシステムを使っていることが多く、部門間の壁(サイロ化)が課題となっています。BOMは、これらの部門をつなぐ「共通言語」としての役割を果たします。
- 設計部門: E-BOMを使って製品の機能・構造を定義します。
- 生産技術・生産管理部門: E-BOMを基に、製造プロセスを考慮したM-BOMを作成し、生産計画を立てます。
- 購買部門: M-BOMから必要な部品の所要量を把握し、発注業務を行います。
- 製造部門: M-BOMに基づいた作業指示書や部品リストを基に、製品を組み立てます。
- サービス部門: S-BOMを使って、保守部品の管理や供給を行います。
これらの各BOMが一つの統合されたデータベース上で連携・管理されていれば、全部門が常に同じ最新の正しい情報を参照して業務を進めることができます。設計部門が行った仕様変更が即座にM-BOMに反映され、購買部門や製造部門はその変更をリアルタイムで把握できます。「設計から図面はもらったが、部品リストは古いままだった」「購買は新しい部品を発注したが、製造現場には情報が伝わっていなかった」といった、部門間のコミュニケーションロスや認識の齟齬に起因するトラブルを劇的に減らすことができます。
この「One Source, One Truth」(情報は一つの源から)の状態を実現することが、BOM導入の究極的なメリットの一つです。これにより、部門間の無駄な問い合わせや確認作業が削減され、各担当者は本来のコア業務に集中できます。結果として、組織全体の生産性が向上し、製品開発から出荷、アフターサービスに至るまでのリードタイム短縮と品質向上に繋がるのです。
BOM(部品表)管理における3つの課題
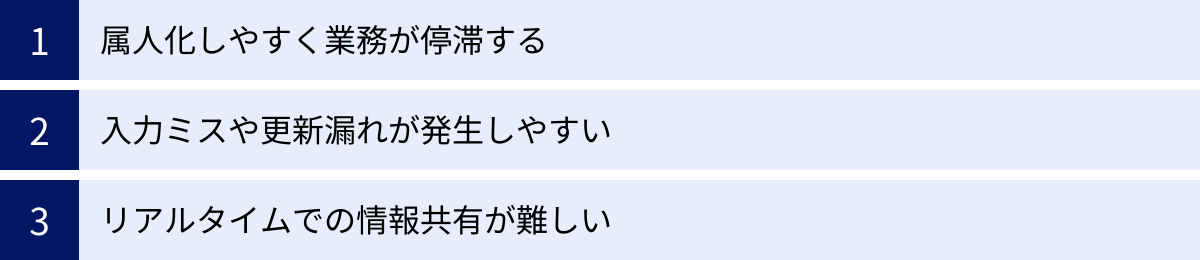
BOMが製造業にとって極めて重要である一方、その管理は容易ではありません。特に、旧来からのExcel(表計算ソフト)を中心とした管理方法では、多くの企業が共通の課題に直面しています。ここでは、BOM管理で陥りがちな3つの代表的な課題について掘り下げます。
① 属人化しやすく業務が停滞する
BOM管理における最も深刻な課題の一つが「属人化」です。属人化とは、特定の業務の進め方やノウハウが、特定の担当者個人の知識やスキルに依存してしまい、組織として共有・標準化されていない状態を指します。
ExcelによるBOM管理は、この属人化を助長しやすい環境と言えます。担当者がそれぞれ独自のフォーマットでBOMファイルを作成し、個人PCや部門の共有サーバー内の分かりにくい場所に保存しているケースは少なくありません。
- ファイル形式の不統一: ある担当者は品目コードを先頭列に、別の担当者は品名を先頭にするなど、フォーマットがバラバラ。関数やマクロが複雑に組まれており、作成者本人にしか修正できない。
- 命名規則の欠如: 部品やファイルの命名規則が個人の裁量に任されているため、必要な情報がどこにあるのか検索できない。
- ノウハウのブラックボックス化: BOMのどの項目を、どのような基準で更新するのかといったルールが暗黙知となっており、マニュアル化されていない。
このような状況では、その担当者が急な休みを取ったり、異動・退職したりした場合、BOMの更新や参照といった業務が完全に停滞してしまうリスクがあります。後任者は、残された無数のExcelファイルの中から最新版を探し出し、複雑な内容を解読することから始めなければならず、膨大な時間と労力がかかります。最悪の場合、業務を引き継ぐことができず、生産計画や原価計算に支障をきたすことにもなりかねません。
BOMは個人の持ち物ではなく、企業の重要な資産です。属人化を脱却し、誰でも同じように作業ができる標準化された仕組みを構築することが、事業継続性の観点からも急務となります。
② 入力ミスや更新漏れが発生しやすい
BOMのデータは、製品の生産やコストに直接影響するため、その正確性が極めて重要です。しかし、手作業に依存する管理方法では、ヒューマンエラーによる入力ミスや更新漏れを完全になくすことは困難です。
- 入力ミス: 手作業で品番や数量を打ち込む際に、桁を間違えたり、類似した品番を誤って入力したりするミスは頻繁に発生します。例えば、「B-101」と入力すべきところを「B-110」と打ち間違えただけで、全く異なる部品が手配され、製造ラインが止まってしまう可能性があります。
- コピー&ペーストによるエラー: 類似製品のBOMをコピーして新しいBOMを作成する際に、修正漏れが発生しがちです。一部の部品だけを更新し、他の部品は古い情報のまま残ってしまうといったミスが起こります。
- 更新漏れ: 設計変更が発生した際に、関連するすべてのBOMファイルを更新し忘れるケースです。例えば、製品Aと製品Bで共通の部品Cを使っているとします。部品Cが後継品の部品Dに変更になった場合、製品AのBOMは更新したものの、製品BのBOMを更新し忘れるといった事態です。この結果、製品Bは古い部品Cで生産指示が出されてしまい、手戻りや不良在庫の発生に繋がります。
これらのミスは、担当者がどれだけ注意を払っていても起こりうるものです。複数のExcelファイルでBOMが分散管理されている状態は、こうしたミスを誘発する温床となります。一つの変更に対して、複数のファイルを手作業で修正する運用自体に、構造的なリスクが潜んでいるのです。
③ リアルタイムでの情報共有が難しい
現代のビジネス環境では、スピードが競争力の源泉です。設計変更などの情報は、可能な限り迅速に、かつ正確に全部門で共有される必要があります。しかし、Excelファイルをメール添付や共有サーバーでやり取りする従来型の管理方法では、リアルタイムな情報共有は実現できません。
- バージョン管理の崩壊: 各部門の担当者が、自分のPCにダウンロードしたBOMファイルを編集し、メールで送り返すといった運用をしていると、どれが最新版のファイルなのかが分からなくなります。「BOM_Ver3_最終版_20240510.xlsx」「BOM_Ver3_最終版_20240511_山田修正.xlsx」といったファイルが乱立し、混乱を招きます。古い情報に戻ってしまう「先祖返り」も頻繁に起こります。
- 情報伝達のタイムラグ: 設計部門がBOMを更新しても、そのファイルがメールで購買部門や製造部門に届き、担当者が確認するまでには時間がかかります。このタイムラグの間に、購買部門は古い情報に基づいて部品を発注してしまったり、製造部門は変更前の図面で準備を進めてしまったりするリスクがあります。
- 同時編集ができない: 共有サーバー上のExcelファイルは、基本的に誰か一人が開いていると他の人は編集できません(読み取り専用になる)。これにより、他の担当者の作業が終わるのを待たなければならず、業務のボトルネックになります。
部門ごとに見ている情報の鮮度が異なるという状況は、致命的な手戻りやロスコストを生み出します。例えば、コスト削減のために部品変更を行ったにもかかわらず、その情報が原価管理部門にリアルタイムで伝わらなければ、いつまでも古い原価で採算評価が行われ、経営判断を誤る可能性があります。
これらの3つの課題は、互いに密接に関連しています。属人化しているから標準的な更新ルールがなく更新漏れが起き、リアルタイム共有ができないから各々がローカルで作業してバージョンが混乱する、という悪循環に陥りがちです。これらの課題を根本的に解決するためには、Excel管理の限界を認識し、より高度な管理手法へと移行することが求められます。
BOM(部品表)の管理方法とそれぞれの特徴
BOM管理の課題を解決するためには、自社に適した管理方法を選択することが重要です。ここでは、代表的な3つの管理方法「Excel」「生産管理システム」「BOMシステム」を取り上げ、それぞれのメリットとデメリットを比較・解説します。
| 管理方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| Excel(表計算ソフト) | ・導入コストが低い ・多くの人が操作に慣れている ・フォーマットの自由度が高い |
・属人化しやすい ・リアルタイム共有が困難 ・バージョン管理が難しい ・データ量増加で動作が重くなる ・階層構造の管理に不向き |
| 生産管理システム(ERP) | ・生産、購買、在庫など他業務と連携 ・データの一元管理が可能 ・M-BOMの管理に適している |
・導入、運用コストが高い ・E-BOMの管理機能が弱い場合がある ・機能が多すぎて使いこなせない可能性 |
| BOMシステム | ・複雑な階層構造の管理に特化 ・設計変更管理、履歴管理機能が豊富 ・E-BOMとM-BOMの統合管理が可能 ・他システムとの連携性が高い |
・専用システムのため導入コストがかかる ・BOM管理以外の機能は限定的 |
Excel(表計算ソフト)
多くの企業、特に中小企業において、依然としてBOM管理の主流となっているのがMicrosoft Excelなどの表計算ソフトです。
メリット
- 導入コストが低い: 多くの企業では既にOfficeソフトが導入されており、追加のコストをかけずに始められます。
- 操作の習熟度が高い: ほとんどの事務作業者がExcelの基本操作に慣れているため、教育コストが低く、手軽に利用を開始できます。
- 自由度が高い: 決まったフォーマットがないため、自社の運用に合わせて自由に項目を追加したり、レイアウトを変更したりできます。
デメリット
Excelの手軽さは、裏を返せばBOM管理における様々な課題の温床となり得ます。
- 属人化と標準化の困難さ: 自由度が高いがゆえに、作成者ごとにフォーマットがバラバラになり、属人化が進みます。全社で統一したルールを徹底させることが非常に困難です。
- リアルタイム性とバージョン管理の問題: 「BOM管理における課題」で述べた通り、リアルタイムな情報共有ができず、どれが最新版か分からなくなる問題が常に付きまといます。
- データ量の限界: 製品の部品点数が増え、BOMの行数や列数が多くなると、ファイルの動作が極端に重くなり、実用性が著しく低下します。
- 階層構造の表現力不足: ストラクチャ型(多段階型)のBOMを表現するには、インデント機能を使ったり、親子関係を示す列を別途設けたりするなどの工夫が必要ですが、直感的ではなく、メンテナンスも非常に煩雑です。親子関係をたどる正展開や逆展開も、複雑な関数やマクロを組まない限り実現できません。
- セキュリティと権限管理の脆弱性: ファイル単位でのパスワード設定は可能ですが、項目ごとやユーザーごとに細かなアクセス権限を設定することは困難です。重要なコスト情報などが誰でも閲覧できる状態になるリスクがあります。
Excelでの管理は、部品点数が少なく、ごく小規模な組織での一時的な利用には適していますが、組織的なBOM管理ツールとしては限界があると言わざるを得ません。
生産管理システム
生産管理システムやERP(Enterprise Resource Planning:企業資源計画)は、企業の基幹業務(生産、販売、購買、在庫、会計など)を統合的に管理するためのシステムです。これらのシステムの多くは、機能の一部としてBOM管理機能を備えています。
メリット
- 業務連携: 生産計画、購買管理、在庫管理、原価計算といった他のモジュールとBOMデータがシームレスに連携します。M-BOMを登録すれば、MRP計算から発注指示、原価計算までが一気通貫で行えるのが最大の強みです。
- データの一元管理: 部品マスタやBOM情報がサーバー上で一元管理されるため、全部門が常に同じ最新の情報を参照でき、Excelのようなバージョン管理の問題は発生しません。
- M-BOM管理への適合性: 主に製造現場での利用を想定して作られているため、製造工程やリードタイムといった情報を持つM-BOMの管理に適しています。
デメリット
- 高コスト: 一般的に導入費用やライセンス費用、保守費用が高額になる傾向があります。
- E-BOM管理の機能不足: 生産管理システムは「どう作るか」に主眼を置いているため、設計部門が使うE-BOMの管理機能が弱い、あるいは備えていない場合があります。図面情報との連携や、設計変更プロセスの管理といった機能は、専用のBOMシステムに劣ることが多いです。
- 柔軟性の低さ: パッケージシステムであるため、自社の特殊な業務フローに合わせるためのカスタマイズには追加費用や時間がかかる場合があります。また、機能が豊富すぎるがゆえに、操作が複雑で使いこなせないというケースも少なくありません。
生産管理システムは、M-BOMを中心とした製造プロセスの効率化を目指す場合には非常に有効な選択肢です。
BOMシステム
BOMシステムは、その名の通り、BOMの管理に特化した専門のソフトウェアです。複雑化する製品情報を効率的かつ正確に管理するために開発されました。
メリット
- 高度なBOM管理機能: ストラクチャ型(多段階型)のBOMを直感的に、かつ効率的に作成・編集できます。正展開・逆展開も標準機能として備わっており、設計変更の影響範囲などを容易に特定できます。
- 設計変更管理機能: いつ、誰が、何を、なぜ変更したのかという履歴(版数)を自動で、かつ詳細に管理できます。変更の申請・承認を行うワークフロー機能も充実しており、内部統制の強化にも繋がります。
- E-BOMとM-BOMの統合管理: 近年のBOMシステムの多くは、設計部門が使うE-BOMと、製造部門が使うM-BOMを一つのデータベースで関連付けて管理する「統合BOM」の思想に基づいて設計されています。これにより、設計変更情報をスムーズに製造部門へ連携できます。
- 他システムとの連携性: CAD、PLM(製品ライフサイクル管理)、ERP(生産管理システム)など、関連する様々なシステムと連携するためのインターフェース(APIなど)が豊富に用意されています。
デメリット
- 導入コスト: 専用システムであるため、Excelに比べて当然ながら導入コストがかかります。
- 機能の特化: BOM管理とその周辺業務(品目管理、設計変更管理など)に機能が特化しているため、生産計画や在庫管理といった機能は別途、生産管理システムなどと連携させる必要があります。
BOMシステムは、特に部品点数が多く、設計変更が頻繁に発生する、あるいはE-BOMとM-BOMの連携に課題を抱えている企業にとって、最も効果的な解決策となり得ます。
BOMシステムでできること(主な機能)
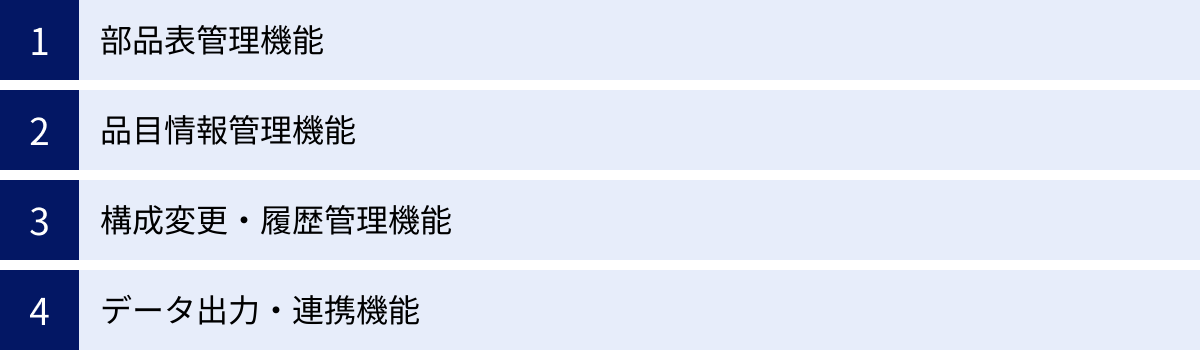
BOM管理の課題を解決し、業務を飛躍的に効率化するBOMシステムですが、具体的にどのようなことができるのでしょうか。ここでは、BOMシステムが持つ代表的な機能を4つに分けて解説します。これらの機能を活用することで、Excel管理では実現が難しかった高度なBOM運用が可能になります。
部品表管理機能
これはBOMシステムの最も核となる機能です。手作業では煩雑だったBOMの作成・編集・参照を、効率的かつ正確に行うための仕組みが提供されています。
- 階層構造の直感的な編集: 製品のツリー構造を画面上で視覚的に確認しながら、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で部品の追加や削除、階層の移動ができます。Excelのように行の挿入やインデント調整に手間取ることはありません。
- 正展開・逆展開:
- 正展開(フォワード展開): 特定の親部品(製品やユニット)を選択すると、それを構成するすべての子部品、孫部品を一覧で表示します。製品を1台作るのに必要な全部品リストを作成する際に使用します。
- 逆展開(リバース展開): 特定の子部品を選択すると、その部品が使用されているすべての親部品(ユニットや最終製品)を一覧で表示します。設計変更や部品の廃版時に、影響範囲を漏れなく特定するために不可欠な機能です。例えば、「ネジA」がどの製品のどこで使われているかを瞬時に調べることができます。
- 構成比較: 2つの異なるBOM(例えば、旧バージョンと新バージョン)を比較し、追加・削除・変更された箇所をハイライト表示します。これにより、設計変更の内容が一目で分かり、確認作業の負担を大幅に軽減します。
品目情報管理機能
BOMは部品の「構成」情報ですが、その構成要素である個々の「品目(部品や材料)」自体の情報も一元管理する必要があります。多くのBOMシステムは、この品目マスタを管理する機能を備えています。
- 品目情報の一元化: 品目コード、品名、仕様、規格、材質、重量といった基本的な属性情報に加えて、図面や仕様書などの関連ドキュメント、サプライヤー情報、購入単価、標準原価といった多様な情報を、一つの品目コードに紐づけて管理します。
- 重複登録の防止: 新しい部品を登録する際に、過去に類似の部品が登録されていないかを検索する機能があります。これにより、同じ部品が異なる品目コードで二重に登録されるといったマスタの不整合を防ぎ、部品種類の削減(標準化)を促進します。
- 属性情報の柔軟な設定: 企業独自の管理項目(例:「環境規制対応フラグ」「競合品情報」など)を自由に追加できるシステムも多く、自社の業務に合わせた品目管理が可能です。
品目情報が正確に一元管理されていることは、精度の高いBOMを構築するための大前提となります。
構成変更・履歴管理機能
頻繁に発生する設計変更プロセスを、体系的に管理し、その記録を正確に残すことは、品質保証やトレーサビリティの観点から非常に重要です。BOMシステムは、この設計変更管理を強力に支援します。
- 版数(バージョン)管理: BOMや品目を変更するたびに、版数が自動的に採番され、古いバージョンの情報もすべて履歴として保存されます。これにより、「いつの時点の構成」であったかを正確に再現できます。
- 設計変更ワークフロー: 設計変更の「起票」→「内容確認」→「関連部門への回覧」→「承認」→「BOMへの反映」といった一連のプロセスをシステム上で電子化できます。誰の承認待ちで止まっているのかが可視化され、プロセスが迅速に進みます。また、承認された変更のみが正式なBOMに反映されるため、不正な変更を防ぎ、内部統制を強化します。
- 有効期間管理: 「このBOM構成は、YYYY年MM月DD日から有効」「この部品は、製品シリアルNo.XXXまで使用し、以降は後継品に切り替え」といった、時間軸や製品ロットに応じた構成の切り替えを予約・管理できます。これにより、計画的な部品切り替えが可能になり、現場の混乱を防ぎます。
データ出力・連携機能
BOMシステムは、それ単体で完結するのではなく、社内の他のシステムと連携してこそ、その価値を最大限に発揮します。
- データ出力: 管理しているBOMや品目情報を、ExcelやCSVといった汎用的な形式で出力できます。これにより、システム化されていない業務でのデータ活用や、帳票作成が容易になります。
- 他システム連携:
- CAD連携: 設計者が利用する3D CADの部品構成情報を直接BOMシステムに取り込み、E-BOMを自動生成します。設計とBOM作成の二度手間をなくします。
- ERP/生産管理システム連携: BOMシステムで承認された最新のM-BOM情報を、ERPや生産管理システムに自動で連携します。これにより、MRP計算や生産指示が常に最新の正しい情報に基づいて行われます。
- PLM連携: 製品ライフサイクル全体を管理するPLMシステムと連携し、企画段階から保守段階まで、製品情報を一気通貫で管理する中核として機能します。
これらのデータ連携機能により、部門間の情報の流れが自動化・高速化され、データの二重入力といった無駄な作業を排除し、組織全体の生産性を向上させます。
BOMシステムを選ぶ際の3つのポイント
BOMシステムの導入は、決して安価な投資ではありません。導入後に「自社の業務に合わなかった」「うまく活用できない」といった事態を避けるためにも、慎重なシステム選定が不可欠です。ここでは、BOMシステムを選ぶ際に特に重視すべき3つのポイントを解説します。
① 自社の業種や業務内容に合っているか
BOMのあり方は、企業の業種や生産形態によって大きく異なります。自社の特性を正しく理解し、それにマッチしたシステムを選ぶことが最も重要です。
- 業種特性:
- 組立加工業(自動車、電機など): 階層構造が複雑になりがちで、設計変更も頻繁なため、ストラクチャ型BOMの管理や設計変更管理機能が強力なシステムが求められます。
- プロセス産業(化学、食品など): 部品の「個数」ではなく、原材料の「配合率」や「レシピ」を管理するBOM(配合BOM、レシピBOM)が中心となります。このような特殊なBOMに対応できるシステムかを確認する必要があります。
- 個別受注生産(産業機械、プラントなど): 案件ごとに仕様が異なるため、過去の類似案件のBOMを流用・編集して、効率的に新しいBOMを作成できる機能が重要になります。
- BOM管理の重心:
- E-BOM(設計部品表)中心か: 設計部門の業務効率化や、CAD連携を最優先するなら、E-BOM管理や設計変更ワークフローに強いシステムを選定します。PLMシステムの一部として提供されるBOM機能も選択肢になります。
- M-BOM(製造部品表)中心か: 製造現場での生産効率化や、原価管理の精度向上が主な目的なら、生産管理システムとの連携がスムーズで、M-BOMの管理機能が充実したシステムが適しています。
- 統合BOMを目指すか: 設計から製造までの情報連携の断絶が最大の課題であるならば、E-BOMとM-BOMを一元的に管理できる「統合BOM」に対応したシステムが必須となります。
まずは自社の現状の課題を明確にし、「何のためにBOMシステムを導入するのか」という目的を社内で共有することが、適切なシステム選定の第一歩です。
② 既存システムと連携できるか
BOMシステムは、単独で利用するよりも、社内の既存システムと連携させることで真価を発揮します。導入を検討しているBOMシステムが、現在利用しているシステムとスムーズに連携できるか否かは、導入効果を左右する重要な要素です。
- CADシステム: 設計部門で利用しているCAD(2D/3D)の種類を確認し、そのCADとの連携実績が豊富なBOMシステムを選びましょう。CADの部品情報を手作業でBOMに再入力するのでは、導入効果が半減してしまいます。
- ERP/生産管理システム: 現在稼働しているERPや生産管理システムとの連携インターフェース(APIなど)が標準で用意されているか、あるいはアドオンで対応可能かを確認します。連携実績がない場合、個別の開発が必要になり、追加のコストと時間が発生します。
- その他のシステム: PDM(製品データ管理)やPLM(製品ライフサイクル管理)など、他の情報システムを利用している場合も同様に、連携の可否を確認することが重要です。
システムベンダーに、自社が利用しているシステム名やバージョンを具体的に伝え、連携の実績や方法、費用について詳細な情報を求めるようにしましょう。理想は、データの流れを自動化し、二重入力を完全に排除できる構成です。
③ クラウド型かオンプレミス型か
BOMシステムの提供形態には、大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社のIT戦略や予算、リソースに合った形態を選ぶ必要があります。
| 提供形態 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| クラウド型(SaaS) | ベンダーが提供するサーバー上のシステムを、インターネット経由で利用する。 | ・初期費用が安い ・短期間で導入可能 ・サーバー管理が不要 ・場所を問わずアクセス可能 |
・月額/年額の利用料が発生 ・カスタマイズの自由度が低い ・セキュリティポリシーはベンダーに依存 |
| オンプレミス型 | 自社のサーバーにソフトウェアをインストールして利用する。 | ・カスタマイズの自由度が高い ・自社のセキュリティポリシーを適用可能 ・既存システムとの連携がしやすい場合がある |
・初期費用(ライセンス、サーバー代)が高い ・導入に時間がかかる ・自社でのサーバー運用・保守が必要 |
- クラウド型が適しているケース:
- 初期投資を抑えたい企業
- 専任のIT管理者がいない、または少ない企業
- スピーディーに導入を開始したい企業
- 複数の拠点やテレワークでの利用を想定している企業
- オンプレミス型が適しているケース:
- 独自の業務フローに合わせた大幅なカスタマイズが必要な企業
- 非常に高いセキュリティレベルが求められ、自社内でデータを管理したい企業
- サーバーの運用・保守を行うためのITリソースが豊富な企業
近年は、導入の手軽さやメンテナンスの負荷軽減から、クラウド型のBOMシステムが主流になりつつあります。しかし、企業の規模や業種、セキュリティ要件によっては、依然としてオンプレミス型が最適な選択となる場合もあります。両方のメリット・デメリットを十分に比較検討し、長期的な視点で自社に最適な提供形態を判断することが肝要です。
おすすめのBOMシステム5選
ここでは、国内で提供されている代表的なBOMシステムを5つ紹介します。各システムはそれぞれ異なる特徴や強みを持っています。自社の課題や要件と照らし合わせながら、システム選定の参考にしてください。
(※掲載されている情報は、各公式サイトで公開されている情報に基づいています。最新の詳細情報や料金については、各提供企業へ直接お問い合わせください。)
① Celb(株式会社クラステクノロジー)
Celb(セルブ)は、株式会社クラステクノロジーが開発・提供する統合BOMシステムです。設計部品表(E-BOM)と製造部品表(M-BOM)の統合管理に強みを持ち、設計から製造までの情報連携をシームレスに実現することを目指しています。
- 主な特徴:
- 統合BOM: E-BOMとM-BOMを単一のデータベースで管理し、相互の関連性を維持したまま運用できます。設計変更がM-BOMへスムーズに反映される仕組みが特徴です。
- 柔軟な品目・構成管理: 品目の属性やBOMの表示形式をユーザーが柔軟に設定でき、さまざまな業種の要件に対応可能です。
- 強力な設計変更管理: 詳細な履歴管理機能や、電子承認ワークフロー機能を標準で搭載しています。
- 提供形態: オンプレミス型、クラウド型
- こんな企業におすすめ:
- E-BOMとM-BOMの二重管理に課題を抱えている企業
- 設計変更が多く、その管理プロセスを効率化したい企業
- 自社の業務に合わせて柔軟にカスタマイズしたい企業
参照:株式会社クラステクノロジー 公式サイト
② rBOM(株式会社アットストリーム)
rBOM(アールボム)は、株式会社アットストリームが提供する製造業向けのBOMシステムです。特に個別受注生産や多品種少量生産を行う企業にフィットするように設計されており、高速なBOMの編集・登録機能を特徴としています。
- 主な特徴:
- 高速な操作性: Excelライクな操作感で、大量の品目や複雑な階層を持つBOMもストレスなく編集できます。類似BOMのコピーや一括編集機能も充実しています。
- 製番管理・MRP対応: 個別受注生産で重要となる製番(製造番号)ごとのBOM管理や、所要量計算(MRP)にも対応しています。
- 柔軟な連携: 各社の生産管理システム(ERP)やCADとの連携実績が豊富です。
- 提供形態: オンプレミス型
- こんな企業におすすめ:
- 個別受注生産や多品種少量生産が中心の企業
- Excelからの移行をスムーズに行いたい企業
- 既存の生産管理システムと連携してBOM管理を強化したい企業
参照:株式会社アットストリーム 公式サイト
③ UM SaaS Cloud(株式会社シナプスイノベーション)
UM SaaS Cloudは、株式会社シナプスイノベーションが提供するクラウド型の基幹業務システムです。販売管理、生産管理、在庫管理といった機能群の一つとして、BOM(部品表)管理機能を備えています。
- 主な特徴:
- クラウドネイティブ: 100%クラウドで提供されており、サーバー管理不要で手軽に導入できます。
- 多機能なモジュール: BOM管理だけでなく、販売、生産、在庫、原価といった製造業の基幹業務をトータルでカバーできます。必要な機能だけを選択してスモールスタートすることも可能です。
- M-BOM中心の管理: 生産管理システムの一部であるため、M-BOMを中心とした管理に適しており、生産計画や原価計算との連携がスムーズです。
- 提供形態: クラウド型(SaaS)
- こんな企業におすすめ:
- BOM管理だけでなく、基幹業務システム全体をクラウドで刷新したい企業
- 初期投資を抑えてスピーディーにシステムを導入したい中小企業
- 製造現場の効率化や原価管理の精度向上を主目的とする企業
参照:株式会社シナプスイノベーション 公式サイト
④ Production Master(株式会社図研プリサイト)
Production Masterは、PLM/PLMシステムベンダーである株式会社図研プリサイトが提供する、製造準備業務を効率化するためのソリューションです。E-BOMとM-BOMの連携に特化した機能を持ちます。
- 主な特徴:
- E-BOMとM-BOMの連携に特化: 設計部門が作成したE-BOMを、生産技術部門がM-BOMへとスムーズに変換・編集するための強力な機能を備えています。両者の差分を可視化し、設計変更への追従を容易にします。
- ビジュアルなBOM編集: 3Dデータを活用し、ビジュアルで分かりやすい製造手順書や作業指示書を作成できます。
- PLM/PDMとの親和性: 親会社である図研のPLM/PDMシステムとの連携はもちろん、他社システムとの連携も可能です。
- 提供形態: オンプレミス型
- こんな企業におすすめ:
- 設計と製造の間の「壁」を取り払い、コンカレントエンジニアリングを推進したい企業
- 3Dデータを活用して、製造準備業務を効率化・高度化したい企業
- E-BOMからM-BOMへの変換作業に多くの工数がかかっている企業
参照:株式会社図研プリサイト 公式サイト
⑤ i-PRODFCUE(株式会社アイ・ディ・エス)
i-PRODFCUE(アイ・プロッヂキュー)は、株式会社アイ・ディ・エスが提供する中小製造業向けの生産管理システムです。BOM管理機能を中核に、見積、受注、生産、出荷、在庫までを幅広くカバーします。
- 主な特徴:
- 中小企業向け: 中小製造業の現場のニーズに合わせて、必要な機能をシンプルで分かりやすく提供しています。
- 柔軟なカスタマイズ: パッケージをベースに、ユーザーの要望に応じたカスタマイズにも柔軟に対応可能です。
- ワンストップ対応: システム導入のコンサルティングから開発、保守までをワンストップで提供しています。
- 提供形態: オンプレミス型、クラウド型
- こんな企業におすすめ:
- 初めて生産管理システムを導入する中小企業
- 自社の業務に合わせたカスタマイズを重視する企業
- 手厚い導入サポートを求めている企業
参照:株式会社アイ・ディ・エス 公式サイト
BOMとPLMを連携させる重要性
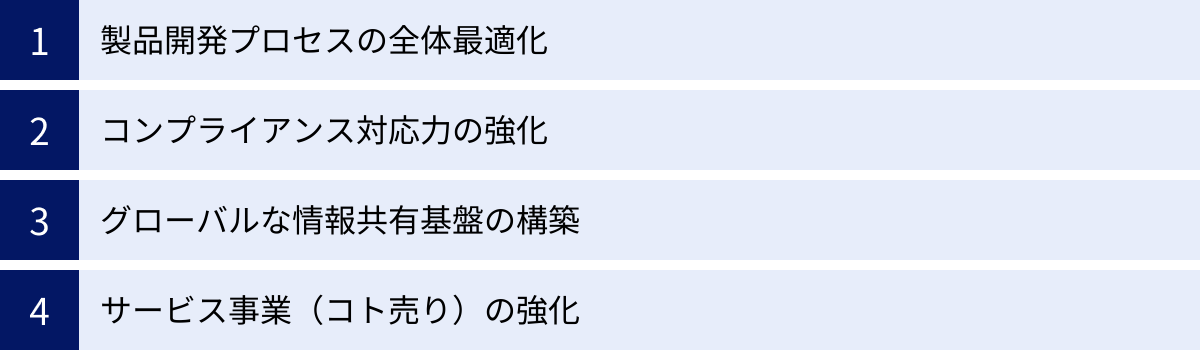
これまでBOMの重要性について解説してきましたが、企業の競争力をさらに高めるためには、BOMをより大きな枠組みの中で捉える視点が不可欠です。それが、PLM(Product Lifecycle Management:製品ライフサイクル管理)との連携です。
PLMとは、製品の企画・構想から、設計、開発、生産準備、製造、販売、保守・メンテナンス、そして廃棄に至るまで、製品が生まれてからその役目を終えるまでの全期間(ライフサイクル)にわたる情報を一元管理し、部門や拠点の壁を越えて共有・活用するための経営手法、またはそれを実現するシステムを指します。
BOMは、このPLMの中核をなす、極めて重要な情報要素です。製品の構成を定義するBOMがなければ、製品ライフサイクル全体の情報を体系的に管理することはできません。
BOMとPLMを連携させることには、以下のような重要なメリットがあります。
- 製品開発プロセスの全体最適化:
PLMシステム上で、製品の企画段階で立てられた要件(コスト、品質、環境規制など)と、設計段階で作成されるE-BOMが紐づけられます。これにより、設計者は常に製品全体の目標を意識しながら設計を進めることができます。設計変更がコストやコンプライアンスに与える影響も、ライフサイクル全体の視点で評価できるようになり、開発プロセス全体の手戻りを防ぎます。 - コンプライアンス対応力の強化:
近年、RoHS指令やREACH規則など、製品に含まれる化学物質に対する国際的な規制は年々厳しくなっています。PLMとBOMを連携させることで、BOMを構成する各部品の材質や含有化学物質の情報を一元管理できます。特定の規制物質がどの製品のどの部品で使われているかを瞬時に特定し、レポートを提出したり、代替部品への切り替えを計画したりすることが容易になります。 - グローバルな情報共有基盤の構築:
開発拠点が海外にあったり、生産を外部に委託したりと、サプライチェーンがグローバルに広がる中で、関係者全員が同じ最新情報にアクセスできる環境は不可欠です。PLM/BOMシステムは、そのための共通プラットフォームとして機能します。時差や言語の壁を越えて、設計情報や仕様変更情報がリアルタイムで共有されることで、グローバル規模でのコンカレントエンジニアリングを実現します。 - サービス事業(コト売り)の強化:
製品出荷後の保守・メンテナンス情報もPLMの管理対象です。市場で発生した不具合情報や、顧客からの改善要望をPLMにフィードバックし、それを次期製品の設計(E-BOM)に反映させることができます。また、S-BOM(サービス部品表)もPLM上で管理することで、設計変更と保守部品情報を連動させ、的確なアフターサービスを提供できます。
BOM管理を最適化することは、いわば「点の改善」です。それに対し、PLMと連携させることは、製品ライフサイクル全体を俯瞰した「線の改善」「面の改善」に繋がります。BOM管理の高度化の先には、このPLMとの統合を見据えることが、持続的な成長を目指す製造業にとって重要な戦略となるでしょう。
まとめ
本記事では、製造業の根幹を支えるBOM(部品表)について、その基本的な概念から目的、種類、管理方法、そしてBOMシステムの選び方まで、幅広く解説しました。
最後に、記事全体の要点を振り返ります。
- BOM(部品表)とは、製品を構成するすべての部品や材料の品目、数量、階層構造を体系的に示した、製造業の「マスターデータ」である。
- BOMの主な目的は、「生産管理の効率化」「正確な原価管理」「発注業務の精度向上」にあり、企業の生産性や収益性に直結する。
- BOMには、用途に応じてE-BOM(設計部品表)、M-BOM(製造部品表)、S-BOM(サービス部品表)といった種類があり、それぞれが異なる役割を担う。
- ExcelによるBOM管理は、「属人化」「入力ミス・更新漏れ」「リアルタイム共有の困難さ」といった多くの課題を抱えている。
- これらの課題を解決するためには、生産管理システムや、特にBOM管理に特化したBOMシステムの導入が有効な選択肢となる。
- BOMシステムを選ぶ際は、「自社の業種や業務内容への適合性」「既存システムとの連携性」「クラウド型かオンプレミス型か」という3つのポイントを慎重に検討することが重要。
- さらに、BOMをPLM(製品ライフサイクル管理)と連携させることで、製品開発から保守までを一気通貫で管理し、企業全体の競争力をより一層高めることができる。
BOMは、単なるデータやリストではありません。それは、企業の設計思想、製造ノウハウ、コスト構造が凝縮された、まさに「企業の資産」です。この重要な資産をいかに正確に、効率的に、そして戦略的に管理・活用できるか。その答えが、これからの製造業の未来を大きく左右すると言っても過言ではないでしょう。
本記事が、皆様のBOM管理に対する理解を深め、業務改善やシステム導入を検討する上での一助となれば幸いです。