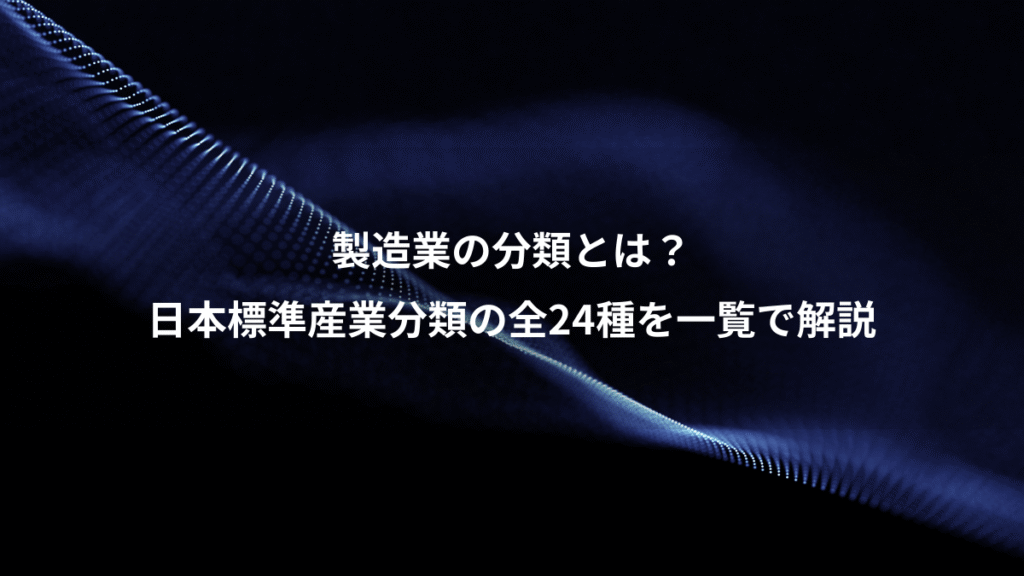日本の経済を支える基幹産業である製造業。一口に製造業といっても、その内容は多岐にわたります。私たちが日常的に使う食品や衣類から、自動車やスマートフォン、さらにはそれらを作るための機械や素材まで、すべてが製造業の産物です。
この記事では、製造業の全体像を理解するために不可欠な「分類」について、網羅的に解説します。公的な統計基準である「日本標準産業分類」における24の分類を一つひとつ丁寧に紹介するとともに、経済的な特徴に基づいたもう一つの分類方法や、現代の製造業が直面する課題、そして未来に向けた展望までを深掘りします。
製造業に関わるビジネスパーソンはもちろん、就職や転職で製造業を視野に入れている方、あるいは日本の産業構造を学びたい方にとっても、必見の内容です。
目次
製造業の分類とは

まずはじめに、「製造業」そのものの定義と、なぜ分類が必要なのか、そしてその基準となる「日本標準産業分類」について理解を深めていきましょう。
製造業の定義
製造業とは、有形の原材料などに物理的または化学的な変化を加え、新しい製品を生産する産業を指します。この「変化を加える」という点が重要で、単に商品を仕入れて販売する卸売業・小売業や、完成品を修理する事業とは明確に区別されます。
具体的には、農林水産物、鉱業生産物、あるいは他の製造業者が作った製品などを原材料として、機械や人の手による作業を通じて、市場で販売される新たな価値を持つ製品へと変換する活動全般が製造業に含まれます。
日本の経済において、製造業は非常に重要な位置を占めています。内閣府の国民経済計算によると、2022年度の名目国内総生産(GDP)に占める製造業の割合は約20.5%にのぼり、全産業の中で最大の構成比を誇ります。これは、製造業が日本の富の創出と経済成長の原動力であることを示しています。(参照:内閣府「2022年度(令和4年度)国民経済計算(2015年基準・2008SNA)」)
製造業を分類する目的は、主に以下の点が挙げられます。
- 統計の正確性と比較可能性の確保: 国勢調査や経済センサスなどの公的統計において、統一された基準でデータを収集・分析するために分類は不可欠です。これにより、産業構造の変化を時系列で追ったり、他国と比較したりできます。
- 経済政策の立案: 政府や地方自治体が、特定の産業分野を対象とした支援策や規制を検討する際、明確な分類がなければ効果的な政策を打つことができません。
- 企業活動の円滑化: 企業は自社がどの産業に属するかを客観的に把握することで、市場分析や競合調査、事業計画の策定がしやすくなります。また、金融機関からの融資や、補助金の申請などにおいても、事業内容を明確に示すために産業分類が利用されます。
- キャリア形成の指針: 就職や転職を考える個人にとって、どのような種類の製造業が存在し、それぞれにどんな特徴があるのかを理解することは、自身のキャリアパスを考える上で重要な情報となります。
このように、製造業の分類は、経済活動のあらゆる場面で羅針盤としての役割を果たしているのです。
分類の基準となる「日本標準産業分類」
日本のあらゆる産業を分類するための統一的な基準が、総務省が定める「日本標準産業分類」です。これは、統計調査の結果を産業別に表示する場合の基準として設定されており、国のすべての公的統計で原則としてこの分類が用いられます。
日本標準産業分類は、社会経済の構造変化に対応するため、おおむね5年ごとに改定が行われています。最新のものは、2023年6月に公表され、2024年4月1日から施行された「第14回改定」です。このような定期的な見直しにより、時代の変化に即した実態把握が可能となっています。(参照:総務省「日本標準産業分類」)
この分類は、以下のような階層構造を持っています。
- 大分類: 産業全体を20の大きなカテゴリに分けたもの(例:A 農業,林業、E 製造業)
- 中分類: 大分類をさらに細分化したもの(例:E-11 飲料・たばこ・飼料製造業)
- 小分類: 中分類をさらに細分化したもの(例:111 清涼飲料製造業)
- 細分類: 小分類をさらに細分化したもの(例:1111 炭酸飲料製造業)
製造業は、この構造の中で「大分類E」に位置づけられています。 そして、その下に24の中分類が設けられており、これが一般的に「製造業の24分類」として知られているものです。
この分類を理解することで、ある企業が「製造業」という大きな枠組みの中で、具体的にどのような領域で事業を行っているのかを正確に把握できます。例えば、「輸送用機械器具製造業」に分類される企業であれば、自動車や船舶、航空機などに関連する事業を展開していることがわかります。
次の章では、この「大分類E-製造業」に属する24の中分類を、一つひとつ具体的に見ていくことにしましょう。
日本標準産業分類における製造業24分類一覧
ここでは、日本標準産業分類(第14回改定)における「大分類E-製造業」に属する24の中分類について、その概要と主な製品例を一覧で解説します。ご自身の業界や関心のある分野がどこに該当するのかを確認しながら読み進めてみてください。
| 分類コード | 分類名 | 主な内容・製品例 |
|---|---|---|
| 09 | 食料品製造業 | パン、菓子、冷凍食品、乳製品、調味料、精肉、水産加工品など、生鮮食品以外の飲食料品の製造 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 清涼飲料、酒類、茶、コーヒー、たばこ、ペットフードを含む配合飼料などの製造 |
| 11 | 繊維工業 | 糸、織物、ニット製品、衣類、じゅうたん、漁網、レースなどの繊維製品の製造 |
| 12 | 木材・木製品製造業(家具を除く) | 製材、合板、木材チップ、集成材、木製容器(たる、おけ)、建具以外の建築用木製品の製造 |
| 13 | 家具・装備品製造業 | 木製・金属製の家具、建具、オフィス用什器、宗教用具、モデル・模型などの製造 |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | パルプ、紙、板紙、段ボール、壁紙、衛生用紙、事務用紙製品などの製造 |
| 15 | 印刷・同関連業 | 書籍・雑誌の印刷、商業印刷(チラシ、ポスター)、事務用印刷物、製本、印刷版の製造 |
| 16 | 化学工業 | 化学肥料、基礎化学製品(ソーダ等)、合成樹脂、医薬品、化粧品、塗料、洗剤、火薬などの製造 |
| 17 | 石油製品・石炭製品製造業 | ガソリン、灯油、アスファルトなどの石油精製品、コークス、練炭・豆炭などの石炭製品の製造 |
| 18 | プラスチック製品製造業(別掲を除く) | プラスチック板・フィルム、工業用部品、発泡製品、プラスチック製容器、建材などの製造 |
| 19 | ゴム製品製造業 | 自動車用タイヤ・チューブ、ゴムベルト、ゴムホース、工業用ゴム製品、ゴム履物などの製造 |
| 20 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | なめし革、革製履物、かばん、袋物、革手袋、毛皮製品などの製造 |
| 21 | 窯業・土石製品製造業 | ガラス製品、セメント、コンクリート製品、陶磁器、耐火物、炭素・黒鉛製品、研磨材などの製造 |
| 22 | 鉄鋼業 | 製鉄、製鋼、熱間圧延鋼材、めっき鋼材、鋳鉄管、鋳鋼品、鍛鋼品などの製造 |
| 23 | 非鉄金属製造業 | 銅、亜鉛、アルミニウムなどの精錬・精製、圧延製品、電線・ケーブルなどの製造 |
| 24 | 金属製品製造業 | 金属製容器(缶、ボンベ)、建築用・建設用金属製品、ボルト、ナット、ばね、金網などの製造 |
| 25 | はん用機械器具製造業 | ボイラ、エンジン、ポンプ、圧縮機、コンベヤ、クレーン、エレベータ、ベアリングなどの製造 |
| 26 | 生産用機械器具製造業 | 農業用機械、建設機械、鉱山機械、工作機械、半導体製造装置、ロボットなどの製造 |
| 27 | 業務用機械器具製造業 | 事務用機械、複写機、自動販売機、冷凍・冷蔵ショーケース、計量器、医療用機械・器具などの製造 |
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 半導体素子、集積回路(IC)、液晶パネル、有機ELパネル、抵抗器、コンデンサ、電子回路基板などの製造 |
| 29 | 電気機械器具製造業 | 発電機、変圧器、配電盤、家庭用電化製品、照明器具、電池、配線器具などの製造 |
| 30 | 情報通信機械器具製造業 | 電話機、ルータ等の有線通信機器、携帯電話等の無線通信機器、放送機器、コンピュータ、サーバなどの製造 |
| 31 | 輸送用機械器具製造業 | 自動車・同部品、鉄道車両、船舶、航空機、自転車などの製造 |
| 32 | その他の製造業 | 上記に分類されないもの(貴金属製品、宝石、楽器、玩具、文房具、運動用具、義肢など) |
(参照:総務省「日本標準産業分類(第14回改定)」)
① 食料品製造業
私たちの食生活に最も身近な産業の一つです。生鮮食品や単純な加工(選別や洗浄など)を除き、農畜水産物を原材料として保存性や付加価値を高めた飲食料品を製造する事業が分類されます。具体的には、精肉・部分肉、冷凍食品、乳製品(牛乳、チーズ、バター)、パン・菓子、調味料(みそ、しょうゆ)、缶詰、レトルト食品などが含まれます。人々のライフラインを支える重要な産業です。
② 飲料・たばこ・飼料製造業
飲料、たばこ、そして家畜やペットのための飼料を製造する産業です。飲料には、清涼飲料水、果実・野菜ジュース、茶・コーヒー、ミネラルウォーター類、さらにはビール、清酒、焼酎といった酒類も含まれます。これらは、食料品製造業と密接に関連しながらも、独立した分類となっています。
③ 繊維工業
天然繊維(綿、羊毛、絹など)や化学繊維から、糸、織物、編物(ニット)を製造し、さらにそれらを加工して最終製品を作る産業です。衣類(アウターウェア、下着)、寝具、じゅうたん、カーテン、タオル、さらには産業用のロープや漁網まで、幅広い製品がここに含まれます。ファッションの流行やライフスタイルの変化に影響を受けやすい特徴があります。
④ 木材・木製品製造業(家具を除く)
木材を加工して、さまざまな製品を製造する産業です。山から伐採された原木を製材して柱や板にしたり、それらを組み合わせて集成材や合板を作ったりする事業が中心です。その他、木箱や樽(たる)といった木製容器、建築用の足場板なども含まれます。ただし、後述する家具や建具は、この分類には含まれません。
⑤ 家具・装備品製造業
主に最終消費者が使用する家具や、建物に取り付けられる装備品を製造する産業です。木製家具(たんす、机、いす)、金属製家具、マットレス、ブラインド、さらにはドアや窓枠といった建具、神棚や仏壇などの宗教用具もこの分類です。デザイン性や機能性が重視され、インテリアのトレンドに大きく左右されます。
⑥ パルプ・紙・紙加工品製造業
木材チップや古紙を原料としてパルプを製造し、そのパルプから紙や板紙を作る産業です。新聞用紙、印刷用紙、包装用紙、段ボール原紙、トイレットペーパーやティッシュペーパーといった衛生用紙などが主な製品です。また、作られた紙を加工して、ノートや封筒、紙コップ、段ボール箱などを作る事業も含まれます。
⑦ 印刷・同関連業
紙などの媒体に、文字や画像などの情報を印刷する産業です。書籍や雑誌、新聞といった出版印刷、チラシやカタログ、ポスターなどの商業印刷が中心です。また、印刷だけでなく、印刷されたものを断裁したり折り曲げたりして冊子にする製本業や、印刷用の版(はん)を作る事業もこの分類に含まれます。
⑧ 化学工業
化学反応を利用して、多種多様な製品を製造する非常に裾野の広い産業です。肥料、基礎的な化学薬品(ソーダ、硫酸など)、プラスチックや合成ゴムといった合成樹脂、塗料、インキ、石けん・洗剤、化粧品、そして医薬品などが代表的な製品です。あらゆる産業に素材や中間財を供給する重要な役割を担っています。
⑨ 石油製品・石炭製品製造業
原油や石炭を精製・加工して、燃料や化学製品の原料などを製造する産業です。原油からはガソリン、灯油、軽油、重油といった燃料油や、アスファルトなどが作られます。石炭からは、製鉄に使うコークスや、練炭・豆炭などが製造されます。国家のエネルギー供給を支える基幹産業です。
⑩ プラスチック製品製造業(別掲を除く)
化学工業で作られたプラスチック(合成樹脂)を主原料として、成形加工によりさまざまな製品を製造する産業です。プラスチック製の板、棒、フィルム、発泡スチロール製品、上下水道管、包装容器、自動車部品、家電製品の筐体(ケース)など、その用途は極めて広範囲にわたります。
⑪ ゴム製品製造業
天然ゴムや合成ゴムを原料として、弾力性のある製品を製造する産業です。最も代表的な製品は自動車用のタイヤやチューブです。その他、コンベヤベルトやVベルトといった工業用ベルト、高圧ホース、防振ゴム、ゴム手袋、ゴム製の履物(長靴など)もこの分類に含まれます。
⑫ なめし革・同製品・毛皮製造業
動物の皮を、腐敗しないように薬品で処理する「なめし」という工程を経て、革を製造する事業が中心です。また、そのなめし革を使って、靴、かばん、ハンドバッグ、ベルト、手袋などの革製品を製造する事業も含まれます。毛皮や毛皮製品の製造もこの分類です。
⑬ 窯業・土石製品製造業
粘土や石、砂などの無機物を、高温で焼く(窯業)か、加工(土石製品)して製品を製造する産業です。ガラスおよび同製品(板ガラス、びん)、セメント、コンクリート製品(ブロック、ヒューム管)、陶磁器(食器、タイル)、耐火レンガ、炭素製品(電極など)といった、社会インフラや建築に欠かせない素材・製品が多く含まれます。
⑭ 鉄鋼業
鉄鉱石や鉄くずを原料として、鉄鋼製品を製造する産業です。高炉で鉄鉱石から鉄を取り出す製鉄業、転炉や電気炉で鋼(はがね)を製造する製鋼業、そして鋼を圧延してH形鋼や鋼板、棒鋼などにする圧延業が主要な工程です。日本のものづくりの根幹を支える素材産業です。
⑮ 非鉄金属製造業
鉄以外の金属(非鉄金属)を製造する産業です。銅、鉛、亜鉛、アルミニウム、金、銀などを鉱石から取り出して精錬する事業や、それらの金属を圧延して板や棒にしたり、合金を製造したりする事業が含まれます。軽量で加工しやすいアルミニウムや、電気を通しやすい銅は、特に重要な素材です。電線・ケーブルの製造もこの分類です。
⑯ 金属製品製造業
鉄鋼や非鉄金属を材料として、さまざまな金属製品を加工・製造する産業です。飲料用の缶やドラム缶、高圧ガスボンベといった金属製容器、橋梁や鉄骨、サッシなどの建築用金属製品、ボルト・ナット・リベット、ばね、作業工具、金網、食卓用ナイフ・フォークなどが含まれます。
⑰ はん用機械器具製造業
特定の産業分野に限定されず、さまざまな産業で共通して(汎用的に)使われる機械や器具を製造する産業です。ボイラ、産業用エンジン、ポンプ、コンプレッサ、送風機、クレーンやコンベヤなどの運搬機械、エレベータ、エスカレータ、そして機械の回転部分を支えるベアリングなどが代表例です。
⑱ 生産用機械器具製造業
特定の生産活動のために使われる専門的な機械や設備を製造する産業です。農業用機械(トラクターなど)、建設・鉱山機械(ショベルカーなど)、金属やプラスチックを加工する工作機械、食品製造機械、繊維機械、そして現代のハイテク産業に不可欠な半導体製造装置や産業用ロボットなどが含まれます。
⑲ 業務用機械器具製造業
オフィスや店舗、病院などで業務のために使われる機械や器具を製造する産業です。複写機やシュレッダーなどの事務用機械、レジや自動販売機などのサービス用・娯楽用機械、はかりやメーターなどの計量器・測定器、レントゲン装置やMRIなどの医療用機械、光学機器(カメラ、顕微鏡)、時計などがこの分類です。
⑳ 電子部品・デバイス・電子回路製造業
あらゆる電子機器の心臓部となる部品を製造する産業です。「産業のコメ」とも呼ばれる半導体素子や集積回路(IC)、スマートフォンやテレビの画面に使われる液晶パネル・有機ELパネル、抵抗器やコンデンサといった受動電子部品、そしてこれらの部品を実装するためのプリント電子回路基板などが含まれます。
㉑ 電気機械器具製造業
電気をエネルギー源として作動する機械器具を製造する産業です。発電機や変圧器、配電盤といった電力供給に関わる電気機械、家庭で使われる冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの電化製品、照明器具、そして乾電池や蓄電池といった電池もこの分類です。
㉒ 情報通信機械器具製造業
情報の伝達や処理を行うための機械器具を製造する産業です。固定電話機や交換機、ルータなどの有線通信機器、携帯電話(スマートフォン)や基地局などの無線通信機器、テレビ・ラジオ放送機器、そしてコンピュータ本体やサーバ、ハードディスクドライブなどの周辺装置が含まれます。
㉓ 輸送用機械器具製造業
人やモノを輸送するための機械器具およびその関連部品を製造する産業です。自動車本体、エンジンやブレーキなどの自動車部品、オートバイ、鉄道車両、船舶、航空機、さらには自転車まで、陸海空のあらゆる輸送機器がこの分類に含まれます。日本の製造業を代表する産業の一つです。
㉔ その他の製造業
上記の23分類のいずれにも当てはまらない、その他の製造業がここに分類されます。具体的には、貴金属製品や宝飾品、楽器(ピアノ、ギターなど)、玩具やゲーム、文房具(鉛筆、万年筆など)、スポーツ用品(ゴルフ用品、釣具など)、義肢や装具などが含まれます。
製造業のもう一つの分け方:3つの種類
日本標準産業分類が公的な統計や行政手続きで用いられる公式な分類であるのに対し、製造業の経済的な特徴やサプライチェーンにおける位置づけに着目した、もう一つの分け方が存在します。それが「基礎素材型産業」「加工組立型産業」「生活関連型産業」という3つの種類への分類です。この視点は、業界の構造や動向、課題をより深く理解する上で非常に役立ちます。
| 分類 | 主な特徴 | 該当する主な産業(日本標準産業分類) |
|---|---|---|
| 基礎素材型産業 | 大規模な設備で原材料を加工し、他の産業の「素材」を生産する。装置産業とも呼ばれ、市況変動の影響を受けやすい。 | 鉄鋼業、非鉄金属製造業、化学工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、窯業・土石製品製造業など |
| 加工組立型産業 | 基礎素材や部品を調達し、組み立て・加工して最終製品を製造する。高い技術力と複雑なサプライチェーンが特徴。 | 輸送用機械器具製造業、はん用・生産用・業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業など |
| 生活関連型産業 | 主に一般消費者の日常生活で使われる製品を製造する。需要が比較的安定しているが、消費者ニーズの多様化への対応が重要。 | 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、家具・装備品製造業など |
① 基礎素材型産業
基礎素材型産業は、天然資源などの原材料に大規模な加工を施し、他の産業が製品を作るための「素材」を供給する産業です。鉄鋼、化学、非鉄金属、紙パルプ、セメントなどがこれに該当します。
この産業群の最大の特徴は、「装置産業」であるという点です。製品を生産するために高炉や化学プラント、抄紙機といった巨大で高額な設備が必要不可欠であり、莫大な初期投資と継続的な設備維持コストが発生します。そのため、一度生産を開始すると、設備の稼働率を高く維持することが収益性を保つ上で極めて重要になります。
また、製品が汎用的な素材であることが多いため、他社製品との差別化が難しく、価格競争に陥りやすい傾向があります。原油価格や鉱物資源価格といった原材料市況や、為替レートの変動が業績に直接的な影響を与えるのも大きな特徴です。
経済における役割は非常に大きく、あらゆる「ものづくり」の川上に位置し、日本の産業全体の競争力を根底から支えています。しかし、国際的な価格競争の激化、エネルギーコストの上昇、そしてCO2排出削減をはじめとする厳しい環境規制への対応が、現代における大きな経営課題となっています。高機能・高付加価値な素材の開発や、省エネルギー技術、リサイクル技術の確立が今後の成長の鍵を握ります。
② 加工組立型産業
加工組立型産業は、基礎素材型産業が生産した素材や、国内外のさまざまなメーカーが製造した部品を調達し、それらを組み立て・加工することで最終的な製品を完成させる産業です。自動車、家電、産業機械、スマートフォンなどがその代表例です。
この産業群は、日本の製造業の国際競争力の中核を担ってきた分野と言えるでしょう。その強みは、精密な加工技術、高品質な製品を安定的に量産する生産管理能力、そして多数のサプライヤーを束ねる高度なサプライチェーン・マネジメントにあります。製品の性能や機能、デザイン、ブランドといった付加価値で勝負する分野であり、継続的な研究開発投資が不可欠です。
一方で、その強みは弱みと表裏一体でもあります。非常に多くの部品(自動車一台には約3万点)から構成される製品を作るため、サプライチェーンは極めて長く複雑です。そのため、特定の部品供給が滞ると生産ライン全体が停止してしまうリスクを常に抱えています。近年の半導体不足や、自然災害、地政学リスクによる物流の混乱は、その脆弱性を浮き彫りにしました。
また、EV(電気自動車)化やIoT化、AIの搭載といった急速な技術革新の波に乗り遅れると、一気に競争力を失う可能性があります。人手不足を補い、生産性を向上させるためのスマートファクトリー化や、グローバルな競争と協調(国際分業)にどう対応していくかが、今後の重要なテーマとなります。
③ 生活関連型産業
生活関連型産業は、主に一般消費者が日常生活の中で直接使用・消費する製品を製造する産業です。食料品、飲料、衣類(繊維製品)、家具、医薬品、化粧品などがこれにあたります。
この産業群の特徴は、景気の変動による影響が他の2つの産業に比べて比較的小さく、需要が安定的である点です。人々が生きていく上で必要不可欠な製品が多いため、不況下でも需要が大きく落ち込むことは少ない傾向にあります。
しかし、安定しているからといって安泰なわけではありません。むしろ、消費者の価値観やライフスタイルの変化に最も敏感に対応する必要がある産業です。例えば、食料品では健康志向や簡便化志向、環境配慮(サステナビリティ)といったトレンドが次々と生まれています。アパレル業界では、ファストファッションからサステナブルな素材への関心、個性を重視する傾向など、ニーズは多様化・細分化の一途をたどっています。
そのため、この分野で成功するには、的確なマーケティングによって消費者ニーズをいち早く捉え、魅力的なブランドを構築し、スピーディーに商品開発を行う能力が求められます。少子高齢化による国内市場の縮小という大きな構造変化に直面する中で、新たな価値を持つ商品をいかに生み出し、海外市場を含めた新しい販路を開拓していけるかが、今後の成長を左右します。
製造業が抱える主な課題
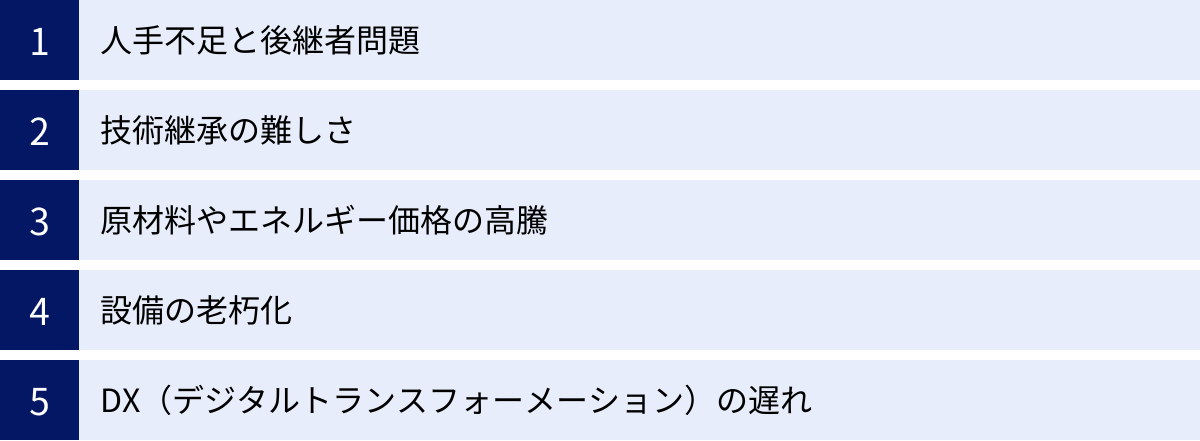
日本の経済を長きにわたり牽引してきた製造業ですが、現在、多くの深刻な課題に直面しています。これらの課題は個別に存在するのではなく、相互に複雑に絡み合っており、日本のものづくりの未来を左右する重要なテーマとなっています。
人手不足と後継者問題
最も深刻かつ喫緊の課題が、少子高齢化の進展に伴う労働力人口の減少、すなわち人手不足です。特に製造業は、全産業の中でも就業者の高齢化が顕著に進んでおり、若手人材の確保が非常に困難な状況にあります。
経済産業省・厚生労働省・文部科学省が発行する「2023年版ものづくり白書」によると、製造業における人手不足を感じている企業の割合は依然として高く、特に熟練技能人材の不足が深刻です。この背景には、いわゆる3K(きつい、汚い、危険)というかつてのイメージが未だに根強く残っていることや、他の産業と比較して賃金水準が見劣りするケースがあることなどが挙げられます。
さらに、この人手不足は、中小企業において「後継者問題」という形で顕在化しています。経営者自身が高齢化する一方で、親族や従業員の中に事業を引き継ぐ後継者が見つからない、あるいは適任者がいないという問題です。独自の高い技術力を持ちながらも、後継者不在を理由に廃業を選択せざるを得ない企業が増加しており、これは日本のものづくり全体の基盤を揺るがす深刻な事態と言えます。
技術継承の難しさ
人手不足と密接に関連するのが、熟練技能の継承問題です。日本の製造業の競争力は、長年の経験と勘によって培われた「匠の技」に支えられてきました。それは、設計図やマニュアルだけでは表現しきれない「暗黙知」であり、金属の微細な削り方、溶接の火花の色の見極め、機械のわずかな異音の聞き分けなど、言葉で伝えるのが非常に難しい領域です。
こうした技能は、従来、熟練技能者が若手と長期間にわたって共に働くOJT(On-the-Job Training)を通じて、時間をかけて伝承されてきました。しかし、団塊世代の大量退職が進み、かつ若手従業員が十分に確保できない現状では、この伝統的な継承モデルが機能不全に陥っています。
貴重な技能やノウハウが、継承されることなく失われてしまうことは、単に一企業の損失に留まりません。それはサプライチェーン全体、ひいては日本の製造業全体の競争力低下に直結する、大きなリスクなのです。
原材料やエネルギー価格の高騰
製造業は、その名の通り「もの」を作る産業であるため、原材料やエネルギーの価格動向に業績が大きく左右されます。近年、世界的なインフレーション、新興国の需要拡大、ウクライナ情勢をはじめとする地政学リスク、そして急激な円安の進行といった複数の要因が重なり、原材料費や燃料費、電気料金などが歴史的な水準で高騰しています。
このコスト上昇は、製造業の収益を直接的に圧迫します。特に、大量のエネルギーを消費する基礎素材型産業や、輸入原材料への依存度が高い産業にとって、その影響は甚大です。
さらに深刻なのは、コストが上昇しても、それを製品やサービスの価格に容易に転嫁できないという問題です。特に、大企業との取引が多い中小企業は、価格交渉において立場が弱くなりがちで、コストアップ分を自社で吸収せざるを得ないケースが少なくありません。この「価格転嫁の難しさ」が、多くの中小製造業の経営を苦しめる構造的な要因となっています。
設備の老朽化
日本の製造業の生産設備の多くは、高度経済成長期からバブル期にかけて集中的に導入されました。これらの設備が現在、軒並み更新時期を迎えていますが、多くの企業、特に中小企業では設備の老朽化が進んでいます。
老朽化した設備を使い続けることには、多くのデメリットが伴います。
- 生産性の低下: 最新の設備に比べて生産スピードが遅く、エネルギー効率も悪い。
- 故障リスクの増大: 突然の故障による生産ラインの停止は、納期遅延や機会損失に直結する。
- 品質の不安定化: 設備の精度が落ちることで、製品の品質にばらつきが生じやすくなる。
- 安全性の問題: 最新の安全基準を満たしていない場合、労働災害のリスクが高まる。
しかし、生産設備の更新には多額の設備投資が必要です。将来の需要が見通しにくい経済状況の中では、企業は投資に慎重にならざるを得ません。また、仮に設備を導入しても、それを使いこなせる人材がいないという問題もあり、設備の老朽化がなかなか解消されない一因となっています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の遅れ
これまで挙げてきた「人手不足」「技術継承」「生産性向上」といった課題を解決する切り札として期待されているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)です。IoTやAI、ロボットといったデジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセスそのものを変革することを指します。
しかし、日本の製造業、特に中小企業においては、このDXへの取り組みが欧米や中国の企業に比べて遅れていると指摘されています。その原因は複合的です。
- IT人材の不足: DXを主導できる専門知識を持った人材が社内にいない。
- 投資余力の欠如: DXツールの導入やシステム構築にかかるコストを捻出できない。
- 経営層の理解不足: 経営者がDXの重要性や効果を十分に理解しておらず、投資判断ができない。
- 文化的な障壁: 「これまでこのやり方でやってきたから」という現状維持バイアスや、失敗を恐れる文化が変革を阻んでいる。
このDXの遅れは、生産性の停滞を招き、結果として国際競争力のさらなる低下に繋がるという悪循環を生み出す危険性をはらんでいます。
製造業の課題解決と今後の展望
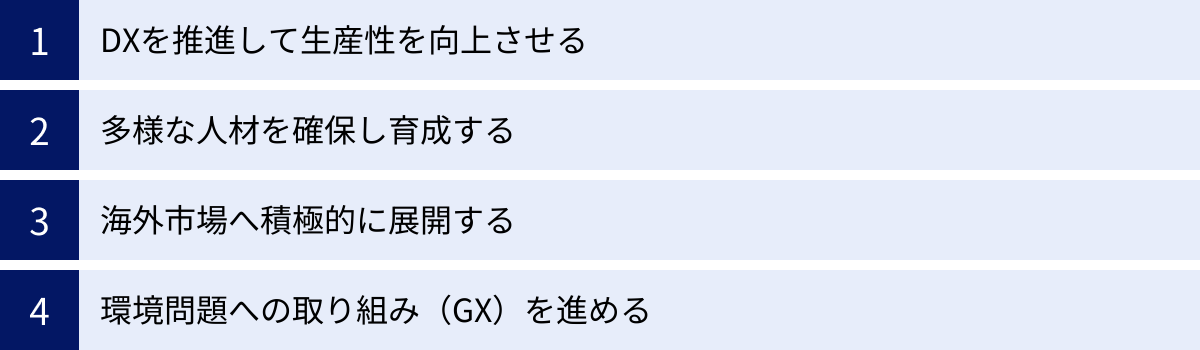
前章で述べたような数多くの厳しい課題に直面している製造業ですが、悲観的な未来ばかりではありません。これらの課題は、裏を返せば変革と成長への大きな機会でもあります。ここでは、日本の製造業が課題を乗り越え、持続的に発展していくための今後の展望と、その具体的な方向性について解説します。
DXを推進して生産性を向上させる
製造業が抱える構造的な課題を解決する上で、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は避けて通れない最重要テーマです。デジタル技術を活用することで、これまで不可能だったレベルでの生産性向上が期待できます。
その究極的な目標の一つが「スマートファクトリー」の実現です。工場内のあらゆる機器や設備をIoTセンサーで繋ぎ、稼働状況や品質に関するデータをリアルタイムで収集・蓄積します。そして、その膨大なデータをAIが分析することで、以下のようなことが可能になります。
- 生産プロセスの最適化: ボトルネックとなっている工程を特定し、生産計画や人員配置を動的に最適化する。
- 予知保全: 設備の劣化や異常の兆候をAIが事前に検知し、故障によるライン停止を未然に防ぐ。
- 品質管理の自動化: 画像認識技術などを用いて、製品の検査を自動化し、品質の安定と向上を図る。
- 技術継承の支援: 熟練技能者の動きや判断をデータ化・可視化し、若手への教育や技能伝承に活用する。
もちろん、いきなり大規模なスマートファクトリーを目指す必要はありません。まずは生産管理システムを導入して製造工程を「見える化」する、単純作業を産業用ロボットで自動化するなど、自社の課題に合わせてスモールスタートでDXに着手することが重要です。DXは単なるツール導入ではなく、データに基づいた合理的な意思決定を行う文化を根付かせる経営改革であると認識することが成功の鍵となります。
多様な人材を確保し育成する
人手不足が恒常化する中で、もはや従来の採用手法や人材観では立ち行かなくなっています。多様なバックグラウンドを持つ人材が、その能力を最大限に発揮できる環境を整備することが不可欠です。
具体的には、これまで製造現場の主役とは見なされにくかった女性や高齢者、外国人材が活躍できる職場づくりが急務です。例えば、重量物の運搬を補助するパワーアシストスーツを導入したり、多言語対応のマニュアルを用意したりするなど、ハード・ソフト両面での環境整備が求められます。
同時に、「働きがい」のある職場を実現するための取り組みも重要です。3Kイメージを払拭するクリーンで安全な労働環境の整備はもちろんのこと、フレックスタイム制や時短勤務といった柔軟な働き方の導入、そして能力や成果が公正に評価され、キャリアアップに繋がる人事制度の構築が、優秀な人材を惹きつけ、定着させる上で欠かせません。
さらに、既存の従業員に対する「リスキリング(学び直し)」への投資も極めて重要です。DXが進展する中で、従業員にはデジタルツールを使いこなす能力や、データを読み解く能力が新たに求められます。企業が主体となって教育・研修プログラムを提供し、従業員のスキルアップを支援する姿勢が、企業全体の競争力を底上げします。人材は消費すべきコストではなく、未来の価値を生み出すための最も重要な資本であるという視点への転換が求められています。
海外市場へ積極的に展開する
少子高齢化により国内市場の長期的な縮小が避けられない中、製造業が持続的な成長を遂げるためには、成長著しい海外市場へ積極的に活路を見出すことが不可欠です。
もちろん、やみくもに海外進出すれば成功するわけではありません。現地の文化や規制、消費者ニーズを深く理解し、それに合わせた製品開発やマーケティング戦略(ローカライゼーション)が重要になります。
近年では、インターネットの普及により、中小企業でも越境EC(電子商取引)を活用して、比較的低リスクで海外の消費者へ直接アプローチすることが可能になりました。また、JETRO(日本貿易振興機構)など、中小企業の海外展開を支援する公的機関のサポートを最大限に活用することも有効な手段です。
グローバルなサプライチェーンの再編が進む中、海外に生産拠点を設ける、あるいは現地の有力企業とパートナーシップを結ぶといった、より踏み込んだ戦略も視野に入れる必要があります。為替変動やカントリーリスクといった特有のリスク管理は必須ですが、それを乗り越えた先には、国内市場だけでは得られない大きな成長の果実があります。
環境問題への取り組み(GX)を進める
脱炭素社会の実現は、もはや世界的な潮流であり、製造業もその例外ではありません。GX(グリーン・トランスフォーメーション)、すなわち化石燃料中心の産業・社会構造からクリーンエネルギー中心へと転換していく取り組みは、今や企業の存続を左右する重要な経営課題となっています。
製造業におけるGXの具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 生産設備をエネルギー効率の高い最新のものに更新する。
- 工場の屋根などに太陽光発電システムを設置し、再生可能エネルギーの自家消費を進める。
- 製品の設計段階から、省資源・長寿命化・リサイクルしやすさを考慮に入れる(サーキュラーエコノミー)。
- 原材料調達から生産、使用、廃棄までのライフサイクル全体でのCO2排出量を算定・開示し、削減努力を行う。
こうした環境問題への取り組みは、規制対応のためのコストという消極的な側面だけではありません。省エネは光熱費の削減に直結し、コスト競争力を高めます。また、環境に配慮した企業姿勢は、ESG投資を呼び込み、企業のブランドイメージを向上させ、環境意識の高い消費者や取引先から選ばれる理由にもなります。GXは、コストではなく、新たな競争優位性とビジネスチャンスを生み出すための未来への投資なのです。
製造業のDXを推進する代表的なITツール5選
製造業がDXを推進し、生産性向上や課題解決を実現するためには、適切なITツールの活用が不可欠です。ここでは、製造業の現場や経営で広く利用されている代表的な5つのITツールについて、その役割と効果を解説します。
| ツール名 | 正式名称/英語表記 | 主な目的 | 解決できる代表的な課題 |
|---|---|---|---|
| 生産管理システム | Production Control System | 生産のQCD(品質・コスト・納期)の最適化 | 生産計画の属人化、進捗の不透明化、過剰在庫・欠品 |
| ERP | Enterprise Resource Planning | 企業全体の経営資源(人・モノ・金・情報)の一元管理 | 部門間の情報分断、経営状況のリアルタイム把握の遅れ |
| SCM | Supply Chain Management | 原材料調達から消費者への供給までの流れを最適化 | サプライチェーンの脆弱性、需要予測のズレ、リードタイムの長期化 |
| CAD/CAM | Computer-Aided Design / Manufacturing | 設計のデジタル化と製造データへのシームレスな連携 | 設計ミスの削減、試作期間・コストの増大、加工の非効率化 |
| CRM/SFA | Customer Relationship Management / Sales Force Automation | 顧客情報の一元管理と営業活動の可視化・効率化 | 顧客情報の属人化、営業ノウハウのブラックボックス化 |
① 生産管理システム
生産管理システムは、製造現場における「いつ、何を、どれだけ作るか」という生産活動全体を管理し、最適化するためのシステムです。その目的は、製造業における最も重要な管理指標であるQCD(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)のすべてを向上させることにあります。
主な機能として、需要予測や受注情報に基づいた「生産計画」、計画通りに生産が進んでいるかを管理する「工程管理」、原材料や仕掛品、製品の数量を管理する「在庫管理」、製品の品質データを記録・分析する「品質管理」、そして製品一つあたりにかかる費用を算出する「原価管理」などがあります。
このシステムを導入する最大のメリットは、これまで熟練者の頭の中にあった情報や、紙の帳票でバラバラに管理されていた情報を一元化し、「見える化」できる点にあります。リアルタイムで生産の進捗状況を把握できるため、問題が発生しても迅速に対応でき、納期遅延を防ぎます。また、正確な在庫管理によって過剰在庫や欠品を削減し、キャッシュフローを改善します。製造原価を正確に把握することで、的確な価格設定やコスト削減の取り組みに繋げることが可能です。
② ERP(統合基幹業務システム)
ERPは、Enterprise Resource Planningの略で、日本語では「企業資源計画」と訳されます。その名の通り、生産管理だけでなく、販売、購買、在庫、会計、人事といった企業のあらゆる基幹業務を統合し、企業全体の経営資源(人・モノ・金・情報)を単一のデータベースで一元管理するシステムです。
生産管理システムが主に「製造現場」を対象とするのに対し、ERPは「企業経営全体」を俯瞰する視点を持っています。多くのERPパッケージには、生産管理機能が標準で含まれています。
ERP導入の最大のメリットは、部門間にあった情報の壁を取り払い、全社のデータをリアルタイムで連携・可視化できることです。例えば、営業部門が受注情報を入力すると、その情報が即座に生産部門の生産計画や購買部門の資材発注、経理部門の売上見込みに自動で反映されます。これにより、データの二重入力といった無駄な業務が削減されるだけでなく、経営層は常に最新かつ正確な全社の状況を把握し、迅速で的確な経営判断を下せるようになります。まさに企業の神経中枢ともいえるシステムです。
③ SCM(サプライチェーン・マネジメント)
SCMは、Supply Chain Managementの略で、原材料を調達するサプライヤーから、自社での製造、そして物流を経て最終消費者に製品が届くまでの一連の流れ(サプライチェーン)全体を、最適化するための経営手法、およびそれを支援するシステムを指します。
自社内の効率化だけを目指すのではなく、サプライヤーや物流業者、販売店といった社外のパートナー企業とも情報を共有し、連携することで、チェーン全体の無駄をなくし、リードタイムの短縮や在庫の削減を目指します。
SCMシステムを導入することで、サプライチェーン全体の「見える化」が実現します。例えば、最終製品の販売実績データをサプライヤーと共有することで、サプライヤーはより正確な需要予測に基づいて部品を生産でき、欠品や過剰在庫のリスクを低減できます。また、災害や地政学リスクなどで特定のサプライヤーからの供給が滞った場合でも、影響範囲を迅速に特定し、代替調達先の検討など、素早い対応が可能になります。サプライチェーンの強靭化(レジリエンス)が求められる現代において、その重要性はますます高まっています。
④ CAD/CAM
CADとCAMは、主に設計・開発部門や製造技術部門で使われるツールで、製造業の根幹を支える技術です。
- CAD(Computer-Aided Design): コンピュータ支援設計と訳され、コンピュータ上で製品の図面を作成したり、3Dモデルを構築したりするシステムです。手書きの製図に比べて、設計の効率と精度が飛躍的に向上します。作成した3Dモデルを使えば、実際に試作品を作る前に、コンピュータ上で強度解析や動作シミュレーションを行うこと(CAE)も可能です。
- CAM(Computer-Aided Manufacturing): コンピュータ支援製造と訳され、CADで作成された設計データ(3Dモデルなど)を基に、工作機械(マシニングセンタなど)を動かすための加工プログラム(NCデータ)を自動で生成するシステムです。
CADとCAMを連携させることで、設計から製造までのプロセスがシームレスに繋がり、デジタルデータで一気通貫に管理できます。これにより、試作品の作製回数や手戻りが大幅に削減され、開発期間の短縮とコストダウンに絶大な効果を発揮します。
⑤ CRM/SFA(顧客管理/営業支援システム)
CRMとSFAは、主に営業部門やマーケティング部門で活用されるツールですが、顧客との関係性が重要となる現代の製造業、特にBtoB(企業間取引)においてもその導入が進んでいます。
- CRM(Customer Relationship Management): 顧客関係管理と訳され、顧客の基本情報、過去の取引履歴、問い合わせ内容、商談の進捗状況などを一元管理し、顧客との良好で長期的な関係を構築するためのシステムです。
- SFA(Sales Force Automation): 営業支援システムと訳され、営業担当者の日々の活動(訪問、電話など)の記録、案件管理、見積作成、予実管理などを支援し、営業プロセス全体の効率化と可視化を図るシステムです。
これらのツールを導入することで、これまで各営業担当者の頭の中や手帳の中にしかなかった顧客情報や商談ノウハウが、組織全体の資産として共有されます。これにより、担当者が異動や退職をしてもスムーズな引き継ぎが可能になり、営業活動の属人化を防ぐことができます。また、蓄積されたデータを分析することで、優良顧客の特定や、新たな商談機会(アップセル・クロスセル)の発見にも繋がります。
まとめ
本記事では、日本の基幹産業である製造業について、その「分類」を軸に多角的な視点から深掘りしてきました。
まず、公的な基準である「日本標準産業分類」では、製造業が24の中分類に分けられていることを一覧で確認しました。食料品や繊維といった身近なものから、化学、鉄鋼、機械、電子部品に至るまで、その多様性と裾野の広さを理解いただけたかと思います。
さらに、経済的な特徴から「基礎素材型」「加工組立型」「生活関連型」という3つの種類に分ける見方を紹介しました。この分類は、各産業がサプライチェーンの中でどのような役割を担い、どのような課題を抱えやすいのかを理解する上で非常に有効です。
そして、現代の日本の製造業が直面する「人手不足と後継者問題」「技術継承の難しさ」「原材料・エネルギー価格の高騰」「設備の老朽化」「DXの遅れ」といった深刻な課題を明らかにしました。
しかし、これらの課題は乗り越えられない壁ではありません。今後の展望として、DXの推進による生産性向上、多様な人材の確保と育成、積極的な海外市場への展開、そしてGX(グリーン・トランスフォーメーション)への取り組みが、持続的な成長を実現するための鍵となります。
その変革を具体的に後押しするのが、生産管理システムやERP、SCMといったITツールです。これらを戦略的に活用することで、業務を効率化し、データをに基づいた的確な意思決定を行い、新たな価値を創出することが可能になります。
多くの困難を抱えながらも、日本の製造業は今、大きな変革の時代を迎えています。この記事が、製造業の全体像を掴み、その未来を考えるための一助となれば幸いです。