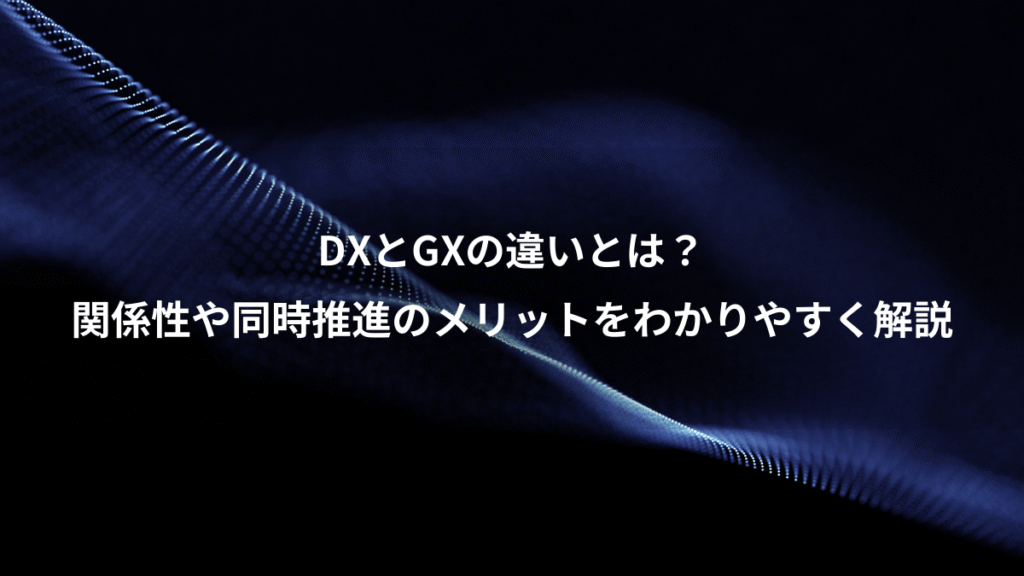現代の企業経営において、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「GX(グリーントランスフォーメーション)」という二つの変革が、持続的な成長を遂げるための重要な鍵として注目されています。これらは、それぞれデジタル技術の活用と環境問題への対応を軸とする変革ですが、単に独立した概念ではありません。
DXとGXは密接に連携し、互いに影響を与え合うことで、企業の競争力や社会全体の持続可能性を大きく向上させるポテンシャルを秘めています。しかし、「DXとGXは何が違うのか?」「なぜ同時に推進する必要があるのか?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。
この記事では、DXとGXそれぞれの基本的な概念から、両者の明確な違い、そして密接な関係性について詳しく解説します。さらに、DXとGXを同時に推進することで得られる具体的なメリット、推進するためのステップ、直面する課題、そしてそれらを支援するサービスやツールまで、網羅的に掘り下げていきます。
この記事を読み終える頃には、DXとGXの本質を理解し、自社の経営戦略にどう組み込んでいくべきかの道筋が見えるようになるでしょう。
目次
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
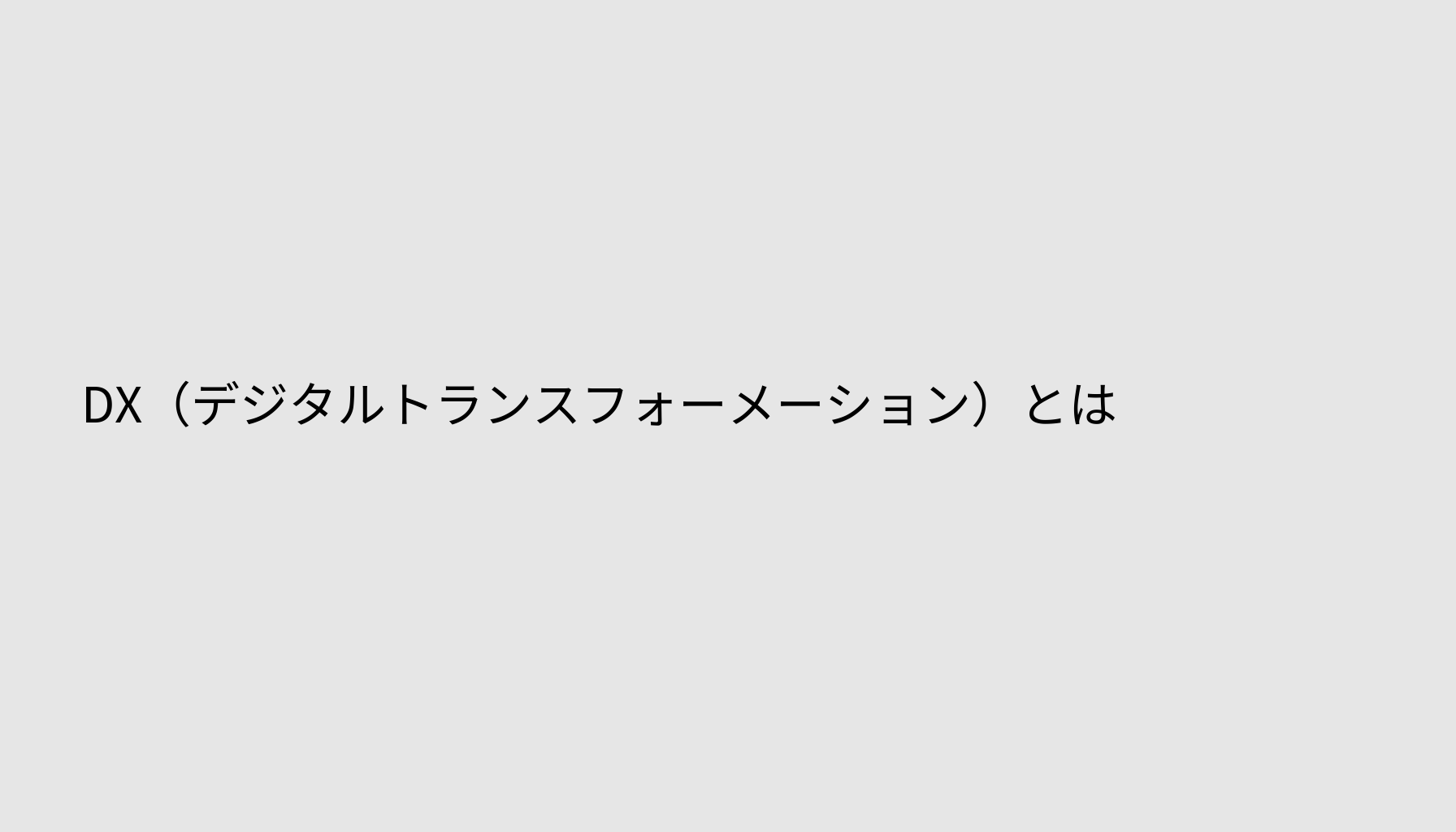
DX(デジタルトランスフォーメーション)は、現代のビジネス環境において最も重要な経営課題の一つとして広く認識されています。単なる「デジタル化」や「IT化」とは一線を画す、より広範で抜本的な変革を指す概念です。その本質を理解するために、まずは定義から見ていきましょう。
経済産業省が公開している「DX推進ガイドライン」では、DXは次のように定義されています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」)
この定義の要点は、「デジタル技術の活用」が目的ではなく、「競争上の優位性を確立する」ことが最終的なゴールであるという点です。つまり、最新のITツールを導入するだけではDXとは言えず、その技術を使ってビジネスのあり方そのものを根本から変え、新たな価値を創出し続けることが求められます。
DXが注目される背景には、いくつかの深刻な社会・経済的要因があります。まず、市場のグローバル化やテクノロジーの急速な進化により、消費者のニーズはかつてないほど多様化・複雑化しています。顧客は単に製品やサービスを所有するだけでなく、それを通じて得られる体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)を重視するようになりました。このような変化に対応するためには、データに基づいて顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、パーソナライズされた価値を提供する必要があります。
また、少子高齢化に伴う労働人口の減少も深刻な課題です。従来の労働集約的なビジネスモデルでは、生産性の維持・向上が困難になっています。デジタル技術を活用して業務プロセスを自動化・効率化し、従業員がより付加価値の高い創造的な業務に集中できる環境を整えることが不可欠です。
さらに、いわゆる「2025年の崖」もDX推進を急がせる大きな要因です。これは、多くの企業で利用されている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、複雑化・老朽化・ブラックボックス化し、2025年以降に大きな経済的損失をもたらす可能性があるという経済産業省の指摘です。レガシーシステムを刷新し、データ活用を前提とした柔軟で拡張性の高いシステムアーキテクチャへ移行することは、DXの重要な第一歩となります。
DXの取り組みは、しばしば以下の3つのフェーズで語られます。
- デジタイゼーション(Digitization):
これはDXの最も初期の段階であり、アナログな物理情報をデジタル形式に変換するプロセスを指します。具体的には、紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議をオンライン化する、手作業で行っていたデータ入力をExcelやスプレッドシートに置き換える、といった取り組みが該当します。目的は、特定の業務の効率化やコスト削減です。 - デジタライゼーション(Digitalization):
デジタイゼーションで変換されたデジタルデータを活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で変革する段階です。例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型的な入力作業を完全に自動化する、クラウド型の会計システムを導入して経理プロセス全体を効率化する、SFA/CRMツールで営業活動を管理・可視化する、といった取り組みがこれにあたります。目的は、業務プロセス全体の最適化と生産性向上です。 - デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation):
デジタイゼーションとデジタライゼーションを基盤として、ビジネスモデルや組織文化、顧客との関係性といった、企業活動の根幹そのものを変革する最終段階です。例えば、製造業が製品にセンサー(IoT)を搭載して稼働データを収集し、そのデータを分析して故障予知や遠隔メンテナンスといった新たなサービス(リカーリングモデル)を提供する、といったケースが典型例です。これは単なる「モノ売り」から「コト売り」へのビジネスモデル変革です。DXの真の目的は、このレベルの変革を通じて、持続的な競争優位性を確立することにあります。
DXを推進することで、企業は様々なメリットを享受できます。生産性の向上やコスト削減はもちろんのこと、データに基づいた迅速な意思決定、顧客体験の向上によるロイヤルティ強化、そして全く新しい収益源となるビジネスモデルの創出などが期待されます。
しかし、その道のりは平坦ではありません。「DX人材の不足」「レガシーシステムの存在」「サイロ化した組織文化」「経営層の理解不足」など、多くの企業が共通の課題に直面しています。これらの課題を乗り越え、全社一丸となって変革に取り組む強い意志とリーダーシップが、DX成功の鍵を握っていると言えるでしょう。
GX(グリーントランスフォーメーション)とは
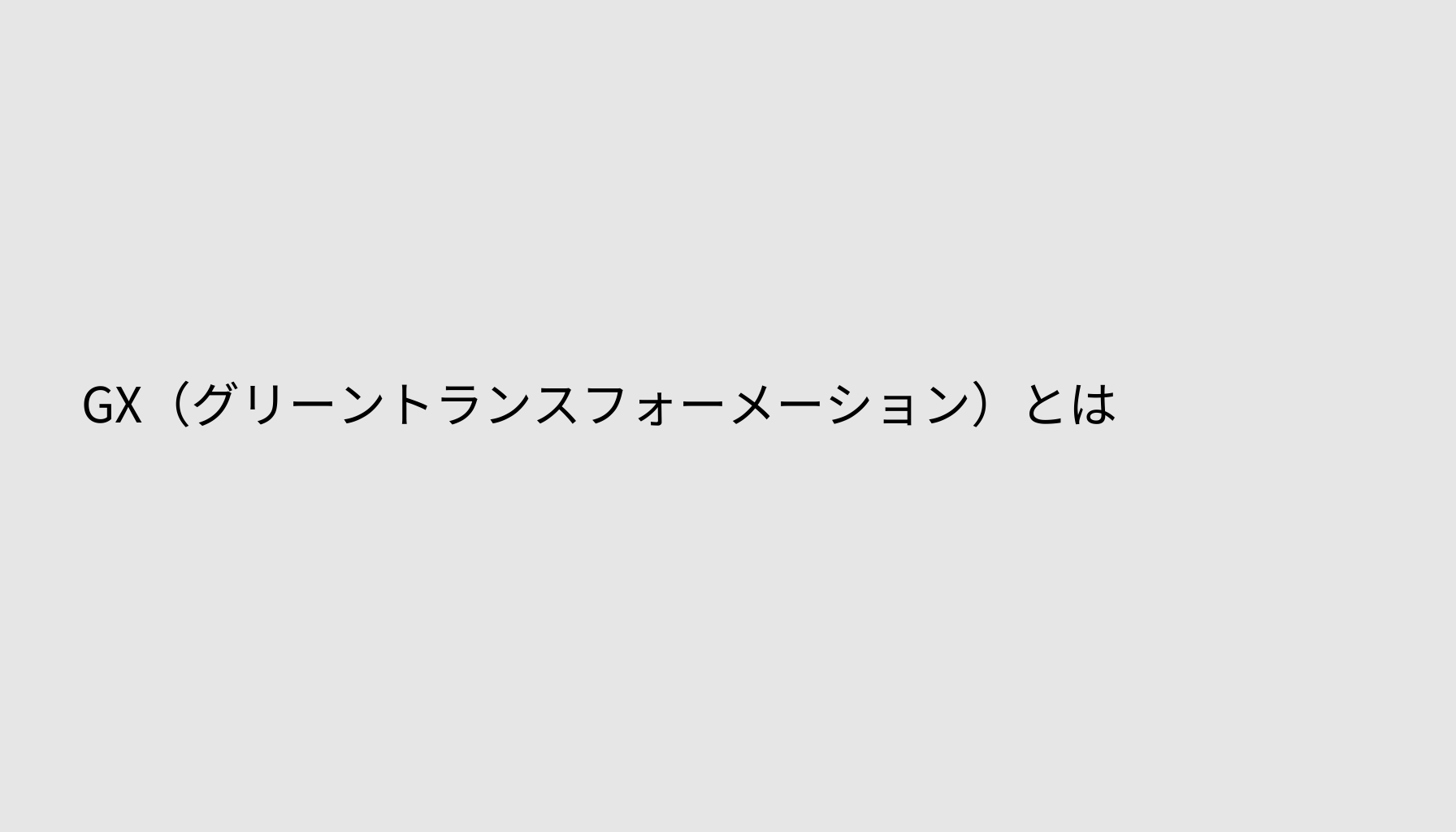
GX(グリーントランスフォーメーション)は、気候変動問題への対応と経済成長を両立させることを目指す、社会経済システム全体の変革を指す言葉です。DXが主にデジタル技術を軸とした企業レベルの変革であるのに対し、GXはエネルギーや産業構造といった、よりマクロな視点での変革を含みます。
経済産業省は、GXを「2050年カーボンニュートラルや2030年の国としての温室効果ガス排出削減目標の達成に向けた取組を、わが国の経済成長の機会へとつなげていくための、排出削減と産業競争力向上の両立を目指す取組」と説明しています。(参照:経済産業省「GX実現に向けた基本方針」)
ここでの重要なポイントは、環境対策を単なるコストや制約として捉えるのではなく、新たな成長の機会として積極的に活用しようという発想の転換です。化石燃料に依存した従来の産業・社会構造を、再生可能エネルギーや省エネルギー技術を中心としたクリーンなシステムへと移行させることで、国際的な競争力を高め、持続可能な社会を実現することがGXの究極的な目標です。
GXが世界的な潮流となった背景には、地球温暖化の進行に対する深刻な危機感があります。2015年に採択された「パリ協定」では、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力を追求することが国際的な目標として掲げられました。この目標達成のため、世界各国が温室効果ガスの排出削減目標を掲げ、具体的な政策を進めています。日本政府も2020年に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、2030年度までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減するという野心的な目標を掲げました。
こうした国際的な枠組みや政府の目標設定は、企業活動に直接的な影響を与えます。炭素税や排出量取引制度といったカーボンプライシングの導入が世界的に進んでおり、CO2排出量が多い企業は経済的な負担が増大するリスクに直面しています。
また、投資の世界でも大きな変化が起きています。企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への配慮を重視する「ESG投資」が急速に拡大しています。投資家は、気候変動リスクに対応できていない企業や、環境への負荷が高い企業への投資を避ける一方で、GXに積極的に取り組む企業を高く評価し、資金を供給するようになっています。つまり、GXへの取り組みは、企業の資金調達能力や企業価値そのものを左右する重要な要素となっているのです。
GXの具体的な取り組みは多岐にわたりますが、主に以下のような領域が挙げられます。
- エネルギー供給の転換:
GXの中核をなすのが、エネルギー源の脱炭素化です。太陽光、風力、地熱、バイオマスといった再生可能エネルギーの導入を最大限拡大することが最優先課題です。また、次世代エネルギーとして期待される水素やアンモニアの製造・利用技術の開発も重要なテーマです。 - 徹底した省エネルギー:
エネルギー需要そのものを削減することも不可欠です。高性能な断熱材やLED照明、高効率な空調・生産設備への更新、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入などにより、産業部門、業務部門、家庭部門のあらゆる場面でエネルギー効率を高める取り組みが進められています。 - 産業構造の転換:
鉄鋼、化学、セメントといったエネルギー多消費型産業では、製造プロセスの抜本的な見直しが求められます。例えば、化石燃料の代わりに水素を使って鉄を製造する「水素還元製鉄」や、CO2を分離・回収して再利用・貯留する「CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)」といった革新的な技術の開発と社会実装が期待されています。 - サーキュラーエコノミー(循環経済)への移行:
従来の一方通行型(採掘→生産→消費→廃棄)の経済モデルから、資源を循環させ続けるモデルへの転換です。製品の長寿命化設計、修理や再利用の促進、使用済み製品からの資源回収(リサイクル)などを通じて、天然資源の消費と廃棄物の発生を最小限に抑えます。
これらの取り組みを推進することで、企業はエネルギーコストの削減や新たな規制への対応といったメリットを得られます。さらに、環境に配慮した「グリーン製品」やサービスを開発することで、環境意識の高い消費者や取引先から選ばれ、新たなビジネスチャンスを創出できます。また、GXに先進的に取り組む企業としてブランドイメージが向上し、優秀な人材の獲得にも繋がります。
しかし、GXの実現には、革新的な技術開発と、それを社会に実装するための莫大な投資が必要です。また、サプライチェーン全体での協力や、社会全体の意識改革も不可欠であり、一企業だけの努力では達成できません。だからこそ、国や業界が一体となった長期的な視点での戦略が求められているのです。
DXとGXの違いを3つの観点から比較
ここまでDXとGXそれぞれの概念について解説してきましたが、両者は似ているようでいて、その目的や対象範囲には明確な違いがあります。この違いを正しく理解することが、両者を効果的に推進するための第一歩です。ここでは、「目的」「対象範囲」「主な取り組み」という3つの観点から、DXとGXを比較し、その本質的な差異を明らかにします。
両者の違いをより分かりやすくするために、以下の表にまとめました。
| 比較観点 | DX(デジタルトランスフォーメーション) | GX(グリーントランスフォーメーション) |
|---|---|---|
| 目的 | デジタル技術を活用し、ビジネスモデルや組織を変革して競争上の優位性を確立する。 | クリーンエネルギー中心の経済・社会システムへ転換し、環境保護と経済成長を両立させる。 |
| 対象範囲 | 主に個別の企業や組織における業務プロセス、ビジネスモデル、組織文化、顧客接点など。 | 企業活動に留まらず、産業構造、エネルギーシステム、社会インフラ全体。よりマクロな視点。 |
| 主な取り組み | AI、IoT、クラウド、ビッグデータ等のデジタル技術の活用。業務自動化、データ駆動型経営、新規サービス開発など。 | 再生可能エネルギー、省エネ、CCUS、水素活用、サーキュラーエコノミー等の環境・エネルギー技術の活用。 |
この表を基に、各項目をさらに詳しく掘り下げていきましょう。
① 目的
まず、両者の最も根源的な違いは「目的」にあります。
DXの究極的な目的は、「競争上の優位性の確立」です。企業がデジタル技術を駆使して業務効率を上げ、顧客体験を向上させ、革新的なビジネスモデルを生み出すのは、すべて市場における競争で他社をリードし、持続的に利益を上げて成長し続けるためです。その根底にあるのは、主に経済合理性や市場原理に基づいた動機です。もちろん、顧客や社会への貢献という側面もありますが、第一義的には自社の成長と存続が目的となります。
一方、GXの究極的な目的は、「環境保護と経済成長の両立」、そしてその先にある「持続可能な社会の実現」です。地球温暖化という全人類的な課題に対応するため、化石燃料への依存から脱却し、CO2排出量を実質ゼロにする(カーボンニュートラル)ことが世界共通のゴールとなっています。GXは、この環境制約を乗り越えつつ、それを新たな産業競争力の源泉に変え、経済成長を実現しようとする壮大な取り組みです。その動機は、企業の経済合理性だけでなく、地球環境の保全や次世代への責任といった、より普遍的で社会的な要請に基づいています。
このように、DXが主に「企業の競争力」というミクロな視点に立脚しているのに対し、GXは「地球環境と社会の持続可能性」というマクロな視点に立脚している点が、根本的な違いと言えます。
② 対象範囲
次に、「対象範囲」の違いを見てみましょう。目的の違いは、自ずと変革の対象となる範囲の違いにも繋がります。
DXの対象範囲は、主に個別の企業や組織の内部、およびその顧客やパートナーとの関係性にあります。具体的には、社内の業務プロセス、組織の構造や文化、従業員の働き方、製品・サービスの開発プロセス、マーケティングや営業活動、顧客とのコミュニケーションチャネルなどです。もちろん、業界全体のプラットフォームを構築するような大きな動きもありますが、変革の起点となるのはあくまで個々の企業や組織です。
対して、GXの対象範囲は、一企業の枠をはるかに超え、産業構造、エネルギー供給システム、交通インフラ、さらには国民のライフスタイルといった社会経済システム全体に及びます。例えば、電力システムを再生可能エネルギー中心に切り替えるには、発電事業者だけでなく、送配電網を管理する事業者、需要を調整する需要家、そして政策を司る政府の連携が不可欠です。また、自動車をEV(電気自動車)に転換するには、自動車メーカーだけでなく、充電インフラの整備、バッテリー技術の開発、リサイクルシステムの構築など、社会全体での取り組みが必要となります。このように、GXは本質的に、国や業界、サプライチェーン全体を巻き込んだマクロレベルの変革なのです。
③ 主な取り組み
最後に、「主な取り組み」における違いです。これは、変革を実現するための「手段」の違いと言い換えることもできます。
DXを推進するための中心的な手段は、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析といった最先端のデジタル技術です。これらの技術を駆使して、業務の自動化・効率化を図り、膨大なデータから新たな知見を抽出し、データに基づいた意思決定(データドリブン経営)を実現します。また、これらの技術を組み合わせて、これまでになかった新しいサービスやビジネスモデルを創出することも、DXの重要な取り組みです。
一方、GXを推進するための中心的な手段は、再生可能エネルギー技術(太陽光、風力など)、省エネルギー技術、CCUS(CO2回収・利用・貯留)技術、水素・アンモニアの製造・利用技術、サーキュラーエコノミーを実現するためのリサイクル技術など、環境・エネルギー関連の技術が主役となります。これらの技術開発と社会実装を通じて、エネルギー消費とCO2排出量を削減していくことが、GXの具体的な活動の中心です。
ただし、ここで重要なのは、両者の取り組みは排他的なものではないという点です。むしろ、GXの取り組みを効率的かつ効果的に進める上で、DXのデジタル技術が極めて重要な役割を果たします。この点については、次の章で詳しく解説します。
以上のように、DXとGXは目的、対象範囲、主な取り組みにおいて明確な違いがあります。しかし、これらの違いを理解した上で両者を見渡すと、それらが対立するものではなく、むしろ強く結びついていることが見えてきます。
DXとGXの密接な関係性
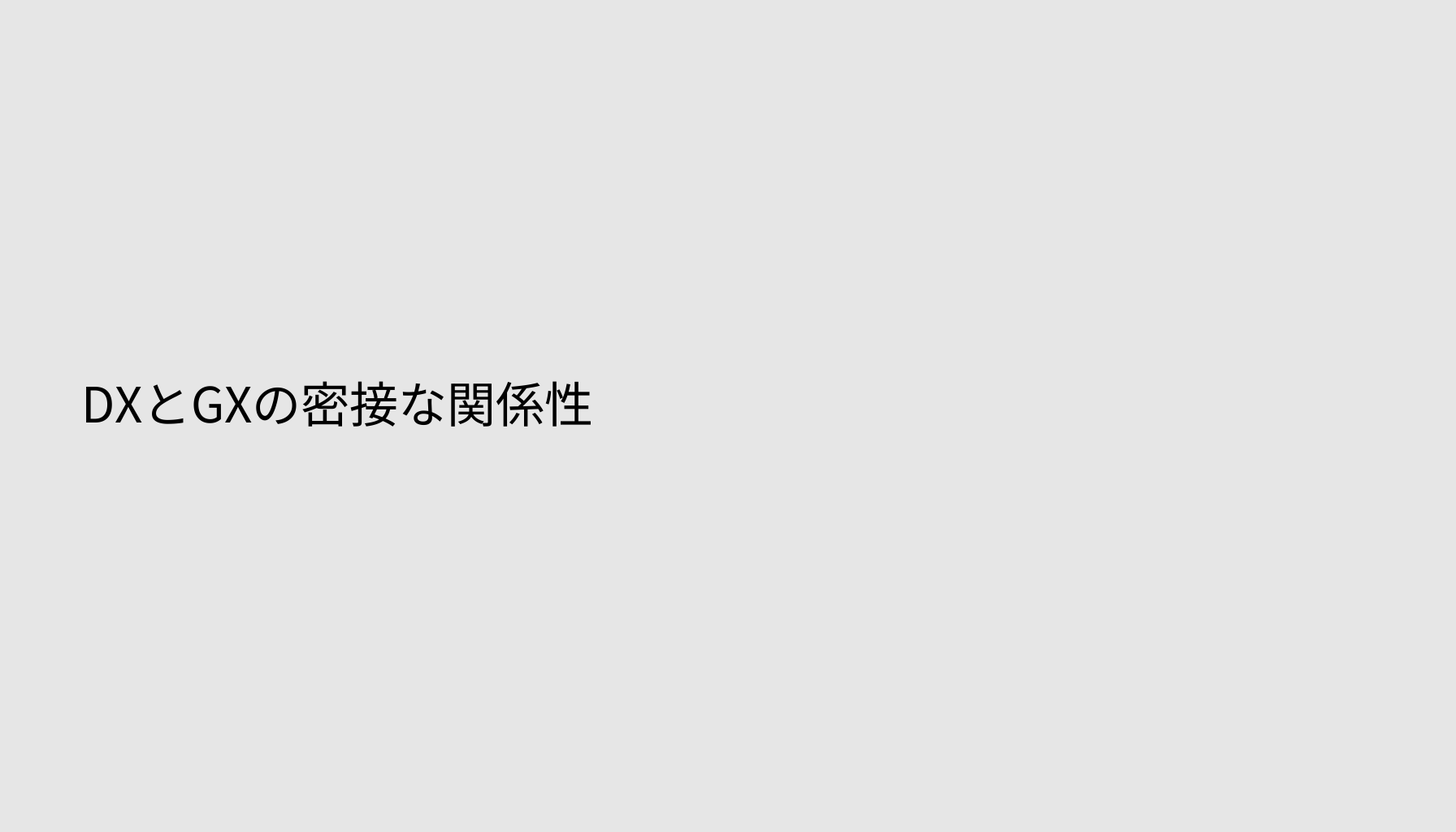
DXとGXは、それぞれ異なる目的とアプローチを持つ変革ですが、決して無関係ではありません。むしろ、現代の企業経営においては、この二つの変革は車の両輪のように、互いを補完し、加速させ合う密接な関係にあります。端的に言えば、「DXなくしてGXの実現は困難であり、GXはDXに新たな目的と価値創造の機会を与える」と言えるでしょう。
この密接な関係性を理解することは、両方の変革を成功に導く上で極めて重要です。ここでは、具体的にどのようにDXがGXを支え、GXがDXを促進するのかを掘り下げていきます。
まず、GXの実現にはDXが不可欠な「手段」となる側面を見ていきましょう。GXが目指す脱炭素社会の実現には、エネルギーの利用効率を極限まで高め、複雑化するエネルギーシステムを賢く制御する必要があります。これらは、まさにDXが得意とする領域です。
一つの具体例は、エネルギーマネジメントの高度化です。工場やビルにIoTセンサーを多数設置し、電力、ガス、水などのエネルギー使用状況をリアルタイムかつ詳細にデータとして収集します。そして、クラウド上に蓄積されたビッグデータをAIが分析することで、エネルギーの無駄が発生している箇所や時間帯を正確に特定し、最適な運用方法を提案できます。これにより、従業員の経験や勘に頼るのではなく、データに基づいた科学的な省エネ活動が可能となり、CO2排出量とエネルギーコストの両方を大幅に削減できます。これは、GXという目標をDXという手段で達成する典型的な例です。
再生可能エネルギーの安定供給においても、DXの役割は決定的です。太陽光や風力といった再生可能エネルギーは、天候によって発電量が大きく変動するという課題を抱えています。この不安定さを克服し、電力システムの安定性を保つためには、高度な予測と制御が不可欠です。AIを用いて気象データや過去の発電実績、電力需要のパターンを分析し、数時間後、数日後の発電量を高い精度で予測します。この予測に基づき、蓄電池の充放電を最適に制御したり、電力需要の大きい工場などに電力使用の抑制(デマンドレスポンス)を要請したりすることで、電力の需給バランスを保ちます。このような次世代の電力網、いわゆる「スマートグリッド」の構築は、DX技術なしには成り立ちません。
さらに、サプライチェーン全体の脱炭素化というGXの重要な課題においても、DXは強力な武器となります。製品が原材料の調達から製造、輸送、消費、廃棄に至るまでの全ライフサイクルで、どれだけのCO2を排出しているか(カーボンフットプリント)を正確に算定・追跡することは非常に困難です。ここに、ブロックチェーンなどの改ざん困難なデジタル技術を活用することで、サプライチェーン上の各企業が排出量データを記録・共有し、製品ごとのカーボンフットプリントの透明性と信頼性を高めることができます。これにより、企業は自社のサプライチェーンにおける排出削減のボトルネックを特定し、効果的な対策を講じることが可能になります。
一方で、GXはDXに対して「新たな目的」と「ビジネスチャンス」を与えるという側面も持ち合わせています。これまでDXの目的は、主に「生産性向上」や「顧客体験の向上」といった経済的な価値の追求に置かれがちでした。しかし、GXという社会的な大義が加わることで、DXの取り組みに「環境価値の創出」という新たな、そして非常に重要な目的が与えられます。
例えば、ある企業がGXの一環として自社のCO2排出量を可視化・削減するシステムをDX技術で構築したとします。この取り組みで得られたノウハウや開発したシステムそのものを、「環境価値を可視化するSaaS(Software as a Service)」として他の企業に提供すれば、それは全く新しいビジネスとなります。これは、自社の課題解決(GX)のために開発したデジタルソリューション(DX)が、新たな収益源を生み出すという好循環の例です。
また、GXへの取り組みは、企業のデータ戦略にも影響を与えます。これまでは販売データや顧客データが中心でしたが、今後はCO2排出量、エネルギー消費量、廃棄物リサイクル率といった「環境データ」の重要性が飛躍的に高まります。これらの環境データを収集・分析し、製品開発やマーケティングに活用することで、環境意識の高い顧客層に響く「グリーン製品」やサービスを開発することも可能です。
このように、DXとGXは相互に依存し、強化し合う関係にあります。GXという大きな目標を達成するためには、DXによるデータとデジタル技術の活用が不可欠です。そして、GXという社会的な要請は、DXに新たな挑戦領域と事業機会をもたらします。したがって、これからの企業経営では、DXとGXを別々の取り組みとしてではなく、一つの統合された戦略として捉え、同時に推進していく視点が不可欠となるのです。
DXとGXを同時に推進する3つのメリット
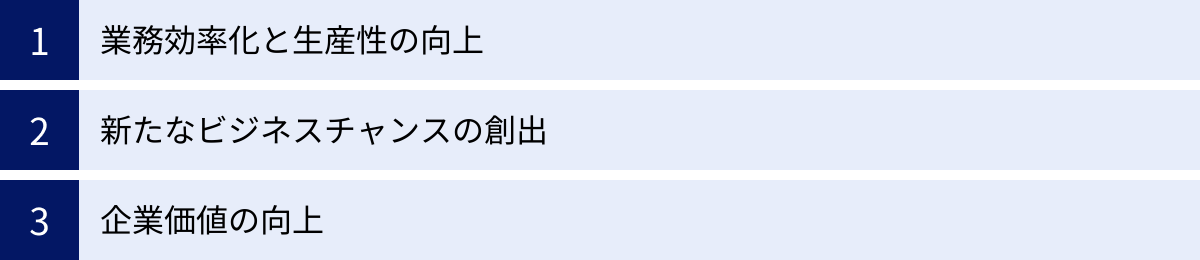
DXとGXを個別に進めるのではなく、統合された戦略として同時に推進することには、単なる足し算以上の相乗効果が期待できます。この「DX×GX」アプローチは、企業に多岐にわたるメリットをもたらし、持続的な成長の強力なエンジンとなり得ます。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリット、「業務効率化と生産性の向上」「新たなビジネスチャンスの創出」「企業価値の向上」について、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。
① 業務効率化と生産性の向上
DXとGXを組み合わせることで得られる最も直接的で分かりやすいメリットが、業務効率化と生産性の劇的な向上です。これは、DXによる「省力化・自動化」と、GXによる「省資源・省エネルギー」が融合することで、コスト構造全体にポジティブな影響を与えるために生まれます。
例えば、多くの企業でDXの第一歩として取り組まれる「ペーパーレス化」を考えてみましょう。これは、会議資料や契約書、請求書などをデジタル化し、印刷や郵送、保管にかかるコストと手間を削減するDXの取り組みです。同時に、紙の使用量を減らすことは、森林資源の保護やごみの削減に繋がり、GXの観点からも非常に有益です。さらに、デジタル化された文書はクラウド上で管理されるため、場所を選ばずにアクセスでき、テレワークの推進や意思決定の迅速化にも貢献します。このように、一つの施策がDXとGXの両方の目標達成に寄与し、生産性を高めるのです。
製造業の工場を例にとると、このメリットはさらに明確になります。GXの取り組みとして、古い生産設備をエネルギー効率の高い最新のものに入れ替えたとします。これだけでも省エネ効果はありますが、ここにDXの要素を加えることで効果は倍増します。各設備にIoTセンサーを取り付けて稼働状況やエネルギー消費量をリアルタイムで監視し、AIがそのデータを分析します。これにより、「どの設備が、どのタイミングで、最もエネルギーを無駄遣いしているか」を正確に特定し、生産計画や設備の稼働パターンを最適化できます。結果として、GXの投資効果を最大化しつつ、DXによって生産プロセス全体の効率も向上させるという、一石二鳥の効果が得られるのです。
また、人的リソースの最適化という観点からも大きなメリットがあります。従来、エネルギー管理や廃棄物管理といったGX関連の業務は、担当者が定期的に現場を巡回してメーターを読み取ったり、目視で確認したりするなど、人手に頼る部分が多くありました。ここにIoTやAIといったDX技術を導入すれば、これらの監視・管理業務の多くを自動化できます。これにより、担当者は単純な監視業務から解放され、より戦略的な削減計画の立案や、新たな省エネ技術の導入検討といった、付加価値の高い業務に集中できるようになります。これは、限られた人材を有効活用し、企業全体の生産性を向上させる上で非常に重要です。
② 新たなビジネスチャンスの創出
DXとGXの同時推進は、既存事業の効率化に留まらず、全く新しい収益の柱となるビジネスチャンスを創出する起爆剤となり得ます。これは、「環境価値」という新しい付加価値を、DXの力で「見える化」し、市場に提供できるようになるからです。
近年、ESG投資の拡大や消費者・取引先の環境意識の高まりを受け、多くの企業が自社のサプライヤーに対してCO2排出量の報告を求めるようになってきています。自社だけでなく、サプライチェーン全体での脱炭素化が求められる時代です。このような状況下で、ある企業がDXとGXの取り組みを通じて、自社のカーボンフットプリントを正確に算定・管理するノウハウとシステムを確立したとします。この企業は、そのノウハウやシステムを、同様の課題を抱える他の企業、特に取引先である中小企業などに対して、「脱炭素化支援サービス」として提供することができます。これは、自社のGX課題を解決するために投資したDXが、新たなBtoBサービス事業へと発展した典型的な例です。
また、製品やサービスそのものに「グリーン」な価値を組み込み、それをDXで証明することで、新たな市場を開拓することも可能です。例えば、アパレルメーカーが、原材料の調達から製造、輸送に至るまでの全工程で環境負荷を低減した製品を開発したとします(GXの取り組み)。そして、製品のタグに付けられたQRコードをスマートフォンで読み取ると、ブロックチェーンで記録されたその製品のカーボンフットプリントや、生産に関わった人の情報などを確認できる仕組みを構築します(DXの取り組み)。これにより、消費者は「環境に良い」という漠然としたイメージだけでなく、データに裏付けられた信頼性の高い環境価値を認識して商品を購入できます。このようなトレーサビリティの高いグリーン製品は、価格が多少高くても、環境意識の高い消費者層から強く支持され、新たなブランド価値と収益源を確立するでしょう。
さらに、DXとGXの融合は、シェアリングエコノミーやサーキュラーエコノミーといった新しい経済モデルにおいても中核的な役割を果たします。例えば、電動工具のメーカーが、製品を「販売」するだけでなく、IoTを搭載した製品を「貸し出す」サブスクリプションサービスを展開します。これにより、ユーザーは必要な時だけ利用でき、メーカーは製品の稼働データを収集して最適なメンテナンスを提供し、製品寿命を延ばすことができます。これは、所有から利用へのシフト(シェアリング)と、製品の長寿命化・再利用(サーキュラーエコノミー)をDXで実現するモデルであり、GXとDXが一体となった新しいビジネスの形です。
③ 企業価値の向上
DXとGXへの同時かつ積極的な取り組みは、財務諸表には直接現れない「非財務価値」を大きく高め、結果として持続的な企業価値全体の向上に繋がります。このメリットは、主に「ブランドイメージ」「人材獲得力」「リスク耐性」の3つの側面から説明できます。
第一に、ブランドイメージの向上です。デジタル化と環境問題という、現代社会が直面する二大テーマに先進的に取り組む企業は、顧客、取引先、そして社会全体から「未来志向で社会貢献意識の高い企業」として認識されます。これは、製品やサービスの価格競争から一線を画す、強力なブランドロイヤルティを構築する上で非常に有効です。特に、環境規制が厳しい欧州市場などへ事業を展開する際には、DXを活用してGXの取り組み成果を定量的にアピールできることが、大きな競争優位性となります。
第二に、人材獲得力と従業員エンゲージメントの強化です。特にミレニアル世代やZ世代といった若い世代は、給与や待遇だけでなく、企業のパーパス(存在意義)や社会・環境への貢献度を就職先選びの重要な基準とする傾向が強いと言われています。DXとGXを経営の柱に据え、持続可能な未来の実現に貢献するビジョンを明確に掲げる企業は、こうした価値観を持つ優秀な人材にとって非常に魅力的です。また、自社の仕事が社会貢献に繋がっているという実感は、既存の従業員のエンゲージメントやモチベーションを高め、離職率の低下にも貢献します。
第三に、将来の事業リスクに対する耐性の強化です。気候変動に関する規制(炭素税の導入など)や、エネルギー価格の変動は、将来の企業経営における大きな不確実性要因です。GXの取り組みによってエネルギー効率を高め、再生可能エネルギーへの転換を進めておくことは、これらの将来的な規制強化やコスト上昇といった「移行リスク」に備えることに直結します。また、DXによってサプライチェーンのデータを可視化しておくことは、異常気象による供給網の寸断といった「物理的リスク」が発生した際に、迅速に代替ルートを確保するなど、事業継続計画(BCP)の実効性を高める上でも極めて重要です。
このように、DXとGXを同時に推進することは、単なるコスト削減や効率化に留まらず、新たな成長機会を創出し、企業のレジリエンス(回復力・適応力)と社会的評価を高める、極めて戦略的な経営アプローチなのです。
DXとGXを同時に推進するための4ステップ
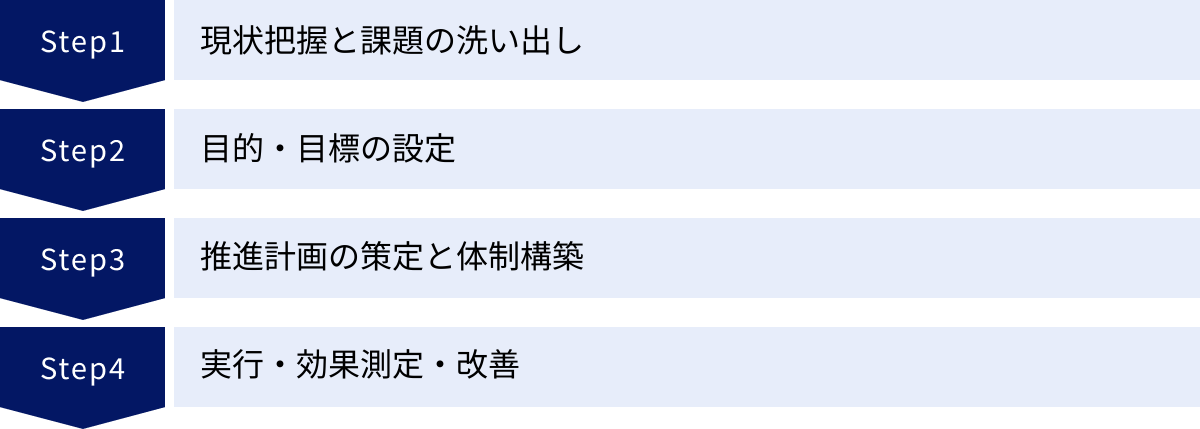
DXとGXを統合的に推進し、その相乗効果を最大化するためには、場当たり的な取り組みではなく、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、そのための具体的なプロセスを「① 現状把握と課題の洗い出し」「② 目的・目標の設定」「③ 推進計画の策定と体制構築」「④ 実行・効果測定・改善」という4つのステップに分けて解説します。
① 現状把握と課題の洗い出し
すべての変革は、自社の現在地を正確に知ることから始まります。この最初のステップでは、DXとGXの両方の側面から、自社の強み、弱み、機会、脅威を客観的に評価します。
まず、DXの側面では、以下のような点を評価します。
- 業務プロセス: 各部門の業務フローはどのようになっているか? 紙や手作業に依存している非効率なプロセスはどこか?
- ITシステム: どのようなシステムを利用しているか? 老朽化したレガシーシステムは存在するか? システム間のデータ連携はスムーズか?
- データ活用: どのようなデータが収集・蓄積されているか? データは意思決定に活用されているか? データ分析を行う人材やスキルはあるか?
- 組織・人材: デジタル技術に対する従業員のリテラシーはどの程度か? 変革に対する抵抗感はないか? DXを推進するリーダーはいるか?
次に、GXの側面では、以下のような環境データを把握することが重要です。
- エネルギー消費量: 工場、オフィス、車両など、事業活動全体でどれだけの電気、ガス、石油を消費しているか?
- 温室効果ガス(GHG)排出量: 自社の直接排出(Scope1)、エネルギー使用に伴う間接排出(Scope2)、そしてサプライチェーン全体での排出(Scope3)を可能な範囲で算定します。特にScope3の把握は、サプライチェーン全体での脱炭素化を考える上で極めて重要です。
- 廃棄物・水使用量: 廃棄物の発生量やリサイクル率、水の使用量なども把握し、削減の余地を探ります。
- 関連法規・規制: 自社の事業に関連する環境法規や、将来導入される可能性のある規制(炭素税など)について情報を収集します。
このステップで最も重要なのは、DXとGXの課題を関連付けて可視化することです。「エネルギー消費量の多いこの製造ラインは、旧式の設備で稼働データも取れていない」といったように、両方の観点から改善すべきポイントをマッピングすることで、次のステップである目標設定がより具体的になります。
② 目的・目標の設定
現状把握で明らかになった課題に基づき、自社がDXとGXを通じて何を目指すのか、そのビジョンと具体的な目標を設定します。この目標は、経営層だけでなく、全従業員が共感し、納得できるものでなければなりません。
まず、「なぜ我が社はDXとGXに取り組むのか?」という根源的な問いに対する答え、すなわち統合的なビジョンを策定します。例えば、「デジタル技術を駆使して、業界で最も環境負荷の低い製造プロセスを実現し、サステナブルな社会の実現に貢献するリーディングカンパニーになる」といった、自社の事業内容と社会的な要請を結びつけた、明確で魅力的なビジョンを掲げることが重要です。
次に、このビジョンを具体的な数値目標に落とし込みます。目標設定の際には、SMART(Specific: 具体的、Measurable: 測定可能、Achievable: 達成可能、Relevant: 関連性、Time-bound: 期限)の原則を意識すると良いでしょう。
- 悪い例:「省エネを頑張る」「DXを進める」
- 良い例:「AIを活用したエネルギー最適化システムを2025年度までに全工場に導入し、CO2排出量を2022年度比で30%削減する。同時に、システムの運用コストを年間5,000万円削減する。」
この良い例のように、GXの目標(CO2削減量)とDXの目標(システム導入)、そして財務的な目標(コスト削減額)をセットで設定することがポイントです。これにより、環境への貢献が経済的なメリットにも繋がることを明確に示し、社内の合意形成や投資判断をスムーズに進めることができます。目標は、短期(1年後)、中期(3〜5年後)、長期(10年後/2050年)といった時間軸で設定し、マイルストーンを設けることで、進捗管理がしやすくなります。
③ 推進計画の策定と体制構築
設定した目標を達成するための具体的なロードマップ(推進計画)を作成し、それを実行するための組織体制を構築します。
推進計画の策定では、目標達成のために「何を(What)」「誰が(Who)」「いつまでに(When)」「どのように(How)」実行するのかを具体的に定めます。優先順位付けも重要です。全ての課題に一度に取り組むのは非現実的なので、効果が大きく、かつ実現可能性の高い施策から着手するのが定石です。例えば、「まずはエネルギー消費量が最も多いA工場で、IoTセンサー導入のPoC(概念実証)を実施する」といったように、スモールスタートで成功体験を積み重ね、徐々に対象を拡大していくアプローチが有効です。
体制構築においては、経営層の強力なコミットメントが不可欠です。DXとGXは全社的な変革であり、部門間の利害調整も必要になるため、経営トップが旗振り役となり、全社に向けてその重要性を発信し続ける必要があります。
具体的な推進体制としては、以下のようないくつかのパターンが考えられます。
- 既存部署の連携: DX推進部と環境管理部などが密に連携してプロジェクトを進める。
- 横断的プロジェクトチーム: 各部門からメンバーを選抜したタスクフォースを組成する。
- 専門部署の設置: 「DX/GX推進室」や「サステナビリティ推進部」のような、両方を管掌する専門部署を設置する。これは、両者の連携を最もスムーズに進められる理想的な形です。
また、社内だけでは必要な知見やスキルが不足している場合も多いため、外部のコンサルタントやITベンダー、大学などの研究機関と積極的に連携することも視野に入れるべきです。必要な予算を確保し、人材育成(リスキリング)計画を立てることも、この段階で重要なタスクとなります。
④ 実行・効果測定・改善
計画と体制が整ったら、いよいよ実行フェーズに移ります。しかし、計画通りに進むことばかりではありません。重要なのは、実行した結果を客観的に評価し、計画を柔軟に見直していくPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回し続けることです。
Do(実行): 計画に基づき、PoCやパイロットプロジェクトを開始します。現場の従業員を巻き込み、彼らのフィードバックを積極的に取り入れながら進めることが成功の鍵です。
Check(効果測定): 設定したKPI(重要業績評価指標)に基づき、取り組みの成果を定期的に測定・評価します。KPIには、CO2削減量やエネルギーコスト削減額といった結果指標だけでなく、システム導入の進捗率や従業員の研修受講率といったプロセス指標も設定すると、多角的な評価が可能になります。収集したデータはダッシュボードなどで可視化し、関係者全員が進捗をリアルタイムで把握できるようにすることが望ましいです。
Act(改善): 評価結果に基づき、計画やアプローチを改善します。PoCで期待した効果が出なかった場合は、その原因を分析し、別の技術を試す、あるいはアプローチを変えるといった判断が必要です。逆に、うまくいった取り組みは、成功要因を分析して「ベストプラクティス」として標準化し、他部署へ横展開していきます。
このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、DXとGXの取り組みは徐々に組織文化として根付き、企業全体の変革へと繋がっていきます。
DXとGXの推進における3つの課題
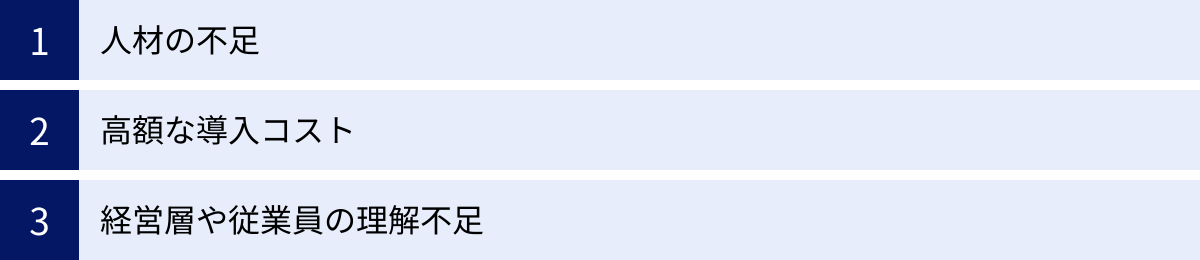
DXとGXの同時推進は、企業に大きなメリットをもたらす一方で、その道のりにはいくつかの避けて通れない障壁が存在します。これらの課題をあらかじめ認識し、対策を講じておくことが、プロジェクトを成功に導くためには不可欠です。ここでは、多くの企業が直面する代表的な3つの課題、「人材の不足」「高額な導入コスト」「経営層や従業員の理解不足」について、その実態と対策を解説します。
① 人材の不足
DXとGXの推進における最大の課題の一つが、専門的なスキルと知識を持つ人材の不足です。特に、DX(デジタル技術)とGX(環境・エネルギー)の両方に精通した「ハイブリッド人材」は市場にほとんど存在せず、極めて希少です。
DXの領域では、AIエンジニア、データサイエンティスト、クラウドアーキテクト、UI/UXデザイナーといった高度なデジタル専門職の需要が供給を大幅に上回っており、多くの企業で獲得競争が激化しています。これらの人材は、企業のデータ活用戦略やシステム構築の中核を担うため、彼らの不在はDX推進の直接的なボトルネックとなります。
一方、GXの領域でも、サステナビリティに関する深い知見、エネルギー管理の専門知識、LCA(ライフサイクルアセスメント)やGHGプロトコルに関する知識を持つ人材が求められます。これらの専門家は、企業の環境戦略を立案し、複雑な環境規制に対応するために不可欠です。
この二つの領域が融合する「DX×GX」プロジェクトでは、例えば「工場のエネルギーデータを分析してCO2削減ポテンシャルを特定する」といったタスクが発生します。このタスクを遂行するには、データ分析のスキル(DX)と、工場の生産プロセスやエネルギーに関する知識(GX)の両方が必要になります。このような複合的なスキルセットを持つ人材を見つけることは、至難の業です。
【対策】
この人材不足という課題に対しては、多角的なアプローチが必要です。
- 社内人材の育成(リスキリング): 最も現実的で重要な対策です。自社の業務に精通している既存の従業員に対して、デジタルスキルやサステナビリティに関する教育・研修プログラムを提供します。例えば、製造部門のベテラン社員にデータ分析の基礎を学んでもらう、IT部門の社員にエネルギー管理士の資格取得を奨励するなど、それぞれの専門領域を軸にスキルを拡張していくアプローチが有効です。
- 外部専門家の活用: 不足しているスキルを迅速に補うためには、外部のコンサルティングファームや専門のITベンダー、フリーランスの専門家などを積極的に活用することも重要です。彼らの知見を借りながらプロジェクトを進め、その過程で社内にノウハウを蓄積していく(内製化を目指す)という視点が求められます。
- 採用戦略の見直し: 求める人材像を「DXとGXの両方ができるスーパーマン」に設定するのではなく、「DXチーム」と「GXチーム」が円滑に連携できるような組織体制を構築し、それぞれの分野の専門家を採用する方針に切り替えることも一案です。また、企業のパーパスや社会貢献性を前面に押し出した採用ブランディングも、優秀な人材を惹きつける上で効果的です。
② 高額な導入コスト
DXとGXの推進には、多くの場合、多額の初期投資(イニシャルコスト)と継続的な運用コスト(ランニングコスト)が伴います。
DXにおいては、老朽化したレガシーシステムを刷新するための費用、新しいソフトウェアやSaaSツールのライセンス料、クラウドサービスの利用料、データを保管・処理するためのインフラコストなどが発生します。
GXにおいては、省エネルギー性能の高い最新設備への更新費用、太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー設備の導入費用、革新的な環境技術を開発するための研究開発費などが大きな負担となります。
これら二つの変革を同時に進めるとなると、投資額はさらに膨らみ、特に経営資源の限られる中小企業にとっては大きなハードルとなります。また、これらの投資は効果が現れるまでに時間がかかるケースも多く、短期的なROI(投資対効果)が見えにくいために、経営会議で承認を得るのが難しいという問題もあります。
【対策】
コストの課題を乗り越えるためには、賢い資金計画と投資戦略が求められます。
- 補助金・助成金・税制優遇の活用: 国や地方自治体は、企業のDXやGXへの取り組みを支援するために、様々な補助金や助成金制度を用意しています。例えば、経済産業省の「IT導入補助金」や、環境省の脱炭素化設備への補助金などが挙げられます。これらの制度を徹底的に調査し、活用することで、初期投資の負担を大幅に軽減できます。(参照:IT導入補助金2024 公式サイト、環境省 脱炭素化事業一覧)
- 段階的な投資とスモールスタート: 全社一斉に大規模なシステムを導入するのではなく、まずは特定の部署や業務に限定して小規模な実証実験(PoC)から始めることで、初期投資を抑えつつ、投資対効果を具体的に検証できます。ここで得られた成功事例と費用対効果のデータは、次のステップへの投資を社内で説得するための強力な材料となります。
- OPEXモデルの活用: 設備やシステムを自社で「所有(CAPEX)」するのではなく、月額料金などで「利用(OPEX)」するモデル(リースやサブスクリプション、クラウドサービスなど)を活用することも有効です。これにより、高額な初期投資を回避し、コストを平準化することができます。
③ 経営層や従業員の理解不足
技術やコスト以上に根深い課題となるのが、組織内の「人」に起因する問題、すなわち経営層や従業員の理解不足と、それに伴う変革への抵抗です。
経営層の理解不足は、プロジェクトの推進力そのものを削いでしまいます。DXやGXを単なるIT化やコストのかかる社会貢献活動としか認識せず、その戦略的重要性を理解していない場合、必要な経営資源(ヒト・モノ・カネ)の投入に消極的になります。短期的な業績を重視するあまり、長期的視点が必要なDX/GXへの投資を先送りにしてしまうケースも少なくありません。
一方で、従業員の抵抗も深刻な問題です。長年慣れ親しんだ業務プロセスが変わることへの不安や、新しいツールを覚えることへの負担感から、「今のままで問題ない」「余計な仕事が増えるだけだ」といった反発が生まれることがあります。特に、変革の目的やメリットが現場に十分に伝わっていない場合、この抵抗はさらに強くなります。
【対策】
この「人の壁」を乗り越えるには、トップダウンとボトムアップの両面からのアプローチが不可欠です。
- 経営層の強いリーダーシップとビジョンの共有: すべての始まりは、経営トップがDXとGXの重要性を自らの言葉で、繰り返し、情熱をもって社内外に発信することです。なぜ今この変革が必要なのか、会社はどこへ向かおうとしているのか、というビジョンを明確に示し、経営層自らが変革の先頭に立つ姿勢を見せることが、全社の意識を変える第一歩です。
- 全社的なコミュニケーションと教育: 従業員向けの研修会やワークショップを定期的に開催し、DX/GXの基礎知識や、変革がもたらすメリット(業務負荷の軽減、新しいスキルの習得など)を丁寧に説明します。成功事例や進捗状況を社内報やイントラネットでこまめに共有し、「自分たちも変革の当事者である」という意識を醸成することが重要です。
- 現場を巻き込む仕組み作り: 変革を「上から押し付けられたもの」ではなく「自分たちで作り上げるもの」として感じてもらうために、計画の初期段階から現場の従業員を巻き込み、彼らの意見やアイデアを積極的に吸い上げる仕組みを作ります。パイロットプロジェクトのメンバーに現場のエース級人材を登用したり、改善提案制度を設けたりすることも有効です。
これらの課題は相互に関連しており、一つを解決すれば他も改善に向かうことがあります。総合的な視点で、粘り強く対策を講じていくことが成功への道筋となります。
DXとGXの推進に役立つサービス・ツール
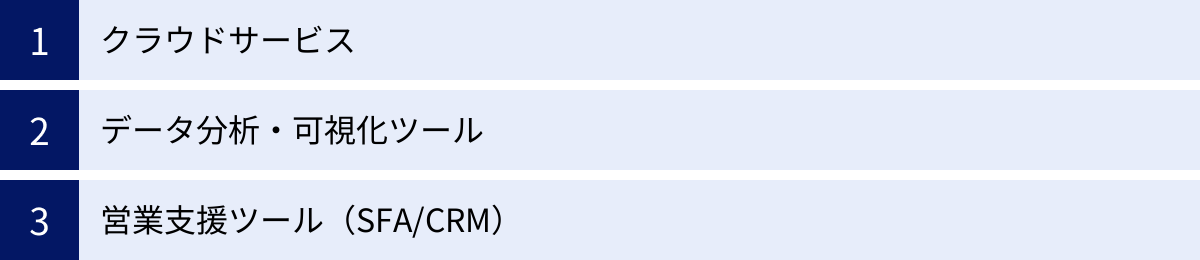
DXとGXを効果的に推進するためには、自社の努力だけでなく、外部の優れたサービスやツールを戦略的に活用することが不可欠です。ここでは、DXとGXの両方の観点から貢献度の高い代表的なサービス・ツールを、「クラウドサービス」「データ分析・可視化ツール」「営業支援ツール(SFA/CRM)」の3つのカテゴリに分けて紹介します。
クラウドサービス
クラウドサービスは、DXとGXを推進するための最も基本的なITインフラです。自社でサーバーを保有・運用するオンプレミス環境と比較して、クラウドは①エネルギー効率の高さ、②スケーラビリティと柔軟性、③データ活用の基盤となる、という3つの大きな利点があります。大手クラウド事業者は、自社のデータセンターの運用において大規模な再生可能エネルギー利用を進めており、クラウドサービスを利用すること自体が、間接的にGXに貢献(Scope2, 3排出量の削減)することに繋がります。
AWS (Amazon Web Services)
世界最大のシェアを誇るクラウドサービスで、コンピューティング、ストレージ、データベース、AI/機械学習、IoTなど、200を超える豊富なサービス群を提供しています。その圧倒的な機能性とスケーラビリティは、あらゆる規模・業種のDXニーズに対応可能です。
GXへの貢献: Amazonは2040年までに事業全体でカーボンニュートラルを達成するという目標「The Climate Pledge(気候変動対策に関する誓約)」を掲げています。その一環として、AWSのデータセンターで利用する電力の100%再生可能エネルギー化を2025年までに達成する目標を前倒しで進めています。また、「Customer Carbon Footprint Tool」を提供しており、ユーザーは自社のAWS利用状況に応じた炭素排出量を算定し、レポートとして出力できます。これにより、ITインフラの環境負荷を定量的に把握し、GXの取り組みに役立てることが可能です。(参照:アマゾン ウェブ サービス(AWS)公式サイト)
Microsoft Azure
Microsoftが提供するクラウドサービスで、特にWindows ServerやOffice 365といった同社製品との親和性が高く、多くのエンタープライズ企業に導入されています。ハイブリッドクラウド(オンプレミスとクラウドの連携)環境の構築にも強みを持ちます。
GXへの貢献: Microsoftは、2030年までにカーボンネガティブ(CO2排出量より除去量が上回る状態)を、2050年までには創業以来の累積排出量をすべて除去するという、極めて野心的な環境目標を掲げています。Azureもその目標達成に向け、再生可能エネルギーの利用とエネルギー効率の向上を推進しています。特筆すべきは「Microsoft Cloud for Sustainability」というソリューションの提供です。これは、企業が様々なソースから環境関連データ(排出量、水、廃棄物など)を統合・分析・報告するのを支援する包括的なプラットフォームであり、GX推進を直接的にサポートします。(参照:Microsoft Azure 公式サイト, Microsoft Japan News Center)
Google Cloud
Googleが提供するクラウドサービスで、同社が誇る強力なインフラを基盤としており、特にビッグデータ解析(BigQuery)やAI/機械学習(Vertex AI)の分野で高い評価を得ています。オープンソース技術への貢献も積極的です。
GXへの貢献: Googleは、2007年以来カーボンニュートラルを維持しており、さらに一歩進んで、2030年までに事業とデータセンターを24時間365日カーボンフリーエネルギーで運営するという目標を掲げています。これは、時間単位で電力消費とクリーンエネルギー調達を一致させるという画期的な取り組みです。ユーザー向けには「Carbon Footprint」ツールを提供し、Google Cloudの利用による二酸化炭素の総排出量をプロジェクト単位や製品単位で可視化できます。これにより、より環境負荷の低いリージョンを選択するなど、具体的なアクションに繋げられます。(参照:Google Cloud 公式サイト)
データ分析・可視化ツール
DXとGXの推進において、データは羅針盤の役割を果たします。しかし、単にデータを収集するだけでは意味がなく、それを分析し、誰もが理解できる形に「可視化」して初めて、データは価値を生みます。データ分析・可視化ツール(BIツール)は、そのための強力な武器となります。
Tableau
直感的なドラッグ&ドロップ操作で、専門家でなくても高度で美しいデータビジュアライゼーション(グラフやダッシュボード)を作成できるBIツールです。データ探索機能に優れており、「データを見て、理解する」プロセスを強力に支援します。
DX/GXへの貢献: 工場のセンサーデータ、エネルギー消費量、CO2排出量の実績、サプライヤーからの環境データなど、散在する様々なデータをTableauに取り込み、一つのダッシュボードに統合できます。これにより、「どの部門の排出量が目標を上回っているか」「省エネ施策の導入前後でコストはどれだけ削減されたか」といったことが一目瞭然になります。経営層への報告資料作成が効率化されるだけでなく、現場の従業員も自らの業務と環境目標との繋がりを視覚的に理解でき、改善活動へのモチベーション向上に繋がります。
Power BI
Microsoftが提供するBIツールで、ExcelやAzureなど同社製品との連携が非常にスムーズです。比較的安価なライセンス体系から始められるため、中小企業でも導入しやすいのが特徴です。
DX/GXへの貢献: Excelで管理しているエネルギー使用量のデータや、Azure上のデータベースに蓄積された生産データなどを簡単に取り込み、インタラクティブなレポートを作成できます。例えば、月次の環境パフォーマンスレビュー会議で、ドリルダウン機能を使いながら「なぜこの拠点の排出量が増加したのか」をその場で深掘りして分析するといった、データに基づいた議論を促進します。データ更新の自動化も可能なため、レポーティング業務にかかる工数を大幅に削減(DX)しつつ、GXの進捗管理を高度化できます。
営業支援ツール(SFA/CRM)
一見するとDX専門のツールに見えるSFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)も、使い方次第でGXに大きく貢献します。これらのツールは、営業プロセスの効率化・可視化を通じて、無駄な活動を削減するからです。
Salesforce
世界No.1のシェアを誇るCRM/SFAプラットフォームです。顧客管理や営業活動支援だけでなく、マーケティング、カスタマーサービスなど、ビジネスのあらゆる側面をカバーする豊富な機能と、AppExchangeによる高い拡張性が特徴です。
GXへの貢献: Salesforceは、SFA/CRM機能による営業活動の効率化(オンライン商談の活用、移動の削減など)に加え、「Net Zero Cloud」というサステナビリティ管理に特化したソリューションを提供しています。これは、企業のGHGプロトコルに基づいたScope1, 2, 3の排出量を追跡・分析・報告するための包括的なツールです。サプライヤーから排出量データを収集するポータル機能や、削減目標に向けたシミュレーション機能などを備えており、企業の脱炭素化経営を強力にバックアップします。(参照:Salesforce公式サイト)
Sales Marker
Web上の行動履歴などから顧客のニーズを分析する「インテントデータ」を活用した、新しいタイプのBtoB向け営業支援ツールです。自社製品やサービスに関心を示している企業をAIが特定し、キーパーソンへ直接アプローチできます。
DX/GXへの貢献: 従来のテレアポや飛び込み営業といった非効率な手法とは異なり、初めからニーズが顕在化している見込み客に的を絞ってアプローチできるため、営業活動全体の生産性が飛躍的に向上します(DX)。これにより、無駄な訪問や移動が劇的に削減され、営業活動に伴うガソリン消費やCO2排出量の削減に直接的に貢献します(GX)。まさに、「営業のDXが、結果としてGXに繋がる」ことを体現するツールと言えるでしょう。また、環境関連のキーワード(例:「Scope3 算定」「省エネ 補助金」)で検索している企業をターゲットに設定すれば、GX関連のソリューションを求めている企業へ効率的にアプローチすることも可能です。(参照:Sales Marker公式サイト)
これらのツールはあくまで一例であり、自社の業種や規模、課題に応じて最適なものを選択することが重要です。ツール導入を目的化するのではなく、自社のDX/GX戦略を実現するための「手段」として賢く活用していく視点が求められます。
まとめ
本記事では、現代の企業経営における二大潮流である「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と「GX(グリーントランスフォーメーション)」について、その違いから密接な関係性、同時推進のメリット、具体的な推進ステップ、そして課題と対策までを網羅的に解説してきました。
改めて要点を整理すると、以下のようになります。
- DXとGXの根本的な違い: DXの目的が「デジタル技術による競争優位性の確立」であるのに対し、GXの目的は「環境保護と経済成長の両立による持続可能な社会の実現」です。DXが主に個別の企業を対象とするのに対し、GXは産業構造や社会システム全体を対象とする、よりマクロな変革です。
- 両者の密接な関係性: DXとGXは対立する概念ではなく、相互に補完し合う「車の両輪」です。GXという壮大な目標を達成するためには、エネルギーの最適化やサプライチェーンの可視化など、あらゆる場面でDXの力(データとデジタル技術)が不可欠な手段となります。一方で、GXはDXに対して「環境価値の創出」という新たな目的とビジネスチャンスを与えます。
- 同時推進のメリット: DXとGXを統合的に推進することで、「業務効率化と生産性向上」「新たなビジネスチャンスの創出」「企業価値の向上」といった、単独で進める以上の相乗効果が期待できます。これは、コスト削減といった直接的な効果だけでなく、ブランドイメージの向上や優秀な人材の獲得、将来のリスクへの耐性強化といった非財務価値の向上にも繋がります。
- 推進の鍵: 成功のためには、①現状把握、②目標設定、③計画・体制構築、④実行・改善という体系的なステップを踏むことが重要です。その過程では、「人材不足」「高額なコスト」「組織内の理解不足」といった課題に直面しますが、リスキリングや補助金の活用、経営層の強いリーダーシップによって乗り越えることが可能です。
DXが企業の「攻め」と「守り」の変革であるならば、GXはその変革に「社会的な意義」と「未来への方向性」を与えるものと言えるでしょう。デジタル化の流れも、脱炭素化の流れも、もはや後戻りすることのない不可逆的なメガトレンドです。
これからの時代、企業が持続的に成長し、社会から選ばれ続けるためには、この二つの変革を別個のものとして捉えるのではなく、一つの統合された経営戦略として捉え、果敢に取り組んでいく必要があります。DXとGXの一体的な推進こそが、未来を切り拓くための、現代企業に課せられた最も重要な経営アジェンダなのです。この記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。