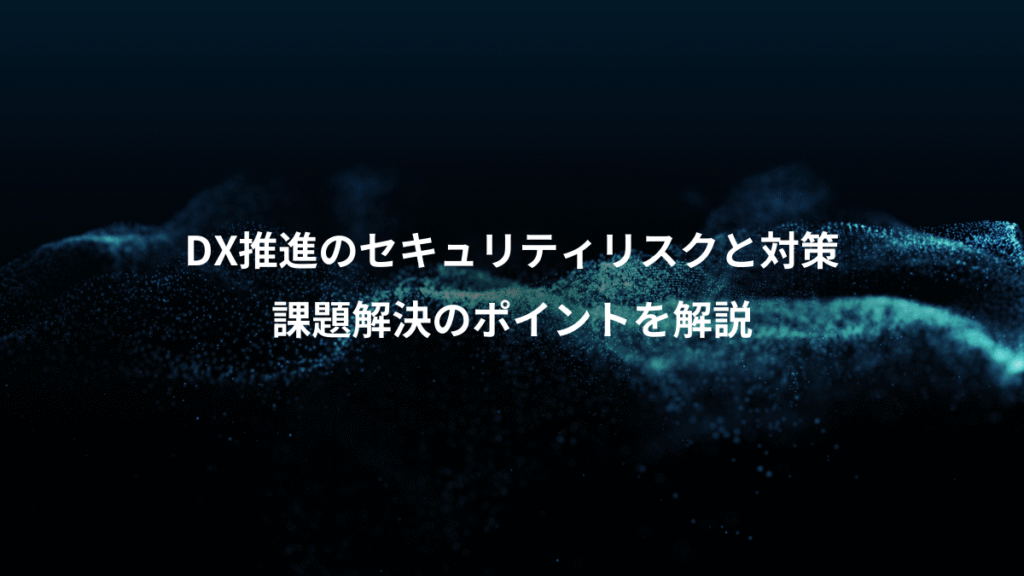現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業が競争優位性を確立し、持続的に成長するための不可欠な経営戦略となっています。新しいテクノロジーを活用してビジネスモデルを変革し、顧客に新たな価値を提供することは、もはや一部の先進的な企業だけの取り組みではありません。しかし、この変革の光には、同時に「セキュリティリスク」という濃い影が伴います。
DXの推進によって、企業活動はクラウド、IoT、モバイルデバイスといった多様なデジタル技術の上に成り立つようになります。その結果、従来の社内ネットワークと外部インターネットを隔てる「境界線」で守るというセキュリティの考え方は通用しなくなり、サイバー攻撃の対象となる領域(アタックサーフェス)はかつてないほどに拡大しています。
情報漏えいやランサムウェア攻撃といったセキュリティインシデントは、事業の停止、ブランドイメージの失墜、多額の損害賠償といった深刻な事態を招きかねません。DXによる「攻め」の成長戦略は、セキュリティという「守り」の基盤があってこそ、初めてその真価を発揮するのです。
この記事では、DX推進におけるセキュリティの重要性から説き起こし、企業が直面する具体的なセキュリティリスクと、それを乗り越えるための7つの実践的な対策、そして対策を成功に導くためのポイントを網羅的に解説します。DXという航海を安全に進めるための羅針盤として、ぜひ最後までご一読ください。
目次
DX推進にセキュリティ対策が不可欠な理由
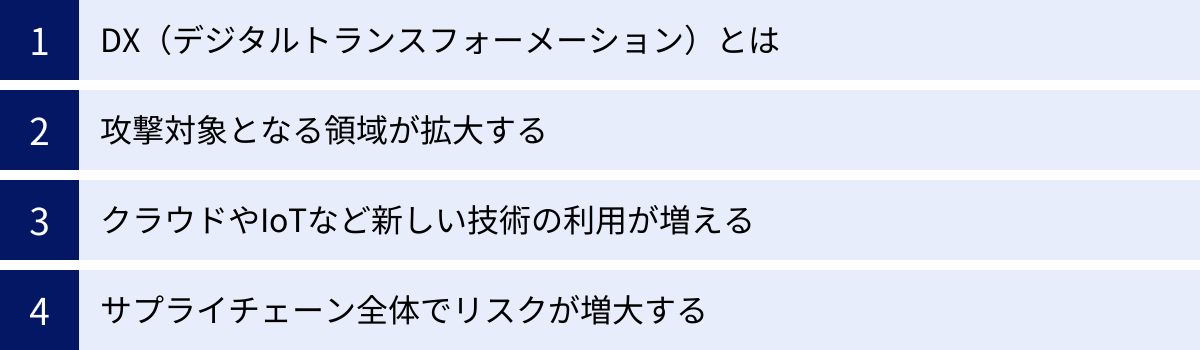
なぜ、DXを進める上でセキュリティ対策がこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は、DXがもたらすビジネス環境の根本的な変化にあります。ここでは、DXの基本的な定義から始め、セキュリティ対策が不可欠となる3つの主要な背景を詳しく掘り下げていきます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
まず、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉の定義を正しく理解することから始めましょう。DXは、単に紙の書類を電子化する「デジタイゼーション(Digitization)」や、特定の業務プロセスをITで効率化する「デジタライゼーション(Digitalization)」とは一線を画す概念です。
経済産業省が発表した「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」
つまり、DXの本質は、デジタル技術を「手段」として活用し、ビジネスモデルや組織文化そのものを根本から変革して、新たな価値を創造し続けることにあります。
例えば、製造業であれば、製品にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析し、故障を予知してメンテナンスサービスを提供する「モノ(製品)」から「コト(サービス)」へのビジネスモデル転換がDXの一例です。小売業であれば、店舗とECサイトの顧客データを統合し、一人ひとりに最適化された購買体験を提供するOMO(Online Merges with Offline)もDXの取り組みと言えるでしょう。
このような変革を目指すDXは、必然的に企業活動のあらゆる側面にデジタル技術を深く浸透させます。そして、このデジタル化の進展が、これまでのセキュリティの常識を覆す新たな課題を生み出しているのです。
攻撃対象となる領域が拡大する
従来のセキュリティ対策は、「境界型防御モデル」と呼ばれる考え方が主流でした。これは、社内ネットワーク(LAN)を「安全な内側」、インターネットを「危険な外側」と位置づけ、その境界線にファイアウォールやIDS/IPS(不正侵入検知・防御システム)といった壁を築いて、外部からの脅威の侵入を防ぐというものです。城壁を固めて敵の侵入を防ぐイメージです。
しかし、DXの推進によって、この「内側」と「外側」の境界は曖昧模糊としたものになりました。
具体的には、以下のような変化が攻撃対象領域(アタックサーフェス)を飛躍的に拡大させています。
- クラウドサービスの利用: 業務システムを自社サーバー(オンプレミス)からクラウドへ移行することで、重要なデータやアプリケーションが社外のデータセンターに置かれるようになります。
- テレワークの普及: 従業員はオフィスだけでなく、自宅やカフェ、出張先など、さまざまな場所から社内システムにアクセスします。使用するデバイスも、会社支給のPCだけでなく、個人のスマートフォンやタブレット(BYOD: Bring Your Own Device)が使われるケースも増えています。
- 外部サービスとの連携(API連携): 顧客管理、決済、物流など、さまざまな機能を外部の専門サービスとAPI(Application Programming Interface)を通じて連携させることで、自社のシステムが常に外部と通信する状態になります。
- 顧客接点のデジタル化: Webサイトやスマートフォンアプリを通じて、直接顧客とデータをやり取りする機会が増えます。
これらの変化により、守るべき情報資産は社内ネットワークの壁を越えて分散し、攻撃者が侵入を試みる「入口」が爆発的に増加しました。もはや、城壁の内側だけを守っていれば安全だという時代は終わりを告げたのです。攻撃者は、防御が手薄になりがちなクラウドの設定不備、セキュリティ対策が不十分な従業員の自宅ネットワーク、連携先のサービスの脆弱性など、あらゆる場所を狙ってきます。この拡大し続けるアタックサーフェス全体を保護するためには、境界型防御に代わる新しいセキュリティの考え方が必要不可欠です。
クラウドやIoTなど新しい技術の利用が増える
DXを加速させる原動力となるのが、クラウドコンピューティングやIoT(Internet of Things: モノのインターネット)といった新しい技術です。これらの技術は、ビジネスに俊敏性や拡張性、新たなデータ活用の可能性をもたらす一方で、特有のセキュリティリスクを内包しています。
クラウドサービスのセキュリティリスク:
クラウドサービスは、その提供形態によってIaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、SaaS(Software as a Service)に大別されますが、いずれの形態においても「責任共有モデル」という重要な概念が存在します。これは、セキュリティを確保する責任を、クラウドサービスを提供する事業者(ベンダー)と、それを利用する企業(ユーザー)とで分担するという考え方です。
例えば、Amazon Web Services (AWS) や Microsoft Azure といったIaaS/PaaSでは、データセンターの物理的なセキュリティや、サーバー、ストレージといった基盤部分のセキュリティはクラウド事業者が責任を負います。しかし、OS以上のレイヤー、例えばネットワーク設定、アクセス権限管理、アプリケーション、そして最も重要な「データ」そのものを保護する責任は、利用者側にあるのです。
多くの情報漏えいインシデントは、クラウド事業者の脆弱性が原因ではなく、利用者が設定を誤ったこと(例:機密情報を保存したストレージを誤ってインターネットに公開してしまう)が原因で発生しています。DXでクラウド活用が深化すればするほど、この利用者側の責任範囲におけるセキュリティ対策が極めて重要になります。
IoT機器のセキュリティリスク:
工場内の産業機械、物流倉庫の管理タグ、ビルの監視カメラ、医療現場の測定機器など、DXの進展とともに、あらゆる「モノ」がインターネットに接続されるようになります。これらのIoT機器は、ビジネスに革新的な効率化や新たなサービスをもたらす一方で、サイバー攻撃の格好の標的となり得ます。
IoT機器には、以下のようなセキュリティ上の課題がしばしば見られます。
- 貧弱なセキュリティ機能: コストを抑えるため、十分なセキュリティ機能が組み込まれていない場合があります。
- 初期パスワードのまま運用: 出荷時の簡単なパスワード(例:「admin」「password」)が変更されずに使われ続け、容易に侵入を許してしまいます。
- 脆弱性の放置: PCのように頻繁にセキュリティパッチが提供されず、一度発見された脆弱性が長期間放置されることがあります。
- 管理の困難さ: 数百、数千という大量のIoT機器をIT部門がすべて把握し、適切に管理することは非常に困難です。
これらの脆弱なIoT機器がボットネット(攻撃者に乗っ取られた機器のネットワーク)に組み込まれ、DDoS攻撃(分散型サービス妨害攻撃)の踏み台にされたり、社内ネットワークへの侵入経路として悪用されたりするリスクが高まっています。
サプライチェーン全体でリスクが増大する
DX時代のビジネスは、自社一社で完結することはほとんどありません。製品の企画から開発、製造、販売、サポートに至るまでの一連の流れ(サプライチェーン)において、多くの取引先やパートナー企業との緊密なデータ連携が不可欠となります。
この相互接続性の高まりは、効率性や競争力を向上させる一方で、「サプライチェーン攻撃」という深刻なリスクを生み出します。サプライチェーン攻撃とは、セキュリティ対策が強固な大企業などを直接狙うのではなく、その取引先である比較的セキュリティ対策が手薄な中小企業や子会社をまず攻撃し、そこを踏み台として本来の標的である企業へ侵入する攻撃手法です。
具体的には、以下のような手口が考えられます。
- 委託先への不正アクセス: システム開発や運用を委託している企業のネットワークに侵入し、そこから自社のシステムへアクセスするための正規のIDやパスワードを窃取する。
- ソフトウェアサプライチェーン攻撃: 取引先が開発したソフトウェアや、広く利用されているオープンソースライブラリのアップデートプロセスに不正なコード(マルウェア)を混入させ、正規のアップデートとして標的企業にインストールさせる。
- ビジネスメール詐欺(BEC): 取引先になりすまして偽の請求書を送付し、送金先口座を攻撃者のものに差し替える。
DXによって企業間のデータ連携が密になればなるほど、一社のセキュリティ侵害がサプライチェーン全体に波及するリスクは増大します。自社のセキュリティをどれだけ固めても、取引先のセキュリティレベルが低ければ、そこが「アキレス腱」となり、サプライチェーン全体が危険に晒されるのです。したがって、DXを推進する企業には、自社内の対策だけでなく、取引先を含めたサプライチェーン全体のセキュリティレベルを評価し、向上させていく取り組みが求められます。
DX推進を妨げるセキュリティ上の課題
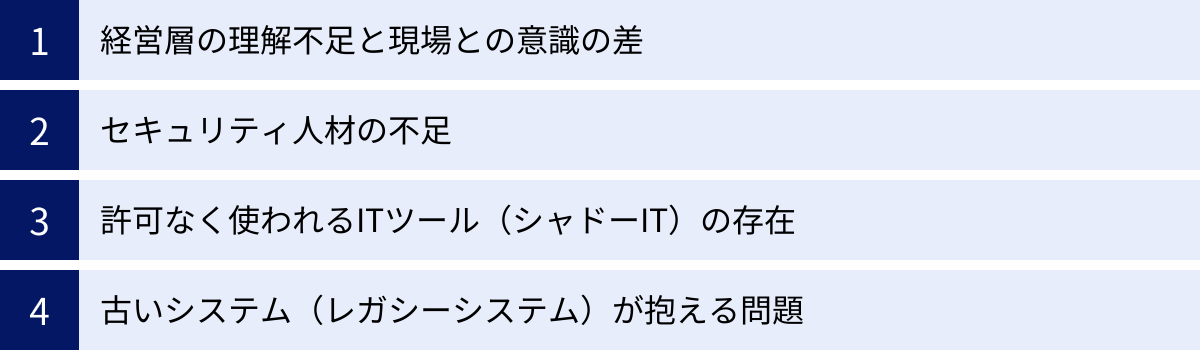
DXの重要性を理解し、いざ推進しようとしても、多くの企業がセキュリティに関するさまざまな壁に直面します。これらの課題を正しく認識し、対策を講じなければ、DXは思うように進まないばかりか、かえって企業を危険に晒すことになりかねません。ここでは、DX推進の足かせとなりがちな4つの代表的なセキュリティ上の課題について解説します。
経営層の理解不足と現場との意識の差
DXを成功させる上で最も根深い課題の一つが、経営層と現場(特に情報システム部門やセキュリティ担当者)との間に存在するセキュリティに対する意識のギャップです。
多くの経営層は、DXを売上向上や業務効率化といった「攻め」の投資として捉え、その実現に強い関心を示します。しかし、その裏側で不可欠となるセキュリティ対策については、「コスト」や「ビジネスの足かせ」と捉え、投資に消極的な傾向が見られます。セキュリティインシデントは「起きなければゼロ」のコストと見なされ、その重要性が過小評価されがちなのです。
一方で、現場の担当者は、日々進化するサイバー攻撃の脅威を肌で感じ、システムの脆弱性や対策の不備に危機感を抱いています。しかし、経営層の理解が得られないため、対策に必要な予算や人員を確保できず、場当たり的な対応に追われるケースが少なくありません。「新しいビジネスのために、とにかく早くシステムを導入してほしい」という経営層の要求と、「安全性を確保しなければ、後で大変なことになる」という現場の懸念が衝突し、DX推進の大きな障壁となります。
この意識の差は、以下のような問題を引き起こします。
- 不十分な予算: 最新のセキュリティツールの導入や、専門人材の確保・育成が進まない。
- 場当たり的な対策: 全社的な方針がないまま、問題が発生した箇所に個別に対応するため、システム全体としての一貫性や網羅性が欠如する。
- 形骸化するルール: セキュリティポリシーを策定しても、経営層がその重要性を理解し、遵守を徹底する姿勢を示さなければ、従業員にも浸透せず、ルールが守られない。
セキュリティ対策は、もはやIT部門だけの課題ではなく、事業継続を左右する重要な経営課題であるという認識を、経営層と現場が共有することが、この課題を解決するための第一歩です。
セキュリティ人材の不足
サイバー攻撃が高度化・巧妙化する一方で、それに対応できる専門的な知識やスキルを持ったセキュリティ人材は、社会全体で慢性的に不足しています。この問題は、多くの企業にとって深刻な課題です。
セキュリティ人材には、以下のように多様な役割が求められます。
- セキュリティエンジニア: セキュリティ製品の導入・構築・運用を行う。
- SOC(Security Operation Center)アナリスト: 24時間365日体制でセキュリティログを監視し、脅威の兆候を検知・分析する。
- CSIRT(Computer Security Incident Response Team)メンバー: インシデント発生時に、被害の拡大防止、原因究明、復旧、再発防止策の策定といった対応を行う。
- 脆弱性診断士(ペネトレーションテスター): 専門的な知識を用いてシステムに擬似的な攻撃を行い、脆弱性を発見・評価する。
- CISO(Chief Information Security Officer): 経営的な視点から、企業全体のセキュリティ戦略を策定し、統括する。
しかし、これらの専門人材を自社で確保・育成することは、特に中小企業にとっては非常に困難です。多くの企業では、情報システム部門の担当者が通常業務と兼任でセキュリティ対策を担っており、専門的な知見や最新の脅威動向を常に追うことが難しいのが実情です。
セキュリティ人材の不足は、DX推進において以下のようなリスクをもたらします。
- インシデントの発見の遅れ: 攻撃の兆候を見逃し、気づいたときには被害が甚大になっている。
- 不適切な初動対応: インシデント発生時に何をすべきか分からず、証拠を消してしまったり、被害をさらに拡大させたりする。
- 形だけのツール導入: 最新のセキュリティツールを導入しても、それを使いこなせる人材がおらず、アラートが放置されるなど、宝の持ち腐れになる。
- DXの遅延: 新しい技術やサービスを導入する際に、セキュリティリスクを正しく評価・対策できる人材がいないため、導入の意思決定が遅れたり、見送られたりする。
この課題に対しては、自社での採用・育成に固執するだけでなく、後述するような外部の専門サービス(SOCサービスやコンサルティングなど)を積極的に活用することも、現実的かつ有効な選択肢となります。
許可なく使われるITツール(シャドーIT)の存在
DXの目的の一つは、従業員の生産性向上です。しかし、会社が公式に提供するITツールやシステムが使いにくかったり、業務の実態に合っていなかったりすると、従業員はより便利な個人向けのクラウドサービスやアプリケーションを、会社の許可なく業務に利用し始めることがあります。これが「シャドーIT」と呼ばれる問題です。
シャドーITが生まれる背景には、以下のような従業員側の動機があります。
- 利便性の追求: 無料のオンラインストレージやチャットツールの方が、会社のツールより手軽で高機能である。
- 迅速な業務遂行: 新しいツールを利用するための社内申請プロセスが煩雑で時間がかかるため、手っ取り早く個人で契約してしまう。
- テレワーク環境への適応: 自宅での作業効率を上げるために、個人所有のデバイスやソフトウェアを利用する。
従業員に悪意はなく、むしろ善意で業務効率を上げようとした結果、シャドーITが発生するケースがほとんどです。しかし、情報システム部門が把握・管理できていないシャドーITは、企業に深刻なセキュリティリスクをもたらします。
- 情報漏えいリスク: 個人のアカウントで管理されるクラウドストレージに機密情報が保存され、アカウントの乗っ取りや設定ミスによって情報が外部に漏えいする。
- マルウェア感染経路の増加: セキュリティ対策が不十分なフリーソフトや個人向けサービスを経由して、マルウェアに感染し、社内ネットワークに拡散する。
- コンプライアンス違反: 企業のセキュリティポリシーや、業界の規制(個人情報保護法など)に準拠しないデータ管理が行われる。
- データ損失のリスク: 従業員が退職する際に、個人アカウント上の業務データが引き継がれずに失われる。
シャドーITを単に禁止するだけでは、根本的な解決にはなりません。現場の従業員の利便性を無視した厳しい規制は、かえって隠れて利用するシャドーITを増やすことになりかねません。重要なのは、従業員のニーズを把握し、利便性と安全性を両立できる公式ツールを提供すること、そして、ツール利用に関する明確なルールを定めて周知徹底することです。
古いシステム(レガシーシステム)が抱える問題
多くの企業、特に歴史の長い企業では、長年にわたって改修を繰り返してきた結果、技術的に古くなり、構造が複雑化・ブラックボックス化した「レガシーシステム」が稼働し続けています。経済産業省は、このレガシーシステムがDX推進の足かせとなり、国際競争力を低下させる問題を「2025年の崖」と名付け、警鐘を鳴らしています。
レガシーシステムは、DX推進の妨げになるだけでなく、セキュリティ上の大きな爆弾を抱えています。
- サポート終了(EOL: End of Life)による脆弱性の放置: OSやミドルウェアのメーカーサポートが終了すると、新たに発見された脆弱性に対するセキュリティパッチが提供されなくなります。これは、攻撃者に対して無防備な状態を晒し続けることを意味し、非常に危険です。
- 最新セキュリティ技術の導入困難: 古いアーキテクチャで構築されているため、ゼロトラストやEDRといった最新のセキュリティ対策を導入することが技術的に難しい場合があります。
- システムのブラックボックス化: 設計書などのドキュメントが残っておらず、開発に携わった担当者も退職しているため、システムの内部構造や仕様が誰にも分からない状態になっています。これにより、脆弱性が見つかっても修正が困難であったり、修正による影響範囲が予測できなかったりします。
- 新旧システムの連携部分の脆弱性: DXのために新しいシステムを導入する際、レガシーシステムと無理に連携させようとすると、その接続部分に新たなセキュリティホールが生まれやすくなります。
これらの問題を抱えたレガシーシステムを放置したままDXを進めるのは、土台が腐った土地に新しい家を建てるようなものです。DXを本格的に推進するためには、レガシーシステムからの脱却(モダナイゼーション)を計画的に進め、セキュリティを確保できるモダンなIT基盤を再構築することが不可欠です。これは時間もコストもかかる困難な課題ですが、避けては通れない道と言えるでしょう。
DX推進で高まる具体的なセキュリティリスク
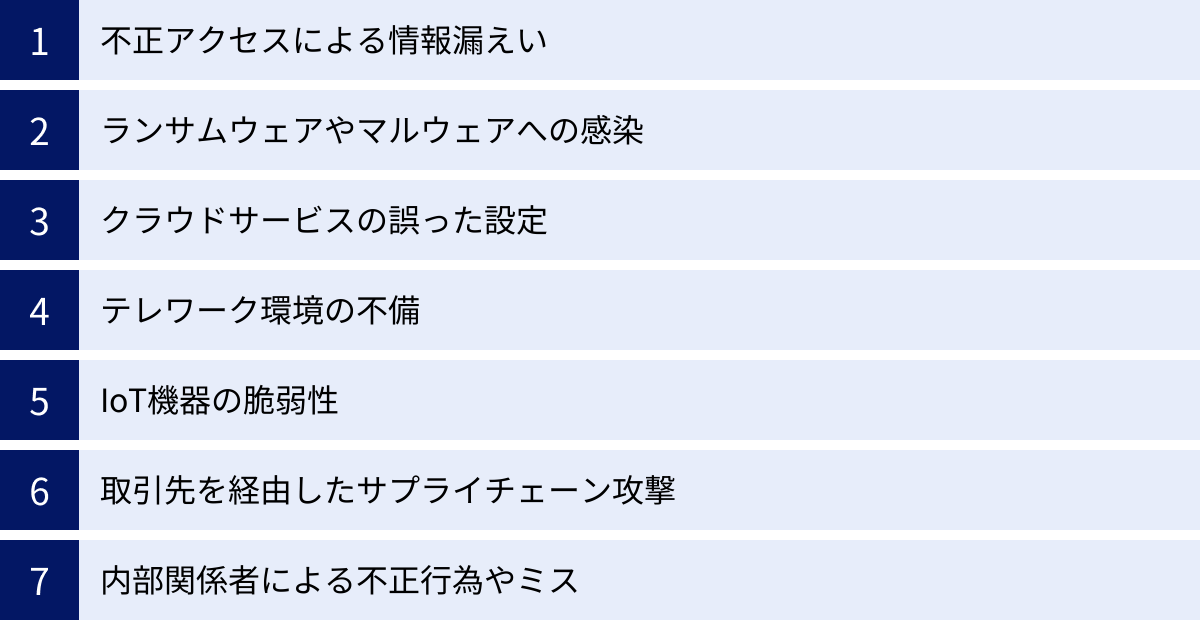
DXの推進は、ビジネスに多くのメリットをもたらす一方で、サイバー攻撃者にとっては魅力的な攻撃対象を増やすことにも繋がります。ここでは、DXに取り組む企業が直面する可能性のある、7つの具体的なセキュリティリスクについて、その手口や影響を詳しく解説します。
不正アクセスによる情報漏えい
不正アクセスは、最も古典的かつ依然として深刻な脅威の一つです。攻撃者は、システムの脆弱性を悪用したり、窃取した認証情報を利用したりして、本来アクセス権のないサーバーやクラウドサービスに侵入し、内部に保管されている機密情報を盗み出します。
DXの進展により、企業の重要データは社内サーバーだけでなく、さまざまなクラウドサービスや外部システムに分散して保存されるようになりました。このため、不正アクセスの標的も多様化しています。
- 顧客情報: 氏名、住所、連絡先、クレジットカード情報などの個人情報が漏えいした場合、被害者への賠償やブランドイメージの失墜に繋がります。
- 技術情報: 製品の設計図やソースコード、研究開発データなどが盗まれれば、企業の競争力の源泉が失われます。
- 財務情報: 未公開の決算情報やM&A情報などが漏えいすると、インサイダー取引などに悪用される可能性があります。
不正アクセスの手口としては、IDとパスワードの窃取が主流です。フィッシング詐欺(正規のサイトを装った偽サイトに従業員を誘導し、ID・パスワードを入力させる)や、他のサービスから漏えいしたID・パスワードの組み合わせを使い回してログインを試みるパスワードリスト攻撃などが頻繁に用いられます。安易なパスワードの設定や、複数のサービスでのパスワードの使い回しは、極めて危険な行為です。
ランサムウェアやマルウェアへの感染
ランサムウェアは、「Ransom(身代金)」と「Software(ソフトウェア)」を組み合わせた造語で、感染したコンピュータやサーバーのデータを暗号化して使用不能にし、その復旧と引き換えに身代金を要求するマルウェア(悪意のあるソフトウェア)です。
近年のランサムウェア攻撃は、単にデータを暗号化するだけでなく、「二重恐喝(ダブルエクストーション)」と呼ばれる、より悪質な手口が主流になっています。これは、データを暗号化する前に、まず機密情報を窃取し、「身代金を支払わなければ、盗んだデータをインターネット上に公開する」と脅迫するものです。企業は、事業停止のリスクに加えて、情報漏えいのリスクにも晒されることになります。
DXによってPCやサーバー、IoT機器など、ネットワークに接続されるデバイス(エンドポイント)が増加すると、それに伴いランサムウェアやマルウェアの感染経路も拡大します。
- メールの添付ファイルやリンク: 業務連絡や取引先を装ったメールに、マルウェアを仕込んだファイルを添付したり、不正なWebサイトへのリンクを記載したりする。
- 脆弱性の悪用: OSやソフトウェアの脆弱性を突いて、ユーザーが気づかないうちにマルウェアを送り込む。
- VPN機器の脆弱性: テレワークで利用されるVPN機器の脆弱性を悪用して社内ネットワークに侵入し、マルウェアを拡散させる。
- 不正なソフトウェア: フリーソフトや海賊版ソフトに偽装して、マルウェアをインストールさせる。
一度ランサムウェアに感染すると、業務システムの全面的な停止、データの完全な喪失、高額な復旧費用や身代金の要求、顧客や取引先からの信頼失墜など、事業の根幹を揺るがす甚大な被害に繋がる可能性があります。
クラウドサービスの誤った設定
クラウドサービスの利用はDXの核となりますが、その設定を一つ間違えるだけで、意図せずして重大な情報漏えいを引き起こす可能性があります。前述の「責任共有モデル」の通り、クラウド環境における設定の責任は、サービスを利用するユーザー企業にあります。
特に、Amazon S3(ストレージサービス)やMicrosoft Azure Blob Storageなどで発生しやすい「ストレージの公開設定ミス」は、典型的なインシデント例です。本来はアクセスを厳しく制限すべき機密情報(顧客リスト、個人情報、アクセスキーなど)が保存されたストレージが、誤って「インターネット上の誰でもアクセス可能」な状態に設定され、情報が流出してしまうケースが後を絶ちません。
その他にも、以下のような設定ミスがリスクとなります。
- 不適切なアクセス権限(IAM)設定: 必要以上に強力な権限をユーザーやアプリケーションに与えてしまい、アカウントが乗っ取られた際の被害が拡大する。
- 管理コンソールの保護不備: クラウド環境全体を管理できるコンソールへのアクセスに、多要素認証(MFA)が設定されていない。
- ファイアウォール(セキュリティグループ)設定の不備: 本来公開すべきでないポート(データベースへの接続ポートなど)を誤って外部に開放してしまう。
これらの設定ミスは、悪意のないヒューマンエラーによって発生することがほとんどです。しかし、その結果は大規模な情報漏えいに直結します。クラウド環境の複雑さと設定項目の多さが、意図しない設定ミスを生みやすいため、設定状態を継続的に監視し、自動で検知・修正する仕組みの導入が重要です。
テレワーク環境の不備
コロナ禍を機に急速に普及したテレワークは、柔軟な働き方を実現する一方で、新たなセキュリティリスクを生み出しました。オフィスという物理的に守られた環境から離れ、従業員がさまざまな環境で業務を行うことで、管理の目が行き届きにくくなります。
テレワーク環境における主なセキュリティリスクは以下の通りです。
- 家庭内ネットワークの脆弱性: 自宅で使用しているWi-Fiルーターのファームウェアが古かったり、簡単なパスワードが設定されていたりすると、そこから通信を盗聴されたり、家庭内のデバイスを踏み台にされたりする可能性があります。
- BYOD(Bring Your Own Device)のリスク: 従業員個人のPCやスマートフォンを業務に利用する場合、会社としてセキュリティ対策(アンチウイルスソフトの導入やOSのアップデートなど)を強制することが難しく、マルウェア感染のリスクが高まります。
- VPNの課題: VPN(Virtual Private Network)は社内ネットワークへの安全な接続手段ですが、VPN機器自体に脆弱性が見つかるケースや、アクセス集中によるパフォーマンス低下といった課題もあります。
- 物理的なセキュリティリスク: カフェなどの公共の場で作業する際の、画面の盗み見(ショルダーハック)や、PC・USBメモリの盗難・紛失のリスクも考慮しなければなりません。
これらのリスクに対応するためには、テレワークを前提としたセキュリティポリシーの策定、安全なリモートアクセス環境の提供、従業員へのセキュリティ教育が三位一体で必要となります。
IoT機器の脆弱性
スマート工場、スマートシティ、コネクテッドカーなど、DXの進展は社会のあらゆる場面でIoT機器の活用を広げています。しかし、これらのIoT機器の多くは、PCやサーバーほど強固なセキュリティ対策が施されていないのが実情です。
IoT機器が抱える脆弱性は多岐にわたります。
- デフォルトパスワードの利用: 出荷時のままの安易なID・パスワードが変更されずに使われている。
- パッチ管理の不備: 脆弱性が発見されても、修正パッチが提供されなかったり、提供されても適用されなかったりする。
- ハードコードされた認証情報: 変更不可能な認証情報がプログラム内に埋め込まれている。
- セキュアでない通信: 重要なデータを暗号化せずに通信している。
攻撃者は、これらの脆弱なIoT機器を乗っ取り、「Mirai」に代表されるようなボットネットを形成します。そして、このボットネットを利用して、特定のWebサイトやサービスに大量のアクセスを送りつけて機能不全に陥らせるDDoS攻撃を仕掛けたり、企業ネットワークへの侵入口として利用したりします。監視カメラの映像が盗み見られたり、工場の制御システムが乗っ取られて生産ラインが停止したりといった、物理的な被害に繋がるリスクも無視できません。
取引先を経由したサプライチェーン攻撃
自社のセキュリティ対策が万全でも、取引先や業務委託先がサイバー攻撃を受け、そこを踏み台にされる「サプライチェーン攻撃」のリスクは、DXによる企業間連携の深化とともに増大しています。
攻撃者は、ターゲット企業を直接攻撃するよりも、セキュリティ対策が手薄になりがちな関連会社や中小の取引先を狙う方が容易であると考えています。
- 侵入の踏み台: 開発委託先や保守業者のアカウントを乗っ取り、正規の経路でターゲット企業のネットワークに侵入する。
- ソフトウェアへのマルウェア混入: ソフトウェア開発会社を攻撃し、正規の製品やアップデートファイルにマルウェアを仕込む。ユーザーは信頼してインストールするため、被害が広範囲に及びやすい。
- ビジネスメール詐欺(BEC): 取引先の担当者になりすまし、「振込先口座が変更になった」といった偽の連絡を送り、金銭を詐取する。
サプライチェーン攻撃の恐ろしい点は、信頼している取引先から攻撃が仕掛けられるため、検知が非常に困難であることです。自社だけでなく、サプライチェーン全体でのセキュリティレベルの底上げが急務となっています。
内部関係者による不正行為やミス
セキュリティ脅威は、必ずしも外部からのみもたらされるわけではありません。企業の従業員や元従業員といった「内部関係者」による不正行為や、悪意のない操作ミスも、重大なインシデントの原因となります。
- 悪意による不正行為: 不満を抱いた従業員や退職者が、顧客情報や技術情報といった機密データをUSBメモリなどで不正に持ち出したり、システムを破壊したりする。権限を悪用されるため、防御が難しい場合があります。
- 悪意のないミス(ヒューマンエラー):
- メールの宛先を間違え、機密情報を含むファイルを外部に誤送信してしまう。
- フィッシングメールに騙され、自らのIDとパスワードを攻撃者に渡してしまう。
- 機密情報が入ったPCやスマートフォンを紛失・盗難される。
- クラウドの設定を誤り、意図せず情報を公開してしまう。
特に、DXによって扱うデータの量と種類が増え、さまざまなツールを使い分けるようになると、ヒューマンエラーが発生する可能性は高まります。「人は誰でも間違いを犯す」という前提に立ち、技術的な対策(誤送信防止ツール、アクセス制御など)と、継続的な従業員教育を組み合わせることが重要です。
今すぐ始めるべきDXのセキュリティ対策7選
DX推進に伴う多様なリスクに対応するためには、包括的かつ戦略的なセキュリティ対策が不可欠です。ここでは、企業がDXを安全に進めるために、今すぐ着手すべき7つの重要な対策を具体的に解説します。これらは個別の対策としてではなく、相互に関連し合う一つの体系として捉えることが重要です。
① 全社的なセキュリティ方針を定める
全てのセキュリティ対策の土台となるのが、組織としての統一された意思決定の基準、すなわち「情報セキュリティポリシー」の策定です。これは、単なる技術的な設定手順書ではなく、企業が情報資産をどのように保護し、どのようなセキュリティレベルを目指すのかを内外に示す、いわば「セキュリティの憲法」です。
情報セキュリティポリシーは、一般的に以下の3つの階層で構成されます。
| ポリシー階層 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 基本方針(トップポリシー) | 企業の情報セキュリティに対する基本的な考え方、目的、責任の所在などを宣言する。 | 全従業員、顧客、取引先など |
| 対策基準(スタンダード) | 基本方針を実現するために、守るべき具体的なルールや遵守事項を定義する。(例:パスワードポリシー、アクセス制御ポリシー、クラウド利用基準) | 全従業員 |
| 実施手順(プロシージャ) | 対策基準を具体的に実行するための、詳細な手順や設定方法を記述する。(例:ファイアウォールの設定手順、サーバーの初期設定マニュアル) | システム管理者、開発者など |
セキュリティポリシーを策定する上で重要なのは、経営層が深く関与し、その策定を主導することです。経営層のコミットメントがあって初めて、ポリシーは全社的なルールとしての実効性を持ちます。また、DXの進展や新たな脅威の出現に合わせて、ポリシーを定期的に見直し、常に最新の状態に保つことも不可欠です。策定したポリシーは、全従業員に周知徹底し、なぜそれが必要なのかという背景も含めて理解を促す教育活動とセットで進める必要があります。
② 「すべてを信頼しない」ゼロトラストを導入する
従来の「境界型防御」が通用しなくなった現代において、新たなセキュリティの指針となるのが「ゼロトラスト」という考え方です。ゼロトラストは、その名の通り「何も信頼せず、常に全てのアクセスを検証する(Never Trust, Always Verify)」という原則に基づいています。
境界型防御では、「社内ネットワークは安全、社外は危険」という前提に立ち、一度社内ネットワークに入ってしまえば、比較的自由にさまざまなリソースにアクセスできました。しかしゼロトラストでは、社内ネットワークであろうと、社外からのアクセスであろうと、区別なく全ての通信を「信頼できない」ものと見なします。
ゼロトラストセキュリティを実現するための主要な構成要素
- IDベースの認証・認可の強化: 誰がアクセスしてきているのかを厳格に確認します。多要素認証(MFA)を必須とし、アクセス元の場所、時間、デバイスの状態など、さまざまな要素(コンテキスト)を考慮して、アクセスを許可するかどうかを動的に判断します。
- デバイスの信頼性の検証: どのようなデバイスからアクセスしてきているのかを検証します。OSが最新か、セキュリティソフトが正常に稼働しているかなどをチェックし、信頼できると判断されたデバイスからのアクセスのみを許可します。
- 最小権限の原則の徹底: アクセスを許可されたユーザーやデバイスに対しても、業務に必要な最小限のリソースへのアクセス権のみを与えます。これにより、万が一アカウントが乗っ取られても、被害を最小限に抑えることができます。
- マイクロセグメンテーション: ネットワークを細かく分割し、セグメント間の通信を厳しく制御します。これにより、仮に一つのセグメントが侵害されても、攻撃者がネットワーク内を横展開(ラテラルムーブメント)して被害を拡大させることを防ぎます。
ゼロトラストは特定の製品を導入すれば完成するものではなく、これらの要素を組み合わせ、時間をかけて段階的に構築していく継続的な取り組みです。まずはテレワーク環境のアクセスセキュリティや、重要な情報資産へのアクセス制御からスモールスタートで導入していくのが現実的なアプローチです。
③ クラウドと利用端末(エンドポイント)の防御を固める
ゼロトラストの考え方を実践する上で、特に重要となるのが「クラウド」と「エンドポイント(PCやサーバーなどの利用端末)」の防御です。これらはDX環境における攻撃の主要な入口であり、出口でもあります。
クラウドセキュリティの強化:
- CSPM (Cloud Security Posture Management): クラウドサービス(IaaS/PaaS)の設定ミスを継続的に監視、検知し、自動で修正するツールです。「S3バケットが公開されていないか」「IAMの権限設定は適切か」といった点を、あらかじめ定義されたベストプラクティスや自社のポリシーと照らし合わせて自動でチェックします。ヒューマンエラーによる設定ミスを未然に防ぎ、コンプライアンスを維持するために不可欠です。
- CWPP (Cloud Workload Protection Platform): クラウド上で稼働するサーバー(仮想マシン)、コンテナ、サーバーレスといった「ワークロード」自体を保護するソリューションです。脆弱性管理、マルウェア対策、不正侵入検知などの機能をワークロードレベルで提供し、アプリケーションの実行環境を安全に保ちます。
エンドポイントセキュリティの強化:
- EPP (Endpoint Protection Platform): 従来型のアンチウイルスソフトが進化したもので、既知のマルウェアのシグネチャ検知に加え、機械学習などを用いて未知のマルウェアを検知・ブロックします。いわば「入口対策」です。
- EDR (Endpoint Detection and Response): EPPをすり抜けて侵入してしまった脅威を検知し、迅速な対応を支援するソリューションです。エンドポイントの操作ログ(プロセスの起動、ファイルアクセス、通信など)を常時監視し、攻撃の兆候や不審な振る舞いを検知します。インシデント発生時に「何が起きたのか」「どこまで影響が及んでいるのか」を可視化し、遠隔から端末を隔離するなどの対応を可能にする「侵入後対策」の要です。
DX環境では、これらEPPとEDRを組み合わせ、多層的な防御を実現することが標準的な対策となっています。
④ 問題発生時の対応チーム(CSIRTなど)を作る
どれだけ高度な防御策を講じても、100%サイバー攻撃を防ぎきることは不可能です。したがって、インシデント(セキュリティ事故)が発生することを前提として、その被害を最小限に抑え、迅速に復旧するための体制を平時から準備しておくことが極めて重要です。その中核となるのが、CSIRT (Computer Security Incident Response Team) と呼ばれる専門チームです。
CSIRTの主な役割は以下の通りです。
- インシデントの受付とトリアージ: 社内外からのインシデント報告を受け付け、その緊急度や影響範囲を評価し、対応の優先順位を決定します。
- インシデント対応の指揮: 専門的な知見に基づき、各関連部署と連携しながら、被害拡大の防止、原因調査、システムの復旧といった一連の対応活動を指揮・支援します。
- 情報集約と報告: インシデントに関する情報を一元的に集約し、経営層や関係機関、場合によっては顧客や社会に対して適切な報告を行います。
- 再発防止策の策定: インシデントの原因を分析し、同様の事態が再発しないための恒久的な対策を立案し、その実施を推進します。
CSIRTは、情報システム部門のメンバーだけでなく、法務、広報、人事、各事業部門の担当者など、部門横断的なメンバーで構成することが理想的です。また、平時からインシデント対応の手順をまとめた「インシデントレスポンスプラン」を策定し、標的型攻撃メール訓練やサイバー演習などを通じて、定期的に対応手順の習熟度を高めておくことが、いざという時の迅速な行動に繋がります。
⑤ 全従業員のセキュリティ意識を高める教育を行う
セキュリティ対策において「最後の砦」となるのは、技術やシステムではなく「人」です。攻撃者は、システムの脆弱性だけでなく、人間の心理的な隙や知識不足を突く「ソーシャルエンジニアリング」を多用します。そのため、全従業員のセキュリティリテラシーを向上させることは、技術的な対策と同等、あるいはそれ以上に重要です。
効果的なセキュリティ教育には、以下のような内容を含めることが推奨されます。
- 標的型攻撃メール訓練: 実際の攻撃メールに酷似した疑似メールを従業員に送信し、開封してしまったり、リンクをクリックしてしまったりしないかをテストします。結果をフィードバックし、見分けるポイントを具体的に教育することで、対応能力を高めます。
- パスワード管理: 推測されにくいパスワードの作成方法、定期的な変更の必要性、パスワードの使い回しの禁止などを徹底します。
- 情報資産の取り扱い: 機密情報の定義、社外への持ち出しルール、安全なデータの共有方法などを学びます。
- シャドーITのリスク: 会社の許可なく個人向けサービスを利用することの危険性を理解させ、公式ツールの利用を促します。
- インシデント発生時の報告ルール: 不審なメールやPCの異常を発見した際に、「隠さずに、すぐに」定められた窓口(CSIRTや情報システム部門)へ報告することの重要性を教えます。
セキュリティ教育は、入社時に一度行うだけでは不十分です。定期的に、かつ役割や職種(一般従業員、管理者、開発者など)に応じて内容をカスタマイズしながら、繰り返し実施することで、組織全体のセキュリティ文化を醸成していくことが大切です。
⑥ 定期的にシステムの弱点(脆弱性)を診断する
自社が運用するシステムやアプリケーションに、どのようなセキュリティ上の弱点(脆弱性)が存在するのかを把握しなければ、適切な対策は打てません。そこで有効なのが、専門家の視点でシステムの安全性をチェックする「脆弱性診断」です。
脆弱性診断は、攻撃者と同じような手法でシステムを調査し、セキュリティホールを発見・評価するサービスです。主な診断対象には以下のようなものがあります。
- プラットフォーム診断: サーバーのOSやミドルウェアに既知の脆弱性がないか、不要なポートが開放されていないかなどをスキャンツールや手動で診断します。
- Webアプリケーション診断: 企業のWebサイトやWebアプリケーションに、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)といった特有の脆弱性がないかを診断します。
脆弱性診断は、一度実施して終わりではありません。システムに新たな機能を追加・変更したタイミングや、年に1回などの定期的なタイミングで繰り返し実施し、常に自社のシステムの健康状態を把握しておくことが重要です。診断で発見された脆弱性は、その深刻度(リスク)に応じて優先順位を付け、計画的に修正していくPDCAサイクルを回すことで、システムのセキュリティレベルを継続的に維持・向上させることができます。
⑦ 最新のセキュリティツールを活用する
高度化・巧妙化するサイバー攻撃に、人間の目と手だけで対抗するには限界があります。特に、人材不足に悩む企業にとっては、セキュリティ運用の効率化・自動化は喫緊の課題です。最新のセキュリティツールを効果的に活用することで、限られたリソースでも高度なセキュリティレベルを維持することが可能になります。
前述のCSPM、EDRなどに加え、以下のようなツールの活用も有効です。
- SIEM (Security Information and Event Management): ファイアウォール、サーバー、EDRなど、社内のさまざまな機器やシステムから出力されるログを一元的に収集・分析し、個々のログだけでは見つけられない脅威の相関関係や兆候を可視化します。
- SOAR (Security Orchestration, Automation and Response): SIEMなどが検知したインシデントに対して、あらかじめ定義された手順(プレイブック)に従って、対応の一部(端末の隔離、特定の通信の遮断など)を自動で実行するプラットフォームです。これにより、インシデント対応の迅速化と、セキュリティ担当者の負荷軽減を実現します。
自社の課題やリソースを正しく見極め、目的に合ったツールを選定し、導入するだけでなく、それを適切に運用する体制まで含めて検討することが、ツール活用の成否を分けます。
セキュリティ対策を成功に導く3つのポイント
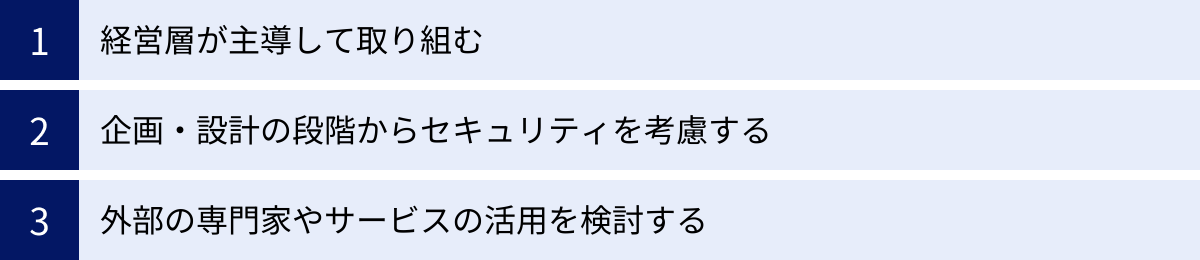
これまで紹介した7つの対策を効果的に実行し、DX時代のセキュリティを確立するためには、技術的な側面に加えて、組織としての取り組み方が極めて重要になります。ここでは、セキュリティ対策を形骸化させず、真に成功へと導くための3つの重要なポイントを解説します。
① 経営層が主導して取り組む
セキュリティ対策の成否は、経営層のコミットメントの強さに懸かっていると言っても過言ではありません。現場の担当者がどれだけ危機感を訴えても、経営層がセキュリティを「IT部門任せのコストセンター」としか認識していなければ、必要な予算や人員は確保されず、全社的な協力も得られません。
成功する企業では、経営層が「セキュリティは事業継続に不可欠な経営課題であり、攻めのDXを支える重要な投資である」と明確に認識しています。そして、そのリーダーシップのもと、以下のような取り組みを主導します。
- CISO(最高情報セキュリティ責任者)の任命: 経営的な視点を持ち、全社のセキュリティ戦略に責任を持つ役員を任命し、必要な権限とリソースを与えます。CISOは、経営会議や取締役会でセキュリティの状況を定期的に報告し、経営判断に必要な情報を提供します。
- 予算の確保と優先順位付け: 事業計画と同様に、セキュリティ対策にも中期的な計画を立て、継続的に予算を配分します。リスク評価に基づき、どこに優先的に投資すべきかを判断します。
- トップメッセージの発信: 社長や役員が自らの言葉で、全従業員に対してセキュリティの重要性を繰り返し伝え、セキュリティポリシーの遵守を促します。このトップからのメッセージが、組織全体のセキュリティ文化を醸成する上で絶大な効果を発揮します。
経営層が「自分ごと」としてセキュリティに関与し、強力なリーダーシップを発揮すること。これが、実効性のあるセキュリティ対策を実現するための最も重要な鍵となります。
② 企画・設計の段階からセキュリティを考慮する
新しいシステムを開発したり、新たなクラウドサービスを導入したりする際に、機能や性能、コストばかりを優先し、セキュリティ対策を後回しにしてしまうケースがよく見られます。そして、開発が完了した後や、運用が始まった後で慌ててセキュリティ対策を追加しようとすると、大幅な手戻りが発生したり、根本的な対策が打てずに付け焼き刃の対応になったりして、結果的にコストも時間も余計にかかってしまいます。
このような失敗を避けるために重要なのが、「セキュリティ・バイ・デザイン」や「シフトレフト」と呼ばれる考え方です。これは、システムやサービスのライフサイクルの初期段階、すなわち企画・設計のフェーズからセキュリティ要件を組み込むというアプローチです。
具体的には、以下のような活動を行います。
- 要件定義: システムが扱う情報の機密性や、求められる可用性などを評価し、必要なセキュリティ要件(例:データの暗号化、多要素認証の導入など)を機能要件と同時に定義します。
- 脅威モデリング: 設計段階で、システムに対してどのような脅威が想定されるかを洗い出し、そのリスクを評価して、設計にセキュリティ対策を反映させます。
- セキュアコーディング: 開発段階で、脆弱性を生み込まないためのコーディング規約を定め、開発者に教育を行います。
- セキュリティテスト: 開発プロセスの中に、脆弱性診断やソースコードレビューといったセキュリティテストを組み込み、早期に問題を発見・修正します。
開発の早い段階(左側)でセキュリティの問題に対応すればするほど、その修正コストは低く抑えられます。 DXで求められる開発のスピードと、セキュリティの堅牢性を両立させるためには、このシフトレフトのアプローチが不可欠です。
③ 外部の専門家やサービスの活用を検討する
多くの企業、特に中堅・中小企業にとって、高度な専門性を持つセキュリティ人材を自社だけで確保し、24時間365日体制で運用を行うことは現実的に非常に困難です。自社のリソースだけで全てを賄おうとすると、担当者の疲弊や、対策レベルの低下を招きかねません。
そこで、自社の弱みを補完するために、外部の専門家やセキュリティサービスを積極的に活用することが、賢明かつ効果的な選択肢となります。
- SOC (Security Operation Center) サービス: 専門のアナリストが24時間体制で企業のネットワークやシステムを監視し、脅威の検知・分析・通知を行ってくれるサービスです。自社で深夜・休日の監視体制を構築する負担から解放されます。
- 脆弱性診断サービス: 専門の技術者が、定期的にシステムの脆弱性を診断し、詳細な報告書と対策案を提供してくれます。自社では発見が難しい高度な脆弱性を見つけ出すことができます。
- セキュリティコンサルティング: セキュリティポリシーの策定支援、CSIRTの構築支援、各種認証(ISMSなど)の取得支援など、企業のセキュリティ態勢全般に関するアドバイスや支援を提供します。
- インシデントレスポンス支援サービス: 実際にインシデントが発生した際に、専門家が駆けつけて原因調査(デジタルフォレンジック)や復旧作業を支援してくれます。
重要なのは、自社の強み(ビジネスへの理解など)と弱み(専門技術、24時間監視など)を客観的に評価し、何を自社で行い(インハウス)、何を外部に委託する(アウトソース)のかを戦略的に判断することです。信頼できるパートナーを見つけることができれば、自社のコア業務に集中しながら、高いレベルのセキュリティを維持することが可能になります。
DX推進に役立つセキュリティツール・サービス
DXを支えるセキュリティ対策は、適切なツールやサービスの活用によって、より強固で効率的なものになります。ここでは、これまでの解説で触れたセキュリティ分野において、代表的なツールやサービスをいくつか紹介します。自社の課題や目指すセキュリティレベルに応じて、これらの導入を検討してみましょう。
| セキュリティカテゴリ | 主な目的・役割 | 代表的なツール・サービス例 |
|---|---|---|
| ゼロトラストセキュリティ | ネットワークの内外を問わず、全てのアクセスを検証し、脅威から保護する。 | Zscaler, Okta, Cloudflare |
| EDR (Endpoint Detection and Response) | PCやサーバーなど端末(エンドポイント)への脅威の侵入を検知し、迅速な対応を支援する。 | CrowdStrike, Cybereason, SentinelOne |
| クラウドセキュリティ (CSPM/CWPP) | クラウドサービスの設定ミスを検知・修正し、クラウド上のアプリケーションやデータを保護する。 | Prisma Cloud, Trend Cloud One |
| 脆弱性診断サービス | システムやアプリケーションに潜むセキュリティ上の弱点(脆弱性)を専門家が診断・報告する。 | GMOサイバーセキュリティ byイエラエ, Rapid7 |
ゼロトラストセキュリティ関連
ゼロトラストの実現を支援するソリューションは多岐にわたりますが、特にSASE(Secure Access Service Edge)やSSE(Security Service Edge)と呼ばれる、ネットワークとセキュリティの機能をクラウド上で統合提供するサービスが注目されています。
Zscaler
クラウドベースのセキュリティプラットフォームを提供するSASEのリーディングカンパニーです。ユーザーがどこから、どのアプリケーションにアクセスする場合でも、必ずZscalerのクラウドを経由させることで、一貫したセキュリティポリシーを適用します。主要なサービスとして、安全なインターネットアクセスを実現する「Zscaler Internet Access (ZIA)」と、社内アプリケーションへの安全なアクセスを提供する「Zscaler Private Access (ZPA)」があります。
参照:Zscaler Inc. 公式サイト
Okta
IDおよびアクセス管理(IAM)をクラウドサービスとして提供するIDaaS(Identity as a Service)の分野で高いシェアを誇ります。シングルサインオン(SSO)や多要素認証(MFA)を中核とし、ゼロトラストにおける「ID」の検証を強力に支援します。数千のアプリケーションと連携可能で、ユーザーの利便性を損なうことなく、セキュアなアクセス環境を構築できます。
参照:Okta, Inc. 公式サイト
Cloudflare
元々はCDN(コンテンツデリバリーネットワーク)で知られていましたが、現在ではDDoS攻撃対策、WAF(Web Application Firewall)からゼロトラストまで、包括的なセキュリティサービスを提供しています。「Cloudflare One」というプラットフォーム名で、ネットワーク機能とゼロトラストセキュリティ機能を統合したSASEソリューションを展開しています。
参照:Cloudflare, Inc. 公式サイト
EDR(エンドポイントでの検知と対応)
侵入後の脅威を検知し、対応を支援するEDRは、エンドポイントセキュリティの要です。AIや機械学習を活用した高度な検知能力が各社の特徴となっています。
CrowdStrike
「Falcon Platform」というクラウドネイティブなプラットフォームを提供しています。軽量なエージェントとクラウド上の膨大な脅威インテリジェンスを組み合わせることで、高度な攻撃もリアルタイムで検知・防御します。脅威ハンティングサービスも提供しており、専門家によるプロアクティブな脅威探索も強みです。
参照:CrowdStrike, Inc. 公式サイト
Cybereason
攻撃の全体像を「MalOp (Malicious Operation)」という単位で可視化することが最大の特徴です。個々のアラートではなく、一連の攻撃活動として関連付けて表示するため、セキュリティ担当者は攻撃の背景や影響範囲を直感的に理解し、迅速に対応できます。運用負荷の軽減に貢献します。
参照:Cybereason Inc. 公式サイト
SentinelOne
AIを活用した自律的な検知・対応を強みとしています。脅威を検知すると、人の手を介さずに自動で攻撃を停止させ、さらにはロールバック機能によって端末を攻撃前の状態に復旧させることも可能です。特にランサムウェア対策で高い評価を得ています。
参照:SentinelOne, Inc. 公式サイト
クラウドセキュリティ(CSPM/CWPP)
マルチクラウド環境の複雑なセキュリティ課題に対応するため、CSPMやCWPPといった機能を統合したCNAPP(Cloud Native Application Protection Platform)が主流になりつつあります。
Prisma Cloud (Palo Alto Networks)
セキュリティ大手のパロアルトネットワークスが提供する、代表的なCNAPPソリューションです。開発から本番環境まで、クラウドネイティブアプリケーションのライフサイクル全体を保護します。CSPM、CWPPに加え、IAMの権限を管理するCIEM、IaC(Infrastructure as Code)スキャンなど、非常に幅広い機能を単一のプラットフォームで提供します。
参照:Palo Alto Networks, Inc. 公式サイト
Trend Cloud One (Trend Micro)
トレンドマイクロが提供するクラウドセキュリティの統合プラットフォームです。ワークロードセキュリティ、コンテナセキュリティ、ファイルストレージセキュリティ、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、そしてCSPM(Conformity)といった複数のサービスで構成されており、必要な機能を組み合わせて利用できる柔軟性が特徴です。
参照:トレンドマイクロ株式会社 公式サイト
脆弱性診断サービス
自社でツールを運用するのではなく、専門家の知見を活用したい場合に有効です。
GMOサイバーセキュリティ byイエラエ
高い技術力を持つホワイトハッカーが在籍することで知られ、ツールでは発見が困難なビジネスロジックの脆弱性などを、専門家が手動で深く掘り下げて診断することに定評があります。Webアプリケーション診断やプラットフォーム診断、スマートフォンアプリ診断など、幅広い対象に対応しています。
参照:GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 公式サイト
Rapid7
脆弱性管理ツール「InsightVM」やペネトレーションテスト(侵入テスト)ツール「Metasploit」で世界的に有名ですが、専門家による脆弱性診断やペネトレーションテストサービスも提供しています。ツールと人の知見を組み合わせたハイブリッドなアプローチが強みです。
参照:Rapid7 LLC 公式サイト
まとめ
本記事では、DX推進におけるセキュリティの重要性から、具体的なリスク、実践的な対策、そして成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。
DXがビジネスの成長に不可欠な戦略である一方、それは同時に企業の攻撃対象領域を拡大させ、新たなセキュリティリスクを生み出す諸刃の剣でもあります。クラウドの設定ミス、テレワークの不備、巧妙化するランサムウェア攻撃、そしてサプライチェーンを狙った攻撃など、企業が向き合うべき脅威は多岐にわたります。
これらの脅威に対抗するためには、もはや従来の境界型防御の考え方では不十分です。「決して信頼せず、常に検証する」というゼロトラストの原則を基本に据え、全社的なセキュリティ方針のもと、組織的・技術的な対策を体系的に講じていく必要があります。
重要なのは、セキュリティを単なるIT部門の技術的な問題として捉えるのではなく、「事業継続を支える経営課題」として、経営層が主導して取り組むことです。そして、開発の初期段階からセキュリティを組み込む「セキュリティ・バイ・デザイン」の考え方を徹底し、人材不足などの課題に対しては、外部の専門サービスを賢く活用することも視野に入れましょう。
DXという変革のアクセルを踏むためには、セキュリティという強固なブレーキとハンドルが不可欠です。両者は対立するものではなく、ビジネスを安全に、かつ迅速に前進させるための「車の両輪」に他なりません。この記事が、皆様の企業における安全なDX推進の一助となれば幸いです。