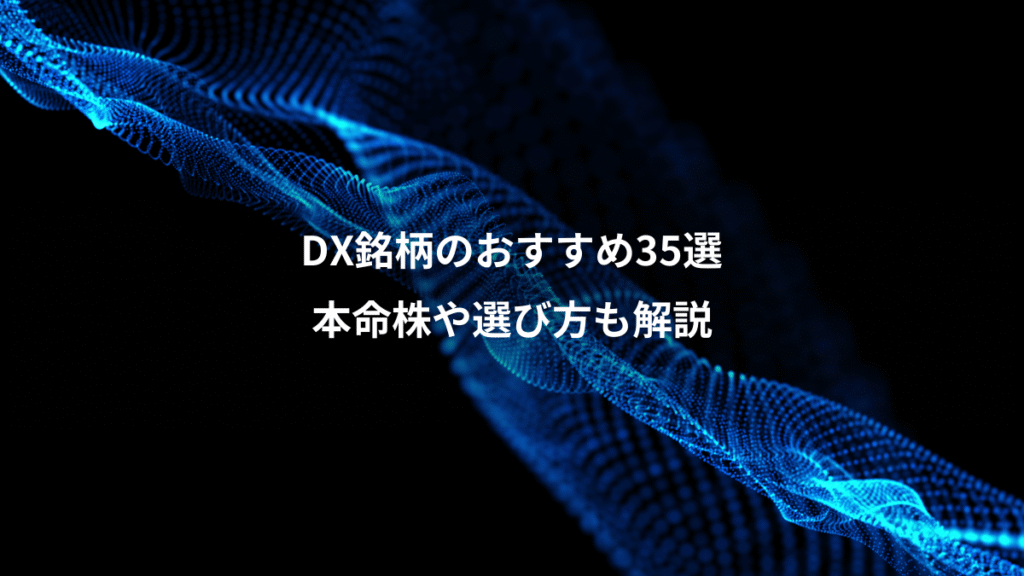目次
DX銘柄とは
近年、株式市場で大きな注目を集めている「DX銘柄」。ニュースや経済記事で頻繁に目にするものの、その正確な意味や、なぜこれほどまでに重要視されているのかを深く理解している方はまだ多くないかもしれません。DX銘柄への投資を検討する上で、まずはその根幹にある「DX」という概念を正しく理解することが不可欠です。
DX銘柄とは、一言でいえば「DX(デジタルトランスフォーメーション)に関連する事業を展開し、その成長が期待される企業の株式」を指します。これには、企業のDXを直接支援するITコンサルティング企業やシステム開発企業(SIer)、業務効率化を実現するSaaS(Software as a Service)提供企業などが含まれます。また、自社のビジネスモデルをデジタル技術によって革新し、新たな価値を創出している企業も広義のDX銘柄と見なされることがあります。
このセクションでは、DX銘柄の核心である「DXの定義」を深掘りし、しばしば混同されがちな「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違いを明確にすることで、DX銘柄の本質的な価値を理解するための土台を築きます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義
DX、すなわちデジタルトランスフォーメーションとは、単に新しいITツールを導入することや、紙の業務をデジタル化することだけを指すのではありません。経済産業省が2018年に公表した「DX推進ガイドライン」では、DXは次のように定義されています。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」
(参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」※旧「DX推進ガイドライン」)
この定義の重要なポイントは、「変革」という言葉が繰り返し使われている点です。DXの本質は、デジタル技術を「手段」として活用し、企業活動のあらゆる側面、すなわち「製品・サービス」「ビジネスモデル」「業務プロセス」「組織・企業文化」のすべてを根本から変革し、最終的に「競争上の優位性を確立する」ことにあります。
具体例を挙げてみましょう。
- 製造業の例:
- 従来のDX以前:熟練工の勘と経験に頼って生産ラインを調整していた。
- DXの実現後:工場内のあらゆる機器にIoTセンサーを設置し、稼働データをリアルタイムで収集・分析。AIが最適な生産計画を自動で立案し、予兆検知によって故障を未然に防ぐ「スマートファクトリー」を構築。これにより、生産性の向上だけでなく、熟練工の技術継承問題も解決し、新たな保守サービスというビジネスモデルを生み出す。
- 小売業の例:
- 従来のDX以前:実店舗とECサイトがそれぞれ独立して運営され、顧客情報や在庫情報がバラバラだった。
- DXの実現後:店舗とECのデータを完全に統合。顧客がECサイトで注文した商品を最寄りの店舗で受け取れたり、店舗で見た商品を後からECサイトで購入できる「オムニチャネル戦略」を展開。顧客一人ひとりの購買履歴に基づいたパーソナライズされた提案を行い、顧客体験を向上させることで、長期的なファンを獲得する。
このように、DXは単なる効率化にとどまらず、企業のあり方そのものを変え、新たな価値創造の源泉となる経営戦略なのです。そして、この壮大な「変革」を支える技術やサービスを提供する企業こそが、DX銘柄の中核をなしているのです。
デジタイゼーションやデジタライゼーションとの違い
DXという言葉を理解する上で、非常によく似た「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」という2つの言葉との違いを明確に区別することが極めて重要です。これらはDXに至るまでのステップと捉えることができ、この違いを理解することで、ある企業が真のDXを推進しているのか、それとも単なる部分的なデジタル化に留まっているのかを見極めるヒントになります。
以下に、3つの概念の違いを表で整理します。
| 段階 | 定義 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| デジタイゼーション(Digitization) | アナログ・物理データのデジタル化 | 情報の保存・検索性の向上、物理的制約からの解放 | ・紙の書類をスキャンしてPDF化する ・会議の音声を録音してデータ化する ・紙のアンケートをExcelに入力する |
| デジタライゼーション(Digitalization) | 個別の業務・製造プロセスのデジタル化 | 特定プロセスの効率化・自動化 | ・経費精算をクラウドシステムで行う ・顧客管理を紙の台帳からCRMツールへ移行する ・マーケティング活動にMAツールを導入する |
| DX(Digital Transformation) | 組織横断的なビジネスモデルや企業文化の変革 | 新たな価値創出と競争優位性の確立 | ・収集したデータを活用し、サブスクリプション型の新サービスを開発する ・AIによる需要予測に基づき、サプライチェーン全体を最適化する ・デジタルを前提とした組織構造や働き方に変革する |
デジタイゼーションは「アナログからデジタルへ」の変換であり、いわばDXの第一歩です。紙の情報を電子データにすることで、保管スペースが不要になったり、検索が容易になったりしますが、業務のやり方そのものは大きく変わりません。
デジタライゼーションは、その一歩先です。デジタル化された情報を活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で置き換えることを指します。例えば、紙とハンコで行っていた稟議プロセスをワークフローシステムに置き換えることで、承認時間の短縮やペーパーレス化といった効率化が実現します。これは大きな進歩ですが、あくまで「既存の業務をデジタルで効率化する」という範囲に留まります。
そして、DXはこれら2つを内包し、さらにその先を目指す概念です。単一の業務プロセスの改善に留まらず、デジタル技術の活用を前提として、「そもそもこのビジネスはどうあるべきか」「顧客にどのような新しい価値を提供できるか」という問いから出発し、ビジネスモデルや組織のあり方、さらには企業文化までをも変革しようとする、より経営戦略的な取り組みです。
投資家がDX銘柄を評価する際には、その企業が提供するサービスや、その企業自身の取り組みが、どの段階にあるのかを見極めることが重要です。真に競争優位性を確立できるのは、デジタイゼーションやデジタライゼーションの先にある、DXの領域で価値を提供できる企業であるといえるでしょう。
DX銘柄が注目される3つの理由
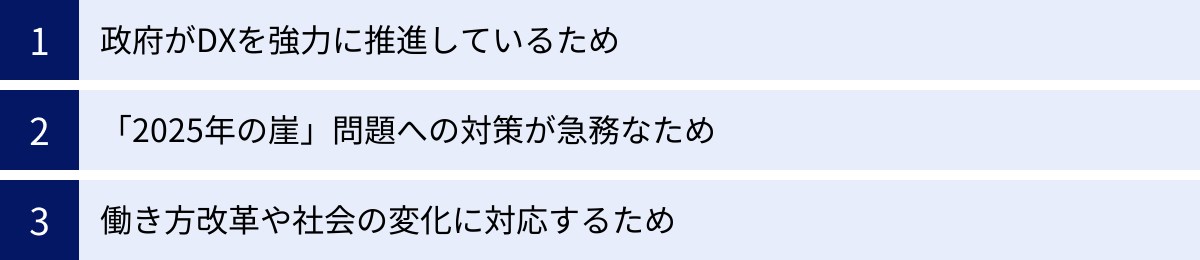
DX銘柄がなぜこれほどまでに株式市場で熱い視線を集めているのでしょうか。その背景には、単なる技術的なトレンドだけでなく、日本が直面する社会構造的な課題や、政府の強力な後押しが存在します。ここでは、DX銘柄が注目される本質的な理由を3つの側面から深く掘り下げて解説します。これらの理由を理解することは、DXというテーマが一時的なブームではなく、長期的な成長ストーリーであることを確信する上で不可欠です。
① 政府がDXを強力に推進しているため
DX銘柄への追い風となっている最大の要因の一つが、日本政府による国家戦略レベルでの強力な後押しです。政府は、日本の国際競争力の低下や生産性の伸び悩みといった課題を克服するための鍵としてDXを位置づけ、様々な政策を打ち出しています。
その象徴的な存在が、2021年9月に発足した「デジタル庁」です。デジタル庁は、国や地方自治体の情報システムを統括・標準化し、行政手続きのオンライン化などを通じて「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を推進する司令塔の役割を担っています。これにより、行政サービスの向上はもちろん、官公庁向けのシステム開発やサービス提供を行うIT企業に大きなビジネスチャンスが生まれています。
また、経済産業省は企業のDXを促進するため、具体的な指針や支援策を次々と打ち出しています。
- 「DX推進ガイドライン」(現「デジタルガバナンス・コード2.0」): 企業がDXに取り組む際の経営者のマインドセットや実行プロセスを具体的に示し、自主的な取り組みを促しています。
- 「DX認定制度」: 上記ガイドラインに沿って優れた取り組みを行う企業を国が認定する制度です。認定企業は、後述する税制優遇などの対象となります。
- 「DX投資促進税制」: DX認定を取得した企業が、DXに資する特定のデジタル関連投資を行った場合、最大で投資額の5%の税額控除、または30%の特別償却が受けられる制度です。これは企業にとってDX投資へのインセンティブとなり、結果としてDX関連サービスを提供する企業の売上を押し上げる効果が期待されます。(参照:経済産業省「DX投資促進税制」)
このように、政府が旗振り役となって法整備や税制優遇を進める「国策」であるという事実は、DX市場の成長に強力な下支えとなります。国策に売りなしという相場格言があるように、政府が推進するテーマは長期的に成長する可能性が高く、投資家にとって非常に魅力的な投資対象となるのです。
②「2025年の崖」問題への対策が急務なため
DX銘柄への需要を構造的に押し上げているもう一つの深刻な問題が、経済産業省が2018年の「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」です。これは、多くの日本企業が抱えるレガシーシステム(時代遅れの古い基幹システム)を刷新できずに放置した場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるという衝撃的な予測です。
「2025年の崖」を引き起こす主な要因は以下の通りです。
- システムの複雑化・ブラックボックス化: 長年の度重なる改修によってシステムが複雑怪奇になり、もはや全体像を把握できる技術者が社内にいない「ブラックボックス」状態に陥っている。
- IT人材の定年退職: これらのレガシーシステムを支えてきたベテランIT人材が2025年頃に一斉に定年を迎え、システムの維持・管理すら困難になる。
- サポート終了: 多くのシステムで利用されている基幹技術(SAP ERPなど)のサポートが2025年以降に順次終了し、セキュリティリスクが急増する。
この「崖」から落ちないためには、企業は既存のレガシーシステムを廃棄または刷新し、クラウドをベースとした最新のシステムに移行する必要があります。しかし、これは単なるシステムのリプレイス(置き換え)ではありません。新しいビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる、データ活用を前提としたシステムアーキテクチャへの変革、すなわちDXそのものが求められているのです。
多くの企業にとって、この課題はもはや「いつかやればいい」というレベルではなく、事業継続のために待ったなしで取り組まなければならない経営上の最重要課題となっています。この巨大な需要が、レガシーシステムの刷新を支援するSIerや、クラウド移行をサポートするコンサルティング企業、そして新たな業務基盤となるSaaSを提供する企業にとって、長期にわたる巨大なビジネスチャンスを生み出しています。「2025年の崖」は、日本のDX市場にとって最大の需要喚起要因であり、DX銘柄の成長ストーリーを語る上で欠かすことのできないキーワードなのです。
③ 働き方改革や社会の変化に対応するため
政府の推進や「2025年の崖」といったトップダウン、あるいは危機回避的な要因だけでなく、私たちの働き方や社会そのものの変化もDXを強力に後押ししています。
その最も大きなきっかけとなったのが、新型コロナウイルスのパンデミックです。感染拡大防止のため、多くの企業が半ば強制的にテレワーク(リモートワーク)への移行を迫られました。これにより、Web会議システム、ビジネスチャットツール、クラウドストレージ、電子契約サービスといった、時間や場所にとらわれない働き方を実現するためのデジタルツールが一気に普及しました。
当初は緊急避難的な措置でしたが、多くの企業や従業員がテレワークのメリット(通勤時間の削減、生産性の向上、ワークライフバランスの改善など)を実感したことで、これは不可逆的な流れとなりました。今や、多様な働き方に対応できる環境を整備しているかどうかが、優秀な人材を確保するための重要な要素となっています。この働き方の多様化を支える基盤こそがDXであり、関連するSaaS企業などが大きな恩恵を受けています。
さらに、日本が直面するより長期的な社会課題である少子高齢化と労働人口の減少も、DXの必要性を高めています。限られた人的リソースでこれまで以上の成果を出すためには、業務の徹底的な効率化と自動化が不可欠です。
- RPA(Robotic Process Automation)による定型業務の自動化
- AI-OCRによる紙の帳票のデータ化と入力作業の削減
- SaaSの導入による情報共有の円滑化と業務プロセスの標準化
これらのデジタル技術を活用することで、従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。これは、企業にとっては生産性向上に、従業員にとっては働きがいの向上に繋がります。
このように、働き方改革の推進や労働力不足という社会課題への対応は、DXが「攻め」の経営戦略であると同時に、「守り」の観点からも必須であることを示しています。この構造的な需要が、DX関連市場の継続的な拡大を支える強固な基盤となっているのです。
DX銘柄の今後の見通しと将来性
DX銘柄が注目される理由を理解した上で、次に投資家が気になるのは「このトレンドは今後も続くのか?」という点でしょう。結論から言えば、DXは一過性のブームではなく、今後も長期にわたって拡大を続ける巨大な成長市場であると予測されています。ここでは、市場規模のデータと、それを支える人材市場の動向から、DX銘柄の明るい見通しと将来性について解説します。
DX市場は今後も拡大していく
DX市場の将来性を客観的に示すものとして、複数の調査会社が市場規模の拡大予測を発表しています。
例えば、市場調査会社のIDC Japanが2023年11月に発表した「国内DX市場予測」によると、2022年の国内デジタルトランスフォーメーション(DX)関連支出額は2兆9,045億円でした。これが、2027年には6兆5,197億円に達すると予測されており、2022年から2027年までの年間平均成長率(CAGR)は17.5%にのぼる見込みです。これは、日本のGDP成長率と比較しても非常に高い成長率であり、DX市場がいかに有望であるかを示しています。(参照:IDC Japan株式会社プレスリリース 2023年11月21日)
この市場拡大の背景には、前述した政府の推進や「2025年の崖」問題への対応といった要因に加え、テクノロジー自体の進化が大きく関わっています。特に、近年急速に発展している生成AI(ジェネレーティブAI)の存在は、DXの可能性を飛躍的に広げるゲームチェンジャーとなり得ます。
- 業務効率化の加速: 文章作成、プログラミングコード生成、要約、翻訳などをAIが代行することで、知的生産活動の効率が劇的に向上する。
- 新たなサービス創出: 顧客との対話型AIアシスタントや、個々のユーザーに最適化されたコンテンツを自動生成するサービスなど、これまで不可能だった新しいビジネスモデルが生まれる。
- データ活用の深化: 専門家でなくても自然言語でデータ分析が可能になり、データドリブンな意思決定が組織の隅々まで浸透する。
このように、AIをはじめとするクラウド、IoT、5Gといった先端技術の進化と普及が相互に作用しあうことで、DXの適用範囲は今後ますます広がり、市場の成長をさらに加速させていくと考えられます。企業にとってDXは、もはや選択肢ではなく、生き残りのための必須条件となりつつあり、その支援を行うDX関連企業への需要は、今後も力強く伸びていくことが確実視されています。
IT・DX人材の不足は継続する
DX市場の拡大という「需要」の側面と表裏一体の関係にあるのが、それを担う「供給」側、すなわちIT・DX人材の深刻な不足です。この人材不足こそが、皮肉にも外部のDX支援企業、つまりDX銘柄にとっての大きな追い風となっています。
経済産業省が2019年に公表した「IT人材需給に関する調査」によると、IT人材の需要が今後も伸び続ける一方で、国内の労働人口は減少していくため、IT人材の不足はますます深刻化すると予測されています。この調査では、将来のIT需要の伸びを「高位」「中位」「低位」の3つのシナリオで試算していますが、需要が中程度に推移した場合でも、2030年には約45万人のIT人材が不足するとされています。需要の伸びが大きければ、不足数は約79万人にまで拡大する可能性も指摘されています。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)
特に、DXを主導できるような高度なスキルを持つ人材(データサイエンティスト、AIエンジニア、DXプロジェクトマネージャーなど)の不足はより深刻です。多くの企業がDXの必要性を認識していても、自社内にDXを推進できる人材がいないため、外部の専門家の力に頼らざるを得ないという状況が生まれています。
この構造的な人材不足は、以下のようなDX関連企業に大きなビジネスチャンスをもたらします。
- ITコンサルティングファーム: 企業のDX戦略立案から実行までをトータルで支援する。
- SIer(システムインテグレーター): レガシーシステムの刷新や新たなシステム基盤の構築を請け負う。
- SaaS企業: 導入が容易で専門知識が少なくても利用できる業務アプリケーションを提供する。
- IT人材派遣・育成企業: 不足するIT人材を企業に派遣したり、社員のリスキリング(学び直し)を支援する。
つまり、IT・DX人材の需給ギャップが拡大すればするほど、これらの外部支援企業への依存度は高まり、その市場価値も上昇していくという構図です。この人材不足は一朝一夕に解消できる問題ではないため、DX銘柄の成長を長期にわたって支える強力な追い風であり続けるでしょう。
DX銘柄の選び方4つのポイント
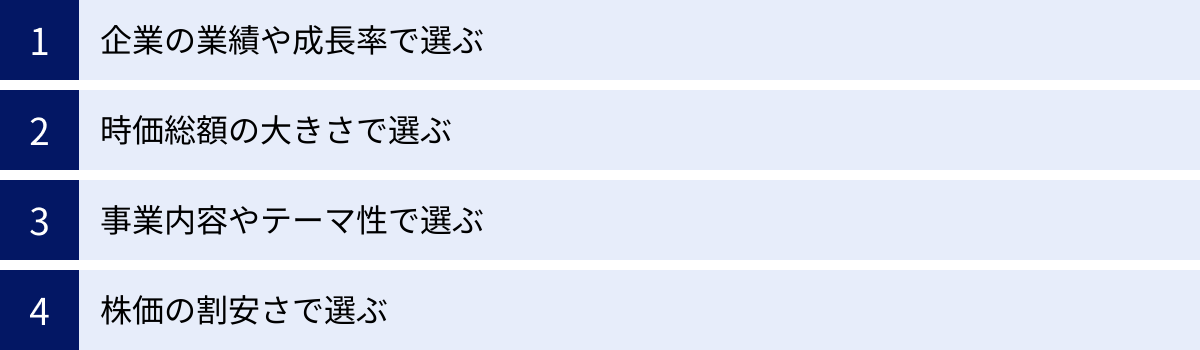
DX市場の将来性が有望であることは間違いありませんが、関連する企業は多岐にわたり、どの銘柄に投資すればよいか迷ってしまうかもしれません。有望な市場だからといって、どの銘柄でも成功するわけではありません。ここでは、数あるDX銘柄の中から、将来性のある優良企業を見つけ出すための4つの実践的なポイントを解説します。これらの視点を組み合わせることで、より精度の高い銘柄選定が可能になります。
① 企業の業績や成長率で選ぶ
株式投資の基本中の基本ですが、DX銘柄を選ぶ上でも最も重要なのが企業の業績、特にその「成長性」です。DXという成長市場の恩恵をしっかりと受けて、それが売上や利益という形で表れているかを確認する必要があります。
注目すべき具体的な財務指標は以下の通りです。
- 売上高成長率: 企業の事業規模がどれくらいの勢いで拡大しているかを示す最も基本的な指標です。特にDX関連のSaaS企業などでは、前年同期比で20%以上の高い成長率を維持している企業も珍しくありません。一過性の特需ではなく、過去数年間にわたって継続的に高い成長を続けているかがポイントです。
- 営業利益率: 売上高に対して、本業でどれだけ効率的に利益を稼げているかを示す指標です。利益率が高い企業は、価格競争力があったり、独自の強みを持つ製品・サービスを提供していたりする可能性が高く、質の高い成長をしていると判断できます。
- 営業利益成長率: 売上だけでなく、利益もしっかりと伸びているかを確認します。売上だけが伸びて利益が伴わない「赤字先行投資型」の企業も成長フェーズでは存在しますが、投資家としては、将来的に黒字化し、利益が拡大していく明確な道筋が見えるかどうかが重要になります。
これらの情報は、企業が四半期ごとに発表する「決算短信」や「決算説明会資料」で確認できます。特に決算説明会資料には、事業ごとの業績や今後の見通しがグラフなどを用いて分かりやすくまとめられていることが多いので、必ず目を通すようにしましょう。過去3〜5年程度の業績推移を見て、安定して右肩上がりの成長を続けている企業は、有望な投資対象候補となります。
② 時価総額の大きさで選ぶ
DX銘柄と一括りにいっても、その企業規模は様々です。企業の規模を表す「時価総額(株価 × 発行済株式数)」に注目することで、自分の投資スタイルやリスク許容度に合った銘柄を選ぶことができます。時価総額は大きく「大型株」と「中小型株」に分けられます。
将来の値上がりが期待できる中小型株
時価総額が比較的小さい(数百億円〜数千億円程度)中小型株は、高い成長ポテンシャルを秘めているのが最大の魅力です。事業がまだ成長途上であるため、DX市場の拡大の波に乗って業績が急拡大すれば、それに伴って株価が数倍になる、いわゆる「テンバガー(10倍株)」となる可能性も秘めています。ニッチな分野で独自の強みを持つ企業や、革新的なサービスで市場を切り開こうとしている企業が多く、大きなリターンを狙いたい投資家にとっては非常に魅力的です。
一方で、デメリットも存在します。事業基盤がまだ盤石でないため、景気の変動や競合の出現など、外部環境の変化によって業績が大きくぶれやすい傾向があります。また、株価の変動率(ボラティリティ)も高いため、ハイリスク・ハイリターンな投資といえます。中小型株に投資する際は、短期的な株価の動きに一喜一憂せず、その企業の長期的な成長ストーリーを信じてじっくりと保有する姿勢が求められます。
安定成長が見込める大型株
時価総額が1兆円を超えるような大型株は、事業基盤の安定性が最大の魅力です。長年にわたって業界のトップランナーとして君臨してきた企業が多く、豊富な資金力、幅広い顧客基盤、高いブランド力を持っています。NTTデータグループや日立製作所、富士通といった大手SIerがこれに該当します。
これらの企業は、官公庁や大企業向けの大型案件を手掛けることが多く、景気が多少変動しても業績が安定しています。また、配当金を安定的に出していたり、株主優待制度があったりする企業も多く、株価の値上がり益(キャピタルゲイン)だけでなく、配当金などのインカムゲインも期待できるのが特徴です。
デメリットとしては、企業規模がすでに大きいため、中小型株のように株価が短期間で数倍になるような急成長は期待しにくい点が挙げられます。そのため、大きなリスクを取らずに、安定的に資産を増やしていきたいと考える投資初心者や安定志向の投資家に向いています。
自分の投資目標に合わせて、これら大型株と中小型株をバランス良くポートフォリオに組み入れる「分散投資」も有効な戦略です。
③ 事業内容やテーマ性で選ぶ
DXと一口に言っても、その関わり方は企業によって様々です。企業の事業内容や、どのようなテーマでDXに貢献しているかに注目することで、より深く企業を理解し、自分の興味や知識に合った銘柄を選ぶことができます。
DX推進を支援する企業
これはDX銘柄の王道ともいえるカテゴリで、他社のDXを直接的にサポートする事業を展開する企業群です。
- SaaS(Software as a Service)企業: クラウド経由でソフトウェアを提供する企業。会計ソフトの「freee」や「マネーフォワード」、名刺管理の「Sansan」などが代表例です。月額課金制のストック型ビジネスモデルであるため、顧客が増えるほど収益が安定的に積み上がり、高い成長性と収益性を両立しやすいのが特徴です。
- SIer(システムインテグレーター): 顧客企業の課題に応じて、システムの企画、設計、開発、運用・保守までを請け負う企業。NTTデータグループや野村総合研究所などが含まれます。特に「2025年の崖」問題で注目されるレガシーシステムの刷新など、大規模なプロジェクトに強みを持ちます。
- コンサルティングファーム: 企業の経営課題としてDX戦略の立案を支援する企業。ベイカレント・コンサルティングなどが代表的です。最上流の戦略策定から関わるため、高い専門性が求められます。
特定領域のデジタル化に特化した企業
総合的なDX支援ではなく、特定の業界や分野に特化してデジタル化ソリューションを提供する企業も非常に有望です。
- 医療(MedTech): エムスリーやJMDCのように、医療情報のプラットフォームを提供したり、医療データの活用を支援する企業。高齢化社会を背景に、医療の効率化は喫緊の課題であり、大きな成長が見込まれます。
- 金融(FinTech): 決済サービスや資産管理アプリなど、金融とITを融合させたサービスを提供する企業。
- 不動産(PropTech): VR内見や電子契約、不動産情報プラットフォームなど、不動産業界のDXを推進する企業。
- 建設(ConTech): AIによる設計支援やドローンによる測量など、建設業界の生産性向上に貢献する企業。
これらの業界特化型企業は、その分野の深い専門知識や業界慣行を理解しているため、汎用的なツールでは解決できない課題に対応できる強みがあります。高い参入障壁を築きやすく、ニッチな市場で高いシェアを握る「隠れた優良企業」が見つかる可能性もあります。
④ 株価の割安さで選ぶ
将来性のある企業の株を、できるだけ安く買いたいと考えるのは当然のことです。株価がその企業の実力(収益力)に対して割安か割高かを判断するための指標として、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)がよく用いられます。
- PER(株価収益率) = 時価総額 ÷ 純利益 または 株価 ÷ 一株あたり利益(EPS)
- 会社の利益に対して株価が何倍まで買われているかを示す指標。一般的に、PERが低いほど株価は割安とされます。
- PBR(株価純資産倍率) = 時価総額 ÷ 純資産 または 株価 ÷ 一株あたり純資産(BPS)
- 会社の純資産に対して株価が何倍まで買われているかを示す指標。PBRが1倍を下回ると、株価が解散価値よりも安い状態とされ、割安と判断されることがあります。
ただし、DX銘柄に投資する際には注意が必要です。DX銘柄の多くは、将来の高い成長性が株価に織り込まれているため、PERが高くなる傾向があります。例えば、一般的な成熟企業のPERが15倍程度なのに対し、高い成長性を持つSaaS企業のPERが100倍を超えることも珍しくありません。
そのため、単に「PERが高いから割高だ」と判断するのは早計です。重要なのは、以下の2つの視点です。
- 同業他社との比較: 同じような事業内容の競合企業と比較して、PERが極端に高すぎないかを確認します。
- その企業の過去のPER水準との比較: その企業の過去のPER推移を見て、現在の水準が平均的な範囲にあるか、それとも過熱気味かを確認します。
将来の利益成長率を考慮したPEGレシオ(= PER ÷ 利益成長率)という指標も参考になります。PEGレシオが1倍を下回ると、成長率に比べて株価が割安であると判断されることがあります。これらの指標を総合的に活用し、成長期待が過度に株価に織り込まれていないかを見極めることが、賢い投資に繋がります。
【カテゴリ別】DX銘柄おすすめ35選
ここからは、これまで解説してきた選び方のポイントを踏まえ、具体的なDX関連銘柄を「本命・大型株」「中核・中小型株」「注目・出遅れ株」の3つのカテゴリに分けて35銘柄ご紹介します。各企業の事業内容や特徴を簡潔にまとめていますので、ご自身の投資スタイルや興味に合った銘柄を見つけるための参考にしてください。
※本記事で紹介する銘柄は、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終決定はご自身の判断と責任において行ってください。証券コードは東京証券取引所のものです。
【本命・大型株】安定成長が期待できるDX銘柄10選
まずは、安定した事業基盤と豊富な実績を持つ大型株からご紹介します。時価総額が大きく、日本のDX市場を牽引する存在です。大きなリスクを取らずに、DXの成長の恩恵を受けたいと考える投資家におすすめです。
| 銘柄名【証券コード】 | 事業概要 | 特徴・注目ポイント |
|---|---|---|
| NTTデータグループ【9613】 | 国内最大手のSIer。官公庁や金融機関向けに強み。 | グローバル展開を加速。大規模システム構築の実績豊富で、社会インフラとしての役割を担う。 |
| 大塚商会【4768】 | 独立系のSIer。中小企業向けに複合機やITソリューションを提供。 | 「たのめーる」が有名。中小企業のDX化をワンストップで支援する「伴走型」のビジネスモデルに強み。 |
| SCSK【9719】 | 住友商事系のSIer。製造・流通・金融など幅広い業種に対応。 | ITサービス全般を網羅。クラウドやセキュリティ分野にも注力し、安定した顧客基盤を持つ。 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ【4739】 | 伊藤忠商事系のSIer。通信、放送、製造、金融など多岐にわたる。 | 特定ベンダーに依存しないマルチベンダー対応が強み。5Gやデータサイエンス分野も強化。 |
| 日本電信電話(NTT)【9432】 | 日本最大の通信事業者。NTTデータやNTTドコモを傘下に持つ。 | 通信インフラに加え、IOWN構想を掲げ次世代のICT基盤構築を推進。高配当・累進配当も魅力。 |
| 野村総合研究所【4307】 | 日本を代表するシンクタンク兼SIer。コンサルティングとITソリューションを両輪で展開。 | 金融・流通業界に圧倒的な強み。上流のコンサルからシステム開発・運用まで一気通貫で提供。 |
| 日立製作所【6501】 | 総合電機メーカーからDX企業へ変革。デジタル事業「Lumada」が中核。 | 製造業としての知見を活かしたOT×ITが強み。インフラ、エネルギー、金融など幅広い分野でDXを推進。 |
| 富士通【6702】 | 大手総合ITベンダー。官公庁や医療・ヘルスケア分野に強み。 | ITサービス分野で国内トップクラスのシェア。スーパーコンピュータ「富岳」開発など高い技術力を持つ。 |
| TIS【3626】 | 独立系のSIer大手。クレジットカードなど決済関連システムに強み。 | キャッシュレス化の進展が追い風。クラウドやAIを活用したDX支援サービスを幅広く展開。 |
| オービックビジネスコンサルタント【4733】 | 中小企業向け業務ソフトウェア「奉行シリーズ」で高いシェア。 | クラウド版「奉行クラウド」への移行が順調に進展。安定したストック収益と高い利益率が魅力。 |
① NTTデータグループ【9613】
国内最大のシステムインテグレーター(SIer)であり、日本のDXを語る上で欠かせない存在です。特に官公庁、金融機関、電力・ガスといった社会インフラを担う大規模なシステム構築に圧倒的な強みを持ちます。近年は海外事業のM&Aにも積極的で、グローバルでの存在感を高めています。盤石な顧客基盤と長年の実績に裏打ちされた信頼性は、安定志向の投資家にとって大きな魅力です。
② 大塚商会【4768】
主に中小企業をターゲットに、IT機器の販売からシステム導入、サポートまでをワンストップで提供する独立系のSIerです。オフィス用品の通販サービス「たのめーる」でも知られています。全国に広がる営業網と、顧客に寄り添う「伴走型」のサポート体制が強み。日本の企業の99%以上を占める中小企業のDX化は巨大な潜在市場であり、その受け皿として中心的な役割を担う企業です。
③ SCSK【9719】
住友商事グループの中核IT企業。特定の業界に偏らず、製造、流通、金融、通信など幅広い業種の顧客に対して、コンサルティングからシステム開発、運用、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)までフルラインナップのITサービスを提供しています。安定した事業ポートフォリオと健全な財務体質が特徴です。
④ 伊藤忠テクノソリューションズ【4739】
伊藤忠商事グループのSIerで、通称CTCとして知られています。特定メーカーの製品に縛られない「マルチベンダー」であることが強みで、顧客のニーズに合わせて最適な製品や技術を組み合わせたソリューションを提供できます。通信キャリアやデータセンター事業者向けの高度な技術力に定評があり、5Gやクラウド、AIといった先端技術分野への取り組みも積極的です。
⑤ 日本電信電話(NTT)【9432】
NTTドコモ、NTT東日本・西日本、そして前述のNTTデータグループなどを傘下に持つ、日本最大の通信事業グループです。安定した通信事業の収益基盤を持ちながら、次世代の光技術を用いた通信基盤構想「IOWN(アイオン)」を推進しており、未来のDX社会を根底から支える存在として期待されています。連続増配を続ける高配当株としても知られ、インカムゲインを重視する投資家からの人気も高い銘柄です。
⑥ 野村総合研究所【4307】
「未来創発」を掲げる日本最大級のシンクタンクであり、トップクラスのSIerでもあります。最大の特徴は、「コンサルティング」と「ITソリューション」を両輪で展開している点です。企業の経営課題の分析・提言といった最上流工程から、それを解決するための具体的なシステムの設計・開発・運用までを一気通貫で手掛けられることが他社にはない強みです。特に金融業界や流通業界向けのシステムでは圧倒的なシェアを誇ります。
⑦ 日立製作所【6501】
かつての総合電機メーカーのイメージから脱却し、デジタル技術を活用して社会イノベーション事業を推進するDX企業へと大きく変貌を遂げています。その中核となるのが、顧客のデータから新たな価値を創出するソリューション群「Lumada(ルマーダ)」です。長年培ってきた製造業としての知見(OT: Operational Technology)とITを融合させたソリューションは、特にスマートファクトリーやインフラ保守の分野で強みを発揮します。
⑧ 富士通【6702】
日立と並ぶ日本の大手総合ITベンダーです。官公庁、医療、文教といった公共分野に強固な地盤を持つほか、スーパーコンピュータ「富岳」の開発で知られるように、世界トップクラスの技術力を有しています。現在はITサービス事業に経営資源を集中させる構造改革を進めており、クラウドやAI、セキュリティといった成長分野での収益拡大を目指しています。
⑨ TIS【3626】
独立系のSIer大手で、特にクレジットカードの基幹システムをはじめとする決済関連分野で高いシェアを誇ります。キャッシュレス化の進展は同社にとって強力な追い風です。決済分野で培ったノウハウを活かし、ペイメント関連のSaaSや、企業のDXを包括的に支援するサービスを拡大しています。安定した収益基盤と成長性を兼ね備えた企業です。
⑩ オービックビジネスコンサルタント【4733】
「勘定奉行」で知られる、中小企業向けの基幹業務用ソフトウェア(ERP)のトップメーカーです。長年にわたり日本の会計ソフト市場をリードしてきましたが、近年は主力製品をクラウドサービス「奉行クラウド」へと移行させる戦略が成功し、安定したストック収益を積み上げています。非常に高い営業利益率を誇る高収益企業としても知られています。
【中核・中小型株】高い成長性が見込めるDX銘柄15選
次に、時価総額は大型株に及ばないものの、特定の分野で高い競争力を持ち、将来の大きな成長が期待される中核・中小型株をご紹介します。株価の変動リスクはありますが、それを上回るリターンが期待できる銘柄群です。
| 銘柄名【証券コード】 | 事業概要 | 特徴・注目ポイント |
|---|---|---|
| チェンジホールディングス【3962】 | 「NEW-ITトランスフォーメーション事業」を展開。ふるさと納税サイトも運営。 | 地方自治体や企業のDX支援、AI・ビッグデータ活用に強み。「ふるさとチョイス」とのシナジーも。 |
| インターネットイニシアティブ【3774】 | 日本初の商用インターネット接続事業者。法人向けネットワークサービスが主力。 | 高品質なネットワーク技術が基盤。MVNO(格安SIM)事業も好調で、クラウドやセキュリティも強い。 |
| メディカル・データ・ビジョン【3902】 | 国内最大規模の診療データベースを構築・活用。製薬会社や研究機関に提供。 | 医療ビッグデータのプラットフォーマー。データ利活用による創薬支援や臨床研究の効率化に貢献。 |
| フリー【4478】 | 中小企業・個人事業主向けクラウド会計ソフト「freee会計」を提供。 | 会計・人事労務を統合したプラットフォーム戦略が強み。高い成長率を維持するSaaSの代表格。 |
| マネーフォワード【3994】 | 個人向け家計簿アプリと法人向けクラウド会計ソフト「MFクラウド」を展開。 | FinTech領域のリーディングカンパニー。会計・請求書・経費精算などバックオフィス業務を幅広くカバー。 |
| JMDC【4483】 | 健康保険組合から提供されるレセプト(診療報酬明細書)データを匿名加工し、データベース化。 | 製薬会社や保険会社向けにデータを提供。医療費の適正化など社会課題解決にも貢献する。 |
| JTOWER【4485】 | 通信インフラシェアリング事業を展開。携帯キャリアの基地局などを共用化。 | 5G普及に不可欠なインフラを効率的に提供。通信事業者の設備投資負担を軽減し、需要は旺盛。 |
| エムスリー【2413】 | 医療従事者向け専門サイト「m3.com」を運営。医薬品情報提供などが主力。 | 30万人以上の医師会員という強固なプラットフォームを持つ。製薬会社のマーケティングDXを支援。 |
| オロ【3983】 | クラウドERP「ZAC」とデジタルトランスフォーメーション支援事業の2本柱。 | 広告・IT業界などに特化した「ZAC」が好調。安定したストック収益とDX支援の成長性を併せ持つ。 |
| UUUM【3990】 | YouTuberなどクリエイターのマネジメントや動画マーケティング支援。 | インフルエンサーマーケティング市場の拡大が追い風。クリエイターエコノミーのDXを推進。 |
| テラスカイ【3915】 | Salesforceの導入・活用支援に特化したクラウドインテグレーター。 | Salesforce市場の拡大と共に成長。高い専門性と技術力で業界トップクラスの実績を誇る。 |
| メルカリ【4385】 | フリマアプリ「メルカリ」を運営。決済サービス「メルペイ」も展開。 | CtoC市場のプラットフォーマー。膨大な利用データとAI活用によるサービス改善が強み。 |
| ユーザーローカル【3984】 | ビッグデータ解析やAI技術を活用したマーケティングツールを提供。 | Webサイト分析「User Insight」やチャットボットが主力。高い技術力と利益率が特徴。 |
| プラスアルファ・コンサルティング【4071】 | テキストマイニングや人事データ分析など、データ活用SaaSを提供。 | 「見える化エンジン」や「タレントパレット」が主力。企業の「知」の活用を支援し高成長。 |
| Sansan【4443】 | 法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」で圧倒的シェア。 | 名刺を起点に企業のネットワークをデータ化。「Bill One」など請求書分野にも事業を拡大中。 |
① チェンジホールディングス【3962】
地方自治体や企業のDXを支援する「NEW-ITトランスフォーメーション事業」が主力。特に、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」の運営会社を子会社化したことで、全国の自治体との強固なリレーションを築いています。このネットワークを活かし、自治体向けのDXソリューションを展開できるのが大きな強みです。
② インターネットイニシアティブ【3774】
日本で最初にインターネット接続サービスを開始した老舗。法人向けの高品質なネットワーク構築やクラウドサービス、セキュリティ対策に定評があります。個人向けには「IIJmio」ブランドで格安SIMを提供。堅実な技術力に裏打ちされた安定性と、5GやIoT時代に不可欠な通信インフラ企業としての成長性を兼ね備えています。
③ メディカル・データ・ビジョン【3902】
全国の病院から収集した大規模な診療データベースを保有し、製薬会社や研究機関、保険会社などに匿名加工したデータを提供する、医療ビッグデータのプラットフォーマーです。新薬開発の効率化や、治療効果の分析など、データに基づく医療(EBM)の推進に不可欠な存在となっています。
④ フリー【4478】
「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに、中小企業や個人事業主向けのクラウド会計ソフト「freee会計」を提供。会計だけでなく、人事労務や会社設立支援など、スモールビジネスのバックオフィス業務を統合的にサポートするプラットフォーム戦略で急成長を遂げています。
⑤ マネーフォワード【3994】
個人向けの資産管理・家計簿アプリ「マネーフォワード ME」で高い知名度を誇りますが、近年は法人向けのバックオフィスSaaS「マネーフォワード クラウド」シリーズが成長を牽引しています。会計、請求書、経費精算、給与計算などを網羅し、企業のDXを包括的に支援。freeeと並ぶSaaS市場の代表格です。
⑥ JMDC【4483】
健康保険組合が保有するレセプト(診療報酬明細書)や健康診断のデータを収集・匿名加工し、独自のデータベースを構築。このデータを製薬会社や保険会社、研究機関に提供しています。高齢化による医療費の増大という社会課題に対し、データ活用による医療の効率化・適正化で貢献する企業です。
⑦ JTOWER【4485】
携帯電話の基地局や通信アンテナなどのインフラを、複数の通信キャリアで共有(シェアリング)する事業を展開。5Gの普及には、従来よりも多くの基地局を高密度に設置する必要がありますが、同社のサービスを利用することで、通信キャリアは設備投資を抑えつつ効率的にエリアを拡大できます。5G時代の「電波塔の大家さん」として、成長が期待されるユニークな企業です。
⑧ エムスリー【2413】
日本の医師の9割以上にあたる30万人超が登録する医療従事者専門サイト「m3.com」を運営。この強固なプラットフォームを基盤に、製薬会社の医薬品情報提供(MR活動)をデジタルで支援するサービスが収益の柱です。コロナ禍で対面でのMR活動が制限されたことも追い風となり、製薬業界のマーケティングDXをリードする存在です。
⑨ オロ【3983】
広告、IT、コンサルティングといった知的サービス業に特化したクラウドERP「ZAC」が主力事業。プロジェクトごとの採算管理などを効率化し、企業の生産性向上に貢献します。安定した収益が見込めるSaaS事業と、企業のWeb戦略などを支援するデジタルトランスフォーメーション支援事業の2本柱で、バランスの取れた成長を続けています。
⑩ UUUM【3990】
HIKAKINなど人気YouTuberが多数所属する、クリエイターサポート事業の最大手。クリエイターのマネジメントや、企業とのタイアップ動画の企画・制作などを手掛けています。個人の影響力が価値を持つ「クリエイターエコノミー」の拡大を背景に、インフルエンサーマーケティング市場の成長を取り込むことが期待されます。
⑪ テラスカイ【3915】
世界的なCRM(顧客関係管理)プラットフォームである「Salesforce」の導入・カスタマイズ支援に特化したクラウドインテグレーターのパイオニアです。Salesforce市場の拡大と軌を一にして成長を続けており、その高い専門性と技術力は業界でも高く評価されています。企業の営業DXに欠かせない存在です。
⑫ メルカリ【4385】
日本最大のフリマアプリ「メルカリ」を運営。二次流通(リユース)市場という巨大なマーケットをデジタル技術で創造した、まさにDXの体現者ともいえる企業です。スマホ決済サービス「メルペイ」との連携強化や、膨大な取引データとAIを活用したサービスの改善・新規事業展開が今後の成長の鍵となります。
⑬ ユーザーローカル【3984】
ビッグデータ解析とAI技術に強みを持つテクノロジー企業。Webサイトのアクセス解析ツール「User Insight」や、問い合わせ対応を自動化するAIチャットボット「SupportChatbot」などをSaaSとして提供しています。技術力の高さを背景とした高い利益率が特徴で、企業のマーケティングDXや業務効率化を支援します。
⑭ プラスアルファ・コンサルティング【4071】
「科学的な意思決定を支援する」ことを目指し、データ分析プラットフォームをSaaSで提供。顧客の声などを分析するテキストマイニングツール「見える化エンジン」や、人事データを活用して人材育成や配置を最適化する「タレントパレット」が主力製品です。企業のデータドリブン経営への移行を後押しし、高成長を続けています。
⑮ Sansan【4443】
法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」で市場の8割以上のシェアを握るトップ企業。名刺をスキャンするだけで、社内に人脈情報をデータとして蓄積・共有できるサービスは、営業DXの基盤として多くの企業に導入されています。近年は、請求書のオンライン受領・管理サービス「Bill One」にも注力し、第二の収益の柱として急成長しています。
【注目・出遅れ株】今後の伸びしろに期待したいDX銘柄10選
最後に、現時点では株価が市場の成長期待に比べて伸び悩んでいたり、調整局面にあったりするものの、事業内容や将来性から見て、今後の再評価が期待される「注目・出遅れ株」をご紹介します。宝探しのような面白さがあるカテゴリです。
| 銘柄名【証券コード】 | 事業概要 | 特徴・注目ポイント |
|---|---|---|
| セレス【3696】 | ポイントサイト「モッピー」を運営。フィンテック・暗号資産関連事業も展開。 | ポイントメディアを基盤に、モバイルペイメントや暗号資産交換所など多角化を推進。 |
| SHIFT【3697】 | ソフトウェアの品質保証・テスト事業が主力。 | 「売れる品質」を保証する独自の手法で急成長。IT開発の上流から関わり、コンサルも手掛ける。 |
| AI inside【4488】 | AI-OCR「DX Suite」で市場をリード。手書き文字を高精度で読み取りデータ化。 | ノーコードでAIを作成・運用できるプラットフォームも提供。AIの社会実装を推進する。 |
| Appier Group【4180】 | AIを活用したマーケティングソリューションをSaaSで提供。 | 顧客獲得からエンゲージメント、コンバージョンまでをAIで最適化。アジア市場に強み。 |
| カオナビ【4435】 | クラウド人材管理システム「カオナビ」を提供。社員の顔写真が並ぶUIが特徴。 | タレントマネジメントシステムのパイオニア。従業員の個性や能力を可視化し、戦略的人事を支援。 |
| ラクスル【4384】 | 印刷・広告のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を運営。 | 印刷会社の非稼働時間を活用する独自のビジネスモデル。物流やテレビCMのプラットフォームにも展開。 |
| カナミックネットワーク【3939】 | 医療・介護分野に特化した情報共有プラットフォームを提供。 | 超高齢社会において、地域包括ケアシステムの実現に不可欠なICT基盤を提供。安定成長が続く。 |
| ベイカレント・コンサルティング【6532】 | 独立系の総合コンサルティングファーム。DXコンサルに強み。 | 特定の製品に縛られず、中立的な立場で戦略立案から実行まで支援。旺盛なDX需要を背景に高成長。 |
| Vコマース【2491】 | アフィリエイト(成果報酬型広告)サービスで国内最大手。 | Yahoo!ショッピングとの連携が強み。EC市場の拡大と共に安定成長。CRM関連SaaSも展開。 |
| アステリア【3853】 | 企業データ連携ソフト「ASTERIA Warp」で高いシェア。 | 異なるシステム間のデータをノンコーディングで繋ぐミドルウェア。企業のDX基盤として需要が堅調。 |
① セレス【3696】
ポイントサイト「モッピー」を運営するモバイルサービス事業が主力ですが、そこで得た顧客基盤やノウハウを活かし、フィンテック分野へ積極的に投資しています。子会社を通じて暗号資産交換所を運営するなど、次世代の金融サービスへの展開に注目が集まります。
② SHIFT【3697】
ソフトウェアのバグを見つける「テスト・品質保証」というニッチな市場で圧倒的な成長を遂げている企業です。開発の上流工程から品質に関与することで、手戻りをなくし開発全体の生産性を上げるコンサルティングも手掛けており、DX時代のソフトウェア開発に欠かせない存在となりつつあります。
③ AI inside【4488】
手書き文字を高精度で認識するAI-OCR「DX Suite」で一躍有名になりました。紙の帳票を扱うことが多い官公庁や金融機関などで広く導入されています。現在は、誰でも簡単にAIを開発・運用できるプラットフォームの提供にも力を入れており、AIの民主化を目指しています。
④ Appier Group【4180】
台湾で創業され、東証マザーズ(現グロース)に上場したユニークな経歴を持つ企業です。AIを用いて、企業のデジタルマーケティング活動(新規顧客獲得、顧客育成、販売促進など)を自動で最適化するソリューションをSaaSとして提供。アジア太平洋地域を中心にグローバルで事業を拡大しています。
⑤ カオナビ【4435】
社員の顔写真を見ながら、スキルや評価、経歴などを一元管理できるクラウド人材管理システム「カオナビ」で、タレントマネジメント市場を牽引しています。従業員のエンゲージメント向上や、データに基づいた適材適所の人員配置など、戦略的な人事(HR Tech)の需要を取り込みます。
⑥ ラクスル【4384】
全国の印刷会社の非稼働時間と、印刷物を発注したいユーザーをインターネット上でマッチングさせるプラットフォーム「ラクスル」を運営。「産業の仕組みを変え、世界をより良くする」というビジョンのもと、同様のモデルを物流(ハコベル)や広告(ノバセル)分野にも展開しています。
⑦ カナミックネットワーク【3939】
医療・介護分野に特化した、地域包括ケアシステムを実現するための情報共有プラットフォームを提供。医師、看護師、ケアマネージャー、介護士などが、クラウド上で患者・利用者の情報をリアルタイムに共有できる仕組みは、多職種連携が不可欠な日本の医療・介護現場のDXを支えています。
⑧ ベイカレント・コンサルティング【6532】
特定のIT製品や資本系列に属さない独立系の総合コンサルティングファームです。企業のDX戦略立案から、実行支援、定着化までをワンストップで手掛けられるのが強み。あらゆる業界でDXコンサルティングの需要が旺盛なことを背景に、高い成長率を維持しています。
⑨ Vコマース【2491】
旧バリューコマース。国内最大級のアフィリエイト(成果報酬型広告)プラットフォーム「バリューコマース アフィリエイト」を運営しています。EC市場の拡大は同社にとって追い風です。また、顧客情報管理ツールなど、EC事業者向けのマーケティングDXを支援するSaaSも手掛けています。
⑩ アステリア【3853】
企業内に散在する様々なシステム(基幹システム、CRM、Excelなど)のデータを、プログラミングの知識なしで簡単に連携できるEAI(データ連携)ソフトウェア「ASTERIA Warp」で国内トップシェアを誇ります。DX推進においてデータ活用は必須であり、そのための「データの血管」となる重要な役割を担っています。
DX銘柄に投資する際の3つの注意点
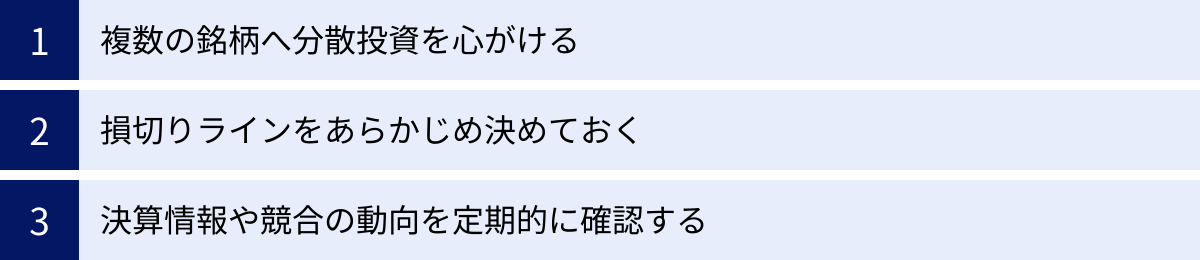
DX銘柄は高い成長性が期待できる一方で、投資にはリスクも伴います。特に成長期待が高い銘柄は株価の変動も大きくなりがちです。長期的に安定したリターンを目指すためには、以下の3つの注意点を常に意識し、冷静な判断を心がけることが重要です。
① 複数の銘柄へ分散投資を心がける
これはDX銘柄に限らず、株式投資の基本原則ですが、特に重要です。「卵は一つのカゴに盛るな」という格言の通り、特定の銘柄一つに資金を集中させるのは非常に危険です。どんなに有望に見える企業でも、予期せぬ業績の下方修正、不祥事の発生、強力な競合の出現など、株価が急落するリスクは常に存在します。
DX銘柄に投資する際は、以下のような観点で分散を意識しましょう。
- 事業内容による分散: 例えば、SIer、SaaS、コンサルティングといった異なるビジネスモデルの企業に分散する。これにより、特定のビジネスモデルに逆風が吹いた際のリスクを低減できます。
- 時価総額による分散: 安定性の高い「大型株」と、高い成長性が期待できる「中小型株」を組み合わせる。これにより、ポートフォリオ全体のリスクとリターンのバランスを取ることができます。
- 業界特化型銘柄の分散: 医療DX、金融DX、不動産DXなど、異なる業界に特化した銘柄を組み合わせる。特定の業界の景気変動の影響を和らげることができます。
複数の銘柄に資金を分散させることで、一つの銘柄が下落しても、他の銘柄の上昇でカバーできる可能性が高まります。 ポートフォリオ全体での安定した成長を目指す上で、分散投資は最も基本的なリスク管理手法です。
② 損切りラインをあらかじめ決めておく
人間は心理的に、自分が買った銘柄の価値が下がると「いつか戻るはずだ」と期待してしまい、売るに売れなくなる「塩漬け」状態に陥りがちです。損失を確定させる痛みから逃れたいという感情が、結果的により大きな損失を招くことは少なくありません。
こうした感情的な判断を避けるために、株を購入する前に「損切りライン」を機械的に決めておくことが極めて重要です。損切りラインとは、「ここまで株価が下がったら、理由はどうあれ無条件で売却する」という自分なりのルールのことです。
損切りラインの設定方法には、いくつかの考え方があります。
- 購入価格からの下落率で決める: 「購入価格から10%下落したら売る」など、シンプルなルールです。
- テクニカル指標で決める: 「移動平均線を下回ったら売る」「前回の安値を更新したら売る」など、チャート上の節目を利用する方法です。
どちらの方法が良いというわけではありません。大切なのは、自分自身が納得でき、かつ、機械的に実行できるルールを持つことです。損切りは、損失を最小限に抑え、大切な投資資金を守り、次のより良い投資機会に資金を振り向けるための必要不可欠な戦略です。一時的な損失は辛いものですが、長期的に市場で生き残るためには、損切りをためらってはいけません。
③ 決算情報や競合の動向を定期的に確認する
DX市場は技術革新のスピードが速く、市場環境も目まぐるしく変化します。そのため、一度投資したら終わり(バイ・アンド・ホールド)という姿勢ではなく、定期的に投資先の情報をアップデートし続ける必要があります。
最低限チェックすべき情報は以下の通りです。
- 四半期ごとの決算発表: 企業は3ヶ月ごとに決算を発表します。「決算短信」や「決算説明会資料」には、最新の業績、事業の進捗状況、今後の見通しなどが詳しく記載されています。当初の成長ストーリー通りに進んでいるか、想定外の事態は起きていないかを確認しましょう。特に、売上高や利益の成長率が鈍化していないかは重要なチェックポイントです。
- 競合他社の動向: 投資先の競合企業が、どのような新製品・サービスを投入してきたか、どのような戦略を打ち出しているかを把握することも重要です。競合の動きによっては、自社の投資先の優位性が揺らぐ可能性もあります。
- 業界全体のニュースやトレンド: DXに関連する新しい技術(例:生成AIの進化)や、法改正、政府の新たな方針など、マクロな環境変化にも注意を払いましょう。これらの変化が、投資先のビジネスに追い風となるか、逆風となるかを見極める必要があります。
これらの情報を継続的に収集し、投資を継続する根拠が揺らいでいないかを定期的に見直すことが、DX銘柄のような成長株投資で成功するための鍵となります。
DXとあわせて注目したい関連投資テーマ5選
DXは単独で存在する概念ではなく、様々な最先端技術が相互に関連しあって成り立っています。DX銘柄への投資を考える際には、その構成要素となる技術や、DXと密接に関わる周辺領域にも目を向けることで、より多角的な視点から投資機会を見出すことができます。ここでは、DXとあわせて注目したい5つの関連投資テーマをご紹介します。
① AI(人工知能)
AIは、もはやDXの中核技術と言っても過言ではありません。膨大なデータを分析して将来を予測したり、業務プロセスを自動化・最適化したり、新たな顧客体験を創出したりと、DXのあらゆる場面でAIが活用されています。特に近年は生成AIの登場により、その重要性は飛躍的に高まっています。 AI開発に必要な半導体メーカー、AIアルゴリズムを開発する企業、AIを活用したSaaSを提供する企業など、関連する銘柄は多岐にわたります。DXが進めば進むほど、AI関連企業への需要も増加していくという密接な関係にあります。
② サイバーセキュリティ
企業のデジタル化が進むことは、裏を返せば、サイバー攻撃の標的となる領域が広がることを意味します。顧客情報や機密情報といった企業の重要なデジタル資産を、ランサムウェアや不正アクセスといった脅威から守るサイバーセキュリティ対策は、DX推進と表裏一体の必須要件です。テレワークの普及により、社外から社内システムへアクセスする機会が増えたことも、セキュリティリスクを増大させています。ファイアウォールやウイルス対策ソフト、不正侵入検知システム(IDS/IPS)、ゼロトラストセキュリティ関連のサービスを提供する企業は、DX市場の拡大と共に着実な成長が見込まれる分野です。
③ クラウドコンピューティング
クラウドは、DXを実現するための土台となるITインフラです。自社でサーバーを保有・管理する従来のオンプレミス型とは異なり、インターネット経由で必要な時に必要な分だけコンピューティングリソース(サーバー、ストレージ、ソフトウェアなど)を利用できるクラウドは、ビジネスの俊敏性、柔軟性、拡張性を高める上で不可欠です。SaaS、PaaS、IaaSといったクラウドサービスを提供する企業はもちろん、企業のオンプレミス環境からクラウドへの移行を支援するSIerやコンサルティング企業も、このテーマの関連銘柄となります。
④ IoT(モノのインターネット)
IoTは、工場内の機械、自動車、家電、社会インフラなど、あらゆる「モノ」にセンサーを取り付け、インターネットに接続することで、それらの状態をリアルタイムにデータとして収集する技術です。IoTは、これまでデータ化されていなかったフィジカル(物理)な世界の情報をデジタル化する役割を担い、DXの「目」や「耳」として機能します。収集された膨大なデータは、AIによって分析され、生産性の向上(スマートファクトリー)、故障の予知保全、新たなサービスの創出などに繋がります。IoTデバイスや通信モジュール、センサー、データ解析プラットフォームなどを手掛ける企業が関連銘柄です。
⑤ 5G(第5世代移動通信システム)
5Gは「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という3つの特徴を持つ次世代の通信規格です。この5Gの普及は、DXの可能性を大きく広げます。例えば、多数のIoTデバイスが生成する膨大なデータを遅延なくクラウドに送信したり、高精細な映像をリアルタイムで伝送して遠隔操作を行ったり、自動運転を実現したりするためには、5Gの通信インフラが不可欠です。通信キャリアはもちろん、基地局などのインフラ設備メーカー、5G対応のデバイスやモジュールを開発する企業などが、このテーマの中心となります。5Gは、高度なDX社会を実現するための「神経網」ともいえる重要な技術です。
DX銘柄の取引におすすめの証券会社3選
DX銘柄への投資を始めるには、まず証券会社の口座を開設する必要があります。数ある証券会社の中から、手数料の安さ、ツールの使いやすさ、情報量の豊富さといった観点で、特に初心者から中上級者まで幅広くおすすめできるネット証券3社をご紹介します。
| 証券会社名 | 特徴 | 手数料(国内株式・現物) | 取扱商品 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 業界トップクラスの口座数。IPO取扱数も豊富。TポイントやPontaポイント、Vポイントが貯まる・使える。 | ゼロ革命:国内株式の売買手数料が無料(※要適用条件) | 国内株、米国株、投資信託、NISA、iDeCoなど非常に豊富 |
| 楽天証券 | 楽天経済圏との連携が強力。楽天ポイントでの投資が可能。取引ツール「マーケットスピードII」が人気。 | ゼロコース:国内株式(現物・信用)の取引手数料が無料(※要適用条件) | 国内株、米国株、投資信託、NISA、iDeCoなど豊富 |
| マネックス証券 | 米国株の取扱銘柄数が業界最多水準。高機能な銘柄分析ツール「銘柄スカウター」が無料で利用可能。 | 主要ネット証券と同水準の手数料体系。 | 国内株、米国株、中国株、投資信託、NISA、iDeCoなど |
(※手数料やサービス内容は2024年5月時点のものです。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。)
① SBI証券
ネット証券業界の最大手であり、口座開設数No.1を誇る証券会社です。最大の魅力は、条件を満たすことで国内株式の売買手数料が無料になる「ゼロ革命」です。また、新規公開株(IPO)の取扱銘柄数が非常に多く、IPO投資にチャレンジしたい方にもおすすめです。三井住友カードでの投信積立(クレカ積立)ではVポイントが貯まるなど、ポイントサービスも充実しており、総合力で非常に優れています。(参照:株式会社SBI証券 公式サイト)
② 楽天証券
SBI証券と並ぶ人気を誇るネット証券です。楽天カードでのクレカ積立や、楽天キャッシュでの投信積立で楽天ポイントが貯まり、そのポイントを使って投資もできるなど、楽天経済圏を頻繁に利用する方にとってはメリットが大きいです。プロのトレーダーも愛用する高機能な取引ツール「マーケットスピードII」や、日経新聞の記事が読める「日経テレコン(楽天証券版)」が無料で利用できるなど、情報収集ツールが充実している点も強みです。(参照:楽天証券株式会社 公式サイト)
③ マネックス証券
特に米国株投資に力を入れている証券会社で、取扱銘柄数はネット証券の中でもトップクラスです。しかし、国内株投資家にとっても大きな魅力があります。それが、無料で使える銘柄分析ツール「銘柄スカウター」です。過去10年以上の業績推移や、詳細な財務データ、PER・PBRの推移などがグラフで視覚的に分かりやすく表示され、企業分析を行う上で非常に強力な武器になります。DX銘柄のような成長株をじっくり分析して選びたい方には特におすすめです。(参照:マネックス証券株式会社 公式サイト)
これらの証券会社はそれぞれに特徴があります。ご自身の投資スタイルや、普段利用するサービスなどとの相性を考えて、最適な証券会社を選んでみましょう。複数の口座を開設して、用途に応じて使い分けるのも賢い方法です。
まとめ
本記事では、株式市場で大きな注目を集める「DX銘柄」について、その定義から注目される背景、将来性、具体的な銘柄選びのポイント、そして投資する上での注意点まで、網羅的に解説してきました。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単なるIT化ではなく、デジタル技術を駆使してビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創造する経営戦略です。そしてDX銘柄とは、この壮大な変革を支援する、あるいは自ら実践することで成長する企業の株式を指します。
DX銘柄が長期的な成長テーマである理由は明確です。
- 政府が「国策」として強力に推進していること
- 「2025年の崖」という待ったなしの課題解決に不可欠であること
- 働き方改革や労働人口減少といった社会構造の変化に対応するために必須であること
これらの強力な追い風を受け、DX市場は今後も高い成長率で拡大していくことが予測されています。
有望なDX銘柄を見つけ出すためには、以下の4つのポイントを総合的に判断することが重要です。
- 企業の業績や成長率:継続的に売上・利益が伸びているか。
- 時価総額の大きさ:安定の大型株か、成長性の中小型株か。
- 事業内容やテーマ性:どのようなDX支援を行っているか。
- 株価の割安さ:成長期待が過度に織り込まれていないか。
本記事でご紹介した35銘柄も参考に、ぜひご自身の投資スタイルに合った企業を探してみてください。
ただし、高い成長性が期待できる一方で、DX銘柄への投資にはリスクも伴います。大切な資産を守りながらリターンを追求するためには、「複数銘柄への分散投資」「損切りラインの徹底」「継続的な情報収集」という3つの注意点を必ず守り、冷静な投資判断を心がけましょう。
DXは、これからの日本社会と企業の成長を左右する、避けては通れない大きな潮流です。この記事が、皆様のDX銘柄への理解を深め、未来を切り拓く企業への投資を検討する一助となれば幸いです。