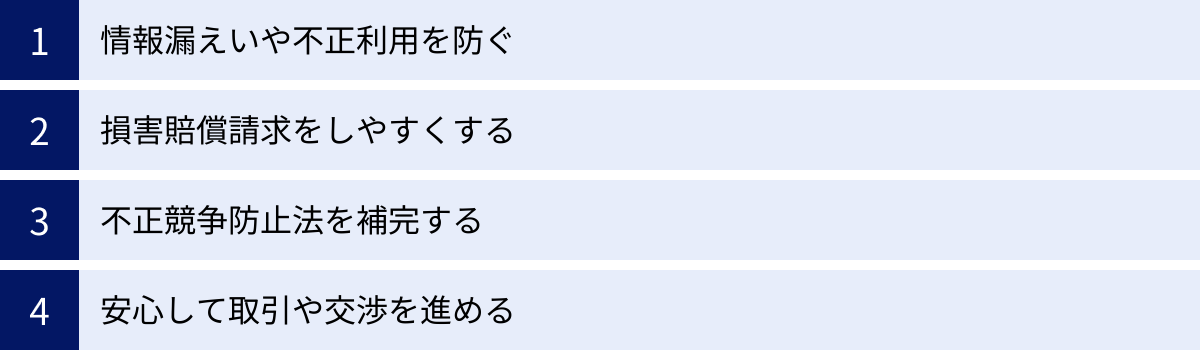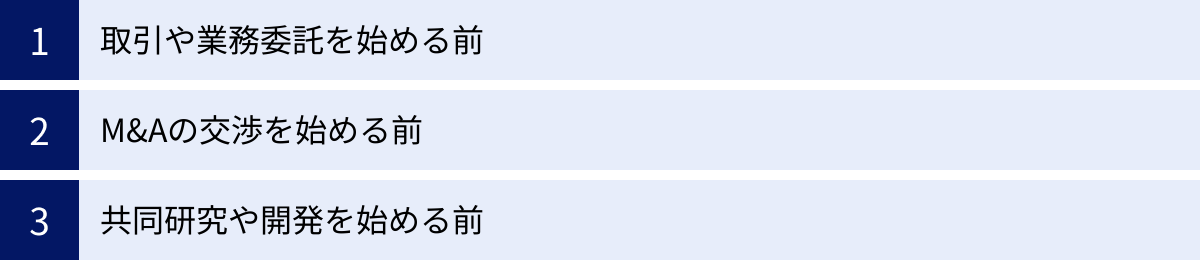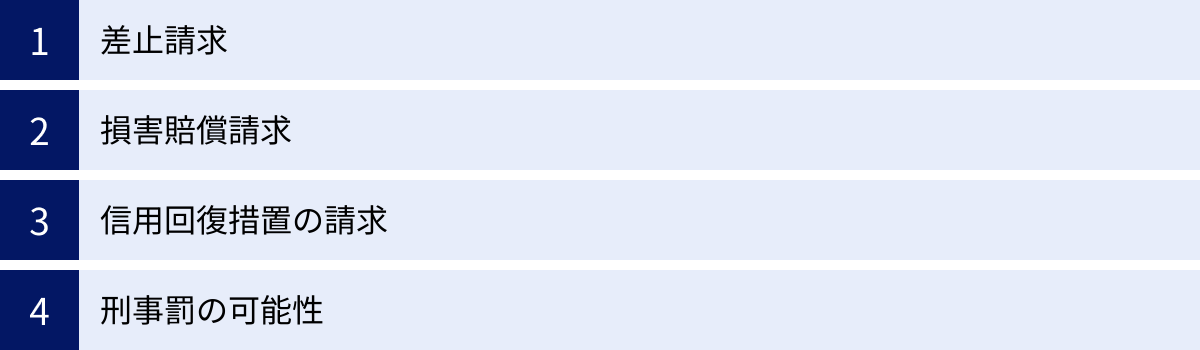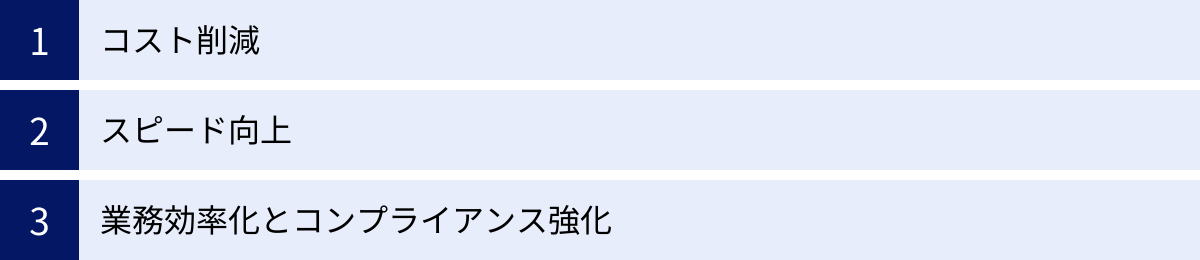ビジネスの世界では、企業の競争力の源泉となる様々な「情報」が日々やり取りされています。新商品の開発情報、独自の技術ノウハウ、顧客リスト、財務データなど、これらの情報が外部に漏洩したり、不正に利用されたりすれば、企業は計り知れない損害を被る可能性があります。こうしたリスクから企業の貴重な情報を守るために不可欠なのが、秘密保持契約書(NDA)です。
秘密保持契約書(NDA)は、取引や交渉に先立って、自社の秘密情報を相手方に開示する際に締結する法的な約束事です。この契約を締結することで、相手方に対して秘密情報を守る義務を課し、万が一の漏洩や不正利用があった場合には、法的な対抗措置を取ることが可能になります。
しかし、一言で秘密保持契約書といっても、その内容は多岐にわたります。雛形(テンプレート)をそのまま利用した結果、自社の状況に合わず、いざという時に役に立たないというケースも少なくありません。重要なのは、自社のビジネスの実態に合わせて、契約書の各条項を適切に設定・確認することです。
この記事では、秘密保持契約書(NDA)の基本的な知識から、その目的と必要性、締結するタイミング、種類、そして最も重要な記載事項について、初心者にも分かりやすく徹底解説します。さらに、契約書を作成・締結する際に陥りがちな10の注意点や、違反された場合の対処法、電子契約の有効性まで、実務で役立つ知識を網羅的にご紹介します。この記事を読めば、NDAの本質を理解し、自社の貴重な情報を守るための第一歩を踏み出せるはずです。
目次
秘密保持契約書(NDA)とは
秘密保持契約書(NDA)は、企業間の取引や交渉の過程で、一方または双方が相手方に開示する営業上・技術上の秘密情報を、第三者に漏洩したり、契約で定めた目的以外に使用したりすることを禁止するために締結される契約書です。ビジネスシーンにおいては、企業の競争力を維持し、安心して情報交換を行うための「信頼のインフラ」ともいえる重要な役割を担っています。
例えば、新しいシステムの開発を外部の会社に委託する場合を考えてみましょう。発注側は、自社の業務フローや既存システムの詳細といった内部情報を、開発会社に開示しなければなりません。これらの情報が競合他社に漏れてしまえば、ビジネス上の優位性を失う可能性があります。このような事態を防ぐため、業務委託契約を結ぶ前、あるいは交渉の初期段階で秘密保持契約書を締結し、開示する情報が外部に漏れないように法的な縛りをかけるのです。
この契約の最大の特徴は、当事者間で「何が秘密情報か」を定義し、それに対する取り扱いルールを具体的に定める点にあります。これにより、情報漏洩や不正利用に対する心理的な抑止力が働くとともに、万が一契約違反が発生した際には、契約内容を根拠として損害賠償請求や差止請求といった法的措置を講じやすくなります。
現代のビジネスでは、協業、M&A、業務委託、共同研究開発など、他社と連携する機会がますます増えています。それに伴い、自社の重要な情報を外部に開示する場面も増加しており、秘密保持契約書の重要性はかつてないほど高まっています。NDAの締結は、もはや特殊なことではなく、ビジネスを円滑かつ安全に進めるための基本的な手続きであると認識することが重要です。
秘密保持契約書とNDAの違い
「秘密保持契約書」という言葉と並んで、「NDA」という言葉を耳にすることが非常に多いでしょう。この二つの言葉の違いについて疑問に思うかもしれませんが、結論から言うと、両者は基本的に同じものを指します。
NDAとは、「Non-Disclosure Agreement」の頭文字を取った略称です。日本語に直訳すると「非開示契約」となり、これが「秘密保持契約書」にあたります。法律の専門家や外資系企業との取引が多い業界では、NDAという呼称が一般的に使われています。
また、場合によっては「機密保持契約書(CA:Confidentiality Agreement)」と呼ばれることもあります。これもNDAとほぼ同義で使われることが多く、契約書のタイトルが「秘密保持契約書」「NDA」「機密保持契約書」のいずれであっても、その法的な性質や目的、記載されるべき内容は本質的に変わりません。
したがって、これらの名称の違いに戸惑う必要はありません。重要なのは、契約書のタイトルではなく、その契約書にどのような内容が記載されているかです。自社を守るために必要な条項がすべて盛り込まれているか、相手方から提示された契約書が自社にとって不利な内容になっていないか、その中身をしっかりと確認することが何よりも大切です。本記事では、以降、一般的な呼称である「秘密保持契約書(NDA)」として解説を進めていきます。
秘密保持契約書(NDA)の目的と必要性
NDAを締結するのは、単なる形式的な手続きではありません。そこには、企業の存続と成長に直結する、明確で重要な目的が存在します。なぜNDAが必要不可欠なのか、その具体的な目的と必要性を4つの側面から深く掘り下げていきましょう。
情報漏えいや不正利用を防ぐ
NDAの最も根源的かつ重要な目的は、企業の生命線ともいえる機密情報の漏えいや不正利用を未然に防ぐことです。企業が持つ情報には、以下のようなものが含まれます。
- 技術情報: 新製品の設計図、独自の製造ノウハウ、ソフトウェアのソースコード、研究開発データなど
- 営業情報: 顧客リスト、販売戦略、価格設定、仕入れ先情報、マーケティング計画など
- 財務情報: 未公開の決算情報、資金調達計画、M&Aに関する情報など
- 人事情報: 従業員の個人情報、人事評価データなど
これらの情報は、長年の投資と努力によって蓄積された企業の貴重な資産であり、競争力の源泉です。もし、これらの情報が競合他社に漏れたり、取引先によって別の目的で勝手に利用されたりすれば、市場での優位性を失い、甚大な経済的損失を被る可能性があります。
NDAを締結することで、情報を受領する側に法的な「秘密保持義務」を課すことができます。これにより、情報を取り扱う相手方の従業員一人ひとりに対しても、情報の重要性を認識させ、厳重な管理を促す効果が期待できます。つまり、NDAは情報漏えいに対する強力な心理的抑止力として機能するのです。契約書という形で明確なルールを定めることで、「この情報は絶対に漏らしてはならない」という意識を当事者間で共有し、偶発的な漏えいや安易な不正利用のリスクを大幅に低減させます。
損害賠償請求をしやすくする
万が一、NDAを締結したにもかかわらず、相手方の過失や故意によって情報が漏えいしてしまった場合、NDAはその後の法的手続きにおいて極めて重要な役割を果たします。
もしNDAを締結していなければ、情報漏えいによって損害が発生したとしても、その責任を相手方に追及することは非常に困難です。なぜなら、そもそも相手方に情報を秘密として保持する法的な義務があったことを立証するところから始めなければならないからです。さらに、どの情報が秘密であったのか、どのような損害が発生したのか、その損害と情報漏えいの間に因果関係があるのか、といった点をすべて自社で立証する必要があり、そのハードルは極めて高いと言わざるを得ません。
一方で、NDAを締結していれば、状況は大きく変わります。NDAには通常、契約に違反した場合のペナルティとして「損害賠償」に関する条項が盛り込まれています。これにより、相手方の情報漏えいが「契約違反」にあたることを明確に主張でき、損害賠償請求の法的な根拠とすることができます。
さらに、実務上は、情報漏えいによる損害額を正確に算定することが難しいケースが多いため、NDAにあらかじめ「違約金」や「損害賠償額の予定」に関する条項を設けておくこともあります。例えば、「本契約の違反があった場合、違反者は相手方に対し、違約金として金〇〇円を支払う」といった定めです。このような条項があれば、実際の損害額を立証する手間を省き、迅速に一定額の賠償を求めることが可能になります。このように、NDAは有事の際に自社の権利を守り、損害を回復するための強力な武器となるのです。
不正競争防止法を補完する
日本の法律には、企業の営業上の秘密を守るための「不正競争防止法」という法律があります。この法律は、一定の要件を満たす「営業秘密」を法的に保護し、不正な手段で営業秘密を取得、使用、開示する行為を禁止しています。
不正競争防止法で「営業秘密」として保護されるためには、その情報が以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
- 秘密管理性: その情報が秘密として管理されていること。
- 有用性: 事業活動に役立つ技術上または営業上の情報であること。
- 非公知性: 一般的に知られていないこと。
この中で特に重要となるのが「秘密管理性」です。裁判などで営業秘密性が争われた場合、「企業がその情報を秘密として管理しようとする意思」が客観的に認識できる状態でなければ、秘密管理性が認められない可能性があります。具体的には、情報に「マル秘」スタンプを押す、アクセスできる従業員を限定する、施錠されたキャビネットで保管するといった物理的・技術的な管理措置が挙げられます。
そして、NDAを締結することは、この「秘密管理性」を証明するための極めて有効な手段となります。取引先に情報を開示する際にNDAを結ぶという行為は、企業がその情報を外部に対して「これは秘密情報です」と明確に意思表示し、法的な保護を求めていることの強力な証拠となるのです。
逆に言えば、重要な情報を開示する際にNDAを締結していなかった場合、裁判所から「そもそもその情報を秘密として厳格に管理するつもりがなかったのではないか」と判断され、不正競争防止法による保護を受けられなくなるリスクが高まります。したがって、NDAは不正競争防止法の保護をより確実なものにするための補完的な役割を担っているといえます。
安心して取引や交渉を進める
法的な側面だけでなく、NDAはビジネス上の円滑なコミュニケーションを促進するという重要な役割も持っています。
M&Aの交渉、業務提携の検討、共同研究開発の企画など、大きなビジネスを動かす際には、当事者間で腹を割って深く議論する必要があります。そのためには、自社の強みや弱み、将来の事業計画といった、通常は外部に明かさないような機密性の高い情報を開示せざるを得ない場面が多々あります。
このような状況でNDAがなければ、情報開示側は「この情報を話してしまって大丈夫だろうか」「悪用されないだろうか」といった不安を常に抱えることになり、どうしても開示する情報が限定的になったり、議論が深まらなかったりする可能性があります。
NDAを締結することは、いわば「ここから先は、お互いに信頼し合ってオープンに話をしましょう」という双方の意思表示です。法的な安全性が担保されることで、当事者は情報漏えいのリスクを心配することなく、安心して必要な情報を開示し、本質的な議論に集中できます。これにより、交渉や検討がスムーズに進み、より建設的で質の高いパートナーシップを築くための土台が作られるのです。NDAは、単なるリスク管理のツールではなく、ポジティブなビジネス関係を構築するための潤滑油としても機能するといえるでしょう。
秘密保持契約書(NDA)を締結するタイミング
NDAの重要性は理解できても、「具体的にいつ、どのタイミングで締結すればよいのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。NDAは、秘密情報を相手方に開示する必要が生じた時点で、その開示に先立って締結するのが大原則です。タイミングを誤ると、最も重要な情報が保護されないまま漏洩するリスクがあるため、慎重な判断が求められます。ここでは、ビジネスシーンでNDAを締結すべき代表的なタイミングを3つ紹介します。
取引や業務委託を始める前
外部の企業や個人に業務を委託する際には、NDAの締結が不可欠です。特に、システムの開発、ウェブサイトの制作、デザイン業務、マーケティング代行、コンサルティングなどを依頼するケースが典型例です。
これらの業務を委託する場合、正式な契約を結ぶ前の「検討段階」や「見積もり依頼段階」で、自社の内部情報を開示する必要が出てくることがよくあります。
例えば、
- システム開発: 既存システムの仕様や課題、業務フローの詳細を発注先候補に伝えなければ、正確な見積もりや提案は得られません。
- デザイン制作: 新商品のコンセプトやターゲット層、ブランド戦略といった情報をデザイナーに共有しなければ、意図に沿ったデザインは生まれません。
- マーケティング代行: 自社の売上データ、顧客属性、過去のキャンペーン結果などを開示しなければ、効果的な戦略立案は不可能です。
このように、正式な業務委託契約を締結するよりも前に、機密情報の開示が必要になることが非常に多いのです。そのため、NDAは、個別の業務委託契約書とは別に、交渉を開始する初期段階で締結しておくのが最も安全です。
もちろん、業務委託契約書の中に秘密保持に関する条項を盛り込むことも可能です。しかし、その場合、契約締結前に開示された情報が保護の対象外となってしまうリスクがあります。したがって、「少しでも機密情報に触れる可能性がある話をする前」にNDAを締結するという意識を持つことが、リスク管理の観点から極めて重要です。これにより、複数の候補先と交渉する場合でも、各社と同様の条件で秘密保持義務を課すことができ、安心して選定プロセスを進められます。
M&Aの交渉を始める前
M&A(企業の合併・買収)は、企業間で取り扱われる情報の中でも、最も機密性が高く、かつ広範囲な情報がやり取りされる取引です。買い手企業は、対象企業の価値を正しく評価するために、財務諸表はもちろんのこと、事業計画、技術情報、知的財産、主要な契約内容、人事情報、法務リスクなど、企業の根幹に関わるあらゆる情報を精査します(このプロセスをデューデリジェンス(DD)と呼びます)。
これらの情報がもし交渉の途中で外部に漏洩すれば、対象企業の従業員や取引先に動揺が広がり、事業価値が大きく損なわれる可能性があります。また、交渉が不成立に終わった場合、買い手候補だった企業が、その過程で得た情報を自社の事業に不正に利用するリスクも考えられます。
そのため、M&Aのプロセスにおいては、本格的な交渉を開始する前の極めて早い段階でNDAを締結することが絶対的なルールとなっています。一般的には、初期的な接触を経て、両社が交渉を進める意思を確認した段階で、まずNDAを締結します。その後、より詳細な情報交換を行うための基本合意書(LOI)を結び、本格的なデューデリジェンスへと進んでいく流れとなります。
M&Aで用いられるNDAは、一般的な業務委託のNDAよりも厳格な内容になることが多いです。例えば、秘密情報の定義が広範であったり、情報の利用目的が「本件取引の検討、評価及び交渉」に厳しく限定されたり、契約の有効期間や秘密保持義務の存続期間が長めに設定されたりします。M&AにおけるNDAは、取引の成否を左右しかねない、極めて重要な第一歩と位置づけられています。
共同研究や開発を始める前
複数の企業や大学、研究機関などが協力して、新しい技術や製品を生み出す共同研究・開発プロジェクトにおいても、NDAの締結は必須です。
共同研究・開発では、各当事者がそれぞれ保有する独自の技術、ノウハウ、研究データ、アイデアといった知的財産を持ち寄ることから始まります。これらの情報は、各組織にとって競争力の核となる部分であり、厳重に保護されなければなりません。
プロジェクトを開始する前にNDAを締結することで、お互いが安心して自社の技術情報を開示し、円滑な協力関係を築くことができます。NDAがない状態では、互いに手の内を明かすことをためらい、研究開発がスムーズに進まない可能性があります。
共同研究・開発におけるNDAで特に重要となるのが、以下の2点です。
- 知的財産権の帰属: このプロジェクトを通じて新たに生まれた発明や考案、著作物などの知的財産権が、誰に、どのような割合で帰属するのかをあらかじめ明確にしておく必要があります。この点はNDAに含めることもあれば、別途「共同研究開発契約」で詳細に定めることもあります。
- 双務契約: 共同研究・開発では、一方だけが情報を開示するのではなく、双方が情報を開示し合うのが一般的です。そのため、後述する「双務契約」形式のNDAを締結し、両当事者が対等な秘密保持義務を負うように設定する必要があります。
NDAは、オープンイノベーションを推進するための基盤ともいえます。法的な保護という土台があるからこそ、組織の壁を越えた知の融合が促進され、画期的なイノベーションが生まれるのです。
秘密保持契約書(NDA)の種類
秘密保持契約書(NDA)は、情報の流れによって大きく2つの種類に分けられます。それが「片務契約」と「双務契約」です。どちらの形式を選択するかは、これから行われる取引や交渉の実態によって決まります。自社が置かれる立場を正しく理解し、適切な契約形式を選ぶことが重要です。
| 比較項目 | 片務契約 (One-way NDA) | 双務契約 (Two-way / Mutual NDA) |
|---|---|---|
| 義務を負う当事者 | 一方のみ(情報を受領する側) | 双方(両当事者) |
| 情報の流れ | 一方向(情報開示者 → 情報受領者) | 双方向(互いに情報を開示し、受領し合う) |
| 主な利用シーン | ・業務委託(発注者が受注者に情報を開示) ・コンサルティング依頼 ・自社製品の評価を外部に依頼する場合 |
・M&A、資本・業務提携の交渉 ・共同研究、共同開発 ・対等な立場での協業検討 |
| 注意点 | 自社が情報を受領するだけの立場でも、安易に片務契約に署名しないこと。将来的に自社も情報を開示する可能性がないか慎重に検討する必要があります。 | 契約内容が双方にとって公平かを確認する必要があります。どちらか一方に有利な条項(秘密情報の定義の広さ、義務の重さなど)が含まれていないか注意深くチェックします。 |
片務契約:一方が義務を負う
片務契約(へんむけいやく)とは、契約当事者の一方のみが秘密保持義務を負う形式のNDAです。情報の流れが「開示者 → 受領者」という一方向である場合に用いられます。
最も典型的な例は、発注者が受注者に業務を委託するケースです。
例えば、ある企業(発注者)が自社のウェブサイトリニューアルを制作会社(受注者)に依頼するとします。このとき、発注者は自社の事業内容、顧客情報、マーケティング戦略などの秘密情報を制作会社に開示しますが、制作会社側から発注者に対して秘密情報を開示することは通常ありません。このようなケースでは、情報を受領する側である制作会社のみが秘密保持義務を負う、片務契約のNDAが締結されます。
片務契約を締結する際の注意点は、自社が情報受領者となる場合です。相手方から「弊社の情報をお渡しするので、このNDAにサインしてください」と片務契約書を提示されることがあります。このとき、契約書の内容をよく確認せずに署名してしまうのは危険です。
たとえ現時点では情報を受け取るだけであっても、今後の交渉や取引の過程で、自社からも何らかの情報を開示する可能性が少しでも考えられるのであれば、片務契約は不適切です。その場合は、相手方に対して双務契約への変更を申し出る必要があります。安易に片務契約に同意してしまうと、いざ自社が情報を開示した際に、その情報が法的に保護されないという事態に陥りかねません。
双務契約:双方が義務を負う
双務契約(そうむけいやく)とは、契約当事者の双方が、互いに相手方から受領した情報に対して秘密保持義務を負う形式のNDAです。お互いに秘密情報を開示し合う、双方向の情報交換が行われる場合に用いられます。
双務契約が用いられる代表的なシーンは以下の通りです。
- M&Aや資本・業務提携の交渉: 買い手と売り手、あるいは提携を検討する両社が、互いの事業内容や財務状況などを評価するために、双方の機密情報を開示し合います。
- 共同研究・開発: 前述の通り、参加する企業や研究機関が、それぞれ保有する技術やノウハウを開示し合い、新たな価値創造を目指します。
- 対等な立場での協業検討: 互いの製品やサービスを組み合わせた新しいビジネスモデルを検討する場合など、両社が対等な立場で情報を交換する際に利用されます。
双務契約では、両当事者が同じ内容の義務を負うため、一見すると公平な契約に見えます。しかし、契約書の細部をよく確認することが重要です。例えば、「秘密情報」の定義が、一方の当事者が開示する情報に偏って広く定義されていたり、契約違反時の損害賠償額が一方にだけ不利益な設定になっていたりする可能性があります。
双務契約であっても、その内容が実質的に公平であるかどうかは、条項の一つひとつを丁寧に読み解かなければ判断できません。自社にとって不利な点はないか、取引の実態に即した内容になっているかを慎重に検討することが求められます。
秘密保持契約書(NDA)の主な記載事項・条項
NDAの効果は、その契約書に何が書かれているかによって決まります。ここでは、NDAに必ず盛り込むべき、あるいは確認すべき主要な条項について、その意味とポイントを一つひとつ詳しく解説します。これらの条項を理解することが、実効性のあるNDAを作成・締結するための鍵となります。
契約の目的
「本契約は何のために締結されるのか」を明確に定義する条項です。例えば、「甲(開示者)が乙(受領者)に委託を検討している〇〇システム開発に関する協議及び検討のため」のように、具体的かつ限定的に記載することが重要です。
なぜなら、後述する「目的外使用の禁止」という条項と連動し、受領者が秘密情報を利用できる範囲を画定する役割を果たすからです。目的が曖昧だったり、あまりに広範だったりすると、受領者が情報を様々な用途に利用できてしまい、開示者の意図しない形で情報が悪用されるリスクが高まります。目的を明確にすることで、情報が利用される範囲をコントロールし、保護を強化できます。
秘密情報の定義
NDAにおいて最も重要といえる条項です。この条項で「何が秘密情報にあたるのか」を定義しなければ、そもそも何を保護すべきかが定まらず、契約全体が意味をなさなくなってしまいます。
一般的には、「本契約の目的に関連して、開示者が受領者に対して開示する一切の技術上、営業上、財務上、その他の事業に関する情報(書面、口頭、電磁的記録媒体その他開示の形態・媒体を問わない)をいう」といった包括的な定義が用いられます。
ここで重要なポイントは2つあります。
- 開示方法を限定しない: 「書面で開示されたものに限る」などと限定すると、口頭やメールで伝えた重要な情報が保護の対象外になってしまいます。あらゆる形態の情報が含まれるように記載する必要があります。
- 秘密情報から除外される情報の明記: すべての情報を秘密とすると、受領者にとって過大な義務となるため、通常は例外を設けます。例えば、①開示された時点で既に公知であった情報、②開示された時点で受領者が既に保有していた情報、③開示後、受領者の責によらずに公知となった情報、④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報、などがこれにあたります。この除外規定が自社にとって不利になっていないか、注意深く確認する必要があります。
秘密保持義務
NDAの中核をなす、中心的な義務を定める条項です。具体的には、「受領者は、開示者の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない」という内容を定めます。これにより、受領した情報を勝手に外部に漏らすことを法的に禁止します。
また、法令や裁判所の命令によって開示を強制される場合に備え、「その場合は、開示者に速やかに通知し、開示範囲を最小限に留めるよう努める」といった例外規定を設けるのが一般的です。
秘密情報を開示・利用できる範囲
受領者が社内の誰にまで秘密情報を共有してよいかを定める条項です。受領者側の担当者一人だけが情報を知っていても、業務は進みません。そのため、「本契約の目的を遂行するために知る必要のある、自己の役員及び従業員」といった範囲に限定して開示を認めるのが一般的です。
この範囲を「子会社・関連会社」や「再委託先」にまで広げる場合は、注意が必要です。その場合、「当該第三者に対しても、本契約と同等の秘密保持義務を課す」という一文を必ず加えるようにしましょう。これにより、情報の共有範囲が広がっても、同レベルの保護が維持されるようになります。
目的外使用の禁止
「契約の目的」条項と連動する重要な条項です。「受領者は、秘密情報を本契約に定める目的以外のために使用してはならない」と定めることで、情報の不正利用を防ぎます。
例えば、システム開発の検討のために開示された顧客リストを、受領者が自社の新規顧客開拓の営業活動に利用する、といった行為を禁止できます。この条項がなければ、たとえ情報が外部に漏洩しなくても、開示者の不利益につながる形で情報が利用されてしまうリスクが残ります。
複製の制限
秘密情報が記載された資料やデータが、むやみに複製されることを防ぐための条項です。「受領者は、本契約の目的を遂行するために必要な範囲を超えて、秘密情報を複製してはならない」と定めます。これにより、情報の拡散リスクを物理的にコントロールすることができます。さらに、「複製物についても、原本と同様に本契約に従って取り扱う」という一文を加え、コピーされた情報も保護の対象であることを明確にします。
秘密情報の管理方法
受領者が秘密情報をどのように管理すべきかを定める条項です。一般的には、「善良なる管理者の注意をもって(善管注意義務)、秘密情報を厳重に保管・管理しなければならない」と定められます。善管注意義務とは、その人の職業や社会的地位からみて、一般的に要求されるレベルの注意義務を指します。
より具体的に、「施錠可能なキャビネットに保管する」「アクセス制限を設けたサーバーで管理する」といった管理方法を明記することもあります。これにより、受領者に対して高いレベルのセキュリティ対策を求めることができます。
秘密情報の返還・破棄義務
契約が終了した際や、開示者から要求があった場合に、受領者が保持している秘密情報をどうするかを定める条項です。通常は、「開示者の指示に従い、秘密情報及びその複製物を、速やかに返還または破棄しなければならない」と定めます。
特に電子データの場合、返還が難しいこともあるため、「破棄」を選択肢に入れることが一般的です。その際、確実に破棄したことを証明するために、「破棄証明書」の提出を義務付ける条項を加えることが非常に有効です。これにより、契約終了後も情報が相手方に残り続けるリスクを低減できます。
契約の有効期間
NDAという契約自体がいつからいつまで有効であるかを定める条項です。一般的には「契約締結日から〇年間」と設定され、期間は1年、3年、5年など、取引の内容やプロジェクトの長さに応じて決定されます。
この有効期間は、後述する「秘密保持義務の存続期間」とは異なる概念であることに注意が必要です。有効期間はあくまでNDA契約そのものが効力を持つ期間であり、この期間が満了すると、新たな秘密情報の開示はNDAの保護対象外となります。
契約終了後の義務
通称「サバイバル条項(存続条項)」と呼ばれ、極めて重要な条項です。この条項は、「NDAの有効期間が終了した後も、特定の条項(特に秘密保持義務や返還・破棄義務など)については、引き続き効力を有する」と定めるものです。
もしこのサバイバル条項がなければ、NDAの有効期間(例えば3年)が満了した瞬間に、受領者の秘密保持義務も消滅してしまいます。つまり、3年が経過したら、それまでに受け取った秘密情報を自由に公開できてしまうことになります。これは開示者にとって致命的なリスクです。
そのため、「本契約第〇条(秘密保持義務)の規定は、本契約終了後も〇年間有効に存続する」あるいは「秘密情報が秘密性を失うまで有効に存続する」といった形で、秘密保持義務だけを契約終了後も生き残らせる(surviveさせる)必要があります。この存続期間の設定は、NDAを意味のあるものにするための必須要件です。
違反した場合の損害賠償
契約違反があった場合のペナルティを定める条項です。「本契約に違反した当事者は、相手方が被った一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償する責任を負う」と定めるのが一般的です。
前述の通り、情報漏えいによる実際の損害額を立証するのは困難な場合が多いため、「違約金」として具体的な金額を定めることも有効です。ただし、あまりに高額な違約金は、公序良俗に反するとして裁判所で無効と判断される可能性もあるため、相当な範囲で設定する必要があります。
差止請求
金銭的な賠償だけでなく、情報漏えい行為そのものをやめさせるための権利を定める条項です。「相手方の契約違反により、自己の権利が侵害されるおそれがある場合、その行為の差止を請求できる」と明記します。これにより、情報がまさに漏洩しそう、あるいは継続的に漏洩しているという状況において、迅速にその行為を停止させるための法的措置を取りやすくなります。
知的財産権の帰属
秘密情報に含まれる特許権、著作権、ノウハウなどの知的財産権が誰に帰属するかを明確にする条項です。基本的には、「秘密情報の開示によって、開示者の知的財産権が受領者に移転するものではない」ことを確認的に定めます。
また、共同開発などのケースで、開示された情報を元に新たな発明や改良が生まれた場合の知的財産権の取り扱いについても、この条項や別途の契約で定めておくことが、将来のトラブルを避ける上で重要です。
準拠法・合意管轄
どの国の法律に基づいて契約を解釈し、万が一裁判になった場合にどの裁判所で審理を行うかをあらかじめ定めておく条項です。
- 準拠法: 「本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈される」と定めます。海外企業との取引では、どちらの国の法律を適用するかが重要な交渉ポイントになります。
- 合意管轄: 「本契約に関する一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」と定めます。これにより、遠方の裁判所で訴訟を起こされるリスクを回避し、自社にとって利便性の高い場所で裁判を行うことができます。
秘密保持契約書(NDA)を作成・締結する際の10の注意点
NDAは、雛形をただコピー&ペーストするだけでは、自社を守る盾にはなりません。契約書に署名・捺印する前に、必ず確認すべき重要なポイントがあります。ここでは、実務で特に注意したい10項目をチェックリスト形式で解説します。
① 当事者を正しく特定する
契約の当事者が誰なのかを正確に記載することは、基本中の基本です。法人の場合は、登記簿謄本に記載されている通り、本店所在地、会社名、代表者名を一字一句間違えずに記載します。
注意すべきは、契約交渉の相手が親会社で、実際に情報にアクセスするのが子会社である場合などです。この場合、契約の当事者に子会社も含まれるのか、あるいは子会社にも秘密保持義務が及ぶのかを明確にしておく必要があります。当事者の範囲が曖昧だと、グループ会社間で情報が共有された場合に契約違反を問えない可能性があります。
② 秘密情報の定義と範囲を明確にする
NDAの心臓部である「秘密情報の定義」は、最も注意深く検討すべき条項です。
- 範囲は適切か: 範囲が広すぎると、受領者にとって義務が過大になり、ビジネスが進めにくくなる可能性があります。逆に狭すぎると、保護したい重要情報が漏れてしまうリスクがあります。取引の実態に合わせて、過不足のない範囲に設定することが重要です。
- 口頭の情報: 口頭で開示した情報も保護の対象に含めるべきです。ただし、後々の紛争を防ぐため、「口頭で開示した場合は、開示後〇日以内に、その内容を書面で特定する」といった手続きを定めておくことが望ましいです。これにより、「言った・言わない」の争いを避けることができます。
③ 秘密保持義務を負う人の範囲を限定する
情報を受領した企業内で、誰までがその情報を共有できるのかを定める条項です。一般的には「目的遂行のために知る必要のある役員・従業員」に限定されますが、この範囲は慎重に検討する必要があります。
例えば、弁護士や公認会計士、再委託先といった外部の専門家や協力会社に情報を開示する必要がある場合は、その旨を契約書に明記し、かつ「当該第三者にも本契約と同等の義務を課す」ことを受領者の責任として定めなければなりません。この一文がないと、再委託先からの情報漏えいについて、契約相手の責任を追及することが難しくなる可能性があります。
④ 目的外使用を禁止する条項を入れる
「契約の目的」を具体的に定め、それ以外の目的で情報を使用することを明確に禁止する条項は必須です。この条項がないと、たとえ情報が第三者に漏えいしなくても、相手方がその情報を自社の利益のために利用する(例えば、得たノウハウを自社製品の開発に流用する)ことを防げません。自社の競争力を守るためにも、目的外使用の禁止は必ず盛り込みましょう。
⑤ 秘密保持義務の例外規定を確認する
秘密情報の定義には、通常、秘密保持義務の対象から除外される情報(公知の情報など)が定められています。この例外規定は、受領者にとってはリスクを軽減するために重要ですが、開示者にとっては、この規定が不当に広く解釈されないか注意が必要です。
例えば、「受領者が独自に開発した情報」が例外とされている場合、それが本当に「独自に」開発されたものなのか、開示された情報の影響を受けていないかを証明するのは困難です。自社にとって不利な例外規定が含まれていないか、あるいは曖昧な表現がないかを精査しましょう。
⑥ 有効期間を適切に設定する
NDA自体の有効期間は、取引やプロジェクトの想定期間に合わせて設定します。1年~5年程度が一般的ですが、短すぎるとプロジェクトの途中で契約が切れてしまい、再契約の手間が発生します。長すぎると、関係がなくなった後も不必要な義務が続くことになります。
特に重要なのは、前述したサバイバル条項(存続条項)です。NDAの有効期間が終了した後も、秘密保持義務が何年間存続するのかを必ず確認してください。この存続期間が設定されていないNDAは、実質的に意味がありません。存続期間は、情報の価値が持続する期間(例えば製品のライフサイクルなど)を考慮して、3年、5年、あるいは「秘密性が失われるまで」と設定するのが一般的です。
⑦ 契約終了後の措置を明記する
契約が終了した際に、受領した秘密情報をどう扱うかを定めた条項も極めて重要です。「返還または破棄」の義務が明記されているか、そしてその手続きが具体的かを確認します。特に、確実に情報を消去させるために、「破棄証明書の提出を義務付ける」という一文は、可能な限り盛り込むことをおすすめします。これにより、相手方の手元に情報が残り続けるリスクを最小限に抑えることができます。
⑧ 違反した場合のペナルティを具体的に定める
契約違反があった場合の損害賠償条項は必須です。しかし、「損害を賠償する」と書かれているだけでは、実際に損害額を立証するハードルが高く、実効性が低い場合があります。
そこで有効なのが、「違約金」や「損害賠償額の予定」を定めることです。「本契約の秘密保持義務に違反した場合、違反者は相手方に対し、違約金として金〇〇円を支払う」と具体的な金額を定めておくことで、損害額の立証をせずとも、定額を請求することが可能になります。ただし、金額は取引の規模に照らして、常識的な範囲内に設定する必要があります。
⑨ 片務契約か双務契約か確認する
提示されたNDAが、一方のみが義務を負う「片務契約」なのか、双方が義務を負う「双務契約」なのかを必ず確認しましょう。
自社が情報開示のみを行う場合は片務契約で問題ありませんが、相手方から情報を受領する可能性が少しでもあるならば、双務契約にするべきです。相手方から提示された雛形が片務契約だった場合、安易に署名せず、自社の立場を考慮して双務契約への変更を交渉することが、自社を守る上で非常に重要です。
⑩ 収入印紙は基本的に不要と理解する
契約書というと収入印紙を貼るイメージがあるかもしれませんが、秘密保持契約書(NDA)は、原則として収入印紙が不要な「不課税文書」にあたります。
印紙税法では、課税対象となる文書(課税文書)が定められており、代表的なものに「請負に関する契約書」や「継続的取引の基本となる契約書」などがあります。NDAは、これらのいずれにも該当しないと解釈されるのが一般的です。
ただし、注意点として、契約書のタイトルが「秘密保持契約に関する覚書」などであっても、その実質的な内容が請負契約や業務委託契約を含んでいる場合は、課税文書と判断されて収入印紙が必要になることがあります。とはいえ、純粋な秘密保持義務のみを定めるNDAであれば、印紙は不要と覚えておいて問題ないでしょう。(参照:国税庁ウェブサイト)
秘密保持契約(NDA)に違反した場合の対処法
NDAを締結していても、残念ながら相手方が契約に違反し、情報が漏洩・不正利用されてしまうケースは起こり得ます。そのような事態に直面した場合、企業はどのような法的措置を取ることができるのでしょうか。ここでは、NDA違反に対する主な対処法を解説します。
差止請求
情報漏洩の事実を察知した場合、まず検討すべきなのが差止請求です。差止請求とは、現に行われている、または将来行われるおそれのある権利侵害行為を停止させることを求める法的手段です。
例えば、競合他社に自社の技術情報が渡り、それを利用した製品が製造・販売されようとしている場合、損害賠償を求めても、一度市場に出回ってしまった情報の拡散を止めることはできません。このようなケースでは、金銭的な補償よりも、まず侵害行為そのものをやめさせることが最優先となります。
NDAに差止請求に関する条項が明記されていれば、それを根拠に請求しやすくなります。また、不正競争防止法においても、営業秘密が侵害された場合には差止請求権が認められています。緊急性が高い場合は、裁判所に「仮処分命令」を申し立てることで、本格的な訴訟を待たずに迅速な対応を図ることも可能です。
損害賠償請求
NDA違反によって自社が具体的な損害を被った場合、その損害の賠償を相手方に請求することができます。これはNDA違反への対応として最も一般的な手段です。NDAに損害賠償条項が定められていることが、請求の直接的な根拠となります。
請求できる損害には、情報漏洩によって失われた利益(逸失利益)、対応にかかった費用(調査費用や弁護士費用など)、ブランドイメージの低下による損害(無形損害)などが含まれます。
ただし、損害賠償請求の最大のハードルは、「損害額の立証」にあります。情報漏洩という行為と、発生した損害との間に明確な因果関係があること、そしてその損害が具体的にいくらなのかを客観的な証拠に基づいて証明する必要があり、これは非常に難しい作業となることが多いです。
この立証の困難さを軽減するため、前述の通り、あらかじめNDAに「違約金」や「損害賠償額の予定」を定めておくことが有効な対策となります。
信用回復措置の請求
情報漏洩によって企業の社会的な評価や信用が毀損された場合、金銭的な賠償だけでは回復できない損害が生じます。このような場合に、失われた信用を回復するために必要な措置を相手方に請求することができます。
これは民法第723条に定められた権利で、具体的には、新聞やウェブサイトへの謝罪広告の掲載、顧客や取引先への謝罪文の送付などが挙げられます。これにより、情報漏洩の事実と自社に非がないことを公に示し、ダメージを受けたブランドイメージや社会的信用の回復を図ります。
刑事罰の可能性
NDA違反が悪質なケース、特に不正な利益を得る目的や、企業に損害を与える目的で情報を漏洩・使用した場合は、民事上の責任だけでなく、刑事罰の対象となる可能性があります。
これは、不正競争防止法に定められた「営業秘密侵害罪」が適用される場合です。この罪が成立すると、違反した個人には10年以下の懲役もしくは2,000万円以下の罰金(またはその両方)が科されます。さらに、違反者が所属する法人に対しても、5億円以下の罰金が科される両罰規定があり、企業にとっても極めて大きなリスクとなります。(参照:経済産業省 不正競争防止法関連資料)
NDA違反が直ちに刑事事件になるわけではありませんが、特に退職者が顧客情報を持ち出して競合他社で利用するような悪質なケースでは、刑事告訴も視野に入れた厳しい対応が検討されます。この刑事罰の存在は、NDA違反に対する強力な抑止力として機能します。
秘密保持契約書(NDA)の作成方法と雛形
NDAを準備する必要が生じた際、具体的にどのように作成すればよいのでしょうか。主な方法としては、「雛形(テンプレート)を利用する」方法と、「専門家に依頼する」方法の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
雛形(テンプレート)を利用する
現在では、インターネット上で検索すれば、経済産業省や中小企業庁が提供しているものから、法律事務所や民間企業が公開しているものまで、多種多様なNDAの雛形(テンプレート)を簡単に入手できます。
【メリット】
- コストが低い: 無料または非常に安価で入手できるため、費用をかけずに契約書を準備できます。
- 手軽でスピーディー: ダウンロードして必要箇所を書き換えるだけなので、迅速に契約書を作成できます。一般的な取引であれば、雛形をベースにすることで効率的に対応可能です。
【デメリット】
- 個別具体的な状況に対応できない: 雛形はあくまで一般的な取引を想定した最大公約数的な内容です。自社の特殊な事情や、取引の具体的なリスクが考慮されていないため、そのまま使用すると、保護すべき情報が漏れていたり、自社に不利な条項が含まれていたりする危険性があります。
- 法改正に対応していない可能性: 古い雛形の場合、最新の法改正や裁判例が反映されていないことがあります。
- リスクの見落とし: 法律の専門知識がないと、雛形に潜むリスク(例えば、サバイバル条項がない、秘密情報の定義が不十分など)に気づかないまま署名してしまうおそれがあります。
雛形を利用すること自体が悪いわけではありません。しかし、雛形はあくまで「たたき台」であると認識し、この記事で解説したような各条項のポイントを一つひとつ確認しながら、自社の取引内容に合わせて適切にカスタマイズすることが絶対条件です。内容を十分に理解せずに雛形を流用するのは、非常に危険な行為であると心得るべきです。
弁護士などの専門家に作成を依頼する
取引の重要性が高い場合や、契約内容が複雑な場合は、弁護士などの法律専門家にNDAの作成やリーガルチェックを依頼するのが最も安全で確実な方法です。
【メリット】
- 安心感と信頼性: 専門家が、取引の実態をヒアリングした上で、自社のリスクを最大限にヘッジした、最適な契約書を作成してくれます。相手方から提示された契約書に潜む不利な点も的確に指摘してもらえます。
- 交渉力の向上: 「弁護士に確認済みの契約書です」と提示することで、相手方に対して安易な修正要求を牽制し、交渉を有利に進めやすくなる効果も期待できます。
- トラブル発生時の対応: 万が一トラブルが発生した場合も、契約書を作成した弁護士にスムーズに相談し、迅速な対応を取ることができます。
【デメリット】
- コストがかかる: 当然ながら、専門家への依頼には費用が発生します。費用は依頼する弁護士や契約内容の複雑さによって異なります。
- 時間がかかる: ヒアリングやドラフト作成、修正などに一定の時間がかかるため、雛形を利用する場合に比べてスピーディーさでは劣ります。
どのような場合に専門家に依頼すべきかですが、例えば、M&A、多額の投資が関わる共同開発、海外企業との取引、自社の根幹技術に関わるライセンス契約など、事業への影響が大きい重要な契約については、迷わず専門家への依頼を検討すべきです。コストはかかりますが、将来起こりうる巨大な損失を防ぐための「保険」と考えれば、決して高い投資ではないでしょう。
秘密保持契約書(NDA)は電子契約でも有効か
近年、契約業務のデジタル化が急速に進んでおり、「NDAを電子契約で締結しても法的に問題ないのか?」という疑問も増えています。結論から言うと、NDAは電子契約で締結しても、書面契約と全く同じ法的効力が認められます。
電子契約とは、紙の契約書に署名・捺印する代わりに、電子ファイル(PDFなど)に電子署名や電子サインを施して、当事者間の合意を証明する契約方式です。
電子契約のメリット
NDAを電子契約で締結することには、多くのメリットがあります。
- コスト削減: 紙の契約書で必要だった収入印紙が不要になります。電子文書は印紙税法の課税対象外であるため、特に契約件数が多い企業にとっては大きなコスト削減につながります。また、印刷代、郵送費、保管用のファイル代なども削減できます。
- スピード向上: 契約書を印刷・製本し、郵送して、相手方の署名・捺印後に返送してもらう、といった一連のプロセスが不要になります。契約システム上でファイルをアップロードし、相手方に送信すれば、数分で契約締結が完了することもあり、ビジネスのスピードを格段に向上させます。
- 業務効率化とコンプライアンス強化: 締結済みの契約書はクラウド上で一元管理されるため、「あのNDAはどこに保管したか」と探す手間がなくなります。検索機能を使えば必要な契約書をすぐに見つけられ、契約の更新時期や有効期限の管理も容易になります。これにより、管理業務が効率化され、コンプライアンスの強化にもつながります。
署名は自筆でなくてもよい
電子契約の有効性を支えているのが「電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)」です。この法律により、本人による一定の要件を満たした電子署名が行われた電子文書は、真正に成立したものと推定され、手書きの署名や押印と同等の法的効力を持つことが定められています。
現在、市場には多くの電子契約サービスが存在します。これらのサービスを利用すれば、誰が、いつ、どの文書に合意したかという記録(ログ)が残り、タイムスタンプによって契約締結時点での文書の存在と、その後の改ざんがないことを証明できます。これにより、従来の書面契約以上に、高い証拠力を確保することも可能です。
NDAのように定型的な内容で、かつ締結頻度が高い契約は、電子契約化によるメリットが特に大きいといえます。業務の効率化とコスト削減、コンプライアンス強化の観点から、電子契約の導入は積極的に検討する価値があるでしょう。
まとめ
本記事では、秘密保持契約書(NDA)の基本的な概念から、その目的、締結のタイミング、種類、そして契約書を構成する主要な条項や作成・締結時の注意点まで、網羅的に解説してきました。
NDAは、単なる形式的な書類ではありません。それは、企業の競争力の源泉である貴重な情報を守り、安心して他社と協業するための「信頼のインフラ」です。情報漏えいや不正利用を未然に防ぐ抑止力として機能するだけでなく、万が一のトラブル発生時には、自社の権利を守り、損害を回復するための強力な法的根拠となります。
この記事で繰り返し強調してきたように、NDAで最も重要なのは、その「中身」です。
- 契約の目的は明確か?
- 秘密情報の定義は適切か?
- 契約終了後も秘密保持義務は存続するか(サバイバル条項はあるか)?
- 自社にとって一方的に不利な内容になっていないか?
これらのポイントを常に意識し、雛形を安易に流用するのではなく、一つひとつの取引の実態に合わせて契約内容を吟味する姿勢が不可欠です。
ビジネスのグローバル化やオープンイノベーションの進展により、企業が外部と連携する機会は今後ますます増えていくでしょう。それに伴い、NDAを締結する場面もより一層増加します。NDAの締結を「面倒な手続き」と捉えるのではなく、自社と取引先双方の未来を守るための、積極的かつ重要なビジネスプロセスであると認識することが、持続的な成長の鍵を握ります。
もし契約内容に少しでも不安や疑問があれば、躊躇せずに弁護士などの専門家に相談しましょう。その判断が、将来の大きなリスクからあなたの会社を守ることにつながるはずです。